FEB. 5 1996
やっと、おもしろさが分かるようなになってきた。
ボールを前にやればいいのだ。シンプルなことだ。












シンプルなことに、おもしろさが発見できたとき、そのゲームの良さが理解されるのだ。難解なルールをどんなに覚えてもダメなのだ。ゲームのおもしろさの本質はいつもシンプルなのだ。そこに気づいたとき、そうか、おもしろいじゃない、と一気にのめり込むのだ。そのために、ちょっとルールの勉強が必要なのだ。
この試合は、スーパーボール一歩手前の試合なのだ。こういう試合がけっこう感動的なのだ。事実、この試合は、おいしいものだった。まだ誰がスターなのか、分からなくても、なんとなく伝わってくるものがあるのだ。でも、期待していたチームの方が負けてしまった。最後の逆転の賭のロングパスが惜しかった。
QBに期待されるのは、頭脳ではなく、身体知なのだ。












思考は頭でしてはいけないのだ。身体と融合してはじめて、思考が活きるのだ。優秀なQBは、その身体知に傑出したプレイヤーなのだ。


インディアナポリスとピッツバーグのどちらのクォーターバックが身体知に優れていたか、それは、あきらかに負けた方だったのだ。でも、試合は負けてしまった。そんなものだ。ゲームには運がつきものなのだ。神は、いつも浮気者なのだ。
FEB. 5 1996
ジーン・ケリーが死んだ。といっても、あっそー、では失礼だ。
フランク・シナトラだって、この人の前では小さい存在なのだ。












フレッド・アステアがケリー・グラントならば、ジーン・ケリー(Gene Kelly)はマーロン・ブランドだ、といわれたって、かろうじてマーロン・ブランドの太った晩年しか知らない人には、何の役にもたたないメタファーで、使えない。それほど古い人だけど、ダンスつまりミュージカルでは圧倒的に凄い人なのだ、という感じだけはつかめるだろう。
ダンスも、そうなのだ。身体知のことが重要なのだ。スポーツもダンスも、単にスポーツとかダンスという狭いカテゴリーに押し込めて、そこでの偉い人を探し、憧れるというだけでなく、その世界こそがこれからの世界の基本を構成するのに不可欠な知性なのだ、という認識をもつことが肝心なことなのだ。マルチメディアの世界は、情報世界の話だから、身体知なんて関係ないぜ、というのは間違いなのだ。スポーツができない奴に、マルチメディアの思考はできないのだ。スピードの感覚、身体のキレ、めまいの快感、冷静な仕掛け、そんなさまざまなことが身体的な瞬時の反応として表現できないかぎり、マルチメディアにはならないのだ。だから教育は、もっと、身体知を大切にしないといけないのだ。そうしないと、間違ったメディアキッズができあがってしまうのだ。
WACOMのART Z 2。これは、これから使えるな。QV-10と双璧になるぞ。
思考のコンセプトが、こうやって広がるのだ。実感するな。うれしくなる。
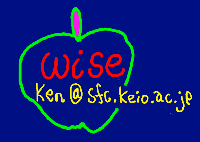
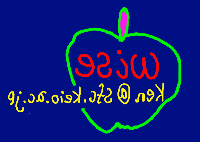
思考は、つねのメディアと相関するものなのだ。まだ、まだ、いままでの思考から離脱しているとはいえないのが現状だ。メディアがやっと何かを予感させる方向で動いてきた。QV-10は、その一つだし、このWACOMのART・Z2もそうだ。ノートの代わりになるお手軽なメディアがないのだ。もっともっと手軽に使えるメディアが開発されないかぎり、思考は変わらないのだ。でも、ユーザーであるこっちも、もっともっと、使い方を試行しないといけないのだ。ポケベルをあんなに使いこなす女子高生は見上げたものだ。えらいガキっ娘たちだ。
こんなのが簡単に書ければ、利用価値はでるのだ。脱ノートは可能か?
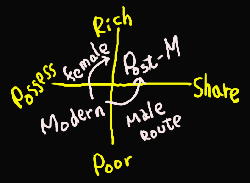
内容は、このさい、どちらでもいいのだ。その解説はいつかしよう。いま興味があるのは、こんな図が簡単に書けることなのだ。まだ多くのテクニックをマスターしないといけないのだろうが、現状でも、そこそこのものになっている。こんなのが、欲しかったのだ。いつもノートのように抱えて、パソコンとつなげれば、それで、言いたいことが簡単に書ける、そんなことが些細ではあっても、非常に重要なことだったのだ。はっは、やっと、いいものに出会えた。最近は、いいものがお安い値段で登場するから、けっこう、わくわくしているのだ。
マイケル・ジョーダンの神業をみた。
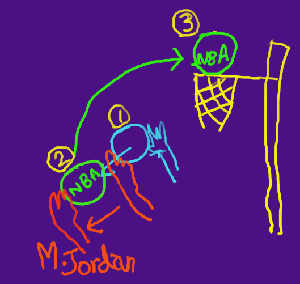
2月7日のゴールデンステイツとの試合での話。ブルズ2連敗という危機での試合で、相手が弱いとはいえ、NBAである以上、ちょっとした気持ちの加減で、勝敗なんか簡単にひっくり返るものなのだ。ブルズはあきらかに弱気になっていた。それを救ったのがやはりジョーダンだった。この試合いくつものプレイ(40ポイント)がでたが、神業はこれだ。一度、相手のセンターにボールをブロックされ、通常ならば、それで終わりなのに、ジョーダンは、その崩れた姿勢から、ボールを離さず、しかもその体勢からゴールに向けてボールを投げ、しかも入れたのだ。その時、ジョーダンは、フロアにきれいに尻餅をついていた。にもかかわらず、得点する、その能力以上に、執念に感服する。これだから、やめられないのだ。すごい、ただそれだけだ。
こんな図もかけるのだ。いいな。ほんとは、こっちがみせたいことなのだ。ごめん。
NBAのオースター戦を祝う
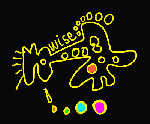
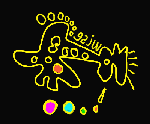
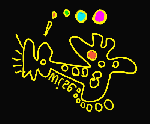
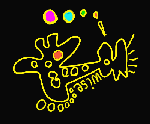
マジック・ジョンソンは、さすがマジシャンだ。だけど、キース・ヘリングは、死んでしまった。そんなものだ。生と死。スポーツとアート。その差は、とっても大きい。でも、同じだ。NBAのプレイヤーをみれば、みんな芸術家だと確信できるはずだ。でも、マジック・ジョンソンだけは、ちょっとダサイぞ、と思ってしまう。そこがマジシャンたる由縁だろうか。胡散臭い、のがいい。
でも、今日はでない。デニス・ロッドマンもでないのだ。ちょっとインチキじゃない、といいたい。ロッドマンは、真のアーチストなのだ。あの頭をみろ、なのだ。かっこいいじゃん。
 BACK
BACK