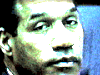
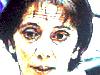
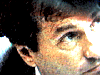
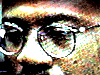
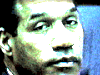
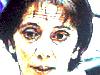
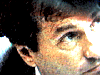
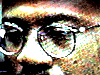
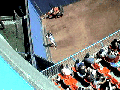


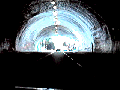
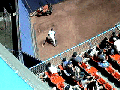
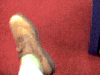
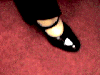
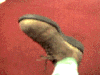














|
ロスにいたときは、会ったことが一度だけで、それだけのことであった。 ぼくが家をでて、沢田夫妻が、その家に新しい住民としてはいってきた。 それ以上のつながりもないし、ただ、それだけのことであった。最初は。 |

|
沢田さんが、インターネットに興味をもち、せっかくだから遠い人にメールをだしたい、と思った。 それが僕だった。そのメールのやりとりは、確実に関係を親密にしていった。遠いからこそ、関係が親密になれる、そんな奇妙な感覚があった。ニューヨークとロスのコミュニケーションは、空間を簡単に超えていった。距離があるほど、距離がない、という新しい発見があった。 |

|
インターネットフォーンに凝っている。電話に近いことが、もうできる。国際電話なんて、これからどうするのか。ローカルの電話代だけで、何時間も海外と普通に電話ができるようになりつつある。その時、国内か国際か、なんて、意味を失ってしまう。どうするのだろう。NTTとKDDって、なーに。 |

|
どこにいても、もう、関係ない。近いか遠いか、その違いは意味を失いつつある。経済的にも、文化的にも、差異は、インターネットを利用するか、しないか、から生じる。活字が読めるか、読めないか、その差異以上の変化がもたらされるのだ。どうする中年、がんばれ中年、つらいぞ中年。高齢化も、女の自立も、この視点をみなければ、何もできないのだ。どうする。 |




 BACK TO KEN'S WORKSHOP
BACK TO KEN'S WORKSHOP