JAN. 8 1996
BEAUTIFUL REALITY
 |
 |
何といわれようが、「だって、きれいなんだもん」、と、ためらうことなく飾り付けするその強さに、ただ感心。プレゼントには、カルチェを、ということなんだろうが、それ以上に、「きれいでしょ、わたし」とささやく、その臆面のなさに脱帽。えらいものだ。これがニューヨークなのだ、と教えられた気分になる。主張は明確に、そうじゃないと、みんなにつたわらない。そうなのだろう。美しい、という言葉が素直にでてくる。
JAN. 8 1996
JAPANESE DREAM
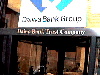 |
 |
 |
 |
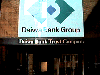 |
日本は、やってはいけなかったのだ。買えるからといって、買ってはいけないものもあるのだ。ロックフェラー・センターを、なぜ、日本企業が買う必然性があったのだろうか。できることでも、その前に、やるべきことの使命に支えられなければ、やってはいけないのだ。この事件は、バブルで日本社会が一瞬だけ見た戦後の貧しさを清算する夢だったのだろう。だから、返すことは、いいことなのだ。この社会のルールは尊重しなければならない。
隣に、あの事件を起こした大和銀行ニューヨーク支店がある。ご近所だ。こんないいところにあっていのだろうか、と思ってしまう。紀ノ国屋書店も、ここにある。みんなとはいわないが、シンボリックな意味をもつロックフェラー・センターとその周辺にオフィスを構えて、その勢力を誇る必要がどこにあったのか、と思わないでもない。ほんとは、もっといい場所があるような気がする。みんなつかまされているのではないか。だまされてはいけない。ここはしっかりとゲームの国なのだ。
JAN. 8 1996
LADY IS TRUMP
 |
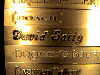 |
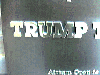 |
 |
あの有名なトランプさんは、その名の通り、勝つ(切り札で、勝つ)人なのだ。だからゴールドが好きなのだ。ご近所のちょっと気取った店は、やはり気が引けるのか、それとも十分な歴史があると思っているのか、ゴールドをストレートにだすことにためらいがあるようだ。でも、トランプは違う。店構えからして、徹底してゴールドなのだ。その潔さが見事だし、その名前もトランプナノだから、恐れ入る。その強さがここでは必要なのだろう。いらん老舗の格式なんか、ここには似合わないのだ。すべてストレートで攻めることだ。そうすれば、ゲームに勝てるのだ。強ければ、ストレートなのだ。その成果がゴールドなのだ。でも、ロックフェラーだって、ほんとはゴールドが好きなのだ。下の写真は、みんなロックフェラー・センターでみつけたものだ。ゴールド万歳、これがアメリカだ。
JAN. 8 1996
GOLDEN EYES
 |
 |
 |
びっくりというとオーバーな表現だが、気がついたひとつに、ゴールドが好きだな、ということがある。いぶし銀への価値なんか、ここにはないのだろう。サクセスへの単純な信仰があるように、ここにあるのは素直に「金が好き」という価値信仰だ。単純と非難するのではない。それがこの国の基本コンセプトなのだ。単純なルールで、しっかり勝つ奴が偉い、という論理は、それなりに共感できるものだ。金はそのシンボルなのだろう。サクセスしたら、ゴールドで飾れ、そうすれば、みんなから喝采される。プロスポーツの支持に共通するメンタリティだ。それでいいのが、このアメリカだ。それを、歴史がないとか、文化がない、と責めても、意味のないことだ。シンプル・イズ・ベストなのだ。わかりやすい。それだけのことだ。でも、確かに、重要なことだ。
JAN. 7 1996
BLACK NIGHT IN CHICAGO
 |
 |
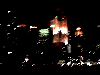 |
シカゴはジョーダンの街だ、といったら、怒られそうだが、ぼくには、それだけのことだが、そんなに凄いことはない。昼も夜も、ブルズのことで一杯の街だ。といっても、その街はぼくの思考の街だ。メンタル・マップなのだ。でも、こんなにブラックが強いところは、ないのかもしれない。そしてNBAほど、ブラックがすべてのスポーツはない。だから、シカゴ・ブルズのジョーダンなのだ。ここは、完璧にブラックによって意味をもつ社会なのだ。シカゴはNBAなのだ。とすると、論理としては、ジョーダンはシカゴ市長なのだ。それ以上に決まっている。
JAN. 7 1996
RESORT OFFICE ?
 |
 |
 |
どこにいても仕事ができる。インターネットの世界にいると、そのリアリティは、利用するほど確実に増大する。ここには、新しい世界が開ける、という確信がある。リゾート・オフィスのコンセプトがかなり前にだされていたが、その実現は、インターネットの社会的な浸透によって、はじめて意味をもちはじめた。どこにいても仕事ができる、という夢は、もう夢ではない、つよく支持される現実なのだ。その実現をこばむものは、あるのか。ないことは、ない。だが、もしもそのリアリティを知ろうとしない経営者がいるとしたら、そんな不幸はなかろう。その不幸は、まずはその経営者にふりかかるのだから。社会は大きく変わろうとしている。もう一度、家庭に仕事が戻るのだ。
JAN. 7 1996
LIVE2 AT GRAND CENTRAL
 |
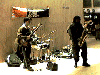 |
 |
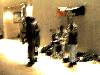 |
グランド・セントラルは、確かに文化会館なのだ。突如というわけでもなく、まあ、いつものように、という感じだろうか、楽器をセットして演奏を始めた。そのさりげなさがいい。しかも、しっかりしていて、自分たちのCDをちゃんと12ドルで売っているのだ。ちょっと高いんじゃ、と思った。空間がなんにでも化ける、その自在さがいい。ここはこれ、という一義性では、何もおもしろいことは起こらないのだ。何かを誘発する装置と環境が必要だ。その環境がここにはある。だから文化がいつも、つぎからつぎへと生成されるのだ。もちろん、嫌いならば、聞かなければいいので、平然とプレイヤーの前を通過する人も多い。その主張もまたいい。好き嫌いは明確に。いいことだ。
JAN. 7 1996
LIVE1 AT GRAND CENTRAL
 |
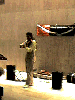 |
 |
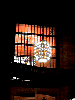 |
たとえ才能が希なるものでなくても、好きだからしていたい、という欲求は、人としてとうぜんのことなのであろう。好きなことをして生きたい、というのは、他の誰にも拒否できない、自己の権利なのであろう。ならば、必要なのは、その権利を主張する力が自分にあるか、それだけなのだろうか。それだけではないのだ。ここには、それを許容する環境がある。
環境がやさしい。
それは、とても大切なことだ。どこの国からきたのか、いろいろの国からきた若者が、ここで、前衛的な実験を追求する場合もあろう、あるいは単純な成功を求めることもあろう、自分の思うかぎりのことに挑戦する。頑張るしかない。環境がスポンサーなのだ。その差はおおきい。
JAN. 7 1996
ターミナルなのに、チャーチ?
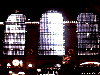 |
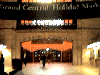 |
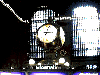 |
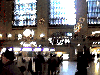 |
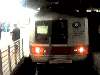 |
グランド・セントラルは、雰囲気がある。単ある機能としてのターミナルを超えた文化がある。ここには、人が行き交う空間に、歩きすぎるのではもったいない、だからせめてゆっくりと歩こうと誘う
アンビエンスがある。暗いし、古いし、けっしてきれいではないが、それだからこそ、迫ってくる迫力がある。あたかも宗教的な空間であるかのように、このアンビエンスはたつ。駅なのに、教会なのだ。毎日、ビジネスマンはここを通過しながら、祈りを捧げるのか。公共空間は何でもいいから底抜けに明るければいいのだ、というルールがいかに特殊な文化か、ということがわかる。
 BACK BACK
|




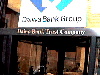



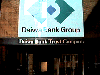

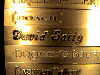
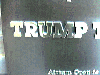






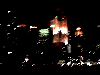




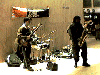

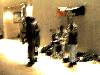

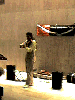

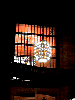
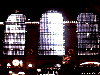
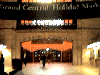
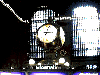
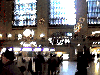
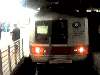
 BACK
BACK