JAN.10 1996
なんとなく、セクシー
 |
 |
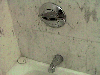 |
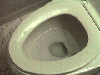 |
すべてを性的イメージで語ることの無意味さは理解しているが、つい、そんな気分で物事を解釈してみたくなる瞬間もあるものだ。なんとなく、そうなんだよね、と、納得させられるものがこの手の解釈にはあるようだ。よく考えると、それでどうしたの、で、終わり、それ以上の展開なんてなにもないのだが。でも、一瞬の座持ちには、これほど安直に人々のイマジネーションを喚起する方法はないようだ。みんな、好きなんだ。ただそれだけのことだ。でも、いい。エッチな想像をどうぞ。ただの便器ですし、ただの洗面台とドアとバスタブのノブにすぎません。そうなのです。すぎません。でも、えー、なんかいいたいんじゃない、と、考えた瞬間、意味の変換がなされます。フレームが変わり、意味世界が変容するのです。まあ、そんなオーバーなことじゃ、ないですが。
JAN.10 1996
FAME OF CALVIN KLEIN
 |
 |
カルバン・クラインは、ニューヨークに似合っている。コマーシャルで物議をかもしだしていたが、ここにいるかぎり何の違和感もない。この程度のコマーシャルで、なんで騒ぐのか、その騒ぎをおこしたおばさんたちの方に、勘違いがあるとしか思えない。もちろん、ここがニューヨークだからなのだろう。ここは確かに特殊であり、スタンダードのアメリカではない。でも、どこが本当のアメリカなのか、と問えば、でもやっぱりニューヨークであってほしい、という気になる。南部でも、ロスでも、シカゴでもないのだろう。ここには、カルバン・クラインのおしゃれがアンダーウェアにまで染みついた文化がある。
カルバン・クラインは、グンゼなのだ。
空気のように、カルバン・クラインを着こなす文化がここのものだ。派手にアンダーウェアのコマーシャルをまとったバスが昼間から(当然だが)街中を堂々を闊歩して、おかしくないのだ。だれも、そんなことに目くじらたてるようなことはしない。みんな、いいじゃん、と思っているのだ。だって、かっこいいじゃない、グンゼと違って、ということだ。25年前の新星カウバン・クライン、ニューヨークの溜息(?だったかな)の登場、というコピーが思い出される。偉くなったものだ。
JAN.10 1996
主役は、QV-10 なのです。
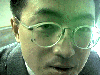 |
 |
 |
 |
QVちゃん音頭
ここまでできるのか、と感心するばかりだ。これこそ、カシオの真骨頂だ。ネットワークに、マルチメディアを簡単にのせるにはどうすればいいのか。そんな回答をさりげなく提示したのがQV-10だ。これさえあれば、いつでもどこでもマルチメディアの表現が、しかもネットワークのなかで容易にできる。こんなことでいいのだ。カシオの路線は、間違っていない。しかももっとも日本的なスタンスで世界に貢献している。これを、日本がやればいいのだ。カシオは日本の見本だ。えらい。そのついでに、というのもつながらない話だが、ぼくのニューヨークでの師匠を紹介します。KIUCHI YOSHINOBUさんです。よく考えたら、かれの名前の漢字が知らないのだ。失礼な。
JAN.10 1996
動かない、でも人形なのか?
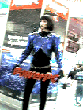 |
 |
バービーは、いきている。
わたしは人形ではない、人間なんだ、なんていう時代がありました。いま、人間が人形になることで、主張をしています。つまり、1>人がいる(人は人だ)。2>人形がある。(人形は人形だ)。3>人は人形ではなないのだ。(女の自立の話)4>人形は人ではない。(ロボット論)。ここにあるのは、そのどれでもない。5>人は人形であり、6>人形が人である、という命題を、パフォーマンスで証明しようとしているのだ。認知プロセスはこうだ。人形がある。あれ、この人形は人だ、この人は人形をやっているんだ。そうか、すごい。こうして、人形は人と等価になる。いま、ぼくたちは、このような新しい関係を模索しているのだ。パフォーマンスする女性は、イプセンの人形よりも、人形であることで、自立しているのだ。もちろん、人形も生きているのだ。バービー人形は、いまの女の子そのものなのだ。
JAN.10 1996
思考する手
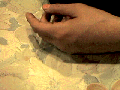 |
 |
 |
みえざる神の手
手は道具だ。道具としての発見があったことで、ここまでの世界が生成された。手は見事だ。手には、神が宿る。しかし手には、指があり、腕がつく。指には、さらに爪がつき、腕は胴につながり、身体をつくる。こう考えてくると、どこまでが手なのだ。手は孤独だ。指にはリングがつき、きれいね、と誉められ、腕には時計がはめられて時間を告げる。役があり、社会につながる。指は、得だ。リングをつけて、みんなからちやほやされるから。腕は、いい。時計があって、役にたっているから。手は、何だ。手は、何を語るのだ。
そうではないのだ。手は、指をつつみ、腕をつつみこむことで、手になるのだ。引くのではない、融合することで、手の意味が見えるのだ。その手に期待されていることは、もはや道具であることではない、思考そのものになることだ。手は考える。指と共振し、腕に融合して、身体そのものを動かしながら、手が思考するのだ。それがマルチメディアの思考だ。
 BACK BACK
|


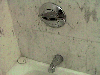
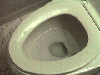


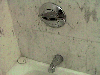
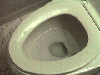


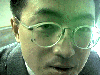



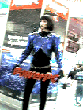

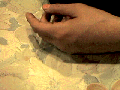


 BACK
BACK