JAN.11 1996
空を飛ぶ、素直に美しい、と思う。
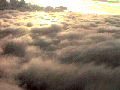 |
 |
 |
芸術家は大変だと思う。こんな自然を相手に、もっと美しいものをつくろうと挑戦するのだから、その意気込みには敬意を払わないといけないだろう。がんばれ、アーティスト。自然は、社会という小さな器を超えて、いつも悠然としている。空の上にくると、いつも圧倒される気分にさせられる。いつもは、社会は偉大だ、と、ほざけるのに、ここにくると、きまじめになって、涙を素直に流すこともいいことなのだ、とつい思ってしまう。自然のパワーは、やはり圧倒的だ。それに刃向かうことの愚は、分かっているつもりだ。でも、何かいわないと、負けてしまうので、言ってしまう。この自然に美しさを認めるのは、社会なのだと。くだらん、戯言だ。ごめん。そもそもこんな写真をとること自体、間違っていたんだ。でも載せてしまった。よわいのだ。
JAN.11 1996
人工的再生への意志
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
なんでこんな砂漠にわざわざ都市をつくらなければならないのか。それは、意志の問題なのだろう。アメリカは、その西部は死の土地だ。そこを再生するには、人工的な力による意志しかないのだ。砂漠に緑を、砂漠に都市を、同じことだ。水も、電気も、何もない土地に、水と電気を付与するには、神をも畏れぬ意志が必要なのだ。ここを、都市に再生したい、という強い意志だ。ラスベガスは、この意味でも強くアメリカ的だ。夢は、水と電気、緑と明かりを人工的に付与することで、実現されるのだ。夢は、意志があってはじめて、社会へもたらされる。その結果が、ギャンブルなのか、とはいうまい。ギャンブルも、ささわかな夢であり、ここはいつまでたっても夢の国であるべきなのだ。
JAN.11 1996
イルミネーションの真実
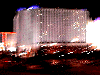 |
 |
 |
ウォルト・ディズニーが20世紀のアメリカの遺産だとしたら、ラスベガスも、同じ重要な生きた遺産なのだ。ラスベガスは、ディズニーランドを超えたディズニーランドなのだ。ホテルのイルミネーションは、当然のことなのだ。シックになんて言葉はない。お子さまランチの見た目の豪華さそれだけでいいのだ。それは嘘なのではないのだ。そこには、オリジナルの本物なんてないのだ。イルミネーションのホテル、それが最初からのものなのだ。ピラミッドを真似たホテルがあるが、それも、真似たのではないのだ。そこにあるのはオリジナルを模倣(真似る)する姿勢ではなく、素直にコピーするだけのことだ。コピーには、もはや、オリジナルを模倣する発想はない。まったく同じものを、いつでもどこでも好きなように、もってきてしまう、だけのことで、本物の無限増殖の操作なのだ。イルミネーションこそが、ここの真実の主張なのだ。考えさせられる都市だ。
JAN.11 1996
カガミの世界が好きですか。
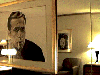 |
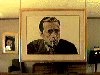 |
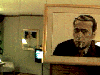 |
ラスベガスのホテルの部屋だから、カガミでいっぱい、と考えたらいけない。みんな、カガミが好きなのだ。普通のいえでも、壁面一面にカガミをとりつけていることなんて、当たり前のことだ。なんでそんなに大きなカガミを備え付けるのだろう。きっとエッチなのだ、と考えるのは間違いで、そうではないのだ。
1:部屋の広さが2倍にみえて、得した気分になれる。
2:やはり、部屋が明るくみえるので、気分が明るくなる。
3:もうひとりの自分がいるので、会話ができて楽しい。
たぶん、最後が一番重要なのだろう。自分を見つめる、しかも可能な限り自己を客体化させたところで、自己との対話をすることが大事なのだろう。自己をしっかりとみつめないといけない、という文化的な要請なのだろう。つい、だらしない自分をみつめて、いかん、ちゃんとしないと、と反省する。いい装置だ。
JAN.11 1996
王国崩壊の予兆
 |
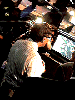 |
 |
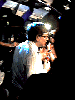 |
頂点をみた時、それを築いてきた人は何をそこにみるのか。まだ頂点ではない、と意識的に自己に思い込ませようとするのか、もうこれで終わりだな、と人生に達観するのか、それともこの状態を維持するには何が必要か、と戦略論を考えるのか。心理学と哲学とマーケティングがそれぞれ必要とされる。
ビル・ゲイツがみるものが、マーケティグの夢であることは確かだ。かれは、まだ強気の人だから、自己を偽るほど弱くはないし、まだ十分に若いから人生に達観するほど老いてもいないし、かれには、再びマスをターゲットにしたマーケティング・ストラテジーしかないのだ。それが、いかにもビル・ゲイツらしいことも事実だ。しかし、だ。マスという幻想が、ネットワークの中でビジネスの対象になるのか。これが、いまの問題なのだ。もはやマーケティングが意味をもたない時代に入りつつあるのだ。どうする、ビル・ゲイツ。
 BACK BACK
|
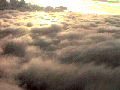


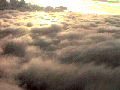












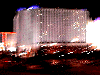


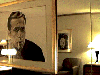
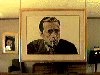
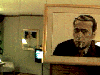

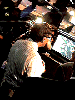

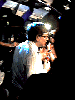
 BACK
BACK