JAN. 30 1996
ブタでさえうっとりさせてしまうカガミ、をめぐる事実としての虚構=現実論









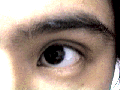
もう25年も昔のことだ、宇高連絡船で高松に着いて、新居浜方面に向かう夜行列車のなかで、といっても、そんなに特定する必要などなく、いつものことなのだが、「またブタだ!」と、カードを投げだし、ふてくされたポーズをきめて、ただ同情だけを買うことで、自分の弱さを隠そうとしていた。下手な奴ほど、ブタが似合うものだ。もちろん、ぼくのことだ。たかだかコーヒーの金を賭けただけの非日常性の世界でのことなのだが・・・、つい本気になってしまった。いかん、どうもブタのようなでだしだな。なんとかせんと。また罵られるぞ。うえは、みんなうるさいからな。いちうら、すがわら、たじま、数えたらきりがないな、こりゃー。
むかしは、よかった。こんなテンポでいいでしょうか? そんなブタども4匹(石井・吉川・木下・ぼく)が、賭にコーヒーにケーキをつけたかつけないかをめぐって大論争をはじめ、ついにブッタぶたない、と喧嘩をはじめて、1時間。(今にして思えばバーチャル・リアリティの)ブッダが(インターネット<注1;これは業界での単なるおまじない>をかいして)突然現れ、ブタどもにカガミをほんなげた。びっくりしたブタどもはそれぞれ、カガミの自分に向かって、喧嘩をしかけた。相手が違ったことには、まったく気がつかなかった。しかし、ほんとうにそうだったのだろうか。いまこそ四半世紀前のあの謎を解かねば。そうなのだ、解釈論というやつは、いつもこうして始まるのだ。しかし冴えんな。シュール<注2;これは昔のいいかた、いまは前述のV・Rといえば、なんでも許される>な駄洒落でしかない安易なメタファーほど醜いものはない、のだぞ、わかっているのか、ブタくん、ギクッ。

わん・のーと・さんば。いかん、また音をはずした。 誰でもよかった、喧嘩さえできれば、なのだろうか。それとも、喧嘩の意味さえわからない、ただのブタだったということなのだろうか。とすれば、もちろんブタにはカガミの意味などさっぱり分からなかったはずだ。そうではなくて、ブタはブタらしくいきることで、筋をとおしたかったのかもしれない。ブタはブタであって、しかしブタではない自分を知りたいと思っていたのかもしれない。知りたいのは、ブタの力なのだ。どこまでいってもブタならば、ブタでしかないが、ブタであることの境界を知りさえすれば、そこからブタでない自分を想像する力がうまれるのだ。ブタはブタであることで、ブタではなくなるのだ。四匹のブタは、自己言及<注3;テクニカル・タームとしてはかなり理解困難、しかし知的ファッションとしては超有効>の意味を身体としてすでに理解していたのだろうか?
イン・ナ・メロー・トーン。酔ってみたい時もあった、とける・とけない・とけたい。
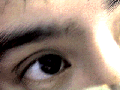
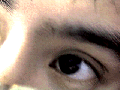
問題はカガミなのだ。カガミはいつもズレをもたらす。だからカガミなのだ。ブタは、びっくりした。なぜか。ブタは、自分であって自分でないブタにたいして、どんなポーズをとればいいのか、途方にくれたのだ。ブタは、突然目の前に現れたブタに、一瞬奇妙な懐かしさを覚えた。しかし自分を知らないブタは、その懐かしさの意味が分からず、とまどい、うろたえ、さけび、そしてそれは敵だと思うことにして一応は闘う素振りをみせることにした。ぶー、しかし何か違うぞ、と感じていた。頭では闘うポーズを忘れず、しかし体では何か親近感を覚えることで、ポーズ以上の行動はなぜか抑制されていた。ブタには、体で考えることが似合っていた。 カガミは、自分と非自分を同時に存立させる奇妙なものだ。カガミのズレの魔力がどんなものだか理解できれば、不思議な世界は単なる摩訶不思議を超えて知的な想像性を喚起する世界として再構成されるはずだ。それが創造という行為を誘発するのだ。としたら、ブタは突然現れたカガミによって否応なしに創造的にさせられた、という推論は無謀だろうか。ブタは、自己の身体をカガミに共鳴させることで、自己言及を無意識のうちにやってしまったのだ。知らないうちに、知ってしまったのだ、ブタであって、ブタでないブタを。そんな装置に偶然めぐりあえたことに、ブタは感謝しなければならなかったのだ、なのに若いという無知がその認知を拒んでしまった。このカガミこそ、自己超越のメディアだったのだ。四半世紀たって、やっとわかった。こんな経験がいまの僕を支えるのだ。
4・5・6。かけることで、ぼくはただ境界を知りたかっただけなんだ。
ばい・ばい・ぶらっくばーど。でも、かこにバイバイ、でも、カガミに至上の愛を。

 BACK
BACK