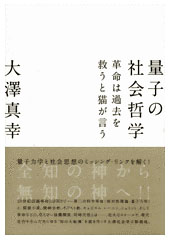アレグザンダー、ヴィトゲンシュタイン、ハイデガー:『仏教が好き!』を読んで
河合 隼雄さんと中沢 新一さんの『仏教が好き!』、いまの僕には、めちゃくちゃ面白かった。
宗教を俯瞰してみたときに、仏教的な思考がこれからの世界にとって重要となるということがわかったし、自分がこれまで何をやってきて、これから何をやるべきなのかということを考えることができて、とても勉強になった。なかでも最も「おおおおー!」となったのが、以下の部分。
これはまさに、アレグザンダーが目指した質が言語化不可能であるとして「名づけ得ぬ質」と呼んだことに通じるし、僕らがパターン・ランゲージをつくり実践知に対して言語を当てることは、「実践知を記述する」ことではなく、あくまでも、直接は表現できない実践知を指し示す言葉をもつことで意識して実践することができるきっかけをつくり、「巡回」するためである、という僕の感覚に通じる。
この箇所で、ヴィトゲンシュタインとハイデガーについて語られたところを読んで、興味深いことに気付いた。
クリストファー・アレグザンダーは、『時を超えた建設の道』では、質そのものについては沈黙した(質を生成するパターンについては語った)という意味でヴィトゲンシュタイン的であり、『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』では、その質に踏み込んで語った(センターとその関係性を捉えた15の基本特性)と言う意味で、ハイデガー的であるといえるだあろう。『時を超えた建設の道』から『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』へのアレグザンダーの変化は、ヴィトゲンシュタインからハイデガーへ、ということで捉えられるのかもしれない。
ヴィトゲンシュタインとハイデガーは、僕にとって、気になる存在ではあったが、なかなか切り口がつかめないでいたが、ひとつよい切り口を見つけたと思った。井筒俊彦やホワイトヘッド、ベイトソンなどとともに、読んだり、再読したりしたい。
ずっと気になってた中沢さんの他の本も読みたいし、発見と知的好奇心を刺激される一冊だった。
河合 隼雄 , 中沢 新一, 『仏教が好き!』, 朝日文庫, 朝日新聞出版, 2008

「ブッダが『空』と言っていることは言語化不能であるというのが原則なんですね。密教だけではなくて、『般若経』でも、『言説不能、言葉で言うことは不能、だけどこれは確実に、肯定的に、ある』と言われます。」(中沢, p.185)
「ユングがよく使う言葉がありまして、英語で circum ambulation、『巡回』という意味です。僕の好きな言葉なのですが、結局、中心には入れないということなんですよ。われわれはまわりをめぐるだけ。まわりを何度も何度もめぐることによって、いわば中心に思いをいたすなり、中心を感じ取るなりということはできるけれども、中心に入ることはできない。僕もそのように思っているわけです。」(河合, p.186)
「すべて比喩で回転しつづけているけれども、その中心部には言葉の能力をもっては踏み込めない部分があるということなんでしょうね。」(中沢, p.187)
「おそらくぐるぐる回っているうちに体験としてはある、ということなんでしょう。」(河合, p.187)
これはまさに、アレグザンダーが目指した質が言語化不可能であるとして「名づけ得ぬ質」と呼んだことに通じるし、僕らがパターン・ランゲージをつくり実践知に対して言語を当てることは、「実践知を記述する」ことではなく、あくまでも、直接は表現できない実践知を指し示す言葉をもつことで意識して実践することができるきっかけをつくり、「巡回」するためである、という僕の感覚に通じる。
この箇所で、ヴィトゲンシュタインとハイデガーについて語られたところを読んで、興味深いことに気付いた。
「『言葉にならないものは沈黙しなさい』というヴィトゲンシュタインのような哲学者もいる。われわれのできることはせいぜい言葉でまわりをめぐることで、中心の言葉にならない領域に関してはもう『黙れ』と。そのとき、ヴィトゲンシュタインはどこにいるのでしょう。彼の心は、この中心にいまあす。ただ、そこについては黙ろうとしている、黙らなくてはいけないという認識をもたらすものがある。」(p.188)
「ハイデッガーが「存在」とか言うじゃないですか。『在る』とか。あれは言ってみれば真ん中のすぱんと抜けたところを『在る』と言っているわけですよね。」(中沢, p.187)
「ところがわれわれは『存在』ではなくて『存在者』だから、まわりをぐるぐる回っているに過ぎないものなのに、中心部には『在るが在る』というふうに彼は言うわけですね。何でそのことをみんな驚かないのかと。」(中沢, p.187)
「『私』はその『在る』の中心部にいる。彼は踏み込む。そこからいろいろな言葉が紡ぎだされて来る、その中心点から、あの独特の言葉と思考がつぎつぎと湧き出てくる。」(p.188)
クリストファー・アレグザンダーは、『時を超えた建設の道』では、質そのものについては沈黙した(質を生成するパターンについては語った)という意味でヴィトゲンシュタイン的であり、『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』では、その質に踏み込んで語った(センターとその関係性を捉えた15の基本特性)と言う意味で、ハイデガー的であるといえるだあろう。『時を超えた建設の道』から『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』へのアレグザンダーの変化は、ヴィトゲンシュタインからハイデガーへ、ということで捉えられるのかもしれない。
ヴィトゲンシュタインとハイデガーは、僕にとって、気になる存在ではあったが、なかなか切り口がつかめないでいたが、ひとつよい切り口を見つけたと思った。井筒俊彦やホワイトヘッド、ベイトソンなどとともに、読んだり、再読したりしたい。
ずっと気になってた中沢さんの他の本も読みたいし、発見と知的好奇心を刺激される一冊だった。
河合 隼雄 , 中沢 新一, 『仏教が好き!』, 朝日文庫, 朝日新聞出版, 2008

最近読んだ本・面白そうな本 | - | -

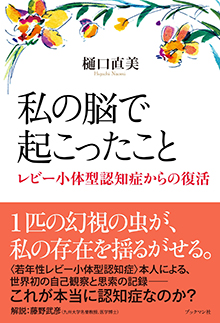 今年出版された樋口 直美さんの『私の脳で起こったこと:レビー小体型認知症からの復活』を、改めてじっくり読み直した。
今年出版された樋口 直美さんの『私の脳で起こったこと:レビー小体型認知症からの復活』を、改めてじっくり読み直した。