2002年度秋学期 小熊研究会1
ポール・ウィリス『ハマータウンの野郎ども』(ちくま学芸文庫)まとめ
総合政策学部4年 高野裕美
79905072 s99524ht
本書は2部8章からなる本であるが、第一部は生活誌であり第二部の分析をよりよく理解するための調査結果であるので省くこととし、第二部「分析」の第四章から第六章までを中心的にまとめることとする。(第七章は抽象的な文化の再生産論であり、第八章は教育現場への具体的な提言であるため、最後に簡潔に補足程度に付け加えた。)
1.問題意識と主要な概念
本書は、労働階級の男子生徒たちが、資本制の中で自らを貶める結果になるにも関わらず、自ら進んで筋肉労働の将来を選び取っていく不思議を解明している。第一部では、このことを定性的に生活誌という形をとって調査研究しており、第二部は生活誌で把握しきれないメカニズムを理論的に整理している。
第一部の生活誌から明らかになることは、簡単にまとめると次のようなことである。労働階級の男子生徒たち(<野郎ども>)は、学校文化を自らの価値観によってインフォーマルなものに読み変える(異化する)過程で既存の労働階級文化に影響を受けながら反学校文化を生み、就職すると今度は仕事場のルールを異化することで労働階級文化を生む。こうして彼らはある種のするどい<洞察>を持ちながら社会通念を転倒させている。しかしながら、その道すがら<洞察>は複雑な<制約>をうけてあらぬ方向へ捻じ曲げられ、結局若者たちは自らを手労働の世界に幽閉してしまう。
第二部は、その<制約>の複雑性ゆえに<野郎ども>の意識にすらのぼらない、それゆえ定性的な調査記述では明らかにできない、この顛末をおおもとで規定している要因を理論的に明らかにする。
2.<洞察>の光
反学校文化が見抜く公教育の論難は3つある。3つに共通するのは、いずれも学校が提供する「等価物」の性質を暴いているという点である。
①学校側は、生徒たちに順応と服従を要求して、その見返りに「成績証明」や将来の昇進や昇格を用意する。しかし労働階級の男子生徒たちは今を「機会の損得勘定」で捉えるかぎり、なんら等価交換になっていないと見抜き、今の喜びに生きることを選択する。つまり、労働階級の男子生徒たちは、成績証明や順応が将来を約束するということが「単なる一片の教育神話」にすぎないことを洞察した上で、「順応者に約束される堅苦しい安寧や、わずかばかりの、幻想的でさえある昇進・昇格をあえて棒にふって、市井の片隅で浮き沈みする道を選びとっている(P208)」。たとえ、労働階級の男子生徒たちがいかに順応になり公教育に与するようになったとしても、その「成績証明」の分だけホワイトカラーの就職先が増えるわけでもなし、資本家ですらそれを増やす事は出来ない。だからこそ、学校は順応さや服従の見返りに「成績証明」を差し出すが、その「成績証明」は将来の可能性を広げることもなく、なんら役に立たないのであるから、ここに「等価物の不公正」を見て、順応や服従を拒否する。
②学校側が見返りとして提示する「成績証明」は、将来の可能性を広げるという約束も果たさないばかりか、それの持ち主にふさわしい質の労働機会をもたらすことも約束しない。それは単なる虚構であり、どんな「成績証明」をもっていても、すべての労働には一般的な等質性が見出せるのである。昨今の労働のますますの非熟練化は、まさしく労働における質の違いを否定する傾向である。また、ブルデューやパスロンが言うように、「成績証明」などというものは支配階級の権威をより強固なものにするだけである。<野郎ども>が、自らを苦しめもする「成績証明」を拒否することにはそれなりの合理性が認められる。
③反学校文化は、集団原理と個人原理が相矛盾すること、しかしそれを公教育の側は混用していることを見抜いており、個人原理に反抗する。公教育は、「だれでも努力すれば報われる」と個人主義をおしつけるが、実際すべての人が努力をしたからといって階級や集団の全体が上昇移動することなどその本性上難しく、またそれはすなわち階級社会自体の破壊に他ならない。つまり、だれでも努力すれば、「無階級という虚偽意識」を手にいれることが出来るのにすぎないのであって、それは<野郎ども>が有している自由と引き換えにするには、不公正である。結局のところ、全員が努力をしても少数の選ばれた人間しか上昇することは出来ないのであって、それは②で触れたとおり、階級関係をより強固なものにするにすぎない。しかし公教育の側はそれをひた隠しにして、どんな「低い」階級や状況においても「だれでも努力すれば成功できる」と弁明して、多用な価値観や生き方を提示する。しかし、それも結局労働の同質性から容易に否定し得るうつろなものなのである。
こうして、上記3つの論難を指摘することで、反学校文化は学校側が企てる「等価交換」の不公正を暴こうとする。そしてその過程で彼らは、さらに労働のある特殊な性質に関する<洞察>を獲得している。それは労働力の可変性であり、またその意味での労働の全般的抽象性のことを指す。
1) 労働力の可変性
労働力とは、資本制生産過程において唯一の可変的契機である。労働力は市場で売り買いされるにも関わらず、その結果的な支出水準は不変量に固定されない点で他の商品とは異なる。つまり、労働力とはたとえある定まった金額で買われたとしても、その金額ぴったりに支出される性格のものではないのだ。だからこそマルクスも指摘したように、労働力こそ利潤の源泉であり搾取の対象となる。ただし、だからこそ労働力の支出は、それでもなお一定程度の自主管理能力を保持しているはずである。
学校でおこる交換関係は、労働力市場の交換関係と相似た性格を持っているが、その労働力自主管理性という性格を多分に残すことに成功する。というのも、生産現場においてはそうした労働力の自主管理が「明日食べるものへの危うさ」につながってしまうため十分に発揮出来ないのに対して、学校ではそれほど抜き差しならない状態ではないゆえ、全面発揮される。したがって、<野郎ども>は教師の学習の質量に対する要請に、ゲリラ的な秩序破壊行動で応戦するのだ。
反学校文化は、公教育が装う「等価交換」の虚偽性を見ぬき、「異化」することで、相似た労働市場の交換関係を先取りすることに成功していると見ることができる。つまり、一人一人が自覚的にこうした認識に至っているとは考えられないまでも、集団として、労働力の可変性とその自主管理能力という性質を<洞察>するに至っていると考えられる。だからこそ、就職後に先輩に「気楽にやれよ」などと言われたとしても、それを実践をもって実感しているのは、むしろ入ってすぐの新米労働者の方かもしれないくらいである。インフォーマルな職場文化は、見せかけの「等価交換」を暴いて、資本家による搾取を免れようとする試みである。(資本家の側が「等価交換」を装うひとつの戦術として週給がある。週給は「時間」と結び付けられて計られるけれども、実際の労働は可変的で不変量に固定されないはずである。実際の労働は働いた日数や残業の時間にかかわらず、発揮された人間性そのものなのであるから、週給とは見せかけの等価交換である。)
2) 労働の全般的抽象性
労働は、①で指摘した「労働力が不変量を固定されない可変性をもったものである」という点において「全般的抽象性」を有している。<野郎ども>が、就職先を選ぶときに職務の具体的な内容はさておいて、文化的な雰囲気が自分にしっくりくればさっさと決めてしまうのは、労働はどれを選んでも所詮同じという考えにたっているからであり、これはその「労働の全般的抽象性」という<洞察>の上に立脚しているのである。
労働の具現性などというものは所詮「利潤」から演繹されたものにすぎないのであって、利益が出なくなれば生産過程も製品も容易に変わりうる。こうして具体性を失った労働を「抽象的労働」と呼ぶことができる。抽象的労働は、搾取の対象として、購入された価格以上のものを生み出す存在として一般的等質を持つ。また、いくら声高に多用な職務があることを強調したところで、第3次産業であっても製造業の労務管理モデルが使われていたり、労働のあらゆる側面が「時間」に結び付けられていることを見れば、その一般的等質性は疑うところがない。そしてそうした等質化の最終段階として、ギルブレスが提案したあらゆる労働を唯一最適な作業方法に向けて収斂させていく努力がある。
労働階級の男子生徒たちは、こうした<洞察>のうえにたって、与えられた職務への主体的な関わりを制限する論理をもつ。そしてそれは十分に資本制生産の阻害要因になり得るものである。
3.<制約>の影
2で見たように、<野郎ども>の<洞察>は十分発展する余地をもった創造的なものとして捉えることができる。にもかかわらず、現実には組織化・政治的表現にまで成長することを阻害する要因が存在するために、彼らは自らを手労働の世界に幽閉してしまう。その要因こそ<制約>であり、ここで明らかになる3つの分断とその複雑な結びつきである。3つの分断とは、①精神労働と肉体労働の分断 ②男女の分断 ③人種間の分断 である。特に、①と②の複雑な結びつきが重要である。(③は補足的に説明されている。)
①精神労働と肉体労働の分断
精神労働と肉体労働の分断は、先述した「等価交換」の拒否、ひいては個人主義の拒否から来ている。反学校の文化は、学校が求める等価交換の不公正を暴き、個人主義の虚偽性を明らかにして、どちらも拒否する。その過程で、野郎どもは精神的行為一般にも学校側の権威をしょわせて、あちらへ追いやってしまう。そうして彼らのなかでは「手足でかせぐ」人間と「頭でかせぐ」人間とに分断されてしまい、彼らのせっかくの労働の一般的等質性という<洞察>が、「すべての“手労働は”みな同じ」という限定的な等質性へすりかえられてしまうのである。そして、その認識は「手労働で汗することこそ意味作用を持つ」という認識まで生んでいってしまう。反学校文化の側が学校に対して「短い勝利」を手にして喜ぶ分だけ、支配的なイデオロギーは内面化されてしまうという矛盾が起こっている。
②男女の分断
男女の分断とは、すなわち性差別の増幅である。反学校文化の側は、学校制度を異化するために、その根拠やヒントを広く一般の労働階級に通有の文化に求める。そのため、労働階級における男性優位や性別役割分担、家父長制などの性意識がそのまま反映されてしまうのだ。
■①と②の複雑な結びつき ~<洞察>のねじれ~
①と②が結びつきをもたなければ、反学校文化の<洞察>の発展性は損なわれなかったかもしれない。悲劇は複雑な結びつきにこそある。
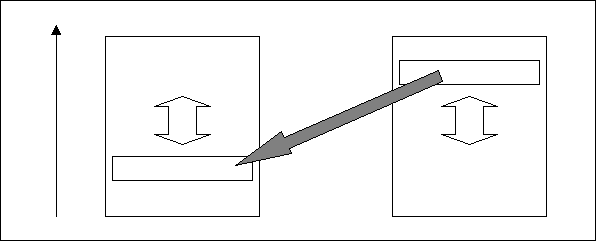
優位 ① ②
精神労働 男
肉体労働 1)補う 女
2)底上げ
劣位 3)精神労働を見下す
上記の図のように結びつく。まず、先ほどから何度も言及しているように個人主義の原理は「だれでも努力すれば成功できる」といいながら、本当に全員が努力したとしても階級全体で上昇することはできないという、本質的な矛盾を抱えている。しかし、そうした矛盾を抱えていることを<洞察>しながらも、個人主義原理のレースに取り込まれている以上、その参加者はそのレースで負けた以上、能力や結果としての報酬が低いことは認める。重要なのは、<野郎ども>が個人主義原理を拒否して能力が低いことは認めても、社会的地位が低いとは認めないことだ。彼らは社会的地位の段になると、精神労働と肉体労働のものさしを逆転させるのである。そして事実<耳穴っ子>も、そうして<野郎ども>がものさしを逆転させて進んで肉体労働に就いてくれるおかげで、精神労働に近づくことができ、社会的地位を確かめることができる。本当は大差ない労働力に、積極的に能力差をとなえる。
この<野郎ども>の価値観の逆転は資本制生産に内包された必然ではない。ここに男女の分断との結びつきが働くのである。肉体労働は、男女の分断にみられた家父長制、男性優位の思想と結びつき、その地位を補完され、底上げされるのである。女性を見下す男性としての優越意識が、精神労働・肉体労働という常識的な尺度における彼らの劣勢を補い、価値観を転倒させる。そして他方の精神労働は、女性的なイメージと結びつき逆に見下されるようになる。この男性優位の思想は、現実の労働階級文化によってますます強められ、最終的には人間的本質に基づく優位であるかのような強固な思いこみにつながっていく。それにしたがって、当初の「労働の全般的抽象性」という<洞察>は完全に捻じ曲げられて、現実の精神・肉体労働の分業体制も固定的に捉えられてしまうのである。また、搾取関係や労働の可変性への<洞察>も、男らしさと結びついてやり遂げることが重視される目的論をとり、意識の枠外へ捨て去られてしまうのであった。これが悲劇的な結びつきのメカニズムである。
③人種間の分断
人種間の分断は、以上の男らしさと結びついた肉体労働の領分にも下限を設けるためになされるものである。例えば、ウエスト・インディアンは白人労働階級よりも汚い仕事をうけもつ人種として捉えられ、アジア系移民たちは上層移動や努力を志向する傾向があるため、<耳穴っ子>と同様の視線で見られると共に、「労働者“らしく”しろよ」という反感を持って捉えられる。
4.文化とイデオロギー
これまでの議論では外部からのイデオロギーの力を過小に評価する部分があったかもしれない。したがって、この章では筆者の考えるイデオロギーの働きが論じられている。それは簡潔に述べるなら、文化とイデオロギーは相互作用のなかでお互いに影響をうけあいながら変化していくということである。ここでは“イデオロギー”を「文化の側の不徹底な洞察をなおさら厳しく制限する」ものとして「支配としてのイデオロギー」の機能を、文化との関わりのなかで考察しておく。
①固定化への誘導
そもそも<野郎ども>の<洞察>は言葉になっていないものであるから、その不確かでもろい部分はイデオロギーの作用によって容易に“自然主義”の文脈に取り込まれてしまうのである。“自然主義”とは「まあこういうものだろう」というような捉え方と言えるだろうか。別の言葉でいうと「常識」である。反学校文化は一面性や限界を拭い切れないまま、常識に流され歪められて、「歴史を相対化するとっかかりだけが宙に浮いているのである」。
②不能化
不能化の段階に至っては、虚偽性を<洞察>したはずの個人主義や能力主義の助言が脳裏にある一定の痕跡を残しており、それによってなおさら自然主義や常識にとりこまれてゆくのである。しかしながら、それは一方的なイデオロギーの勝利ともいえないのであって、反学校文化の側にそうしたイデオロギーを迎え入れる素地があるからこそ、影響を及ぼし得るのである。
しかしこうしたイデオロギーによる誘導→不能化の段階にも増して、反学校文化の内部にある「内なるイデオロギー」の働きも無視できない影響力を持っている。それは、弁証法的に言えば「対自」の状態にとどまっているという弱点であり、ルールに対する例外としてのみ留保され得る反学校文化という存立基盤の弱さである。つまり、学校に対する反学校文化というその対立を生んでいる社会の仕組みそのものへの洞察や分析視点を欠いているのである。したがって、いつまでも反学校文化は「対自」的存在にとどまるのであり、内なるイデオロギーからの詰問に対して反学校文化は苦し紛れに弁明するしかないのである。これが根本的に反学校文化の政治的去勢をもたらしているのであり、イデオロギーの作用を容易に取りこんでしまう内部的弱さであろう。
5.おわりに
第七章では、これまでの議論を踏まえて、文化の再生産理論が総まとめされている。さらに簡単に述べるならば、再生産には2つのモメントがある。
①大局的な規定要因そのものが文化のレベルに媒介される→洞察する
②その洞察を外部構造としてしまうことで、かえって自らを規定する→自然主義に帰してしまう
また、この章では資本主義制の不確実性と労働階級に対する著者の楽観的な視点が描かれてもいる。著者は資本主義を「何を結果するかもしれない自由の余地を広げながら支配関係への同意をわずかながらにとりつけてゆくという動的な過程」とか「延命と絶命の条件を同時に合わせもっている賭けである」とか定義して、そういう過程のなかで労働階級が半ばまで至る<洞察>に、「突発的な変動の予感」を淡く期待している。
また、第八章は教育現場への具体的提言である。本書では全体を通じて、構造と文化の相互作用のなかに政治的展開への希望が見出されるという論調が続いているが、著者は、本書が具体的提言において理論と実践の一体化を促がす理論書のようなものになればよいと考えているようである。
<蛇足(感想)>
一度夏休み中に読み、もう一度先生の解説や発表を思い出して読み返しましたが、先生のおっしゃる通り「よくできた」「かっこいい」本だと思いました。わたしは面倒くさがりの性分が災いしていつも詳しい資料や調査は読みきれず、すぐに抽象的な理論を求めてしまうのですが、本書は調査部分が読み易いこともあって勉強になりました。先生も「自分が綿密な調査や資料を踏まえて書くのが好きだから、著者に共感する」とおっしゃっていましたが、改めて読み返してみて、それが少し理解できた気がしました。そしてフーコーをじっくりと読んだ去年の秋学期とはまた別の意味で、自分にもこんなことができたら…という思いが募りました。