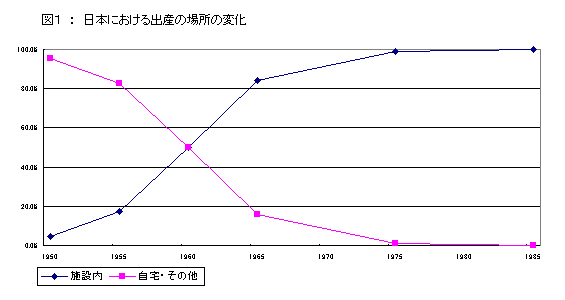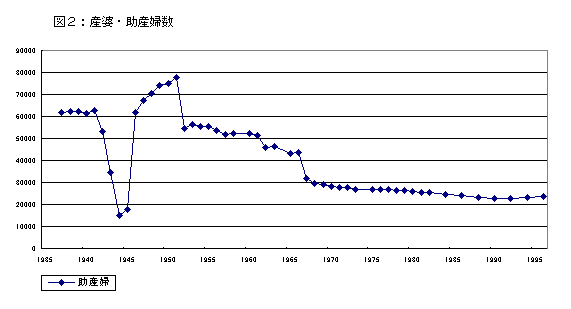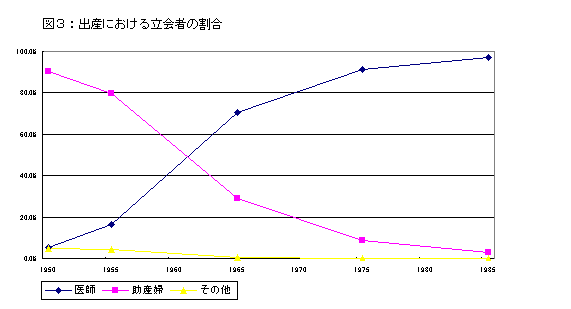�Y�k�E���Y�w�@�@���i���Ƃ��̕��Q�A�����ĉ\��
��������w���S�N�@79710449
�n�ӑ��is97045dw�j
���������͂��ׂĐV�����ɒ����ċL�ڂ��Ă���܂���
���_
�@���݁A�o�Y��99���ȏオ�{�ݓ��ɂ����čs���Ă���B[1] �����ł����{�݂Ƃ́A�a�@�̎Y�ȁA�Y�w�l�Ȉ�@�A���Y�@�A��q�Z���^�[�Ȃǂ������Ă���B���̂悤�Ȏ{�ݓ����͂���������������嗬�h�ƂȂ����̂��낤���B�����̐}1�����Ă��炢�����B���̍��x�o�ϐ����ƕ��s���ċ}���ɐi��ł��邱�Ƃ�������B���̂��Ƃ́A�o�Y�Ƃ��������̎������Ƒ���n��̐l�ԊW����}���ɐ藣���ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ă��邾�낤�B
���āA���̂Ƃ��{�ݓ��ł̒S���肽��l�Ԃ͒N�Ȃ̂��B����͎Y�Ȃ̈�t�ł���A���Y�w�ł���B�����̐l�́A�u���Ƃɂ���ď��Y�����邱�Ƃ�F�߂�ꂽ�l�ԁv�ł���A���̂��߂��́u���i�v�����l�X�ł���B�t�������A���i�������Ȃ�������̍s�ׂ�E�ƂƂ��čs���Ȃ��̂ł���B�������A���R�̂��Ƃł��邪�O�ߑ�ɂ����Ă��̂悤�Ȏ��i�Ȃǂ͑��݂��Ă��Ȃ������B���Ƃɂ���ĔF�肳�ꂽ���i�ɂ���ėl�X�ȐE�Ƃ��K�肳���̂́A�ߑ���L�̌��ۂ��Ƃ����Ă悢���낤�B�E�Ƃ����i�����邱�ƂŁA���̓��e���剻����ƂƂ��ɓ��艻����B���̋ߑ���L�̌��ۂɂ����āA�����炳�ꂽ���͉̂��ł���A�t�Ɏ���ꂽ���͉̂��ł���̂��낤���B���ꂪ�{���|�[�g�ɒʒꂷ����ӎ��ł���B�����ŁA�O�q�����o�Y���e�[�}�Ƃ��A���̏o�Y�ɐ��I�Ɋւ��ׂ����i�����ꂽ�E�ƁA���Ȃ킿�Y�k�E���Y�w�ɏœ_�ĂĎ��i���̈Ӗ����l���Ă䂫�����B[2]
�@�{���|�[�g�ł́A��1�͂ɂ����ē��{�̎��i���x�j�Ɋւ��ĊT�ς��A��Q�͂ɂ����đ�P�͂ł̋c�_�����~���ɎY�k�E���Y�w�̐��x�j���݂Ă䂭�B����ɁA���i���ɂ���Ď���ꂽ���̂����ł������̂����Y�k�E���Y�w���Ƃ��čl����B��R�͂ł͏o�Y�Ɋւ���V�������݂��l�@���A���i���ɂ���Ď���ꂽ���̂Ƃ̊W�����l�@����B
��1�́@���i
��1�߁@���i�̒�`
�@�܂����i�̒�`������K�v�����邾�낤�B�u���i�v�Łw�L�����x�������ƁA�u�g����n�ʁB����B�܂��A���̂��߂ɕK�v�Ƃ��������v�ƂȂ��Ă���B�����Ŗ��Ƃ������̂́A�E�Ƃ̏����Ƃ��Ă̎��i�ł���B�Ⴆ�Γ����p��Ɋւ��Ă̎��i�ł��A�^�A�Ȃ̔F�肵�NJ�����u�ʖ�ē��Ɓv�ƁA���c�@�l���{�p�ꌟ�苦��F�肷��u���p�p��Z�\����v�͂܂������قȂ���̂ł���B�O�҂͌��I�E�Ǝ��i�ł���̂ɑ��āA��҂͔\�͂������w�W�Ƃ��Ă̈Ӗ������ȊO�@����̌��͂͂����Ȃ��B�{�e�ɂ����Ď�舵���̂͑O�҂Ƃ������ƂɂȂ�B
�Ҍ��͂��̐E�Ƃ̏����Ƃ��Ă̎��i���u���I�E�Ǝ��i�v�ƌĂсA�T�̏����������Ē�`�����B���̏����͂P�D�@�����߂Ȃǂɂ���Đg�����K�肳��A�Q�D�E�Ə�̐g���Ɍ����A�R�D�s���葽�������Ȃǂ̍s�������Ȃǂ̋����I�R�����邱�ƂŁA�����I�ɕ����̐l���l���ł�����̂ł���A�S�D�������ȊO�ł��擾�\�Ȑg���ł���A�T�D��Ƃ��Ēm���E�Z�p�Ɋւ�����̂ł���A�ƂȂ��Ă���B[3] ���̒�`��p���邱�ƂŁA�����قǂ̢�ʖ�ē��ƣ�Ɓu���p�p��Z�\����v�̈Ⴂ�����N���ɂȂ邾�낤�B����A���i�Ƃ������t���g���Ƃ��́A���̌��I�E�Ǝ��i���Ӗ����Ă��邱�ƂƂ���B
��Q�߁@���{�ɂ�������I�E�Ǝ��i���x�j
�@�Y�k�E���Y�w�̎��i�̐��x����j�I�ɍl�@����O�ɁA�O�߂Œ�`�������I�E�Ǝ��i�����{�łǂ̂悤�Ȍo�܂Ő��x�Ƃ��ċK�肳��Ă����̂��A�܂��ǂ̂悤�Ɉ����Ă����̂����T�ς���B�Ҍ��͓��{�̌��I�E�Ǝ��i���x�̕ϑJ�����̂T�̎����ɕ��ނ��čl�@���Ă���B[4] ���ꂼ��̓������ȒP�ɏЉ��B
�E�n������1868�i�������j�N�`1878�i����10�j�N��
�@�@�@1868�N�́u��w����y��w�m�����ւ���z���v�i�������z����1039���j�ɂ����
��t�����Ƃ��F�肷�鎑�i�Ƃ��Ē�߂��̂��͂��߂ɁA���i���݂̖�t�j�A�Y
�k�i���݂̏��Y�w�j�A���w�Z�E���w�Z�E��w�̋����Ȃǂ����i�Ƃ��Ē�߂�ꂽ�B��
�̎����͊w�Z���x�������ĂȂ��A���i�̔F��͔F�莎���ɂ����̂�]������̊J
�Ǝ҂͖������ŔF�肷����̂Ȃǂ����������B[5] �܂��A��ʂ̊w���ɂ�閳�����F��
�������݂�ꂽ�B
�E��������1879�i����11�j�N�`1908�i����40�j�N��
�@�@�@����30�N�Ԃ́A����܂łɐ��肳�ꂽ�����i���x�̖@�I�Ȑ����ƕ��������̌X����
���Ă�������B�F��`�����A�l�X�Ȏ��Ɗw�Z�E���Ɛ��w�Z�E�u�K���Ȃǂ̖@��
�w�肳�ꂽ�u�w��Z�v���ݗ����ꂽ���Ƃɂ��A���i�F�莎�����i�҂ƂƂ��ɁA��
�̎w��Z�̑��Ɛ��ɂ͖������ŔF�肷��`���Ƃ���̂������݂�ꂽ�B���̎�����
�����́A���̎w��Z�Ɍ����ɕ\���悤�ɁA�����F�肩��w���ˑ��Ɉڂ������Ƃ�
���낤�B
�E�Q�i����1909�i����41�j�N�`1945�i���a20�j�N��
�@�@�@���̎����́A�Ȋw�Z�p���������ꔭ�B�������Ƃɂ��A�H�ƌn�̐E�Ǝ��i�������o
�������B���̂悤�Ȏ��i�͈ȑO�ɂ݂͂��Ȃ��������̂ŁA�Ⴆ�A�d�C���Ǝ�C
�Z�p�Ҏ��i�i���݂̓d�C��C�Z�p�Ҏ��i�j�⎩���ԉ^�]�Ƌ�[6] �Ȃǂ̎��i���o�ꂵ���B
�E���v����1945�i���a20�j�N�`1956�i���a31�j�N��
�@�@�@����10�N�͐�O�̎��i���x�̌��������͂����������ł���A���̑������������ꂽ�B
�������F�萧�x���p�~����A��������݂̂̔F������ɕύX���ꂽ���̂������B��
���A���ȉq���m�A���ʎm�ȂǐV�����Z�p���i�������n�݂���Ă���B
�E���W����1957�i���a32�j�N�`���݂܂Ł�
�@�@�@�Z�p�v�V�̂����Ȃ��̂��̎����̓����́A�Z�p�̊v�V�ɂƂ��Ȃ������̐��x�̏[��
�ƁA�Ǘ��I�E�Ǝ��i�E��Ǝ�C�I�E�Ǝ��i�̑���ɂ݂邱�Ƃ��ł���B���̎�����
���i�̗ʓI�g��͒������A���i�Љ�Ƃ����Ă������l����悵���̂����̎�������
�Ƃ����Ă��ǂ���������Ȃ��B
�@�ȏ�T�̎������T�ς������A���{�̌��I�E�Ǝ��i�͍���̕K�v���i��t�E�������i�Ȃǁj�ƁA�Z�p�v�V�ɂ��K�v���̑���Ƃ�����̒�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ������邾�낤�B�����ŁA���_��������ł���B
��R�߁@���i�̖��_�ɂ���
�@��P�͂̍Ō�ɁA���i���̖��_�Ɋւ����s�������Љ�Ă����B
�q�E�R�����Y�́A���i���擾���邽�߂̎�����w�����̂��̂ւ̔ᔻ���s���Ă���B�R�����Y�́u����E�Ƃɂǂꂾ���̊w�𐅏���v�����邩�́A�����ݒ�ł��邾���̌��͂��������W�c�̗��Q�W�����f���Ă���v[7] �Əq�ׁA�������i������邱�Ƃɂ���ē��艻����܂����Љ�����邩�͏W�c�̗��Q�W�⌠�͊W�ɂ���Č��߂��Ă���A���i���̂��\�͂������Ă��邱�Ƃ�K�����������Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ�_���Ă���B
�܂����S�q�́A���i�ƃW�F���_�[�̊W��_���A���i�������W���E�����Ƃ����w�E�����Ă���B[8]
�@�ȏ�A���i�ɂ��āA���{�ł̐��x�̕ϑJ�ƁA���_���݂��B���͂ł͂���̓I�ɎY�k�E���Y�w�Ƃ����o�Y�Ɋւ��鎑�i���l�@���邱�ƂŁA�����ł͎w�E����Ȃ��������i���̖��_���l���Ă݂����B
��Q�́@�Y�k�E���Y�w���x�j
��P�߁@���i���ȑO
�@�O�ߑ�ɂ�����o�Y�́A���Y����l���K���������Ȃ��ꍇ������A�n��ɂ���ďo�Y�l���̍��������������B�܂��A���̏��Y�҂̌Ăі����n��ɂ���č�������A�u�g���A�Q�o�o�v�u�g���A�Q�o�A�T���v�u�R�g���o�o�v�u�R�i�T�Z�v�u�R�[���{�v�ȂǗl�X�ɌĂ�Ă����B[9] ���ɂ����ďo�Y�Ƃ�����厖��S���ޏ��B�́A�n��ɂ����邨�Y�̑��ݕ}���̕R�тł�����d�v�Ȉʒu�����ߑ��h����Ă����Ƃ���������[10]�A�������A�ق�Y��̂��Ƃ������Ĉ�ʂɂ͑G�Ƃƌ����Ă����Ƃ����w�E������B[11]
�@���̂悤�ɁA�n��ɂ���č��͂��邪�O�ߑ�ɂ����鏕�Y�҂ł���u�g���A�Q�o�o�v��́A���ꂼ��̒n��ɂ����ēƓ��̕����̒S����Ƃ��đ��݂��Ă����B
��Q�߁@�Y�k�̎��i��
�@�u�g���A�Q�o�o�v�炪�A�S���ꗥ�Łu�Y�k�v�Ə��Ȃ��Ƃ��@����Ăꂽ�͖̂����ȍ~�ł���B
�@�������{�́A1968�i�������j�N12���������z�B�ɂ����ĎY�k�̑فE����s�ׂ��֎~����B����́A���N11���ɏo���ꂽ�u��w����y��w�����ւ���z���v�ɂ���Ĉ�t�Ɩ��̎��i���߁A�����������ƂƂ̐�������ۂ��߂ł���Ɛ����ł���B�Ƃ͂����A�Y�k�ɑ��閾�����{�̎����͂͂��߂���Ď��I�E�Ǘ��I�Ȃ��̂ł��������Ƃ͎w�E�ł��邾�낤�B
�@1874�i����7�j�N�A�������{�͕����ȒʒB�u�㐧�v��ʒB���A�u�g���A�Q�o�o�v���u�Y�k�v�Ƃ����E�Ǝ��i�Ƃ��ĔF�肷��B[12] �܂��A���̒ʒB�ɂ���ĐE�ƂƂ��Č��F���ꂽ���߁A�����ɐE�����e�Ɋւ���K����݂���ꂽ�B����́A�E�������Y�Ɍ��肵�A�����ً}���ȊO�̈�Ís�ׂ��֎~������̂ł������B�����A���̈㐧�͂��̎Y�k�̋K��Ɍ��炸�����܂�ȂǗl�X�ȖʂŎ������̔������̂ł���A���ۂ̋K��͒n��ɂ��ꂼ��C���Ă����B[13]
���āA���̂悤�ɒn�悲�Ƃł������Y�k�̋K���S���ꗥ�̋K���Ƃ����@�����A1899�i����32�j�N�́u�Y�k�K���v�u�Y�k�����K���v�u�Y�k����o�^�K���v�ł���B�Y�k�K�������ɂ́A�u�Y�k�����j���i�V�N���\�Έȏ�m���q�j�V�e�Y�k����j�o�^����P�^���҃j�o�Y�k�m�ƃ��c���R�g�����Y�v�Ƃ��Ď����ɂ��F����߂��B�������A10�N���1910�i����43�j�N�A�Y�k�K���̑��������̂悤�ɉ��肳���B
�u�Y�k�^�����g�X���҃n��\�N�ȏ�m���q�j�V�e���m���i���L�V�Y�k����j�o�^����
�N���R�g���v�X
��D�Y�k�����j���i�V�^����
��D������b�m�w��V�^���w�Z���n�u�K�������ƃV�^����
�O�D�O���m�w�Z��n�u�K�������ƃV���n�O���j���e�Y�k�m�Ƌ������^���҃j�V�e������b�m�K���g�F���^���ҁv
����́A��P�͑�Q�߂ŏq�ׂ��w��Z���ւ̖������F��̓����������Ă���B���̂悤�Ȕw�i�ɂ͉����������̂ł��낤���B
�{����q�́A�x����������̈�Ƃ��āA�]������̊J�Ǝ҂ł�����I�ȋ�����Ă��Ȃ��`���I�Y�k����A�w��Z�ɂ���ċ��炳�ꂽ���Ƃɂ��ߑ�I�ȏ��Y�Z�p�����Y�k�����{���d���������߂Ǝw�E���Ă���B[14] �܂������b���q�͂���Ɉ���i�߂āA���̒��̑��݂ł���`���I�Y�k���獑�Ƃɂ���ċ��炳��F�肳�ꂽ�Y�k�ւ̈ڍs�́A�u�o�Y�̍��Ɖ��v�ł���Ƃ��āA�����ɂ����ďo�Y�̐S�����傫���ω����Ă���Ǝw�E���Ă���B[15]
�@�Y�k�̐��x�I�Ȗʂ͂���ȍ~���ɕω��͂Ȃ����A�����ŎY�k�̎���ɂ��đ������y����K�v�����邾�낤�B�`���I�Y�k�i���Y�k�Ƃ��Ă��j�ƁA�����ɍ��i���邩��������Y�k�i�V�Y�k�Ƃ��Ă��j���ǂ��F�����邩�ɂ��āA1906�i����39�j�N�ɏo�ł��ꂽ�w���q�E�ƈē��x�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B�u�R�������Ԃ͍L�����̂ŐV���̑���o���̎Y�k�����o���̂���Y�k�����S���ȂǂƉ]�ė��h�ȎY�k�̂���ɂ��S�炸�ԁX���Y�k�Ɉ˗�����l�����邪�A���̋����̎Y�k�́A�������͓����̊w��͒m��ʂ����S�l�ƂȂ���Ɋ|���Ď��n�̕��ɂ݂͜�Ȃ��瓖���̎Ⴂ�Y�k�ɂ͕��������ʁA�Y�v��͌o���Ŋw��◝���ł͐����邱�Ƃ͏o������̂Ŗ����ƒ��X�̉��C����f���̂��ʔ����v�B[16] ���҂̋ߓ�����͒m���l�ł���A�܂����q���E�Ƃɂ����Ƃ����߂�{�ł����邽�ߋ��Y�k�ɑ��Ĕᔻ���Ă��邪�A�����ŏq�ׂ��Ă��鋌�Y�k�̏،������ł��Ȃ�̒��x�̃R���Z���T�X�Ă������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B1925�i�吳15�j�N�ɋ��Y�k�ƐV�Y�k�̐����t�]���邪�A�D�w���V�Y�k��I�ԌX���ɔ��Ԃ�������̂�1929�N���ȍ~�ł���B���̕ω��ɂ��ċ{����q�́A�u����̐Z���ɂ��������A�u���炳�ꂽ���Ɓv�ւ̐M���������A�u�g��荂�����m���Ȍ��ЂقǗǂ��h�Ƃ���ړx�v���A���Y�����x�z���Ɏ��߂����Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł���v[17] �Əq�ׁA����̓����ւƎ�荞�܂�Ă����l���w�E���Ă���B
��R�߁@�Y�k���珕�Y�w��
�@���AGHQ�̎w���E�w���̂��ƂŐ��x���v���Ȃ����Ȃ��A1947�i���a22�j�N�A�Y�k�K�������Y�w�K���ɉ�������A�Y�k�Ƃ����ď̂����Y�w�ւƕς�����B����ɗ��N�A�ی����Y�Ō�w�@�i�ʏ́A�ۏ��Ŗ@�j���肳��A�ی��w�E���Y�w�E�Ō�w����t�̎w���Ɋ�Â��u�Ō���E�v�Ƃ��Ĉꊇ���Ĉ�̖@���̂��ƂŋK�肳�ꂽ�B���Y�w�ɊW����Ƃ�����݂Ă݂�ƁA������b�̎w�肵���w��Z�ł��鏕�Y�w�{�����𑲋Ƃ������̂��A������b�̎w�肵���w�Z�ŏ��Y�w�Ɋւ���w�Ȃ��C�߂����̂ɂ̂ݏ��Y�w���Ǝ������錠�����F�߂��Ă���B[18] ����ɂ���āA��O�̎Y�k�K���ŔF�߂��Ă����w��Z���Ƃɂ�閳�����F�肪�p�~����A�w��Z�̑��ƂƎ����̍��i�o�����K�v�ɂȂ����B���̂��Ƃ͂�荂�����I�m���E�Z�p�������̎��i���K�����邽�߂ɕK�v�Ƃ��邱�Ƃ��Ӗ����A��肢�������̔��W�����҂��ꂽ�B
�@�������A���̌�̊Ō�w�i���݂̊Ō�w�E�Ō�m�j�͐��������Â������A�}�Q������ƕ�����悤�ɏ��Y�w��1950�N�������Ɍ����X���ɓ���A���݂ł͑S���łQ���l�����Ƃ��ۂ��x�ł���B[19] ���̌X�����������̂Ƃ��ĎQ�l�����̐}�R���݂Ă��炢�����B���̐}�͏o�Y�ɗ���l�̊��������߂������̂ł���B���̐}������ƕ�����悤�ɁA���Y�w�����t�̗���̂��Ƃł̏o�Y�ɋ}���ɕω����Ă��邱�Ƃ��݂ĂƂ��B���̂��Ƃ͓����ɁA�}�P�Ŏ������ǂ��ŏo�Y�����邩�Ƃ��������Ƃɂ��ւ���Ă��邾�낤�B���Y�w�͕K���������Y�@��a�@�E�f�Ï��ŏ��Y���s���킯�ł͂Ȃ��A�D�w�̉Ƃɍs���ď��Y���s�����Ƃ������������A���ꂪ�Y�Ȃ̂���a�@��f�Ï��ւƈڍs�����̂ł���B�܂��A���̗���ɔ����A�Ɨ��ŊJ�Ƃ��Ă��鏕�Q�@���������Ă���B[20]
�@���̂悤�ȕω��̗v�����l����ƁA�S���I�ȕω��Ɋւ��ẮA��O����풆�ɂ����ĐV�Y�k�̂��Ƃł̏o�Y����ʉ�������ɁA���M�����������Ǝv�����t�̂��Ƃł́u��ÂƂ��Ă̏o�Y�v�ւƈڍs�������߂��ƍl������B�܂��A�Љ�I�ȕω��Ɋւ��ẮA�o�����̌����ɔ������Y������������B1950�i���a25�j�N��3.65�ł��������v����o�����́A1993�i����5�N�j�ɂ�1.46�܂Ō������Ă���B���̂��߁A���Y�̐��E�ł��鏕�Y�w�ɂȂ���͊Ō�w���A�܂��Y�Ȑ��ł͂Ȃ��Y�w�l�Ȃ��Ƃ������ꂪ���܂ꂽ�Ƃ�����B���̂悤�ɍl����ƁA���Y�w�͍��x�ɋߑ㉻�����Љ�ɂ����ẮA���i�ɂ���ē��艻���ꂽ�E���͈͎��̂��Љ�I�v���ɂ���Ă��̏d�v����D���Ă������Ƃ����邩������Ȃ��B
�@���Y�w�̐��x���̂̕ω��͕ۏ��Ŗ@�ȍ~���ɕς���Ă��Ȃ����A�O�q�����悤�ȎЉ�I�ȕω��ɑΉ����邽�߂ɁA�ߔN�A���Y�w�̎��͂ł͗l�X�Ȋ������s���Ă���B1972�i���a37�j�N�A���ۏ��Y�w�A���]�c��Łu���Y�w�̒�`�v���̑�����A���N�ɂ�WHO�i���E�ی��@�\�j�ɂ����Ă��̑�����Ă���B���̒�`�ɂ́A���Y�w�͔D�P�E�o�Y�E�Y��̃P�A�y�я����̒S����ł���A�u���Y�w�͏����̂��߂����łȂ��A�Ƒ��y�ђn��Љ�̒��ɂ����Ă����N�J�E���Z�����O�Ƌ���ɏd�v�Ȗ����������Ă���B���̊����ɂ͎Y�O����Ɛe�ɂȂ邽�߂̏������܂܂�A����ɕw�l�Ȃ̈ꕔ�̗̈�A�Ƒ��v��y�ш玙�ɂ܂ŋy�ԁv[21] �Ƃ���Ă���B���̂悤�ɁA���Y�s�ׂ����ł͂Ȃ���Y������l�X�ȏ�ʂɂ�����P�A�����Y�w�̐E��Ƃ��Ă���B
�@�܂��A1986�i���a61�j�N�ɂ͓��{���Y�w��X�^�[�g���A�ŋ߂̎��R�o�Y�^���Ȃǂɔ����ď��Y�w�̌��������͂��낤�Ƃ��Ă���B�Ȃ��A���̎��R�o�Y�^���Ɋւ��Ă͑�R�͂ōl�@����B
�@�ȏ�A���Y�w�̐��x�Ƃ��̏��݂Ă����B�Y�k�E���Y�w�̐��x�I�ȕϑJ�́A��P�͂Ō����������{�̌��I�E�Ǝ��i�̕ϑJ�Ƃ���ׁA���W�����������̂܂܈�v����Ƃ�����B����́A���{���Y�k�E���Y�w�̕K�v����F�����A��ɑΉ����Â��Ă������Ƃ�\���Ă���B�������A���̂悤�Ȋm�ł��鐧�x�̂��Ƃɂ���ɂ��ւ�炸�A�����Y�w�͏����悤�Ƃ��Ă���B���̌���ɑ��Ă̗l�X�ȓ����͑�R�͂ōl�@����Ƃ��āA��Q�͂̍Ō�Ƃ��Ď��߂ɂ����āA����ł͏o�Y��҂��Y�k�E���Y�w�Ƃ��Ď��i�����邱�Ƃ͂��������ǂ̂悤�ȈӖ��������Ă����̂��A���i���ɂ���ē��艻���ꂽ���̂Ǝ���ꂽ���̂��l����B
��S�߁@���艻���ꂽ���̂ƁA����ꂽ����
�@���̐߂ōl�������A���i���ɂ���āu���艻���ꂽ���́v�Ɓu����ꂽ���́v�́A�����Ă��ꂼ�ꂪ�Ɨ��������̂ł͂Ȃ��A���肷��Ƃ������Ƃ͂���܂ł̏��̏ۂ��邱�Ƃł���A�\����̂̂��̂ł���B
�g���A�Q�o�o�͒n��ɂ���Ă��̊����͈͂��傫���Ⴂ�A�܂����̔F���̂�������Ⴄ���Ƃ͑�P�߂ŏЉ���B����ɑ��āA�S���ꗥ�Ŏ��i�����ꂽ�Y�k�͂��̒n�捷����ؖ���������̂Ƃ��č���Ă���B�������A���ۂ̊����͕����̈Ⴂ�Ȃǂ����邱�Ƃ���n�悲�Ƃō������������낤���A���Ȃ��Ƃ����O�`�Ƃ��Ă̎Y�k�͋ߑ�I�ȏ��Y�p���݂ɂ����q���I�ȏ����ł������B[22] ����ɑ��Đ��A�Y�Ȉ�́A�o�Y�ɑ��ėl�X�Ȍ`�̃P�A������̂ł͂Ȃ���Ís�ׂƂ��ĂȂ����߁A�Y�Ȉ㎩�g����̂ƂȂ�A��͈̂�Ís�ׂ���ΏۂƂ��ċq�̉��������B���̂��Ƃ���A��t�͏o�Y�̃}�l�[�W�����g�����鑶�݂Ƃ�����B���̂悤�ȏo�Y�̈�É��ւ̔��Ȃ���A���Y�w�͏o�Y�̃P�A�����鑶�݂Ƃ��āA�������ꂽ�B����͂����܂ł����̏��Y�w�ɑ��Ă̔F���ł��邪�A�D�w���o�Y�ɑ��Ĉ��S�����߁A����_�ʂŃP�A����Ƃ������ƂɊւ��ẮA�Y�k�E���Y�w�ɓ���̂��̂ł���ƍl����B�����ŁA���Y�w�̗��O�`�ɂ�����Q�̃|�C���g�A�u�ߑ�I�ȏ��Y�p�v�Ɓu�o�Y�̃P�A�����鑶�݁v��ʂ��Ă��̖��ɂ��Ă݂Ă݂�B
�Y�k���ߑ�I�ȏ��Y�p���l�����邽�߂ɂ́A���Y�p�̋��ȏ��ŕ����邩�A�Y�k�w�Z�E�Y�k�u�K���Ŋw�Ԃ����Ȃ������B�����Ŋw�ԓ��e�́A�Y�k�����K���ȂǂŎY�k�ɂƂ��ĕK�v�Ȓm���ł���ƋK�肳�ꂽ���̂ł���A����܂ł��������Y�Z�p�̒n�捷�Ȃǂ͈�؍l������Ă��Ȃ��B���̂��߁A�n��̏��Y�Z�p�͎�����B���R�Ȃ���A���̂悤�Ȓn��̏��Y�Z�p�\�\�Z�p�Ƃ����ׂ��łȂ��A�o�Y�Ɋւ���K���Ƃ����ׂ���������Ȃ��\�\�ɂ��������ǂ̂悤�ȉ��l������̂��A�Ƃ����ᔻ�����邾�낤�B�������A���̂悤�Ȓn��̏��Y�Z�p�͋ߑ�I�ȏ��Y�p�ɂ��Ȃ��Ă��炸�����I�łȂ��Ƃ��������ŁA���l���Ȃ��Ƃ��������̂��낤���B�����Ŗ��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�ߑ�I�ȏ��Y�p��g�ɂ������Y�̐��ƂƂ��Ă̎Y�k�Ƃ��Ă����łȂ��A�o�Y�̃P�A�����鑶�݂Ƃ��Ă̎Y�k�ł���B
�o�Y�̃P�A�͑���ɂ킽��B�����ɂ́A�o�Y�Ƃ�����厖���ɒ��ʂ���D�w�����S������Ƃ������̂����R�܂܂��B���̈��S�邽�߂ɋV����V��Ƃ������K��������A������g���A�Q�o�o�⋌�Y�k���S���Ă����B[23] ���̂悤�ȁA�o�Y�Ƃ����s�ׂ������S���čs���悤�ȁA�o�Y�̃P�A�̖ʂɊւ��Ă̈ӎ����A���i�̔F��ɂ͔��������Ă���A�K�R�I�ɂ��̂悤�ȋZ�p�������Ă䂭�B[24] ����ƂƂ��ɁA���i�̔F��ɕK�v�Ƃ����ߑ�I�ȎY�k�Z�p���Y�k�̐E���͈͂Ƃ��ē��艻�����B
�@�܂��A�V�������艻���ꂽ�ߑ�I�ȏ��Y�Z�p�̓`�B�o�H����قǏq�ׂ����ȏ���w��Z�Ƃ��������݂̂̂ɂȂ�B����́A�Z�p�̏��`�B�o�H�̓��艻�Ƃ����悤�B����ɑ��āA�g���A�Q�o�o�⋌�Y�k�����̋Z�p���̂͑��̒��őO�C�҂���k�퐧�x�I�Ɏp�������̂ł���B�����āA���̋����̏��`�B�o�H�͂��̂܂ܑ��̒��œ`����`������`�B�o�H�ł��������B��������i������邱�ƂŁA���`�B�o�H�����艻����邽�ߎ�����B�����ɁA�Y�k�͑��̒��̎Y�k����A�l�Ƃ��Ă̎Y�k�ɁA���Ȃ킿�u�E�Ɓv�ƂȂ�B����͎��i���E�Ƃ�F�肷��킯�ł͂Ȃ��A�E�Ƃ����Ƃ����Ӗ��������Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�@���i�����邱�ƂŁA���̎��i���S���ߑ�I�ȋZ�p�����艻����A���̎��i�����l�͂��̒S����ł��邱�Ƃ��������B�������A���̓��艻�̉ߒ��ɂ����āA����܂Ř_���Ă����悤�ɗl�X�Ȃ��̂�������B����́A�K�������ڂɌ�������̂ł͂Ȃ��A�K���ł������葺�̒��̏��`�B�o�H�ł�������ƒ��ۓI�Ȃ��̂��܂܂��B���̂悤�Ȃ��͈̂�T�ɐ�̂Ă���̂��낤���B���̋^����l���邽�߂ɁA���͂ŏo�Y�Ɋւ���V�����^�����l�@����B
��R�́@�Y�k�E���Y�w�͕K�v�Ȃ��̂�
��P�߁@���R�o�Y�^��
�@���R�o�Y�^���́A���̑O�j���u�ɂ��Ȃ��o�Y�v�̒Njy�ɋ��߂邱�Ƃ��ł���B[25] ���̒Nj��́A�ɂ݂��~�߂邽�߂̖̎g�p�▃���̎g�p�ւƈڍs���Ă䂭�B�����ē����ɁA�o�Y�̈�É��ւ̈ڍs�Ƃ��d�Ȃ��Ă������B[26] �������A�o�Y�̈�É��ƁA����ɂƂ��Ȃ��̎g�p�\�\���ɖ����ɂ�閳�ɉ��ƁA�r���U���܂̎g�p�ɂ��o�Y���̊Ǘ��\�\�ɂ������ẮA���̎g�p�̐�����߂��铮�������܂��Ă������B���̓����ɂ͂������̎咣�����݂��Ă��邪�A���̎咣�̒��́A�P�D�g�p�̋��ہA�Q�D��Ì��͂̉���̋��ہE�Y�ގ�̂̉A�̂Q�_�ɂ���Ƃ�����B
��P�_�̋c�_�Ɋւ��Ă͈�É��ɂ���āu�V�X�e���������o�Y�v�ɂȂ邱�ƂŁA�����������ᔻ�ɖ��g�p���Ă��邱�Ƃւ̔ᔻ�ł���B[27] ���_�́A�ɑ��镛��p��A�@����̗��R����̎g�p���ł��Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�o�Y����Ís�ׂƂ��čs���邽�߂Ɏg�p�����ꍇ������Ƃ������`�ł����Ă���B���̖��ɑ��čs���Ƃ��Ă̑Ή��Ƃ��āA�����Ȃ�1992�i����4�j�N�ɐw�ɑ��i�܂̎g�p������߂Ă��邪�A����ȍ~�ł�����p�ɂ�鎀�S���̂������Â��Ă���B���̓_�Ɋւ��ẮA�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�̓O���}��s���[�u�Ȃǂ��Ƃ��Ă��邪�A�����ɂ͓O�ꂳ��Ă��炸�܂��s�\���ȓ_�������B[28]
��Q�_�Ɋւ��ẮA�l�X�ȋc�_������܂����ۂ̉^�������푽�l�ł���B�����̉^���ɋ��ʂ�������́A��P�ɂ͐�i���ŋN���Ă���_�ł��낤�B����͋ߑ㉻�̐i��i���ł������قǁA�o�Y�̈�É����i��ł��邽�߂ł��邾�낤�B��Q�_�́A�o�Y�́u�l�ԉ��v�E�u���R���v���������Ă���_�ł���B���̏ꍇ�́u���R�v�Ƃ͐l�H�I�łȂ��Ƃ����Ӗ��ŗp�����Ă���悤�ł��邪�A�l�Ԑ������R���Ƃ����_�����W�J����Ă��邱�Ƃ͋����[���_�ł���B���̋c�_�𐄂��i�߂�̂ł���A�ߑぁ��ÂƎ��R���l�Ԃ��Η�����`�ɂȂ�ł��낤�B���̓Η��}���ɂ��ẮA���߂ł��ڂ������͂������B�܂��A�������̉^���`�Ԃ��Љ�悤�B
�@���ۂ̎��R�o�Y�^���Ƃ��ẮA�l�X�ȏo�Y���@�ɂ��[�֊������s���Ă���B���������������ƁA���{�ł��L���s���Ă���A�Ɠ��̌ċz�@��v�̗���Ȃǂ������I�ȃ��}�[�Y�@�A����܂ł̏o�Y�@�͔D�w���҂̗��ꂩ��̂��̂ł����Ƃ����ᔻ����u�Ԃ����ɑ��Ă₳�����o�Y�v��Nj����郋�{���C�G�@�A���ގ�̂̉����i���A��{�I�Ɉ�̏��Y�s�ׂ����Ȃ��A�N�e�B�u�E�o�[�X�Ȃǂ���\�I�ł���B[29]
�@�����̎��R�o�Y�^���̂��ׂĂ���Â�S�ʓI�ɔے肷��킯�ł͂Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��ᔻ�𓊂������Ă���͎̂����ł���B�����ŁA���߂ł͋ߑ��ÂƎ��R�o�Y�̖��Ɋւ��čl���A���̏�ŏ����悤�Ƃ��Ă���Y�k�E���Y�w���čl���Ă݂�B
��Q�߁@Alternative Birth
�@�o�Y���߂����É��Ǝ��R�o�Y�^���̊������l����ɂ������āA�g���͂��̌����̒��ɓ�ґ����������\����T��o���Ă���B�g���͎��R�ȏo�Y�̌����ɑ��A�u�{���Ɏ��̐S����u���S���v�Ƃ������Ƃ����������āA������ł��A���h�͂�ł��Ȃ��A�S�ꂩ��̔[���ŁA��������ɒ��߂邾�낤���H�c�c���̎����̌���ł́A�u�ً}���ɑ����ł���v�Ƃ������ƂƁu�D�܂������Y���@������v�Ƃ������Ƃ̗��҂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ɣ��f�����ꍇ�A��ґ�������܂���ꍇ�ɂ́A���ł�����ς�O�҂��Ƃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�����ȂƂ���A����ȋC������v�ƁA���̗��z�̌��E�����w�E����B[30] ��Â����S�����A����Ƃ��댯������������Ȃ�����̓I�ł��鎩�R�o�Y���Ƃ�����ґ���́A�O�q�����悤�ɗ������w�E�����o�Y�̈�É��ɑ��Ă̐S���̕ω����o����ł́A�g���̌����悤�ɑO�҂��Ƃ�X���ɂȂ����Ƃ��Ă��d�����Ȃ��ł��낤�B[31] �������A�����������̂悤�ȓ�ґ���̓Η��\�����̂����S����É��Ƃ����u�ߑ㉻�̘_���v�ɂ����Đ����i�߂�ꂽ���̂ł���B
�@�����ōl���Ă݂����̂��A�I�[���^�i�e�B�u�E�o�[�X Alternative Birth �Ƃ����l�������ł���B���̍l�����́A�ߑ��Âɑ���ᔻ�Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂ŁA���R�o�Y�^���̂�݂����Ȉ�Ë��ۂɌ����郉�f�B�J���ȑ��ʂ�ᔻ���A�u���R�ɏo�Y�ł���Ƃ��ɂ͎��R�̉ߒ��ɐg���ςˁA�^�Ɉ�Ẩ�����K�v�ȏꍇ�ɂ͓K�Ȉ�Ẩ���������v�悤�ȏo�Y�̖͍��Ƃ����Ă悢���낤�B[32] ���̍l�����́A�u�ߑ㉻�̘_���v�ɑ��āA�ߌ��a�q�̒���u�����I���W�̘_���v�Ɍ��т����̂ł͂Ȃ��̂��낤���B�ߌ��a�q�̂��������I���W�Ƃ́A�u�ڕW�ɂ����Đl�ދ��ʂł���A�ڕW�B���ւ̌o�H�ƁA���̖ڕW����������ł��낤�Љ�̃��f���ɂ��ẮA���l���ɕx�ގЉ�ω��̉ߒ��v�ł���A�u�����Ɏ���o�H�ƁA�ڕW����������Љ�̎p�ƁA�l�X�̕�炵�̗��V�Ƃ́A���ꂼ��̒n��̐l�X����яW�c���A�ŗL�̎��R���Ԍn�ɓK�����A������Y�i�`���j�Ɋ�Â��āA�O���̒m���E�Z�p�E���x�Ȃǂ��ƍ����A�����I�ɑn�o����v���̂ł���B[33] ���̘_�����o�Y�ɓK�p����̂ł���A���̒n��ɍ��������`���I�ȏo�Y���čl���邱�ƂŁA��Á����S�Ǝ��R�o�Y�̓Η�����̂��A���l�������肩���S�ȏo�Y�`�Ԃ��m������邱�Ƃ����߂邱�ƂɂȂ낤�B
�@���Ȃ���́A�ǂ̂悤�ɂ��đ��l�������肩���S�ȏo�Y�`�Ԃ��m�����邩�Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ŏ��߂ɂ����āA����܂ł݂Ă����Y�k�E���Y�w�ɉ��߂Ē��ڂ��Ă݂����B
��R�߁@�Y�k�E���Y�w�čl
�@��Q�͑�R�߂ɂ����āA�Y�k�E���Y�w�����i������邱�Ƃɂ���ċZ�p�̓��艻�������錻�ۂ��l�@�����B�����ŁA���l�������肩���S�ȏo�Y�`�Ԃ��m���ł��邩�ǂ���������O�ɁA���̓_�ɂ��čl�������B����́A���i���ɂ���ē��艻���ꂽ�Z�p��N���������悤�ȑ̐������Ƃ��ɋN������ɂ��Ăł���B
�@�Y�k�E���Y�w�����i�������ڍs���ɂ����ċZ�p�̓��艻�ƒn��̏o�Y����Ƃ̃M���b�v�͂ǂ̂悤�ɉ�������Ă����̂��낤���B���ؑ̈ʂ̍��Y�����Y�ւ̈ڍs��V�Y�k���ς����_���o�Y�̎Љ�j�̒��ł͂悭���ڂ���邪�A���R�E�x�]�͏��a��O���̊J�ƎY�k�����́A�w��ł������Y�w���ꗥ�ɓK�p����킯�ł͂Ȃ��A���ؑ̈ʂȂǂɊւ���]���̏o�Y�d���Ă������Ƃ����Ȃ��Ȃ����Ƃ��w�E���Ă���B[34] ����́A��Ís�ׂƂ��Ă̏��Y���s���Y�Ȉ�̔�_��Ƃ͈قȂ�A�Y�k�E���Y�w�̏��Y�s�ׂ͏��ł̓O��ȂǂƂ������ߑ�I�ȏ��Y�Z�p���������A�����ɒn��̃j�[�Y�ɂ��������Y�����Ă������Ƃ������Ă���B����͓����ɁA�Y�k�E���Y�w�����l�������肩���S�ȏo�Y�`�Ԃ̒S����ƂȂ��Ă������Ƃ������Ă���̂Ƃ����悤�B
�@���āA�����Ŗ��ƂȂ��Ă���̂��Ƃ��n��̏o�Y����ɂ���悤�ȁA������`���I�ȏo�Y���̂��̂��A�o�Y�̓����I���W�ɂ����Ďc���ׂ����̂ł��邩�Ƃ����_�ł���B�t���́A�n��̏o�Y����ɂ�����Ă���Y�k�E���Y�w�̓`���̏��v�f�ɂ����āA�u�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́u�V���{���b�N�Ȏ��Áv�ł���v�Əq�ׁA�o�Y�Ɋւ���l�X�Ȓn��̕����ɂ�����ے��I���Ñ̌n�̈Ӌ`���������Ă���B[35] ���̘_�Ƃ����t���́A�t�����X�ɂ�����A�t���J�ږ��̏o�Y�ɍۂ��A���S����ޗ��͋ߑ�I�Ȉ�Âł͂Ȃ������̓`���I�ȏo�Y�`���ł��������Ƃ��ɂ����Ă���B�܂��A�����͕��ؑ̈ʂɂ��āA��w�I���n�����ʂ̖��_���w�E���A��肪����ɂ��ւ�炸��ʂ��Y�ȕa�@�Ȃǂō̗p����Ă��闝�R�́A��w�I�����ȊO�́u�a�@���Ƃ��������ł͊��҂͐Q����̂Ƃ���Ă���v�Ƃ��������ɂ���Ă�������ꂽ���̂ł���Ƙ_���Ă���B�����āA��ʂł͂Ȃ����K�I�Ƃ��ċߑ��Â����̂Ă�ꂽ���Y�Ȃǂ̕��ؑ̈ʂ̂ق�����荇���I�ł���Ƃ��Ă���B[36] ���̂悤�ȋc�_������݂Ď��邱�Ƃ́A�`���I�Ȓm���E�Z�p���������Y�k�E���Y�w�̕����ł���A�I�[���^�i�e�B�u�E�o�[�X�̒S����̈�l�Ƃ��Ă̎Y�k�E���Y�w�̎p�ł͂Ȃ��̂��낤���B
�@��Q�͑�R�߂ŏq�ׂ��悤�ɁA���ݓ��{�ɂ����ď��Y�w�͏����悤�Ƃ��Ă���B�������A�g�����q�ׂ��悤�ȏo�Y�ɂ܂��Η�������A�V�����o�Y�`�Ԃ�͍����邽�߂ɂ͏��Y�w�̕�����}��ׂ��ł��낤�B�܂��A���̖��͋ߑ㉻������i���ɂ����Ă̂ݓ��Ă͂܂���ł͂Ȃ��B���A�t���J�ł́A�o�Y1000�ɑ��ĕ�̂̎��S�����V�l�Ɣ��ɍ����m���ɂȂ��Ă���A����甭�W�r�㍑�E��i���̏o�Y����͉��P����K�v������B[37] ���̂Ƃ��A���̂悤�ȍ��ɂ����ċߑ��Â����̂܂܍��t�����邱�Ƃ͋��K�I�ɂ����_�I�ɂ�����B�����ŁA�Y�k�E���Y�w�ɂ�鍑�ۓI�ȋZ�p�x�����l���邱�Ƃ��ł���B���ۂɁA���ۏ��Y�w�A���iICM�j�₻�̊֘A�c�̂͌�i���Ȃǂւ̋Z�p�x�����s���Ă���B�܂����ۏ��Y�w�A���́A���̂Ƃ��ɋߑ�I�Ȉ�Âɂ���ċN�����`���I�Ȓm����Z�p�������Ȃ��悤�ɁA1996�N�Ɂu���ۏ��Y�w�A���́A�����Ƃ��̉Ƒ��Ƌ������鏕�Y���炨��ю��H�𐄐i���G�l�ƕ����̑����Ɍh�ӂ��G���̌h�ӂ��m�肵�G���Z���鏗���Ƃ��̐l�X�̕����I�ȕ\������ъS��F�߂���̂ł���v�Ƃ������M�\�����s���Ă���B[38]
�@�Y�k�E���Y�w�́A�I�[���^�i�e�B�u�E�o�[�X�ɂ����ččl���邱�ƂŁA�o�Y�ɂ�����ߑ��ÂƎ��R�o�Y�̓Η��̖����ˋ����鑶�݂Ƃ��ĐV�����ʒu�t�������邱�Ƃ��ł���̂ł���B
��S�߁@�\�z�����ᔻ�ւ̉�
�@���̐߂��{�_���̍Ō�̐߂ɂȂ邪�A�O�߂܂łŘ_���Ă����Y�k�E���Y�w�̐V�����ʒu�t���ɂ��Ă̗\�z�����Q�̔ᔻ�ɑ��āA��^���Ă��������B
�@��P�̔ᔻ�́A�D�w�ɂƂ��ďo�Y���̈��S�����A�ߑ��Âł͂Ȃ��u�V���{���b�N�Ȏ��Áv�Ƃ������`�ł̓`���I�ȏo�Y�`�Ԃ��{���ɂ����炵����̂��Ƃ������̂ł���B�������ɁA�t���̋c�_�́u�V���{���b�N�Ȏ��Áv�ɑ��Ă̎v�����ꂪ�����A�����Y�k�E���Y�w���S���ׂ����̂ł��邩�ɂ��Č��y���Ă��Ȃ��B�܂��A�O�ߑ���݂Ă݂��Ƃ��A�Y�k�E���Y�w�͌����ē`���̋Z���p���������Y�҂Ƃ��Ă̈ʒu�t�������łȂ��A�َ҂Ȃ����͑قɂ���Ďq���B�����݂Ƃ��Ă̈ʒu�t�������������Ƃ͎����ł���A�V���{���b�N�ȑ��ʂᔻ�Ɏ�グ��ׂ��ł͂Ȃ����낤�B[39] �������A������Ƃ����ē`���I�ȋZ�p��S�Đ�̂Ă�ׂ��łȂ����Ƃ͂����܂łŏq�ׂĂ����Ƃ���ł���B�����ɂ��ċߑ�̏��Y�Z�p�Ɠ`���I�ȋZ�p���u�ƍ�����v���͓�����ł��邪�A���̒n��̃j�[�Y���\���ɍl��������ŁA�D�w����̓I�Ɏ����������Ȃ�o�Y�`�Ԃ����ׂ����I�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȑ��x�������Ă����ׂ��ł͂Ȃ����B���ɂ���Ĉ��S��������̂��͕��G�Ȗ��ł��邪�A�����Ȃ��Ƃ������ɂƂ��Ă̈��S�����ł���̂����A�����t���łȂ��l���ł���������z�I�ł���ƍl���Ă���B
�@��Q�̔ᔻ�́A�ߑ��Â̖��_����������ΎY�k�E���Y�w�͕K�v�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����B�ނ���A�Y�k�E���Y�w�͋ߑ㉻�̉ߓn���ɏo�Y����É�����܂ł́u�Ȃ��v�Ƃ��Ă̑��݂ł͂Ȃ������̂��A�Ƃ������̂ł���B�������ɁA���{��A�����J�ł͏��Y�w�̑��݈Ӌ`�͋}���ɔ���Ă��Ă���A����͑��̐�i�����ł��w�E�ł���X���ł���B���A��Âɂ���������C���t�H�[���h�E�R���Z���g�̓O���A�r���U���܂̎g�p�K��̋����ȂǗl�X�Ȏ��g�݂��s���Ă���B���̂悤�Ȏ��g�݂͈�Éߌ�ɂ����@����ƂƂ��ɁA�D�w�Ɉ�Âւ̐M��������荂�߂���̂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͂������ł���B�������A�ߔN�ɂȂ��ď��Y�w�čl�̓��������{�ł��A�����J�ł��N���Ă��邱�Ƃ��܂������ł���B[40] ���̘_�ł��q�ׂĂ������Ƃł��邪�A�o�Y�̈�É��̖��_�͂�����Éߌ�̖�肪�N���邾���łȂ��A��É������o�Y�͔D�w����u�Y�ގ�́v�Ƃ��Ă̗����D��������̂ł��邱�Ƃł���B����̓I�Ȃ��Y��]�ތ���A�o�Y�̈�É��Ƃ͑��e��Ȃ��B�Y�k�E���Y�w���čl���邱�Ƃ͋ߑ㉻�̈�ʂ�S���Ă����Y�k�E���Y�w���A���x�͂��̋ߑ㉻�̘_���ɐ��ޖ��_����̂��鑶�݂Ƃ��ĂƂ炦�Ȃ������Ƃł���B���̂��߁A�Y�k�E���Y�w�͋ߑ㉻�ɂ�����u�Ȃ��v�Ƃ��Ă̖�����S���Ă��邾���ł͂Ȃ��̂ł���B
���_
�@�ߌ��a�q�́u�����I���W�_�̌n���v�ɂ����āA�s��O�Y�̗p������p���āA�u�L�[�p�[�X���v�Ƃ����T�O��_���Ă���B����ͤ�u�n��̏��`���̒��ɁA���ݐl�ނ����ʂ��Ă��鍢��Ȗ��������������A�������̂�V�������ɏƂ炵���킹�Ă��肩���A�������邱�Ƃɂ���āA���l�Ȕ��W���v�n��̏����Ȗ������Ƃ����Ӗ��ł���B[41]
�@�o�Y�ɂ�����ߑ㉻�́A���̈��S��������I�ɍ��߂����̂́A��Q������s���A��Ì��̖͂��Ȃǂ��Ă����B�܂��A���̃A���`�Ƃ��ďo�Ă������R�o�Y�^�������E���܂�ł����B���̑Η����ˋ�����L�[�p�[�X�����A�Y�k�E���Y�w�ł͂Ȃ��̂��낤���B�����āA�Y�k�E���Y�w�̊����ɂ���āA�o�Y�ɂ����鍑�ۓI�Ȋi���̐����������ʓI�ɉ������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��̂��낤���B
�@�Y�k�E���Y�w�́A���i���ɂ���ėl�X�Ȃ��̂��������B���̎��������̂����߂ččl���邱�Ƃ������߂��Ă���ƌ��_���A�_���I���B
�Q�l����
���S�q�w�W�F���_�[�E�o�����X�̒���@�\�\���������i�����ɂ́\�\�x�w���ЁA1997
�V����w�o�Y�Ɛ��B�ς̗��j�x�@����w�o�ŋǁA1996
Collins, Randall , 1979�A�V�x�ʖ�Ė�w���i�Љ�@����ƊK�w�̗��j�Љ�w�x�L�M������
�ЁA1984
���c�^��w���Y�v���x�����V���ЁA1979
�t���b�q�w�Ԃ������Y�ނƂ������Ɓ@�Љ�w����̎��݁xNHK�u�b�N�X�A1994
���J�씎�q�u�Y�k�̃L���X�g�����Ɗ��K�̌`���@�\�\�������̑������ɂ��Y�k�̑I��
���߂����ā\�\�v������䑼�w���E�Y�E�Ƒ��̔�r�Љ�j�@���x�Ƃ��Ắ������x��
�}�ЁA1990
�����x�q�w�o�Y�̕����l�ފw�@�V��ƎY�k�@[���������]�x�C�ЁA1991
�{����q�u�u���Y�v�̎Љ�j�v�w�p�����Y�ށE��Ă�E������\�\�����̋���j���P�@����
�灄�\�\�a���ƏI���x�������X�A1990
�����b���q�w�ߑ�Ƒ��ƃt�F�~�j�Y���x�������[�A1989
�����b���q�u����Y�k�̓��{�ߑ�@�\�\���C�t�q�X�g���[����Љ�j�ց\�\�v������䑼
�w���E�Y�E�Ƒ��̔�r�Љ�j�@���x�Ƃ��Ắ������x���}�ЁA1990
�ߓ�����u���q�E�ƈē��v1906�A�w���ƐE�ƂQ�@���q�E�ƈē��x���ЁA1993
��ѓ��q�w���Y�w�̐��x�������[�A1989
���R���q�E�x�]�D�q�w���R�Ȃ��Y�����߂āx�������[�A1996
��؎����w�o�Y�̗��j�l�ފw�@�Y�k���E�̉�̂��玩�R�o�Y�^���ցx�V�j�ЁA1997
�Ҍ��w���{�̌��I�E�Ǝ��i���x�@�\�\���j�E����E�����\�\�x���{�}���Z���^�[�A2000
�ߌ��a�q�u�����I���W�_�̌n���v�ߌ��a�q�E��c���ҁw�����I���W�_�x������w�o�ʼn�A
1989
���c���j�u�Y�k���Ӗ���������v1926�A�w��{�@���c���j�W�@��\�܊��x�}�����[�A1963(a)
���c���j�u�Љ�Ǝq�ǂ��v1941�A�w��{�@���c���j�W�@��\�܊��x�}�����[�A1963(b)
�g���T�q�w���Y�Əo��x�������[�A1985
�g���T�q�u���Y�Əo��@���v�����G��E��{���ߌb�E���n�R�p�w�t�F�~�j�Y���E�R���N
�V�����U�x1993
�g�i�^�q�u���a��O���ɂ�����o�Y�̕ϗe�Ɓu�ꐫ�̋����v�@�\�\�������c�����ɂ��
���瑺���Ƃ𒆐S�Ɂ\�\�v�w������w��w�@����w�����ȋI�v�@��37���x1997
�����ȁw��q�q���Ɋւ��铝�v�x
�����ȁw�q�����v�N��x
�����{���v�ǁw���{���v�N��x
�Q�l����