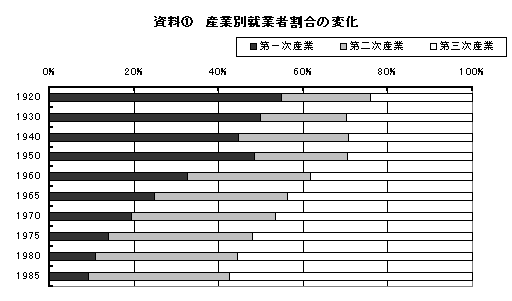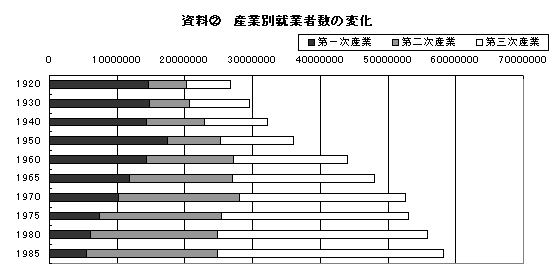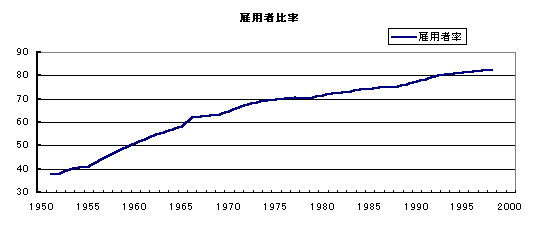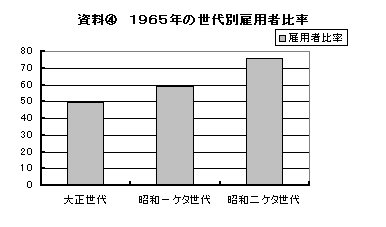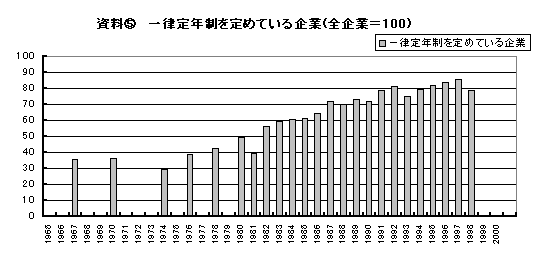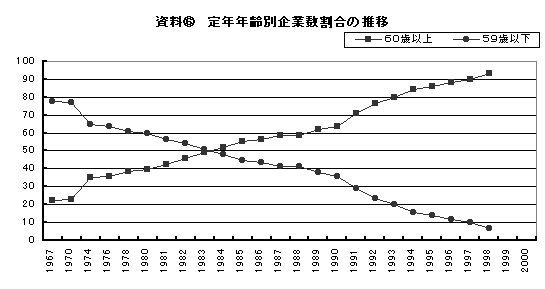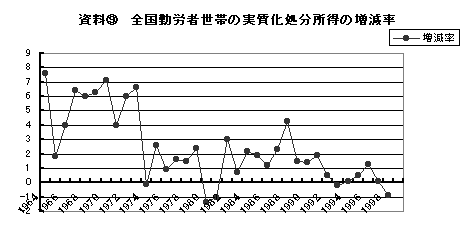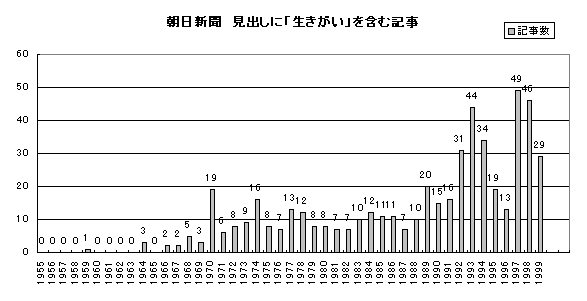���Ƙ_���@1999�N�x�@�i����11�N�x�j
�w�u�V���v�Ƌߑ�x
�\�\�J���Ɓu���������v��ʂ��ā\�\
�c��`�m��w�@��������w���@4�N�@79607241
�����@�F�I�q
�y�͂��߂Ɂz�i�v��j
�u�V���v�A�Ƃ����킽�������ɂƂ��Ă��܂�ɂ��g�߂Ȃ��̂�E�^���������Ƃ��A�u�ߑ�v�Ƃ����Љ�͂��������ǂ̂悤�ȎЉ�Ƃ��ĕ����яオ���Ă���̂��낤���B
���{������̎��Ƃ��Đ������Ă���u�ߑ�v�ɂ����āA�u�V���v�́A���J���̎����ω����邱�Ƃɂ���āi�Ɠ��J����������J���ɂȂ邱�Ƃɂ���āj�A�J���҂�����N��ɒB����Ƃ݂�����̘J���͂̔�����������A���̌��ʁu�����Ȃ��Ȃ邱�Ɓv�ł��遄�A�ƒ�`���邱�Ƃ��ł���B���{�ł́A���̍��x�o�ϐ����Ƃ����ߑ㉻�̒��ŁA�u�V���v���u�L�����v�̎����ƂƂ��Ɂu��N�v�Ƃ����\���Ƃ��ċ�������B21���I���}���悤�Ƃ��Ă��鍡�܂��ɁA�u�V���v�ɒ��ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�Ԃ��}�����Ă���B
���ۂɁu�V���v���}���������̐l�Ԃ́A�o�ϓI�L������ۏႳ��Ă��Ȃ���A�����́u���ꏊ�v�������A�u���������v�����߂Ȃ���i�^�����Ȃ���j�Ȃ�Ȃ����݂ƂȂ����B����҂̕����E�J������Ƃ��Ắu�V���o�[�l�ރZ���^�[�v�́A�����I���ʂ�F�Z���L�����u���������v��ł���B���̒����V���̎��ʂł́A�u���������v�Ƃ������Ƃ��܂ދL�����A�o�ϐ����Ɍĉ�����悤�ɑ��������B
�u�ߑ�v�́A�킽�������̐����̒��S�Ɂu�s��v�𐘂��邱�Ƃɂ���āA���ʓI�Ɂu�s��v�ɋ߂Â��Ȃ��l�Ԃ����炩�́u���������v�����߂Ȃ��Ă͐����Ă������Ƃ̂ł��Ȃ��Љ�����o���Ă��܂����B�u�V���v�́u����ҁv��u�V�l�v�����̖��ł͂Ȃ��B�u�V���v�𐭍�̑ΏۂƂ��āu���v������̂���߂��Ƃ��A�u�V���v�����ނ灄�̖��ł͂Ȃ����킽���������̖��ł��邱�Ƃ������Ă���̂��B
�y�ڎ��z
�S�@��N�\�\�������Ȃ��Ȃ遄�\���\�\..................................................................................... 16
�R�@�V���o�[�l�ރZ���^�[�ݗ��̈Ӑ}�\�\�Ȃ��ٗp�W���Ȃ��̂��\�\....................................... 22
����
�P�@���ӎ�
���̘_���̖ړI�́A�u�Ȃ��ߑ�ɂ����āu�V���v�͔ے�I�Ɏ~�߂���̂��v�A�u���������A�ߑ�́u�V���v�Ƃ͂����������Ȃ̂��v�Ƃ����₢�𗧂Ă邱�Ƃɂ���āA�킽��������������u�ߑ�v�Ƃ����Љ�̂��̂�ᔻ�I�Ɍ������邱�Ƃł���B
�u���Ƃ�v�܂��͢�V���飂Ƃ������t���������Ƃ��ɁA���邢�C���[�W���Â��C���[�W���肪������ł���̂͂Ȃ����낤���B�ނ��A�N��ɑ��鉿�l�ς͌l�ɂ���đ傫���قȂ�B���ɂ́u���Ƃ�v���Ƃɑ��đO�����Ȏp���̐l�����邾�낤�B�܂��͈�l�̐l�Ԃ������Ă��鉿�l�ς̒��ɂ��A�u���Ƃ���ꂾ�������̐l���o�����邩��l�ԂƂ��Ă̕����L����v�Ƃ����l���ƁA�u�ł�����ς�Ⴍ���肽���v�Ƃ�����������l�������݂��Ă��邩������Ȃ��B���������Ԉ�ʂɂ́A��͂�u�V���Ă���v���Ƃ����u�Ⴍ���邱�Ɓv�ɂ�葽���̉��l��������Ă���悤�ł���B�����łȂ���A�u����v���C�ɂ�����A�u�͂��v���B�����߂ɍ��z���͂����Ă�������肵�Ȃ��͂��ł���B�X�L���P�A��w�A�P�A�̍L��������A���̒��Ɂu�Ⴓ�v���d�����镗�������邱�Ƃ��悭�킩��B�Ȃ��A�u����v��u�͂��v�͂���Ȃɂ������̐l�Ɍ�����̂��낤���B�Ȃ��l�́A�u���Ƃ�v���Ƃ�������A���܂ł��u�Ⴍ�v���肽���Ɗ肤�̂��낤���B�u���Ƃ�̂͒N�����Ă���Ȃ��̂��v�ƌ����Ă��܂��A����܂ł�������Ȃ��B�������A�u���Ƃ肽���Ȃ��v�Ƃ����C�����́A�K������������Đl�Ԃ����L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ӎ��Ȃ̂��낤���B�u�Ⴍ���肽���v�Ɗ肤���Ƃ́A�l�ԂɂƂ��Ė{���Ɏ��R�ȗ~���Ȃ̂��낤���B
�u���Ƃ�v���ƁA�܂����́A�����̂ł���l�ԂɂƂ��Ă��܂�ɂ����R�Ȃ��Ƃ䂦�ɁA�N�����̂��Ƃɂ��Ă��炽�܂����^��������͂���͂��Ȃ��B����Ɠ����悤�ɁA�u���Ƃ肽���Ȃ��v�Ƃ����C���������̂͂Ȃ��Ȃ̂��A�ȂǂƂ������Ƃi�̐����̒��Ő^���ɍl���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ́u������O�v�����炾�B���i�A�킽���������S��������̂́A�u�ڗ����Ɓv��u�����ƈ�������Ɓv�ł���B�킽���������u������O�v���Ɗ����邱�Ƃɂ́A���ӂ�����ꂽ��ӎ����ꂽ�肷�邱�Ƃ���Ȃ��B�������A�킽�������������u������O�v���Ǝv���Ă��邱�Ƃ́A�ق�Ƃ��ɂ��̎���ɂ��ǂ��̎Љ�ł��u������O�v�̂��Ƃ������̂��낤���B���������łȂ��Ƃ�����A�킽�������͎��������������u������O�v���Ǝv���Ĉӎ����炵�Ȃ����̂��ƂɁA���͈�ԑ傫�����E����Ă���̂�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�u�������v���͂���Ƃ��A�킽���������u������O�v���Ǝv���Ă�����̂��Ƃ́A�u���v�̑O��Ƃ��Ă킽�������̖ڂɂ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��邩��ł���B
�u�͂Ƃ肽���Ȃ��v�Ɗ�����̂��u������O���v�ƌ����Ă��܂킸�ɁA�ǂ����Ă���������̂��^���Ă������Ă݂�B���������ƁA���������C���[�W�Ɋւ��错�R�Ƃ����b���͂��܂�悤�ɕ������邩������Ȃ��B�������킽���́A�u�u�V���v��ے�I�Ɏ~�߂�v�Ƃ������Ƃ́A�C���[�W�̖�肾���ł͂Ȃ��A�����Ɏ��̂���̓I�Șb���ƍl���Ă���B���Ƃ��A�u�V�l���v�ɂ��ď����l���Ă݂悤�B���������u�V�l���v�́A�Ȃ��u���v�Ȃ̂��낤���B�Љ�w�̎��T���J���Ă݂�ƁA�u�V�l���v�Ƃ������ڂ��o�Ă���B�����ł́u�V�l���v�Ƃ͑傫�������āA�@�n�����A�A�����A�B�ǓƋ��V�l���s���̖��A�ł���Ɛ�������Ă���B���z�̍���ɂ���̂́A�u�V�l�v���킽���������邢�͎Љ�Ώ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��u���v�Ƃ��đ����鎋�_���B�܂��A�����������ɐ��Ԃ̒��ڂ����тĂ���u�V�l���v�̈�ɁA���ی����x����������B�V����e���r�̕ŁA���ی��ɂ܂��g�b�s�b�N���o�Ă��Ȃ����ȂǁA1�����Ȃ��قǂ��B�����̒̕��Łu���ی��v���c�_�����Ƃ��A�u���v�Ƃ����̂́A�u���ی��̍����ɏ���łĂ�ׂ����v�A�u�v���F��̃V�X�e���̌��������ǂ��ۂ��v�A�Ƃ��������e���قƂ�ǂł���B�F��̍ۂɗv���̃��x�����ǂ����f���邩�ɂ��ċc�_����邱�Ƃ͂����Ă��A���������Ȃ�����҂��u�v���v�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����c�_����邱�Ƃ͂Ȃ��B����҂����ی��̑ΏۂƂȂ邱�ƂɊւ��ẮA�N���^�����͂��܂Ȃ��̂��B�����Ɂu���v�̑O��Ƃ��Ă���̂́A�u�V�l�����̑ΏۂƂȂ�͓̂��R���v�Ƃ������ӎ��̈ӎ��ł���B�ł́A�V�l�̖ʓ|���ł邱�Ƃ��u���v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A��������������Ȃ̂��낤���B�V�l�̖ʓ|���ł�̂́A���Â̐̂���u�ł̎d���v�������̂��낤���B�܂��́A�u�z�[���w���p�[�v�Ƃ������̌����m�炸�̐l�Ԃ������̂��낤���B�ʓ|���łĂ��炤���Ƃɑ��Ă������B�������u���{�l�v�Ƃ����ƂĂ��Ȃ��傫�Ȑl����ɂ��āA���̃��X�N�w�b�W������B����Ȃ��Ƃ�吨�̐l�Ԃ��u�s���R�łȂ��v�Ɗ�����悤�ɂȂ����̂́A���͂��������ŋ߂̂��ƂȂ̂ł͂Ȃ����낤���B�����l����ƁA�ی��̍�����V�X�e���ɂ��Ă̋c�_�́A���S�̂̂ق�̕\�w�����Ƃ炦�Ă��Ȃ��悤�ɂ킽���ɂ͎v����B�u�Ȃ�����҂����̑ΏۂƂȂ�̂��v�Ƃ������_����b���͂��߂Ȃ���A�{���̈Ӗ��ł̖������ɂ͋߂Â��Ȃ��̂��B
�킽�������������Ă���u�V����v���Ƃɑ���ے�I�ȃC���[�W��A�u�V�l���v�Ƃ������z�̑O��ɂ���ӎ��B�����̉��l�ς��A�u�ߑ�v�Ƃ������Ԃ̘g�g�݂̒��ňʒu�t�����Ƃ��A�u�V���v�Ƃ͂����������Ȃ̂��낤���B�����ċt�ɁA�u�V���v��ے�I�Ȃ��̂Ƃ��Ĉʒu�t���Ă���u�ߑ�v�Ƃ́A���������ǂ�ȎЉ�Ȃ̂��낤���B���Ƃ́A�C���[�W��ӎ������̖��ł͂Ȃ��A�ނ��낻�������C���[�W��ӎ������o���Ă���y��̖��ł���B�킽�������ɂƂ��Ă��܂�ɂ��g�߂����邪�䂦�ɁA�������Ă킽�������̖ڂɂ͌����ɂ����Ȃ��Ă��܂��Ă���u�ߑ�v�Ƃ����Љ�B���́u�ߑ�v���A�u�V���v�Ƃ������_����f���o�����Ƃ��A�{�_���̖ړI�Ȃ̂ł���B
1�́@�ߑ�ɂ�����u�V���v�̔����@�\�\�����̗��_�I�g�g�\�\
�{�͂ł́A�u�V���v�ɂ��Ă̋�̓I�ȕ��͂̑O�i�K�Ƃ��āA�{�_���ł������u�V���v�Ƃ������t�̒�`�ƁA�u�V���v���͂̂��߂̗��_�I�g�g�m�ɂ���B
�P�@�u�V���v�̒�`
�킽�����{�����ɂ����Ĉ������Ƃ��Ă���u�V���v�Ƃ́A���ԂƋ�Ԃɂ���Č��肳�ꂽ�Љ�ɂ���āu�Ӗ��t���v���ꂽ�u�V���v�̂��Ƃł���B
�킽���́A�u�V���v�ɂ͑傫�������ē�̃��x��������ƍl���Ă���B�����w�I�ȃ��x���ł̘V���ƁA�Љ�I�ȃ��x���ł́u�V���v�ł���B�O�҂̐����w�I�ȘV���́A�P���ɉ���Ƃ���ɔ����g�̓I�ȕω��݂̂��w���B�ǂ�Ȑl�Ԃł����Ă��A�q�g�ł������͍��d�˂�ƂƂ��ɂ��̐����@�\���ቺ����B�ǂ�Ȏ���̂ǂ�ȏꏊ�ł����Ă��A�����w�I�ȘV���͕K�����݂��邵�A�V�l������B����ɑ��Č�҂̎Љ�I�ȁu�V���v�Ƃ́A�����w�I�ȉ���Љ�ɂ���ĈӖ��t�����ꂽ�A�Љ�ہA�������͕������ۂƂ��Ắu�V���v�ł���B�l���u�V���v�Ă��邩�ǂ����͂��̎Љ�̉��l������Ƃɔ��f�����̂ŁA�u�V���v�͎Љ�ɂ���ĈقȂ邵�A�u�V�l�v�Ƃ����l�Ԃ̕����قȂ�B�킽�����{�����̒��łƂ炦�悤�Ƃ���Љ�I�ȁu�V���v�Ƃ́A���肳�ꂽ���ԂƋ�Ԃ̒��ňӖ��t�����ꂽ�u�V���v�̂��Ƃł���B
�킽��������������Љ�������傫���u�ߑ�Љ�v�ƂƂ炦���Ƃ��A�ߑ�Ƃ������ԂƋ�Ԃ̒��ňӖ��t������Ă����u�V���v�Ƃ́A���������ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��낤���B�����Ŏ��ɁA�u�ߑ�Љ�v�Ƃ����ňӖ��t�������u�V���v�͂��邽�߂̘g�g�݂Ƃ��āA�u���{���v�u�J���v�u�ߑ�Ƒ��v�ɂ��ď���ǂ��ĊȒP�ɐ�������B
�Q�@���{���Ƌߑ�
���{���Ƃ������_������j���l����Ƃ��A�O�ߑ�Ƌߑ�̕���_�ƂȂ�̂́A���������̒n�拤���̂̕���Ǝs��̐����ł���B�s��̐����͌o�ύ\����傫���ς��������łȂ��A����ɔ������܂��܂Ȗʂł̕ϊv��l�X�̐����ɂ����炵���B
�O�ߑ�A�܂莩�����������藧���Ă���n�拤���̂̒��ł́A�Ɠ��J���͑S�Đ����ɕK�v�Ȃ��̂Y���邽�߂̘J���ł������B�����ł́A�u���Y�v�Ɓu����v�̖��m�ȋ�ʂƂ������̂͑��݂��Ȃ��B���Ƃ��A�c�A�������Ĉ����āA�����������E�����ĉ�ʂ��Č��ɂ���܂ł̈�A�̍�Ƃ̒��ŁA���������ǂ��܂ł��u���Y�v�ŁA�ǂ����炪�u����v�Ȃ̂��m�ɋ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̂ɕ�炷�l�Ԃ̂��ꂼ��ɖ������S���������Ƃ��Ă��A�S�Ă̘J���݂͂ȂЂƂ������Y�ɂ��������̂ł������B�Ƃ��낪���������̒n�拤���̂����A�l�X�̌o�ϊ����Ɏs�ꂪ�������悤�ɂȂ�ƁA���͈̂�ς����B���Y���ꂽ���i���s��Ɏ������ނ܂ł̍�Ƃ��u���Y�J���v�ƌĂ��悤�ɂȂ�A����ȊO�͑S�ď�����Ɋi�������ꂽ�B�܂�A�s��ɂ����Č������l�������i�ݏo���J�������Y�J�����������A�u�J���v�Ƃ��ĔF�߂���悤�ɂȂ����̂ł���B�H�Ɖ����i�ނƁA���R�u�J���v�Ƃ��ĔF�߂���̂́A�����J���ɂȂ�B�����邱�Ƃ��ł���u�J���v�A����������ΘJ���s��ɂ����Č������l�����J���������ߑ�́u�J���v�Ȃ̂ł���B�㉿���x�����Ȃ��J�����Y�J�����́u�J���v�ł͂Ȃ��̂��B�������A�����Y�J�����^���Y�J�����̋�ʂ́A�X�̘J�������ݓI�Ɏ����Ă�������ɂ���Ĕ��f�����킯�ł͂Ȃ��A�˂Ɏs��̑�����̐������ɂ���ċ�ʂ������Ă����B�N���[�j���O����A���X�g�����A�ۈ牀�ł̘J���͒������x������̂Łu���Y�v�����A�������Ƃ���w��������A����́u����v�Ƃ��ĕЕt������B�s��̐����ɂ���Ĉ����ꂽ�u���Y�v�Ɓu����v�̋��E���́A���ł��s��̗v���ɂ���Ĉړ�����̂ł���B
�u���Y�v�Ɓu����v�����m�ɋ���邱�Ƃɕt�����āA�O�ߑ�I�Ȓn�拤���̂̒��ł͑��݂��Ȃ��������܂��܂ȋ�ʂ��������B�u���Y�v�ɂ������̈悪�u�s��v�ł���̂ɑ��A�u����v�ɂ������̈�Ƃ��ĉƒ낪���܂ꂽ�B�s��Ƃ����u���̈�v�ƁA�ƒ�Ƃ����u���̈�v�̋�ʂ��ł����̂��ߑ�ɂȂ��Ă���ł���B���̌��ʁA���̈�Łu�J���v�ɏ]������u�v�v�ƁA���̈�ʼnƎ��Ƃ������́u����v�����ɏ]������u�ȁv�A�Ƃ������ʖ������S���ł����������B�����A�s��^�Ƒ��A���^���A���Y�^����A�̋�ʂƍ��E�̑Ή������Ƃɂ��Đ��藧���Ă���Љ�̃V�X�e�����u���{���v�ƌĂԁB
���āA�Y�Ɖ��������ނƎs�ꂪ�������Љ�̈�͂��悢��g�債���B���ɂ͎s�ꂪ�l�ԎЉ�̒��S�ɂ������A�킽�������̐������܂ł������܂��܂Ȃ������Ŏx�z����悤�ɂȂ����B�Ƃ��ɂ͖ڂɌ����邩�����ŁA�܂��Ƃ��ɂ͖ڂɌ����Ȃ��������ŁB���ꂪ�u�ߑ�v�ł���B�u�ߑ�v�́A�s��̗̈�Łu�J���ҁv�Ƃ��ē����l�Ԃ������u�l�ԁv�Ƃ��ĔF�߂Ă���B���C�t�R�[�X�́A�u�l�ԁv�\���R�Ƃ��Ă̎q������A�����u�l�ԁv�Ƃ��Ă̐��N����A�u�l�ԁv���ތ�̘V��A�Ƃ����Ȃ���Őݒ肳���B�t�B���b�v�E�A���G�X�́��q�����͋ߑ�ɂȂ��Ă͂��߂Ēa�������ƌ����Ă��邪�A�����悤�Ɂ��V�い�Ƃ����l���̈���Ԃ��A�ߑ�Ƃ�������ɓ��L�̂�����Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B�ǂ�ȎЉ�ɂ����Ƃ����l�Ԃ͂��邪�A���킽�����������Ɏv���`���u�V�l�v�́A���͋ߑ�ɂȂ��Ă���a�������̂�������Ȃ��B�����ċߑ�́u�V�l�v�u�����v�u�q���v�́A�˂Ɏs��Ƃ����Ŋ���u�l�ԁv�̎��ӂɈʒu�t�����Ă����̂ł���B�u�l�ԁv�Y���邽�߂̋@�ւƂ��Ă̋��琧�x�A�u�l�ԁv�Ƃ����J���͂��Đ��Y�����Ƃ��Ă̋ߑ�Ƒ��A�J���͂Ƃ��Ă͎g���Ȃ��l�Ԃ̎M�Ƃ��Ă̕������x�A�����̐��x�Ƌߑ�I���l�ςƂ��A���{�������ɂ��ĉ��u�ߑ�v�Ƃ����Љ���x���Ă����̂ł���B
�R�@�J���Ƒa�O
���ɁA�ߑ�̘J�����Ƃ炦�邽�߂ɁA�}���N�X�́u�a�O���ꂽ�J���v�ɂ��čl���Ă݂�B
�a�O�Ƃ́A�N�w�I�ȈӖ��ŗp������Ƃ��ɂ́A�u�l�Ԃ����o�������̂�l�����A���̐l�Ԃ̎�𗣂�Đ��������������A�t�ɂ��̐l�Ԃ��x�z����悤�ɂȂ�v���Ƃ��Ӗ�����B�}���N�X�͂��̑a�O�Ƃ����T�O�������āA���L���Y���̂��Ƃł̘J������������B�}���N�X�ɂ��u�a�O���ꂽ�J���v�Ƃ́A�u���L���Y���̂��ƂŁA���l(���Y���L��)�̂��Ă��ړI�ɂ��������āA���l(���Y���L��)�̐��Y��i�������čs����J���v�̂��Ƃł���B���������l�Ԃ͐����Ă������߂ɁA��������(���Y��i)�������Ď��R�E�ɓ��������A�������琶�Y���Đ���������B�����ʼn�����邩�Ƃ����ړI�����āA����ɂ��������čs����J���́A�l�ԂɂƂ��Đ����Ă������߂̖{���I�Ȋ����ł���A�{���Ȃ�Ί�������̂ł���͂����B�Ƃ��낪�A���L���Y���̂��Ƃł́A���Y(���Y��i)�������Ȃ��l�Ԃ݂͂�����̘J���͂𑼐l(���Y���L��)�ɔ����Đ��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���R�J���҂͎����ŖړI�����Ă鎩�R�������Ȃ��̂ŁA���l(���Y���L��)�̂��Ă��ړI�ɂ��������āA�܂�͑��l���疽�߂��ĘJ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����Ɠr�[�ɁA�{���͐l�ԂɂƂ��Ė{���I�Ŋ�������̂ł������͂��̘J�����A�J���Ҏ��g���ꂵ�߂���̂ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�A�u�a�O���ꂽ�J���v�ł���B���{��`�̂��Ƃł͘J���҂͎��{�ƂɘJ���邵���Ȃ��A���Y�̖ړI�Ǝ�i�����L�ł��Ȃ������łȂ��A���Y���܂ł������{�Ƃ̂��Ƃɂ킽���Ă��܂��A�J���҂̎�Ɏc��̂́u�����v�����ł���B
�S�@�ߑ�Ƒ��Ɓu�V���v
�ߑ�ɂ�����u�V���v�ɂ��čl���邤���ł̏d�v�ȃL�[���[�h�Ƃ��āA���̈�Ƃ��Ắu�Ƒ��v����������B�V�l�́u���ꏊ�v�̖����A�u�ƒ�v���ɂ��čl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����āA���̘V�l�Ɓu�ƒ�v�Ƃ̊W�����܂��܂Ȗ����͂��ł���̂́A�V�l�̐�������u�ƒ�v���u�ߑ�Ƒ��v�Ƃ��Ă̓�����F�Z���L���Ă��邩��ł���B
�Љ�j�I�A�v���[�`����̉Ƒ��j�����́A�킽�����������z�I�����R�Ȃ��̂Ǝv������ł����Ƒ������͋ߑ�ɂȂ��Ă���o�ꂵ�����Ƃ����A������u�ߑ�Ƒ��v�Ɩ��Â����B�ߑ�Ƒ��Ƃ́A���{���̐����ɂƂ��Ȃ��āA�J���͂��Đ��Y���邽�߂̏�Ƃ��Ďs��̊O���ɂ���ꂽ���I�̈�ł���B�����b���q�́A�ߑ�Ƒ��̗v�����ȉ���8�ɐ������Ă���B[1]
�@�@�Ɠ��̈�ƌ����̈�̕���
�A�@�Ƒ��\�������݂̋�����I�W
�B�@�q�ǂ����S��`
�C�@�j�͌����̈�E���͉Ɠ��̈�Ƃ������ʕ���
�D�@�Ƒ��̏W�c���̋���
�E�@�Ќ��̐��ނƃv���C�o�V�[�̐���
�F�@��e���̔r��
(�G�@�j�Ƒ�)
�ߑ�Ƒ��́A���{����s��̓o��Ƃ���ɂƂ��Ȃ��J���̕ω��ɋN�����Ă���A�����̗v���͂������瓱���o�����B�����A�킽�������ꂩ��u�V���v�ɂ��Ă̘b��i�߂Ă�����ŁA�^���������������Ȃ��v�������������B���ꂪ�A8�Ԗڂ́u�j�Ƒ��v�Ƃ����v���ł���B�������g������̓J�b�R�ɓ���Ă��āA���̗��R���u�c����Ɠ������Ă��Ă��A���I�ɂ͋ߑ�Ƒ��I�Ȑ��i�������Ă��邱�Ƃ����肤�邩������܂���v�Ɛ������Ă���B�܂�����ߎq���A�����́u�j�Ƒ��v�̏������J�b�R�ɓ���邱�Ƃɂ���āu�w��O�Ƒ��Ɛ��Ƒ��̘A�����x���������邱�ƂŁA���ɐ�O�Ƒ��̋ߑ�I���i�ƁA���ɐ��Ƒ��̉ƕ������I���i�Ƃ��A�����ɘ_���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�v�ƌ����Ă���B[2]�@���҂̈ӌ��́A�u�O���㓯���̉Ƒ����ߑ�Ƒ��ƌĂׂȂ��ƍ��邩��v�j�Ƒ��Ƃ��������͓���Ȃ��Ă悢�A�Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă���B�������킽���́A�j�Ƒ����ߑ�Ƒ��̗v���Ƃ��Ȃ����ƂɁA�����ƐϋɓI�ȗ��R������悤�Ɏv���B����́A�j�Ƒ������ނ���O���㓯���̂ق����A���͋ߑ�Ƒ��̗v���Ƃ��Ă̑Ó��������A�Ƃ����_�ł���B�ߑ�Ƒ��Ƃ́A���{���̂��ƂŎs���������J���͂��Đ��Y�����ɂق��Ȃ�Ȃ��B�ߑ�Ƒ����u�v�v�Ƃ����J���͂̍Đ��Y�Ɓu�q�ǂ��v�Ƃ��������̘J���͂��Đ��Y�����Ƃ��ċ@�\����̂��Ƃ�����A�u�V�l�v�Ƃ����J���͂ɃJ�E���g����Ȃ��Ȃ����l�Ԃ̐����̏�ł�����͂��ł���B�܂��́A�����Ȃ��Ȃ����u�V�l�v�́u���v�Ƃ����d�����ߑ�Ƒ��͒S�킳��Ă���͂��ł���B�����l����A�����I�ȁu�Ɓv���x�Ƃ��ė�������Ă�����O�Ƒ����A���͋ߑ�Ƒ��̏o���_�ł������ƌ�����B�܂�A�j�Ƒ��͋ߑ�Ƒ��̕K�v�����ł͂Ȃ��A�ߑ�Ƒ��̃o�[�W�����̂ЂƂȂ̂��B�����āA�O���㓯�����j�Ƒ������l�ɋߑ�Ƒ��̃o�[�W�����ł���ƍl����ƁA�����ЂƂo�[�W�����Ƃ��ĉ�����ׂ����̂����邱�ƂɋC�����B���ꂪ�A�q�����Ɨ��������Ƃ̘V�v�w���тł���B
�ߑ�Ƒ��ɂ��Ă̕�����ǂ�ł���ƁA�c�_�̑O��ɕ��E��E�q����Ȃ�j�Ƒ������邱�ƂɋC�����B�ΏۂƂ���Ă���̂́A�˂Ɂu�q���v�̂��鎞�_�ł̉Ƒ��ł���B���R�A�������Ău�q�ǂ��v�͓Ɨ����A�v�w�������Ƒ��̒��Ɏc����鎞��������Ă���B�Ƃ��낪�A�ߑ�Ƒ��_�̒��ɘV�v�w���o�Ă��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�c�_�̒��Ɂu�V�l�v���o�Ă���̂́A��삪�K�v�ƂȂ����e���ǂ̉Ƒ����������̂��A�Ƃ������������B���������ۂɂ́A�u�q���v���Ɨ����Ă����삪�K�v�ɂȂ�܂łɂ͂��Ȃ�̔N��������B�������ɕ��ώ���80�Ƃ������オ30�Ŗ��q�݁A���̎q��25�œƗ������Ƃ�����A�Ō��5�N�Ԃ͉���K�v�Ƃ��Ăǂ����Ɉ������ꂽ�Ƃ��Ă��A��20�N���̍Ό���V�v�w���тő��邱�ƂɂȂ�B���̊��Ԃ͎��ɐl����4����1�ɂ�����B����20�N�Ԃ́A�ߑ�Ƒ��́u��O�v�Ȃ̂��낤���B�킽���͂����͎v��Ȃ��B�V�v�w�����ɂȂ������̊��Ԃ��A��͂�ߑ�Ƒ��̃o�[�W�����̈�Ȃ̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�ߑ�Ƒ����K�肵�Ă���̂͂��̍\�����ł͂Ȃ��A���Y�W�̕ω��ɂ���Đ������\�����̐��ʁE�N��ʖ������S������ł���B
�����́u21���I�Ƒ��ցv�̒��ŁA�j�Ƒ������̂悤�ɒ�`���Ă���B�u�j�Ƒ��̊j�Ƃ����̂́A�j���e�̊j�A���q�j�̊j�ŁA����ȏ㕪���ł��Ȃ����̂Ƃ����Ӗ��ł��B�j�Ƒ��Ƃ́A�v�w�Ɩ����̎q�ǂ�����Ȃ�Ƒ��ł��B�v(80�y�[�W)�@�킽���ɂ́A�܂������ł���悤�Ɍ����ĂȂ�Ȃ��B���������A�O���㓯�����ɕ����������_�œ�̊j�Ƒ����ł��Ă���̂�����A�Ⴂ����̕v�w�Ƃ��̎q�ǂ����������グ�āu�j�Ƒ����v�ƌ������Ǝ��̂��A�ߑ�Ƒ��C�f�I���M�[�ł���ƌ����Ă��悢�B�����́A�j�Ƒ���l�ނɕ��ՓI�ȒP�ʂł���Ǝ咣����}�[�h�b�N�́u�ߑ�Ƒ��̓������A�Ƒ���ʂ̓����Ǝv���Ⴆ���v(106�y�[�W)�ƌ����Ă��邪�A����ł��Ȃ��j�Ƒ��́u�Ƒ��v�̍ŏ��P�ʂɌ������̂��낤���B
�Ƒ��Ƃ������܂�ɂ����R�ȗ̈��E�^���������Љ�j�ƁA����ɂ��̒��ɃW�F���_�[�Ƃ����g�g�݂������t�F�~�j�Y���́A�킽����������i�߂邤���ł̔��ɏd�v�ȓ�����ׂł���B�������u�ߑ�Ƒ��v�Ƃ����c�_�̒��ɂ��A�܂��ˑR�Ƃ��āu���R�Ȃ��́v�ɂƂǂ܂��Ă�����̂�����B���ꂪ�u�V���v�ł���B�����{�Љ�́u�V���v�͂��悤�Ƃ���Ƃ��A�����Ɍ����Ă���̂͘V�v�w���т̎��ߑ�Ƒ����Ȃ̂ł���B
�T�@�ߑ�́u�V���v�Ƃ�
�Ō�ɁA�ȏ�̗��_��O��Ƃ��āA�{�����ɂ�����ߑ�́u�V���v���`���Ă��B�g�̓I�ȕω��Ƃ������ʂ���u�V���v���͂���̂ł͂Ȃ��A���{�������ɂ���u�ߑ�v�Ƃ����Љ�̂Ȃ��ňӖ��t����ꂽ�u�V���v��T��ƁA���̂悤�Ɍ������Ƃ��ł���B���Ȃ킿�ߑ�́u�V���v�Ƃ́A�J�����Ɠ��J����������J���ɕς�邱�Ƃɂ���āA�J���҂�����N��ɒB����ƘJ���s��ł݂�����̘J���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƁA�܂�u�����Ȃ��Ȃ邱�Ɓv�ł���B�������A�u�����Ȃ��Ȃ�v�͉̂���ɂ���ē����̗͂��Ȃ��Ȃ邩��ł͂Ȃ��A�����܂ł��J���s��ł̔�������������Ƃɂ���āu�����Ȃ��Ȃ�v�̂ł���B�s��́A����܂Łu�l�ԁv�Ƃ��āu�J���v�ɏ]�����Ă����l�X���A����N��ɂȂ�Ǝs��̓s���ŘJ���s��̊O���ւƒǂ����B��̓I�ȗ��������A��N�⒆���N�̃��X�g�����A�s��̑�����̘J���҂̒��ߏo���ɂ�����B���邢�́A��ٗp�҂łȂ����ق��J���҂ɂƂ��ẮA�J���s��̊O���ւ̐������͂����Ɨ����I�ɂ������I���ɕ\���̂�������Ȃ��B
�J���҂��N��𗝗R�Ɏs�ꂩ��ǂ��o�����\���́A���ۂɂ͂ǂ̂悤�ɂ��ďo���オ���Ă����̂��B�ǂ��o���ꂽ�u����ҁv�������������u�ƒ�v�Ƃ����ߑ�Ƒ��B�ނ�͂����ł��̂悤�Ȗ����������A����K�v�Ƃ��Ă���̂��B�����m�邽�߂ɁA���͈ȍ~�ł͎��ԂƏꏊ����̓��{�Љ�Ɍ��肵�A��̓I�ȃf�[�^�����ǂ��Ă������Ƃɂ���B
2�́@�����{�Љ�Ɓu�V���v
�{�͂ł́A���̓��{�Љ�Ƃ�����̋ߑ�Љ�̒��Łi�������͈�̋ߑ㉻�̉ߒ��ɂ����āj�A�O�͂Œ�`�����u�V���v���ǂ̂悤�Ȍ��ۂƂ��Đi�s�����̂����A���v��p���ă}�N���̎��_����T���Ă����B
�P�@���̘J�����̕ω��@�\�\�u�T�����[�}���v�̑�O���\�\
��ꎟ�Y�ƁA�܂�_�Ƃɏ]������l�Ԃ�����A��E��O���Y�Ƃɏ]������l�Ԃ������Ă����ߒ��́A�܂��ɋߑ㉻�̉ߒ����ƌ�����B��E��O���Y�Ƃɏ]������l�Ԃ̑����́A�H����ЂȂǂɌق��ē����J���ҁA�܂�u�����J���ҁv�ƂȂ邩�炾�B�����@�́A20���I�ɓ����Ă���̓��{�̎Y�ƍ\���̕ω����A�ƎҊ����ɂ���ĕ\�����O���t�ł���B
���̃O���t������ƁA��ꎟ�Y�Ƃ����E��O���Y�Ƃւ̘J���͂̃V�t�g���A1950�N���_�@�ɂ��Ĉ�C�ɉ������Ă��邱�Ƃ��킩��B1920�N����50�N�ɂ����Ă��ω��͌����邪�A1950�N�ȍ~�A����70�N�ɂ����Ă͒������ω��̌X����������B�قڂP�P��������ꎟ�Ƒ���O���Y�Ə]���҂̊����́A���̂킸��20�N�̊ԂɂP�S�ɂȂ��Ă���B
���̎Y�ƍ\���̕ω����A�A�ƎҐ��̊����ł͂Ȃ������Ō��Ă݂�ƁA�����A�̂悤�ɂȂ�B�����̕ω������Ă݂�ƁA�Y�ƍ\���̃V�t�g�ɉ��S���Ă���̂͑�ꎟ�Y�Ə]���҂̌����������A��E��O���Y�Ə]���҂̑������̂ق����Ƃ������ƂɋC�����B�܂�A�_�Ə]���҂̐������������Ƃ������́A��_�Ə]���҂̐��������I�ɑ��������̂������{�̋ߑ㉻�̓����������̂��B1950�N����70�N�ɂ����āA��ꎟ�Y�Ə]���҂̌�����700���������̂ɑ��āA��E��O���Y�Ə]���҂̑�����2400���l�ł���B��E��O���Y�Ƃ����ɒ��ڂ��Ă݂Ă��A1930�N����50�N�ɂ����Ă�20�N�Ԃ̑�������������300���l�ł���̂ɑ��āA50�N����70�N�ɂ����Ă�20�N�Ԃɂ͂���8�{�ɓ�����2400���l���̑�����������B����́A����25�N�Ԃɂ����đ��������J���͐l�����A�قƂ�ǂ��̂܂ܔ�_�Ə]���҂ƂȂ������Ƃ��Ӗ�����B�����ɁA�����{�̋ߑ㉻�̒S����ƂȂ�������w�̉e�������Ă���B
���Ɏ����B�́A�ٗp�Ҕ䗦�̕ω��A�܂�S�A�ƎҐ��ɐ�߂�ٗp�Ґ��̊����̕ω����O���t�ɂ������̂ł���B[5]���������ƁA����т��Ă���ٗp�Ҕ䗦�̏㏸�̒��ł��A����1955�N����65�N�ɂ����Ă�10�N�ԂɁA�������㏸�����邱�Ƃ��킩��B1960�N�ɂ͌ٗp�Ҕ䗦��50�����Ă���B�܂��ɁA�u�T�����[�}���v����O����������ƌ����Ă������낤�B�����Ă���͂��傤�ǁA�����̘J���͗���50���������A�܂�u��w�v����O������1970�N�ɑk�邱�Ƃ��傤��10�N�ł���B
�Q�@�T�����[�}����O����S�����ڍs������
�ł́A1950�N�ォ��60�N��ɂ����Ă̑�E��O���Y�Ƃɂ�����J���͂̔����I�����̒S����ł���A�ٗp�҂Ƃ��ăT�����[�}����O������̎���ƂȂ����̂́A��̓I�ɂ͂ǂ̂悤�Ȑl�Ԃ������̂��낤���B
�����b���q�́w21���I�Ƒ��ցx�̒��ŁA�l���w�I�Ɍ����ڍs�����オ�������ߑ�Ƒ����u�Ƒ��̐��̐��v�ƌĂ�ł���B�l���w�̈ڍs������Ƃ́A������ߑ㉻�ȑO�̎O�p�`�̐l���s���~�b�h���A�ߑ㉻���ꂽ�ޏ��`�̐l���s���~�b�h�ւƈڍs����ߒ��Ő����鐢��̂��Ƃ��w���B�O�҂͑��Y�����̎Љ�ŁA��҂͏��Y�����̎Љ�ł���B���Y�������班�Y�����ւ̈ڍs�̗��R�́A��ɐH�Ƃ�q����Ԃ̉��P�Ɨ{���̍�������������B�������ߑ㉻�͂�����x�̔N���������ď��X�ɐi�s����̂ŁA���S���͒ቺ���Ă���̂ɏo�����͂���܂łƂ������ĕς��Ȃ��Ƃ�����Ԃ��ꎞ�����邱�ƂɂȂ�B���̑��Y�����̐�����A�ڍs������ƌĂԂ̂��B���R�A�ڍs������͂��̑O��̐���ɔ�ׂĐl���������̂ŁA�ނ�̂Ƃ�s���͎Љ�ɑ傫�ȉe����^����B���{�̏ꍇ�A���̈ڍs�������1925�N���܂ꂩ��1950�N���܂�ɂ�����B�����́A���̐��オ1950�N�ォ��70�N��ɂ����Ă̐��ɁA���ɕω��̏��Ȃ����肵���Ƒ��̐���z�����̂��Ɛ������Ă���B�����Ă��̐���̋�̓I�ȒS����Ƃ́A�_�Ƃɐ��܂ꂽ���j�O�j�ł���B�ނ炪�s�s�ɏo�Ă��Čٗp�҂ƂȂ��Č������A��Ǝ�w�̍ȂƂƂ��Ɋj�Ƒ��^�ߑ�Ƒ����������̂��B���̐���̓����́A���������̌Z��o���͑����̂ɁA�������������q�ǂ��͏��Ȃ��Ƃ����_���B�܂�ނ�̂������j�Ƒ��������A���킽�������̑��������ɕ`��������u���z�̉Ƒ��v���Ȃ̂ł���B
��ɂ����������������Ă������Ƃ́A�����́u���Ƒ��v���ƈ�v����B�_�Ə]���Ґ��̌����ł͂Ȃ���_�Ə]���Ґ��̔����I�ȑ����Ƃ������ۂ��N�������̂́A�_�Ƃ̎��j�O�j�Ƃ����ڍs�����オ��������Ȃ̂��B�����Ă��̈ڍs�����ケ�����A��ꎟ�Y�Ƃ����E��O���Y�Ƃւ̘J���̓V�t�g�̔g�ɏ���ĐV���Ȍٗp�ґw������o�����A�����{�̋ߑ㉻�̒S���肾�����̂ł���B
���ɂ��̈ڍs������ɒ��ڂ��āA�ٗp�Ҕ䗦���o���R�[�z�[�g�ʂɌ��Ă݂�B1925�N���܂ꂩ��1950�N���܂�܂ł̈ڍs����������������ׂ���������ƁA�u���a��P�^����v�i1925�`34�N���܂�j�u���a��P�^����v�i1935�`44�N���܂�j�����āu�c��̐���v�i1945�`49�N���܂�j�̎O�ɕ����邱�Ƃ��ł���B����Ɉڍs������ȑO�̈ꐢ����u�吳����v�i1910�`24�N���܂�j�ƌĂԂ��Ƃɂ���B[7]�����C�́A1965�N�����̌ٗp�Ҕ䗦���e���ゲ�Ƃɒ��ׂ����̂ł���B���������ƁA�u�吳����v����u���a��P�^����v�Ɉڍs����Ƃ���Ōٗp�җ���5�����A�T�����[�}������O�����Ă��邱�Ƃ��킩��B����Ɂu���a��P�^����v�u�c��v�ɐi�ނɂ�āA���̊����͋}���ɑ����Ă����B[8]�ڍs������́A�܂��Ɂu�T�����[�}���̐���v�ł���ƌ�����B
�R�@�u��N�v�Ƃ������́A�ڍs������́u�V���v
���̃T�����[�}����O����S�����ڍs�����オ�A���Ƃ��ĘJ���s�ꂩ����ߏo����邫�������ƂȂ���́A���ꂪ�u��N�v�ł���B�����D�́A�ꗥ��N���̕��y���O���t�ɂ������̂ł���B
��N���ɂ́A��ʂɂ͐E�\�ʒ�N����E�K�ʒ�N���A�j���ʒ�N��������B�ꗥ��N���Ƃ́A�����E���ʂɊW�Ȃ��A�ЂƂ̊�Ƃ̒��ňꗥ�̒�N�N���݂�����N���̂��Ƃł���B�S��Ƃ�100�Ƃ����Ƃ��Ɉꗥ��N�����̗p���Ă����Ƃ̊����́A80�N�ɓ����������瑝�����A80�N��㔼�ɂ�7�����A90�N�㏉���ɍ���8���O��̐����ɒB���Ă���B
�܂������E�́A��N�N��̕ϑJ������킵�Ă���B���̒�N����55����ʓI���������A1984�N�ɂ�60�Έȏ��N�̊�Ƃ�59�Έȉ���N�̊�Ƃɋt�]���ď����Ă���B1986�N�ɂ�60�Έȏ��N���@���ɂ���ċ`�������ꂽ�̂ŁA����ȍ~��60�Έȏオ��ʓI�Ȓ�N�N��ƂȂ����B[12]���Ȃ݂�60�Έȏ��N���ƌ����Ă��A���̂قƂ�ǂ�60���傤�ǂ���N�N��ł���B98�N�̒i�K�ŁA�ꗥ��N�����̗p���Ă����Ƃ�100�Ƃ����Ƃ��ɁA60���N�N��ɂ��Ă����Ƃ�86�D7���ɂȂ�B
���āA��قǂ̈ڍs������̃g�b�v�o�b�^�[��60�ɓ��B����̂͂��傤��1985�N�ł���B��������ƁA��Ƃƍ��ɂ���Đ�������A���������Ƃ���ʓI�ƂȂ����u60�Β�N���v�ɂ҂�����Ɠ��Ă͂܂�̂��A���͂��̈ڍs������Ȃ̂ł���B�ڍs������̓����́A����ȑO�ɔ�ׂĔ��ɐl���������A���������̑������ٗp�҂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��B�܂�A1960�N�オ�u�T�����[�}���v��O���̎����70�N�オ�u��w�v��O���̎���Ȃ�A80�N��㔼����90�N�ɂ����Ắu��N�v��O���̎���Ɍ����Ă̂��傤�Ǔ�����Ȃ̂ł���B������2000�N���}�������A�܂��Ɂu��N�v��O���͋}���ɐi�s���A5�N��ɍT�����u�c��̐���v�Ƃ����ƂĂ��Ȃ��傫�Ȑl���̒�N�N��B�Ɍ����Ă܂�������ɓ���i��ł���B�u��N�v�̑�O���́A1�͂ŏq�ׂ��ߑ�́u�V���v�����{�Љ�ɂ����đ�O���x���Œ蒅���Ă����ߒ��ł�����B�吨�̐l�Ԃ��A�u�����J���ҁv�ƂȂ�u�ٗp�ҁv�Ƃ��ĒN���Ɍق��ē����悤�ɂȂ�B���̌��ʁA�J���͂��������l�������Ȃ��N��ɒB�����Ƃ��A�ނ�͂��������ɘJ���s��̒��S������ӂւƒǂ������̂��B���{������̃s�[�N���}���悤�Ƃ��̂��鍠�A�����ɕ�炷�u����ҁv�̂قƂ�ǂ́A�u��N�v�Ƃ����u�V���v���}�����V�l�����Ȃ̂ł���B
�S�@��N�\�\�������Ȃ��Ȃ遄�\���\�\
�ł́A��N���}��������҂��Ƃ肩���ޘJ�����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���B
�@���ł́A��N���65�܂ł̌p���ٗp��Čٗp�����サ�Ă���B[13]�����������ɂ́A��N���65�܂œ����E��œ������Ƃ��ł���P�[�X�͌����đ����Ȃ��B
�����F[14]
�����F�����Ă݂�ƁA�ꗥ��N�����̗p���Ă����Ƃ̒��ŁA65�Έȏ��N�����̗p���Ă���̂́A�킸��5�D1���ɉ߂��Ȃ��B60����64�܂ł̒�N���̊�Ƃ̂����A��]�ґS���Ɍp���ٗp��Čٗp��F�߂Ă����Ƃ�15�D2��������A��]�����Ј��S����65�܂œ������Ƃ̂ł����Ƃ́A20�D3�������Ȃ��B�܂��A���Ƃ��Čٗp���ꂽ�Ƃ��Ă��A�قƂ�ǂ̏ꍇ����܂ł̎d������͑啝�ȃ|�X�g�I�t�ɂȂ�A������������B�����ɂ���̂͂�͂�u��N�v�Ƃ����J���s��̋��E���Ȃ̂ł���B
���Ɏ����G�́A�������N�̔N��ʗL�����l�{���ł���B98�N�̗L�����l�{��������ƁA60�Έȏ��0.07�{�Ƃق��̔N��ɔ�ׂĂ���߂ĒႢ�B�Ƃ������قƂ�Nj��l���Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B92�N����98�N�ɂ����Ă�6�N�Ԃ̓��������Ă��A90�N��ɓ����Ă���̕s���̉e���ŁA���Y�N��S�̂ł��L�����l�{���͂Q����1�Ɍ������Ă��邪�A�N��ʂɌ����ꍇ�A60�Έȏ�̔{���͂U�N�ԂɂR���̂P�ɂȂ��Ă���B�s���ŘJ���s�ꂪ�k�����悤�Ƃ���Ƃ��A�s��̊O���Ƃ��Ē����̑ΏۂƂȂ�͍̂��N��҂ł��邱�Ƃ��悭�킩��B������ɂ��Ă��A���݂̏ł͒�N�ސE�����J���҂��V�����E�邱�Ƃ͌���Ȃ��s�\�ɋ߂��ƌ�����B
�����G�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[15]
�܂�A�ڍs������ɂƂ��Ă̐��̘J�����Ƃ́A�����J���҂ƂȂ��ĒN���Ɍٗp����ē����Ƃ����A�ƍ\���ƁA�u��N�v�Ƃ����N��𗝗R�Ɍٗp�҂�J���s��̊O���ɒǂ��o�����x���g�ݍ��킳�ꂽ�������Ȃ��Ȃ遄�\���ł������B1�͂ł��q�ׂ��悤�ɁA�u�����Ȃ��Ȃ�v�̂͌����đ̗͂����ނ��ē��̓I�ɓ����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��A�N��𗝗R�ɘJ���̔����肪���Ȃ��Ȃ邽�߂Ɂu�����Ȃ��Ȃ�v�̂ł���B
�T�@�������Ȃ��Ȃ遄���������Ȃ��Ă��悢���\��
�����܂ł́A���̓��{�Љ���A�ٗp�҂���O���������オ��N�N��ɓ��B���邱�Ƃɂ���āu�����Ȃ��Ȃ�v�l�Ԃ��吨���܂��Љ�Ƃ��ĐU��Ԃ��Ă����B���������́A�������Ȃ��Ȃ遄�\���́������Ȃ��Ă��悢���\���ƃR�C���̂悤�ɗ��\��̂ɂȂ��ďo���オ�����B
���{�̐��́A�O�q�̎Y�ƍ\���̃V�t�g�ɂ���āA���E�ł��܂�Ɍ���قǂ̃X�s�[�h�Ōo�ϐ����𐋂�������ł������B��20�N�ɋy�ԁu���x�����v�̊ԂɁA�o�ϐ�������10�����z����N���������D�i�C��2�x���K��A�u�����{���v��v�������̂��̂ƂȂ������Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���B�����H�́A�ΘJ�Ґ��т̎������������̑��������O���t�ɂ������̂ł���B���������ƁA60�N�ォ��73�N�̃I�C���V���b�N�ɂ�����܂ł̊��ԁA�����������������قږ��N6���ȏ���������Ă��邱�Ƃ��킩��B�_�Ƃ��o�Ē����J���҂ƂȂ��ē����Ƃ������Ƃ́A���N�̂悤�ȏ����ƒ��~�A����ɂ���Ď�������u�L���Ȑ����v�ւ̃X�e�b�v�ł��������B�u�O��̐_��v�ƌĂꂽ����@�A�①�ɁA�e���r���A�_�����s�s�����ɕ��y�����B[16]�T�����[�}���ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�Љ�I�n�ʂ̌���ł��������̂��B
���̍��x�����Ɏx�����ċ}���ɔ��W�������́A���ꂪ�e��̎Љ�ۏᐧ�x�ł���B������l������̎Љ�ۏዋ�t��[18]�́A1951�N�x��1900�~����1996�N�x��53��6600�~�ւƁA����280�{�ɂ��Ȃ��Ă���B������96�N�x�̒i�K�ŁA�Љ�ۏዋ�t��̖�5�����߂Ă���̂��N���ł���B���I�N�����x�͑傫���킯�āA�S�������������鍑���N���i��b�N���j�A���Ԍٗp�҂�������������N���ی��ƁA�����������������鋤�ϔN���Ƃɂ킯����B98�N�̒i�K�ŁA�����N���̕��ϔN�����z��4��7��~�ł���̂ɑ��A�����N���ی���17��2��~�ł���B����ɉ����āA�����̊�Ƃ��ސE�����x���̗p���Ă���B�����܂ł��Ȃ��A�����̎�����V��ۏႪ���������̂͐��̍��x����������������ł���A���x������S�����J���҂���������ł���B�܂�A�ڍs������̘J���҂����́A�ٗp�҂Ƃ��ē����Â������ʁu��N�v�ɂ���ĘJ���s�ꂩ��ǂ��o����Ă��܂������A����͓����ɁA��N�ސE�ɂ���ē�����ސE���ƔN���Ɏx����ꂽ�u��Ƃ肠��V��v�̊l���ł��������̂��B�Љ�ۏ�̊g�[�Ƃ����������Ȃ��Ă��悢���\���́A���x�����Ƃ�����x�������̏A�ƍ\���i���������Ȃ��Ȃ遄�\���j�ɂ���ĉ\�ɂȂ����B�����������ɁA�������Ȃ��Ȃ遄�\�����\�ɂ��Ă���̂́������Ȃ��Ă悢���\���ł�����̂��B
���̌������o�Ϗ̒��Ő����ی�̑ΏۂƂȂ�V�l���吨�����ɂ����āA���R�u��Ƃ肠��V��v�Ƃ́u���z�̘V��v�ł������͂����B�s�s�ɏZ��ŃT�����[�}���Ƃ��ē����A��Ǝ�w�̎��ƒ�Ƃ����ߑ�Ƒ��̒��ŁA���N�g�傷�鏊���ɂ���āu�L���Ȑ����v���������A�u��N�v���}���āu��Ƃ肠��V��v�𑗂�B����Ӗ��ł͐��̓��{�l�ɂƂ��ā����z���Ƃ���Ă����������A�����̐l�ԂɂƂ��ā��������̂��̂Ƃ����̂��ڍs������ł������B���������́����z�������������ƂȂ����Ƃ��A�T�����[�}���������ڍs�����オ���܂��ɒ��ʂ��Ă���̂͂܂��ɋߑ�́u�V���v�ł��������̂��B�u��N�v�Ƃ����u�V���v�́A���ȓI�Ȋ�Ƃɂ��؎̂Ă����������Ő�����̂ł͂Ȃ��B���������āA��Ƃ��S�����ւ��č���҂�65�܂ō̗p�����Ƃ���ŁA�ǂ��ɂ��Ȃ���ł͂Ȃ��B�ٗp������Čٗp�̗v���́A����A�J�҂ɂƂ��Ă̓��ʂ̎��Ԃ��D�]�����邩������Ȃ����A����͌����Ė{���I�Ȗ������ɂ͂Ȃ���Ȃ��B�u��N�v�𐬗��\�ɂ��Ă���̂́A�ނ玩�g���l�������u�L�����v�ł�����A�u�V���v�͂��̕��G�ɓ���g�\���̒��ɑg�ݍ��܂�Ă���̂��B
�����āA��N��̍���҂������A���Ă���ꏊ�A���ꂪ�V�v�w���тƂȂ����u�ߑ�Ƒ��v�Ȃ̂ł���B�����͓��{�̐����A�o�ς���U��Ԃ���x�����̎���ł���A��������U��Ԃ��55�N�̐��̎���ł��������A�u�Ƒ��v�Ƃ������_���猩��u�Ƒ��̐��̐��v�̎��ゾ�����ƌ����Ă���B���́u�Ƒ��̐��̐��v�́A�ڍs������Ƃ��������I�Ȑ���ɂ���ĒS��ꂽ���ʁA���j�I�ɂ��܂�ȂقLj��肵���Ƒ�������A���̉Ƒ������킽�������̈ӎ��̒��ɂ�������ƐA�����B�ɂ�������炸�A�����ɂ́u���̉Ƒ��̐��v�͂킽�������ɂ��̉Ƒ����������c�����܂܁A�ߋ��̂��̂ɂȂ낤�Ƃ��Ă���B���ꋎ�낤�Ƃ��Ă���u���z�̉Ƒ��v�̐�ɂ́A�܂��킽�������ɂ͂��ݓ��Ȃ����l�������Ƒ����҂��\���Ă���A���́w21���I�Ƒ��ցx�����Ă̓W�]���J�����߂ɗ����͂��̖{���������ƌ����Ă���B���̑��l�������u21���I�Ƒ��v�̒��ɁA�q�ǂ������łɓƗ����A��N���}�����V�v�w���т���̈ʒu���߂Ă��邱�Ƃ́A�����炭�ԈႢ�Ȃ��Ƃ킽���͍l����B�u�q�ǂ���ł����Ƒ��̋@�\���ʂ����Ă���̂ł����āA�q�ǂ����Ɨ����Ă��܂�������͂�Ƒ��ł͂Ȃ��v�Ƃ������_�����邩������Ȃ��B�������ɁA�V�v�w���т͎q�ǂ��̍Đ��Y�Ƃ����Ƒ��̋@�\�͉ʂ����I�����B���̂����A�u��N�v���}�����v�w�́A�v�̘J���͂��Đ��Y����Ƃ����@�\���ʂ����I���Ă��܂��Ă���B����ł��Ȃ��킽�����V�v�w���т��u�ߑ�Ƒ��v�ƌĂԂ̂́A�V�v�w���т͘J���͂̍Đ��Y�Ƃ����ړI���������u�Ƒ��v�Ƃ��č\������@�\�������Ă����̂ł����āA�q�ǂ����Ɨ����ĕv���u��N�v���}��������ƌ����āA���̍\�����}�ɕς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B�V�v�w���тƂ́A�u�Ƒ��v�Ƃ����@�\���ʂ����I���Ă��܂����Ƒ��Ȃ̂ł���B
3�́@����ҏA�Ƃ̌���
�{�͂���́A�O�͂œ��v��p���ĊT�ς��������{�ɂ�����u�V���v���A����̓I�Ɍ�����B���ۂɁu��N�v���}��������ҒB���߂����āA�����ɂ͉����N�����Ă���̂��낤���B�����̑ΏۂƂ��Ď��グ���̂́A����҂̕�����J������Ƃ��Ắu�V���o�[�l�ރZ���^�[�v�ł���B�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ́A�ȒP�Ɍ�������Ҍ����̐E�ƏЉ�̂悤�Ȃ��̂ł���B�{�����ɂ����āA�킽�����V���o�[�l�ރZ���^�[�ɒ��ڂ����ړI�͓����B���̖ړI�́A����҂ɑ���A�J����ɂ��Ēm�邱�Ƃł���B����҂ɏA�J�̋@������ړI�Ƃ͉��Ȃ̂��낤���B�����Ď��ۂɂ����Œ���Ă���A�J�̓��e�͂����Ȃ���̂Ȃ̂��낤���B���̖ړI�́A�V���o�[�l�ރZ���^�[��ʂ��Ď��ۂɏA�J���Ă��鍂��҂ɂ��Ēm�邱�Ƃł���B�N�������Ă��鍂��҂ɂƂ��ẮA�V��́u�����Ȃ��Ă悢�v�����ł���B�����炭������ɋ�J���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤����҂́A�Ȃ�����ł��������Ƃ���̂��낤���B
�����ł܂��{�͂ł́u�V���o�[�l�ރZ���^�[�v�Ƃ�������ɒ��ڂ��A���̐ݗ��o�܂ƌ���A����ҏA�Ƃ̎��Ԃɂ��Ė��炩�ɂ���B�����ĂT�͂ŁA�V���o�[�l�ރZ���^�[��ʂ��ē�������҂̈ӎ����A�u���������v�Ƃ������t���L�[���[�h�ɂ��ĕ��͂���B
�P�@�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ�
�@�@�V���o�[�l�ރZ���^�[�̕ϑJ
�V���o�[�l�ރZ���^�[�i�ȉ��A�{�����́u�Z���^�[�v�Ɨ����j�́A���l�����鍂��҂̏A�Ƃɑ���j�[�Y�ɂ������邽�߂ɁA�����s����̂ƂȂ��āA�����s����Ҏ��ƒc�Ƃ���1974�N�ɐݗ����ꂽ�B����܂ł̍���҂̏A�Ǝ{�J���s���ƕ����s�����ꂼ��̑��ʂ���ʌɂȂ���Ă����̂ɑ��A����Ҏ��ƒc�͘J���ƕ����̗��ʂ�����V�����A�ƃV�X�e���Ƃ��č\�z���ꂽ�B�A�Ƃ�ʂ�������҂̎Љ�Q���ƁA�n��𒆐S�Ƃ�������Ҏ��g�̎���I�ȍs���ɂ��g�D���A�V�����V�X�e���̗��O�ł������B75�N�ɂ́A�n�捂��Ҏ��ƒc�i�n��Ŏ��ۂ̎��Ƃ��s���c�́j�̃��f���Ƃ��č]�ː�捂��Ҏ��ƒc�������B�ȍ~�A�e��s������P�ʂƂ��Ēn�捂��Ҏ��ƒc�������ݗ����ꂽ�B70�N��㔼�ɂ́A�s�������ɂƂǂ܂炸�S���e�n�̓s�s�ɂ��n�捂��Ҏ��ƒc���ݗ������悤�ɂȂ�B����ɔ����A80�N�ɂ͘J���Ȃɂ���āu���N��ҘJ���\�͊��p���Ɓi�V���o�[�l�ރZ���^�[�j�v�Ƃ��ĕ⏕���x���n�݂��ꂽ�B���N�A�⏕���x�̗v���������߂ɁA�C�Ӓc�̂���Вc�@�l�ւƈڍs���Ă���B�����86�N�ɂ́A�u���N��ғ��̌ٗp�̈��蓙�Ɋւ���@���v�ɂ���ăV���o�[�l�ރZ���^�[���Ƃ͖@�������ꂽ�B�n�悲�Ƃ̃Z���^�[�i���n�捂��Ҏ��ƒc��������j�͂��̌���S���I�Ȋg��𑱂��A98�N�x���܂łɂ͑S���ɖ�800�̃Z���^�[���ݗ�����A�������47.6���l�ɏ���Ă���B
�A�@�V���o�[�l�ރZ���^�[���Ƃ̊T�v
�e�n��̃Z���^�[�ɂ́A���̒n��ɋ��Z���邨���ނ�60�Έȏ�̒j���̊�]�҂�����Ƃ��ĉ������Ă���B�e�Z���^�[�́A���̂قƂ�ǂ��A���ꂼ��̋�s���������L���Ă��錚���i���Ƃ��Ό����قȂǁj�̒��Ɏ����ǂ������Ă���A���������̓���Ɩ��͂����ōs���Ă���B�����ǂł́A�Вc�@�l�Ƃ��ẴV���o�[�l�ރZ���^�[�ɂ���Čق��Ă��鎖�����������Ă���A����̂��߂̎��������ɓ������Ă���B��̓I�ɂ́A�����ǂ̉^�c�A����ɑ���A�Ƌ@��̊m�ہA����̔\�͊J���̂��߂̌��C�Ȃǂ������ǂōs���Ă���B�������A�V���o�[�l�ރZ���^�[�̎��ƑS�̖̂ڕW��v��𗧂Ă���A�ۑ����̉����ɓ��������肷��̂̓Z���^�[�̉���ł���B�N�ɂQ��A����S�̂��Q�����鑍��J����A�����ŗ�����������I�o����A�^�c�̕��j�Ȃǂ����肳��Ă���B�����Ō��肳�ꂽ�^�c���j�́A������ɂ���Ď��s����闬��ƂȂ��Ă���B
�Q�@�V���o�[�l�ރZ���^�[��ʂ����A��
�{�̖͂`���ŁA�u�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ́A�ȒP�Ɍ�������Ҍ����̐E�ƏЉ�̂悤�Ȃ��̂ł���B�v�Ə��������A���m�ɂ̓Z���^�[�́u�E�ƏЉ�v�ł͂Ȃ��B�u�E�ƏЉ�v�Ƃ����̂́A������n���[���[�N�i�E�ƈ��菊�j�̂悤�Ȃ��̂ŁA���E�҂ɑ��ċ��l���Љ�邾���̋@�\���������Ȃ��B���E�҂͏Љ�ŏЉ�ꂽ�E��ɂ݂�����o�����Ă����āA�����ŋ��l������̗p�̔��f���Ȃ����B����ɑ��ăZ���^�[�ł́A�Z���^�[���̂���Ƃ�����c�́A��ʉƒ�Ȃǂ́u�����ҁv����d���̔������A���������ɒ��Ă���B��̓I�Ȏd�g�݂́A���̂悤�ɂȂ��Ă���B�@�܂������҂���Z���^�[�Ɏd���̔���������A���҂̊ԂŌ_���킳���B�A���ɔ������ꂽ�d�����A���炩���߃Z���^�[�ɓo�^���Ă�������ɃZ���^�[��������B�B��������ۂɏA�Ƃ���B�C�����҂���Z���^�[�Ɍ_������x������B�D���̌_�������萔���T�����������z�������A�Z���^�[�������Ɏx������B
���̃V�X�e���͈ꌩ����ƈ�ʂ́u�l�ޔh���v�̂悤�Ɍ����邪�A�Z���^�[�́u�l�ޔh���v�Ƃ�����Ă���B�l�ޔh����Ђ�ʂ��ē����A�Ǝ҂̏ꍇ�́A�h����̊�ƂƂ̊Ԃɂ͌ٗp�W�͂Ȃ����A�h����ЂƂ̊ԂɌٗp�W������B����ɑ��ăZ���^�[�̉���́A�����҂Ƃ̊Ԃɂ��Z���^�[�Ƃ̊Ԃɂ��ٗp�W���������Ă��Ȃ��B�d���̌_���킳��Ă���͔̂����҂ƃZ���^�[�̊Ԃ����Ȃ̂��B�_�ꂽ�d��������ɒ��邱�Ƃ́A�u�ĈϔC�v�܂��́u�Đ����v�ƌĂ�Ă���B�Z���^�[�́u�E�ƏЉ�v�ł��Ȃ���A�u�l�ޔh���v�ł��Ȃ��̂��B���̃Z���^�[�̉���̔����ȗ���ɁA�V���o�[�l�ރZ���^�[���Ӑ}���鍂��ҏA�ƃV�X�e���́u���z�v����߂��Ă���B�����������ɁA���̕��G�ȏA�ƃV�X�e���̂����ɂ́A����ҏA�Ƃ́u���ԁv���̂��̂��I�悵�Ă���̂��B
�R�@�V���o�[�l�ރZ���^�[�ݗ��̈Ӑ}�\�\�Ȃ��ٗp�W���Ȃ��̂��\�\
�V���o�[�l�ރZ���^�[���A����҂̂��߂́u�E�ƏЉ�v�ł��Ȃ��u�l�ޔh���v�ł��Ȃ��A�ٗp�W�𐬗������Ȃ��Ƃ������G�ȏA�ƃV�X�e�������g�D�Ƃ��Ēa�������̂͂Ȃ����B�����T�邽�߂ɁA����Ҏ��ƒc���������̉�ł���A����Ҏ��Ƃ̗��O�̒҂ł����͓���j�̕����ɒ��ڂ��Ă݂�B��͓��́A�V���o�[�l�ރZ���^�[�ł̏A�ƂɊւ��āA�����I�Ȍٗp�W��O��Ƃ��Ȃ��������Ƃ̗��R�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�i����҂̂��߂̏A�J�{�j����҂̒����I�Ȍp���ٗp��O��Ƃ�����̂ł�������A�i�����j�w�z�����x�ɂ���Ă̂ݍ���҂����̐������x���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ȃ�A����͂��̂�����ٗp�ۏ�̗v���ƌ��т����ƂɂȂ邾�낤���A�����Ȃ�A����͐��̘J�������@�A���Ƃ��ΘJ����@��J�Еی��@��J���g���@�̘g�̒��ł̒c�̍s���ƂȂ��Ă��܂��A����Ҏ��ƒc�̐��_�Ƃ͉����͂Ȃꂽ���̂ɂȂ��Ă��܂��B�v
�w�����s����Ҏ��ƐU�����c�̊�{�v��̂��߂̊o���x���
��͓��́A����҂̏A�Ƃ��ٗp�W��L���Ă��܂��ƁA���ǂ͘J�g�Ԃ̓����Ɋ������܂�邾���ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��뜜���Ă����悤���B���ɁA����҂��z�����ɂ���Đ��v�𗧂Ă�悤�ȏɂȂ��Ă��܂����̂ł́A�]������������ɔ�₷���Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B�����ƌ����A�u�ٗp�W�v�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A����҂̘J�����u�a�O���ꂽ�J���v�ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��������B����҂��u���ꂼ��̒n��ɂ����邳�܂��܂ȃj�[�Y�ɉ����āA����I�E�����I�Ɏd���������A���ꂼ��̔\�͂ɉ����ē����A���̂��Ƃ�ʂ��ĎЉ���ɎQ�����A�����ɐ����b������o���v[19]���߂ɂ́A����҂̏A�J�����Y��i�Ɛ��Y�ړI��D���Ă��܂����u�a�O���ꂽ�J���v�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B70�N��ɓ��������̍���҂Ƃ����̂́A�푈����̐����ی�̑ΏۂƂȂ炴��Ȃ���������҂Ƃ͈Ⴂ�A�N���⒙�~�ɂ���ď[���ɐ����ł���B������A�����ٗp�҂ƂȂ��Ē����̂��߂ɓ����K�v�͂Ȃ��B��͓��͂��̂悤�ɍl���āA�Љ�Q���̂ЂƂ̂�����Ƃ��āA�ٗp��O��Ƃ��Ȃ��A�Ƃ��Ă����̂ł���B�ނ����z�Ƃ�������ҏA�Ƃ̂�������A���̕��͂ɂ܂Ƃ߂��Ă���B
�u����Ҏ��ƂƌĂ����̂́A�J�g�Ԃ̌ٗp�W��O��Ƃ�����ł̍���ҏA�J�ł͂Ȃ��A�����܂Œn��̍���҂���������I�ɓ������Ƃ���Ƃ���̌ݏ��Ƌ����̂��߂̏A�J�����ł���A�ނ��남���悻�Z�\�Έȏ������҂������A�����̒����l���̒��Őg�ɂ����o���ƋZ�\�Ɛ����̒q�d�Ƃł������ׂ����̂�n��̂��߂ɒ��邱�ƂɁA�V��̐ϋɓI���������������o�����Ƃ���^���Ȃ̂ł���B�v�i�T���͕M�҂ɂ����́j
�w�����s����Ҏ��ƐU�����c�̊�{�v��̂��߂̊o���x���
��͓����J���o�ϊw�̐��Ƃł���A�������}���L�X�g�ł��邱�Ƃ��l����A�ނ̈Ӑ}���Ă������Ƃ͏[���ɗ����ł���B���O�I�ɂ́A����ҏA�Ƃ̂ЂƂ́u���z�v�ł���Ƃ킽�����l����B�����������ɂ́A��͓������Ď��������u�ٗp�W��O��Ƃ��Ȃ��J���v�́A�u����҂̌ٗp���Ȃ��v�Ƃ�������ҏA�Ƃ̎��ԂƂƂȂ肠�킹�������B
�S�@����ҏA�Ƃ̎���
�@�@�u�Վ��I���Z���I�v�ȍ���ҏA��
�܂��͂��߂ɁA�u�V���o�[�l�ރZ���^�[�v�Ƃ�������̒��ō���ҏA�Ƃ��ǂ̂悤�ɑ������Ă���̂���m�邽�߂ɁA�Z���^�[�̎��Ƃ�@�������Ă���u���N��ғ��̌ٗp�̈��蓙�Ɋւ���@���v�ɒ��ڂ��Ă݂�B��46���ŁA�V���o�[�l�ރZ���^�[�̋Ɩ����K�肳��Ă���B
��l�\�Z��
�u�s���{���m���́A��N�ސE�҂��̑��̍��N��ސE�҂̊�]�ɉ������Վ��I���Z���I�ȏA�Ƃ̋@����m�ۂ��A�y�т����̎҂ɑ��đg�D�I�ɒ��邱�Ƃɂ��A���̏A�Ƃ��������āA�����̎҂̔\�͂̐ϋɓI�Ȋ��p��}�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��A���č��N��҂̕����̑��i�Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����ݗ����ꂽ���@��O�\�l���̖@�l�i�����y�ё�l�\�����̓��ꍀ�ɂ����āu���N��ҏA�Ɖ����@�l�v�Ƃ����B�j�ł����āD�D�D�v
�܂�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ́A�u�Վ��I���Z���I�ȏA�Ɓv����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�������ł����āA����҂������I�ȐE��������Ƃ������Ƃ͑O��Ƃ���Ă��Ȃ��̂ł���B��͓��Ɍ��킹��A�u�Վ��I���Z���I�ȏA�Ɓv�������̗͓I�ɂ����l�����鍂��҂̃j�[�Y�ɂ����������ʁA�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B����������͗���Ԃ��A����҂́u�����I�Ȍٗp�v�̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�܂����̖@���ł́A��l���Łu60�Έȏ��N�̋`�����v�����A65�܂ł́u�p���ٗp���x�̓����v�����サ�Ă���B���̓_�����킹�čl����ƁA60�܂ł͊�ƂɌٗp���p�����邱�Ƃ��`�������A�����65�܂ł͂Ȃ�ׂ��p���ٗp���x��Čٗp���x�����邱�Ƃ����シ�邪�A����ȍ~�̍���҂ɑ��āu�����I�Ȍٗp�v�����K�v�͂Ȃ��A�u�Վ��I���Z���I�ȏA�Ɓv�ł悢�A�Ƃ������ƂɂȂ�B���ۂɁA���錧���ŃV���o�[�l�ރZ���^�[��S�����Ă���E���ɂ킽�����C���^�r���[�������Ƃ��A�ނ͎��̂悤�ɓ������B
�M�ҁu�ł́A65���߂����l�����ɑ��Ă͂����܂ł��Վ��I���Z���I�ȐE����邾���A�Ƃ������Ƃł����B�v
�E���u����Ⴀ�����ł���A������65�ɂȂ������N�������Ă��킯�ł�����B�v�i�T���M�ҁj
�u�N����������Ă���l�Ԃɑ��āA�s�����ŋ��������Ă܂ŁA�����I�Ȍٗp��O��Ƃ����E����邽�߂̎{����Ƃ�K�v�͂Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B�m���ɁA�u����ҁ��Љ�I��ҁ��Љ�̕��S�v�u���~�ώ��Ɓv�Ƃ����v�l�@�̂��Ƃł́A���ɘ_���I�Ȕ��z�ł���B
�A�@��������Ă��Ȃ��u�L���Ȍo���ƒm���v
���̕\�́A�ڍ���V���o�[�l�ރZ���^�[�̎�Ȏ��Ɠ��e�ł���B���������ƁA�Z���^�[�ɔ��������d���̂قƂ�ǂ��A�P����Ƃł��邱�Ƃ��킩��B
|
���� |
�������|�A�w�O���]�Ԑ����A�����{�݊Ǘ��A |
|
���� |
�}���V�����Ǘ��E���|�A�ѕM�E�M�k�A�����n��ƁA���ԏ�Ǘ��A���p�يĎ� |
|
�ƒ� |
�A�̙���A�ӂ��܂̂͂肩���A��H��ƁA�Ǝ������T�[�r�X�A |
|
�Ǝ����� |
�w�K�����A�Ƌ�̃��T�C�N���A�a�E�m���̃��t�H�[���A���������A���{�拳�� |
�V���o�[�l�ރZ���^�[���܂߂āA����ҏA�Ƃ̂��߂ɍ��ꂽ�p���t���b�g��`���V������ƁA�����u����҂̖L���Ȍo���ƒm�����������āv�Ƃ����t���[�Y��ڂɂ���B��ň��p������͓���j�̌��t�̒��ɂ��A�u�����l���̒��Őg�ɂ����o���ƋZ�\�Ɛ����̒q�d�Ƃł������ׂ����̂�n��̂��߂ɒ���v�Ƃ����t���[�Y���o�ꂷ��B�������d�����e�̂قƂ�ǂ���̕\�̂悤�ȒP����Ƃł́A����҂�����܂ł̐l���Ŕ|���Ă����u�L���Ȍo���ƒm���v����������Ă���Ƃ͓��ꌾ���Ȃ��B�܂��A�A�̙����ӂ��܂̂͂肩���ƌ������悤�ȁA�ꌩ����ƋZ�p����������Ă��邩�̂悤�Ɍ������Ƃ��A���͂����ł͂Ȃ��B�����Ɍg��鍂��҂̂قƂ�ǂ́A�V���o�[�l�ރZ���^�[�ɗ���܂łɐA�̙����ӂ��܂̂͂肩������������Ƃ͂Ȃ��B�Z���^�[�ɗ��Ă��猤�C���Ďd�������Ă���̂��B
�������ɁA�Z���^�[�̉���ɂ͌��T�����[�}���������l���吨����B����܂ł̓��{��Ƃ̘J�����e�����Z�p�E�m���̏K����O��Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ���A��N��̍���҂�����܂ł̎d���Ŕ|���Ă����o����m����n��Љ�̒��Ŋ������Ă������Ƃ͓���B���̌���������ҏA�Ɛ���Ƃ��ẴV���o�[�l�ރZ���^�[�ɂ���̂��A�͂��܂����{��Ƃɋ߂�T�����[�}���̘J�����e�ɂ���̂��B�����₤���Ƃ͖{�_���̒��ł͂��Ȃ��B������������ɂ��Ă��A��͓������z�Ƃ��Ă����悤�ȁu�L���Ȍo���ƒm���v����������鍂��ҏA�Ƃ́A�����ɂ͐������Ă��Ȃ��B
�B�@����́u�J���ҁv�Ȃ̂�
��͓���j���ٗp�W��O��Ƃ��Ȃ��J�����Ă����̂́A����ҏA�Ƃ��u�a�O���ꂽ�J���v�ɂ��Ȃ����߂ł������B�����������ɂ́A�ٗp�W���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����Ɍٗp�҂Ƃ��Ă̌������Ȃ��Ƃ������Ƃł��������B���Ƃ��A�Z���^�[�̉���ɂ͘J�Ђ��K�p����Ȃ��B�V���o�[�l�ރZ���^�[�ł́A�Ǝ��̃V���o�[�ی��Ƃ������̂�����ďA�J���̎��̂₯���ɑΉ����Ă���B����������́A�J�Ђقǂ̕⏞�ł͂Ȃ��B�����ɁA���̘J�ГK�����߂����čٔ��ɂȂ��Ă���P�[�X������B�����s�V���o�[�l�ރZ���^�[��ʂ��ē����Ă����������́A�H��łق��̐E���Ɠ����d�������Ă���Ƃ��ɁA���̂Ŏw�������Ă��܂����B�Ƃ��낪�ނɂ͘J�Ђ��K������Ȃ������B[20]�Z���^�[�̉�����A�E��ő��̐E���Ɠ����d�������Ă��Ă��A���̂̍ۂ̕⏞�͑��̐E���Ƃ͈Ⴄ�A�Ƃ�������������̂��B����ɁA��������z�����͌ٗp�W���������Ă��Ȃ��̂Łu�����v�ł͂Ȃ����A�u�G�����v�Ƃ������ڂŏ����ł̉ېőΏۂɂ͂Ȃ��Ă���B
�܂��A�Z���^�[�̉��������Ă���z�����́A�ʏ�̒����ɔ�ׂĒႢ�Ɛ����ł���B�����d�����e�ɑ���Z���^�[�̔z�����ƈ�ʂ̒������ׂ邱�Ƃ͎����I�ɂ͕s�\���B�����������ɁA�Z���^�[�Ɏd�������Ă����Ƃ�����c�̂́A���ł͂Ȃ��Z���^�[�Ɉ˗�����傫�ȗ��R�Ƃ��āA�u�Z���^�[�������v���Ƃ������Ă���B�Z���^�[�Ɍ��炸�A��ʂɍ���҂���ƂɌق����Ԃ̗��R�͒�����Ōق��邩��ł���B�킽�����C���^�r���[�����������s���̍���ҐE�Ƒ��k���̐E���́A����҂̎d���̂قƂ�ǂ��P���J���Œ�����ł���ƒf�����Ă����B����҂̒������Ⴂ��ԑ傫�ȗ��R�́A�ނ炪�N��������Đ������Ă��邱�Ƃɂ���B��ʂ̘J���҂ł���A����������Ő��v�𗧂ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����A�ق�������R����Ɍ��������������x����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ɑ��āA����҂͔N���Ő��v�𗧂ĂĂ��邽�߂ɁA�َ�͍���҂̘J���͍Đ��Y�ɂ������p�����ׂĎx�����K�v���Ȃ��̂��B����̓p�[�g�^�C���J���Ƃ悭���Ă���B��͓���j�́A����҂��N����������Đ������Ă��邩�炱�����グ���ɑ���K�v���Ȃ��̂��A�ƌ����Ă����B�����������ɂ́A�ނ炪�N�������҂ł���Ƃ������̎������A�ނ�̘J���������Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��Ă���̂ł���B��͓����ڎw�����u�a�O����Ȃ��J���v�́A���ʂƂ��Ắu������̒P���J���v�ł���A�����ł����œ�������҂����͌���u���v�����^���A���v���ꂽ���ӘJ���҂Ȃ̂ł���B
�T�@�u���������v��Ƃ��ẴV���o�[�l�ރZ���^�[
���ǂ̂Ƃ���A�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ͂����������̂��߂̑g�D�Ȃ̂��낤���B���̏͂̂͂��߂ɁA����Ҏ��ƒc�����̖ړI�́u�J���ƕ����̗��ʂ�����V�����A�ƃV�X�e���v���\�z���邽�߂������A�Ə������B����͓����s����Ҏ��ƐU�����c�̔N��ɋL����Ă���B�u�J����ʂ��Ēn��Љ�ɎQ������v�Ƃ����R���Z�v�g�́A�������ɘJ���ƕ����̗��̈�ɂ܂������Ă���B�Z���^�[�̋Ɛт����̖����x�𐳊m�ɔ��f���邱�Ƃ́A����킽���̎�ɗ]��B������������i�߂��ŁA�����ɃZ���^�[���F�Z���L���Ă���͕̂����̑��ʂȂ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����ۂ��������B�Z���^�[�̎d���̓��e�����̂�����Ă���@�I������l����A�V���o�[�l�ރZ���^�[���Ƃ��J������Ƃ��Đ������Ă���Ƃ͌����������B�ނ���Z���^�[�́A����ҏA�Ƒ�ł͂Ȃ�����҂̂��߂́u���������v��Ƃ��ċ@�\���Ă���B�V���o�[�l�ރZ���^�[���o���Ă��銧�s����e��̃p���t���b�g�����Ă���ƁA�u�������ƂŐ����������v�Ƃ������e�̃t���[�Y���������o�Ă��邱�ƂɋC�����B������Ă����L�̒��ɂ��A�V���o�[�l�ރZ���^�[�œ������Ƃ͎����ɂƂ��Ă̢������������A�Ƃ����ӌ����p�ɂɏo�Ă���B����ɁA�Z���^�[�̕����I���ʂɏd�����u����Ă��邱�Ƃ��������Ƃ��āA��������ł̃Z���^�[�̈�������������B�]�ː������̒��ŃV���o�[�l�ރZ���^�[��S�����Ă���̂́A������ۂ̢���������W�裂Ȃ̂ł���B�����̓_���l�����킹��ƁA�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ͢��N����}��������҂̘V��ɓ������Ƃ�ʂ��Ģ�����������^���镟������Ȃ̂ł���B�����Ă����ł��A�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ������z�̍���ɂ���̂́A�u�������Ƃ͐����邱�Ƃł���v�Ƃ�������܂����ɋߑ�I�ȉ��l�ςȂ̂��B�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ƃ�������̑O�ɗ����͂������Ă���̂́A����ҏA�J�����������Ȃ������ł���B
4�́@�u���������v�Ƃ������t
���̏͂ł́A����ҏA�Ƃ̒����̉ߒ��ŏo�Ă����u���������v�Ƃ������t�ɂ��āA�����ڂ������Ă݂邱�Ƃɂ���B�ʏ�u���������v�Ƃ������t�́A�u�����Ă��Ă悩�����v�Ƃ��������������Ă��鐸�_��ԁi�����������j��A���̂悤�Ȑ��_��Ԃ̌���ƂȂ��Ă���Ώۂ������B����ɍׂ������Ă����ƁA���������̑Ώۂ��ނɂ͂��܂��܂Ȓ�`���Ȃ���Ă���B�����������ł́A�u���������v�Ƃ������t�����������̂��A�Ƃ������t�̒�`���ڂ����ǂ����߂邱�Ƃ͂��Ȃ��B���t�̒�`�ł͂Ȃ��A�@�u���������v�Ƃ������t�����̓��{�Љ�̒��łǂ̂悤�Ɏg���Ă����̂��A�A�u���������v�Ƃ������t��ʂ��Đl�X�����߂Ă�����̂͂����������Ȃ̂��A��2�_�ɒ��ڂ���B
�ł́A���̓��{�Љ�̒��ŁA�u���������v�Ƃ������t�͂ǂ̂悤�Ɏg���Ă����̂��낤���B�����m�邽�߂ɁA1950�N����90�N�ɂ����Ă̒����V���̒��ŁA���o���Ɂu���������v���܂ދL���𐔂��Č����B�����J�͂��̌��ʂł���B�@�L�����́A����50�N�Ԃ�ʂ��đ������Ă����B�����Ă����炭���̑����X���́A�����{�̌o�ϔ��W�Ƒ傫���W���Ă����̂��낤�Ƃ������Ƃ������ł���B�푈���ォ��50�N��ɂ����ẮA�u���������v�Ƃ������t�����o���Ɋ܂܂��L���͂������P�������Ȃ������B�o�ϓI�����̒��ŁA�u���������v���l����]�T�ȂǂȂ������̂��낤�B60�N��㔼�ɂȂ��āA�悤�₭���N�����̋L�����f�ڂ���Ă���B�����Ă��̐�����������19���ɂ̂ڂ�̂�1970�N�A���傤�Ǒ��Ŗ������J���ꂽ�N�ł���B�Œ��L�^��L�����u�����Ȃ��i�C�v���I���N�A�O��s�s���ւ̓]���l�����������钼�O�̔N���A70�N�ł������B���x�������قڏI���ɋ߂Â��A�����̓��{�l���푈����ɖ��ɕ`�����u�L�����v���݂�����̎�ɂ������ł���B�����Ă��́u�L�����v����ɂ����Ď��������̕����������ɂ߂悤�Ƃ����Ƃ��A�����ɖ���n�߂��̂��u���������v�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�u�L�����v�ɂ��ċc�_�����Ƃ��A�u�킽�������͕����I�w�L�����x�͎�ɓ��ꂽ���A�w�{���̖L�����x�������Ă��܂����B�킽���������{���Ɏ�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́w����ꂽ�L�����x�̂ق��Ȃ̂ɁB�v�Ƃ����_�����悭���ɂ���B�u���������v�ɂ��Ę_������Ƃ����A�悭�����_��������B�u�킽���������{�l�͂���܂ŕK���ɓ������Ƃ��w���������x�Ƃ��Ă����B����ǁw�L�����x�������������A�����Ɓw�{���̐��������x�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƁB���������̃O���t�����Ă���ƁA�u�L�����v��u���������v�ɑ���₢���̂��A�u�L���v�ɂȂ�Ȃ���Ώo�Ă��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��悭�킩��B�u�L�����v��u���������v�Ƃ������z�́A�܂��Ɂu�L�����v�̎Y���Ȃ̂��B�����l����ƁA�L���ɂȂ�ȑO�͂킽���������L���Ă����Ƃ����u�{���̖L�����v��u�{���̐��������v�Ƃ����̂��A���́u�L�����v���������Ă͂��߂č��o�����T�O�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
���āA���ۂɂ����̋L���̌��o���ɖڂ�ʂ��Ă���ƁA����ɂ�����̎����ɋC�����B���o���̑����́A�w�����ɂƂ��Ă̐��������Ƃ́x�Ƃ����悤�Ȍ`���Ƃ��Ă���B�����āA���́����̕����ɓo�ꂷ��̂́A�������u�����v�Ɓu�V�l�v�Ɓu��Q�ҁv�Ȃ̂ł���B�Ȃ��ނ�́u���������v�͂���Ȃɂ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���B�ނ�́A���̐l�Ԃ����u���������v��K�v�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���B�����āA�ނ�́u���������v�Ƃ������t��ʂ��Ă��������������߂Ă���̂��낤���B
�T�́@�����V�l�̐�
�{�͂ł́A�V���o�[�l�ރZ���^�[�̉���ɑ��čs�����C���^�r���[�̌��ʂ̈ꕔ�ƁA����ɑ��镪�͂��s���B
�C���^�r���[�̑Ώێ҂́A��������ڍs������ɑ�����N��ł���A�n������㋞���ďA�E�A�������A��N���}���Ă���V���o�[�l�ރZ���^�[�ɉ���o�^���Ă���B�ނ�́A���̏A�ƍ\���̕ω��ƍ��x�����̌��ʂł����������������Ȃ��Ă悢�����������Ȃ��Ȃ遄�\���̒��ŁA���܂��Ɂu�V���v�ɒ��ʂ��Ă���l�����ł���B�ނ�́A�u�V���v�������Ɏ�e�����̂��B�u�����Ȃ��v�����āu�����Ȃ��Ă悢�v���ɂ����āA����ł��V���o�[�ɉ��������ړI�Ƃ͉����B�ނ�́A�u���������v�Ƃ������t��ʂ��Ĉ�̉������߂Ă���̂��낤���B
�P�@�C���^�r���[�̊T�v
����̃C���^�r���[�́A1999�N��11������12���ɂ����āA�R�l�̑Ώێ҂ɍs�����B���ꂼ��̃C���^�r���[�́A�Ώێ҂̐E��̈ꕔ��q���āA���ꂼ��1���Ԃ���2���Ԓ��x�̎��Ԃ������čs��ꂽ�B�{�_���ł̓C���^�r���[�̒����甲�������ꕔ���ڂ��A����ɑ��镪�͂����Ă����B�Ώێ҂̌��t�ɂ͈�̎�������Ă��Ȃ����A������r���̏ȗ��ȂǍŏ����̕ҏW�������s�����B���̌��ʔ����ȃj���A���X�̂��ꂪ�����Ă��܂���������Ȃ����A���̐ӔC�͂��ׂĒ����҂ɂ���B
�C���^�r���[�̖{�����ɏo�Ă���i�J�b�R�j���̌��t�́A�����̂��߂ɂ킽�����ォ����M�������̂ł���B�i�D�D�D�D�D�j�͒����ł���B�{�����̖T���́A���ׂĕM�҂ɂ����̂ł���B�܂��A�{�_���̓C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W��ɍڂ��邽�߁A�Ώێ҂̖��O�͂��ׂĉ����ɂ��Ă���B
�Q�@����F����@67�@���c�J�V���o�[�l�ރZ���^�[���
�@�@�͂��߂�
���삳��́A���a7�N���܂��67�A�É����̏o�g�ł���B���a25�N�ɑ�w�i�w�̂��ߏ㋞���A���ƌ�͖^�n����s�ɓ��Ђ����B����15�N��ɓ]�E���A2�Ԗڂ̉�Ђł̓V�J�S�A�j���[���[�N�A�n���u���N�A�����h���ƊC�O�]���J��Ԃ����B����ɂ��̉�Ђ�15�N�őސE���A52�̂Ƃ���3�Ԗڂ̉�ЂɈڂ����B3�Ԗڂ̉�Ђ�63�Œ�N�ސE�ɂȂ�A���̌�͎��ƕی����Ȃ���ٗp���i���ƒc�̐E�Ɗw�Z�ɒʂ������A�A�E�͂��Ȃ������B64�̎��ɂӂƂ������������ŃV���o�[�l�ރZ���^�[�̎d������`�����ƂɂȂ�A���݂܂ł��̎d���𑱂��Ă���B�Ƒ��͍ȂƓ�l�ŁA�q�ǂ��͂��Ȃ��B���݂͐��c�J��ɍݏZ�B�V���o�[�l�ރZ���^�[�ł̎d���́A�悩��ϑ����ꂽ�w�O���֏��̊Ǘ������Ă���B�d���͏T��4���قǁB���삳��́A�d�����͂��߂Ă����̍��ɒ��֏��ɓ������ꂽ�R���s���[�^�̈������}�X�^�[���A���ł͑��̒��֏��œ�������Ɏw�������闧��ł�����B
�A�@�V���o�[�l�ރZ���^�[�����̖ړI
�\�\�\���삳�V���o�[�Z���^�[�ɓ���ꂽ�ړI�͉��ł����B
����F���i���ƒc�i�E�Ɗw�Z�j�ɂ�������ɉċx�݂�����܂��ĂˁA���̂Ƃ��͖����}���قɒʂ����肵����ł����ǁA�ǂ����d�����Ȃ��Ɛ����̃��Y�������Ă��܂��āB���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ƃ��Ȃ����āA��肽�����Ƃ�������Ă���悤�ɂȂ�ƁA���߂ɂȂ��Ă��܂���ł���ˁB���̓��������d��������A�V�тɍs���ĂĂ������A�낤�Ƃ��I�d�����邤���ɂ��Ă������ƂɂȂ�܂����ǁA���̓����ɂ��Ȃ��ƂȂ�Ƃ��܂ŗV��łĂ���������Ȃ������Ă������ƂɂȂ��āA�A��Ȃ��Ȃ�����߂��̃z�e���ɔ��܂��������Ȃ������Ă������ɂȂ�������āB���ۂ����������Ƃ���������ł���B
�\�\�\��������ƁA���삳�����ړI���Ă����̂͂ǂ��������ƂɂȂ�܂����B
����F�����ł��ˁA�܂����N�B���ꂩ�畛�����B����͂��������ł��ˁB����ς莩�������R�ɂȂ邨����������Ă����̂͂���Ⴂ�܂�����B���ꂩ��A�l�Ƃ̂ӂꂠ���ł��ˁB
�\�\�\����͂����̒��֏��ɗ���l�ƁA���ꂩ�炢������ɓ����Ă���l�������Ă������Ƃł����B
����F�����̒��֏��ɗ���l�̂��Ƃł��B���͂����ɗ��Ă��炸���Ɨ�s���Ă��邱�Ƃ������ł����A�K�����֏��ɗ����l�Ɉ��A��������Ă������ƂȂ�ł��B
�\�\�\��������ɓ����Ă���l���m�͂ǂ��ł����B
����F���������܂���B�����A������Ă����̂��Z���^�[�̂ق��ł����ł��B�ł�����͂����{���Ɏ����I�Ȃ��Ƃ����ŁA�p�����I�������݂�ȂƂ��ƂƋA�����Ⴄ��ł��B���͂��������̂������ƌ𗬂�[�߂邽�߂ɂ��낢��Ȃ��Ƃ�������炢���Ǝv���Ă��ł���B
���삳��ɂƂ��ē����ړI�́A�@���N�A�A�������A�B�l�Ƃ̂ӂꂠ���̎O�ł���B
���N�Ɋւ��Đ��삳��́A�d���Ȃ��Ȃ��������Ɂu�����̃��Y�������āv���܂����A�Əq�ׂĂ����B����܂ł̒����l���̐����T�C�N�����A�u�d���v�𒆐S�ɂ��Đ��藧���Ă����̂�����A������O�Ƃ����Γ�����O�ł���B�Ђ�����u���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓv�����Ȃ������Ă����l�Ԃ��ˑR�u�������Ȃ��Ă����v��Ԃɒu����Ă��A�����ȒP�Ɂu����ׂ����Ɓv�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͂����炭�A��N�ސE��̍���҂����ʂ��Ē��ʂ��Ă�����ł��낤�B�ސE�ȑO����n��̎����ɐ[����������Ă����A�܂��͑��q�i���j�v�w�Ɠ������Ă��đ��̖ʓ|���݂Ă���A�Ȃǂ̏ɂȂ�����A�u���������炢���̂��v�͏d�v�Ȗ�肾�B
���삳��̓C���^�r���[�S�̂�ʂ��āA�Ƃɂ����u�l�Ƃ̂ӂꂠ���v��厖�ɂ��邱�Ƃ������ɂƂ��ĂƂĂ���Ȃ��ƂȂ̂��A�Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��������Ă����B���ɁA�d����ʂ��ĐG�ꍇ�����֏��̗��p�҂ւ̈��A���b���ƂĂ��厖�ɂ��Ă���B���ۂɂ킽�������֏��ŃC���^�r���[�����Ă���Ԃɂ��A�l�ߏ��̑O��ʂ闘�p�҂ɂ͕K���u���͂悤�������܂��v�Ɛ��������A�猩�m��̗��p�҂Ƃ͊ȒP�Ȑ��Ԙb�����Ă����B���֏��œ��������Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ɋւ��Ă��A�u�����ƌ𗬂�[�߂邽�߂ɂ��낢��Ȃ��Ƃ�������炢���v�ƁA�ϋɓI�Ȏp���������Ă���B
�B�@�]�ɂ̂�������
�\�\�\�d���ȊO�̎��Ԃ͂ǂ�Ȃ��Ƃ��Ȃ����Ă����ł����B
����F�d���ȊO�ł����B�����ł��ˁ\�A���̓}���V�����̗��������Ă����ŁA�������̂ق������\�Z������ł���ˁB���N�̂T���ɂ͉����H�����܂��ĂˁA�P���T�疜�����Ă������ł���B�[�l�R���I�肷�邱�Ƃ���͂��߂ĂˁA�v��ɂR�N���炢������܂�������B
�\�\�\���x�݂̓��Ƃ��͂ǂ�Ȃ��ƂȂ����Ă��ł����B
����F�����ł��ˁA�X�|�[�c�N���u�ɍs������A�S���t�ɍs������B�S���t���ǂ��s���܂���A���x���V���o�[�R���y���Č����̂������ł��B
�\�\�\���Ⴀ���̂��ܐ��삳���t����������Ă�F�l�̕����Ă����̂́A���\�V���o�[��ʂ��������吨�����������ł��ˁB
����F����܂��ˁB�킽���͂��́A�o����Ă����̂���ɑ�ɂ��Ă��ł���B�l�Ƃ̏o����B���̑O����X�T���Ō�������������ł����ǁA���̃X�s�[�`�ł��o����Ă������Ƃ��e�[�}�ɘb��������ł����ǂˁB
�d���ȊO�̎��ԂɊւ��Ă���т��Ă���̂́A�u�l�Ƃ̂ӂꂠ���v�ł���B��ȗ]�ɂ̉߂������́A�@�}���V�����̗����A�A�X�|�[�c�N���u�̂悤���B
���֏��̎d���͏T��4���B���̂ق��ɂ��Z���^�[�ł̘A�����������A���c�J��S�̂̒��֏��̊Ǘ��̎d���ɂ��g����Ă���̂ŁA�����ĉɂȂ킯�ł͂Ȃ��B����ɉ����āA�}���V�����̗����̎d���ɂ����Ȃ�M�S�Ȃ̂ł���B
����ɋ����[���̂́A���삳��̒ʂ��Ă���X�|�[�c�N���u�ł���B���삳��ɂ��ƁA���̖^�X�|�[�c�N���u�͍`����ɂ���A�|�\�l��X�|�[�c�I�����������炵���B�����100���~�A�N���18��5��~�A���ꗿ1000�~�A����ɐH��������2�`3000�~�B���̋��z�͎��ۂɃX�|�[�c�N���u�ɖ₢���킹�Ă��Ȃ��̂łǂ��܂Ő��m�Ȑ������͂킩��Ȃ��B���������Ȃ��Ƃ��A���܂�����X�|�[�c�N���u�̒��ł����Ȃ荂�z�ȕ��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����ĉ������A���삳�g���u���z�ȃX�|�[�c�N���u�ɒʂ��Ă���v���Ƃ���̐��_�I�Ȃ��ǂ���Ƃ��Ă���B���삳��̃}���V�����ɏZ��ł���m�l�݂͂�Ȑ��c�J����̃X�|�[�c�N���u�ɒʂ��Ă���A���삳��ɑ��āu����Ȃ����Ƃ����������Ȃ��v�ƌ����������B�������ނ́A�u�ł�����͂�͂�A�������������ӂ��Ɏd�����Ă邩��s�����ł���ˁv�ƁA�C���^�r���[�̒��Ō���Ă����B����ɁA���֏��̗��p�҂Ƃ̓����b�̒��ŁA���삳���̖^�X�|�[�c�N���u�ɒʂ��Ă��邱�Ƃ�b���ƁA�u���肪��F�ς��v�������B���삳��́A���֏��œ����Ă��鎩�����A���p�q����u��x���Ȑl�v�Ƃ��������N���Č����邱�Ƃ���������ƌ����B���̕Ό���Ŕj���邽�߂ɁA�X�|�[�c�N���u�̘b������̂��������B�܂萼�삳��ɂƂ��āA���z�Ȕ�p���ėL���ȃX�|�[�c�N���u�ɒʂ����Ƃ́A�u�L���ȘV��v�Ƃ����X�e�[�^�X�ł���Ɠ����ɁA���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̈���@�ł�����̂��B
�����āA���R���̃X�|�[�c�N���u�̂��߂̔�p�́A�Z���^�[�̎d���œ��������ɂ���Ęd���Ă���B���삳��́A�����ړI�̓�ԖڂɁu�������v�������Ă����B������͔N���ł܂��Ȃ��Ă���B�����炭�����̓��{�Љ�ŁA�N�������ł͕����ʂ�u�H�ׂĂ����Ȃ��v�A�Ƃ����l�Ԃ͔��ɏ��Ȃ����낤�B�ނ���A�Z��[�����I�����Ă��Ă���Ɏq�ǂ����Ɨ����Ă���A�N�������ł�������x�ȏ�̕�炵���ł���B����������ł��A�L��]��قǂ̎��Ԃ�����邽�߂ɂ́A�u����ȏ�̂����v���ǂ����Ă��K�v�ɂȂ��Ă���B���ɁA�s�s�ɏZ��ł�����W���[����۔�ɂ�������z�͌����ď��Ȃ��Ȃ��B�u�������v�́A�������ґ�ł͂Ȃ��̂��B���삳��́A���̂悤�ȁu�������v�����邱�Ƃ��A���ɏd�v�Ȃ̂��A�Ƙb���Ă����B���삳�炢�̔N��ɂȂ��āA�܂荂��҂ƌĂ��N��ɂȂ��āu�����̎��R�ɂȂ邨���v���Ȃ��Ƃ����̂́A�u�ƂĂ��S�߂Ȃ��Ɓv���������B����������Ƃ̎��������Ȃ���A��F�W���ێ����Ă������Ƃ�����B����ɐ��삳��ɂƂ��ẮA�u���z�ȃX�|�[�c�N���u�ɒʂ��v�Ƃ������Ƃ��A�P�ɉ^��������Ƃ������Ƃ��đ傫�ȈӖ��������Ă���̂��B���삳��ɂƂ��ē������Ƃ́A�����ĐH�ׂ邽�߂̂������҂����Ƃł͂Ȃ��B
�C�@�ȂƂ̊W
�\�\�\���l�͉������d���Ƃ��Ȃ����Ă��ł����B
����F����A�d����A���Ă��������������ƂȂ���ł��B�i�D�D�D�D�D�j���m�Î������肵�Ă��ł��B��������s���Ă邩��B�܂����j���͂ł��ˁA���n�����Ă܂��B���j���ɂł��ˁA���M�ɊG��`���āB�i�D�D�D�D�D�j���ꂩ����j���͂ł��ˁA�����h���ɂ���Ƃ��̎h�J����Ă܂��B�����h���ɂ���Ƃ��̂��F�B���݂�ȏW�܂��ĂˁA����Ă܂�����B��s�̎x�X������Ƃ��A���Ђ̏d���Ƃ��̉����������B
�\�\�\���Ⴀ�A���l�̂ق��͂������������W�܂肪���������ĖZ�����B�ŁA���삳���g�͂�����ɏo�����Ă炵�ĖZ�������Ă��������ł��ˁB
�\�\�\�Ȃ�قǁB�ł��y���Ƃ��͈ꏏ�ɏo������ꂽ�肷���ł����B
����F����S���B��͑S���Ⴄ����ł�����A�s���͂Ƃ��ɂ��邱�Ƃ͂���܂���B
����F�Ƃł��낢��s���Ȃ��Ƃ��́A�����Ȃ��Ⴂ���Ȃ��ł���B���n��s�����͐��n��`���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����B���M�s���Ƃ��͂��M�����ŊG��`���āB�i�D�D�D�D�D�j�ł����玄������ƁA�����Ȏ������Ȃ��Ⴂ���Ȃ���ł���B���Ȃ��ق����B����͂����ł���B������̂���́B�ƒ�~���̈�̂ˁB���͏o�Ă�̍D���ł�����B�Ƃɂ���̑匙���ł�����ˁB�ł�������R�Əo�ĕ�����킯�ł���B
�\�\�\�ꏏ�ɗ��s�s���ꂽ��Ƃ��͂Ȃ���ł����B
����F���s�B����A�Ɠ��͗��s�s���܂����ǂˁB���͎��̃O���[�v�ŗ��s�s���܂��B�v�w�ł��Ă����̂͂Ȃ��ł��ˁB�����Ɠ����ˁA���s���������Ă������Ƃł͂Ȃ��āA���F�B�Ƃ��t���������������Ă������Ƃŗ��s���Ă�݂����Ȃ�ł��ˁB�����ˁA���s���Ă����̂́A�s���ΕK���A���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł���B�A���Ă���̂�����Ȃ�ł���B�킴�킴�y���݂ɍs�����̂ɂ܂��ƂɋA���Ă���Ȃ�āB
��ʓI�ȁu��N��̕v�w�����v�̃C���[�W�Ƃ����ƁA�v�w������Ă̗��s������B��N���ԋ߂ɍT�����T�����[�}���̒��ɂ́A�u��N��͍ȂƂ�����藷�s�ł����悤�v�ƍl���Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B���������ۂɃC���^�r���[�����Ă݂�ƁA�Ώێ҂R�l�̒��ōȂƈꏏ�ɏo�������藷�s�ɍs�����肷��Ɠ������l�͈�l�����Ȃ������B���삳��̏ꍇ���A���s�ɂ͍s�����A���݂����ꂼ��̗F�l�ƈꏏ�ɍs���̂��B�Ȃ͍ȂŎ��ʂ��Ă̌�F�W���\�z����Ă���A�����Ɏ����̋��ꏊ������B���삳�g���V���o�[�l�ރZ���^�[�̎d���Ƃ��̒��ԓ��m�̒��ɋ��ꏊ������B���삳��́A�����������ĊO�ɏo�Ă��邱�Ƃ��u�v�w�~���́i�錍�́j�P�v�ł���Ƃ��������Ă���B�����[���̂́A��N��ɂȂ��Ă���͂�A�u�ȁv�́u��v�̐��E�A�u�v�v�́u�d���v�̐��E�A�Ƃ����敪�ł���B
�D�@�u�����v�Ƃ������Ƃɂ���
�\�\�\�����œ����Ă��Ĉ�Ԋy�������Ƃ��ĉ��ł���
����F���}�ł͂��邯��ǂ��A1��1�����߂����Ă�����邱�Ƃł��ˁB�����Ƃ����Ԃ�1���I������Ⴂ�܂���B���ꉽ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��l������ˁA���悭�悵����A�����Ȃ��ƂŁA
�\�\�\�����Ă��āA����͂炢���Ďv���悤�Ȃ��Ƃ͂���܂����B
����F�i���炭�l���āj�����ł��ˁA���̎d���ɓ����Ă���́A�炢�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB���������낤�����낤���Ă����A���̒��֏��ɂ��Ă̂ˁA���ƂŁA���������A�J�̋K��ł��ˁA�����ō���Ă݂悤���ƁB�������������́A130�l�̒��֏��̐l�����܂��܂Ƃ߂ĂˁA���[�Ȃ�Ƃ���̂ˁA����g�D����Ȃ��ł����ǁB�l�����킽�������ĂȂ��ł�����B���������������������̂���ꂽ��Ȃ��Ƃ����B
�i�D�D�D�D�D�j
�\�\�\�ȑO�߂Ă�����Ђł̎d���ƍ��̎d���Ƃ̈Ⴂ���ĂȂ�ł����B
����F���́\�A���܂ł̎d�����Ă����̂͑S���m���}������܂����B�m���}�������āA���X���i���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��ł���ˁB����ێ����Ⴞ�߂ł�����A��Ђ��Ă����̂́B���v��Nj����Ă��܂�����ˁB��ɂ��낢�뎩���ōl������������肵�Ȃ����Ⴂ���Ȃ��B�����͂����������Ƃ���܂������ˁB���܂�ϋɓI�Ȃ��Ƃ����A�ނ���ْ[������܂�����ˁB�ł����炻�������Ȃ��悤�ȃ��[�������Ȃ�������Ȃ��킯�ł���B���Ƃ����́A���̒n��i���삳�S�����Ă��钓�֏��j�ł���Ă���d�����Ă����̂́A���Ƃ��Ă̓p�[�t�F�N�g���Ǝv����ł���A���֏��̊Ǘ��Ƃ��ẮB�����炱����ł��ˁA���̒��֏��ɑS�����肢������Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv����ł���ˁB�ł��Ȃ�����A�K�������āA����ɏ����ĊF����Ȃт��Ă��炦��A���Ȃ��Ƃ��R�`4�N�̊Ԃɂ͂��̒n��̌`���ɂȂ�̂ł͂Ƃ����ӂ��ɁB�i�D�D�D�D�D�j
�\�\�\���Ⴀ�A���܂͂��������m���}�ł͂Ȃ��A���ł��傤�A�������������������Ďv���悤�Ȏd���������őn���Ă�������Ă����Ƃ��낪�B
����F�����ł��ˁI�@�����B���́A���߂���Ă���Ȃ��ĂˁB����Ƃ��́A���Q�W���Ȃ����炢���ł���A�S���B���������Ă�悤�Ȃ���ł�����B���Ƃ������̒��ɂ���P�V�A�W�l�̕��Ƃ͂��t���������Ă܂����ǂˁA�S���t�ɍs������A���݂ɍs������A�f��ӏ܉�ɍs������B���낢�낵�Ă܂����ǂˁB�i�D�D�D�D�D�j����ƂˁA��b�������Ȃ�܂��ˁB����ׂ邱�Ƃ������Ȃ�܂���B
���֏��̎d���́A���삳��ɂƂ��Ă܂��Ɂu�a�O����Ȃ��J���v�ł���B���삳��́A�R���s���[�^�̎g�����̃}�j���A�������ݐ��쒆�ŁA�킽���ɂ������Ă��ꂽ�B����ɔނ̖ډ��̖ڕW�́A���c�J����ɂ��钓�֏����܂Ƃ߂āA��̊ɂ₩�ȑg�D�̂悤�Ȃ��̂���邱�Ƃ��B�����̎d���́A�����Đ��c�J���V���o�[�l�ރZ���^�[����v�����ꂽ���Ƃł͂Ȃ��A���삳����I�ɍs���Ă��邱�Ƃł���B��Ƃɋ߂Ă������̂悤�ȁu�m���}�v���Ȃ����ƁA���֏��������̎v���悤�Ɏd�邱�Ƃ��ł��邱�ƁA�R���s���[�^�̓����ɂ���āu���Ȃ��Ă͍���l�v�ɂȂ������ƂȂǂ��A�i�C���^�r���[�̍Ō�ɘb���Ă��ꂽ�悤�Ɂj���֏��ł̎d����ނɂƂ��Ắu���������v�ɂ��Ă���̂��B
�\�\�\���삳��ɂƂ��āA�������Ƃ��Ă����̂͐��������ł����B
����F�����������Č����ƁA������Ƃ���ł��ˁA�������ǂ����܂��ˁB���t�ɕ\���ƂˁA���������Ƃ����낢�댾���܂����ǁA���ۂɂ͂�������Ȃ��Ǝv���܂���A�킽���́B�\���ł��Ȃ����炻�������Ă邾���ł����āA���̌��t����Ԑg�߂Ȍ��t�����炻�������Ă邯��ǂ��B����ς�ˁA
�\�\�\�����Č��t�ɂ��悤�Ƃ���Ɖ��ł����B
����F�i���فj�@���[��A�d�������Ă邱�Ƃ���͂�l���̈�x���ɂȂ��Ȃ��ł����B���ꂾ�Ǝv���܂���B���ꂪ�ł��ˁA�}�t�ɕ�����ĂˁA���N�ł���A�������ł���A���ꂩ��l�Ƃ̑Θb�Ƃ��A�����������̂��o�Ă��܂�����ˁB
�i�D�D�D�D�D�j
�ł����炻�������Ƃ���𑍍����Ă����ƂˁA���̎d�������������ɂȂ��Ă��ł��ˁB�������̎��_�ł́A�����ł��A���N�ł��A�]�ɂ̉߂������ł��Ȃ�ł��Ȃ���ł���B���֏���Ă��Ǝ��̂��A���͔��ɑ�D���Ȏd���ɂȂ����������ł���B�͂��߂ĂˁA���̍ɂ��ĂˁA�����ɂ���Ă݂����d�����Ԃ����Ă�����ł���B
���삳��ɂƂ��āu���������v�Ƃ́A���t�̕\�ʂɂ܂Ƃ����Ă���u�������ǂ��v�ł͂Ȃ��B�ނɂƂ��āu���������v�́A�d���������Ƃł���A���̎d���ɂ���ē����錒�N�A�������A�l�Ƃ̂ӂꂠ���ł���A����ɂ���炪�����炷���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ȃ̂ł���B
�R�@�ێR���v����@64�@�]�ː��V���o�[�l�ރZ���^�[
�@�@�͂��߂�
�ێR����́A���a10�N���܂�A64�̒j���B�o�g�́A�������������哇�̊�E���B��E���́A���̎��͂�48�L���Ƃ������ɏ����ȓ��ł���B�o��l�ƒ��l�̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���w�Z5�N���̂Ƃ��ɂ��������S���������Ƃ������āA19�̂Ƃ��ɐE�����߂ď㋞�����B��������������ЂŐE�l�Ƃ���15�N�قǓ�������A�Ɨ����Ď����̉�Ђ�ݗ������B�Ƃ��낪�����ɂȂ��Ă���̕s���̂�������A30�N�قǑ�������Ђ�97�N�ɓ|�Y���Ă��܂����B���̐��Z���ς܂��A99�N��4������V���o�[�l�ރZ���^�[�Ńh���C�o�[�Ƃ��ē����Ă���B���݂͍ȂƓ�l��炵�ŁA���j�ƒ����͂��łɓƗ����Ă���B
�A�@�����ړI�A��������
�\�\�\�V���o�[�Z���^�[�œ����Ă���ړI�͉��ł����B
�ێR�F�E�E�E�������R���B��������̂��߂�����܂���ˁB�����ǎ������ꐶ�����Ă���������Ƃ�����Ă����Ƃ���ς�V���o�[�l�ރZ���^�[��������܂���ˁB
�\�\�\�������Ȃ����Ă�̂́A������̎����Ő����Ȃ����Ă��ł����B
�ێR�F�Ƃ��ƔN���ł��B
�\�\�\�N�������ł������ł��邯��ǂ��A����Ƀv���X���邽�߂ɂ�����œ����Ă���Ƃ������Ƃł����B
�ێR�F�����ˁA�������69�őސE�ł�����A������N�������̐����ɂȂ�܂�����ǂ��B[22]
�\�\�\�����œ����̂́A�����̂��߂Ƃ����킯�ł͂Ȃ���ł����B
�ێR�F�S�������ꂶ��Ȃ����Ă������Ƃł��ˁB�i�D�D�D�D�D�j�܂����Ƃ́c�܂������������Č����Ƒ傰���ɂȂ�܂�����ˁB�i�D�D�D�D�D�j�@���N���āA����Ȃ����ԂɋN���āA����Ȃ����Ԃɍs���Ƃ��낪������Ă������Ƃł���ˁB�������B�܂����ꂪ�Ȃ��ƁA�ƂłˁA�ڂ��Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ����B���_�I�ɂ��A���̓I�ɂ����߂ɂȂ��Ă�����Ȃ��ł����ˁB
�i�D�D�D�D�D�j
�\�\�\��������Ɠ������Ƃ��Ă����̂́A�u���������v�ł����B
�ێR�F�����������Ă����̂͂ˁA�傫�����āA�������������ł����B�l���̖ړI�Ƃ��A���ł����A�����������āB�i�D�D�D�D�D�j����́A���邱�Ƃɖv�����邱�Ƃ���Ȃ��ł��傤���B�ł������������Ă����͓̂��X���y���������邱�Ƃ���Ȃ��ł��傤���ˁB�������������߂Ă��Č����Ă��A��̓I�ɉ����������������Č����Ă��A
�\�\�\����Ƃ͌����Ȃ��A
�ێR�F�Ǝv���܂��B
�\�\�\�ł�����ς�d���𑱂��Ă������Ƃ͑�A
�ێR�F�����ł��B
�ێR����̏ꍇ���A�����̂��߂ɓ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�C���^�r���[������3�l�̑ΏێґS�����A�N���Ő��������Ă������Ƃ͂ł��邪�A����ȊO�̎����邽�߂ɓ����Ă���A�Ƃ������Ă����B����҂̏A�Ɨ��R�ɂ��Ă̈ӎ������̌��ʂ�����ƁA�u�o�ϓI�ȗ��R�v�Ƃ����I������I��ł���l�͏��Ȃ��Ȃ��B�����������炭�A���̒��̑����̐l�ɂƂ��āu�o�ϓI�ȁv�Ƃ����̂́A��������҂��Ƃ������͂ނ�������ہA�����̒��ł̂�����Ƃ����ґ�̂��߂Ɂu�o�ϓI�ȗ��R�v�œ����Ă��邱�Ƃ������ł���B
����ɐ��삳��Ɠ��l�A�ێR������������Ƃɂ���Đ����̃��Y�����ۂ���Ă���B���N���āu�s���Ƃ��낪����v���Ƃ��A���_�I�ɂ����̓I�ɂ��x���ɂȂ��Ă���̂��B�u����ׂ����Ƃ�����v�u�N���ɕK�v�Ƃ���Ă���v�Ƃ����������Ȃ��A�������ĂȂ������Ă������Ƃ͓���B
���삳��̏ꍇ���������������A�ێR������u�������Ƃ͐��������ł����v�ƕ������ƁA�����ɂ͂���ɉ��Ȃ������B�ނ�ɂƂ��āu���������v�Ƃ����̂́A�u����v��u����v�Ǝw����悤�ȋ�̓I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��悤���B�ނ���u���t�ɂ͂��Â炢�v���̂Ȃ̂ł���B�܂��A�C���^�r���[�̒��Łu���������͉��ł����v�u�������Ƃ͐��������ł����v�Ƃ�����������邱�Ƃ́A�����҂̂킽���������S�O�����B�����˂ꂽ�ق����A�ŏ��͌˘f���Ȃ���A�����������́u���������v�ɂ��Č���Ă��ꂽ�B�ނ�ɂƂ��āu���������v�Ƃ������Ƃ́A���R�Ƃ������̂ł���Ɠ����ɁA����ȂɊȒP�ɑ��l�ɘb����悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�B�@�ȂƂ̊W
�ێR�F�i�D�D�D�D�D�j���Ƃ��Ζ����������ԂɋA���Ă��āA�u�������܁v���ċA���̂ƂˁB�u�����Ă��܂��v���ďo�Ă��āu�������܁v���ċA���Ă���Ɓu�͂�����J�l�A���������ł��傤�v���Č����Ă���邶��Ȃ��ł����B���ꂪ�s���ꏊ���Ȃ��ĂˁA�Ƃł��낲�낵�ĎU���������ċA���Ă��邩�B
�\�\�\������͂����ƉƂɂ����ł����B
�ێR�F��Ǝ�w�ł��B
�\�\�\������������ł����B
�ێR�F��������Ă��Ȃ��ł����B
�\�\�\�����W�܂�݂����Ȃ̂͂����ł����B
�ێR�F����݂����ł���B
�\�\�\�����ł����B���Ⴀ������͂�����Ŋy����1�����߂����āA�ێR����͂��d�����Ȃ����āB
�ێR�F�����ł��ˁA����łȂ��ƁA����ς�A�N����l�ł����ɂ�����A�ƒ됶�����ˁA�ق�ƂɁA�M�N�V���N���Ă�����̂�����Ǝv���܂���B
�\�\�\�Ȃ�قǁB����͂��Ƃ��A�O�̉�Ђ��Ȃ��Ȃ��āA�V���o�[�ɗ���܂ł̊ԂɁA�����������Ƃ��Ă����̂͂���܂����H
�ێR�F����܂��B���ɂ͏o���Ȃ����ǁA���Ƃ��Γ~�߂����܂�������ǂ��A�u�ǂ����U���ł����Ă���v���Č������ł�����ǂ��u���̂��������������Ȃ�����s����v���Č����Ă��邤���ɁB���̓I�ɂ����_�I�ɂ��ˁA���߂ɂȂ��Ă����܂��ˁB
���삳��Ɠ��l�A�ێR����ɂƂ��Ă��ƒ�́u1����������ꏊ�v�ł͂Ȃ��B���Ԃł͂����A�u�ƒ�v�Ƃ́u���炬�̏�v�ł���u�Ō�̂��ǂ���v�ł���A�Ƃ����F�����Ȃ���Ă���B�������ɋߑ�Ƒ��́A���_�I�Ȍ��т�����̓����Ƃ��Ă���B��������͂�A�����́u�A���Ă���ꏊ�v�ł����āA�i���ɒj���ɂƂ��Ắj�u�����Ƃ�����ꏊ�v�ł͂Ȃ��̂��B�u��N�v���}���āA�u�ƒ�v�ɉi�v�A��������Ƃ��A�����ɂ́u�v�v�̋��ꏊ�͂Ȃ��B�ێR����̌��t�̒�����A�d�������Ă��Ȃ����������̉ƒ�̋C�l�܂肪�悭�`����Ă����B
�S�@�R�{��������@72�@�]�ː��V���o�[�l�ރZ���^�[
�@�@�͂��߂�
�R�{����́A���a2�N���܂�A72�̒j���ł���B�o�g�͐V�����슗���B8�l�Z��̏ォ��4�Ԗڂɐ��܂ꂽ�B15�̂Ƃ��ɁA���B�J��`�E�R�Ƃ��Ė��B�ւ킽��A�����ŏI����}���ăV�x���A�֑����A3�N��ɓ��{�ɋA���Ă����B���̌�t�������킸�炢�A��p���A�×{���Ȃ���V���̉��قɋ߂Ă������A1961�N�A��ɏ㋞���Ă����e�ʂ𗊂�ɍ]�ː��Ɉڂ�Z�B�]�ː������̓y�؉ۂɋ߁A�͐�̔r���Ȃǂ̎d�������Ă����B60�Œ�N���}�������A�Čٗp���x�ő����̕����W�ɂ���6�N�قNjΖ����A���̌�ސE�����B�ސE���1�N�قlj������Ă��Ȃ��������A94�N�ɃV���o�[�l�ރZ���^�[�ɉ������A���݂܂Ŏ��]�Ԃ̃��T�C�N���̎d�������Ă�B���݂͍ȂƓ�l�邵�ŁA�C���^�r���[�̂��傤��1�T�ԑO�ɁA���łɓƗ����Ă��钷�j�̑������܂ꂽ�B
�A�@�R�{����̎
�\�\�\�R�{����̎�͉��ł����B
�R�{�F���͂ˁA���n�������Ă��ł���B
�\�\�\������n�߂�ꂽ��ł����B
�R�{�F6�N���炢�O���ȁB
�\�\�\�ǂ������Ƃ���ł���Ă��ł����B
�R�{�F�T�[�N�����Ă������A���������̂������āB�����Ȃ����������Ƃ�������Ă������A���������̂�����܂���ˁB���������Ƃ������āA�K���Ă�킯�B
�\�\�\�T�ɉ���ł����B
�R�{�F����́A����2��ł���B
�\�\�\����͍]�ː����ł���Ă��ł����B
�R�{�F�����A�]�ː����ŁA�e�n����Ă����̂������ĂˁA���͏���L�O�ق��Ă����Ƃ��s���Ă��ł��B
�\�\�\�����̂��F�B�Ƃ͒���������ł����B
�R�{�F�����A���ǂˁA���̐l�����ł���B�����ʼn�����������Ă�̂͂ˁA�����Ă��ł���B������d���I����Ă���s���킯�B�Ȃ��Ȃ��Z������ł���B
�\�\�\�Ƃł��`�����肷���ł����B
�R�{�F�����B�`���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����ǁA���݂���܂莞�Ԃ��Ȃ��ĂˁA���X�͕`����ł����ǂˁB
�\�\�\�R�{����̎���Ă����Ɛ��n��Ȃ�ł��ˁB
�R�{�F����A��Ԋy���݂͐��n��ł���ˁB���̑��ɂˁA�j�����̗����������Ă����̂������ł��B�����ւˁA��1��s����ł���B
�\�\�\�ǂ�Ȃ���������ł����B
�R�{�F����܂��A���̎��ł��낢��ˁA������l�����̓��A�u�����͂����������j���[�v���Ă������ƂŁB
�\�\�\����͂ǂ����������Ȃ�ł����B
�R�{�F���₱��͂ˁA�]�ː��łˁA�ی����W�ł��n�߂���ł���ˁB����͂����A5�N���炢����ł��B����ɍs���ƂˁA�ޗ��̎d���ꂩ��n�܂�킯�ł��B�ǂ�����Ďd���ꂽ�炢�������Ă������ƂłˁB���ꂩ�獡�x�͑卪�̐���Ƃ��ˁB�������������ŁA�ŏ����狳���Ă�����ł���ˁB
�\�\�\����͒j��������Ώۂɂ��Ă����ł����B
�R�{�F����͂ˁA65�Έȏ�̒j���������Ă������ƂɂȂ��Ă��ł��B������ق��͏��̐l�ł����ǂˁB
�\�\�\���Ⴀ�����ŏK�����̂��A���ƂɋA���Ă��Ď��̓�����Ă݂���Ƃ��B
�R�{�F�܂������������Ƃ����܂����ǂˁB�܂������Ԃ߂ɂȂ�܂���ˁB��̐���Ƃ���̂ނ����Ƃ��B
�\�\�\�����ł���ˁA����܂ł͑S�R����Ȃ������ł���ˁB
�R�{�F����A���X�͂���Ă���ł����ǂˁA����ł��ˁA�Ɠ����ق�|�ꂽ��Ȃ����Ƃ��A�������ł��Ȃ������獢��Ȃ��Ă������ƂŁA�܂��������킯�Ȃ�ł����ǂˁB
�\�\�\���Ⴀ��������������y���݂ł����B
�R�{�F�����A������y���݂̂ЂƂłˁB
�\�\�\�ق��ɉ����X�|�[�c�݂����Ȃ��Ƃ́A
�R�{�F�����������Ƃ͂���ĂȂ��ł��ˁB
�R�{����́A�Ώێ�3�l�̒��ł���ƌĂׂ���̂�����������A���ۊW�����l���B���n��̃T�[�N���◿�������ɐϋɓI�ɒʂ��A��F�W���A�Z���^�[�̐E��ł̓����A������̑ސE�҂̉�A���B����̗F�l�Ȃǂ��������A���̌��۔�ɃZ���^�[�ł̎��������Ă��Ă���B
�����[���̂́A�R�{����̒ʂ��Ă��闿�������ł���B�j�������̗����������ł��Ă����Ƃ����b�͍����悭���ɂ��邪�A�u65�Έȏ�j������v�̗��������Ƃ����̂͒������B���������������́A�R�{����ɂ��A�]�ː��ɂ���Ē���Ă���炵���B���R�����ɂ́A�Z���̊ԂɃj�[�Y������̂��B
�B�@�����ړI
�\�\�\�R�{���V���o�[�ɓ������ړI�͉��ł����B
�R�{�F�������R�A���ǂˁA�l�Ԃ͂��A�������Ȃ��ł��A�Ƃ���ƂˁA�ǂ��������đ̂��Ȃ܂ɂȂ���Č������ˁA�������C���N���Ȃ��Ȃ����Ⴄ�ˁA����܂�Ԃ�Ԃ炵�Ă�ƂˁB�����炻����A������܂������߂ɂ͂�͂�ˁA�����قꎩ���̍D���Ȏd��������Ă���ˁA���������ɂȂ��Ȃ������Ă������ƂłˁB�i�D�D�D�D�D�j��͂�A���������邱�ƂƁA��͂蓭���Ă��钇�ԂˁA���ԂƂ̃R�~���j�P�[�V�����A���������̂��A��͂�ˁA���������̂���ɂȂ��Ȃ��ł����B���ĉ��������Ęb�����邾���ł��ˁA�����Ԃ�Ⴂ�܂���B
�\�\�\�����̎d�����ԂƂ́A�d����ȊO�ł��H���ɍs�����肵�܂����B
�R�{�F�����������Ƃ͂���܂�Ȃ��ł����ǂ��A����ł��ˁA���ƒc�ł͂ˁA�N�Ԃ������P����ǂ��ˁA���s�������ł���B����ɍs�����肷��ł���B
�\�\�\������́A�N���Řd���Ă����ł����B
�R�{�F���������ł���B
�\�\�\���Ⴀ�A�����ł̎������Ă����̂́A�ǂ�Ȃ��ƂɎg���Ă��ł����B
�R�{�F��̂͂�����A���n�����Ă�ł���A���������Ƃ��֑����̋��͂�����܂���ˁB����Ƃ܂��A�l�Ƃ̕t���������ˁB����ƂˁA��͂������߂Ă���ސE�҂̉���Ă����̂������ł���B�����ł����\�A�V�N��Ƃ���������������āA���������Ƃ��֎g����ł���B
�\�\�\�l�Ƃ̕t�������ɂ������������ł��ˁB
�R�{�F���������B�t�������ɋ���������B
�\�\�\���������̂͂���ς�N���������Ɩ����ł����B
�R�{�F�����A�����ɂȂ邱�ƂɂȂ�܂��ˁB�����炱���œ����Ă镪�́A������֎g�����Ă������ƂɂˁB
�\�\�\���Ⴀ�A�v���X�A���t�@�̎������Ă������Ƃł����B
�R�{�F���������A���������i�D�Ŏg���Ă܂��B
�R�{������A�����ړI�͑��̓�l�̑Ώێ҂Ǝ��Ă���B�܂����ɐ����̃T�C�N���𐮂��邱�Ƃł���A���ɐE��œ����鑼�҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����A�����đ�O�ɕ������ł���B���̕������́A�R�{����̏ꍇ���A��̃T�[�N������۔�ɓ��Ă���ȂǁA�X�Ȃ�R�~���j�P�[�V�����̂��߂ɔ�₳��Ă���B
�C�@��������
�\�\�\�������Ƃ́A���������ł����B
�R�{�F������������ˁA��͂蓭�����Ƃ��Ă����̂͂ˁB�����Ă���Ƃ�͂肳�A��������������A���N��Ԃ���낵�����Ă������ƂłˁB
�\�\�\������ɋ߂Ă����Ƃ��A30��40��̍����A���̂悤�ɍl���Ă܂������B
�R�{�F���̍��͂���Ȃɍl���ĂȂ������ł���B�����������Ƃ��l����悤�ɂȂ����̂͒�N��ł���ˁB��N��A���ǂˁA�����͏��Ȃ��Ȃ邵�A�u���ꂱ��ǂ����Đ������炢�����v���Ă������ƂŁB��������ƂˁA��͂茒�N�����Ԃ��Ȃ��Ƃ������Ɏ��͎v����ł���ˁB
�\�\�\�Čٗp����āA66�ŋ���������߂����͂ǂ�Ȋ����ł������B
�R�{�F����ł�����ˁA�l���͏I���ɂȂ�̂��ȂƎv��������ǁA����ł��ˁA���ꂩ��܂���邱�Ƃ͂���낤�Ƃ������ƂłˁA�C�����߂��Ă��B���������炱�̎��ƒc���Ă����̂����邩��A���Ⴀ�����œ���������Ȃ����Ȃ��Ă������ƂŁB
�\�\�\��N�ɂȂ�O�A������ɋ߂Ă������́A��N��͂���Ȃ��Ƃ����悤�Ƃ�����]�͂���܂������B
�R�{�F���₢�₻��Ȃ��Ƃ͑S�R�l���ĂȂ������B�܂��Čٗp���āA�Čٗp�������I��肾���������Ă������ƂɂȂ�����A�u���ꂩ�牽��������炢���̂��v���Ă������Ƃ͍l���o���܂������ǂˁB
�\�\�\���Ⴀ���̍Čٗp���I����Ă���Z���^�[�ɗ���܂ł́A�����Ƃɂ�����ł����B
�R�{�F�����B
�\�\�\���n����n�߂��̂��A���傤�ǂ��̍��ł����B
�R�{�F����A���̑O���������ȁA���n���������̂́B��������Čٗp�I��鍠���ˁB�������������A�u���n�������Ă�A���ꐶ�������̂���ɂȂ��Ȃ����v���Ă������ƂłˁB���ꂩ��n�߂��킯�Ȃ�ł���B
�R�{����́u�������Ƃ͐����������v�Ƃ����Ă��邪�A�����l����悤�ɂȂ����̂͒�N��ɂȂ��Ă���ł���B30��40��̍��A�܂茻���œ����Ă����Ƃ��ɂ́A�������Ƃ����炽�߂āu���������v���Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B�����~�܂邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ŗ���Ă������X�̒��ŁA�u���������v�ȂǂƂ͌����Ă����Ȃ��B�l����K�v���Ȃ��B�Ƃ��낪�u��N�v���}���āA�R�{����́u�l���͏I���ɂȂ�̂��ȂƎv�����v�B���������ɒu����Ă͂��߂āA�u�ǂ������炢�����낤���v�ƍl����悤�ɂȂ����B�����ăV���o�[�l�ރZ���^�[�̖�����������̂��B��̐��n����͂��߂��̂��A�Čٗp�̊��Ԃ��I��鍠�ɂȂ��Ă��炾�B
�S�@�C���^�r���[���I����
�@�@�@
�͂����O�ɁA3�l�̃C���^�r���[���狤�ʂ��ē���ꂽ���ʂɂ��āA�����ŏ����������Ă����B
�܂����ɁA�ނ炪��N����������Ƃ���ړI�́A�����̂��߂ł͂Ȃ��B�O�q�̂悤�ɁA3�l�Ƃ���b�I�Ȑ�����͂��ׂĔN���Řd���Ă���B�ނ�̖ړI�͑傫�������āA�@���N�ێ��i�����̃��Y����ۂ��Ɓj�A�A���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����A�B������ȊO�̃v���X�A���t�@�Ƃ��Ă̕������A�̎O�ł���B
�u���N�ێ��v�Ɋւ��āA���������Ɍ��N���ێ����邱�Ƃ��ړI�ł���̂Ȃ�A�����ȊO�ɂ����ɕ��@��������ł�����͂����B�Ƃ��낪�C���^�r���[�̑Ώێ�3�l�����ʂ��ĉ��Ă������Ƃ́A�u�d�����Ȃ��Ɛ����̃��Y��������Ă��܂��v�Ƃ������Ƃ������B���N�ٗp�҂Ƃ��ē����Ă����l�Ԃ̐����T�C�N���́A�u�����������ԂɋN���ďo���A���������������ԂɋA��B���ꂪ���j��������j�Ȃ����͓y�j���܂ő����v�Ƃ������Y���ɌŒ肳��Ă���B�܂�A�����T�C�N���́u�J���v�𒆐S�ɂ��ĉ�]���Ă���A���̏�Ԃ����\�N�ɂ킽���Ĉێ�����Ă����B���̌��ʁA�ނ�́u�����Ă��Ȃ��Ɓv���͂⌒�N�ł��邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����B����������ŁA�d�����Ȃ��ƌ��N���ێ��ł��Ȃ��Ƃ������́A�ނ炪�ٗp�҂Ƃ��Ă̐l�������ł����A�Ƃ����_�ɂ�������������̂ł͂Ȃ��B�u��N�v�ɂ���ĉ�Аl�Ԃ����ނ����Ƃ��A�����ނ�ɂƂ��Đ^�Ɂu�A��ꏊ�v������A�܂������Ŏ��Ɂu����ׂ����Ɓv������̂Ȃ�A���͐����Ă��Ȃ��͂��ł���B���̂��Ƃ́A��ŏq�ׂ�u�ƒ�v��n��Љ�̖��Ɩ��ڂɂ�������Ă���B
�Ώێ҂��u���N�ێ��v�̂ق��ɂ����Ă����ړI�́A�l�Ƃ̂ӂꂠ���A�܂�u���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����v�ł���B���R�A�����ł̑��҂Ƃ͐E��ł̓����₨�q����̂��Ƃł���B�����Ă����ł�����d�v�Ȃ��Ƃ́A�����ړI��3�Ԗڂł���u�������v���A���́u���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����v�Ƃ����ړI�ɒ������Ă���_�ł���B�Ώێ҂�3�l�́A�݂Ȉ�l�Ɂu�������v�̑�����������Ă������A���̎g�r�͂قƂ�ǂ����W���[��ƌ��۔�ł���B�N���Ő����͂ł��邪�A�����ē������������邩��A���ʂ��Ă̐l�ԊW���ێ�������A�F�l�ƐH���◷�s�ɍs�����肷�邱�Ƃ��ł���̂��B�s�s�ɐ������Ȃ���A������x�ȏ�̋��z���x���킸���ė]�ɂ�����邱�Ƃ͓���B�����Ă����ł��A�l�ԊW�̍\�z�ƈێ��Ƃ������Ɛ[����������Ă���̂��A�u�ƒ�v��n��Љ�ł���B
���ɁA�Ώێ҂́u���ꏊ�v���A�u�ƒ�v��n��Љ�ɂȂ��A�Ƃ����_����������B�Ώێ҂́A��N��ɉƂɂ���������U��Ԃ��āA�u���邱�Ƃ��Ȃ��v�u�M�N�V���N���Ă���v�ƌ����Ă����B
�s���̃V���o�[�l�ރZ���^�[�̎����ǂœ����E���ɃC���^�r���[�����ۂɁA�j������҂��V���o�[�l�ރZ���^�[�ɉ������闝�R�ɕt���āA���̂悤�ɏq�ׂĂ����B�u�����͉Ƃɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���������܂����ǁA�j���͂��Ă����������ނ��炢�������邱�Ƃ��Ȃ���ł��B�v�����̃Z���^�[�ɉ�������j���̑������A���̐E���Ɂu�Ƃɂ����Ƃɂ����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ𑊒k���Ă��邻�����B�u�Ƃɂ����Ƃɂ������Ȃ��̂ŁA���ł��������牽���d���͂Ȃ��ł����v�ƌ����āA�Z���^�[�ւ̉�������]���Ă���̂ł���B����ɂ��̐E���̕��́A�����ւ��I�Șb�����Ă��ꂽ�B�ނ͂�����A�P�������ƃX�[�p�[�}�[�P�b�g�̒��ɗ����Ĕ������q���ώ@�������Ƃ����邻�����B����ƁA�����q�̑����͔������r���ɒm�荇���ɉ�����ꍇ�����Œ��X�Ƙb�����ނ̂ɑ��āA�j���q�͒m�荇���ɂ����Ă����A�����邾���Ȃ̂��������B�ނ͎��̂悤�ɉ�����Ă����B�u�����͂��̒n��ɂ����낢��ȃl�b�g���[�N�̍L���肪����܂����ǁA�j���͉�ЎЉ�ł����Ɠ����Ă��܂�������A�ƒ낾������Ȃ��Ēn��Љ�ɂ����ꏊ���Ȃ���ł��ˁB�v�@
�����炭���̂��Ƃ́A�ނ�́u�ƒ�v�A�܂�V�v�w���т��u�ߑ�Ƒ��v�Ƃ��Ă̓����������Ă��邱�ƂɋN�����Ă���B�{�_����1�͂Ő��������悤�ɁA�ߑ�Ƒ����K�肵�Ă���̂͂��̍\�����ł͂Ȃ��A���Y�W�̕ω��ɂ���Đ������\�����̐��ʁE�N��ʖ������S�ł���B�Ώێ�3�l�́A���Ƃ��Ǝq�����Y��ł��Ȃ������肷�łɎq�ǂ����Ɨ����Ă�����ŁA���݂͍ȂƓ�l�Ő������Ă���B��Ђ���N�ސE���Ă��܂����B���łɁu�v�v�u�ȁv�A�������́u���e�v�u��e�v�Ƃ��������͉ʂ����I���Ă��܂����̂ɁA�l�ԊW�̘g�g�݂Ɓu�Ƒ��v�Ƃ������ꕨ�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B�u�ߑ�Ƒ��v�́A�u�s��E���̈�E�j�v�^�u�Ƒ��E���̈�E���v�A�Ƃ����敪���x�[�X�ɂ��Ă���B���������āA�s�ꂩ������グ�Ă����j���ɂƂ��āu�ƒ�v�͋��ꏊ�ł͂Ȃ��̂��B�����āA�n������㋞���ďA�E�A�����������ނ�ɂƂ��ẮA���ڂȒn��Љ�Ƃ̂��������Ȃ��B���̌��ʁA�Ƃɂ��Ă��u���邱�Ƃ��Ȃ��v���A�u�M�N�V���N���Ă���v�̂ł���B�v�w�̊W�͐��Y�W����Ղɂ��Đ��藧���Ă��邩��A��N��́u�C�����̐�ւ��v�Ȃǂł����������ł͂Ȃ��B�����Œ�N��́u�v�v�́A�V���Ȃ鎩���́u���ꏊ�v�����߂ăV���o�[�l�ރZ���^�[�ւƂ���Ă���̂ł���B�u���ꏊ�v�Ƃ́A���̐l�Ԃ��Ƃ�܂����肵���l�ԊW�̂��Ƃł���A���̐l�ԂɂƂ��āu����ׂ����Ɓv�̂���ꏊ�Ȃ̂ł���B
�I��
�{�_���̖ړI�́A�u�ߑ�v�Ƃ����Љ���u�V���v�Ƃ������_��ʂ��Ĕᔻ�I�ɍČ������邱�Ƃł������B�����̌��ʁA�u�ߑ�v�Ƃ́u���������v�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�Ԃ��ʂɐ��ݏo���Ă��܂����Љ�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̌��_�ɒB�����B
�{�_���ł́A�܂��u���{���v�Ƃ������_�I�g���݂���A�u�ߑ�v�́u�V���v���A�J���̎����ω����邱�Ƃɂ���āi�Ɠ��J����������J���ɂȂ邱�Ƃɂ���āj�A�J���҂�����N��ɒB����Ƃ݂�����̘J���̔�����������A���̌��ʁu�����Ȃ��Ȃ邱�Ɓv�ł���A�ƒ�`�����B���̓��{�Љ�ɂ����Ă��́u�V���v�́A�ڍs������Ƃ�������Ȑl���ɂ���đ�O�����ꂽ�\���ƂȂ����B�Y�ƍ\���̋}���ȕω��ɂ��ٗp�Ҕ䗦���㏸���A����ɒ�N���x�����y�������ʁA80�N��㔼����u��N�v�Ƃ����u�V���v���}����l�Ԃ����債���̂��B21���I���}���悤�Ƃ��Ă��鍡�A�܂��Ɂu�V���v�ɒ��ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�Ԃ��}�����Ă���B
���ۂɁu��N�v���}���������̍���҂́A�݂�����̘J���ɂ���Ď�ɓ��ꂽ�u��Ƃ肠��V��v�̂����Ȃ��ŁA�u���������v�Ƃ������Ƃ��l������Ȃ������B�����E�J������Ƃ��ẴV���o�[�l�ރZ���^�[���A�����ɂ͎�Ɂu���������v��Ƃ��ċ@�\���Ă��邱�ƁB�����V���́u���������v�L�����o�ϐ����ƂƂ��ɑ������A���̑������u�V�l�v�́u���������v��₤�Ă��邱�ƁB�����̎������A���Ȃ��炸����҂��u���������v�Ƃ������ɒ��ʂ��Ă��邱�Ƃ��ؖ����Ă���B
�u��N�v���ތ�̍���҂́A�u���ꏊ�v�������B�J���͍Đ��Y�̂��߂̏�ł������u�ƒ�v�́A�ނ炪�]����x���u���ꏊ�v�ł͂Ȃ��B�n������㋞���ďA�E��������ɂ́A��N��̔ނ������Ă����n��Љ���Ȃ��B���͂⓭���Ȃ��Ƃ���ɓ���N���A�ۏႳ��Ă��鐶���B���z�Ƃ���Ă����u��Ƃ肠��V��v�͌����̂��̂ƂȂ����ɂ�������炸�A�ނ�́u���ꏊ�v��u���������v��T�����߂Ȃ���Β�������V������Ȃ��̂��B�����炭�ނ�́A�u���������v�Ƃ������Ƃ�ʂ��āA������K�v�Ƃ��Ă����l�Ԃ�A�����̂Ȃ��ׂ����Ƃ�T���Ă���B
�������A�u�V���v�́��ނ灄�̖��ł͂Ȃ��B
�ߑ㉻�i���{���̐������s��o�ς̐����j�ƁA����ɔ���������������S�A���C�t�T�C�N���̕ω��B���̌��ʐ��ݏo���ꂽ�̂��A�u�������Ɓv�𒆐S�ɂ��Č`�����ꂽ���x�≿�l�ςɂ���Ďx������u�ߑ�v�Ƃ����Љ�ł������B����䂦�u�ߑ�v�́A�����Ȃ��l�ԁA�������Ƃ̂ł��Ȃ��l�Ԃ��u���v�̑ΏۂƂ��Ă����B�u�V�l���v���A���̓T�^�ł���ƌ�����B������s��̒��S������ӂւƒǂ�����Ă���u�V�l�v�A�܂��́u�����v��u��Q�ҁv�B�ނ�́u���v�̑Ώۂł���A�u���������v��t�^�����Ώۂł���B�u�������Ɓv�����S�ɐ������Ă��܂������ʁA�����Ȃ��l�Ԃ⓭���Ȃ��l�Ԃ��A�u�������Ɓv�ȊO�̑I������I�Ԃ��Ƃ͔��ɍ���ȏɂȂ��Ă��܂����B�����Ȃ��ł��邽�߂ɂ́A�u���������v�����߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�s��́A�o�ϔ��W�ɔ����āA����܂Łu�O���v���������̂������u�������v���Ă����B���Ƃ��u�������v�Ɋւ��ẮA���{�ł�����܂łɒj���̕�����}�邽�߂̂��܂��܂ȑ[�u���Ȃ���Ă����B�������ɁA�����ɂƂ��āu�������v�̑I�����������邱�Ƃ͖]�܂����B�������j��������B�����Ă������Ƃ́A�u���v���������Ă���悤�Ɍ����āA���́u���v�̉A�ɂЂ���ł�������ƍ����I�ȁ���聄����ڂ����炵�������B���̂����ƍ����I�ȁ���聄�ɍĂѕʂ̊p�x�������̂����߂ɁA�u�V���v�ɂ��čl�����B�������s��̒��S�ւ̓�����ɂ����Ƃ��Ă��i�u�������v���Ȃ��Ȃ��Ă��j�A����聄�͉������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�s��́u�O���v�͌����ĂȂ��Ȃ�Ȃ����炾�B�����Ă��́u�O���v���A���E�V�X�e���̎��ӂ�ݓ��O���l�J���҂ɂƂ��Ắu���v�Ƃ��Ă����c����Ă���̂ł͂Ȃ��A���͎s��̒��S�ɂ���l�Ԉ�l��l�̐��U�̒��ɂ���̂��Ƃ������Ƃ��A�u�V���v�͂킽���B�ɂ������Ă����B�s��̒��S�ɂ���l�Ԃ͂���܂ŁA�V�l���u���v�̑ΏۂƂ��Č��Ă����B�������A�u�V���v�́��ނ灄�̖��ł͂Ȃ��A�˂Ɂ��킽���������̖��Ȃ̂ł���B
�Q�l����
|
�w�ߑ�Ƒ��̐����ƏI���x |
����ߎq |
1994 |
��g���X |
|
�w21���I�Ƒ��ցx |
�����b���q |
1994 |
�L��t |
|
�w�ƕ������Ǝ��{���x |
����ߎq |
1990 |
��g���X |
|
�w�o�ϊw�E�N�w���e�x |
�}���N�X |
1964 |
��g���X |
|
�w���{�_�̐��E�x |
���c�`�F |
1966 |
��g���X |
|
�w�t�B�[���h���[�N�x |
������� |
1992 |
�V�j�� |
|
�w�Љ���̊�b�x |
��i���@��˗Y��@������j�@�� |
1996 |
������w����U���� |
|
�w�Љ�w�����T�x[�V��] |
�_���N�@�|����Y�@�ΐ�W�O�@�� |
1997 |
�L��t |
|
�w20���I�̓��{�U�@���x�����x |
�g��m |
1997 |
�ǔ��V���� |
|
�w���{�V�l�����j�x |
�S���F |
1997 |
�����@�K |
|
����̃G�X�v���w����̐��������x |
|
1990 |
������ |
|
�w��N����̉Ƒ����N�x |
�����m |
1996 |
���|�t�H |
|
�w�Ȃ����̎v�H���x |
�֓��Βj |
1994 |
�u�k�� |
|
�w�J�������x |
|
|
|
|
�w���������x |
|
|
|
|
�w�������������x |
|
|
|
|
�w�ٗp�Ǘ������x |
|
|
|
|
�w�J����{�����x |
|
|
|
|
�w����ҏA�Ƃ̎��ԁx |
|
|
|