�c��`�m��w��������w����������w��
2004�N�x���Ƙ_��
���a���k�b��Ɛ��m���l
�`�s�풼��ɂ�����m���l�̎v�z�I����`
�w�������F���F�p��
�����F�J�쒼�f
�w�Дԍ��F70105665
�q�v��r
�@�{�_���́A�s���1948�N�Ɍ������ꂽ�i�����Ȍ�����1949�N�j���a���k�b��ƁA����ɎQ�������m���l�̎v�z����������̂ł���B���a���k�b��́A�������炢�O��̐����\���A�傫�Ȕ�����^�����B�Ƃ�킯�A1950�N�̐����Łu�S�ʍu�a�E�����E�R����n���E�ČR�����v�̕��a�l�����������Ĉȗ��A�u�a�_���̈ꗃ��S�������Ƃł悭�����Ă���B�����āA���k��ƎЉ�}���h��]�����т����ƂŁA���a�^���̈�吨�͂�z�����ƂƂȂ����B�������A���̌�1950�N��12���Ɂu�O���ѕ��a�ɂ��āv�\�̌�A�}���ɂ��̊����̊������͎����Ă������ƂɂȂ�B
�@�����āA���k��ɎQ�������m���l�͊ێR���j��v����E���������Y�ȂǁA50�N��ȍ~�ɒ����ƂȂ����҂������B�܂��A�ێR�炾���łȂ����{�\���������q�E�a�ғN�Y�ȂǁA���N���̐l�X���Q������Ƃ������̍L�����̂ł������B���̂悤�Ȓ��ŁA���k������̎v�z�I�E����I�ȑ���������A���̕���ߒ���ǂ����Ƃ��{�_���̖ړI�ł���B
�@�܂��A��͂ł́A���a���k�b����Ɏ���܂ł̑O�j�������B�����ł́A���k��̑g�D�҂ł���g�쌹�O�Y�̐풆������̓��������Ƃ��āA�g��Ɗ�g���X�Ƃ̊W�A���k���Ȑ������\�̏�ƂȂ�w���E�x�n���̌o�܂Ɓu���S��v�Ƃ̊W�Ȃǂ𒆐S�Ƃ��Č��čs���B�܂��A��̓I�ɕ��k����̌o�܂�����ƂƂ��ɁA�����̒m�I�����킹�ĊT�ς���B
�@�����āA��͂ł́A���k��ɎQ�������m���l���u����I�w�i�v�u�v�z�I�w�i�v�Ȃǂ̊ϓ_�ɒ��ڂ��A�ǂ̂悤�ɕ��k��Ɋւ�����̂��A���邢�͊ւ�肩���ɕω����������̂�����������̂ł���B���̏�ŁA�e�m���l�̗l�X�ȑ��Ⴊ���k��̊����ɂǂ��������e����^���Ă������̂��Ƃ����_�����킹�Č�����B��̓I�ɂ́A�ێR���j�E���{�\���E�v��������Ƃ��Ȃ���A���킹�Ė��씎�E�P�����E���������Y�̓������K�X���y���Ă���B
�@�O�͂ł́A��͂Ō������m���l�̎v�z�̑��l���⍷�ق��A���k��̊����̂ǂ̂悤�ȉe�����������A�m���l�̕���̌_�@�Ƃ��̉ߒ����A��܂��ł͂��邪�����Ă���B��̓I�ɂ́A���k��Ƃ��̌�̕��a�^���̗���̒��ŁA�m���l�̕��������悤�ɂ��Ă���B
�@���_�̏͂ł́A�ȏ�̌��؉ߒ���������x�m�F���A�{�������瓱���o���錋�_���q�ׂĂ���B
�q�ڎ��r
���_
�@���ӎ�
�@����
�@�����Ώ�
������@
�@��s����
�{�_
�P�D���a���k�b��O�j
�@�P�|�P�D�g�쌹�O�Y�Ɗ�g���X
�@�P�|�Q�D�w���E�x�Ɠ��S��
�@�P�|�R�D���a���k�b��̍\�z�ƌ���
�@�P�|�S�D�g��̐��
�Q�D���m���l�ƕ��a���k�b��
�@�Q�|�P�D�ێR���j�̎v�z
�@�@�Q�|�P�|�P�D�u�����v�Ɓu��̐��v
�@�@�Q�|�P�|�Q�D�u�m���l�̘A�сv�Ɓu���O�v
�@�@�Q�|�P�|�R�D�I�[���h�E���x�����X�g�Ɛ���_�I���z
�@�Q�|�Q�D���{�\���ƃI�[���h�E���x�����X�g
�@�Q�|�R�D�v����E���������Y�ƕ��a���k�b��
�@�@�Q�|�R�|�P�D���W�X�^���X�̎v�z
�@�@�Q�|�R�|�Q�D���a�_�Ǝs����`
�@�@�Q�|�R�|�R�D���������Y�ƕ��a�^��
�@�Q�|�S�D�c���^�E����ɂ����镽�a���k�b��
�@�@�Q�|�S�|�P�D�w�҂Ɩ��O�Ƃ̘A��
�@�@�Q�|�S�|�Q�D���씎�ƕ��a���k�b��
�@�Q�|�T�D���a���k�b��̐���
�@�@�Q�|�T�|�P�D�u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v
�@�@�Q�|�T�|�Q�D�u�u�a���ɂ��Ă̕��a���k�b����v
�@�@�Q�|�T�|�R�D�u�O���ѕ��a�ɂ��āv
�R�D���a���k�b��̕���
�S�D���_
�@�S�|�P�D�m���l�̑��l��
�@�S�|�Q�D�u�����v�Ƃ����R��
�@�S�|�R�D�u�i���I�����l�v�Ƃ����ď�
��
�Q�l����
�ӎ�
�q���́r
���ӎ�
�@��シ����1948�N�A���a���k�b��Ƃ������̌����c�̂��������ꂽ�B�i�����́A���a��蓢�c��B�܂��A���̑��ɂ����l�X�R�̉�╽�a��荧�k��ƌ������ď̂����݂������A�㐳���ɕ��a���k�b��Ɩ����j���̕��k��ɂ́A�ێR���j�E�v����E�s���d�l�E���������Y�E���{�\���ȂǁA�����Ȑ��m���l������50���ȏ�Q���������̂ł��邱�ƂŒm���Ă���B����ɉ����āA�T���t�����V�X�R�u�a���̒����Ɋւ���_���������Ȏ����ɁA�u�S�ʍu�a�E�����E�ČR�����E�R����n���v�Ƃ����e�[�[��ł��o�������Ƃł��悭�m���Ă���B���̕��a�l�����́A��ɎЉ�}���h��]�Ɏp����Ă����A���a�^���̐��I�Ȗ������ʂ����ƈʒu�Â��邱�Ƃ��\�ł���B�������A���k��̂̊����̃s�[�N��1949�N����1951�N�̊Ԃƌ����Ă悭�A���̌�͑g�D���͎̂c���Ă͂�����̂́A�����I�Ȋ����͋}���ɏI�����Ă������ƂɂȂ�B
�@���̑傫�Ȕw�i�̈�ƂȂ���̂��A���k������̒m���l�Ԃ̎�X�̑���ł���B����͓x�X���y����邱�Ƃł��邪�A���k��ɂ͎v�z�I�Ȕw�i�␢��I�ȑ���Ƃ����_���猩���ꍇ�A���̐��m�͂��Ȃ葽�l���ɕx��ł���ƌ�����B�����āA���k��ɎQ�������m���l�̒��ł��A�ێR���j��v����E���������Y���̂悤�Ȓm���l�͂��悻1950�N��ȍ~�ɒ����ɂȂ����ƌ����邾�낤�B[�P]
�@�ȏ�̂悤�ȓ_�܂��Ė{�_���ł́A���k���������A���̊������s�[�N�ɒB���A�₪�Đ��ނɌ���������̒��ŁA���k������̎v�z�I�E����I�ȑ���������A�m���l�̕���̉ߒ��������Ă������Ƃ�ړI�Ƃ���B
����
�@�܂���_�ڂ́A�O�q�̒ʂ�A���k���������A���̊������s�[�N�ɒB���A�₪�Đ��ނɌ���������̒��ŁA���k������̎v�z�I�E����I�ȑ���������A�m���l���݂̕���̉ߒ���ǂ����Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�ł���B�t�Ɍ����A��X�����Ă����悤�ɁA���k��ɎQ�������m���l���݂̎v�z�I�ȍ������m�ł���ɂ��ւ�炸�A�Ȃ������c�̂��������A�Z���Ԃł͂�����̂̐^���Ȋ������s���Ă������Ƃ��ł����̂��Ƃ����^������藧�B����ɁA���̕��k��������Ă��������́u��㖯���`�ҁv��u�i���I�����l�v�Ƃ������C���[�W�͖����`������Ă͂��Ȃ������B�m���l�̏W�c���������番���ւƌ������ߒ��́A�e�X�̒m���l�̐��i�K���C���[�W�����m�ɂȂ��Ă����ߒ��ł���Ƃ�������B���������Ӗ��ł́A�u��㖯���`�ҁv��u�i���I�����l�v�Ƃ������C���[�W���`������Ă����ߒ��ɂ������I�ł͂��邪���ł���ƍl����B[�Q]
�����Ώ�
�@�{�_���̌����Ώۂ͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B
�@ �s�풼�ォ�畽�k��I���Ɏ���܂ł́A�ێR���j�E���������Y�E���{�\���E�v����E��
�씎�E�P�����̒���ށi���k���G�b�Z�C���܂ށj�A���k��̐����ⓢ�c��̋c���^
�B ���k��̑g�D�҂ł���g�쌹�O�Y�𒆐S�Ƃ��镽�k��W�҂̉�z�ނ�A���k����
���\�̏�Ƃ��Ă����G���w���E�x�n���̌o�܁B�܂��A�@�Ɋւ��Ă͓������k��Ƌ��s���k��̎v�z�I�ȍ��ق╽�k��ɂ�����v�z�I�w�i�y�ѐ���I�w�i�Ȃǂ̍��قƑ��l���������邽�߂ł���B�����ćA�Ɋւ��ẮA��ɕ��k��̋c���^�𒆐S�Ɍ��Ă������Ƃɂ���B�O��̐����̕��͂͐�s�����ɂ����Ă��A������Ă��邱�Ƃł���A�{�_���̕����ł����Ό����I�Ȑ��������c���^�̂ق��������鉿�l�͑傫���ƍl�����B�B�ɂ��ẮA���k��̑O�j��A���k��̎�ȑg�D�҂ł���g�쌹�O�Y�̊����܂��邽�߁B
������@
�@�{�����ł́A��ɗ��j�w�Ƃ�킯�v�z�j�̃A�v���[�`���̗p����B�e�X�̒m���l�̎v�z�ƍs�������k��̊����Ƃǂ̂悤�Ɋ֘A���Ă���̂��Ƃ����_�ƁA���k��̓����̎v�z�I�ȑ��l����������Ƃ�����ɓ�_�ɂ��Ċe�m���l�̒���������Ă����B���̍ہA������m���l�Ƃ��ẮA�ێR���j�E���{�\���E�v����E���������Y�E���씎�E�P�����𒆐S�Ɍ��Ă������Ƃɂ���B�O�q�����悤�ɕ��k��ɂ�50���ȏ�̒m���l���Q�����Ă���A���̑S���̓�����ɂ����钘���������͕̂s�\�Ƃ͌���Ȃ����A�ǂ��܂ňӋ`������̂��Ƃ����_�ŋ^�₪�c��B�ł���̂ŁA��q�̒m���l���@�������k����s���k��A�N��E����I�Ȕw�i�B��O�ɂ�������ԓx��m���l�ςƂ����O�_�𒆐S�Ɍ��Ă������Ƃɂ���B
��s����
�@���k�����Ɉ�������s�����Ƃ��Ă͈ȉ��̂��̂���������B
�@�֊����u���a�̐����w�v�i�w���{�����w��N��x�u�s���_�Ȍ�̐����w�v��g���X,1977�j
�A�\�����m�w�Γ��u�a�Ɨ��x�i������w�o�ʼn�A1986�j
�B���F�p��w�q����r�Ɓq�����r�x�i�V�j�ЁA2002�j
�C��菲�u�w���E�x�ƕ��a���k�b��v�i�w���O�j������x��45���A���O�j������A1993�j
�D����݂ǂ�u���m���l�ƕ��a�^���̏o���v�i�w�N����{����j�x��8���A�u�����{�̖��O�ӎ��ƒm���l�v�A����j���o�ŁA2002�j
�E�s�z�ׁw�����{�̒m���l�x�i���D���[�A1995�j
�F�O�����E�t�b�N�u�����{�̕��a�̎v�z�̌����v�i�w���ې����x��69���A�u���ۊW�v�z�v�A���{���ې����w��A1982�j
���̂����@�E�F�͎�Ɂu���a�w�v�Ƃ������_�I�Ȏ��_���畽�k��̐�����_�������́B�A�́A��ɕ��k��ƍ��h�Љ�}��]�Ƃ̉e���W��_���Ă���B�B�́A���k��Ɩ��O�̕��a�ӎ��╽�a�^���𒆐S�Ƃ��Ă���B�C�́A���{���a�������̑�R��v��G���w���a�x�𒆐S�ɁA���k��ƑΔ䂳���Ȃ���_���Ă���B�D�ƇF�͒m���l�̎v�z�ƕ��k��Ƃ̊֘A���q�ׂĂ��邪�A�m���l�̕���ߒ��𒆐S�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ĕ��k��̌�����80�N��ɂ����ẮA���a�w���邢�͕��a�����Ƃ������_�����Ɉ����Ă����B���̂�90�N��㔼���猻�݂Ɏ���܂ł́A�v�z�j�I�ȃA�v���[�`�̈�Ƃ��Ę_�����Ă���X���������B���̈Ӗ��ł́A�{�_�����܂��v�z�j�I�ȃA�v���[�`���̗p���Ă͂��邪�A�m���l�̎v�z�I�ȕ���ߒ��ɒ��ڂ��Ă���_�������ƌ�����B
�q�{�_�r
�P�D���a���k�b��O�j
�P�|�P�D�g�쌹�O�Y�Ɗ�g���X
�E�E�E�����ł́A�����邭�낤�ƈӎ������������Ƃ͂��ɂȂ��A�������낤�Ƃ̂悤�ȋC�����ƁA���낤�Ƃ����炩�����Đ��ԕ��ʂ̂��낤�Ƃ��͏����܂��Ȏd�����ł���̂��Ƃ����A�Ђ����Ȏ����������Â��č����Ɏ���܂����E�E�E[�R]
�g�쌹�O�Y�ƌ����A��g���X�̑����G���w���E�x�̕ҏW���Ƃ��Ēm���Ă��邾���łȂ��A�w�N�����͂ǂ������邩�x�̒���ł��L���ł���B[�S]�������A��L�̉�z�����������Ƃ���A1899�N���܂�̋g��́A��������ҏW�҂̎d�������Ă����킯�ł��A�ҏW�҂�ڎw���Ă����킯�ł��Ȃ��B���̐߂ł́A�g��̐��������Ɛ풆�̌o�܂�ǂ��A�ҏW�҂ƂȂ��Ă����ߒ��������邱�ƂƂ���B
�g��́A������Z���瓌��o�ϊw���ɓ��邪�A���̌シ���ɕ��w���N�w�Ȃɓ]���A�Ȍ�J���g�̔F���_��w�[�Q���̗��j�N�w�Ɉ�т��ĊS�������������B���w���E�x�ҏW���̗ΐ엺���A�u�g�삳��́A�ꌾ�Ō����ΓN�w�҂ł����v�Əq�ׂĂ���قǂł���B[�T]
�@�g�삪���w�O�N�̎��ɁA��ꎟ���E��킪�u�����A��Z���w�̑O�N�Ƀ��V�A�v�����N���钆�ŁA�����̎Љ���ɊS�����߂Ă������B���̎��g�삪�؎��Ɋ��������Ƃ́A�u�������������Đ��������̒��ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA�����̐ӔC�ł��Ȃ��̂ɕs�K�Ȗڂɂ����Ă���l�������ɑ������v�Ƃ������ӎ��������B[�U]���̌����ɑ�����ӎ��́A�풆���Ƌg��̒��ɑ��݂������Ă����A�Ƃ�킯���̊����ɂ�����v�z�I��ՂƂȂ��Ă������̂ł���B
�@1925�N�ɓ�����w���w���N�w�Ȃ𑲋Ƃ�����A�������o��������A�O�ȓ��̕ҏW��
�Ⓦ��}���ق̎i���̎d���𑱂��Ȃ�����A��w���w�ȗ����g��ł����J���g�N�w��
���𑱂����B�J���g��w�[�Q�����I���̉ۑ�Ƃ��Ă������Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B��
���ɑ�����ӎ��Ɠ��l�A�g��̎v�z�I�w�i�Ƃ��Ċʼn߂ł��Ȃ����̂́A����������
�N�w�A�Ƃ�킯���j�N�w�ɑ���S�ł���B���̓_���A���̊������x�����ՂƂ�
�Ĉʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�g��͌�N�A���̕ҏW�Ҏ���̊����̓��@���A�����ɑ�
������ӎ��ƓN�w�I�S�Ƃ�����_�����z���Ă���B
�@�E�E�E���̖Z�����d���Ɂi���̕ҏW�҂̎d���\���p�ҕ�j�����ǂ��ɂ�����ė���ꂽ�̂́A��ɂ͎��̓N�w�I���������j�N�w�ɂ��������߂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����킹�ɂ��A���������Ċ�O�Ɍ}���Ă���̂́A���E���j�͂��܂��Ĉȗ��A�O����Ȃ��قǑ�K�͂ȁA�s��ȓ]���ł����B�ǂ�ȏ����ɂ�������Ă��Ȃ����j�̑傫�ȈӖ��������̎��̑O�ɓW�J���Ă���B���ꂪ�ǂ݂Ƃ�Ȃ��ŁA�Ȃ�̗��j�N�w�����낤�A�Ƃ����C�����A���̊����X�̎����ɏW�������Ă���܂����B������ɂ́A������������ɐ����Ă��铯����̓��{�l�ɂƂ��āA�܂����̖��́A���̐V�����������ǂ��������炢�����Ƃ������ł����āA�o�ł̎d���͂���ɓ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����l���������܂��Ă���܂����E�E�E[�V]
����ŁA1931�N�̗\�����Z����ɂ́A�����@�ł��������Y�}�Ƃ̊W���猟��
����A�R�@��c�ɂ�������Ƃ����o�������Ă����B�R�@��c�̔����͎��s�P�\�O�N�ł���A�Y�����ň�N�����߂����o�������Ă���B
�@�{�e�̓��e����肵�ďq�ׂ�A���a���k�b��́A��킪�������钆�ŁA�ă\��
�w�c�̐ϋɓI������ł��o�����߂ɁA�u�v���v�Ɓu���a�v��藣�����v�l�l����ł�
�o���Ă����B���a���k�b��ɐϋɓI�ɂ������A���ۓ�����x���A�̎��H�����ɂ��Q
�������N�w�҂̋v����́A�u�v���v�Ɓu���a�v��藣�����l���͊ێR���j��s���d�l�A
���������Y�ɂ͂��������A�g��́u���Ă͋��������v�ł���A���a���k�b��̌���
�������u��������^�v�������Ɖ�z���Ă���B[�W]�R�@��c�ɂ������A�Y�����ʼn߂���
�����Ƃ�����e�Ղɗ����ł���悤�ɁA���̎����̋g��͋��������ł������B
�@�������ɏڏq���邱�Ƃł��邪�A�g�삪���a���k�b��̌����𐬂�������ɂ���
���āA�Љ�}�Ƌ��Y�}�Ƃ̑Η���Y�ʉ�c�Ɩ����h�Ƃ̕������ɗJ�����Ă�������
���傫�Ȗ��ӎ��Ƃ��đ��݂����B���̖��ӎ�����͂�풆�̌o�܂ɋ��߂�ׂ��ł�
�邱�Ƃ��킩��B
�@���R�Y��������o����A���悻�O�N�Ԃ̎��Ə�Ԃ��������ƂɂȂ�B���̌�A�R�{�L�O�Ƃ̊W����A�u���{���������Ɂv�̕ҏW��C�������A���g���w�N�����͂ǂ������邩�x���o�ł����B���́A���_�e���Ɣ������������Ȃ�n�߂�1937�N�̌܌��ł���A�R�{�̂悤�Ȏ��R��`�I����̐l�Ԃł��A���R�Ȏ��M������ƂȂ��Ă����B���́u���{���������Ɂv�́A�t�@�V�Y�����������Ȃ鎞��Ɂu���ȍ�����`�┽���I�Ȏv�z�����A���R�ŖL���ȕ����v��������ɓ`����Ƃ����ړI�Ŋ��s���ꂽ���̂ł���B[�X]�����Ƃ��ẮA���E���肬��̒�R�ł������ƌ�����B
�@���ہA�w�N�����͂ǂ������邩�x�Ƃ������N���������̏����̒��ɂ��A��l���̃R�y���N�����~���N�Ƃ������i���l�@���A���̔w��ɂ͑��푽�l�Ȑl�X�̌��т������݂��邱�Ƃ������ʂ�����B���̂��Ƃɑ��āA��������̎�l���ł���u��������v�́A������u���Y�W�v�ƌĂсA�o�ϊw�̊�{�ł���Ɛ�����ʂ�����B����́A��̏��i�̍l�@���珉�߂đS���Y�W�ւƍl�@����w���{�_�x��A�z��������̂ł���B�����ɂ��A�g��̐펞���̒�R�A���Ȃ킿�u�������������Đ��������̒��ł͂Ȃ��v�Ƃ������ӎ���ǂݎ�邱�Ƃ��o����B
�@���̂悤�ȈӖ��ł́A�펞���̌��_�e���Ɣ����̒��ŁA���N�����ɑ��������w�N�����͂ǂ������邩�x�́A�g��̎��g�ɑ���u�ǂ������邩�v�Ƃ����₢�����̏��ł��������ƌ����悤�B�g��́u�ǂ������邩�v�Ƃ������́A1938�N�̊�g�V���n���ŁA�ЂƂ̓�����������邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@���́u�ǂ������邩�v�Ƃ������Ɗ֘A���āA�����̖����G����Ă���B���Ƃ��A�ȉ��̂悤�ȋL�q������B[�P�O]
�@�E�E�E�������A���������ꂵ�݂̒��ł��A��Ԗl�����̐S�ɓ˂�����A�l�����̊Ⴉ���Ԃ炢�܂����ڂ肾�����̂́A�\��������肩�����̂��Ȃ��߂���Ƃ��Ă��܂����Ƃ����ӎ����B�����̍s����U��Ԃ��Č��āA��������ł͂Ȃ��A���`�S����A�u���܂����v�ƍl����قǂ炢���Ƃ́A���炭���ɂ͂Ȃ����낤�Ǝv���E�E�E�l�������A�����̎v���ɑł����Ƃ����̂́A�����͂����łȂ��s�����邱�Ƃ��o�����̂Ɂ\�A�ƍl���邩�炾�B���ꂾ���̔\�͂������ɂ������̂Ɂ\�A�ƍl���邩�炾�B�����������̐��ɏ]���čs�����邾���̗͂��A�����l�����ɂȂ��̂�������A���ʼn����̋ꂵ�݂Ȃ��키���Ƃ����낤�E�E�E
�ȏ�̂悤�Ȕ�������A�펞���̋g��̎v�z�I�ԓx�������Ȃ���̂ł������̂��Ƃ������Ƃ͗����ł���ł��낤�B
�@�����āA��q�́u���{���������Ɂv�̕ҏW��C�����������Ƃ����������ƂȂ�A��g�ΗY�̗U���Ŋ�g���X�ɓ��Ђ��邱�ƂɂȂ�B��������A�{�i�I�ɕҏW�҂Ƃ��Ă̋g�삪�n�܂����B����ȗ��A�펞���Ŋ�g�V���̑n���Ɍg���A���͌��݂ł��̔��𑱂��Ă��鑍���G���w���E�x�̕ҏW���Ƃ��Ĉ�т��ĕҏW�̔C�����ƂɂȂ�B
�@1938�N�ɐ��ɏo����g�V���́A�听�������߁A�u�����Ɠ����ɂ����ւ�Ȋ��}����
�āA�����܂��ł��d�˂�悤�ɂȂ����v�Ƃ����B[�P�P]�������A��g�V�����������ꂽ��
���́A�����푈���J�n����A�����m�푈�ɂ�����펞�̐��������B����͓����ɁA���_
��o�ł̎��R���D���Ă����������ł����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@���̂悤�ȏ���ŁA��g�V����n�����悤�Ƃ��Ă����g��̓��@�́A�O�q�́u����
�͌����Đ��������̒��ł͂Ȃ��v�Ƃ������ӎ��������B�g��͊�g�V���n���Ɍg���
�Ă��铖�����ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B
�E
�E�E��g�V���́A���̎����̓��{���x�z���悤�Ƃ��Ă����_������ȍ�����`
�⒆���̎����̑��̒鍑��`�I�Ȏv�z�ɒ�R���āA�����̊ԂɉȊw�I�ȍl�����␢�E�I�Ȃ��̂̌������L�߁A�����ɑ�����{�̌R���s���Ȃ��ᔻ���鎑������悤�Ƃ����l������o�������E�E�E[�P�Q]
�@�@���̂悤�Ȗ��ӎ����x���Ă����̂́A��g�ΗY�̉e�����傫�������B��g�V���̔��������f���A�g����e�Ŏx���Ă�����g�́A�펞���̒��ł��A�u�����푈�ɂ��Ă��A����͓��{�l�̔Ƃ����傫�Ȍ��ł����āA���{�l�͒����l�ɂ��̍߂�����܂�˂Ȃ�Ȃ��v[�P�R]�ƁA��Ɏ咣���Ă����B����䂦�A�����m�푈���u�����A���Ƒ������@�ɂ��ƂÂ��V�����f�ڐ����߂�A���_�o�ŏW��Г��Վ�����@�Ȃǂ��o����A�e��o�ŎЂ�V���Ђ́A�p���̊m�ۂ̂��߂ɐ푈���͂̊��𗧂Ă钆�ŁA��g���X�͐푈���͂̊�����x�����Ă��A���Ǖ��ɉ�l�Ԃ����Ȃ������B
�@�@
�P�|�Q�D�@�w���E�x�Ɠ��S��
�ȏ�̂悤�ȁu�����ɑ�����ӎ��v��u���j�N�w�v�ɑ���S�A�����ċ�����
���ł������Ƃ����_���ӑR��̂ƂȂ�g��͐����}���邱�ƂɂȂ�B���̐߂ł́A���̋g��̊����������邱�ƂƂ���B���_���猾���A�����������v�z�I��Ղɉ����A���̋g��̊����̃o�l�ƂȂ��Ă������̂́A�u�����v�̖��Ɓu�s��̋L���v�ł������B�g��́A�O�q�����w�N�����͂ǂ������邩�x�̒��ŁA�ȉ��̂悤�ɏ����Ă���B
�E�E�E�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B
�@�@�@�@�@���������Ƃ����Ƃ�����B
�@�@�@�@�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B
�@�@�@�@�@������A��肩�痧�����邱�Ƃ��ł���̂��E�E�E[�P�S]�@
���a���k�b���Ȋ����̏�Ƃ��Ă����w���E�x�̑n�������������ꂽ�̂́A�I
��̔N��12���ł������B���Ƃ��Ƒ����G���́A��g���X�Ƃ��Ă͖��J��̕���ł��������A�w���E�x�̏o�ł�����������̂͊�g�ΗY�������B���̔w�i�ɂ́A��g�Ȃ�̐푈�̌��Ɋ�Â��u�����v�̔O�����݂����B��g�́A�s�풼��ɐV���ȑ����G���̑n���̕K�v����͐����钆�ŁA���{���푈�����Ă���Ԃɂ��u���̌o�߂�S�O�̂��Ƃƍl���A�����ے肵�Ă��������ꂽ�w�҂�v�z�Ɓv���F���Ƃ͎v��Ȃ����A�ŏI�I�ɂ́u���{�������̂悤�ȔߎS�ȏ�Ԃɗ�������ł����̂��Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������v�Əq�ׂ��B[�P�T]
����䂦�A��g�͕����Ƒ�O�Ƃ̌��т������ɂ����d���Ƃ��āA�V���ȑ����G��
��n�������Ă������B�����āA�u����ǂ̐푈�ł�������̐N���������Ȃ����̂��A��ɂ͎��������N�y�̎҂����a�ŁA����˂Ȃ�ʂ��Ƃ��A�����ׂ��Ƃ��ɂ��킸�ɂ����������v�ƕt��������̂�Y��Ȃ������B[�P�U]
���̂悤�ȐS��́A�u���S��v�̃����o�[�ł���A��ɕ��a���k�b��̋c����
����{�\���Ȃǂ̂�����I�[���h�E���x�����X�g�ɋ��ʂł������Ƌg��͉�z���Ă���B[�P�V]�����Ă܂��A���̂悤�Ȋ���͓��̋g��ɂ����݂��Ă����B�I��̓��̑O���A���łɋ{���Łu�d���c�v���J����Ă��邱�Ƃ𖧂��ɒm���Ă����g��́A���W�I�ŋ�P���Ă�������Ă����B
�E�E�E���͂�S�����Ӗ��ƂȂ�����R���R����{���Â��Ă������ɁA�����̔ߎS���A�������ĂƂ߂ǂ��Ȃ��Ђ낪���Ă䂭�B�E�E�E���������̂�����Ă���^����m�炸�ɂ����E�]���Â��Ă��鉽�S���A���疜�̐l�X�ƁA����������͒m��Ȃ��牽�ЂƂł��Ȃ��ł��邱�̎����Ɓ\�\�A���ɂ́A���ꂪ�ꂵ���قǂ���ꂾ�����E�E�E[�P�W]
�@���̂悤�ȐS���w�i�Ƃ��āA�g��́w���E�x�̑n���Ɍg��邱�ƂɂȂ�B�g��ɂƂ��āA���̎d���́u���{�̍Č��v�ɂƂ��đ�Ȗ������ʂ������̂ł���A�Â����l�̌n���s����̂ƂƂ��ɕ��Ă������ŁA�u���{�̍Č��v�̂��߂Ɏ��R�Ȍ��_�@�ւ����݂���Ƃ����Ӗ��ȏ�ɁA���R�Ȍ��_�@�ւ̍Č����ꎩ�g���d�v�ȍČ��Ȃ̂ł������B
���a���k�b��Œ��S�I�Ȗ������ʂ��������������Y���A�u���_�̎��R�́A�w�����x�̂��̂łȂ��A�S�߂Ȕs�킨��ѓƗ��̑r���Ƃ����㏞�������̂ł��邱�Ɓv��Ɋ����Ă����B[�P�X]�����ł�������A���_�̎��R�y�і����`�̌������u�����̂��̂ƔF�߁A��l�����̓w�͂������������p���v���邱�Ƃɂ���āA�u�^����ꂽ���R�v����u���݂����������R�v�ɓ]�����邱�Ƃ���ł���B[�Q�O]�ł��邩��A�����`�̌������u����ǂ��������̑O�Ɉޏk���邱�ƂȂ��A�ʂ������Ďg�p���Ă䂭�̂łȂ���ΈӖ����Ȃ��v�Ƃ������S���g��͂��Ă���B[�Q�P]�܂�A�g�����̒��ɂ́A��㒼��́u�J�����v�ƂƂ��ɁA�����́u�ْ����v���������Ă����ƌ�����B�g��́A�u�V�����G�����n����̂͐V��������̂��߂ł������B�������A�����������}���悤�Ƃ��Ă��鎞��́A�Ȃ܂₳��������ł͂Ȃ������B�v�Ƃ������Ă����B[�Q�Q]��N���猩���ꍇ�A���̎����̂��Ƃ��w���āu�o���F�̌[�֎���v�ƌĂ�邱�Ƃ�����B�����I�ɂ͂������������ʂ��������ɂ���A������o���F�̌[�֎�`�̎���Ƃ����ď̂ɂ͈ꊇ�ł��Ȃ��A���G�Ȋ���������Ă����Əq�ׂ�ق����K�ł��낤�B
�@����ŁA�g��͐풆�̎����ɂ����锽�Ȃ̔O����g����{��Ƌ��L�����A��g�́u�����Ƒ�O�����т���v�Ƃ����u�[�֎�`�I�ȁv�d���Ƃ��Ắw���E�x�ɂ́A���^�������Ă����B�g��̍l���ł́A�펞���Ɂu�����̖��͂╶���l�̎コ�v�������Ă������߁A�����P�Ɂu�����Ƒ�O�����т���v�݂̂Ȃ炸�A������͂ނ���u��������O�̉^������Ƃ���悤�ɂȂ邱�ƁA�����ꂽ�w�҂�v�z�Ƃ���O�̉^���ɂ���������S�ɂ����A��O�ɂ�����Ăł����̖��Ɗi������悤�ɂȂ邱�Ɓv�̕����K�v�ł������B
�@�܂��A�w���E�x�͓����A�O�q�́u���S��v�̓��l�G���Ƃ��ăX�^�[�g�����B�u���S��v�Ƃ́A��g�ΗY�̊W�𒆐S�ɁA���{�\���E�u�꒼�ƁE���ҏ��H���āE�R�{�L�O�Ȃǂ�i���邢����u�I�[���h�E���x�����X�g�v�W�c�ł���B���̒��ł́A���{�\���������q�A�c���k���Y�炪�A��Ɍ��Ă������a���k�b��ɎQ�����邱�ƂɂȂ�B
�@�ނ�̑����́A��㕜�����������l�����ł���A�u�������Ƙ_�v�̒S����ł��������B[�Q�R]�������q���邪�A��ɕ��a�^���ɐϋɓI�ɃR�~�b�g���A�Љ�}���h��]�Ƃ��W��[�߂Ă������������Y��v��������a���k�b��ɎQ�����邱�Ƃ��|�C���g�ƂȂ邪�A�����u�I�[���h�E���x�����X�g�v�����a���k�b��ɎQ���������Ƃ���̃|�C���g�ƂȂ�B
�@�����Ŋm�F���Ă����K�v�����邱�Ƃ́A��_����B��_�ڂ́A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�Ƌg��Ƃ̎v�z�I�����̉����ł���B���̂��Ƃ�[�I�Ɏ����̂́A�u���S��v���w���E�x�Ƃ������M�̏�𗣂�A�V���ɎG���w�S�x��n�������Ƃ������Ƃł���B���S��Ɓw���E�x�̕����Ɋւ��ẮA�g��́u���ۓI�A�����I�������������Ă��āA�G���Ƃ��ẮA�}���Ɍ����ɐڋ߂��Ă䂩�˂Ȃ炸�A�������Ƃ̗��O�����ł͂���Ă䂯�Ȃ��Ȃ��Ă�������v���Ɛ������Ă���B[�Q�S]�g��͂܂��A�Âɐ�O�̃��x�����X�g���w���āA�u�t�@�V�Y���ɑ��Ĕ����Ђ��߂�̂́A���ꂪ�w�҂�|�p�Ƃ��������A�ނ�̎��R��D������ŁA�J���҂̒c������D������A�s���̎��R��Ƃ����肷�邱�Ƃɂ́A���������Ƃ��ĕ��������Ă�����悤�ɂ͌����Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B[�Q�T]�t�ɁA��̕��a���k�b��̋c���ł�����{�\�������A�g��̐^�ʖڂ��Ƃ����_�ł͐M�����Ă��邪�A�u�g��̎v�z�ƍs���ɂ͓��ӂ����˂�v�Əq�ׂĂ���B[�Q�U]
���̂悤�ɁA�ێR����Ɣ�ׂĔN���ł���g�삩�猩�Ă��A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�Ƃ̎v�z�I�����͗���Ă���ƌ�����B
�@��_�ڂƂ��ẮA��_�ڂ̊֘A�ŋg�삾���łȂ��ێR���n�߂Ƃ�����Ⴂ����̒m���l���A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�Ƃ̎v�z�I�E���_�I�����������Ă������Ƃł���B
�Ƃ�킯�ڗ��̂́A�ێR���j�̌����ł���B�ێR�́u���k��̖���v�ƌ����Ă�����ł��邪�A�s�풼�ォ��1950�N�O��ɂ�������k��ɂ����Ă��A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ɑ���ɗ�Ȕᔻ���q�ׂĂ���B�Ⴆ�A1949�N�ɂ�����G���w�l�ԁx12�����u�C���e���Q���c�B�A�Ɨ��j�I����v�Ƃ������k��̒��ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�c������I�[���h�E���x�����X�g�Ƃ�����l�B���푈�ɂ������āA�������Ă�����Ⴂ�l�B�����B�R����ԓx���Ƃ肦���Ƃ������Ƃ��A����������x������Ȃ�A�ނ��낻�������l�B�́A���j�ӎ����Ȃ���������A�g���X�g�C�◝�z��`�ň���āA�Ȃ܂��q�Ϗ�Ƃ����j�I�����Ƃ�����ɂ��Ȃ��������炾�c[�Q�V]
�@���̂悤�ɁA�펞���ɑ��鉽�炩�̔��Ȃ�����̔O�����L�����A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ƁA���Ⴂ�N������Ƃ̎v�z�I�Η��A���邢�͂��Ⴂ����́u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ւ̔����Ƃ������G�ȗv�f���܂݂Ȃ���A�w���E�x�y�ѕ��a���k�b��̓X�^�[�g��邱�ƂɂȂ�B���̓_�͉��߂ďq�ׂ邪�A������ƐV����Ƃ̑Η��W�Ƃ����̂͐��v�z�j�̌����ɂ����Ă���r�I�悭���y�����_�ł���B[�Q�W]�@�@�@
�����ł��邩��A�g��̈Ӑ}�Ƃ��Ắu�ꗬ�̖��҂ɂ��ꗬ�̎ŋ����A�v���Ԃ��2�{�̊ϋq�ɂ݂���悤�ȋC���ł������B�����āA�₪�āA�������̂Ɩ��҂���ցv���Ă����Ƃ������̂������B[�Q�X]�����ɂ��A�I�[���h�E���x�����X�g������Ⴂ����ւƃo�g���^�b�`���Ă����Ƃ����܈ӂ��F�߂���B
�������āA1945�N��12���w���E�x�͑n�����ꂽ�B�w���E�x�̐V���ȑD�o�͏����ŁA�����������āA�����܂��ɔ���ꂽ�B[�R�O]�u���{�^���̏G�˂̂悤�ȎG���v�Ƃ��u�ێ�}���h�v�Ƃ������]���ł������B[�R�P]�����̎��M�w���l������A�����������ێ�I�ł���Ƃ����]��������Ӗ��ł͓��R�̋A���ł������B
�P�|�R�D�@���a���k�b��̍\�z�ƌ���
���̐߂ł́A�w���E�x���n������A1948�N�̂V���P�W���Ƀ��l�X�R���甭�\���ꂽ�Z�J�����l�̎Љ�Ȋw�҂ɂ���ďo���ꂽ�����u���l�X�R���\���Љ�Ȋw�҂̐����v�ɋg�삪�G������A���a���k�b���g�D����Ɏ������o�܂�������B
�@�g�삪���l�X�R���甭�\���ꂽ���l�̎Љ�Ȋw�҂ɂ�鐺������ɓ���邱�Ƃ��ł����̂́A���͋��R�ł������B���Ƃ��ƁA���̃��l�X�R�̐����́A���l�X�R�̑���ŁA�푈�̌����̈�Ƃ��đ��ݓI�ȍ��ۗ����������Ă���Ƃ������ӎ��̂��ƂɁA�푈�������N�����ٔ��̌������������邱�Ƃ����c���ꂽ���Ƃ�[���Ƃ��ē��c�E���\���ꂽ���̂ł������B���̐����͑O�q�̒ʂ�A�Z���������̎Љ�Ȋw�҂ɂ���č쐬���ꂽ���̂ł��邪�A���̐������쐬���������o�[�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@
�@�@�E�S�[�h���EW�E�I�[���|���g�@�@�n�[���@�[�h��w�S���w����
�@�@�E�W���x���g�E�t���C���@�@�@�@�@�u���W���A�o�q�A��w�Љ�w�������A�A���[���`���A�u�G�m�X�A�C���X��w�Љ�w����������
�@�@�E�W�����W���E�M�������B�b�`�@�@�X�g���X�u�[����w�Љ�w�����A�p���Љ�w����������
�@�@�E�}�N�X�E�z���N�n�C�}�|�@�@�@�@�j���[���[�N�s�A�Љ��������
�@�@�E�A���l�E�i�G�X�@�@�@�@�@�@�@�@�I�X���[��w�A�N�w����
�@�@�E�W�����E���b�N�}���㔎�@�@�@�@�u�p����w�I�S���w�G���v�@�gBritish Journal
of Medical Psychology�h�劲
�E
�n���[�E�X�^�b�N�E�T�����@���㔎�@���V���g�����_�a�w���w�Z�]�c��c���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���_�a�w���v�劲
�@�E�A���L�T���_�[�E�\���C�@�@�u�^�y�X�g��w�Љ�w�����A�n���K���[�O���茤������
�Ȃ��A���̐����ɋg�삪�G������āA���a���k�b��̌����Ɏ������̂��B�������m
�F���Ă������Ƃ́A�����̍��ۏ��m�I�𗝉������ł���ȓ_�ł���B�܂�A�Ȍ��ɏq�ׂ�g������́A���̐����ɗB��u���v���̍�����Q�����Ă���A���L�T���_�[�E�\���C�̑��݂ɒ��ڂ����̂��B��㒼��̂P9�S6�N�ɁA�p���̎`���[�`�����u�S�̃J�[�e���v�������s���A���̓�N��ɂ̓x�������������s����B�u���v���u�M��v�̈����O�̏�Ԃɂ܂Ői��ł����̂ł���B�Ⴆ�A�w���E�x��1948�N4�����̑O�����ŋg��͂��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�R�Q]
�E�E�E1945�N���{�̍~���̒���ɁA�u�����̐��U�ɍĂё�킪����Ǝv�����B��
��������ɑ��A�u����Ǝv���v�Ɠ������A�����J�s����100�l��38�l�ł�������
�ɁA���̌�킸����N�œ��������́A�ă\�����̋��͂��\�ƐM����҂���l����
���A�E�E�E65�p�[�Z���g�ɒB���鑽�����u����25�N�̂����ɃA�����J�͍Ăѐ푈��
�������܂��ł��낤�B�v�ƐM���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����E�E�E
�܂�A���̓����ł�����킩��M��ւƂ������ɑ��āA���Ȃ�ٔ�����������
�����Ƃ������Ƃ�������B�@
�܂�����ŁA���{�����̒m�I�ɖڂ��ڂ��A���̓����u���a�v�Ƃ������t�͂��
���������������Ă����B���̓����A�����Ɍ����Ắu���a�v�Ƃ������ɑ��ẮA�Ƃ�킯���Y��`�҂�}���N�X��`�͗�W�ł������B�Ȃ��Ȃ�A�ނ�ɂƂ��Ắu���a�v�́u�����`�v���v�ƕs���̖��ł���A�u���a�v�̖�肻�ꎩ�̂�Ɨ������čl����Ƃ��������A�܂��́u�����`�v���v���������A���̏�Łu���a�v�͒B�������Ƃ����l�����ł������B
����ɉ����A�����̓��{���Y�}�͓��c�����u��`�Y��u������]�������v�𒆐S��
���Ȍ��Ђ�ێ����Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�ێR�̌��t�����A�u�����A�m�I�ɖ��ɂȂ��Ă����̂̓}���N�X��`�ł���A�}���N�X��`�ɂ�����v���̖��ł������B�v[�R�R]�Ƃ��q�ׂĂ��邵�A����Ɂu�����`�v�Ƃ������Ƃ̊܈ӂɂ��Ắu�����ł͍l�����Ȃ��قǁc���Y�}���������悤�Ȃ��̂��܂悤�Ȗ��剻�v�ł������Ɖ�z���Ă���B[�R�S]�����̋��Y�}�͖����`�v���̌�Љ��`�v���ւƎ���Ƃ����A�������i�K�v�������f���Ă����B����䂦�A�u�푈�ƕ��a�̖��Ƃ������̂́A�Љ��`�v���̑O��Ƃ��Ă̖����`�v���̖��̂Ȃ��ɕ�܂���Ă��܂��v�Ƃ������̂������B[�R�T]
�ȏ�̂悤�ȏ�w�i�Ƃ��āA�g��̓��l�X�R�̐�������ɓ���邱�ƂɂȂ�B��
�̉������́A�C�O�Ŕ��s�����o�ŕ������R�Ɏ�ɓ���邱�Ƃ��o���Ȃ���Ԃ������BGHQ��CIE�i���ԏ��ǁj�̏o�ʼnۂ���z������镨����ɓ���邱�Ƃ��o������x�ł������B�����ł��邩��A�g�삪CIE��ʂ��ă��l�X�R���������o�����̂́A�����R�ł��������A�g�쎩�g�̖��ӎ��Ƃ��ẮA���̐����ɐG�����ꂽ�Ƃ����_�Ō����ΕK�R�ł������B�g��́A�O�q�̍��ۓI�y�э����I�ɉ����āA���Q�O�̋A���O��ɂ�����A�ЁE���������̎��s�̘A���ɗ��_���Ă����B[�R�U]���̓������ւ̊��҂͑��������A���ꂾ���ɗ��_���������̂��������B1967�N�̕��͂ɂ����āA�u���͂��܂ł��A�u���̂Ƃ��A��������⎁��R�쎁�̒����悤�ȓ��������Ă��āA���l���N���납��͂͂�����Əo�ė�����̐���̉E�]��ȑO�ɓ��{�̐�����S�����Ă�����c�v�ƍl���邱�Ƃ�����v�Əq�ׂĂ���قǂł���B[�R�V]�Ȃ̂ŁA�w���E�x1947�N7�����Ɍf�ڂ��ꂽ�AJ�E�n�b�N�X���[�u���l�X�R�A���̖ړI�ƓN�w�v�ɑ���܂������ŁA�u�L�ĂȖ���I��������K�v�Ƃ��Ă���킪���̒m���l�ɂƂ��āv�A�n�b�N�X���[�̘_���͎����ɕx�ނ��̂ƍ����]���Ă���B[�R�W]
�����炱���A���Y������\���C�����l�X�R�����ɎQ�������Ƃ��������́A�g��╽�a
���k�b��̃����o�[�ɔ��ȗE�C��^�����B���{�̊w�҂��푈�y�ѕ��a�̖��Ɋւ��ċ������Č�������Ƃ����u�K�v���v�́A�g�����Ȃǂɂ��c�_�̗]�n�̂Ȃ����̂ł������B���A���ꂪ�u�\�v���Ƃ������͕ʖ��ł��邱�Ƃ��܂��A�c�_�̗]�n�̂Ȃ����Ƃł������B�������A�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�\���C�̑��݂͂��́u�\���v�ɑ���g�삽���̕s������|������̉e�����������̂��B�g�삩��A���l�X�R����������������́A�u�\���C�̖����������̍���̈ꕔ���������Ă����悤�Ɏv��ꂽ�B�v[�R�X]�Ɖ�z���Ă���B�����͂܂��A�u���l�X�R�̕����̉��l�́A�\���C�Ƃ�����l�̐l���Ɏς߂��ė����悤�Ɏv�����B�p���ʼn\�Ȃ��Ƃ́A�����ł��\�ł͂Ȃ��̂��B�v�Əq�ׂĂ���B[�S�O]
����ŁA1948�N�̂X���Ƀ��l�X�R��������肵���g��́A�����͊w�҂����̉��
���łȂ��A���}�l�����܂߂��g�D���\�z���Ă����B���a���k�b��̎����̑g�D�҂́A�g�����A�ɉ����A���{�\���������q�A�m�ȖF�Y�A���s�ł͋v�����ł��������A���{�̂Ƃ���ɋg�삪���k�ɍs���O�ɁA����M�O�̂��Ƃ�K��Ă����B
�����́A�u�ێ�h�̐l�X�ƍł����f�B�J���ȗ���̍����̐l�X�Ƃ̊ԂŘb�������Ă�
��v�g�D���\�z���Ă����B[�S�P]�����ċg��͖��Q�O��̐��}�l�̎Q���𑣂����߂ɁA���̑�w����̎t�ł��鏬��̂��Ƃ�K�ꂽ�B�������A����̕ԓ��͏��ɓI�Ȃ��̂������B�u���Y�}�����ł͂Ȃ��A���悻���}�̐ӔC�҂��o�Ă����Ƃ��ɁA�l�I�Ȍ������Ȃ��q�ׂ邱�Ƃ͖]�݂��������Ƃ��E�E�E���}���甭�\����Ă�������̌����ȏ�̂��Ƃ͏q�ׂȂ��悤�ɂȂ��Ă��邩�疳�Ӗ����낤�v�Ƃ����̂��A����̕ԓ��ł������B
���݂Ȃ��c�_���o���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��ƍl�����g��́A�w�҂����̑g�D�ɂ��邱�Ƃ�
���肵���B�����ŁA���{�A�m�ȁA����̌Ăт����ŕ��a���k�b��g�D����邱�ƂɂȂ�B��������A���{��a�҂炩��A�ێR��s���Ȃǂ̐���I�ɕ��̍L�����̂��g��͍\�z���Ă����B�����ɂ��A�u�������̂Ɩ��҂Ƃ���ւ��Ă����āA�E�E�E���̃o�g���^�b�`�̒��ɐ��̎v�z�̖{�����L�^���Ă����v�Ƃ����g��̈Ӑ}�����݂����̂ł���B�@�@�@�@�@
�܂�����Ӗ��ł́A��g�́u�����Ƒ�O�����т���v���̂ł͂Ȃ��A�u�����ꂽ�w
�҂�v�z�Ƃ���O�̉^���ɂ���������S�ɂ����A��O�ɂ�����Ăł����̖��Ɗi������悤�ɂȂ邱�Ɓv�Ƃ����g��́w���E�x�������̎v������������悤�Ƃ��Ă����Ƃ������邾�낤�B�O�q�̒ʂ�A���{�Ƌg��Ƃł́u�v�z�ƍs���v�̓_���傫���قȂ�Ƃ����_�͊m�F�����B�������Ȃ���A���{�����k��ɎQ�������̂́A�g��̔M�S�Ȋ��U�ƁA���{���ĂьR����`�Ɋׂ邱�Ƃ̕s�\�s��������Ɋ����Ă�������ł������B[�S�Q]���{�̉�z�ɂ��A�g��╽�k��̃����o�[�̎v�z�I�ȍ��Ƃ������̂��������Ă����ɂ�������炸�A���k��ɎQ������\���߂����@�͏�L�̂��̂ł������B
�O�q�̒ʂ�A�g�삪���l�X�R��������肵���̂́A1948�N��9���i���k��ɂ����
�́A8���Ƃ��q�ׂĂ���j�ł���A���̌�m���l�̐��ʂɁA�@����������A�o�ϕ���A���ȕ�������Ƌ��s�ł��ꂼ��g�D����Ă����B10������11���ɂ����Ă̂��Ƃł���B���Ȃ݂ɁA�m�Ȃ̌Ăт����œ��������ɁA���R�Ȋw������ݗ�����Ă���B�e����P�ʂŁA���l�X�R�����ɉ����邩�����ŕ��Ȃ���A���̕����Ƃ�1948�N��12��12���A�����̖����L�O�قő���J�����B�����ŁA���l�X�R�����������āA���{�̎Љ�Ȋw�ҋy�ю��R�Ȋw�҂ɂ���āu�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�����肳��A1949�N�́w���E�x�O�����Ɍf�ڂ���邱�ƂɂȂ�B
��q���邪�A���̒i�K�ł͕��a���k�b��͈�w�҃O���[�v�ł���A�w���c�̂ɂƂǂ܂��Ă����B�Q���҂̑唼���w�҂ł��邱�Ƃ�����e�Ղɗ����͂ł���B���ہA�ێR�͌�N�ɂȂ��ĕ��k����u�ŏ��̓A�N�`���A���Ȏ������������̂ł͂Ȃ��āA�Ƃɂ�������Ɛ푈���������ꂽ����A���a�����Ȋw�I�ɍl���悤�v�Ƃ����_����n�܂����Əq�ׂĂ���B[�S�R]
�������A�C�[���Y���m������b�h�p�[�W�E���N�푈�̖u���Ƃ������������o�钆�ŁA���a���k�b��́u�����v�ɑ�����Ɍ��������������o���Ă����B���̂��߁A����ڂ̐����ȍ~�A�����܂Ŋw���c�̂Ƃ����X�^���X�����Ȃ�����A�����㐭���I�Ȗ��ɃR�~�b�g���Ă������ƂɂȂ�̂ł���B�t�Ɍ����A���k��������͊�{�I�ȃX�^���X�Ƃ��Ĉꌤ���c�̂Ƃ����F�������邩��A�����o�[���݂̍��������Ă��Ȃ�Ƃ����������Ă������Ƃ͉\�������ł��낤�B
���ՂȐ����͂ł��Ȃ����A���b�h�E�p�[�W�⒩�N�푈�Ƃ����������̋}���ȕω����Ȃ���Ε��k��͈ꌤ���c�̂Ƃ��Ă̊����ɏI�n�����Ƃ����\�����l������B�������A���k����ꌤ���c�̂ɗ��߂��A�����I�ȃR�~�b�g��������Ȃ����ɍ�����̕ω��͋}���ł������Ƃ�������B���ہA�ێR���u����Ȃɑ����������ς��Ƃ͎v��Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B[�S�S]
�P�|�S�D�g��̐��
�@���̂悤�ɁA�w���E�x��u���a���k�b��v�͋g��Ƃ̊ւ��̒��Ō�������邱�ƂƂȂ�B�g�쎩�g�͕ҏW�҂̎d���ɐ�S���Ă������߁A�߂��������슈�������Ă���킯�ł͂Ȃ����A�w���E�x�̑n����u���a���k�b��v�̌����̎����ɂǂ̂悤�Ȕ��������Ă����̂��Ƃ������Ƃ��m�F���邱�Ƃ͏d�v�ł���B
�g��͑O�q�����悤�ȁu�����ɑ�����ӎ��v��u���j�N�w�v�ɑ���S�A����
�ċ��������ł������Ƃ����_���ӑR��̂ƂȂ�����}���邱�ƂɂȂ�B���̐�
�ł́A���̋g��̎v�z�������邱�ƂƂ���B���_���猾���A�O�q�����v�z�I��
�Ղɉ����A���̋g��̊����̃o�l�ƂȂ��Ă������̂́A�u�����v�̖��Ɓu�s���
�L���v�ł������B�g��́A�O�q�����w�N�����͂ǂ������邩�x�̒��ŁA�ȉ��̂悤��
��������B
�E�E�E�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B
�@�@�@�@�@���������Ƃ����Ƃ�����B
�@�@�@�@�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B
�@�@�@�@�@������A��肩�痧�����邱�Ƃ��ł���̂��E�E�E[�S�T]�@
�@�����ł́A�u�����Ŏ��������肷��́v�������䂦�ɁA�u�����v���o�l�Ƃ��āu��肩�痧�����邱�Ɓv���\�ł���Ƃ����Ӗ����ǂݎ���B���̕��͎��̂͐풆�ɏ����ꂽ���̂ł͂�����̂́A���ɂ����Ă��A���̊�{�I�Ȕ��z�`�Ԃɑ傫�ȕω��͌����Ȃ��B�����A�u�����Ŏ��������肷��́v���u�Ɨ��v��u���含�v�Ƃ������t�ɒu�������Ă��邱�Ƃ͌������Ȃ��B�܂��O�q�����悤�ɁA�u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v���s���̃o�l�ɂ��Ă���_���A���̔����̒��ŎU���������̂ł���B
�@�g��̎v�z���������ŁA�u���含�v��u�ߋ��ւ̔��ȁv�Ƃ������t���U������邪�A�O�q�����Ƃ���풆�Ɛ��ł̎v�z�I�f��͖��m�ɂ͔F���ł��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�s�펞��46�ł���A��O�̒i�K�ň��̎v�z�`���𐬂������Ă���_���傫���ł��낤�B�܂��A�s��̔N��4���̎��_�ŁA���{�̔s���\�����A���ւ̏��������Ă��邱�Ƃ�����A��L�̎����͖T�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�O�߂ŁA�g��̕��a���k�b��\�z�̌o�܂����グ�����A���Ƃ��Ɓu���������v�ł���A���͊v���I�ȘJ�g�A���ł���Y�ʏ����̈���o�ŘJ�g�̏��L�ǎ�C��S�����Ă����B���R�̂��ƂȂ���A��㏉���ɂ����ẮA�u���ꂩ��̓��{�̐^�̎�̂ƂȂ�ׂ���O�v�Ƃ�������������킩��Ƃ���A��O�ւ̊��҂������ێ����Ă����B[�S�U]
�@�������Ȃ���A�����������u��O�ւ̊��ҁv�������������A���a���k�b���g�D�����ł́A��ҏW�҂��邢�͑g�D�҂Ƃ��Ĕ��ɍI���Ȑl�I�����Ă��邱�Ƃ����ڂɒl����B
�@������O�߂Ō������Ƃ����A���a���k�b����Ɏ���܂ł̋g��́A���Q�O�A����́A�������̎��s����ɗJ�����Ă����B��N�̉�z�ł́A�����̋��Y�}�ƍ����}�Ƃ̓������ɓ��{���s�ꂽ�Ƃ������ƂɐG��Ȃ���A�u���{�̔s���ɂ͂����������s�Ɛ����̌o������������v�邱�Ƃ͂Ȃ��A�������畜�A�������̋��Y�}�n�̐l�X�̎w���́A�u����ȑO�̐�p�v�ł���A����䂦�u�l������̓������͂����ƒ���Ȃ�������߁v�ł������Ƃ����B[�S�V]
�@�����������J���̒��ŁA�������̂悤�ȍ\�z��͍����Ă����g��Ɏ�����^�������̂́A�R�~���t�H�����́u�P�v���a�Ɛl�������`�v�Ƃ����@�֎��ł������B���̋@�֎��Ɍf�ڂ���Ă���_���̒��ł́A�u���Ăڂ��������Ⴍ�ĕ����Ă���܂�������́A�����Ƃ��ᔻ���ꂽ�悤�ȁu�l�ނ̖��ɂ����āv�Ƃ��A�����������t�v���U������Ă����B[�S�W]
�@�����āA�����������v�z�X�����A�l�I�̒i�K�ɂ����ẮA�I�[���h�E���x�����X�g�̓c���k���Y����{�\���ɂ͓`�����A�t�Ɏ��H�I�ȉ^���_�Ƃ����_�ɂ����ċg��Ƌ߂��ʒu�ɂ���v����ɂ́A���x�ɂ킽��b�������Ƃ����B[�S�X]���̓����̋v��͂܂��A���H�I�Ȏu���̋��������̐����Ɛe�����ԕ��ɂ��������Ƃ��t�������Ă������B����ɁA���H�I�ȉ^���_�I�u����ێ����Ȃ��ێR���j�́A�u�����܂ł̋g�삳��̒�ӂ͎c�O�Ȃ���ǂ߂Ȃ������v�Ɖ�z���Ă���B[�T�O]
�@�ȏ�̎��ɂ��킦�A���a���k�b��ɐ����Ƃ�������ׂ����ۂ��c���Ă����g�̖������ɂ́A���̓����̏o�ŘJ�g�̏��L���ł���������Y�����Ȃ��Ă����B[�T�P]
�@��������킩�邱�Ƃ́A�u��O�ւ̊��ҁv�����������Ȃ�����A���a���k�b���g�D����ɂ������āA�g��Ɖ^���_�ɂ����ċ�����v��ƁA�����ł͂Ȃ��c������{�A�ێR�Ƃɑ���ڂ����̔����ł͂��邩�I���Ȍ���I�Ⴂ�ł���B�����āA��������o�ŘJ�g�̈��������a���k�b��̍\�z���̉�c�ɓ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����킩��Ƃ���A�g��̒��ł͕��a���k�b��ƘJ���g���Ƃ̘A�g��͍����邱�Ƃ́A�K��̘H���ł������Ƃ������Ƃł���B����Ӗ��Ō����A�g��̂��������Ή��́A��ɕ��a���k�b��ɎQ�������m���l�̒��ŕ��ڗ����Ă������Ƃ�\�����Ă��邩�̂悤�Ȃ��̂ł���B�{�_���́A���̕���ߒ�����������̂ł��邪�A������㉟�����錈��I�Ȍ_�@�̎w�E�ȏ�ɁA�������番��̖G�肪�����Ă����Ƃ����w�E�̕������K�ł��낤�B
�@���Ɂw���E�x�̂��Ƃ��������番����A�g��̎v�z�Ƃ��Č����ȌX���́A���x�Ɩ����u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v��\�����Ă��邱�Ƃł���B�Ⴆ�A1950�N4�����́w���E�x�����u�ǎ҂֑i���v�̒��ŁA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B[�T�Q]
�@�E�E�E���Ă����̑����́A���{�����F�ɐN�o���A������N���A�����m�푈�ɓ˓����Ă䂭�̂��A��͂�R���������吨�Ƃ��Č��߂����Ȃ������낤���B�����͍Ăт��̑傫�ȉߎ���Ƃ������Ȃ��B�����́A�ނ���푈�ƕ��a�Ƃɑ�������̂��̎������A�f�p�ɐM���悤�ł͂Ȃ����B�����āA���̎����̏�ɗ����āA����ꂪ�ɓx�ɂ݂��߂ȏ�Ԃ̒�����Q���ɂ��Ēz���グ�ė������̂��Ăѐ�̒��ɓ����邩���m��Ȃ���̊댯�ɑ��A��_�ɖ₢�����悤�ł͂Ȃ����\�u���̂����̂��߂��v�ƁB���悻�A����ꎩ�g�����ɑi���ď����ł��邱�Ƃ������������A�����ɑi���Ĕ[���ł��Ȃ������ɑ��Ă͗����ɍR�c���邱�ƁE�E�E���܂����A���̎���I�Ȑ��_���ӂ邢�N�����A���đS�����̉^���ɂ��������̌�����A�������\�̐����Ƃ△�v���̌R�l�̎�ɂ䂾�˂Ă��܂������̉߂����A��x�Ƃӂ����ьJ�肩�����Ȃ��悤�ɂ��悤�ł͂Ȃ����E�E�E
�@�����ł́A�u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v�Ƃ���������ƁA������v�z�̃o�l�Ƃ��āu�����ɑi���Ĕ[���ł��Ȃ������ɑ��Ă͗����ɍR�c����v�u����I�Ȑ��_�v�������ɕ\������Ă���B���v�z�ɂ����āA�u��̐��v���L�[���[�h�ɂȂ邱�Ƃ͓x�X���y����邱�Ƃł���B�g��̎v�z�����̗�ɘR��邱�Ƃ͂Ȃ��ƌ����Ă悢���낤�B
�@�����āA�u���������G���̕ҏW�ɂ���������āA�������S�ɖ����Ă�����̂́A���̉ߋ��̌o���ł���v�Ƃ����悤�ɁA�ߋ��̌o�������̍s���̃o�l�ɂȂ��Ă���Ƃ��������ł͂Ȃ��B�����������ߋ��̌o�����o�l�ɂ���Ƃ��������́A�u�a�_�����������Ȃ�ɂ�ĉ��x�����y����邱�ƂɂȂ�B
�@����ɁA�����������u�����v��u�ߋ��ւ̔��ȁv�����ǂ���Ƃ��āA�u�a�_��������オ�钆�ŁA�u�����Ŏ��������肷��́v���u���含�v��u�Ɨ��v�ƌ������t�ɓ]�����A�i�V���i���Y����\�����Ă����ʂ��������Ă����B
�@�g��ɂ��A���̐��N�Ԃ��A�u���������̎���I�Ȏ��ƂƂ��Ă̂݉�ڂł��Ȃ����Ƃ��A���������{�l�ɂƂ��Ă͉������h�����Ƃł͂Ȃ����낤���v�Əq�ׁA�������Ȃ���A�u�^�ʖڂȐN�v��u�����̎����ȁA���������ΘJ�ҁv�̓����̎v�z�Ɋ��҂�������ƂƂ��ɁA�����������u���ݓI�ȃG�l���M�[������ȏ�A���������{�l�͂��������̎��含�����߂��ł��낤�v[�T�R]���邢�́A�u���Ȃ̉^���ɂ�����鎖�������A���Ȃ̔��f�ƌ��ӂƂɂ���Ă���ɑΏ����邱�ƁA����������Ăǂ��ɂ����́A�����̋��痧�������鑫��������Ƃ��ł��悤�B���̂悤�ȋC���������āA�ǂ��ɂ������{�l�̓Ɨ������蓾�悤�B�v�Əq�ׂĂ���B[�T�S]
�@�u�����������{�������A�����������A�����Ǝ��ȂƂ̎��含�������܂��v[�T�T]�Ƃ�������������킩��Ƃ���A���邢�́u�������ЂƂ�ЂƂ�̐l�ԂɂƂ��Ă��A�S�̂Ƃ��Ă̖����ɂƂ��Ă��A���ׂē��{�l�ɂƂ��ẮA�����̖�肪�݂�Ȃ��̏\�N�O�̔����\�ܓ��ɂȂ����Ă���v[�T�U]�Ƃ��锭��������킩��Ƃ���A�g��ɂƂ��ẮA�u���含�v��Nj����邱�Ƃ��i�V���i���Y���ւƌq�����Ă�����H�ł������B�u�N�����͂ǂ������邩�v�Ƃ������t�́A�s�풼��̋g��ɂƂ��ăi�V���i���Y���ւƐڑ����錾�t�ł������ɈႢ�Ȃ��B�ҏW�҂Ƃ��Ă̋g�쎩�g���u�ǂ������邩�v�Ƃ�����肪�A�s�퍑���邢�͓����l�����Ƃ��Ă�Ă����u���{�v��u���{�����v���u�ǂ������邩�v�Ƃ������Əd�����Ă����Ƃ����悤�ɏq�ׂ邱�Ƃ��ł���B
�@���a���k�b��̈�g�D�҂Ƃ��āA���{���u�ǂ������邩�v��͍����������g��ɂƂ��āA�u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v����ՂƂ����u���含�v�u�Ɨ��v�Ƃ����o�H�͈�̕s���̂��̂��������낤�B�������̎��s��J�����A�C�f�I���M�[�Ԃ̕ǂ����z���āu���a�v��͍����鎎�݂��Ȃ����g��ł��������A����ɂ͈ȏ�̂悤�Ȏv�z�����݂��Ă����B���߂Č����܂ł��Ȃ��A���̋g��́w�N�����͂ǂ������邩�x�ŏ��N�����ɓ����������₢�����g�ɓ��e���邩�����ŁA�����̋O�Ղ�`���Ă������B�I�n�A���a�̖��A���H�^���ɍS�葱�����g�삾���A���̈ӎ��̒��ɂ́u�l�����͎����Ŏ��������肷��͂������Ă���B�������肩�痧�����邱�Ƃ��ł���̂��v�Ƃ������t�������Ă������Ƃł��낤�B
�Q�D���m���l�ƕ��a���k�b��
�Q�|�P�D�ێR���j�̎v�z
�@�Q�|�P�|�P�D�u�����v�Ɓu��̐��v
�ێR���j��������ɂ����ĕ��k��Ɋւ��ďq�ׂĂ�����̂͌����đ����͂Ȃ��B��N�ɂȂ��Ă���̉�z�̗ނ͏��Ȃ��炸���݂���B�{�͂ł́A������̊ێR�̒������k��Ȃǂ���ՓI�Ɍ��āA�ێR�̎v�z���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���A���ꂪ���k��Ƃǂ̂悤�Ȋ֘A�������o���邩�Ƃ����_���猟���Ă������Ƃɂ���B
�܂��́A1950�N�����u���a�̖��ƕ��w�v�ɂ�����ێR�̔��������Ă����B
�c�����A�ڂ��͕��a���k�b��ɂ͊֗^���Ă��邩��A���ٌ�ɂȂ�킯�ł����A��̂��Ƃ�\���グ�����B�܂��́A�ǂ��������������Ƃ����l���肢�����B�Ƃ����̂́A�����������Ƃ����ƁA�����A���������������Ă����悤���Ȃ�����Ȃ����A�����I�ɂ͉���͂̂Ȃ��������o���Ă����C�ɂȂ��Ă��邾�����A���������}�Ƃ������A�P�Ȃ�V�j�J���Ț}�������A��ʂ̐V���A�Ƃ��ɔ����I�ȑ�������ɗ��т����܂��B�Ƃ��낪�A��Ȃ��ƂɁA�ꕔ�̍����̐l���A�Ӑ}�͔��ł���Ȃ���S���������t�Ŕ��𗁂т���̂ł��B���{�l�Ƃ������̂͑�́A����Ȃ��Ƃ͂����̗��z�Ō����I����Ȃ��Ƃ����悤�Ȍ��������D���ł��B���̏ꍇ�̌����Ƃ����̂͗^����ꂽ���̂��ƂȂ�ł��ˁB�ŁA�����I�����I�Ƃ������Ƃɂ���āA���������ɂǂ�ǂ�������Ă��܂��B�������邾���Ȃ�܂��悢����ǂ��A�܂����������ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ܂ŁA�݂�����i��Ŋ��������ɂ��Ă��܂��Ă�����߂Ă��܂��B�c�ނ��뗝�z�Ƃ��C�f�[�̗͂������Ƃ����Ƌ������ׂ��Ȃ�Ȃ����B���ꂪ�A����ꍇ�ɂ͐������Ӗ��ł����Ƃ������I�Ȍ��ʂ����Ƃ������Ƃ����Ă���B�P�Ɍ����I����Ȃ��Ƃ����Đ����Ԃ������邱�Ƃ��A�͂����āA�{���ɕ��a�^�������͂ɐ��i���čs����ɗL�����ǂ����B�l�͋^���̂ł��B�c������̓_�́A�w�҂̗��ꂩ��v������Ƃ������Ƃ́A�����w�҂̖������ߑ�]������Ƃ������Ƃł͑S�R�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�c���̏ꍇ�ɑg�D�J���҂Ƃ̌��т��Ƃ������Ƃ́A�N�����ł��Ȃ��悤�ȓ��R�̂��Ƃł����A�����������Ƃ��ς��Ǝ����Ă��āA�����ɂ�������H���悤�Ƃ���ƁA�l�͌��݂̒i�K�ł͑啔���̒m���l�́A�����Ɍ����ė����Ǝv���܂�[�T�V]
���̈��p�͓����̊ێR�̎v�z��T���ŋ����[���B�����ŊێR���������Ă��邱�Ƃ́A�u�����v���邢�́u�����F���v�ɑ���l�������ł���B�ʏ팾����u�����v���邢�́u�����I�v�Ƃ������̂́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�ォ��u�^����ꂽ�v�u���^�v�́u���v��u�����v���Ӗ����A���̌��ʁu�S�̓I�����ւ̐ӔC�Ȃ��ˑ��v�Ƃ����ԓx�ݏo���B[�T�W]���̑ԓx���o�����Ă���ƁA�u���������v�ɋ������邱�Ƃ��u�����I�ȔF���v���Ƃ����A���ɂȂ�A���邢�́u�����ւ̓����v�����܂�u���ӔC�̑̌n�v���`�������B[�T�X]
�ł͊ێR�����z�Ƃ���u�����v�ւ̐ڂ����͂����Ȃ���̂��B����͂܂�u�����v�Ƃ́u���ɑn��ꂽ�v���̂ł��锽�ʁA�u�V���ɍ��o�����v�ʂ�����B�[�I�Ɍ����A�u�����v�Ƃ́u�����ւ̎�̓I�`���v�Ƃ��đ�����ׂ��Ƃ����A������u��̐��v�̒ƕs���̊W�ɂ���B[�U�O]
���̎v�z�͔s�풼�ォ��ێR���ł������������̈�ł���B�Ⴆ�A�u�����Ǝ�`�̘_���ƐS���v��u�R���x�z�҂̐��_�`�ԁv�E�u�u�����v��`�̊��v�v�Ȃǖ����ɉɂ��Ȃ��B����Ɍ����A�s�풼��Ƃ����͕̂s���m��1943�N�́u����ɉ����钁���Ɛl�ԁv�ł����l�̃e�[�[������Ă���A�ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B[�U�P]
�c������P�ɊO�I���^�Ƃ��Ď��l�Ԃ���A�����ɔ\���I�ɎQ�^����l�Ԃւ̓]���͌l�̎�̓I���R���_�@�Ƃ��Ă̂ݐ��A�����B�u�Ɨ������v���Ȃɂ��l�I���含���Ӗ�����͓̂��R�ł���B���䂪���̓`���I�ȍ����ӎ��ɉ����ĂȂɂ�茇���Ă���ƌ����͎̂���I�l�i�̐��_�ł������B�c�����銯�����ځA�܂���l�����ł̌��͂̉��Ɍ������Ắu�c���v�A��Ɍ������Ắu���k�v�B�c�����������ۂ͂��Â������I�l�i�̐��_�̌��R���؎�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ������B�c���̈Ӗ��Łu�Ɨ������v�͌����ĂȂ܂Ȃ��Ɉ��ՂȂ��̂ł͂Ȃ��A�p���Ă����ɂ͗e�ՂȂ�ʏs�������܂܂�Ă���B���ՂƂ����A�S�̓I�����ւ̐ӔC�Ȃ��ˑ��̂ق����͂邩�Ɉ��ՂȂ̂ł���c
���v�z�ɂ����āA�u��̐��v�Ƃ����p��͊j�ƂȂ錾�t�ł���B��̓I�Ȍl���m�������ŁA���邢�͐�O�̑O�ߑ�I�ȁu���͋C�̎x�z�v�ɓۂ܂ꂽ�l�X��ᔻ�����ŁA�ێR���q�ׂ�u�����v�Ƃ������̎v�l�l���͌������Ȃ����̂ł������B��q���邪�A���̎v�z�͕��a���k�b��̎v�z�Ƃ��������Ȃ����̂ł������B
�܂��A�O�q�̍��k��ł́A���z��C�f�|���d�����A�������u��̓I�v�u�����I�v�Ɍ������邱�Ƃōł������I�Ȍ��ʂ����Əq�ׂĂ���B�܂�u���z��`�I�v�Ȏv�l���ł��u�����I�v�Ȍ��ʂɂȂ���\��������Ƃ������Ƃł���B�ׂ����悤�����A���̌��������s�풼�ォ��ێR�������Ă������Ƃł���B�Ⴆ�A�s�풼���1945�N11��4���̓��L�ɂ́u�C�f�A�[���Ȃ��̂����ł����A�[���ł���v�Ƃ�����������B[�U�Q]���̎v�z�����a���k�b��̎v�z�Ɩ������Ȃ����̂ł���B���Ƃ��A�ێR���j�����M������O��ڂ̐����u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̒��Łu�푈���ő�̈��Ƃ��A���a���ő�̉��l�ƍl���闝�z��`�I�ȗ���́A�푈�����q�͐푈�̒i�K�ɓ��B�������Ƃɂ���āA���������x�̌�����`�I�ȈӖ���тт�Ɏ������v�Əq�ׂ��Ă���B[�U�R]
�������x�ȃ��t�X�P�b�`�ł͂��邪�A�s�풼�ォ��ێR���q�ׂĂ����u��̐��v�Ɓu�����v�ւ̑ԓx�́A���a���k�b��Ƃ̊����Ƌ������������������ƌ����悤�B�O�q�����悤�ɕ��a���k�b��́A�W�҂̏،��𑍍�����Ɠ����́A�u�S�ʍu�a�E�����E�R����n���E�ČR�����v�Ƃ��������������ɃR�~�b�g����悤�ȃO���[�v�ł͂Ȃ������B�����܂ŁA�w��I�ɕ��a�����l����c�̂������̂ł���B
�������Ȃ���A��̌R�̕��j�]���ȍ~�A�C�[���Y���m������b�h�E�p�[�W�A���N�푈�Ƃ����������I���������X�ƋN����B�܂�A���a���k�b��̌����Ɍ������������킵�Ă����Ƃ������邾�낤�B�ێR�����ہu�����Ɍ����āA�S�ʍu�a��肠������_�@�ɂ��āA�R�~�b�g�����킯�ł���B�푈����̐����ɑ��āA�����A�߂Ɍ��Ă����l��������A�����ƐϋɓI�ɂƂ������A�c���������̓����̈�ɃR�~�b�g����悤�ɂȂ��Ă����v�Əq�ׂĂ���B[�U�S]
���������Ӗ��Ō����A�s�풼�ォ��u��̐��v��u���グ�錻���v�����ɕ����Ă����ێR���A���k���}��Ƃ��āA���邢�͕��k���ʂ��Ď��ۂ̐��������ɖ{�i�I�ɑΛ������ƍl������B
2�|1�|2�@�u�m���l�̘A�сv�Ɓu���O�v
�@���ɕ��a���k�b��Ƃ̊֘A�ɂ����āA���̓����ێR���p�ɂɏq�ׂĂ��邱�Ƃ̈�Ɂu�m���l�̘A�сv����������B�펞���ɗǐS�I�Ȓm���l���o���o���̏�Ԃɂ���A�܂Ƃ��ȘA�тƒ�R���o���Ȃ������Ƃ������Ƃ͂悭�w�E����邱�Ƃł���B
�@
�@�c�푈�ɔ����Đh���ڂɂ����������̒m���l�ł������A���������̂�������Ƃ͂����������ɓI�Ȓ�R�ł͂Ȃ����A�c��X�̍��ɂ͂قƂ�ǂ����ɑ��郌�W�X�^���X�̓����������������Ƃ��A�m���l�̎Љ�I�ӔC�̖��Ƃ��Ĕ��Ȃ��˂Ȃ�Ȃ��c[�U�T]
�@���̂悤�ɒm���l�Ƃ��Ă̐g�̏������ɑ���ɗ�Ȕ��Ȃ��L�ĂɍL���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�Ȓ�����A�s�풼��ɂ́A�u�m���l�Ƃ͂����ɂ���ׂ����v�Ƃ��u�w��Ɛ����v�Ȃǂ̃e�[�}�Ɋւ��钘�����k��}������B�����Ă܂��A�m���l�̖����Ƃ̊֘A�ŁA�u���O�v�ւ����ɑΛ����邩�Ƃ������Ƃ��傫�ȃe�[�}�ƂȂ�B����Ӗ��Ō����A�����������u�m���l�ρv��u�w��ρv�E�u���O�ρv�Ȃǂ́A�m���l�Ƃ��Đ풆�̐g�̏������̔��Ȃƕs���̊W�ł���B�ȉ��ł́A��܂��ł͂��邪�ێR�́u�m���l�ρv��u�w��ρv�E�u���O�ρv���T�ς��Ă����B�����܂ł��Ȃ��u�m���l�ρv�����āu�m���l�̘A�сv�Ƃ����e�[�}�́A���a���k�b��Ƃ����u�m���l�W�c�v�Ƃ���������e�[�}�ł���B�����āA�{�e�̓��e���ɏq�ׂ�A���ꂼ��̒m���l�ɂ���āu���O�v�ւ̌[�ւɓO����̂��A����Ƃ��w��̐��E�ɂ�������������Łu���O�v�Ƃ̂Ȃ�������߂�̂��Ƃ������u���O�ρv�̑�����A���a���k�b��̕���̌_�@�ƂȂ�̂ł���B
�@��N�A�ێR���j�͑�ˋv�Y��쓇����ƂƂ��Ɂu���[�֎v�z�̎O�H�K���X�v�I�ȑ�����������邱�Ƃ������B[�U�U]�������Ȃ���A�ێR�͔s�풼�ォ��u�m���l�̘A�сv������ƂƂ��ɁA�u�[�֊����v�ɑ��Ă͔ᔻ�I�ȃX�^���X���Ƃ��Ă����B�Ⴆ�A1947�N�P���w�����x�́u�V�w��_�v�Ƃ������k��̒��ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�c�܂�A�w�҂̎��H�Ƃ��A�w�҂ƃ}�b�Z�Ƃ̌��т����A�ϔO�I�ɂ͕����邪�A�ǂ̂悤�ɂ�����炢���̂��Ƃ������Ƃ������ɂ͂��낢��̖�肪����Ǝv���B����͊ȒP�Ɍ����ƁA���O�̖��Ƃ����̂́A�ނ����͂莩���̒��ɂ�����ʓI�ӎ��̖��ŁA�₽��ɖ��O���O�Ƃ�����肶��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�₽��ɕ��X�ɍu�����ĕ�������A�W���[�i���Y���ɏ������肷���ł͂Ȃ����āA�ł��{�i�I�Ȏd�������邱�ƁA���ꂪ�͂邩�ɖ��O�̂��߂ł���Ƃ������Ƃ��l������B��������{�̊w�E�̖��Ƃ��Ă͖{���̃A�J�f�~�Y���Ƃ������̂������Ă���̂ł͂Ȃ����B�c�w��̍s�����Ƃ��āA�ō������Ƃ����悤�Ȃ��̂́A��͂茻�����Ƃ��ĕ��ʂ̐��Y�J���ɒǂ��Ă��閯�O�ɂ́A�����ɍ������Ǝv���B���ꂩ�Ƃ����Ċw�҂��݂Ȍ[�֊����ɏo�Ă����Ă��܂�����{���Ɋ����͏o���Ȃ��B[�U�V]
�@���̔����͊ێR�́u�m���l�ρv�Ɓu�[�֊����v�ւ̔ᔻ�I�X�^���X���@���Ɍ���Ă���B
����A�ێR�ɂƂ��Ă̗��z�̒m���l�Ƃ́A�m���̓Ǝ��Ȏ����̉��l��F�߁A���O����Ɗw�₪�قȂ鎟���i���W�ł͂Ȃ��j�ɂ��邱�Ƃ��A�^���Ɂu���o�v���w��E�����ɓO����Ƃ������̂ł������B�����������m���l��l��l���A�풆�̂��Ƃ��o���o���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�A�т��Ă����Ƃ������ƁB�����āA���O�Ƃ̊W�Ō����A���ՂɌ[�֊����ɑ���̂ł͂Ȃ��A�����܂Ŋw��I�Ȏd���ɓO���邱�ƂŌ��ʓI�ɖ��O�ƂȂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł������B�t�Ɍ����A�w��ȊO�̂��̂ł��ʂ�����悤�Ȏd���Ɋw�₪�U���Ă��܂��̂́A�Љ�I�ȘQ��ł���Ƃ����B[�U�W]���̂悤�ȍl�����́A�s�풼�ォ�璘�����k��ŕp�ɂɏq�ׂ��Ă��邱�Ƃł���B�����āA���́u�[�֊����v�ւ̔ᔻ�I�ȃX�^���X�́A�����I�ɋg��Ƃ��ʒꂵ�Ă�����̂ł������B�g��̏ꍇ�A�u�[��
�����v���̂��̂ɑ���ᔻ�I�Ȕ����͌��o���Ȃ����A�I�[���h�E���x�����X�g�̌����u�������O�Ɍ��т���v�������ł́u�[�ցv�ɑ��Ă͔ᔻ�I�ł������B
�@����ŁA�ێR�́u�w��ρv���l�����ŋ����[���̂́A���̓����ɂ����āA�u�l�Ԃ��g�[�^���ɔc������v���Ƃ̑�����������Ă��邱�Ƃł���B���l�X�R�̔��l�̎Љ�Ȋw�҂ɂ�鐺���̒��Ɂu�l�Ԃ̊w�Ƃ��Ă̎Љ�Ȋw�v�Ƃ����������邪�A����ɑ��ĊێR�́u���X�̂悤�Ɋ��������v�Əq�ׂĂ���B[�U�X]
�@�ȏ�̂悤�Ȏv�z�ƕ��a���k�b��Ƃ̊W�������������̂ł͂Ȃ������B����Ӗ��ŁA�@
�ێR�͈ȏ�̂悤�Ȏv�z���A���H�Ɉڂ���Ƃ��ĕ��a���k�b��Ƃ̊ւ����������Ƃ�������B���Ƃ��A1948�N��12���ɍs��ꂽ���a���k�b��i�����͓��c��j�̑���ɂ����Ă��A�u�Љ�Ȋw�҂̃R�~���j�P�[�V�����v�Ƃ��u�Љ�Ȋw�҂̉��̒c���v���A�m���l�����O�ƌ�������ȑO�̏d�v�Ȗ��Ƃ��Ē�N���Ă���̂ł���B�܂��A���N�푈�u����́u�O���ѕ��a�ɂ��āv�ɂ����āA�ێR�͂�����u��̐��E�v�̐ϋɓI�����̉\����_�����B���A����͈���Ŕ�r�I���h�̃����o�[�������������s�̊w�҂ƁA�����̊w�҂Ƃ̘A�т������Ɉێ����Ă������Ƃ������Ƃ��q������̂ł������B�u��̐��E�v�̐ϋɓI�����݂̂Ȃ炸�A���k������ɂ�����v�z�I�ȑ���̐ϋɓI�������v��Ƃ������ӎ������ݎ���B�����ɊێR���u�m���l�̘A�сv��^���ɖ͍��������Ƃ������Ƃ̖����ł���B
�@�O�q�̒ʂ�A���a���k�b��̑g�D�ҋg������a�̖��ɑ���m���l�̘A�тƂ������Ƃ��\�z���Ă������A�����������ӎ����ێR�Ƌ��ʂ��Ă������Ƃ�������B�����āA�ێR���p�ɂɁu�m���l�̘A�сv��������w�i�ɂ́A�m���l�Ƃ��ẮA�w��Ɍg���҂Ƃ��Ă̐풆�̔��Ȉӎ������������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�u�m���l�Ƃ��Ă̔��ȁv���u�m���l�̘A�сv�ւ̋�����]�ƌ��т��ƂƂ��ɁA�����Ɂu�m���l�̖����̖͍��v�ւ̊�]�Ƃ����т����̂������B�s�풼��ɂ́u�w�ҁv�Ƃ��u�m���l�v�Ƃ������݂͂��܂��������Ă͂��Ȃ������B�������Ă��Ȃ����炱���A�m���l�̖����̖͍����^���ɍs����B
�@���̌��ʁA�u�m���l�Ƃ��Ă̔��ȁv���u���a�v�ւ̈ӎu�ƌ��т��B�m���l�Ƃ������͈̂�̉��ŎЉ�ɍv���ł���̂��Ƃ����ӎ��Ƃ���͕��a�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӎ����������邱�ƂŁA���a���k�b��ɂ�����m���l�̘A�шӎ����ۂ���Ă����Ƃ����Ă������낤�B[�V�O]
�@�����ČJ��Ԃ����A�u�m���l�Ƃ��Ă̖����v�ς̑��Ⴀ�邢�́u���O�ρv���A��X���a���k�b��̕���ɔ����ȉe�������^���邱�ƂɂȂ�B
�Q�|�P�|�R�D�I�[���h�E���x�����X�g�Ɛ���_�I���z
��قǂ��A�g��̗��ێR�̔����Ō����Ƃ���A���̎����̊ێR�̎v�z�̓����Ƃ��ċ�������̂͂�����u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ւ̔ᔻ�ł���B�O�q�̂悤�ɁA�I�[���h�E���x�����X�g�ƁA������Ⴂ����Ƃ̑Η��Ƃ��������̂͐��v�z�j�����̂Ȃ��ł́A��r�I�悭���グ������̂ł���B�����ł́A�ێR�����̓����A�I�[���h�E���x�����X�g�ɑ��Ăǂ̂悤�Ȏ����q�ׂĂ����̂��Ƃ����_���܂��m�F����B�������Ȃ���A�v�z�I�ɂ͕������Ă����Ƃ��Ă��A���ە��a���k�b��͐���I�E�v�z�I��������z����`�ň�v�����������o���Ă����B
�@�O�q�̂悤�ɁA�s�풼��ɕ���������O�́u�����l�v�����́A�u���`���Ɓv��u�������Ƙ_�v����Ă����B���Ƃ��A���{�\���́w���E�x�̑n�����ɂ����銪���_���ŁA���`�̍Č����Ƃ��Ă����B�����������ێ�_�d�̎v���ɑ��āA�ێR�́u�w����N�w�ɑ���シ�ׂ肵���u���`�v��u�����v�v�ƈʒu�Â��A�I�[���h�E���x�����X�g�ɑ��Ă͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�V�P]
�c�I���A���R���Ȃ����ɒ[�Ȃ鍑�Ǝ�`���͂̑ޏ�̂��Ƃ��āA�����E�o�ρE�����̂�����ʂň�ĂɃw�Q���j�[���������Â�����́u���R��`�ҁv�����ɂ��Ă��A���Ƃ�蔪�E��܈Ȍ�̌��ς͕��X�Ȃ�ʋ����ł������Ƃ͂����A�ޓ��́A������Ȃ��Ĕނ�́u���肵�悩�肵���v�ւ́\�\�����������f�B�J���Ȍ`�Ԃł́\�\���A�ƍl���邱�Ƃɂ���āA���Ƃ̐V���ȋύt��Ԃ��r�I�e�ՂɂƂ���ǂ������ł����c
����������������ւ̔ᔻ�͑O�q�̒ʂ�g��ɂ�������ԓx�ł���B�����āA�I�[���h�E���x�����X�g�́u���肵�悩�肵���v�ւ́u���A�v�Ƃ����ᔻ���ꎩ�̂��A������x�I�Ă����ƌ�����B��܂��Ɍ����āA������̒m���l�͓V�c���i��̗�����Ƃ��Ă������A�g�c���t�ŕ����߂��c���k���Y�́A�������ƂȂ��Ă������璺����ɑ��āA���璺��́u���E�l�ނ̓��`�I�Ȋj�S�ɍ��v����v���̂ł���u���R�@�Ƃ������ׂ��v���̂ƕ]���Ă����قǂł���B[�V�Q]
�@�ȏ�̊ێR�̔ᔻ�͕��a���k�b��ɎQ������ȑO�̔����ł��邪�A���a���k�b������������ڂ̐������o��������������x�ɗ�ȋ�����ᔻ���Ȃ��Ă���B
�c��̖����Ȍ�́u�ߑ㉻�v�͒m���K���ƍ�����O�Ƃ̊Ԃɔ��ȃM���b�v����������Ȃ����Ǝv���܂��B�m���K���������l���Ă݂�ƁA����Ӗ��ł̓��[���b�p�̃C���e�������ɂ��Ă������悤�ȃe�[�}���A��͂�₦�����{�̃C���e�������ɂ��Ă������Ǝv���܂��B���Ƃ����O�Ƃ��̎v�z�I���x���́A�����̃��[���b�p�̐����ɔ䂵�Ă��������Ēp���������Ȃ��B����̖����I�Ȑl�ԂƂ����Ă���l�́A���{�̍ŋ߂̃E���g���E�i�V���i���Y���������Ȍ�̍��ƂȂ����Љ�̐��̕K�R�I�Ȕ��W�Ƃ��ďo�Ă������̂��Ƃ������Ƃ��A�ǂ����Ă����F���܂���B�Óc���E�g�搶�Ȃ�������ł��ˁB���Ă͓��{�͂����Ƌߑ㉻����Ă��������A����������s�ӂɗ��\�ȌR����E�����o�Ă������̂����炱���������ƂɂȂ��Ă��܂����B�ȑO�́A���{�ɂ����R�����������ᔻ�I���_���������Ƃ������Ƃ��������Ă���܂��ˁB�Ȃ������̃C���e���������������������������Ƃ����_���ʔ����̂ł��B�������ɒm���l�̏Z��ł������E�͊ϔO�I�ɂ͂��Ȃ�ߑ�I�������̂ł����A���������ϔO�̐��E�͈�ʍ����̐������K�肵�Ă���u�v�z�v����͉��������ւ������Ă��āA�����������̂��̂̋ߑ㉻�̒��x�Ƃ̊Ԃɔ��ȕs�ύt���������B�Ƃ��낪�m���Љ�ɏZ��ŁA���̎Љ�̋�C��m���Ă������l�ɂ́A�ǂ����Ă��ŋ߂̐_������I�t�@�V�Y���̏o�����˔����ۂƂ��Ă����~�߂��Ȃ��B�c���͂ނ���t�ɂ��������l�̏Z��ł������m���Љ���ʂ̎Љ�Ȃ̂ŁA��ʂ̍����w�͑S������Ɗu�₳�ꂽ���ƎЉ�ӎ��̒��ɂ������B�c�ڂ��͖����I�Ȓm���l�Ƃ����悤�Ȑl�́A�d�b�w�I�Ȉӎ��Ƌ��ʂ������̂������Ă���Ǝv���B�܂胊�x���������f���N���e�B�b�N�łȂ��B���������d�b���x�����Y���͍����I�Ȋ�b���Ȃ������̂Ŗ��͂������̂���Ȃ����Ǝv���܂��c[�V�R]
���̂悤�ɁA������r�I���ł������ێR�̋�����ɑ���ᔻ�͌��������̂��������B�����Ă����������ӎ��͈�l�ێR�̂��̂Ƃ����킯�ł͂Ȃ������̂ł���B
�܂��A�ʏ�̏ꍇ�A���a���k�b�����鎞�ɂ́A�u�v�z�I�ɂ�����I�ɂ����̍L���m���l�W�c�v�Ƃ������\���̂��������~�X�U�������B�������Ȃ���A�������ׂ����Ƃ́A�u�v�z�I�v�ɂ��u����I�v�ɂ����̍L���Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���Η��_�������Ƃ������Ƃł���B���x���q�ׂĂ������Ƃ����A�����̒k�b��Ƌ��s�̒k�b��Ƃł͎v�z�I���͋C���傫�����ƂȂ�B���Ȃ�ڋ߂Ȍ������ł��邪�A�����̒k�b��̃{�X�͈��{��a�҂ł���A���s�̒k�b��̃{�X�͐i���h�̖���ł������B���������v�z�I���͋C�̒��ŁA�ӌ��̈�v�����邱�Ƃ͍���Ȃ��Ƃł���A�ێR����A�v�����m���l�͈ӌ��̒����̂��߂ɉ��x�������Ƌ��s�Ƃ��������Ă���B�܂�́A�傫���킯�āu�v�z�I���فv�E�u����I���فv�E�u��ԓI���فv�Ƃ������t�@�N�^�[�����G�ɗ��ݍ����Ȃ���k�b��̒��ɑ��݂����A���x���̐������o�����Ƃ������Ƃ��d������K�v������B
�@
�Q�|�Q�D�@���{�\���ƃI�[���h�E���x�����X�g
�@�����A��g���X�̎G���w���E�x�́u���S��v�̓��l���Ƃ��ďo���������Ƃ͑O�q�����B�����āA���́u���S��v�͏��X�Ɂw���E�x���痣��Ă������ƂɂȂ�A�w���E�x�͓���30�ォ��40����x�̎�肪���̎��M�҂̒��S�ƂȂ��Ă����B�����āA���́u���S��v�́A�u������v���������āA1948�N��7���Ɂw�S�x��n�����邱�ƂɂȂ�B���́u�S�v�O���[�v�́A���̎Q���҂̂قƂ�ǂ��I�[���h�E���x�����X�g�Ő�߂��Ă���A���k��̉���Ƃ��d�����Ă���҂������B
�@�Ⴆ�A�u�S�v�O���[�v�ɂ͈��{���n�߂Ƃ��āA�V���S�E����M�O�E�c���k���Y�E�a�ғN�Y�E���ҏ��H���āE������q�炪�Q�������̕ێ�_�d���`�����Ă������B[�V�S]�u�S�v�O���[�v�͂����v����ɂ��A���́u�S�v�̊������@�͎�ɂӂ�����Ƃ����B��ڂƂ��ẮA�u�푈�ӔC�v�̖��B�u�S�v�O���[�v�̎Q���҂͔s�퓖���ł����Ȃ�N���ł���A�ڋ߂Ȍ�����������u��搶�v�ƌĂ��ׂ��l�����ō\������Ă����B���́u��搶�v�́A�u��搶�v�Ȃ�Ɂu�����������܂��������v�Ƃ����l���͂������̂ł���B[�V�T]�����āA��ڂɂ́A���̔M�ɕ������ꂽ�悤�Ɍ����������I�����ɑ���[���ȕs�����������B[�V�U]
�@�����ł��邩��A���́u�S�v�O���[�v�ɂ͗Ⴆ������ł����Ă��푈�ɕ֏悵���悤�Ȑl�͎Q�����Ă��Ȃ��B����ɁA���H�I�ɐ��̕ێ�v�z���Č����悤�Ƃ���l�X���Q���͂��Ă��Ȃ������B���ꂪ�A�O�q�̓�̓��@���炭��Q���҂̍\���ł���B�ł��邩��A�s�퓖��53�̖��씎��A�������s�퓖��57�̍P�������A���́u�S�v�O���[�v�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�ȏ�̓_�܂�����ŁA���{�𒆐S�ɕ��k��Ƃ̊֘A�������Ă������Ƃɂ������B���{��1883�N���܂�ŁA�s�펞��62�Ƃ����N��ł���B���{�͐�㕶����b��w�K�@�̉@���߂Ă���B���̈��{�����k��ɎQ���������������́A�g��̔M�S�ȗU�������������炾�����B�����͕��k��ɎQ�����Ă���A2�E3�N�̊Ԃ͕��a���ɔ��ɔM�S�ł���A���k��̎咣�ɂ���{�I�ɂ͓��ӂ��Ă����ƌ�����B�Ⴆ�A���k��S�ʍu�a�Ȃǂ̕��a�l������ł��o�������Ƃɂ��A�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�V�V]
�@�c�������傭���E�̕��a�Ƃ���Ɍq������{�̕��a�Ƃ́A���卑�̑R�Ƌْ��Ƃɂ���Ă͖]�܂ꂸ���āA�����̑Ë��Ɠ����Ƃɂ���Ă̂݊��҂�����̂ł���B�������X�́A�����̑Η����I�ǓI�Ȃ��̂ƌ������āA��ɗ��������g���w�߂Ă��̋��ʂȗ��Q�����o���āA���Ë������������邱�Ƃ�M�]����ƂƂ��ɁA�A�����J�͒P�ƍu�a�Ń\�A�͑S�ʍu�a�ł���A�P�ƍu�a�����A�����J�ɖ������ă\�A��G�Ƃ�����̂ł���A�S�ʍu�a�����\�A�ɗ^���ăA�����J��G�Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃ��A�ȒP�ɂ��߂Ă��܂������Ȃ��̂ł���B
�@�ȏ�̔����́A����Ӗ��ł����Ε��k��̌������������̂܂܌J��Ԃ��Ă���Ƃ�������B���̓������͒��ɂ����Ă��A�u���E���a�̍��{�͕ă\�̑Η��v�ɂ���A�u���ɓI�ɂ��̋�����W���ʁv�悤�ɓw�߂�u���a���k�b��̏����ɑ�̓����v�Əq�ׂĂ���B[�V�W]���{�́A���̌�A���k��u�O���ѕ��a�ɂ��āv�\���A�T���t�����V�X�R�u�a�����ꂽ���Ƃ����l�̎�|�̕��͂��q�ׂĂ���B�S�ʍu�a��ČR�����咣���A���a���ƁE�������Ƃ��咣���Ă���̂ł���B���������Ӗ��ł́A���{���g�́u���a�_�v�ɂ���قǂ̓Ǝ���������킯�ł͂Ȃ��B
�@�������A���̂悤�Ɉ��{���g�͕��k��̌��������ɉ������������ێ��������A���k��ɑ���ւ����ɂ́A����Ƃ͈قȂ�ʂ����݂��邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ł܂��A���ڂ��Ă����ׂ��_�́A�O�q�́w�S�x�n���̎����ƁA���k����̎������قړ������Ƃ������Ƃł���B�����̉�z�ɂ��A���k��̐����ȃ����o�[�����肵���̂́A1948�N��11��15���ł���B[�V�X]�܂�A���{�͂قړ������Ɂw�S�x�Ŏ��M���A���k��ɎQ�������̑�\���߂��Ƃ������Ƃł���B�u�S�v�O���[�v�ƕ��k��Ƃł́A���悻���̎v�z�w�i�͈قȂ�B��قǂ��q�ׂ��Ƃ���A�u�S�v�O���[�v�͐��̍��h�I�ȕ����ɔᔻ�I�ł������B���ۈ��{���g���A�u���a���̏W���ɌĂꂽ���A�����ɏW�܂����J���ҕ��̋C�������\�A���S�����₤�ȕ��a�̋��тɂ́A����������ł��Ȃ������B�v�Ɖ�z���Ă���B[�W�O]
�@�����Ă܂��A��ɕ��k��̑S�ʍu�a�_�ɗ��_�I�Ȕᔻ�������Ă�������M�O���u�S�v�ɎQ�����A�قړ�����ł��蕽�k��ɎQ�����閖���P�����u�S�v�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ����Ƃ������[���B���ہA����͕��k��̑����쐬�̓��c��̒��ŁA�����̑�O�g�D�̕K�v�����J��Ԃ��������Ă��邱�Ƃ�����A�قړ�����Ƃ͂������{�Ɩ���Ƃł́A���̎v�z�X���ɍ��ق�������B
�@�����Ă܂��A���{�̉�z�ɂ��ƁA���k��ɔM�S�ɗU�����g��̎v�z�ƍs���ɂ́u���ӂ����˂�v�Əq�ׂĂ���B[�W�P]�g��̎v�z�I�Ȕw�i�Ɋւ��Ă͑O�q�����Ƃ���ł���B�����āA�g��y�єނƓ����̐��̊�g���X�̒��҂����Ƃ́A���̎v�z�X��������Ă���Ƃ�����z�����Ă���̂��O�q�̒ʂ�ł���B�����ł����u���̊�g���X�̒��ҁv���A�ǂ��������l�X�Ȃ̂��A��������܂ł��Ȃ��ł��낤�B�����āA�ێR���������̐���̒m���l�����́A���̈��{��̐���ɑ���ᔻ�ӎ�������Ă����̂��O�q�����B
�@����ɊێR�̉�z�ɂ��ƁA�S�ʍu�a���n�߂Ƃ������a�l�����������������������������A���k������Łu�����肳��肪�o�Ă����v�B[�W�Q]�����āA�����̉�z�ɂ��ƁA�u���{�\���A�a�ғN�Y�A�c���k���Y�v�Ƃ������I�[���h���x�����X�g�����́u�P�ƍu�a�ɍ����]����^���Ă����v�B[�W�R]���ہA�������ŁA�c���k���Y��Óc���E�g�A��ؑ�ق�͒P�ƍu�a�̈Ӌ`��F�߁A���k����Ă���B
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA���{�ƕ��k��Ƃ̊ւ��A���{�ƊێR��v��A����Ƃ������l�����Ƃ̊W�������Ă���B�܂��A���{�ƕ��k��Ƃ̂������Ɋւ��ďq�ׂ�ƁA�u���a�v�����߂�Ƃ����_�ł͈�v���Ă��邵�A�푈�ɑ���O�ꂵ�������������{�����k��ɎQ���������@�̍ł��傫�Ȃ��̂ł������낤�B�����āA���k��̑�\���Ƃ��������A���k��̌����������q�ׂĂ����Ƃ����̂������͓������Ă���̂ł͂Ȃ����B�������Ȃ���A����I�ȑ���E�v�z�I�ȑ���ł͑傫����������Ă���Ƃ����_���܂������ł��邵�A�u�S�v�O���[�v�Ɣ�ׂĂ݂邱�Ƃł���w�͂����肷�邾�낤�B������v����������A��X�܂ŕ��a�^���ɃR�~�b�g���Ă����������o�[�ł���A�������炱���������v�z�I�ȑ��l���ƍ��ق�����ꂽ���̂����k��̎��ۑ��ł������̂ł͂Ȃ����B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���{�ƕ��k��Ƃ̊ւ��A���邢�͈��{�Ɩ����v�쓙�̒k�b�����Ƃ̊W�́A���悻���`�I�Ȃ��̂ł������Ƃ�����B���{�͕��k��̂��Ƃ���z���Ĉȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���̉�ɂ���Ď����V���ȗF�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂́A�N��␢��̊u����ɂ���邪�A���̂��̉�̎�̐��̕s�����匴���ł������낤�v�B�u��̐��v��S�ʓI�ɔ����ł��Ȃ��A���r�o�����g�Ȋ�������������̉�z�́A���{�ƕ��k��Ƃ̊W���ł��I�m�ɕ\���Ă���̂�������Ȃ��B
�Q�|�R�@�v����E���������Y�ƕ��a���k�b��
�@�v�����1910�N���܂�A�s�펞�ɂ�35�̎��m���l�ł������B[�W�S]���܂ŏq�ׂĂ����ێR����{�Ƃ͂܂��قȂ�v�z�X���������A���k��̎v�z�I���l���̈ꗃ��S���Ă����ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B���������Ӗ��ł́A�ێR����{�Ƃ͂��ƂȂ鎖��Ƃ��Č��ł���B
�@���_���猾���A�s�펞��35�Ƃ����Ⴓ�̓_�ł͊ێR�Ƌ��ʂ��镔��������B�܂�A����I�ȑ���Ƃ����_�ł������ł��邵�A�ێR����Ɠ��l�v����A���k��̎����I�ȓ�����Ƃ��ē����Ƌ��s�̊Ԃ���������Ƃ��������������Ă���̂ł���B�����āA�v�z�I�Ȕw�i�Ƃ����_�ł́A�v��͂����H�I�ȕ��a�^�����u�����Ă����B��N�A�v��́u�s����`�̐����v���L���A���쓬����x�E�@���Γ����A60�N���ہA�ו��A�ɂ��ւ���Ă������ƂɂȂ邪�A�����������u���H�I�ȁv�^�����d������X���͔s�풼�ォ��v��̒��ɂ͑��݂����B
�@����Ɍ����A�v��̂����������u���H�^���v���d������u���͐풆�̌o���ɋ��߂�ׂ��ł��낤�B�v��͓��l���w���E�����x��T���V���w�y�j���x�̊֘A�Ŏ����ێ��@�ɂ��A���������Ƃ����o���������Ă���B��N�̉�z�ł́A�u�ߕ�����Ė��i�炦����A�^���ɐg�����悤�v�ƌ��S�����Ƃ����B[�W�T]���邢�͋����쎖���ʼn^�����o�����Ă���̂��傫���ł��낤�B���̂悤�ɁA�����쎖���A�w���E�����x�E�w�y�j���x�E�����o���Ȃǂ���ՂƂ��Đ��̋v����̊������n�܂����ƈʒu�Â���̂͊ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��낤�B
�@�ȏ�q�ׂĂ����Ƃ���A�v��͂��̐��U�ɂ����Ĉ�т��ĕ��a�^���┽��^���A���邢�͎s���^���ɍS���Ă������m���l�ł���B���݂ɂ����āA�v��́u�s���v�̗��ꂩ��s�������m���l�Ƃ������]�����Ȃ���邱�Ƃ������B���̔��ʁA���a�^���ɂ���т��ăR�~�b�g�𑱂��Ă������B
�@����������Ȃ�A�u�s���^���v�̑��ʂƁA�u���a�^���v�̑��ʂ̓�d����������m���l�ƌ������Ƃ��ł���B�����āA�v�삪�u���a�^���v�Ɋւ�肾�����̂́A�s�풼�ォ��ł���A�u�s����`�̐����v���L���āu�s���^���v�Ɋւ�肾�����̂́A�x�E�@���Ή^������60�N���ۂɎ��闬��ł���B
�@�������A�u�s���^���v�Ɓu���a�^���v�̓�d���Ƃ����\���͐��m�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�ނ���A���҂͏d�Ȃ荇���Ă�����̂ƈʒu�Â��邱�Ƃ̕����K�ł���B�����āA��q���邱�Ƃł��邪�A�v��ɂ�����u�s���^���v�Ɓu���a�^���v�Ƃ́A�v��ɓ��݂��鍪�{�v�z�ɒ��ڂ����ꍇ�A���̍��͓���ł���ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B���̍��{�v�z�ɂ�������́A���ꂱ���O�q���������쎖���Ȃǂ̐풆�̑̌��Ȃ̂ł������B
2�|3�|1�D���W�X�^���X�̎v�z
�@�����쎖���́A����Y�@�w�̑��K�C�����̍ߌY�@��_�̎v�z���E���炪�댯�v�z�ł���Ƃ݂Ȃ��A1933�N�A�����̔��R��Y�������A�����⋳��������đ����x�E�����ɂ��A�����̒���w�Y�@�ǖ{�x�ւɂ������Ƃ���n�܂�B
�@���̏����ɑ��āA�@�w��������������E�����肵���B�w�������́A���̑��ɑ��鏈���ɐ^�������甽�Ή^�����s�������A�^�����̂͌Ǘ����A�@�w���������S�������E����Ƃ��������̌�������������ŏI�����Ă��������̂ł���B[�W�U]
�@���̓����A�v��͋��s��w�̎O�ł���A���_���T�����g�ł��邽�߁A�u�@�w���̊w���^�����x���͂��邯��ǂ��A���S���͂̈�l�ɂȂ��đފw�������Ă܂ł��������ӎv�͂Ȃ������v�B[�W�V]�����̕��w���̑��Ƙ_���̐��тɑ����d�́A���ɏd�����̂�����A�v��͑��_�ɏW���������ł������悤�ł���B
�@���_�������ɂ������āA�v��͖����_���e�[�}�ɂ��悤�ƍl���Ă����B���̖��ӎ��́A���{�ɂ����ẮA�u�����I�l�P�ʂ��ߑ�I�C�Ӓc�́A�������ЁA���邢�͌_��g�D�Ƃ������Љ�W�c�����Ƌ@�ւ̓�����r���āA����A���l�Ȏp�ŏo�Ă��Ă��Ȃ��v�B�ł��邩��A����������ߑ�Љ�̐����Ɩ����̔��W�Ƃ̊W�ׂ閯���_����\�z���Ă����炵���B[�W�W]���_���炢���A���{�ɂ����āu�ߑ�I�C�Ӓc�́v��u�����I���Ёv�A�u�_��g�D�v�����Ƌ@�ւ̓����ɕ������ƂȂ��A���W�X�^���X�̌`�ŏo�����邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ������ӎ��͋v��Ɉ�т������̂ł���B
�@���Ƃ��A1930�N��O���̊w������̖��ӎ����A��N�̋v��Ƃǂ̂悤�Ɉ�т��Ă���̂��͈ȉ��̔���������킩��B[�W�X]
�E�E�E���{�̈�Ԃ̐����I�A�����I�n�����́A�����\�͂̂Ȃ����甭���Ă���̂ł͂Ȃ����B���R�͎��R�ł��A�����̔w�i�������Ȃ����R������A�����\�͂̂Ȃ��W�c��l�����Ƃ��炠�Ƃ��猻��āA���R�̒D������������L���Ă���B�c�h�C�c���̌l�̎����͓��{�ɂ��蒅������悤������ǁA�����Ƃ����̂́A��͂�Ƃ⑺�⒬�̎�������n�܂�Ȃ��Ɩ{���ɂ͂Ȃ�Ȃ���ł��E�E�E
���̔����́A1996�N3�����w�L����]�x�f�ڂ̕��͂̈ꕔ�ł���B�����ł��A�u�����v��u����v��w�i�Ƃ���g�D�������Ȃ����{�̕����I�E���j�I���ꐫ����������Ă��邱�Ƃ��킩��B���킹�āA�w������̋v��̖��ӎ��Ƃ������ɐڑ�����Ă��邱�Ƃ𗝉�����̂͗e�Ղł��낤�B
�@�ȏ�̂悤�ȁA��N�ɂ܂ň�т������ӎ����������v��ł��������A�O�q�����悤�ɁA�����͋��厖���Ƃ͋���������Ă����B���̋v��̈ӎ����傫���ς��_�@�ƂȂ����̂́A�����E���鋳���S�����w���Ɏ��E��������@�w���w�����ւ̏o�Ȃł������B���̑��ɂ͂Q��l�ɂ��̂ڂ�w�����������l�ߏ�ԂŎQ�����A���E������𑼂̖@�w�����������݂͂Ȃ���A�����̋{�{�w���������̂悤�ȗL���Ȍ��ʂ̈��A���s�����B
�@�E�E�E�����E�͖@�w�������c���̗p����������Ȃ��Ȃ����w�����N�ɂ�������Ō�̋����i�ł���B�����͂��̂悤�ȍs���ł������N������ł��Ȃ��Ȃ�����͂�[���p�������Ă���E�E�E[�X�O]
�@���̐������ǂ܂�钆�A�w�����J����Ă��鋳���̎���Ƃ���ŁA�w�������̂ނ��ы����������Ă����Ƃ����B[�X�P]
�@���̑���T�����Ă����v��́A���_�ɏW�������厖���Ƃ͋�����u���Ă����p�������߁A�^���ɗ͂����邱�ƂƂȂ�B���̎��̐S���͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�E�E�E����͑��Ƙ_���ǂ���̘b�ł͂Ȃ����B�����ɂ̓}�X�v����������w�ł����Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ɍ�������������̂Ƌ���������̂Ƃ̂ق�Ƃ��̑Θb�A�ق�Ƃ��̊w�т������������Ă���ł͂Ȃ����B���̐��_����݂����点�邽�߂ɂ́A����w���Ƃ��Ĉ����������Ă���ׂ��ł͂Ȃ��E�E�E[�X�Q]
�@�������ċv��͋��厖���ɑS�͂𒍂����ƂɂȂ�B���ʓI�ɂ́A�O�q�����悤�ɁA���̊w�������̉^���͏I�����Ă����A�ڂ��������ʂƂ������͓̂����Ȃ������B�v��́A�����\�肵�Ă��������_�ł͂Ȃ��A�w�[�Q�����e�[�}�Ƃ������Ƙ_���������đ�w�𑲋Ƃ��邱�ƂɂȂ�B
�@�������Ȃ���A�v��ɂƂ��Ă��̋��厖���́A���̎v�z�`���ɂ����ďd�v�Ȍ_�@�ƂȂ����B���厖���́A�Ȍ��Ɍ����A�u�w��̎��R�v�̂��߂̓����ł������B���Ƌ@�ւ��A�{���N���ׂ��ł͂Ȃ��u�w��̎��R�v�m�ɐN�Ƃ������Ƃɑ���ᔻ�I�ӎ����v��̒��ŐA���t������B�������A����ȏ�ɋv��ɂƂ��đ傫�������̂́A��w�ɂ�����u�A�w�̎��R�v�̌����ł������B��N����z���ċv��́A�u�ڂ��͑�쎖���ő�w���̎��R�ɂЂ��ތ��ׂɂ��Ɋ��������܂����v�Əq�ׂĂ���B[�X�R]
�@�u�w��̎��R�v�Ƃ́A�{���A�u�����鎩�R�v�Ɓu�w�Ԏ��R�v�̓�ɕ�������B�������A�v��ɂ��A���{�̑�w�ɂ́u�w�Ԏ��R�v�ȂǑ��݂��Ȃ��B�u�w�Ԏ��R�v�Ƃ́A�u�A�w�̎��R�v�ł���A���Ƙ_�����o������w�����Ƒ�w�Ƃ��ĔF�肳���悤�Ȃ��Ƃł���B�������A��w�̎��R�ƌ����Ă�����������̎��R�ł��邵�A���̕Ј���̎��R�����̂��܂��܂Ȏs���I���R�ɂ���Ďx�����ď��߂ċ@�\������̂ł��낤�B[�X�S]
�@�����āA���́u���܂��܂Ȏs���I���R�v�Ƃ������̂����{�ɂ͌��o���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�{���A�ߑ�Ƃ������̂́A�u����v�u�����v��w�i�Ƃ����u���R�v�ȑg�D�����Ƃ���h����ɑ��ăv���e�X�g����`�Ő��܂����̂ł��邩��ł���B�s�s��M���h�Ȃǂ́A���������u����v�u�����v�I�g�D�ł���A�{���̑�w�����̗�ɘR��Ȃ��B
�@�����Ƃ���A���{�ɂ����āA�����ɂ��āu����v�u�����v�������Ƃ���g�D�A����̏�ɂ��u�s���I���R�v�͐�����������̂��B�ȏ�̂悤�Ȗ��ӎ����v��̒��ŏ�������Ă������ƂɂȂ�B�����쎖�����v��ɗ^�������̂́A�ȏ�̂悤�Ȗ��ӎ��ł������B���̋����쎖���ł́u���W�X�^���X�v�̌o�����A��N�̕��a�_��s����`�̃e�[�[�ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ�B
�@���́u���W�X�^���X�v�̎v�z�́A1934�N�ɑ�w�𑲋Ƃ����v�삪�A���̗��N��1935�N�ɖ������̎G���w���E�����x��w�y�j���x�����邱�ƂɌq�����Ă����B�w���E�����x�́A�t�����X�̖������ɑ傫�Ȏ����Ĕ����������t�@�V�Y���̏��ł������B�����ł��̓��e�̕��͂܂łɂ͗�������Ȃ����A���厖���Ŕ|�������ӎ��ƒ����������̂ł������Ƃ����_���������Ă����B
�@����ɁA�v�삪��w�𑲋Ƃ����N�́A�q�g���[��������D�悵�����N�ł������B���̌�A���{�̓i�`�X�Ɩh������������ł����B���̎��A�v��́u���{�̏ォ�����o�������ɁA�����E��������O���Ȃ�����قǏ]���Ȃ̂��Ƃ��������A��������˂�����ꂽ�v�Ƃ����B[�X�T]�������������ӎ����܂��A��q���邪���̋v��ւƎp����Ă������̂ł���B
�@�����āA�O�q�����悤�ɁA�v��͂��́w���E�����x��w�y�j���x�̊֘A�œ��������B���̓����̌����ߎS�Ȃ��̂ł������B�������̏��v��͈ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B
�E�E�E�x�@�̗��u�ꎞ��A�܂���̃V���o�́A�싞�ח��̑�`���E�`���s��̑呛���łˁB�����A�����Y�������A�e�x�@���O�������炢���A�����ƁA�^���C�����ق��������Ƃ���ǂ������ł���B�m�~�A�V���~�A�싞���ɂ������A���C��U���͑S�������ꂸ�A�Ђǂ����b�\�E�тŁA�ڌ��͂��ׂċ֎~�B�\�����炢�̕����ɓ�ܐl���炢�߂��܂�ĐQ��̂ł�����A�ꕔ�͂܂��ɗ����Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏�A����������蒲�ׂ��Ȃ��u�^���ɍ��킳���킯�ł�����ˁE�E�E[�X�U]
�@���̌�́A���a������A��㏗�q�o�ϐ��w�Z�ŋ��������Ȃ���A�풆���߂������ƂƂȂ�B���̓����A�v�삪�t�@�V�Y���ɒ�R���钆�ŁA�Â�悤�ɓǂ̂��A�W�����E�f���[�C�ł������B�f���[�C�́w�_���w�x��w���R�ƕ����x�w�N�w�ƕ����x�w�V���l��`�x�ɐ[���e�����ꂽ�B���̃f���[�C����A�v��͖{���̌l��`�Ƃ������̂��z�����Ă����B
�@�v��ɂ��ƁA���{�ɂ����ẮA�u�l��`�v�́u�l�G�S�C�Y���v�Ɖ��߂��ꂪ���ł��邪�A�{���́u�l��`�v�́A�u���l�̐g�ɂȂ��čl���A���l�𗝉����A���l�Ƌ����̍s�����l���o���ԓx�ɂ���Ď����̌���[�߁A�Ђ�߂�X�^�C���v�ł���A�u���҂ւ̗����Ɗ��e�v�������X�^�C���ł���B����ɂ��킦�āA�u�Љ���˂ɐV�����`���������̂��l��`�ł���v�Ƃ����B[�X�V]
�@�ȏ㌩�Ă����悤�ɁA�풆�̋v��̑̌��͗l�X�ȃ��x���ŋv��ɉe����^�����B�Ƃ�킯�A�����쎖����w���E�����x�w�y�j���x�̔����͑傫�Ȍ_�@�ł������B���̂悤�ȑ̌���|�����v�삪�A�u���v�ɏo����Ĉȍ~�̋O�Ղ����߂Ō�����B
�Q�|�R�|�Q�D���a�_�Ǝs����`
�@�v��́A�ǂ̂悤�Ȏv�z�������āu���v�ƑΛ������̂��낤���B��ڂ́A�t�@�V�Y���ɒ�R���������v��ɂƂ��āA��O�����Ƃ��ȒP�ɐ��{��V�c�Ƃ������u��́v�g�D��l�ɒǐ����Ă��������Ƃł���B����ɂƂ��Ȃ��āA��O�Ƃ������̂ɑ傫�Ȋ��҂������ʁA��O�ɑ���^�`��悵�Ă������B���Ƃ��A�v��͐�㒼����ȉ��̂悤�ɉ�ڂ��Ă���B
�E�E�E�Ƃɂ����A�ォ��̗U������͂̊�F�̓����ɏ]���Ȃ���A����ɉ����ă��m�������A�s��������{�l�̑吨�ǐ��I�Đ��́A����ȑ�s��ɂȂ��Ă��A�V�c�ُ̏��ŃP��������̂ł�����A���܂�ς���Ă��Ȃ��B�V�c�ُ̏��œˑR������v�ŁA�푈�ɓ���A���܂܂��ُ��ŋ�����v�ŁA�P����������{�l�̎v�l�l���A�s���l�����ǂ��l����̂��B��������߂邽�߂ɂ́A�ڂ��͂����l����Ƃ����ԓx���܂��o�������v�����̂ł��B�Ƃɂ����ڂ��́A��O�́A�ォ��w�����ꂽ�^���̌������������A�v���I��O�Ƃ��Ă܂�܂�M������C�����ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ������͎̂����ł��ˁB[�X�W]
��_�ڂ́A�ォ��̎w���ɏ]���ȑ�O�ł͂Ȃ��A�e�l�����m�Ȗ��ӎ������ƂƂ��ɁA���̘A�т�͍�����Ƃ������̂ł������B
�E�E�E�݂�Ȃ��A�߂��߂�������̖��ӎ���l�����������悤�ɂ���B���ꂩ��A���l�̈ӎ���l�����̗�����[�߁A��ň�v�����l�����Ŏ��s�Ɉڂ��Ă����B�u�s���̈�v�v�����������̑��݂̂ق�����l���Ȃ��ŁA�����܂ł��l�������̃��x���̖��Ƃ��Ĉ����Ă����B[�X�X]
����́A�����쎖���Ŕ|�������ӎ��Ƃ�͂茋�т����̂ł���B�u����v�u�����v�̑g�D��w�i�Ƃ����A�u���R�v�Ȍl���A�����̑��K���x�ɏ]���̂ł͂Ȃ��A�����I�Ɂu�s���̈�v�v�����߂Ă����B���邢�̓f���[�C�̉e���������Ƃ��ӂ݂�A�u���҂ւ̗����Ɗ��e�v�Ǝ����ƂƂ��ɁA�u���҂Ƃ̋����v��͍����邱�ƂŁu�l�v��F�����Ă����u�l��`�v�Ƃ������Ƃł��낤�B
�@���̌�A�v��͕��a���k�b��ɎQ�����A�v��Ǝ��̕��a�_��͍����Ă������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A�J��Ԃ��q�ׂ�悤�ɁA�v��̕��a�_���܂��A�u����I�ȑg�D�v��f���[�C���̌l��`�̐ڍ��̒�����A���邢�͋����쎖���̑̌��̒����甭�����邱�ƂɂȂ�B�����Ă܂��A��q���邪�A60�N��ȍ~�̋v��́u�s����`�v���܂��A���̔��z�`�Ԃ͕ς��Ȃ����̂ł���B
�@�����āA�t�@�V�Y���ɒ�R�����v��ł��邪�A���̉�����ƂƂ��Ɂu�����v�̈ӎ����܂��������킹�Ă����B
�@�E�E�E�����푈�͏I������Ƃ���������́A���܂�Ȃ������B�������̌�A�푈���s�ɁA�ǂ����Ă����ƌ�����R�������Ȃ��������A�Ƃ������������Ƃ��炠�Ƃ��畬���o���Ă��āA�ڂ��͐S�̒ɂ݂ɔY�܂���܂����B��R�̑���Ȃ����������̒��́u���{�l�I�������v�ւ̉������[�����Ƃ������Ă��܂����E�E�E[�P�O�O]
�@�v��̉������[�����̂��������B���Ȏ��g�̒��ɑ��݂���u���{�l�I�������v���������邽�߂ɁA�O�q�̖��ӎ�������ɔ��W�����Ă������̂ł��낤�B���������Ӗ��ł́A�v��̐��̋O�Ղ��܂��A�v�쎩�g�������Ă����̂�������Ȃ��B
�@�܂��A�v��͔s�풼�ォ�狞�s�l���w���̍u�t�Ƃ��ĐV���������`������s������A���̎Љ�}���h�̍u�t�Ƃ��ĘJ���u�����������肵�Ă����B���̓�������A��̎Љ�}���h�̈ψ����ƂȂ��ؖΎO�Y�Ƃ��W�������Ă����Ƃ��������͎����I�ł���B���̌�A���������Y�̗U���ŕ��k��ɎQ�����邱�ƂɂȂ�B�v�삪���k��ɎQ���������ڂ̓��@�́A���l�X�R�����ɒm�Ȃ̃z���N�n�C�}�|���Q�����Ă������Ƃ������B
�@�O�q�̂悤�ɁA�v��̑傫�ȓ����͂��̎��H�I�ȉ^�����u�����Ă����Ƃ������Ƃł������B���ہA1949�N����1951�N�̊Ԃɂ����āA�u���h�Љ�}�Ɓw���]�x�̑S�ʍu�a�^���ɑS�͓������Ă����v�Əq�ׂĂ���B[�P�O�P]�������Ȃ���A�v�삪�P���Ȏ��H�����Ƃł������Ƃ����]���͂���������ʓI�ł���B�m���Ɏ��H�������d�����Ă����̂͒N�������F�߂邱�Ƃł��邪�A���̔��ʁA�u�푈�ƕ��a�v�Ɋւ��闝�_�I�ȕ��͂��������Ȃ������B
�v��́w���E�x��1949�N11�����Łu���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�Ƃ����_���������A�u���a�v�̖��Ɓu�v���v�̖���藣�����_��ł��o�����B�Ȃ����̂悤�Ȏv�l�l�����Ȃ����̂��A���邢�͂��̂悤�Ȏv�l�`�Ԃ����K�v���������̂��Ƃ����_�̔w�i�͈�͂Ō��y�����B���́u���a�v�Ɓu�v���v�Ƃ������e�[�[�́A���̌�̕��k��̐����ɔ��f����Ă������ƂɂȂ�B�ێR���u�v���ƕ��a�̖����͂�����Ɛ藣���ċc�_�������߁A�^���������߂Ȃ�����߂��Ǝn�߂Ď咣�����̂͋v�삳���������v�Əq�ׂĂ���B[�P�O�Q]�@�@�@
���́u���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�ɂ����āA�푈�ɑ���h���ςƂ����_����˂��A�u�\�͂̒���ɉ����Ē����ɖ\�͓I���������킦�邱�Ƃ́A�����܂Ŏ������邪�A�����ł́A���̒���ɓO���O���A��R���Ă䂭�v�Ƃ����ԓx�̕K�v�����q�ׂ�B[�P�O�R]����䂦�A�u�푈�ɑ���ϋɓI�����̊��o�v�ƁA�u�푈�̔����l��������M�O�v�ɗ��ł����ꂽ�A�g�D����ł���Ɛ����B[�P�O�S]
���̑g�D���܂��u�ォ��v�̂��̂ł͂Ȃ��B�푈�ɑ���s���]�E�͂́u�M�O�ɔ�����e�l�̎v�z�ƍs�����A�݂�����̈�A�̉^���Ƒg�D�����ʂƂ����`�Â��邩�A�����̉^���Ƒg�D���A���̖ړI�̂��߂ɗL���Ɋ��p���邩�ɂ���āA���a�̖h�g��̖������ʂ��̂ł����āA���̋t�ł͂Ȃ��v�i�T�_�A�M�ҁj�Ƃ����B[�P�O�T]
�܂�A�u�l�v���u���a�ɑ��鋭����]�v�������A�u����I�v�u�����I�v�Ɂu���҂Ƃ̋����v��͍����Ă����B���̌��ʁA�u������v�g�D���`������Ȃ���Ȃ炸�A�ォ��̎w���ɏ]���̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��������Ă���B���̎v�z���A�풆�̑̌��Ɋ�Â��v��̍��{�v�z�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�܂��A�푈�ɑ���s���]�E�͂ɂ��I��R�̉^���̗��j���T�ς�����ɁA�u�����̉^�������ׂāA�ߑ�̎s���I���l����闧����d�v�ȓ��@�Ƃ��āA�o�����Ă��邩����A����͎s���I���a�̘_���v�Ƃ��āA���ʂ̂��̂ł���Ƃ���B[�P�O�U]
�����āA�푈�ɑ���ő�̗L���Ȓ�R���A�g�D���ꂽ�J���K���̃[�l�����E�X�g���C�L�ł���A���̒�R�^���ł���B[�P�O�V]�u�푈�ɑ���I��R�̉^���́A�����ɂ������āA���łȑg�D���l�����A�푈�̑g�D�Ɩ\�͂ɑR����g�D�Ǝ��͂��n�߂Ċl������v���ƂɂȂ�B[�P�O�W]
���̂悤�ȘJ���g�����A�푈�ւ̒�R������悭�Ȃ��Ƃ��邽�߂ɂ͂������̑O����������݂���B��ڂ́A�L�ĂȈ�ʖ��O�̒��ɁA�푈�ւ̑������L�����Ă���Ƃ������Ƃł���B[�P�O�X]
�@��ڂ́A�푈�ւ̍ő�ۗ̕ۂƂ��Ė𗧂��Ƃ��A�J���҂̑g�D�̍ł��d�v�ȔC���̈�ɑ�����Ƃ����_�̎��o���A�J���҂̒��ɍs���킽���Ă��邱�Ƃł���B[�P�P�O]���̂悤�Ȃ��Ƃ�O��Ƃ���A�푈�̊�@���[���Ȃ��̂ƂȂ��Ă����Ƃ��A�u���̓��@�⑼�̖ړI���s��̑���A�����͑Η����x�O�����āA�푈�ɑ���I��R�̉^���ɁA��v���ė����オ��p�ӂ��A��l��l�̘J���҂̒��Ɂv���܂��Ƃ����B[�P�P�P]
�@����Ɋ֘A���āA�u��v���ė����オ��v�Ƃ������Ԃ́A�u��l��l�̘J���҂̐[���F���ƌł����f���琶����̂ł����āA�w���҂ɂ�������ւ̓���̂��߂̍�����_��琶����̂ł͂Ȃ��v�i�T�_�A�M�ҁj[�P�P�Q]�����ɂ��A�g�D���܂�����A���̎w���҂̎w���ɂ���ĘJ���҂��ʖ��O�������悤�ȑg�D�ł͂Ȃ��A��l��l�́u����I�v�u�����I�v���f���A�L�ĂȘA�тƑg�D�ݏo���ׂ��ł���Ƃ����A�v��̎v�z���f����B
�O�ڂɁA�푈�̏����y�ыA���Ɋւ��闝�_�I�F�����J���҂̈�l��l�ɐZ�����A�J���҂̂��������s�����x�����鐢�_�̕K�v�������݂���B[�P�P�R]���̂��߂ɁA�푈�ɑ����R�̌������A���@�̊�{�I�l���̍ō��̕����Ƃ��Ċm�ۂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B�����āA�l�Ԃ͐푈�Ɂu�\���t�����Ă���v�킯�ł͂Ȃ��A�u�����t�����Ă���v�̂ł���A���̏����̒T����������ł���B[�P�P�S]
���̒�R�̌����̊m�F���������ŁA�����̎���I�ȑg�D��h�q����K�v������ċv��͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@�E�E�E���ꂼ��̎���I�g�D�A�Ⴆ�ߑ�I����A�ߑ�I�J���g���y�т��̑��̑g���A�ߑ�I�w�Z�A�����͊w��̂悤�ȏ��c�̂��A���ꂼ�ꎩ�Ȃ̐E�\�ɉ����āA�푈�ւ̒�R�ƁA���a�̊m�ۂ̂��߂̉^����͋����W�J���鎞�A���a�̘_���́A���Ȃ���������L�͂ȕۏ�������ƂƂȂ�ł��낤�E�E�E[�P�P�T]
�����������l�������́A��́u�s����`�̐����v�ȍ~����т��Ă�����̂ł��邱�Ƃ͑O�q�����B
���_�Ƃ��āA�u���a�̘_���v��F�����A�u�푈�̘_���v�ɓO��I�ɒ�R���Ă�����͎̂Љ�I���݂ɂ���Ĉ�`�I�Ɍ��肳���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B��������A�J���҂����畽�a�̖����ł���A�u���W�����K�������畽�a�̓G�ł��舫���̐��͂ł���Ƃ����u�����v�ȊO�́A�u���a�v�Ɋւ���V���Ȏv�l�̒n�����J���Ă���̂ł���B
�@�t�Ɍ����A���k������̂悤�Ș_����K�v�Ƃ��Ă����Ƃ�������B�Ƃ�킯�A���s���k��́u���h�v�I�Ȏv�l�̎����傪�����A�������k��Ƌ��s���k��Ƃ̊Ԃ̋c�_�ŁA�u���a�v�̖��Ɋւ��Ĉ�v�����邽�߂ɂ͂��̂悤�Ș_�����s���ł������B���������Ӗ��ł��A�v��́u���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�����k��ɗ^�����e���͑傫���ƈʒu�Â��邱�Ƃ͊ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��낤�B
�@�����������A�u���a�v�Ɓu�v���v�������������āA�v�l���邱�Ƃ��A��͂�풆�̑̌����傫���e�����Ă����B
�E�E�E�����A���������l�������͂ڂ��ɂ�����̌o����ʂ��Đ[���Z�����Ă��܂����B�E�E�E���������Ȃ�ƁA�^���̎�̂́A�Љ�I���݂ɂ�錈��̘_�������ɗ����Ă͂����Ȃ��Ȃ�B�J���҂����畽�a�̖����ł���A�u���W�����W�[�����畽�a�̓G�ł���Ƃ����ӂ��Ȍ��������ł͂��܂�L���łȂ��Ȃ�̂ł��ˁB�����A���a�ɂ��Đl�X�̈ӎv��s���̓����傫���}�낤�Ƃ���Ȃ�A���ׂĂ̐l�X�������̑��݂�����������o����镽�a�_�Ƃ������̂��A��������f����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����́A�L���ȃt�����X�������̃X���[�K���u���j�e�E�h�E���N�V�����E�A�E�g�D�v���i������]�������s���̓���j�v�i���O�l�N�j���т��_���ł��������Ǝv���܂��B�ڂ��̐��ł́A���a�̂��߂̍s���Ƃ����̂́A�g�ɂ�������炸�h�Ƃ����A����Ύ����I�_�@�����Đ��藧�Ƃ�������ł��傤�E�E�E[�P�P�U]
�@�������Ȃ���A�����������u�v���v���u���a�v�̑O��ł���Ƃ����l�������₵�A�u���a�v��Ɨ��������Ƃ��đ�����v�l�l���͌����ē����̒m�I�̒��Ŏs�����Ă����Ƃ͌����������B���m�̒ʂ胆�l�X�R�̌��͂́A�u�푈�͐l�̐S�̒��Ő��܂����̂ł��邩��A�l�̐S�̒��ɕ��a�̍Ԃ�z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����錾����o�����Ă�����̂ł���B
�@�����������A�푈�̍������l�Ԃ̐S�ɂ���Ƃ��������߂����āA�v��̓��f�B�J�������̃w�[�Q���w�ҏ�����l�ƈȉ��̂悤�ȑΘb�������Ƃ����B
�E�E�E�v�삳��A����ȊϔO�_�̃A�z�_���o�����Ȃ��܂ŐM���Ă���̂ł���
�@�E�E�E�ڂ��͏o���_�Ƃ��ĐM���Ă��܂�[�P�P�V]
�@�푈�ƕ��a�̖����A�Љ�̐���o�ϓI�����̖��Ƃ��čl���鏼���ɂ́A���悻�������̂Ȃ����ݒ肾�Ǝ~�߂�ꂽ�̂ł��낤�B
�@���̘_���̌�A�v��͎��H�����ɏ]�����Ă������ƂɂȂ�B�v��́A���̓����̂��Ƃ��ȉ��̂悤�ɉ�ڂ��Ă���B
�@�E�E�E�k�b��̒��łڂ��́A��͂���H�����h�̓���I�Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B�����Ƃ��A����ȑO���Ȍ���A�s���^���ɒ�������������̂ł�����A����͓��R�Ƃ����Γ��R�ł��傤�E�E�E[�P�P�W]
���������Y�̉�z�ɂ��ƁA1949�N��5���ɂ́A���łɓ����g�ƕ��k��Ƃ̋��͊W���`������������B���̓����g�Ƃ̘A�g�ɁA�������v��͑S�͂𒍂����B�v��ȊO�ɂ�������g��炪���S�ƂȂ��Ă����悤�ł���B[�P�P�X]���̂悤�Ɍ��Ă݂�ƁA�v��͎��H�^���ƂƂ����C���[�W�����ł͂Ȃ����ƂɋC�Â��B���̌���A���쓬����x�E�@���Ή^���A�w�����x�p�����Ή^���A60�N���ہA�ו��A�Ɓu�s���v�̗��ꂩ��̉^���ɎQ�����Ă������ƂɂȂ邪�A���̓s�x���_�I�ȍv�����ʂ��Ă���B���������Ӗ��ł́A���̓����A�u���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�Ő������@���A�u���_�I�F���𑫏�ɂ��Ď��H�^���v������Ƃ����e�[�[�����g�Ŏ��s�����Ƃ��l������B
�@�����āA���x���q�ׂ��Ƃ���A�v��ɂ�����u���a�_�v�Ɓu�s����`�v�́A�v��ɓ��݂��鍪�{�v�z�Ƃ�������̍�����o�Ă��Ă�����̂ł���B�������A���鎞���܂ŁA�v�쎩�g�͂��̂��ƂɎ��o�I�ł͂Ȃ������B�u�p�b�V�u�E���W�X�^���X�Ƃ������̂��������a�̘_���ł���B���ꂪ�ق�Ƃ��Ɏ��o����Ă����̂́A�E�E�E�Z�Z�N�Ȍジ���Ǝs���^�������Â��āA��������s���^���ƕ��a�^�������߂āA���W�X�^���X�Ƃ��Č��т��Ă���_�����o����āv�����炵���B[�P�Q�O]
�@�I���W�X�^���X�Ƃ��Ă̕��a�_�╽�a�^���Ǝs���^���̍��{�v�z�͓���ł���B�����āA���̃��W�X�^���X�̑O��Ƃ��āA�u����v�u�����v��w�i�Ƃ��鍑�Ƌ@�ւƑR�I�ȏ��W�c�E���g�D�̔������l������B�����������u����v�I�ȑg�D��n��グ��l�Ƃ́A�u���҂Ƃ̈�v�v��u���҂Ƃ̘A�сv���u�����A���́u�A�сv��͍����钆�Ŏ����̌���[�߂�u�l��`�v�I�l�Ԃł���B�����āA�u�A�сv�����߂鎞�́A�Љ�I���K���x�Ȃǁu�ɂ�������炸�v�l���A�т���̂ł���B
�@��N�́A�u�s����`�̐����v�ł́A�v��́u�s���v���ȉ��̂悤�ɒ�`���Ă���B
�@�E�E�E�g�s���h�Ƃ́A�g�E�Ɓh��ʂ��Đ��������ĂĂ���g�l�ԁh�Ƃ�����`�ɂȂ邾�낤�B�E�E�E�܂��A�E�ƂƐ����Ƃ̕������K�v���B�ǂ�����ǂ��܂ł������̐E�ƂŁA�ǂ�����ǂ��܂ł������̐��������������Ă��Ȃ�����������́A�g���I�l�Ԃ����܂�Ă��A�s���I�l�Ԃ͐��܂�Ă��Ȃ��B�E�ƂƐ����Ƃ��������Ă���A�_�����s���̗L�͂Ȉꕔ�������A�_�����s���Ƃ��ɂ����̂́A���{�̔_���ł́A���̗�����������܂��Ȃ肪���ŁA���̉��v���܂��āA���̕���������ƒn�ɂ����������炾�����B�E�E�E���܂͐E�Ƃ̑��̓����ɂ��낤�B���̓����Ƃ́A�E�Ƒg�D�͖{�����ƌ��͂Ƃ͖��W���Ƃ������Ƃ��B���ƌ��͂���̉��߁A���ƌ��͂̃e�R����̓x�����ɂ���ĐE�Ƃ̍�������߁A���ƌ��͂̍���ɂ̓A�v���I���Ɏア���{�̍����ГI�E�l�̏K�����炷��ƁA���̓����͂Ȃ��Ȃ��킩��ɂ������A���o����ɂ����A�������E�Ɛl�̎���I�g�D�ł���M���h�i���Ǝґg���j��c���t�g���l����A���̓����͎��ɂ͂����肵�Ă���B�M���h�͎��������̐E�Ƃ����ƌ��͂Ƃ͖��W�ɂ��錠�������������č��ƌ��͂��甃���Ƃ��āA����Ǝ����Ǝ��R�̕�̂ɂȂ����B���Ƃ�������Љ�A���Ƃ̒��ɂłĂ���Ƃ������ƁA���ꂪ�ߑゾ�B�E�E�E[�P�Q�P]
�@�v��{�l�����o�������Ƃ��A�풆�̑̌�����h���������{�v�z�����ӎ��I�Ɏp����Ă������̂ł��낤�B�v��̃��W�X�^���X�v�z�́A���{�v�z�ł���A�������ւ̃��b�Z�[�W�ł�����B�풆���ƈ�т��āu���W�X�^���X�v�́u�v�z�ƍs���v���L�����O�Ղ��₵�����͈ˑR�Ƃ��Ė������Ȃ̂�������Ȃ��B
�Q�|�R�|�R�D���������Y�ƕ��a�^��
�@�����āA�O�q�̋v��ƂƂ��ɁA���a���k�b������Ŏ��H�^���ɐϋɓI�ł������̂��A���������Y�ł���B[�P�Q�Q]�����́A���a���k�b�����̒��ł��A�ł��M�S�Ɋ������s������l�ł���B�������A���̊����ɂ́A�����Ɠ��ƌ����鎖�����������w�E�ł��悤�B
�@���_�����Ɍ����A�����͒k�b��̒��œ����Ƌ��s�Ƃ̒������̂悤�ȓ��������Ă����B�������A���̒������ɂ͋v���ێR�������邱�Ƃ����������A��ʎ���������̂Ȃ��A�����Ƌv��͉��x�������Ƌ��s���������Ă���B���Ȃ݂ɁA���a���k�b��̊������Ԓ��A�����Ƌv��͑����ɐe���Ȋԕ��ł��������Ƃ�t�������Ă������B
�@�܂��A���a���k�b��̎O�̐����̂����A�ŏ��̓�̋N���̔C�𐴐��������A�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�ł́A���̑��_��S�����Ă���B�����Ă܂��A�����i�K�ɂ����Ă��A�����͊e����ɏo�Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A���̔M�S�����f����B
�@�������ĕ��a���k�b��̊����ɋɂ߂ĔM�S�ł����������́A���{��ێR�Ƃ͂��ƂȂ�A����������H�I�Ȋ�����O���ɂ����Ă������Ƃ��q�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B���̓_���A���_�I�ɕ��a�����Ɋ�^���悤�Ƃ���ێR�Ƃ��A�����ĘJ���g���ɑ��ċ���������Ă������{�Ƃ��A���́u���H�^���ɑ���u���v��u��O�ρv�Ƃ������_�ő傫���قȂ���̂��������B
�@�����āA�O�q�����悤�ɁA�u���H�^���ɑ���u���v��u��O�ρv�Ƃ����_�ŁA�����ɋ߂��ʒu�ɂ����̂��v��ł������B����Ӗ��A�}���I�Ɍ����A���Ɓu��O�ρv�Ƃ����_�ł͖���Ƃ��߂��ʒu�ɂ����Ƃ�������B
�@���������Y�������������F�p��ɂ��A�����́u���v�z�v�ɂ�������̂��A�����]���Ă���B�u�u�����n�_�v���璊�ۓI�ȊT�O������u�C���e���v�ɔ������Ȃ�������ۂ���B���������A���r�o�����g�Ȏp���́A�����̂Ȃ��Łq���m�I�Ȓm���l�r�Ɓq���{�̏�����O�r�Ƃ����Η��}��������A�₪�Ĕނ̃i�V���i���Y���̍�����Ȃ��Ă����v[�P�Q�R]
�@���́u���m�I�Ȓm���l�v�Ɓu���{�̏�����O�v�Ƃ����}���́A�����̕��a�^�����������ł��������Ȃ��B�����Ă܂��A�u�����v�ɍD�������߂��Ƃ����_�ł��A�A�����J�N�w��m�I�w�i�Ƃ��Ă���Ƃ����_�ł��v��Ƃ̋��ʐ����w�E�ł���B�v�삪�f���[�C�ɑ傫�ȉe���������Ƃ͑O�q�������A�������܂��f���[�C�̓N�w�ɑ傫�ȉe�����Ă���̂ł���B�����āA�v��́u��O�v�Ƃ������̂Ɂu100���M���͂ł��Ȃ��v�Ƃ����C����������Ă͂������̂́A��{�I�ɂ͊��҂������Ă����ʂ������B
����ɁA�s�풼��ɐ����������߂�20���I�������ł��A�{�鉹��A��͓���j�A����D�v�A�ь����Y�Ƃ����������o�[�ɉ����āA�����̊��߂ŋv����Q�����Ă���B�v�삪��z���Ă���悤�ɁA���̓����̋v��Ɛ����́u�̒_���Ƃ炷�W�v�ł������B���a���k�b����������ȑO�̎����ɂ́A�v��̋��s�ɂ���l���w����20���I���������A�����Ŗ��ԑ�w�u�����J�Â��Ă���B
���a���k�b����ȑO�ɁA�����Ƌv��́u�̒_���Ƃ炷�W�v���`������Ă������Ƃ��A�̂��̂����a���k�b����ɑ傫�Ȗ�ڂ��ʂ����ƂɂȂ�B�����ɁA���a���k�b����������ȑO�ɁA�����͋g�삩��w���E�x�̏����i�C�O�������S���j���ȗ�����Ă����B���̔s��̔N�ɋg��Ɓw���E�x�̘b���������������Ƃ��A���ʓI�ɂ͐�����k�b��̊����ɓ����Ă������ƂɂȂ�B�����́A�w�킪�l���̒f�Ёx�̂Ȃ��ŁA�u�ォ��l����ƁA�s��̔N�̏H�ɋg�쎁�ɉ�A�w���E�x�ɂ��Ęb�������Ƃ́A���̎��̐����̈��镔�������肷�錋�ʂɂȂ����v�Əq�ׂĂ���B[�P�Q�S]�u���v�́u���镔���v�������w�����͌����܂ł��Ȃ����낤�B
�@���̂悤�ɁA���a���k�b��Ɋւ�����m���l�̒��ŁA�����͈��Ɠ��̗v�f���܂��݂ł���B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���̂��Ƃ́A��͂�A�풆�E�펞�̑̌���A�o�g�K�w�₻�̌o�����������Ă������u���v�z�v�̈ӎ��I�E���ӎ��I�e�����傫���B�����āA���a���k�b������̕����݉����Ă����ߒ��������Ă�����ŁA�d�v�Ȑl���ł��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��B�ȏ�q�ׂ����Ƃ���A�ȉ��ł͐������ǂ̂悤�ɕ��a���k�b��Ɋւ�����̂��Ƃ����_�A�����āu�O���ѕ��a�ɂ��āv�Ȍ�A���H�^���ɌX���Ă����܂ł̉ߒ������Ă������ƂƂ���B�������邱�ƂŁA�v���ێR�A���{��g��ȂǂƂ̕����I�ȊW������藝�����₷���Ȃ�Ƃ��v����B
�@�����̕��a���k�b��Ƃ̏o��́A�g�삩��̈˗��ł������B1948�N��9���A���Ƀ��l�X�R��������肵�Ă����g��́A��g�ʑ�������K�˂Ă���B�����́A�[���A�g�삩���n���ꂽ���l�X�R������ǂ݁A���l�X�R�����̒��ɓ���������T���C���Q�����Ă��邱�Ƃɑ傫�ȏՌ�����B
�@�����́A���̂Ƃ��̂��Ƃ������L���Ă���B�T���C�̂��Ƃ��ڂ����͒m��Ȃ��������������A�u�̂��w�҂��ۂ��A���͒m��Ȃ��B�������A�̂��Ă��A�̂��Ȃ��Ă��A�ނ��n���K���A�̐l�Ԃł��邱�Ƃ���v�ł���B�Ȃ����Ƃ����A�u�n���K���A�v�́u���Y���̍��v�ł���A�u���V�A�̑����̂悤�ȍ��̊w�҂��A���V�A�̏��F�Ȃ��ɁA�p���֏o�����ė��āA�������A���������d��Ȗ��ɂ��Đ����̊w�҂Ǝ��R�ɋ��������ȂǏo���锤�͂Ȃ��v����ł���B�Ƃ������Ƃ́A�u���V�A�ɂ���������v�Ƃ������Ƃ��l�����A�ǂ����Ɂu�����̈�v�_�v�u���a�����藧��_�v������Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����B
�@�����āA���̋g���}��Ƃ������l�X�R�����Ƃ̏o����A�u���ꂩ��\���N�ɘi�鎄�̐����̑����̕��������肷�邱�Ɓv�ƂȂ����B[�P�Q�T]
�@���̓����͂��łɁA�x�������̕�����A�����̓���̖��ȂǁA���ɑ����@�������債�����������ł�����B�����͓�������ɕ��a���k�b��ɎQ�����钆��D�v�ƁA����u�ܔN�ȓ��ɑ�O�����E��킪�N�邩�ۂ��v�Ƃ����q���������Ƃ����B[�P�Q�U]���Ԃ́A����قǐ[���ł������Ƃ������Ƃł��낤�B
�@�ł��邩�炱���A�����͐�̃��l�X�R�����ɓ���������B��Q�������T���C�̑��݂ɔ��ɗE�C�Â���ꂽ�B�����̔�������z�����w�킪�l���̒f�Ёx�̂Ȃ��ł́A�u�T���C�̖����������̍���̈ꕔ���������Ă����悤�Ɏv��ꂽ�v�u���l�X�R�̕����̉��l�́A�T���C�Ƃ�����l�̐l���Ɏς߂��ė����悤�Ɏv��ꂽ�v�Ƃ����悤�ɁA�T���C�̑��݂��������Ă���ӏ����U�������B
�@�k�b��̑g�D���̒i�K�ɂ����ẮA�����\���A������q�A�m�ȖF�Y���句�҂Ƃ������Ƃł������B����������͂�����x�܂Ō`���I�Ȃ��̂ŁA�l�I�Ⓦ���Ƌ��s�Ƃ̈ӌ������Ȃǂ́A�����ł͐����A���s�ł͋v�삪���S�ɂȂ��Đi�߂�ꂽ�B���ہA�g�D���̒i�K�ł́A�g��ƂƂ��ɋ��s�Ɠ����Ƃ̊Ԃ��������Ă���B����Ӗ��ŁA���ۂɊ��������l���������Ƌv��ł���Ƃ����_���܂��A�g��̍I�����̏؍��ł���ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@����Ɏv�z�I�ȑԓx�̓_�ł́A�u�v���v���u���a�v�̑O��ƍl����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�u���a�v��Ɨ��������Ƃ��čl����H���𐴐������L���Ă����B�v��̉�ڂɂ��A�����������I�Ȋv����ʂ��Ȃ����a�_���ێR�ƂƂ��ɋ��L���Ă����Əq�ׂĂ���B[�P�Q�V]
�@�����āA�g�D�����I�����k�b��́A�e����̉�������J���Ă������ƂɂȂ�B���������̉�ɏo�Ȃ��������́A�����̌o�ϕ���̉���L�������L�̂Ȃ��ŁA�u�݂��objectivists�Ƃł����ӂ̂��A�V�j�b�N�Ȍ�������B�K�b�J������v�Ə����Ă���B[�P�Q�W]
���̂悤�ɁA�k�b��ɎQ�������m���l�ɑ���ᔻ�I�����́A�w�킪�l���̒f�Ёx�̂Ȃ��ŎU���������̂ł���B�����Ɂu�����v�ɍD���������������A���悻�u�����v�Ƃ͒������u�m���l�v�ɔ��������������Ƃ������ł���B����ɁA�����������u�m���l�v�ɑ���ᔻ�⌶�ł���ɐ����̒��ł��܂Ƃ��Ȃ�����A�k�b���E���ǂ��납�A�����Ӑg���ĕ��a���ɏW���������Ƃ́A�����̕��a���ɑ���M�S�����w�E���邱�Ƃ��ł���ł��낤�B���������������́u�M�S���v�́A�k�b��̊w�҂ւ̌����Ƃ���������܂݂Ȃ�����A�����������̂ł������ƌ������Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤���B
�@�����āA1948�N��12���ɍs��ꂽ����ł́A�������܂Ƃ߂����Ă��A�O����}������ȊO�傫�ȏC�����{���ꂸ�A���F���ꂽ�B�O�q�̒ʂ�A�����͑����̕���ɏo�Ȃ��Ă������Ƃ���A�g��̂�����܂��˗��ő���ɁA���Ă��o���邱�ƂƂȂ����B�k�b��̒m���l�ɑ��锽�����炩�A���̑��Ă��u�ꏊ���������Ă��邤���A�����͎��̎咣�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ����v�Ǝv��ꂽ�B[�P�Q�X]�u���̕��͂́A���̑���łǂ̂悤�Ɉ�����̂ł��낤�B����͎����g�̉^���̂悤�Ɏv��ꂽ�v�Ƃ��L����Ă���B[�P�R�O]
�@����̂Ȃ��ŁA�������O��Łu�M�S�Ɂv���������Ă�ǂݏグ���Ƃ��A�k�b��̉���́A�������猩��Ζʔ����Ȃ��Ɗ������悤�ł���B�e����ł܂Ƃ߂��_�_���A�������u�M�S�Ɂv���������ĂŐܒ��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���Ɗ�����ꂽ����ł��낤�B�u�F�����\��v�ɂȂ�A�����Ɂu�G�ӂ̂悤�Ȃ��́v����������ꂽ�Ƃ����B[�P�R�P]����ȊO�ɂ��A�G�ӂ��������Ƃ������L�q��������B�������k�b�����ɑ��ĕ����Ă������������K�v�ȏ�ɁA�G�ӂ������������̂�������Ȃ��B
�@�����āA�H�m�ɂ��u�w�҂̐푈�ӔC�v��₤�����ɑ��Ă��A�u��́A�ǂ̕���̒N�����Ȕ��Ȃ⎩�Ȕᔻ���s�����̂ł��낤���v�u���ꂪ�����̕���ōs���Ă�����A���͕K��������L�q�����ł��낤�v�u����{���A�����̏������\���ڂ����͉������ł�����Ă�낤�v�Ƃ��Ȃ�ᔻ�I�Ɋ�����ꂽ�悤�ł���B[�P�R�Q]
�@����̂��ƁA�d���͂����ł͏I��炸�A�����͐����̋N�����s���Ă���B���̎����A�����ᔻ�I�Ȉӎ��Ő����N���̎d�����Ȃ��Ă����B���Ƃ��A�u�傢�ɔ���v�u�Ђǂ���J�Ȃ�v�u�U�X�Ȃ�v�ƋL����Ă���B�����́A�H�m�����[�Ƃ����A�u�O���v�ɂ������Ă��A�u���̐ȂŐ��������l�����������悢���̂��v�Ɠ��L�ɏ����Ă���B[�P�R�R]
�@����������ŁA����قǒk�b��ɔᔻ�I�Ȋ��������Ă��������ł��邪�A�k�b��̍�ƂɔM�S�Ɏ��|�����Ă������Ƃ��w�E�����B���ہA�����u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�͐��������������̂ƌ����Ă悢�B�����āA�����͐����ɑ��Ă��̂悤�Ɍ����Ă���B[�P�R�S]�u��������������ŏ����A����������ŗi�삵�����Ƃɂ���āA�������A���Ƃ����l�Ԃ̈ꕔ���ɂȂ����B���́A����������ŏ����Ȃ������l�ԁA�����ŗi�삵�Ȃ������l�ԂƂ́A�������A�����ʂ̐l�ԂɂȂ����v
�@�u�����v�Ƃ͂��悻�����̂���u�m���l�v�ɑ��锽�R����������ŁA���́u�m���l�v��������u�G�Ӂv�������Ă܂Ȃ��ꂽ�u�����v��i�삷�邱�ƂŁA���a���ɐ�S���鐴�������݂����B�u�m���l�v�Ƃ̑R�W���ӎ����������Ȃ�����A���́u�m���l�v�����̈ӌ����W�Đ������N������C���������ƂŁA�t���I�Ȃ�����u�����ʂ̐l�ԁv�ƂȂ��Ă����̂ł���B�O�q�����悤�ɁA�v��ɂ��A�u�����v�Ƃ́u�����ւ̑i�������v�ł���u��̓I�Ȏ��H�������ׂ����́v�ł���B�����āA����ȍ~�A�u�����ʂ̐l�ԁv�ƂȂ��������́A�������������ł͖O�����炸�A�v���Ƌ������Ȃ���A�u�����ւ̑i�������v�Ɓu��̓I�Ȏ��H�^���v��Nj����Ă������ƂɂȂ�B
�@�����́A�N�����M�S�Ɋ��������k�b�����̈�l�Ƃ������Ƃ�������ł��낤���A���ۂ���ȍ~�̐����͑��Z���ɂ߂Ă����B�ł��邩��A�u�\���N�ɘi���āA�Â��ȕ��̎��Ԃ������Ă��܂����v�Ɠ��L�ɋL���Ă���B[�P�R�T]���ہA�����͓����g�ƘA�g���ču��������x���s���ȂǁA���H�����ɐ�S���Ă��������߁A�����̕��a�_���̂��̂ɂ͓Ǝ���������Ƃ͌����Ȃ��B���Ƃ��A�����̎�Łu�ČR���͂����Ȃ��v�u�u�a��c�Ɋv�Ƃ����������_����������Ă���B����́A�ČR������u�a�_�����������Ȃ��ĈȌ�̘_���ł��邪�A���e�I�ɂ͕��a���k�b��̌��������̏Ă������Ɍ���Ȃ��߂��ƌ�����B�ڗ��̂́A�����Ɠ��́u�M�S���v�̕\��ł��낤���A�ČR���̖��ɂ��Ắu�S�����낢��Ɨ���A�����ɂ��Ȃ�v�u���͂��̋C�������ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�u���͂��̒ɂ݂����ƕ\��������悢�̂ł��낤���v�u�l�Ԃ͉��x����������悢�̂ł��낤���v�Ƃ�������I�ȕ��͂��U�������B���Ȃ�M���̂����������͂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A���e�I�ɂ͖}�f�ȕ��a�_�ł���Ƃ�������B[�P�R�U]
���̓_�́A���H�^�����u�����Ȃ�����A����̑O��Ƃ��āu���_�I���́v���������Ȃ������v��Ƃ̈Ⴂ�ł��낤�B�v��͑O�q�����悤�ɁA���H�^���ɃR�~�b�g������̂́A�w�푈�̘_���ƕ��a�̘_���x�Ƃ������_�I�Ȋ�^���Y��Ȃ������B�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̌�A�����͓��哬���Ȃǂ̔���n�^���ɂ����g������ăR�~�b�g���邪�A�����������R�~�b�g�̂������́A�v��ɂ��A�u�C���e���̎��ȕ����v�ƌ������ᔻ����Ă���B[�P�R�V]
�@�����āA1949�N�̌܌��ɂ́A�����g�Ƃ̘A�g��������g��A�v���𒆐S�Ƃ��Ďn�܂��Ă���B�����������A�g���Ƃ̘A�g�͋g��̓����̍\�z������l�����Ă������̂ł��������Ƃ͑O�q�����B�����āA�����g�Ƃ̘A�g�̂Ȃ��ŕ��a���ɂ��Ă̍u����e�n�ŊJ����邱�ƂƂȂ�B�k�C���A�X�A���A�R�`�A���m�A�a�̎R�A���ɁA�R���̊e�s���{���ōu�K��͍s��ꂽ�Ƃ����B[�P�R�W]
�@�����������A�u�a��肪�����ȋc�_�Ƃ��Ď��グ���A���a���k�b��������̂��߂̑����1949�N12���ɊJ�Â����B���̂Ƃ����A�����̓��L�ɂ́u���܂��s���ʁv�ƋL����Ă���B[�P�R�X]����͑����ƈႢ�A�u�S�ʍu�a�v���u�P�ƍu�a�v���Ƃ������f�����邱�Ƃ́A�����I�ȏd��ȈӖ��������Ă�����̂ł���A���a���k�b��́u���i�K��v�ɂ��������̂ł��������B���̎��A�I�[���h�E���x�����X�g�����́A�P�ƍu�a�������]�����Ă����B���̏ڍׂ͌�q���邱�ƂɂȂ낤�B
�@����̐������A�����Ɠ��l�A�����̋N���ɂ�芮�����ꂽ�B���̓��e�́A�u�S�ʍu�a�v�u�����v�u�R����n���v�Ƃ����L���Ȃ��̂ł���B���̐����N���̂Ƃ��̐S���𐴐��͈ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B[�P�S�O]
�@�E�E�E����̐����Ɠ����悤�ɁA�u�a���Ɋւ��鐺�����A�����̊Ԃɂ��A���R�̂��Ƃ̂悤�ɁA���̎d���ɂȂ��Ă����B�����́A�哹�|�l�̂悤�ȃW���[�i���X�g�Ƃ��ĕ邵�ė������Ȃǂ̏����ׂ����̂ł͂Ȃ������A�ƑO�ɏq�ׂ����A��炩������ς���ƁA�����������ł��������犸���ċN���҂ɑI�ꂽ�̂��Ƃ��v���B���́A���_�̎��R�����𐋂��Ď����čs�������ɁA���͂������ȊO�ɐ����̕��@�̂Ȃ��l�ԂƂ��Đ����ė����B�܂��A�����̈Ӓn���������̂ŁA�����鎞�ǂɕ֏悵�Ĕh��ɐU�������Ƃ��p���������A���̂��߁A�����̗v���ƊO���̗v���Ƃ͂̏�Œ��a������e�N�j�b�N�Ƃ������A���ꂪ�哹�|�l�̏����@�ł��邪�A�����g�ɂ��Ă����̂ŁA���낢��ȗ���̐l�������琬�镽�a���k�b��̐����̋N���ɂ́A���̃e�N�j�b�N�������͖��ɗ������̂ł��낤�E�E�E
�@�u�m���l�v�ɑR���u���a���v�ɔ��ɔM�S�Ɏ��g�����ɂƂ��āA�u�����v�I�ł���u�W���[�i���X�g�v�u�哹�|�l�v�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�͋������̂��������B
�@���̑����u�u�a���ɂ��Ă̕��a���k�b����v�����肳���ƁAUP��AP�Ȃǂ̊C�O�ʐM�Ђɑ��t������A�����̎�v�V����G������ɐ�������J���Ƃ������������Ă���B�Ɠ����ɁA�����͒n���ɍu����ɏo��������A���s�̕��a���k�b��̉�֏o�Ȃ�����ȂǁA���Ȃ萸�͓I�ɕ��a���Ɏ��g��ł��邱�Ƃ��킩��B[�P�S�P]
�@���̂悤�ɁA���������\���ꂽ1950�N��6���A���N�푈���n�܂�B����́A���a���k�b��ɂƂ��āA�傫�ȑŌ��ł������B�k�b�����́A���܈�x�A�k�b��Ƃ��Ă̗�����m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɒǂ����܂ꂽ�B1950�N��8��31���ɁA��O���̂��߂̑���J����Ă���B��O���u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̓��e�Ƃ��̈Ӌ`�Ɋւ��Ă͌�q���邱�ƂƂ���B
�@���������X�Ɣ��\���钆�ŁA�����̈�ʓI�E���ۓI�ȁu���a�_�v�̒i�K����A���X�ɐ����I�ɃR�~�b�g������Ȃ��悤�ȓƎ��́u���i�K��v���s����悤�ɂȂ�ƁA���̕��A�k�b��̒��ł̈ӌ�����������ȍ�ƂɂȂ�B
�@���ہA���������̓����̂��Ƃ���z���āA�u����̈Ⴄ�����o�[�̈ӌ��������傫�Ȏd���v�ł���A�����Ƌ��s�Ƃ̈ӌ������̍�Ƃ��܂��u�ς킵���v�Əq�ׂĂ���B���̂Ƃ��ɂ́A�����͓����Ƌ��s�Ƃ̊Ԃ��x�قlj������āA����ɉ�ɏo�ȂƂ������Z�̂Ȃ��ɂ������B[�P�S�Q]
�@���̂悤�ɁA��O���i���m�Ɍ����A�u�����v�ł��邱�Ƃ͑O�q�����j�N���̂��߂ɁA�k�b�����̒N�������̊����ɐ�S���������ł��������A����Œk�b�����ɑ���ᔻ�I�ӎ��͂��悢�拭�܂��Ă������B���Ƃ��A�w�킪�l���̒f�Ёx�ł́A���̂悤�ɏ�����Ă���B[�P�S�R]�u�����ނ�����������Ƃ���X�c�_���˂Ȃ�Ȃʃo�J�炵���B���Â����ɂȂ�B�����y����journalist�ɖ߂낤�B�c�Ɏ҂͌������v�u�c�Ɏґ����A�C���C������̂݁v�Ƃ����悤�Ȕ����ł���B
�@���̂悤�Ȓk�b��́u�m���l�v�ɑ��錙�������ł͂Ȃ��A�����͂Ƃ��Ƃ����a���k�b��̉��U��N�܂ōs���Ɏ���B���ǁA���̎��_�ł͉��U���Ȃ����ƂɂȂ������A���ɓn���ĉ��U�̒�N�������Ӗ��͑傫���B�O�q���������̎����_��������ƁA���a���k�b��̍��{�����ɑ��ẮA�^���̈ӂ�\�����Ă���B����ɂ��ẮA�����́u�{�S�v�ł���Ɣ��f���Ă悢�ł��낤�B�������A���a���k�b��́u�����v�u�v�z�v�ɂ͓��ӂ����A���a���k�b��Ƃ����g�D���̂ɑ��ẮA�Q���҂̑��l���Ƃ������Ƃ�A�u�����v�Ƃ͋�����u���A���ւɂ������Č������鉸���ȁu�m���l�v�������Ƃ������Ƃ�����A�����̕��a�_�Ƃ͋�����������̂Ɖf�����̂ł��낤�B������ɂ��Ă��A�����u�����v�����邾���ŁA�����Ȓk�b��ɂ͖O������Ȃ������Ƃ����_�͊m���ł��낤�B
�@���̓����̐S���𐴐��͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�P�S�S]
�@�E�E�E���a���k�b��̐����͐s�����A�Ǝ��͍l���Ă����B���O�̐��ǂ́A�k�b��̌����◝�z�Ƃ͖��W�ɓ����čs�����̂ŁA���̓������`�F�b�N����͂��������ɂ���킯�ł͂Ȃ��B����ɓ����čs�����ǂ�ǂ��āA�����L�Ӗ��Ȕ��������邽�߂ɂ́A�k�b��́A���X��������̐l�X�ō\������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�k�b��̉��l�́A�E���獶�܂ŁA���낢��ȗ���̐l�X���܂�ł���Ƃ���ɂ���B���낢��ȗ���̐l�X���܂݂Ȃ���A�ؔ��������ɂ��ċ��ʂ̌��������Ƃ��Ƃ���A�����Ă�����Ȃ��Ă������悤�Ȓ��ۓI�Ȍ��_�ɂȂ��Ă��܂��ł��낤�B���������C�̔��������́\�i���Z���X�Ȃ��́\��Z�ߏグ�邽�߂ɂ��A�����̋�J�͖��X�傫���Ȃ�ł��낤�B�悸�{�[�����Ȃ���t�b�g�{�[�����n�܂�Ȃ��悤�ɁA���ꂩ����A�悸���̏����������������āA���ꂪ�݂�ȂɏR���Ȃ���A��������̍�Ƃ͐i�܂Ȃ��ł��낤�B���́A�����{�[���ɂȂ�̂͑�R�ł������E�E�E
�@�����ɁA�k�b��́u�O���Ɍ��������͖w�Ǎs���Ȃ��Ȃ�v�A�����āA�u���ۂ́A���ɉ��U�����悤�Ȃ��́v�u�����������c����Ă���悤�Ɂv�������Ƃ��q�ׂĂ���B[�P�S�T]����ȊO�ɂ��A�u���ꂼ��̑�w�֖߂��čs�����Ԃ����c����A�ǓƂɂȂ�ߑs�ɂȂ��Ă����v�Ƃ����L�q��������B[�P�S�U]
�@���ہA�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�ȍ~�́A���a���k�b��̊������̂����Ȃ萨���������Ă����B���a���k�b��̉���́A�����̂悤�ɃW���[�i���X�g�����Ȃ��A�}�M���Y���炢�ł������B���̊}�́A���Ȃ݂Ɂu�O���ѕ��a�ɂ��āv�̂Ƃ��ɁA�k�b���E�ނ��Ă���B����ȊO�̉���́A�قƂ�ǂ�������w�̋����Ȃǂł���A�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�Ȍ�́A�Ƃ肽�Ăāu�O���Ɍ��������v�ɃA�s�[������킯�ł͂Ȃ��A��w�̌������⏑�ւɖ߂�҂����������B
�@�܂��A���a���k�b������v���Ƃ��āA�v��́A�u���̒i�K�i�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�Ȍ�̒i�K�\���p�ҕ�j�őS�̂Ƃ��ăR�~�b�g������@��������Ȃ���������v�������Ɖ�z���Ă���B[�P�S�V]�u�S�́v�Ƃ��ăR�~�b�g������@���͍��ł��Ȃ��قǁA�k�b������̕����݉����Ă��Ă���Ƃ������邾�낤�B
�@�������Ȃ���A�����͂����u�m���l�v�����Ƃ͈قȂ�O�Ղ�`�����ƂɂȂ�B�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�ȍ~�A���a�l���������h�Љ�}��GHQ�̗͂ŏo�������]���p���ƁA������v��͂����̊����ɐ��͓I�Ɏ��g�ނ��ƂɂȂ�B���ɍ��h�Љ�}����A�����ɋ��͗v��������A���ꂪ��̌_�@�ƂȂ��āA��̕��a�^���ɑ傫���R�~�b�g���邱�ƂɂȂ�B�����͈ȉ��̂悤�ȋ@��獶�h�Љ�}�ƘA�g���邱�ƂɂȂ�B[�P�S�W]
�@�E�E�E���́E�E�E�_�c�̊O�o��ŁA���h�Љ�}�̗�ؖΎO�Y���y�ѓ��{�J���g�����]�c��̍�������̗��K�����B�ܘ_�A��l�Ƃ��ȑO����m���Ă͂������A���̎��͈���Ό����̖K��ł������B�p�����́A�\������̏O�c�@�c���̑��I���̂��߂ɕ����l�ꓯ�̋��͂����A�Ƃ������Ƃł������B���͋��͂�����E�E�E
�@���̗�ؖΎO�Y�Ƃ́A�v�삪�s�풼�ォ��W��L���Ă������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���B
�������āA���̌�̐����́A�k�b��̐����̌����������̒��Ŋт����߂ɓ��哬����A���쓬���Ƃ��������H�����ɑ̒�������܂łɃR�~�b�g���Ă����A���̊����Ԃ�́u���a�Y�Ƃ̑�В��v�ƌĂ��قǂł������B[�P�S�X]
�@�Ȃ��A�����܂Ŏ��H�����ɑS�͓��������̂ł��낤���B����ɂ́A�l�X�ȗv�f�������I�ɗ��܂肠���Ă���ł��낤�B�u�����v�ւ̍D���A���m�I�ȁu�m���l�v�ɑ��錙���A���邢�͕��a���Ɂu�M�S�Ɂv���g���i��r���}�Œ��p�Lj��ƂȂ����o���Ȃǂ��l������B�����ƘA�g�������H�����ɔM�S�Ɏ��g�v��́A�����̂��Ƃ��ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B[�P�T�O]
�@�E�E�E�k�b��̃����o�[���w�҂����������B�w�҂����H�����ɏo�Ă������̂ł͌��������������Ȃ��Ƃ����̂ŁA���ւɓ��݂Ƃǂ܂�l�X������������ł��B����ɑ��������́A�V���Ђ̍őO���Ƃ����g����h�ɂ����āA�����m�푈�̐i�s�������̖ڂŌ��Ƃǂ��Ă����B�������ɂ́A�푈�̒��ŁA���ׂĂ��g��̂܂�h�Ƃ����ɐȑ̌����������̂ł��傤�B������A���a�^���A�s���I��R�^���ɑS�G�l���M�[�𓊓����ĉ�����Ƃ��낪�Ȃ������̂��Ǝv���܂��E�E�E
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�l�X�ȈӖ��ŁA�����͕��a���k�b��ɉe����^�����ƂƂ��ɁA�ێR���w�E���Ă���悤�ɁA���a���k�b��̕���ߒ��̂�����u��̋A���v�ł��������B[�P�T�P]
�Q�|�S�D�c���^�E����ɂ����镽�a���k�b��
�Q�|�S�|�P�D�w�҂Ɩ��O�Ƃ̘A��
�@�{�߂ł͈ȏ㌩�Ă����m���l�������A�u�푈�ƕ��a�ɂ�����{�̉Ȋw�҂̐����v��������������c���^�𒆐S�ɕ��͂��Ă����B�O�q�����͈͓��ł́A���a���k�b��ɎQ�������m���l�̐���_�I�ȍ��ق�A���H�^����u��O�v�Ƃ��������̂ɑ���v�z�I�ȌX���̍��ق𒊏o����悤�Ȍ`�Ō���i�߂Ă����B
�@����ȊO�ɂ��A�u�������a���k�b��v�Ɓu���s���a���k�b��v�Ƃ̍��قƂ������̂����R�Ƃ��đ��݂��Ă����B���s���a���k�b������[�h���Ă������҂ɁA���씎�ƍP��������������B�{�߂ł͂��̓�l�̂�������ɏœ_�Ă�ƂƂ��ɁA�u�����v�Ɓu���s�v�̍��ق͂����Ȃ���̂ł������̂��Ƃ������Ƃ���ȃe�[�}�Ƃ��Č����Ă������ƂƂ���B���a���k�b��̎O�x�̐����͂��邱�Ƃ��ܘ_�̗v�ł͂��邪�A�l�X�ɌX���̍��Ȃ�m���l�������ꓯ�ɉ������Ƃ�����ł̋c���^���܂��A�{�����̕����ł͏d�v�ł���B[�P�T�Q]
�@�܂��́A1948�N12���ɍs��ꂽ����̋c���^�𒆐S�Ƃ������͂�i�߂Ă����B���_���猾���A����ɂ����Ă͐���_�I�ȍ��وȏ�ɁA���H�^���ɑ���u����A�������a���k�b��Ƌ��s���a���k�b��Ƃ̊Ԃ̎v�z�I���ق������Ɍ��o������̂ł���B
�@���̑���ł́A���̖`���ɂ����Ēm���l�̐푈�ӔC��₢���������H�m�ܘY�̈ȉ��̂悤�Ȕ����Ŏn�܂邱�ƂɂȂ�B
�@�H�m�ɂ��A���l�X�R�̎Љ�Ȋw�҂ɑ��āA�u���{�̊w�҂��������ɂ���ɉ����邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����v�u���ɑ傫�����v������Ƃ����B[�P�T�R]�Ȃ��Ȃ�A���ɁA�u���{�ł͊w�҂̐ߑ��Ƃ������̂��܂��m���v����Ă��炸�A���̂��ƂȂ���K�v�����邽�߁B[�P�T�S]���ɁA�u���܂œ��{�̊w�҂́A�Љ�̒��ɂ����鎩�Ȃ̗���ɂ��ƂÂ��Ė{�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��̐ӔC���������Ȃ������v�̂ł����āA�u�l���ɑ��Ă����A�w�҂͍ł��[���ӔC�������ׂ��v�ł��邽�߁B[�P�T�T]��O�ɁA���{�̊w�҂����E�̉i�v���a�̂��߂ɍv�����悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�u�����͐₦���l���ɑ��ĐӔC�������čs�����Ƃ��K�v�ł���A���w�҂̌��_�Ɛl���Ƃ̊Ԃɋ����A�ъ�����肠���Ă䂭���Ɓv����ł��邽�߁B[�P�T�U]
�@���̉H�m�̔����̒��ŁA���̗��R�Ƃ��ċ������Ă���u�w�҂̐ߑ��v�u�w�҂̎��Ȕᔻ�v�̖��ɑ��āA���{�\������������������Ƃ������Ƃ͗L���ł���B�ŏI�I�ɂ́A�u�푈�ƕ��a�ɂ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�̑O���Ɂu�w�҂̐ߑ��v�̖��͐D�荞�܂�邱�ƂɂȂ�B
�@�����������w�҂Ƃ��Ă̎��Ȕᔻ�̈ӎ��͂���Ȃ�ɑ���ɂ����Ă����L����Ă����B�Ⴆ�A����ɎQ�������c���Γ�Y�́A����̂��Ƃ���z����Ȃ��ŁA�u�c�_�͏I�n�ْ��������M�������͋C�̒��ł����߂�ꂽ�B�v�u�m���l�̂�����ɂ��Đ[�����Ȃ𔗂��A�Ăт��̂悤�Ȑ푈���J��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���߂��C�����A���ׂĂ̂ЂƂ̔������狭��������ꂽ�B�v�Əq�ׂĂ���B[�P�T�V]
�@�u���ꂾ���̐l�тƂ��W�܂��ĕ��a�̖���_����Ƃ��������Ƃ́A��O�ɂ͂܂������z�������Ȃ��������Ɓv[�P�T�W]�̐V�N���������ƂƂ��ɁA����̋�C�ɒꗬ���Ă����u�w�҂̐ߑ��v�Ƃ����ٔ������W��I�ɕ\�������̂́A����̌㔼�ɂ����钆��D�v�̈ȉ��̔����ł��낤�B
�@�E�E�E���݂ł͂܂��������́A���a�ւ̈ӎu��\��������A���a����邱�Ƃ����Ɋy�ł���܂��B����A�y�Ȃ���łȂ��A����Ӗ��ł͕��a����邱�Ƃ��ނ���l�C�̂��邱�Ƃ�������܂���B�������A���邢�͋߂������ɕ��a����蕽�a�̈ӎu�����ɏo�����Ƃ��A���ɍ���Ƃ������������邩���m��܂���B���邢�͂����������_�ɑ��댯��������Ƃ�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂Ƃ��ɂ����Ă����������E�E�E�Ƃɂ����������a������Ă���l�X���A��������ł��܂�Ȃ��Ƃ������ƁA���ꂪ��ȓ_���Ǝv���̂ł���܂��B���悤�Ȃ��Ƃ����������Ƃ����̂��A���Ď��������A���̓_�Ō���Ƃ����ɂ��o�������邩��ŁA�����m�푈�O��Ɏ������͊m���Ɍ���Ƃ����Ɨ����Ɍ���Ȃ���Ȃ�ʂƎv���܂��B���̌o���ɓO���Ă��A�����������ܕ��a�����Ȃ���A���������댯�̏�ԂɂȂ����Ƃ��ɁA���̕��a����鐺���������Ȃ�Ƃ������Ƃł́A���̂��߂ɂ��Ȃ�Ȃ��E�E�E[�P�T�X]
�@�e�l�ɂ���Ē��x�̍��͂���A�����������w�҂Ƃ��Ă̎��Ȕᔻ�Ƃ�������͂����ނˋ��L����Ă����ƌ����Ă悢�B�t�Ɍ����A�����������ꗬ���Ȃ�����e�l�ɋ��L����Ă������炱���A�v�z�I�ȑ�������z���邱�Ƃ��ł����ƌ�����ł��낤�B
�@�H�m�������_�@�Ƃ��āA���̊w�҂̎��Ȕᔻ�͑傫�ȋc��̈�ƂȂ����B�����āA����Ɠ��l�傫�ȋc��̈�ƂȂ����̂��A�u�w�҂ƈ�ʖ��O�E��O�g�D�Ƃ̊W�v�ł���B���̖����߂����ẮA�傫���ӌ����قɂ��邱�Ƃ����݉����Ă������ƂɂȂ�B�Ƃ�킯�A���s���a���k�b�����̖����P���A�c������c�Ƃ������ʁX���A�w�҂Ɩ��O�Ƃ̌������J��Ԃ��q�ׂĂ���B����ɑ���`�ŁA�����Ă������̂��ێR�ł������B
�@�O�q�����悤�ɁA�H�m�́u�w�҂Ƃ��Ă̐ߑ��v�̖��ƂƂ��ɁA�u�w�҂Ɛl���Ƃ̘A�сv�̕K�v�������������Ă����B
�@����ɑ��āA�ێR�́A
�@�E�E�E�푈�ɂ���ĉ��瓾��Ƃ���̂Ȃ��l���Ƃ̌����Ƃ������Ƃ���������܂����B������A�������d�v�ł͂���܂�����ǂ��A���͂���ƕ���ŁA�ނ��낻�̑O������Ƃ��āA�Љ�Ȋw�ґ��݂̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V�������A�����Ƌٖ��ɂȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�E�E��ʖ��O�ɑi����Ƃ������Ƃ��K�v�ł���Ɠ����ɁA����ɕ���ŎЉ�Ȋw�̉��̒c���Ƃ������̂��������A����ΎЉ�Ȋw�҂���̘A�ёg�D�����Ɏ���A�Ƃ������Ƃ����ɕK�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��E�E�E
�Əq�ׂĂ���B[�P�U�O]���̑���̒��ŁA�u�w�҂Ɛl���Ƃ̌����v�ȑO�̖��Ƃ��āA�w�ґ��݂̘A�тƂ����������x���q�ׂĂ���B�ێR���A���ՂȌ[�֊�����ᔻ�I�Ɍ��Ă������Ƃ͑O�q�����Ƃ���ł���B����ɉ����A�풆�ɂ����錤�������ɑ���}����h�����߂ɂ��A�ێR�ɂƂ��ẮA�w�ґ��݂̘A�т̕����܂��挈�ł���Ǝv��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B��㒼��̒m�I���͋C����z���āA�ێR�́u�Љ�Ȋw�҂Ȃ������R�Ȋw�҂̉��̌𗬂Ƃ������́A��O�[�֊����̕��ɔM�S�ŁA�����}��Ƃ��Ċe�w�҂����т����̂ł����āA�e�w�҂̐��̈���z���āA�w�҂Ƃ��ĉ��Ɍ��т����������Ƃ͂������Ȃ��B�v�Əq�ׂĂ���B[�P�U�P]���̂悤�ȊێR�̔����ɑ��āA���s�̊w�҂𒆐S�Ɂu�w�҂Ɩ��O�Ƃ̘A�сv�����߂锭�������������o�����B�Ⴆ�A���s���a���k�b��̃��[�_�[�I���݂ł���A���씎�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�P�Ȃ鐺���ɏI���Ȃ����a�^���A���̎��H�̈��Ƃ��āA�Љ�Ȋw�҂����܂ŋ������邱�Ƃ�m��Ȃ�����������O�g�D�̖�����肠���v�邱�Ƃ��d�v�ł���B[�P�U�Q]�܂��A�푈�����҂ɑΉ����邽�߂ɂ́A��͂�u�����̑�O�g�D�̕K�v����肠���v��ׂ��ł��邵�A�����Ɂu�J���҂̊��S�Ȋ�{�I�l����ۏႷ��Ӗ��ł́A���ۘJ���@�\�̖��v����Ă���ɒl����Ƃ����B[�P�U�R]
�����ē��������s���a���k�b��̍P��������̔�����⑫���邩�����ŁA���l�X�R�����́u��ʂ̖��O�ɂ��i����Ƃ����ړI�������Ă���v�̂ł��邩��A�u�w�҂̖��ł͂Ȃ��A��ʂ̖��O�̖��Ƃ��čl���܂��ƁA���ꂾ���̂��Ƃł����O�̗����̒��ɐZ������A���̌��ʂ͌����ď����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�v�Ɣ������Ă���B
���������s���a���k�b��̓c���́A����܂ł̎Љ�Ȋw�҂́u���O�Ƃ̊Ԃɂ��鋗�����������v�Əq�ׂĂ���B�����āA�����P���A�c����́u�w�҂Ɩ��O�Ƃ̘A�g�v������̓I�ɏW�ďq�ׂ��̂��A���s���a���k�b��̏��c��Y�ł���B
�@�E�E�E�W���[�i���X�g�ɋ����邱�Ƃ��厖�ł���܂����A���킹�āA������҂���������Ƃ������A�w�҂��Љ�ɂƂт���ł����ĎЉ�狳�炳���K�v������B������҂��O�ɂ��ĕ����Â��邩�炢�낢��̖�肪�N��B���ɓ����Ă����āA�ނ��뎩�����������悤�Ƃ��邱�Ƃ��̐t���Ǝv���B���̂��߂ɂ́A���낢��̑g���Ȃǂ��A��̐���������̏�ł���E�E�E[�P�U�S]
�@���̔����̌�ɁA�c�����̈��{���A�u�w�҂����O�ƌ��т��čs���Ƃ������Ƃł����v�Ɣ����̈Ӗ����m�F���A����ɑ��ď��c�́A�u��̓I�ɂ����A�g���̒��ɓ����āA�g���̐l�����Ƃ����Ƌ߂Â��A��ʓI�̊S��[�߂čs���A�Ƃ������Ɓv�ł���ƕԓ����Ă���B[�P�U�T]�J���g���ɑ��Ă���قNJS�̋����Ȃ����{�ɂƂ��ẮA�Ȃ��Ȃ����L�̂��ɂ��������ł������̂�������Ȃ��B
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA���̕����v�V�I�E�i���I�Ƃ����Ӗ�����藝������̂��e�ՂƂȂ�ł��낤�B1948�N��12���̑���ɐ旧���čs��ꂽ�e����ł̕ɂ����Ă��A�ߋE�n���@������ł́u�w�҂ƈ�ʖ��O�Ƃ̘A�сv�Ƃ�������|�����荞�܂�Ă���B���̈���ŁA�����̊e����ł́A������������|�̕��f�ڂ���Ă�����̂͌�������Ȃ��B���Ȃ݂ɋߋE�n���@������́A�����P�����Q�����Ă�����̂ł���B
�������a���k�b��ł́A���{�\���E�c���k���Y�E�Óc���E�g�E�a�ғN�Y�Ȃǂ���\�I�ȉ���ł���A������s���a���k�b��ł͖��씎�ƍP���������̑�\�I���݂ł������B�g������̓_�𗝉�������Ől�I�����Ă����B
�@�����Ă܂��A�P���▖��͔N��I�ɂ͈��{��I�[���h�E���x�����X�g�Ƃقړ�����ł͂�����̂́A���̎��H�I�u������u�S�v�O���[�v�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��������Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B���̂��Ƃ��A�{�߂̋c�_��ǂ߂Ηe�Ղɔ[���̂������Ƃł���ƍl������B
�Q�|�S�|�Q�D�@���씎�ƕ��a���k�b��
�@�����āA�g�삪�n�߂ċ��s�ɖ����K��A���̑g�D��ɗ����ɁA����ɓ����̎Q���ҁA�܂���{��c���A�a�҂�̖��O���o�����Ƃ���A����̊炪�܂����Ƃ����B�����āA�g��Ɍ������āA�u�N�A�ڂ��Ɠc������Ƃ�������ɂ���Ǝv�����v�ƕ����Ԃ����Ƃ����B[�P�U�U]
�@���̂悤�ȋ��s���a���k�b��̖��씎�́A���ǂ̂悤�ȕ��a�_������Ă������̂ł��낤���B�O�q�����悤�ɖ���́A�P���ƂƂ��Ɋv�V�I�ȋ��s���a���k�b��̒��S�l���ł���B�@�w�҂ł��閖��́A���a���k�b��̂̂��ɂ��A�j�h�@���Ή^����A1958�N�Ɍ������ꂽ���@��茤����ɎQ������ȂǁA����т��ĕ��a�^����쌛�^���ɐϋɓI�Ɋւ���Ă����l���ł���B���a���k�b��ɂ��ϋɓI�Ȏp���ŗՂ�ł����悤�ł���B
�@����́A�O�q�����悤�ɕ��a����쌛�^���ɊS�������������Ƃ���A���a���ɂ��镶�͂͂���Ȃ�ɑ������M���Ă���B�Ⴆ�A�u���a�Ɛ��_�v�u���a�̂��߂̉^���v�ȂǁA�u���a�v�Ɩ��̂��_���␏�z���������B[�P�U�V]
�@����̕��a�_�ɂ������т��������́A����Ӗ��ł��̓����̂Ȃ��ł���B�u���a�v�Ƃ������t��S�ʓI�ɏ^���Ȃ���A�u�����v��u�����v�̗͂��K�v�ł���Ƃ������Ƃ��������Ă���B����������́A��������ɋ���Ă������̗��s��Ƃ�������u�������Ƙ_�v����b�ɂ��A�u���`�v������Ƃ����I�[���h�E���x�����X�g�̌X���ɉ��������̂ł������ƈʒu�Â��ĊԈႢ�Ȃ��ł��낤�B
�@�������������Ƃ́A�u�����͐V���@�̂��Ƃɕ��a�����D�������������ߖ���I�ȍ����Ƃ��Đ����Â��邱�Ƃ�O�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v[�P�U�W]�u�����͎��������Ă��̕��a�̂����������ʂ��˂Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ������������痝���ł���B[�P�U�X]
�@�u���������āv���ׂ����a�Ƃ������t�ɕ\��Ă���悤�ɁA����́u���a�v�ɑ���v������͑����Ȃ��̂�����B�O�ꂵ�ĕ��a�̏d�v�����J�肩�����Ă���Ƃ����_���t�ɖڗ������X���Ƃ�����̂�������Ȃ��B
�@�����������܂ł̘_���ł́A��͂蓖���̎x�z�I�ȁu�������Ƙ_�v�u���a���Ƙ_�v�̘H���ƋO����ɂ��Ă���Ƃ�����ۂ������B�������A����̈�т��������́A�u�������ꕔ�x�z�҂̂��̂ł͂Ȃ��āA���ׂĂ̖��O�̂��̂ł���ׂ����Ƃ�v������v[�P�V�O]�Ƃ����������ɑ�\�����悤�Ɂu��O�v�u���O�v���J��Ԃ��q�ׂĂ���Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ́A�O�q�����c���^�̌����痝���ł��邱�Ƃł���B
�@������_�A����̕��a�_�̒��œ����I�Ȃ��Ƃ́A�u�a�_�����������ɂ߂钆�ŁA�S�ʍu�a�̘_���Ƃ��āA�u���`�I�v�Ȋϓ_����A�W�A�ɒ��ڂ��Ă���Ƃ������Ƃł���B
�@�����1951�N10�����́w���E�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���{�����Ƃ��Ă̐؎��Ȃ˂����v�̒��ňȉ��̂悤�ɂׂ̂Ă���B�܂��A�u���{�͓��m�̈�p�Ɉʂ��A���{�����͓��m�����̈�v�ł��邱�Ƃ��m�F���邱�Ƃ���n�߂�B�����āA�u�������̎���������悤�ȍu�a���Ȃ��ꂽ��A����͐^�ɕ��a�������炷�����I�ȈӖ����������铹���v�͂Ȃ��B���Ȃ킿�A�u�����͂������A�W�A�Ȃ����A���u�A�C���h�̏����Ƃ̕��a�I�ȘA�g�������炷���Ƃ��ł��ʂ悤�ȍu�a�́A�^�̍u�a�ƌĂԂɒl���Ȃ��v�Əq�ׂ�B���ꂪ�A�o�ϓI�ȗ��R���炾���ł͂Ȃ��A�u���`�I�ɍl���Ă������ł���B�v�u���x�̐푈�ň�ԑ傫�Ȗ��f���������Q���������̂́A���Ƃ����Ă������̖��O�ł���B�v�u���̒����̖��O���ʂ��ɂ��ču�a�������̂ł́A���{�̓��`�I�ȐӔC���ʂ����Ƃ͂����Ȃ��B�v�ƌ��_�t����B���`�I�Ȋϓ_����̑S�ʍu�a�_�ł���B�S�ʍu�a�_�̒��Œ����Ƃ̊W���l���������͎̂U������邪�A�����͎�ɒ����Ƃ̌o�ϓI�W���ؒf����Ă��܂����Ƃւ̗J������ł������B���̈Ӗ��ŁA����̘_�͋����[�����̂ƌ����悤�B
�@�{�߂���́A���s���a���k�b��Ɠ������a���k�b��Ƃ̊W�������Ȃ���̂ł������̂��A�Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����Ǝv���B�����Ƌ��s�Ƃł͂��悻����Ă���v�z�X���͈قȂ��Ă����B�����Ă܂��A����̕��a�_���T���I�ɒ����B�������܂ł́A���{��Ƌ��L����ʂ��������A���H�I�Ȏu���Ƃ����_�ł͖��m�ȈႢ������ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���ł��낤�B
�Q�|�T�D���a���k�b��̐���
�@���̏͂ł́A1949�N��3���ɕ��a���k�b������ɔ������A1950�N��12���ɎO�x�ڂ̐����u�O���ѕ��a�ɂ��āv�Ɏ���܂ł̕��a���k�b��̂̊�����������B[�P�V�P]
�Q�|�T�|�P�D�u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v
�O�q�����Ƃ���A1948�N��12��12���ɖ����L�O�قœ����̍�������J�Â���A���l�X�R�����\���������ɉ����邩�����ŁA�u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�����c�E�쐬����A���N�́w���E�x�O�����Ɍf�ڂ����B���Ȃ݂ɁA���l�X�R�̐����͓��������N�́w���E�x�ꌎ���Ɍf�ڂ���Ă���B
�@���l�X�R�̐�����A�`L��12���ڂ��琬���Ă���B����ɁA���u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�͂P�`10��10���ڂ���Ȃ��Ă���B���{�̐����́A�����̍�������ɐ旧���A11������12�����{�܂łɂ킽���Ċe����ɂ����ă��l�X�R�����������������̂𐴐����܂Ƃ߁A�����Ŕ��\�E���c���A�����ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���̂ł���B
�@���l�X�R�̐����̊e���ڂ�v�ċL���Ɖ��L�̂悤�ɂȂ�B[�P�V�Q]
�E
A�@�푈���u�l�Ԑ��v���̂��̂̕K�R�I�s��I���ʂł��邱�Ƃ����������ȁ@�@�@
��؋����Ȃ��B
�E
B�@���a�̖��Ƃ́A�W�c�ԔT�����ƊԂ̋ٔ���N���������ɓ���\�͈̔́@�@�@�@�@
���ɗ}���A�Ăѐl���l����悷�邪���Ƃ��Ȃ��炵�߂邩�Ƃ��������ł���B���̂��߂ɂ́A�Љ�g�D�Ȃ�тɂ����̂��̂̍l�������̂ɂ����鍪�{�I�ω����̗v�ł���B
�E
C�@���͍R���ɓ����N��������邽�߂ɂ́A�ő���̎Љ�I���`���s�����@�@
���ɁA�ߑ�I���Y�͂Ȃ�тɎ����̗��p���v�悵�A�������邱�Ƃ��K�v�ł���B
�E
D�@���ƊԔT�����ƌQ�Ԃɂ�����ߑ�푈�́A���ォ�琢��p������Ă���@
���ƓI�����̐_�b�A�`���A�ے��ނɂ���Ă͂����܂��B
�E
E�@����́A���Ǝ�`�I���Ȑ��`�ςɍR������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�E
F�@����ɂ����鍂���A�L�ĂȌ�ʎ�i�̔��B�́A���E�I�A�ѐ��̑��i�������@
����̂ł���B�����̑�ʓI�ʐM��i��P�p���A���̏������Ɋւ��鐳���������𑣐i���邱�Ƃ����́A���A�̐ӔC�ł���B
�E
G�@�����Ȃ�l��I�W�c�Ƃ����ǂ��A�V���I�ɗ҂ł���Ƃ����؋��͂Ȃ��B
�E
H�@�Љ�Ȋw�҂́A���܂Ȃ��A�C�f�I���M�[�I�E�K���I����ɂ���Ċu������
����B
�E
I�@�Љ�Ȋw�ɂ�����q�ϐ���B�����邽�߂ɂ��A���ۓI�Ȍ����y�ы���v���O�@�@
�������K�v�ł���B
�E
J�@���ۓI�K�͂ɂ�����Љ�Ȋw�҂̋��͂��邢�͐��E�I�Љ�Ȋw�������̐�
�����K�v�ł���B
�E
K�@���q�͐푈�̔��B�ɔ����A�Ȋw�Z�p�̗͂����ݓI�ɗ��p���邱�Ƃ̏d�v���B
�E
L�@�u�l�Ԃ̊w�v�ł��鏔�Љ�Ȋw�Ԃ̏�ǂ��A�����邱�ƁB
����ɑ��ē��{���̐����͂ǂ��ł��낤���B�O�q�̂悤�ɁA���{���̐����͐��������Y������̑O�ɓ����Ƌ��s�̊e�����쐬�����A���̍ő���I�ȑ��Ă����Ƃɓ��c���ꂽ���̂ł��邪�A���_�����ɏq�ׂ�ƁA���̐����̑��ĂƂقƂ�Ǒ���͂Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B����́A�������ɑ���̉�c���e���R�������Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B����ɂ��Ă͌�q����B
���ʓI�ɂ́A���{���̐��������l�X�R�������p���������ƂȂ��Ă���B���Ȃ킿�A���{���̐����̂P�`�S�̓��l�X�R������A�`D�ɑΉ����A5�E7�E8�E10�͂��ꂼ�ꃆ�l�X�R����G�EK�EF�EE�ɑΉ����Ă��邱�ƂɂȂ�B�c���H�EI�EJ�EL�Ń��l�X�R���́A�Љ�Ȋw�҂̑��݈Ӌ`�⍑�ۓI�K�͂ł̋��́A���邢�͍��ۓI�ȎЉ�Ȋw�������̐ݗ��̕K�v�����q�ׂ��Ă���B����ɑ��A���{���̎c���6��9�ł́A�ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���B[�P�V�R]
�E�U�@�����́A���ݓ�̐��E�����݂���ƌ��������𗦒��ɔF�߂�B�����Ȃ��炱�̎����������ɕ��a�����{�I�ɕs�\�ɂ���ƐM����̂́A��Ȋw�I�ƒf�Ə̂��ׂ����̂ł��낤
�E9�@�����푈�́A�l�Ԃ���������������邽�߂ɗp�����́A�������ɂ߂Č��n�I�ȕ��@�ł���B���Ă��̕��@���L�����L���ƔF�߂��鎞�オ�������ɂ��Ă��A����͑S�����Ⴗ��
�@�����ɂ́A���炩�ɓ��{�̐푈�ɑ���u���ȁv�̐S��q�ׂ��Ă���B�܂��A�u���ݓ�̐��E�����݂��邱�Ɓv�͔F�߂邪�A����̓C�R�[�����a��s�\�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��Ƃ�����������A���̉e�����ɂ�����Ă������{�̓����̏�z�N����Εs�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B����ɁA�J��Ԃ��q�ׂĂ����悤�ɁA�������������z�͕��a���k�b������ňӌ��̈�v�������ł��������Ȃ��v�l�g�g�݂ł������B�܂��A�ȏ�̑���_�ȊO�ɂ��A���{�̐�������́A�����̓��{�ɑ��鎩�Ȉӎ���ǂݎ�邱�Ƃ��ł��鋻���[�����t������B����́A���{�̐����̒��ɂ́A�u��i���v��u�s�퍑�v�A�u�R����`�I�x�z�ɂ��r�p�v�ƌ��������t���U������邱�Ƃł���B�������A�s�풼��̌o�ϓI�E�����I�r�p�̕��i��w�i�Ƃ������t�ł���A���܂���̉��̓��{���̒m���l�������ǂ̂悤�Ȃ��̂ƌ��Ă����̂����������̂ł���ʼn߂ł��Ȃ��_�ł���B
�@�����������u��i���v��u�l�����v�Ƃ����ے�I�ȔF����������x�[�����Ă��邩�炱���A�u���a���Ɓv��u�������Ɓv�Ƃ������̂ɓ��{�̃A�C�f���e�B�e�B�����߂�������Ȃ������Əq�ׂ邱�Ƃ��ł���B
�@�ێR�́A���������̒m���l�̊�����ȉ��̂悤�ɉ�ڂ��Ă���B[�P�V�S]
�@�E�E�E�܂��푈�̎S�Ђ͐��X�����A���������̐푈�ɂ���ē��{��ߎS�ȏɂ��Ƃ����ꂽ���Ƃɑ��āA�E�E�E�m���l���m���l�Ƃ��Ă̐Ӗ����ʂ����Ă����̂��Ƃ����_�ŁA�E�E�E���Ȃ�ɐȔ��Ȃ���Ղɂ����āA���̋��ʂȋC���Ŋ��W�܂����Ƃ����������E�E�E�����̂ł��B�E�E�E�����ɂ��鋤�ʂ̐S��Ƃ������̂́A��͂���{���Ăт��̂悤�ȔߎS�Ȗڂɍ��킵�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����ʖ��肾���ł͂Ȃ��āA�E�E�E�����ɂ������A���E�ɂ������Ăǂ������d���ŐӔC���ʂ����Ă䂭�ׂ����Ƃ������Ƃɂ��Ă̔��ȂƐV�����o���̋C�����A�݂Ȃ����Ă����E�E�E
�����ɂ��A�w���E�x�n���O��̋g��Ɠ��l�A�s��ɂ��u�J�����v�Ɠ����Ɂu�����������}���悤�Ƃ��Ă��鎞��́A�Ȃ܂₳��������ł͂Ȃ������B�v�Ƃ����S��ɉ����A�m���l�Ƃ��Ă̎��Ȉӎ�������ɕێ����Ă��邪�̂́u�����v�����݂��Ă������Ƃ͖��炩�ł���B���̊���A����ƃC�f�I���M�[�̗�������f�����u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�Ƃ�����v�_�ɓ������B
�@���̂悤�Ȓm���l�̔��Ȃ͑���̓��c�ɂ����Ă����x�ƂȂ��q�ׂ��Ă���B�Ⴆ�Γ����Q�c�@�������H�m�ܘY�́A����̓��c�`���Łu����ꂪ�ߋ��ɂ����ĔƂ����߂���[���ɔ��Ȃ��A�����ď������������߂����J��Ԃ��Ȃ��Ƃ����V�������ӂ���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����|�̔��������Ă���B�܂��A��������@�w�������̐쓇������u�푈�������̊w�҂ɁE�E�E�ߑ��ɂ��Ĉ⊶�ȓ_�����������Ƃ͎����ł���܂��B�v�Əq�ׂĂ���B[�P�V�T]
�@���������A���a���k�b��̃����o�[�ɂ́A�펞���ɐ푈���͂̎d���������悤�ȃ����o�[�͓����Ă��Ȃ������B�N��������푈�ɒ�R�����҂������������Ƃɉ����A���̊w�҂��t�@�V�Y���ɔᔻ�I�Ȃ��̂����������B���a���k�b��́A�}���N�X��`�҂��甽����`�̃I�[���h�E���x�����X�g�܂ł��܂ނ��̂ł��������A���̎�`�咣�̈قȂ�҂������A�тł����w�i�ɂ́A�u�푈���Ȃɂ�������������鎞��ł����āA�܂���̂��̂Ƃ��ɂ����闧��̖��ł͂Ȃ������v�Ƃ������l������B[�P�V�U]
�@������ɂ���A�O�q�����悤�ɁA�u�푈��j�~�ł��Ȃ������v�Ƃ��u�����Ƃ��܂��푈�ɒ�R�ł����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������͋C�͊m���ɑ��݂����B����䂦�A�O�q�̂悤�Ȕ���������Q���҂��瑊�����ŏq�ׂ�ꂽ���߁A�������N���������ĂɁA���{�̒m���l�́u���ȁv���ׂ̂������܂ޑO�����������邱�ƂɂȂ����B���ʓI�Ɍ����A�����ɍł��傫�ȕω�����������̂��A���̑O���̑}���ł������B���Ȃ݂ɁA���̑O���������̎��M�ɂ����̂ł���B�O���͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B[�P�V�V]
�@�E�E�E�|���āA�������{�̉Ȋw�҂�����ڂ݂čł��⊶�Ɋ����Ȃ��̂́A�E�E�E���̕��a�����i���l�X�R�����j�Ɋ܂܂�Ă���@�����������L���Ă������ɂ��S�炸�A�킪�����N���푈���J�n�����ۂɂ������āA�͂��ɔ���Ȓ�R�����݂��ɗ��܂�A�ϋɓI�ɂ����h�~����E�C�Ɠw�͂Ƃ������Ă����_�ł���E�E�E
�@���ɁA�e����̓��e�Ɍ��y�������B�܂��A�����Ƌ��s�̌o�ϕ���ɋ��ʂ̂��ƂƂ��āA���l�X�R��C���ځA�܂�u�ߑ�I���Y�͂Ȃ�тɎ����̗��p���v�悵�A�������邱�Ɓv�ɑ��āA�����̕s�������푈�̒��ڂ̌����Ƃ��Ă��邱�Ƃ��B�����́A�o�ϕ���Ƃ�����傩��C���ڂɍł��傫�ȊS���������Ƃ́A���R�ł���ƌ���ׂ���������Ȃ����A���o�ϕ���u��̐��E�v�̋����̓���T��K�v���}���ł���ƍł������q�ׂĂ��邱�Ƃɂ͒��ڂɒl���邾�낤�B���l�X�R�����́A��̐��E�̍��قƂ��̋����Ɋւ��ďq�ׂĂ͂��Ȃ����A���̂��Ƃɑ��ē����̌o�ϕ���́u�l���̌��������^�����̂ł���v�ƒɗ�ɔ�]���Ă���B[�P�V�W]
�@�܂��A�����̖@������́A���{�̐푈�ӔC�̖��ɂ��āA�u�����A�푈�ӔC�̖�肪�����s��ӔC�Ƃ��Ă̂ݎ��グ���A���{�̔Ƃ������ۓI�߉߂ɂ��Ă̐ӔC�����r���������v�Əq�ׂĂ��邱�Ƃ������[���B[�P�V�X]�ǂ��炩�Ƃ����A���a���k�b��ɏW�܂����w�҂́u��w�ҁv�Ƃ��Ă̐펞���ɑ���u�����v�͋���Ɏ����Ă������A�����ɐ푈�ӔC������ƍl���Ă���҂͏��Ȃ������B�m���l�́u�����v��u���ȁv���ǂ��炩�ƌ����A�u�Ȃ������������E�C�������Ē�R���Ȃ������̂��v�Ƃ��u�ʂ����Ă���ł悩�����̂��낤���B�����ƁA���ɂ��ׂ����Ƃ��������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������`�I�E�ϗ��I�ȉ����ӎ��ł���B���������Ӗ��Łu�푈�ӔC�v�͈א��҂̖��ł���ƍl���Ă�����̂������Ȃ��������炱���A�����œ��{�̐푈�ӔC��Njy����悤�Ȍ�����悷�邱�Ƃ��ł����̂�������Ȃ��B
�@�܂��A��L�̊֘A�Ō����A�ł��푈�ɑ��ĐӔC�������Ă����͎̂��R�Ȋw�҂������B���R�Ȋw�҂͂��̊w��̐�����A�C�f�I���M�[�̔@�����킸�푈�ɋ��͂��Ă��܂����߁A���̕��u�����v�̔O���[�������Ƃ�����B�Ⴆ�A�u�l�ނɑ�Ȃ�ЊQ�������炵������܂ł̐푈�ɑ��āA�����́A���R�Ȋw�҂����Ȃ��Ƃ��ꔼ�́A�������d��ȐӔC��L���邱�Ƃ��͂�����\���������v�Ǝ��R�Ȋw�҂̕���ɋL����Ă���B[�P�W�O]���̂��߁A�����x�Ɠ����߂���Ƃ��Ȃ����߂ɂ��A�u���R�Ȋw�҂̍��ۓI���͂���ɕK�v�v[�P�W�P]�ł���Əq�ׁA���R�Ȋw����̃��[�_�[�ł���m�Ȃ����c��̍Œ��ɉ��x�����̂��Ƃ��������Ă���B
�@�Ō�ɁA�i�V���i���Y�����邢�͖��������̌��Ɋւ��ē����Ƌ��s�ł͑ΏƓI�Ȉӌ����q�ׂ��Ă���B�����̕��ȕ���ł́u���Ƃ̍��ۉ��͍������̖v�p��K�v�Ƃ��Ȃ��v[�P�W�Q]�Əq�ׁA�����̖@������ł͂���ɁA�u���������̌��I�ȑ��l���͐^�̍��ێ�`�Ɩ��������A�������Ă��̓��e�����L���Ȃ炵�߂���́v[�P�W�R]�Ƃ��āA�i�V���i���Y���ƃC���^�[�i�V���i���Y���̐ϋɓI�����̈Ӌ`���������Ă���B�ێR�ɂ��A���̌��́u�A�����J�I�����l���ɒ����ɕ��Ր���^����̂́A�C���^�|�i�V���i���Y���ł͂Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł���B[�P�W�S]
�@����ɑ��ċߋE�n�����ȕ���ɂ��A�u���{�ɂ����Ă͓`���Ƃ����Ă����͓`���ɂق��Ȃ�Ȃ����Ƃ��l�����A�܂������`�v�������s����ꂽ���Ăɂ����Ă����A����ȑO����̒����E�v�z�E���l�Ȃǂ�`���Ƃ��Ď�낤�Ƃ���^�����Ӗ������̂ł��邪�A�E�E�E���{�ɂ����Ă͂��̂悤�ȈӖ��̓`���͌��@���Ă���v�Ƃ��Ȃ�ے�I�ɏq�ׂ��Ă���B����ɍ���E�����̉��ǂ��v��˂Ȃ�Ȃ����Ƃ�A�G�X�y�����g�̕��y�̈Ӌ`��F�߂Ă���̂ł���B[�P�W�T]
�@�{�����Ŏ�ɎQ�Ǝ��ɂ��Ă���m���l�ȊO�ɂ��A�ǂ̂悤�ȃ����o�[���Q�����Ă����̂����m�F���Ă������߁A�ȉ��ɑ������̒k�b�������L���B
�u�����n�����ȕ���v
�@�@���{�\���A�V���S�A���������Y�A���c���q�A�W������Y�A�ߌ��a�q�A����D�v
�@�@�씎�A�{�鉹��A�{������A�a�ғN�Y
�@�u�����n���@������v
�@�@��c�i�A�L���M���A�쓇����A���ؔ��ځA�c���k���Y�A�ێR���j�A�X�R����
�@�u�����n���o�ϕ���v
�@�@�L�V�A���A������q�A�����P�ƁA�s���d�l�A��������Y�A�}�M���Y�A�X�R�F�Y�A�e���`���Y
�@�u�����n�����R�Ȋw����v
�������A�u�p�ʁA�x�R�����Y�A�m�ȖF�Y�A�n�ӌd
�u�ߋE�n�����ȕ���v
�v����A�K�����v�A�d���r���A�V���ҁA�c�����m���Y�A��c���v
�u�ߋE�n���@������v
�鑺�N�A���{����A���씎�A�c���Γ�Y�A�c���E�A�P�����A���c��Y�A�O�Ŋm�O
�@�X�`��
�u�ߋE�n���o�ϕ���v
�R�G�v�A�����F�A�V�����A�L�薫�A���a����A����F��
���̑��A�Óc���E�g�A��ؑ�فA�H�m�ܘY�i�ȏ�A55���j
�Q�|�T�|�Q�D�u�u�a���ɂ��Ă̕��a���k�b����v
�@��̌R�ɂ�铖���̑Γ�����́A1948�N�ɓ]�����ꂽ�B���̂̂��A�A�����J���́A���{�������ɐ����w�c�Ɏ�荞�ނ��Ƃ����_���A�u�a�̊�ڂƂȂ��Ă����B�����ȑ��͓��{�̍���������d�����đ����̍u�a���咣���A���h�Ȃ̌��O�͍u�a����֘A��茈�߂ʼn����ł���Ƃ��A1949�N10���ɂ́A�T���t�����V�X�R�u�a���̌��^�����A�����A�u�a���������ł��邱�Ƃ����\�����B[�P�W�U]
�@����ɂ��A���{�����őΓ��u�a���Ɋւ���c�_�����X�Ɋ����Ȃ��̂ƂȂ��Ă����B�����̕��a���k�b��͂��̓��N��12���Ɋe����œ��c���s������A12��21���ɓ����̘A��������J���A�u�u�a���ɂ��Ă̕��a���k�b����v�̑��Ă�����B���̑��Ă��܂��A���������Y�̎�ɂ����̂ł���A1950�N�́w���E�x3�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B
�@����̐����̓��e���Ȍ��ɏq�ׂ�ƈȉ��̒ʂ�ɂȂ�B[�P�W�V]
�P�@�u�a���ɂ��āA�������{�l����]���q�ׂ�Ƃ���A�S�ʍu�a�ȊO�ɂȂ�
�Q�@���{�̌o�ϓI�����͒P�ƍu�a�ɂ���Ă͒B������Ȃ��B
�R�@�u�a��̕ۏ�ɂ��ẮA�����s�N���A�����č��A�ւ̉�����~����
�S�@���R�̔@���ɂ�炸�A�@���Ȃ鍑�ɑ��Ă��R����n��^���邱�Ƃ́A��ɔ�����
�@�܂��A�����̖{�����ɂ́u�푈�̊J�n�ɓ���A����ꂪ���玩�Ȃ̉^�������肷��@����킵�����Ƃ��X�߂Ĕ��Ȃ��A�������A�����͎��Ȃ̎���ȂĎ��Ȃ̉^�������肵�悤�Ɨ~�����B�����A�����́A���a�ւ̈ӎv�Ƒc���ւ̈���Ƃɓ�����A�u�a���߂��鏔����T�d�Ɍ������A�I�Ɋe���̐����I������āA���ʂ̌����\����ɓ������v�Əq�ׂ��Ă���B
�@�u�����v�̕\���A�u�c���v�������邪�̂́u�S�ʍu�a�v�̈ӌ����A�e�X�̐����I������āu���ʗ����v�Ɏ������Ƃ������Ƃł���B
�@�������Ȃ���A�u�c���v�������邪�̂́u�S�ʍu�a�v���A���a���k�b������́u���ʗ����v�������ꂽ�̂��ǂ����͕ʖ��ł���B����̐����ł́A���l�X�R�����������̂Ƃ��āA�u��������̂Ȃ��v���e�ł������ƌ�����B�u���a�v���w�p�I�Ɍ�������c�̂Ƃ��āA�����I�ɃR�~�b�g���Ă����Ƃ������̂ł͂Ȃ������B
�@�Ƃ��낪�A���̎�����50���ȏ���z����V���m���l�������A�u�S�ʍu�a�v�u�����v�u�R����n���v�����������Ƃ��ďq�ׂ邱�Ƃ͏d�v�Ȑ����I�Ӗ���ттĂ�����̂ƌ��킴������Ȃ��B
�@���ہA����̐������ɂ����āA�c���k���Y��Óc���E�g�́A�u�S�ʍu�a�v�ɍ����]����^���A���a���k�b���͔����Ă���B
�@�������̒k�b�����z���Đ����͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�P�W�W]
�@�E�E�E���a���k�b��ɂ́A���܂��܂̗���̐l�������܂܂�Ă����B���̒����爽���Q�̐l������������A���{�\���A�a�ғN�Y�A�c���k���Y�A���ؔ��ځE�E�E���̃����o�[�ɔ�ׂāA���̐l�����͒P�ƍu�a�ɍ����]����^���Ă����E�E�E
�@�����A������`�̃I�[���h�E���x�����X�g�����́A�P�ƍu�a�ɔ�r�I�����]�����Ȃ��Ă����B���{�Ɍ����Č����A���炭������̈ӌ��̕������{�S�ɋ߂������悤�Ɏv����B
�@����ɁA�������̑���c���^�̔����ł���u�⑫�u�a���̘_�_�v�ňȏ�̎������e�Ղɗ����ł���B[�P�W�X]�u�⑫�u�a���̘_�_�v�̂�����ƁA����ɂ�����S����̑��ӂƂ��āA�u�S�ʍu�a���ł��]�܂����v�Ƃ����_���m�F����Ă���B�����A�u�S�ʍu�a���ł��]�܂����v�Ƃ��Ȃ�����A���ۂ͑S�ʍu�a�̉\�����������ς��鑽���h�ƁA�u���ې����̔����Ȏ���̂��߁A�����ɂ͐��N��v���A���͕s�\�ɋ߂��v�Ƃ݂Ȃ��u�����h�v�Ƃɕ�����Ă����B[�P�X�O]
�@�S�ʍu�a�ɑ��āu�s�\�ɋ߂��v�Ƃ݂Ȃ��u�����h�v�̍����Ƃ��ẮA�u�P�ƍu�a��嫂��A������̂̌p���ɔ�r����A�����̐ϋɓI�Ӌ`��L����v���̂ł������B���̑S�ʍu�a���u�s�\�ɋ߂��v�Ƃ݂Ȃ��u�����h�v���A�O�q�̃I�[���h�E���x�����X�g�����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�k�b��̒��ł́A�����܂Łu�����h�v�ł������B
�@����ɑ��āA�u�S�ʍu�a�̉\���������v�l����u�����h�v�̍����Ƃ��ẮA�u�P�ƍu�a�͎������̂̌p���v�ł���A�u�|�c�_���錾������v�����ȏ�A�|�c�_���錾�Ɂu�]���u�a�݂̂��e���`��������v�Ƃ������̂ł������B�܂��A����ȊO�̗��R�́A��Ɍo�ϓI�Ȃ��̂ł������B�܂�A�P�ƍu�a�����Ԃ��Ƃ́A�u���{�̌o�ϓI�����ɂƂ��Ď����̏d�v����L����v�u�����y�ѓ���A�W�A�����Ƃ̖f�Ձv������ɂ�����Ƃ������Ƃł���B[�P�X�P]
�@���̂悤�ȁA�u�S�ʍu�a���ł��]�܂����v�Ƃ����O��̏�ŁA�u�P�ƍu�a�v���u�S�ʍu�a�v���Ƃ����c�_�̍\�}�́A�k�b�������L�̂��̂ł͂Ȃ��B�����̑�V���̘_���Ȃǂ��A���Ă��u�S�ʍu�a���ł��]�܂����v�Ƃ����O��̏�Łu�S�ʍu�a�̌����\���v�̖��ƁA��̂̌p�����́u�Ɨ��v���Ƃ����_�����x�z�I�ł������B[�P�X�Q]
�@�����Ŋm�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͈ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃł���B���Ȃ킿�A�O�q�̂悤�ɓ����̕��a���k�b��́A�u��������̂Ȃ��v�����c�̂Ƃ��Č��Ȃ���Ă������߁A������`�҂���Y�n�m���l��}���N�X��`�҂܂łƂ������l�Ȏv�z�I�n�}�����A�u���ʗ����v�Ɏ��邱�Ƃ��ł����B
�@�������Ȃ���A�₪�āu�S�ʍu�a�v�u�����v�u�R����n���v�Ƃ��������I�ɃR�~�b�g������Ȃ������Ɏ���ߒ��ł́A�u��������v���u�\�ʉ��v���Ă��Ă��܂����Ƃ������Ƃł���B�Ǝ��F�̂Ȃ��u��������̂Ȃ��v�����c�̂��A�����F�̋����c�̂ւƑO�i�������قǁA���l�Ȏv�z�I�n�}�����u���ʗ����v�ɒH�邱�Ƃ�����ƂȂ�B
�@���ہA�قƂ�Ǒ傫�Ȕ����̂Ȃ����������ɂ���ׁA�����ł́A�u�S�ʍu�a�v�u�����v�u�R����n���v�Ƃ������m�Ɏ��������߁AGHQ�Ȃǂ����莋����邱�ƂɂȂ�B
�@�u�����̓��Đ��{���i�߂Ă����u�a�Ƃ͐����v�̓��e���������߁A�g�쌹�O�Y�̂��Ƃɂ́uGHQ�����ɂ������肩�A���{�̌x������@���Ȃ̓��R�ǂ�������点�āA���\�シ���A���X�ƑO��4�A5��ɂ킽���āA��̐����ɂ��ĐR�₳�ꂽ�v�Ƃ������Ƃł���B[�P�X�R]
�@���̓��e�͂قƂ�Ǔ������ɔ��\���ꂽ�Љ�}�̂��̂��A���e���i��ł������߁A�Љ�}�ȏ�Ɉ��͂�������ꂽ�B
�@�k�b������Ő���I�ȍ��ق�A���H�^���ɑ���p���̍��قȂǂ���薾�m�Ɍ��݉����Ă���̂́A�u�O���ѕ��a�ɂ��āv���\�Ȍ�ł���B�Ȍ��ɏq�ׂ�A���̂Ƃ��́A���a���k�b��Ŕ��\���������̓��e���A���ア���Ɍ��������̒��Ő������Ă䂭���A�ǂ̂悤�Ɍ��������ɃR�~�b�g����̂��Ƃ�������͍�����ߒ��ł̕���̌��݉��ł������Ǝv����B
�@�����āA���̑��������������̂��A�v��Ɛ����́u�����畽�a���k�b��̗��_�I�����������Ƃ����āA��͂茾���������ł͋�������A����������ƃA�s�[��������@�͂Ȃ����v�ƍl���A���������Ȍږ�̃_���X�ɐ�����n�����Ƃ����B[�P�X�S]
�@�������A���̈ȑO�̑����̒i�K�ŁA�����̕����݉����Ă����Ƃ����_���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������_�@�ƂȂ��āA�ꋓ�ɕ��Ă����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���X�ɕ���̉ߒ����i�s���A�u���ʗ����v��͍����Ă����ƈʒu�Â���ׂ��ł��낤�B���������Ӗ��ł́A���̑����̕��͂��Ӗ���������̂ł������B
�Q�|�T�|�R�D�u�O���ѕ��a�ɂ��āv
�@���a���k�b������\���������1950�N6��25���A���N�푈���u�������B�A�����J�́A�k���u�N���ҁv�ƒf�肵�A���A�R�̖��̉��ɎQ�킵���B���̐푈�͖k�R�ƍ��A�R�Ƃ̈�i��ނ��������A1953�N7���̋x�틦��܂łɁA�펀�҂Ɩ��Ԏ��ҍ��킹��460���l���̔�Q���o�����B
�@���{�ł́A�Љ�}��]�܂ł����A���A�R���x������\�}�ł������B�����āA��̌R�̑Γ���̐���̓]���͒��N�푈���_�@�Ƃ��Ċi�i�ɐi�݁A��R�����E���剻�H����180�x�]������邱�ƂɂȂ����B[�P�X�T]
�@���N�푈�シ���ɁA�}�b�J�[�T�[�ɂ��x�@�\�����̑n�݂̎w�߂��o�邱�ƂɂȂ�B�Ɠ����ɁA�ȑO���珙�X�Ɏn�܂��Ă������b�h�E�p�[�W���g�傷��B1950�N��7���ɂ́AGHQ�͋g�c���t�ɑ��āw�A�J�n�^�x�Ƃ��̌�p���̖������⊧���w�߂����B���N��8�����{�܂łɁA�V���E�����ЂȂǂ�704�l���Ǖ�����A11���܂łɊ��������ʊ�Ƃɂ܂ŋy�B�����ɁA�������⍑�J�E�����g�Ȃ�17�g����365���l�����W���A���{�J���g�����]�c������������B�������A���̑��]�́A1951�N3���̑�����ł́A���a�l�������f���邱�ƂɂȂ�B���̈���ŁA���E�Ǖ��̉����ɂ��A�����}�l����E�l�̑��������A���Ă������B[�P�X�U]
�@���������������ƍ��ۏ̋ٔ����́A���a���k�b��̃e�[�[�ł���u��̐��E�̕��a�I�����v�ɑ���d��Ȓ���ł���A���a���k�b��̂̊�@�ł��������B�O�q�����悤�ɑ����ɑ���ᔻ�I�����ƁA�k�b��ɑ��鈳�͂͌������A�u�O����̈��́v�́u��ρv�Ȃ��̂��������B[�P�X�V]
�@���a���k�b��͑����ŁA�����I�ɏd�v�ȈӖ���тт鐺�����o�������Ƃ͑O�q�����B�������A�u��̐��E�̕��a�I�����v�������܂Ŗ͍�����Ƃ����p���ɕω��͂Ȃ������ƌ�����B�����āA���N�푈�����������Ƃ��Ďn�܂������{�̓��O�̏ω��́A���́u��̐��E�̕��a�I�����v�Ƃ������{�����ɑ���d��Ȓ���Ƃ����`�ƂȂ����B
�@���̓����̂��Ƃ��A�ێR�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�P�X�W]
�E�E�E���a���k�b��A�͂��߂͒��ۓI��������o�����āA����ɋ�̓I�Ȑ����I���ɃR�~�b�g���Ă������Ƃ������́A�ނ���t�Ɍ��������̓�����������������A���a���k�b��̌����ɐ荞��ł����E�E�E
�@���̂悤�Ȓ��ő���s���A��O���u�O���ѕ��a�ɂ��āv���A1950�N�́w���E�x12�����Ɂu�����v�Ƃ����������Ōf�ڂ��ꂽ�B[�P�X�X]����͈ȑO�̓��̐����Ƃ͎�����ƂȂ�A���_�𐴐����A���͋y�ё��͂��ێR���A�Â���O�́E��l�͂͂��ꂼ��L���M���E�s���d�l�����M����Ƃ����A�l�����I�Ȉ�ۂ̋������̂ł������B���̕��A�e���M�S���҂̕��S�͑傫�����̂��������B�ێR��s����́A���̎��M�̂��߂ɎO���Ԃقǂ̍��h���͂�ʋl��Ԃł������Ƃ����B[�Q�O�O]���̒���ɊێR�́A�a�ɓ|����@��]�V�Ȃ������B
�@�܂��A����ȑO�̐����Ƃ͈قȂ��ڂ̓_�́A�u�����v�ł͂Ȃ��u�����v�Ƃ����������ɂ������Ƃł���B[�Q�O�P]�v��ɂ��A�ȑO�̓��́u�����v�ƈقȂ�A�u�O���ѕ��a�ɂ��āv���u�����v�Ƃ����̂́A�u���̎��H�͊e�����o�[�̎��R�Ȉӎv����ɔC�������v�Ƃ����k�b������̈ӌ����������炩���Ƃ����B�܂�A�u�����v�Ƃ́u�����ւ̑i�������v�ł���u��̓I�Ȏ��H�������Ƃ��Ȃ��ׂ��v���̂ł���B���̈���ŁA�u�����v�́A�u�����܂Ŏv�z�I�����v�ł���B�����āA�u��̓I�Ȏ��H�������Ƃ��Ȃ�ׂ��v�X�^�C���ō��㊈������̂��A�u�����܂Ŏv�z�I�����v�Ƃ����������Ŏv�z�I�E���_�I�Ɋ�������̂��Ƃ����I���̑O�ŁA�u�ǂ���̃X�^�C�����Ƃ邩�v�Ƃ������́A�u�k�b��̃����o�[�e�l�̎��R�Ȕ��f�Ɉς˂�v�Ƃ����Öق̗��������̎��������Ƃ����B
�@���̓�ґ���́u�Öق̗����v����A���H�������d������l�X�ƌ��������Ɏ��Ȑ�������l�X�̗��h�����܂�A���ꂼ�ꎩ���́u�����v�ɕ�����Ă������B
�@����Ɠ��l�̏��A�ێR�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�܂�A�u���{�搶�Ɠ����悤�ȍl�����������Ă���ꂽ��������A���a���k�b��̌������A�����̏̂Ȃ��Ŋт����߂ɂ́A��n���Ή^���ɂ��Q�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����ꂽ��������̂悤�ȗ�������a���k�b��̂Ȃ�����͏o�āv�����B�����āA�����������u����v���\�ʉ������̂́A�u��̉^���I�Ȃ��Ɓv�ł���Ƃ��Ă���B[�Q�O�Q]
�@���l�ɐ������A�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̌�̏������L���Ă���B�u���̌�A������͉��x���J���ꂽ���A�O���Ɍ��������͖w�Ǎs���Ȃ��Ȃ�A�₪�āA��������J����Ȃ��Ȃ����v�B������́u���U�����悤�Ȃ��̂ł������v�B[�Q�O�R]
�@�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�Ɋւ��Č��y�����ŁA�ł��d�����������Ƃ͈ȏ�̂悤�ɁA���́u�����v�����a���k�b��̒m���l���݂̊ԂŁA����ߒ��ɂ�����d�v�ȃ����N�}�[���ł������Ƃ������Ƃł���B
�@�����āA���Ɂu�O���ѕ��a�ɂ��āv�̓��e���ȒP�Ɋm�F���Ă����B�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�͑O�q�����悤�ɁA�S�̂̑��_�𐴐������Y�����M���A�ێR�����́E���́A�L������O�́A�s������l�͂�S�������B�Ƃ�킯�A���a���k�b��̌����I�ȗ���W�I�ɖ��炩�ɂ����̂��ێR�S���̑��́E���͂ł���B
�@�ȒP�ɓ��e���L���A�܂��u�푈�͖{����i�ł���Ȃ���A���͂��i�Ƃ��Ă̈Ӗ��������ȁv���A�u�푈�͂܂�����Ȃ��A�n��ɂ�����ő�̈��v�ƂȂ������䂦�ɁA�u�푈���ő�̈��Ƃ��A���a���ő�̉��l�Ƃ��闝�z��`�I�ȗ���́A�푈�����q�͐푈�̒i�K�ɓ��B�������Ƃɂ���āA�����ɍ��x�̌�����`�I�ȈӖ���тт�v���Ƃ��m�F�����B���̂����ŁA��̐��E�̋������\�Ƒ����邩�ۂ��́A����o�̑I���̖��A�v�l���@�̖��ł���Ƃ���B[�Q�O�S]
�@�����āA�l�X�Ș_�҂��p���Ă���u��̐��E�v�Ƃ����B���ȊT�O���A���̂悤�ɎO�ɂ킯��B�܂�A�u�C�f�I���M�[�Ƃ��Ă̎��R�����`�Ƌ��Y��`�̑Η��v�u�p�Ă𒆐S�Ƃ��鐼�����ƌQ�ƁA�\�A�𒆐S�Ƃ��鋤�Y��`���ƌQ�Ƃ̑Η��v�u�����̐��E�ŋ����Ƃ��Ă̕ă\�̑Η��v�ł���B[�Q�O�T]
�@�������āA�u��̐��E�̑Η��v���A���ꂼ��u��̐��E�v�Ƃ͉����A�u�Η��v�Ƃ͂ǂ������Ӗ��ɂ����Ă��Ƃ������f�̉��ɁA���̂悤�Ɍ��_�Â���B�܂�A�u�C�f�I���M�[�̑Η��͒����ɐ푈���Ӗ����Ȃ����Ɓv�u�C�f�I���M�[�ƕ������͂Ƃ��Ă̌����̍��ƂƂ̊Ԃɂ́A�M���b�v�����邱�Ɓv�u���R�����`�Ƌ��Y��`�Ƃ����}���ȊO�ɑ��̎����ł̑Η����������Ă��邱�Ɓv�u���E�̗L�͍����K�������ă\�̑Η��Ɠ������Ɛ[���őΗ����Ă���킯�ł͂Ȃ����Ɓv�u�ă\�����Ƃ��ɗ͑S�ʓI�Փ˂�������悤�Ƃ��Ă��邱�Ɓv�ł���Ƃ����B[�Q�O�U]
�@����ɁA��O���͂̌`����A�C���h�y�ђ����̏�ɒ��ڂ��A�u���E�����̗��ɉ��ɂ������錡���I�v�f�v�A���̌p���ɂ�闼�̐��̋ߎ����Ȃǂ��w�E���u�ă\���������ʂ��鋤���̊댯���̖��v��u���A�̖����v�ɑ�����҂�u�\�A�ɂ�����s���I���R�̐L���ƃA�����J�o�ς̌v�扻�ɂ�闼�̐��̐ڋ߁v�Ƃ������u��̐��E�v�̋����ɂ�����ϋɓI�_�@����o�����B[�Q�O�V]
�@���������v�l���@�A�u��̐��E�v�̋������\�ƌ������o�̎����ɂ���āA�u��̐��E�̑Η��v���u�s�\�v�ł���Ƃ���_����˂����Ƃɐ������Ă���B
�@�����������_�̐i�ߕ��A���Ȃ킿���̒�o�̎d���ɂ���āA�����ɑ���F�����ϗe����Ƃ����v�l�ԓx��A�ێR�炵�����̂ł���B�ǂ��܂ł��A���z�I�ȖړI��Nj����邱�Ƃ��A�t���I�ɂ�����āu������`�I�ȁv�ԓx�ł���Ƃ������Ƃł��낤�B
�@�������A����Ɠ����ɁA��L�̘_�_�̒��ɂ�����A�푈�̐��m�̕ω��Ƃ��A���a�Ǝv�l�ԓx�̖��͑����Ŏw�E����Ă�����̂ł�����B�܂��A�u��̐��E�̊W�𐫋}�Ɋ��Œ�I�Ɍ��邱�Ƃ͌��v�ł���A�u�����ڂŃv���X�e�B�b�N�Ȃ��̂Ƃ��Č��邱�Ɓv���d�v�Ȏv�l�ԓx�ł���Ƃ���F���́A�u�⑫�u�a���̘_�_�v�Ŋ��ɒ�o����Ă���B���̒��ł́A����ɁA�u�A�����J�̎��R��Ƃ����V�A�̋��Y��`�����ɑ����̕ω��𐋂�����A�o���̕ω������҂̕��a�I�����̉\���債����v���Ƃ�A�u���҂̊Ԃɒ����̐i�߂���\���v���������ƁA�u���҂̑Η��v�͐��E�����̒��Łu����I�Ȃ��́v�ł͂Ȃ��A��O���͂ւ̒��ڂ�������Ă���B[�Q�O�W]
�@���������Ӗ��ł́A�ێR�����M�����_�����A�ێR�̓Ǝ����ƂƂ��ɁA���a���k�b��̌����I�ԓx�̏W�听�ƈʒu�Â��邱�Ƃ��Ó��ł���悤�Ɏv����B
�R�D���a���k�b��̕���
�@�ȏ㌩�Ă����悤�ɁA���k������ɂ͐���I�ȑ����v�z�I�Ȕw�i�̍��ق𑽕��Ɋ܂�ł�����̂ł������B�Ƃ�킯�A���l���̉�z������A�����č��܂ł̘_������킩��Ƃ���u���H�^���ɑ���u�����v�Ƃ����_�͑傫�ȕ���_�ƂȂ���̂ł������B
���̎��H�����ɏ]�����邩�A����Ƃ������܂Ō��������ɏ]�����邩�Ƃ����̂́A�u���a�v�𗝘_�I���w��I�ɒNj����Ă������k��̃����o�[�ɂƂ��đ傫�ȕ���_�ł������B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A1949�N1���ɔ��\���ꂽ�u�푈�ƕ��a�Ɋւ���Ȋw�҂̐����v�ɂ����ẮA���̐������e�̓��l�X�R�����Ɣ�ׂĎ�̑���͌����邪�A��܂��Ɍ����ă��l�X�R�����Ƒ卷���Ȃ��ƌ�����B���̒i�K�ł́A�����܂ł��u���a�v�ɍ��߂�v���͗l�X�ł����Ă��A�u���a�v�𗝘_�I���w��I�ɒNj�����w�ҏW�c�Ƃ������摜�͈ێ�����Ă����Ƃ�����B
���ՂȔ�r�͊댯�ł��邪�A���̂悤�ȈӖ��ł́A�u���ȁv��u20���I�������v��u�v�z�̉Ȋw������v�Ƃ����������Ƌ��ʂ��镔�����������Ƃ�����B�������Ȃ���A�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���b�h�E�p�[�W�⒩�N�푈�E�u�a�_���Ƃ����������y�э��ۏ̕ϓ]�͋}���������B���k����m�ɐ����ɃR�~�b�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɁA���̏ω��͋}���ł������Ƃ�������B
���̎��ɁA�S�ʍu�a���n�߂Ƃ��镽�a�l�������ł��o���ꂽ���Ƃ�����I�ɑ傫�������B�܂�A����Ӗ��Łu���a�v�Ɋւ��Ċw�p�I�Ɍ������Ă���悩�����i�K���āA���m�ȁu���i�K��v���\��n�߂�Ɖ�����݂̍��ق��傫���������������傫�������ƌ��킴��Ȃ��B����ɂ����A��S�ʍu�a��m�ɑł��o��������u�u�a���ɂ����̕��a���k�b����v�́A�u�ΊO�I�v�Ȕ������傫�����̂����������A����ȏ�ɁA�k�b������ɂ����锽�����傫�������Ƃ��킴��Ȃ��B
������O�q�����Ƃ���ł��邪�A������`�҂̃I�[���h�E���x�����X�g�����́A�P�ƍu�a�ɍ����]����^���Ă����B���Ƃ��A�v��ɂ��A���{�́u�S�ʍu�a�����������A�S�ʍu�a�̖������̂܂܂ŁA��n��P�p���A�������ɂӂ݂��錋�ʂ̂����炷�s����ɐɊ����Ă����v�Ƃ����B[�Q�O�X]�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�u���H�^���ɑ���u���v�ȊO�ɂ��A���a���k�b����m�Ȑ����I�ʒu�Â������Ă��܂��悤�ȁu���i�v�����Ȃɑ����Ă����ɂ�āA���̒m���l�ɑ��Ĉ��{��c���k���Y�A�Óc�A�a�ҁA�c�����m���Y�炪�v�z�I�Ɂu�S�ʍu�a�v���痣�E���Ă������ƂɂȂ�B���̈���A�����������I�[���h�E���x�����X�g�����́A�u�S�ʍu�a�v�ɂ������Ă͉��^�I�ł��锽�ʁA�u�R����n���v�ɂ͊��S�ɓ��ӂ����Ă����B���������Ӗ��ł́A���{��̏�����u���a�v�̓����́A�u�S�ʍu�a�v�́u�����v�Ƃ����v�f�ł͂Ȃ��A�u�R����n���v�u�R����`���{��Δ��v�Ƃ����v�f�̕������������̂ł͂Ȃ����낤���B���ہA���N���̎҂�����̐������畽�k����Ă����̂͑O�q�����Ƃ���ł���B
����Ɠ����ɁA����̐������o���āA�����ɕ��k��������ꂽ���ォ��A������v��E�g���Ɠ����g�Ƃ̋������n�܂��Ă����̂����������Ƃ��o���Ȃ��B���������A���܂��s�������ł͋�������Ȃ����Ƃł��邪�A�k�b��̍\�z�i�K�ɂ����āA�g���Ƃ̘A�g���g�삪�\�z���Ă������Ƃ͌J��Ԃ��q�ׂĂ����Ƃ���ł���B���k��͂��̌�A1950�N�́w���E�x12�����Łu�O���ѕ��a�ɂ��āv�\���邪�A������1950�N��12���ɎЉ�}�́u���a�O�����v�����肵�A���N�̂P���掵��}���Łu�ČR�����v���������u���a�l�����v��ł��o�����ƂɂȂ�B�܂��A���]��1951�N��3���Ɂu���a�l�����v��ł��o���A�m���l�̉^�����J���^���ƌ��т��A���ꂪ�Љ�}���h�Ɏp����Ă������ƂɂȂ�B�v��́A���ڍ��h�Љ�}�Ƃ������}���͂ɌĂт�����̂ł͂Ȃ��A��������x���𗎂Ƃ��đ��]�ƘA�g���悤�Ƃ����Ɖ�z���Ă���B�����Ă܂��A�k�b��̌����E�����O���x���ɂ܂ŗ��Ƃ��Ď��H�I�ɐ������Ă������ƍl���Ă����v��ɂƂ��āA�����̑��]�́A�u���{�����̐��Ȃ������\���Ă���v�Ǝv��ꂽ���Ƃ��傫���Ƃ����B[�Q�P�O]�������A����������̐߂ŏq�ׂ��悤�ɁA�����͍��h�Љ�}����̗v���ŁA���h�Љ�}�Ɩ��ڂȘA�g���Ƃ�悤�ɂȂ�B
���Ƃ��A51�N6���̍��S�J�g�V�����Łu���a�l�����v�𐳎����c�������A���́E���R���H��͕��k��̎O��ɂ킽�鐺��������ŃK���ō���ɂ��A�����̑g�����ɓ����������B�����ē����g���A�吼�����E�������Ƃ����������Ƃ������A���k��̋v������Ƌ��͂��A���a�^����W�J���Ă������B���̌��ʂ��A�w�\�����E���ɑi����|�����q���Ăѐ��ɑ���ȁx�Ƃ��������Ɍq�����Ă����B
�����������̒��ŁA�����Ƌv��͎��H�^���ɑS�͂𒍂����B�v��́u���a���k�b��̂����̕����������o�����ȏ�A�s����O�ɑi������j�𗧂āA��������H���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂����B���������Y���Ƃڂ������́A�����ɗ͂����Ă������S�������v�Əq�ׂĂ���B[�Q�P�P]�v��Ɛ�����S������̒n���Ř_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�s�풼�ォ���l�̐l�ԊW�͌`������Ă����B����ɉ����A�O�q�������Ƃł͂��邪�A�u��O�v�ς�w�i�ƂȂ�A�����J�N�w�Ƃ����_�ɂ����Ă͋��ʍ������o����B�����́A�u�v���O�}�e�B�Y���̗��ꂩ��A�ڂ̑O�ً̋}�ۑ�ɑ��āA���肪�N�ł��낤�Ƃǂ�ȃC�f�I���M�[�������Ă��悤�ƁA��v�ł���咣������A�����ōs���̈�v���v�v�銈�����j�ł������B[�Q�P�Q]�v������������������̎p���ɂ͋������Ă����̂��낤�B
�@�܂��A�u�O���ѕ��a�ɂ��āv���o���Ă��炢�A�u���H�������d������l�X�ƌ��������Ɏ��Ȑ�������l�X�̗��h�����܂�A���ꂼ�ꕪ����Ă������v�Əq�ׂĂ��邵�A[�Q�P�R]�������u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̂��Ɓu���ۂɂ́A���ɉ��U�����悤�Ȃ��̂������v�u���a���k�b��̒��Ԃ́A���ꂼ���w�֖߂�A�ނ�ɉ���Ƃ͋H�ɂȂ����B�v�Əq�ׂĂ���B[�Q�P�S]
�@�ێR���j�́u�O���ѕ��a�ɂ��āv�Ȍ�A�a�C�œ��@�������A���H�I�ȉ^���Ɏ�Ɋւ��Ƃ����`�Ԃł͂Ȃ����_�I�ȃo�b�N�A�b�v�����Ă����Ƃ����`���Ƃ����B�v����u�ێR���j���a���̒����痝�_�I�o�b�N�A�b�v�������݂Ȃ��^���Ă��ꂽ�v�Ɖ�z���Ă���B[�Q�P�T]�����āA���{�͊��l���̉�z�����������Ƃ���A���悻���H�^���Ƃ͋����̉����l�Ԃł������B����͂���Ӗ��ł͓��R�̂��ƂŁA��O����̃I�[���h�E���x�����X�g�ł�����{�ɂƂ��Ă̑�O�ςƋv������̑�O�ςƂ͑������x�̋������������̂ł���B���{�́A�s���d�l�ƕ��a�̖��ɂ��Đ^��������_�����s��������M�O�Ƃ��A�u�S�ʍu�a�v��u�����v�ɔᔻ�I�Ƃ����_�ł͓���̒n���ɗ����Ă����_���lj����ďq�ׂĂ����B�܂��A�����P���͂��̌�����s�ŕ��k��̉�����������A��l�Ƃ����a�^���E���@�i��^���ɗ��_�I�Ȋ�^�����Ă������ƂɂȂ�B�����́A���́u�ێ��`�v�Ƃ����ʂł́A���{�Ɣ����ȑ��Ⴊ����A�܂��A�s�펞�ɂ��ꂼ��50��Ƃ����N��I�Ȗʂ�����v�����̕��a�^���Ƃ͔����ȑ��Ⴊ���݂����B�O�q�����悤�ɁA�������u�ێ��`�v���u�����Ȃ�����A�u�����v�̈��{��ƁA�u���s�v�̖���E�P����Ƃ͂܂����悻�قȂ�v�z������Ă���B
�@���̕��k��́A�u���@��茤����v�Ɓu���ۖ��k�b��v�ւƁA�����o�[����ւ����Ȃ��甭�W�I�ɉ������Ă������ƂɂȂ�B���k��̎����I�Ȋ������Ԃ͂R�N�قǂł������B�������A�����ɎQ�������m���l�����͕��k����o�āA���ꂼ�ꎩ�g�́u���i�v�𖾗Ăɂ��A50�N��ȍ~�̊����𑱂��Ă������ƂɂȂ�B�����āA���ꂼ�ꎩ�g�́u���i�v���K�肵�Ă������ŁA���]�⍶�h�Љ�}�ƘA�g���ĕ��a�^����E����^���ɃR�~�b�g���Ĕ����{�I�ȗ���ɗ����Ă����u��㖯���`�ҁv�Ƃ����F�������܂�Ă���B50�N��ȍ~�A���̂悤�ȕ��a���k�b��̕���ߒ��̗��ꂩ�畽�a�^���E�쌛�^���Ɍg�������A�̗�����ꊇ��Ƃ��āu�i���I�����l�v��u��㖯���`�ҁv�Ƃ��������̂����܂�Ă����A�m���l�ɑ����́u�_�b�v���`������Ă������ƂƂȂ����B����Ӗ��ł����A���a���k�b��̕���̉ߒ��������邱�Ƃ́A���́u�i���I�����l�v��u��㖯���`�ҁv�Ƃ����J�e�S���[���`��������̌_�@������������̂ł������̂�������Ȃ��B
�S�D���_
�@�S�|�P�D�@�m���l�̑��l��
�@�{�e�̋c�_�ɂ���āA���a���k�b��̉���ɂ�����l�X�Ȏ����ł̍��ق���[�ł����炩�ɂȂ����Ǝv���B�ȉ��ł́A�ȏ�̋c�_�����܈�x�m�F����B
�@�܂��́A����I�Ȕw�i�ł���B����I�Ȕw�i�Ǝv�z�I�Ȕw�i�m�ɕ������邱�Ƃ͕K�������o���Ȃ����A���{�����Ƃ��Č����ꍇ�A���Ⴂ����Ƃ̑���͖��m�ł���B�s�펞�Ɉ��{��62�ł���A�s�펞��30�ゾ�����ێR��v��Ƃ̎�X�̎v�z�I�ȍ��͖��m�������B���{��I�[���h�E���x�����X�g�́u���v��K�������ǂ����̂ƌ��Ă����킯�łȂ��A�������������ςƂ��������̂��ێR����Ƃ͑傫���قȂ��Ă����B
�@�����āA���x���q�ׂĂ����悤�ɁA���{��u�N���v�̎҂����ƁA���̒m���l�Ƃ��Ƃ́A�����u���a�v�Ƃ������t��p���Ă��Ă��A���̈Ӗ�������̂͂��ƂȂ��Ă����ƌ�����B���{��ɂƂ��āA�u���a�v�Ƃ͉������A�u�R����`���{�v�̕��������Ƃ����v�f�������ł���A�K�������u�S�ʍu�a�v��u�����v���Ӗ����Ă����킯�ł͂Ȃ������B
�@�����Ă܂��A�ێR��g���̐��ォ�猩�āA�I�[���h�E���x�����X�g�ɑ��鋭���ᔻ�I�ӎ��ӎ�������Ă������Ƃ����x�����Ă����B�I�[���h�E���x�����X�g�������A�u���`�v��u�������Ɓv�̗��O�̗L�����ɂ͉��^�I�ł������B���̈���ŁA���{����݂Ă��A�g�삽���́u�v�z�ƍs���v�ɂ́u���ӂ����˂�v�v��������Ă������Ƃ͑O�q�����Ƃ���ł���B�u����v�Ƃ��������ЂƂƂ��Ă��A���ɑ傫�ȍ��ق������Ă������Ƃ��킩��B
�@�����āA�ێR����{�ƁA�v��E�����Ƃ̌���I�ȑ���́A���́u��O�ρv��u�m���l�Ƃ��Ă̎��摜�v�ɋ��߂邱�Ƃ��o����B�{�e�ł��q�ׂ��悤�ɁA�����v�삪�A�m���l�Ƒ�O�Ƃ̌��т����������a�̖��ɂƂ��ďd�v�ł���Ƃ̖���N���Ȃ��ƁA�ێR�͂܂��͒m���l�̘A�сE�c���������K�v�ł���Əq�ׁA���́u��O�ρv�u�m���l�Ƃ��Ă̎��摜�v�̑��Ⴊ�_�Ԍ��邱�Ƃ��o����B
�@�����v��E������ɂƂ��āA���ɂ�����ً}�ۑ�̈�́A�u�m���l�Ƒ�O�v�Ƃ̌��т��ł������B�����͂�������A�u�����v��u��O�v�Ƃ��������̂ɍD��������Ȃ���A�u���v�ƑΛ����Ă������̂ł���B���������u��O�ρv�Ƃ����_�ł́A������قɂ��Ȃ�����A�����v��Ƃ����u���s�v�̒k�b�����Ɛ����Ƃ����u�����v�̒k�b�����Ƃ͋߂��ʒu�ɂ����ƌ������Ƃ��ł���B
�@���̈���ŁA����I�ɂ͋v��Ƌ߂��ێR���A���Ղȁu�[�֊����v��ᔻ���Ă������Ƃ����Ă����Ƃ���ł���B�����ɂƂ��ẮA�ێR��́u�����v�Ƃ͂��悻�S���I�ɋ����̗��ꂽ�u�m���l�v�Ƃ����悤�Ɏv��ꂽ�ł��낤�B���̊ێR�́A�u�m���l�Ƒ�O�Ƃ̌��т��v���u����������A�ނ���u�m���l���݂̘A�сv�������咣���Ă������Ƃ����Ă����Ƃ���ł���B���̎咣���܂��A�ێR�̐푈�̌����瓾��ꂽ���ݒ�ł��낤�B�v����푈�̌�����w�сA���̊����ɐ������Ă������u���m���l�v�̈�l�ł��邪�A���́u���ݒ�v�͊ێR�Ƃ͂��悻���ƂȂ���̂��������B
�@�����āA��������u���H�^���ɑ���u���v���̍��ق������Ă���B���̎��ɉ����Č����A�v��Ɛ����́A�Ƃ��ɕ��a���k�b��̌����������ɐ��������߂ɁA�����g��J�g�A���h�Љ�}�Ȃǂƒ�g���Ă����B�ێR�́A���a���k�b��̌����E�������u���_�I�v�ɒNj����Ă����A�v�����قǂɎ��H�����Ɋւ�����Ƃ͌����Ȃ��B���{�́A���̎�����u��O�ρv���猾���āA�������������H�����Ɏ�̓I�ȎQ�^����Ƃ͌����������B�����P�����A���a�^���ɍS���Ă������҂����ł��邪�A�v�����̊������j�Ƃ͂��悻�����̂���m���l�ł������B
�@�Ō�ɁA�u�����v�Ɓu���s�v�̒k�b��̒��ł��傫�ȍ��ق����o����B�u�����v�̒k�b��͈��{��a�ҁA�c���k���Y�Ȃǂ̉�����嗬�ł���A�u���s�v�ł͊v�V�I�Ȗ����P���炪���̑�\�ł���B�����������_������A�u�����v�Ɓu���s�v�̈ӌ�������A�k�b��́u���i�K��v�����炩�ɂȂ�ɂ�A���邢�͒��N�푈�Ƃ��������O�̎������N����ɂ�A����ɂȂ��Ă������B
�@���̂悤�ɁA�k�b������ɂ����āA���̗l�X�ȃ��x���ł̍��ق͌����������B�ȏ�q�ׂĂ������Ƃ��ȒP�ȃ}�g���b�N�X�Ƃ��Č����}�������ƁA�ȉ��̕\�T�̂悤�Ȃ��̂��쐬���邱�Ƃ��ł���B
�\�T
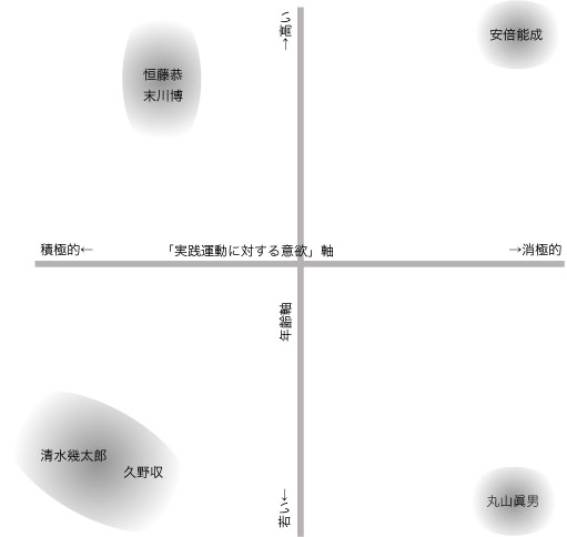
�@���悻���̕\�T�̂悤�ɗ����o����ł��낤�B�{�����Ŗ��炩�ɂ����������̂́A���̂悤�ȍ��ق�����A�ǂ̂悤�ɂ��́u���فv�����݉����Ă������̂��Ƃ����ߒ��ł���B
�@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A��������k�b������ɂ����ẮA���ق������Ă����B���ꂪ�A���������O���ւƎ���Ȃ��ŁA���X�ɂ��̍��ق����݉����Ă��������Ƃ����߂ė�������悤�B
�S�|�Q�D�u�����v�Ƃ����R��
�@�������A�ȏ㌩�Ă����悤�ȓ����ɂ����鍷�ق������ł������ŁA�k�b��͔��ɔM�S�ɁA���̐����̔��\���s�����B�Ⴆ�A�ێR������̎��̂���G�s�\�[�h���ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B[�Q�P�U]
�@�E�E�E����S�̉�c�̐ȏ�ŁA�L��L���搶�����̂������ɍ����Ă��āA���̉�͋������ȁA����ȂɔM�S�ȉ�Ƃ����̂́A���܂�Ȃ��ȂƁA����ꂽ�̂��A�o���Ă��܂��E�E�E
�@���ق����Ȃ�����A����Ȃ�ȏ�ɔM�S�ɒk�b��͐����\���Ă����B���̗��R�Ƃ��ẮA�펞���A�e�m���l���o���o���Ɍ��j���ꂽ�̌�����A�m���l�������W�܂��ċ����������s���Ă��������Ƃ��������悤�B��㒼��́A����������������e���ł������������ꂽ���Ƃ��悭�m���Ă��邱�Ƃł���B
�@�Ȃɂ����A�푈���́A�u�M�S�Ɂv�c�_�ł���悤�ȕ��͋C�ł͂Ȃ������B�N�ɖ��������̂��킩��Ȃ��悤�ȏł���A���_�e���������������B���̂悤�Ȓ��ŁA�����Ɋw�҂��u�W�܂��āv�c�_�����邱�ƂȂǂ͂ł��Ȃ��B���̂悤�Ȕ��ȑ��ꂵ�����������ꂽ�Ƃ��������傫���Ǝv����B
�@�����āA�{�����ł��A���т��ь��y���ꂽ�悤�ɁA�m���l��M�S�Ɍ��т����R�тƂ��ẮA�m���l�Ƃ��Ắu�����v�����������݂����B�ێR�́u�ߑ���{�̒m���l�v�̂Ȃ��ŁA�u���������́v�Ƃ����e�[�[���o���Ă��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�Q�P�V]
�@�E�E�E�푈�ɔ����Đh���ڂɂ����������̒m���l�ł������A���������̂�������Ƃ͂����������ɓI�Ȓ�R�ł͂Ȃ����A���قƉB�ق��ꎩ�g���͂Ƃ����ȋ^�̖ڂł݂��鎞��ł͂������Ƃ͂����Ȃ���A��X�̍��ɂ͂قƂ�ǂ����ɑ��郌�W�X�^���X�̓����������������Ƃ��A�m���l�̎Љ�I�ӔC�̖��Ƃ��Ĕ��Ȃ��˂Ȃ�Ȃ��A�������ꂪ���{�ɂ����錠�͂�A���I�ȁu���_�v�ɂ��������R�̓`���̕s���ɗR�����Ă���Ȃ�A�����͓��{�́u�����ׂ��ߑ㉻�̐����v�̃��_���̗����ᖡ���邱�Ƃ���A�V�炵�����{�̏o���̊�b��Ƃ��͂��߂悤�ł͂Ȃ����B���{�̒��ʂ���ۑ�͋��̐��̎Љ�ϊv�����łȂ��A����ꎩ�g�́u���_�v���v�̖��ł���\���������l������u����܂Œʂ�ł͂����Ȃ��v�Ƃ����C���́A�͒m���l�̑��������Ƃ炦�Ă����A�Ǝv���܂��B�E�E�E�m���l�̍ďo���\�m���l�͐��̊k���z���Ĉ�̘A�тƐӔC�̈ӎ������ׂ��ł͂Ȃ����A������������̊g����A��������͂���Ɂu���������́v�ƌĂԂ킯�ł��E�E�E
�@�����������A�u�����v��R�тƂ����u�����v���Č��������Ă����Ƃ����m���l�Ȃ�̖͍����s�풼��ɂ͎U�����ꂽ�B�ێR�͂܂��A���a���k�b��ɂ��āA�m���l�̎��Ȕᔻ�Ƃ����u���ʊ��o�v�����������炱���A�{�����Ō��Ă����悤�ȁA�l�X�ȃ��x���ł́u���فv�����z���āA�u�W�܂蓾���̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂĂ���B[�Q�P�W]
�@�����̕��a���k�b��ɂ����Ă��A�����������u�����v�Ƃ�������L�͂ɍL�����Ă������Ƃ́A�{�����̒��ł��т��ь��y���Ă������Ƃł���B���������Ӗ��ł́A�u���a���k�b��v�Ƃ����A�펞���ɒ�R�����m���l���W�܂��������c�̂��̂��̂��A�u���������́v�̂ЂƂƂ��Ēł���̂ł͂Ȃ����Ƃ��l������B�푈�̌����瓾���A���炩�́u�����v���s���̃o�l�ɂ��ďW�܂����m���l���{�����ň������҂̒��ɂ͎U�������B
�@�������܂��A���܂��܂ȁu���فv�����z�����т���R�т��u�����v�Ƃ����u����v�ł��邱�Ƃ́A���݂ł������݂ł��������B���R�̂��ƂȂ���A�u����v�Ƃ������̂͌��������̈��͂̒��ŁA���邢�͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɂu�����v���Ă������̂ł���B�ێR���A�u�ߑ���{�̒m���l�v�̂Ȃ��ŁA�u���������́v�Ƃ��Đ��������Ƃ������Ƃ��A���̋����̂́u���E�v�ł���A�u�S�̂̌X���Ƃ��ẮA�푈�̌�����������悤�ɁA�u�����v���܂����̗���̌o�߂ɂ���ĕ�����Ƃ�Ȃ������v�Ə����Ă���B[�Q�P�X]
�@���a���k�b����܂����l�ɁA�u�����v��R�тƂ����u���������́v�Ƃ��Đ����������ʂ��傫���������A�t���I�Ȃ��炻�́u�����v�̕����ɂ���āA�m���l�̕����݉����Ă������Əq�ׂ邱�Ƃ��ł���ł��낤�B
�S�|�R�D�u�i���I�����l�v�Ƃ����ď�
�@���̂悤�ɁA�u�����v���u�����v���Ă����ɂ�A�t���I�Ȃ��畽�a���k�b��̂Ȃ��́u���فv�����݉����Ă������ʂƂȂ����B�O�q���Ă����悤�ɁA�O�x�̐������o�������ƁA�k�b��S�̂Ƃ��āA�ǂ̂悤�ɕ��a���ɃR�~�b�g���Ă����̂��Ƃ������@��������Ȃ������Ƃ������ʂ�����B����Ɠ����ɁA�O�x�ڂ́u�O���ѕ��a�ɂ��āv���u�����v�Ƃ����������ł͂Ȃ��A�u�����v�Ƃ������������Ƃ������Ƃ����̕\��ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B
�@���̂悤�Ȓk�b��̍s���l�܂�̒�����A��́u�A���v�Ƃ��āA�v������ɑ�\�����悤�ȁA���H�^���]�⍶�h�Љ�}��ƒ�g���A���a����쌛�^���E����^���Ɏ�̓I�ɃR�~�b�g����m���l�Ƃ����������n�o����Ă������ƂƂȂ�B
�@�ێR�ɂ��A�i���I�����l�́A�u�Љ�}�E���Y�}�E���]���̌����̐������͂ƌ��т��A�����������{���ΐ��́v���u�x�����Ă���ҁv�ƌ��Ȃ���Ă���Ƃ����B[�Q�Q�O]�����āA�u�i���I�����l�v�Ƃ����p��́A���A�Ƃ�킯50�N��ȍ~�ɍ��ꂽ���̂ł�����B
�@�{�����ɂ�����A�k�b������̕���ߒ��̈�̋A���Ƃ��āA��ɋv���E�����炪���h�Љ�}��]�ƘA�т����a�^���ɃR�~�b�g�����ʼnE���ł���B�ێR�͂ǂ��炩�Ƃ����A������u���āu���_�I�Ɂv�o�b�N�A�b�v���Ă������ʂ̕��������B���������Ӗ��ł́A�̂��̂��ɂȂ��Đ��ݏo���ꂽ�u�i���I�����l�v�Ƃ������̂̓����ɁA�����Ƃ����Ă͂܂�̂́A�v�����Ƃ������ʁX�ł���B�t�ɂ����A�v������̊�������u�i���I�����l�v�Ƃ������̂��`������Ă������ƌ�����B
�@����ɂ��ւ�炸�A�\�T�ł��w�E�����悤�ɁA�v�����Ƃ͋֗~�I�Ɉ�����悵�Ă����ێR���u�i���I�����l�v��u��㖯���`�ҁv�Ƃ������t�́u��\�i�v�Ƃ��āA�̂��̂��ᔻ����Ă������Ƃ������Ƃ����킹�Ďw�E�ł��悤�B�ł��u�i���I�����l�v�Ƃ����J�e�S���[�`���Ɋ�^�����v������Ƃ������ʁX�ł͂Ȃ��A�ێR���ᔻ�̑ΏۂƂ��ꂽ�̂͂Ȃ��Ȃ̂��Ƃ����^�₪�����Ă�����Ȃ��B�ʂ����āA�u�i���I�����l�v�Ƃ͂����������҂ł���̂��B���̗p��������{�ɂ������́u�_�b�v�ł��邾�낤�B���́u�_�b�v�̌`���ߒ��̂킸����[�ł��A�{������������Ƃ��낪����̂�������Ȃ��B���������Ӗ��ł́A���a���k�b��ɎQ�������m���l�̕���̋O�Ղ́A�u�_�b�v�̌`���ߒ��ł��������Ƃ������Ƃł��낤���B���̂��ڍׂȓ_�́A����̉ۑ�Ƃ��Ă��������B
��