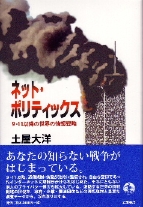
『ネット・ポリティックス―9・11以降の世界の情報戦略―』
岩波書店
2003年6月10日
本体2400円+税
ISBN4-00-001797-7
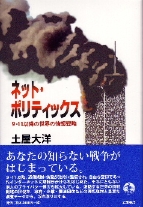 |
土屋大洋 『ネット・ポリティックス―9・11以降の世界の情報戦略―』 岩波書店 2003年6月10日 本体2400円+税 ISBN4-00-001797-7 |
はじめに:市民への危機
2003年3月20日(日本時間)、ついにアメリカは国連決議案を取り下げ、イラクに侵攻した。イラク時間午前五時半過ぎの最初の攻撃は、大量爆撃の予想に反してピンポイントで行われた。CIA(アメリカ中央情報局)の情報に基づいて、会議中と思われるイラクのサダム・フセイン大統領を狙ったのである。
攻撃開始の一月ほど前には、コリン・パウエル米国務長官がニュースの主役になっていた。アメリカ東部時間の2月5日、ニューヨークの国連安全保障理事会外相級会合でパウエル長官は、イラクの国連決議違反の証拠を並べ立てた。人工衛星がとらえたイラク施設の写真、イラク政府の役人と見られる人物たちの電話の会話の録音テープなどである。
この席でもパウエル長官の後ろには、ジョージ・テネットCIA長官が控えていた。CIA長官は、CIAを統括するだけでなく、アメリカの「インテリジェンス・コミュニティ」全体を統括する役目も持っている。あの席にテネット長官がいたということは、アメリカのインテリジェンス・コミュニティが総力を挙げて情報を集め、それを提示しているのだと暗に訴えていたのである。そして、4月7日には、CIAがフセイン大統領の所在情報を得てからわずか45分で目標のレストランに爆弾を落とした。本稿執筆時ではフセイン大統領の行方は不明だが、その直後、イラクの首都バグダッドは米軍によって「解放」され、戦局の大勢は決したかに見える。
2003年3月のイラク戦争は、インテリジェンス・コミュニティがかつてないほど前面に出てきた戦争といえよう。
日本ではインテリジェンス・コミュニティは正確に訳されていない。情報機関や諜報機関、あるいは情報体制とされているが、「インテリジェンス」は「情報」でも「諜報(相手の情勢などを秘密裏に探って知らせること)」でもない。それは「情報を精製した結果作られる判断・行動のために必要な知識」である。インテリジェンス・コミュニティは国家の安全という問題意識でつながっている政府機関の集まりである。個々の機関に焦点を置けば、この場合コミュニティの訳語は「機関」になるし、複数の機関の集合性に注目すれば「体制」にもなるだろう。
インテリジェンス・コミュニティにはどうしても後ろめたいイメージがつきまとう。その活動のひとつにスパイ活動があるからである。日本人の感覚では、スパイは表舞台に立てない裏の世界の住人であり、できればかかわりたくない存在である。
しかし、アメリカ人の感覚では必ずしもネガティブなものだけでもない。例えば、最近ワシントンDCにできた国際スパイ博物館に行ってみると、子どもたちにスパイとは何かを教え、むしろスパイであることに誇りを持たせようと、さまざまなアトラクションや仕掛けが施されている。インテリジェンスの活動は知的なものであり、高い知性を持つ人がその役割にふさわしいという感覚が少なからずあるようだ。自分の持つ高い知性を国家の安全保障のために使うことは、戦場で戦うのと同じくらい名誉なことなのだ。
アイビー・リーグの秀才たちが、ビジネスの世界での成功や、学者としての名声を求めるのではなく、インテリジェンス・コミュニティに入って「静かに国家に奉仕する」のも価値ある選択とみなされている。世界で最も多くの数学者を雇っているのは、インテリジェンス・コミュニティの支柱を担うNSA(国家安全保障局)だといわれるのもおそらく事実であろう。NSAはアメリカの暗号解読と防諜を担っており、暗号解読には数学的素養が不可欠である。
インテリジェンス・コミュニティの役割は、国家の安全を保障するということに他ならない。アメリカのインテリジェンス・コミュニティは第二次世界大戦終了後にその形を整え、冷戦を戦い、現在に至っている。彼らがいなければ、良いか悪いかは別として、冷戦の様相は変わっていたかもしれない。
しかし、もともとインテリジェンス・コミュニティのない世界を想像するほうが無理かもしれない。人が争う限り、それは存在し続ける。国家にとって、外交と安全保障そして戦争を優位に展開するにはインテリジェンス・コミュニティが不可欠だからである。
ところがいま、そのインテリジェンス・コミュニティが、市民にとっての自由な情報インフラであるインターネットを脅かしつつある。20001年9月11日の対米同時多発テロ(9・11)を機に、われわれには縁遠い存在だったインテリジェンス・コミュニティと、市民を代表とするインターネット・コミュニティの間に「見えない戦争」とでもいうべき軋轢が起こっているのである。
インターネット・コミュニティは、これまでいくつかの転機を迎えてきた。まず、1990年代以降、参加者の数が増え、グローバルなネットワークになるとともに、その文化的・社会的背景の違いゆえに異質な考え方が入ってきた。その結果、インターネットは放って置いてもつながるものではなく、政治的・制度的な差異を越えてつなげる努力をしなくてはならないものになった。
また、当初インターネットは学者やエンジニアたちが使うネットワークだったものが、商用利用が拡大するにつれ、ビジネスの弊害が目だってきた。ビジネスは市場の拡大と独占を本質的に求める。その結果、インターネットをここまで成長させてきた技術革新(イノベーション)が阻害され始めている。
そしていま、国家のセキュリティの高まりによって、通信の傍受や規制を認める法制化が進み、インターネットの自由とプライバシーが危機にさらされている。もはやインターネットは自由なメディアではなくなりつつあるのだ。
国家の「安全・秩序」を使命とするインテリジェンス・コミュニティ、そして、インターネットという新しいグローバルなメディアが可能にする精神的「自由」を擁護しようとするインターネット・コミュニティ、このまったく性格の異なるふたつの情報コミュニティがぶつかるきっかけとなったのが9・11だった。
インターネット・ガバナンスが抱える問題は自由とプライバシーだけではない。インターネットが現実社会において存在感を増すにつれ、既存の政治組織と離れて自律してはいられなくなっている。インターネット・コミュニティは、自分たちの望むインターネットの姿を維持・発展させていくには、立法府、行政府、司法府という現実の政治の場で訴えていかなくてはならない。
そして、かつての「サイバースペースはグローバルであり、インターネットは国境を超えて人々を少なくとも意識のレベルでつなげることができる」という展望も妥当性を失いつつある。各国でインターネットに対する情報戦略はまったく異なることがわかってきた。インターネット普及を推進するにしても、各国それぞれの社会情勢との関係で取り組みが行われ、人々をむすぶことがそれほど容易なことではないということも見えてきている。
本書のねらいは、9・11以降、大きく変化し続けるインターネットのガバナンスをめぐる政治力学(ネット・ポリティックス)を考察することである。本書は大きく4部に分かれている。第1部はインテリジェンス・コミュニティとインターネット・コミュニティとの「見えない戦争」について論じている。第2部はインターネット・コミュニティがアメリカ社会の中で試行錯誤しながら政治的影響力をどう拡大させつつあるかを論じている。第3部はブロードバンドの普及を軸にグローバルな視点で、アメリカ、中国、韓国、アイルランドがどのような情報戦略をとろうとしているか、そして無線=ワイヤレスの利用をめぐっていかなる問題が起こっているかを扱っている。第4部は現実の政治に対してインターネット・ガバナンスが内在する問題と将来像を論じる。
人は今や情報なしでは生きられない。われわれは常に五感で情報を知覚し生きている。インターネットや電話、新聞、雑誌、テレビ、中吊り広告、料理の香りや彩り、景色の移り変わり、人との会話、あらゆるものが情報としてわれわれの脳を刺激し、その刺激がわれわれの生活に影響を与えている。インターネットはもはやアメリカ軍のサバイバル・ツールでも学者の余技でもない。われわれ市民の生活の一部になりつつある。インターネットはわれわれがこれまで得られなかった情報、得るのに時間やコストがかかった情報をいとも簡単にもたらし、われわれの可能性を広げてくれた。
本書に一貫する問題意識は「大きく揺れ動く世界の情報戦略のなかで、インターネット・コミュニティがどのように変わりつつあるか、それはなぜなのか、そしていかに変容すべきなのか」ということである。
この問題が重要なのは、インターネット・コミュニティの動向が、インターネットのガバナンス、ひいては情報社会に生きるわれわれの市民生活に深刻な影響を引き起こすからである。