

世の中でよく出回ってりる勉強法、”覚えるのではなく、理解する”は、実は大変なのです。それは、多くの場合理解するのに必要な前提知識がそもそも欠けているからです。本塾では、独自のメソッドにより”理解するために必要な前提知識”を長期記憶として蓄えることから始めます。そして、上の写真にあるよに、1,2,3.と知識をつなぎ合わせ答えを導き出す思考力(矢印の部分)を養う、というように段階的に生徒を育みます。
理解ができるのは最低限の知識があるから。誰がなんの話しをしているのかが分かっていて初めて理解ができます。なので、最低限の知識をまず覚えることが大切だと確信しています。本宿ではこの前提を大切にしていますので、今から一つ身近な例を出します。そしてその次に具体的にどう授業を進めていくのかの2つの例を順に出していきます。
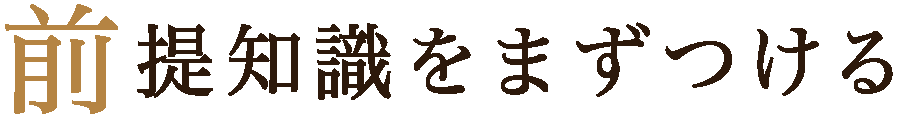
皆さんがご家族の話しを聞くとき、特にお子様のお話を聞くときに注目して考えてみましょう。”今日ね、田中くんとね、休み時間にね、お散歩したの”といったとします。このとき、文章にはどんな魔法が潜んでいるでしょう。おそらく、この話しを聞いた人がお母さんなら、”◯◯小学校で近所の友達の田中くんと校庭付近を散歩したのかな?”こういう風に解釈すると思います。しかし、この文章を赤の他人が読んだ場合どうでしょう。たとえば、OLが彼氏に今日あったことを話している場合どうなるでしょうか。”◯◯株式会社の同僚の田中くんと駅周辺かオフィス周りで散歩したのかな?”と彼氏は解釈します。
つまり、同じ文章でも、”誰がなんの話しをしているか”が少し違うだけでこんなにも解釈が変わってしまします。日常会話でならこの解釈の違いが起こっても仕方がないでしょう。しかし、勉強でこれが起こってしまえば大問題です。”区間a,b間の平均変化率f’(x)を、微分公式を用いて求めよ”という問題を解くとき、”平均変化率ってなに?。微分公式ってなに?。そもそもこれは僕に何を聞いているの?”といったことを理解していなければ、さっきのような”解釈の違い”が出てしまいます。そうなってしまっては、問題は解けません。
したがって、本塾では解釈の違いを最小限に抑えるために、数学であれば公式の知識だったり用語の確認、英語であれば単語や文法の基本であったり英語の特徴、国語であれば文章のルールといったように、知っておかなくてはなないことをしっかりと生徒にしってもらうことを心がけます。

このように、”自分が何を聞かれているのか””微分公式とは何か””平均変化率とはなにか”をまず知ってから、理解します。このように、知る→理解するというように段階的にハードルを上げた方が負担ではありません。勉強を長期的に続けるためにも、塾長オリジナルの練習シートを活用してなるべくハードルを下げて段階的に学習することが大切です。このように、本塾では負担なく効率的かつ効果的に指導することを心がけます。