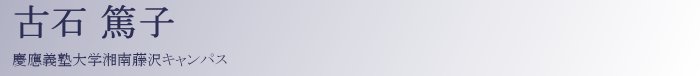| 尋媶僾儘僕僃僋僩俛乮侾乯丂乮屆愇丂撃巕乯 乽僶僀儕儞僈儕僘儉偲尵岅嫵堢惌嶔丂嘨亅係乿 2006擭搙弔妛婜 |
丂僶僀儕儞僈儕僘儉偲偼俀偮乮埲忋乯偺尵岅偺嫟懚偡傞幮夛嬻娫丄偁傞偄偼俀偮乮埲忋乯偺尵岅擻椡傪傕偭偨屄恖偺偁傝曽偺偙偲傪偝偟傑偡丅俀侾悽婭偵擖傝丄偦偺偳偪傜傕偑傑偡傑偡恎嬤側懚嵼偲偟偰敆偭偰偒偰偄傑偡丅傕偟偐偟偨傜偁側偨帺恎偑乽僶僀儕儞僊儍儖乿偐傕偟傟傑偣傫偟丄嬤強偵撿暷偐傜偺堏廧幰偑偍偍偤偄廧傫偱偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅挬慛岅傗僗儁僀儞岅側偳偺奜崙岅傪廗偭偰偄傞偁側偨偩偭偰丄偁傞堄枴偱偼僶僀儕儞僈儖偲偄偊傑偡丅幚嵺偺偲偙傠丄儌僲儕儞僈儖幮夛傗屄恖偼偙傟傑偱偺悽奅偺拞偱傕彮悢攈偱偟偨偟丄傑偨偙傟偐傜傕傑偡傑偡偦偺妱崌偑尭偭偰偄偔偵偪偑偄偁傝傑偣傫丅 |
僨傿僗僇僢僔儑儞丒墘廗 |
丂 慡懱偼埲壓偺傛偆偵愝寁偟偨偄偲巚偄傑偡丅嵟弶偺僆儕僄儞僥乕僔儑儞偺偁偲丄愭
丂 慡懱偼埲壓偺傛偆偵愝寁偟偨偄偲巚偄傑偡丅嵟弶偺僆儕僄儞僥乕僔儑儞偺偁偲丄侾乣俁偺奣愢傪宱偰杮榑偵擖傝傑偡丅暥專偺椫撉丒摙榑偲暯峴偟偰丄奺帺嫽枴偺偁傞崙偲僥乕儅傪慖戰偟偰儕僒乕僠傪峴偄傑偡丅慡懱僥乕儅乽懡暥壔庡媊偲懡尵岅庡媊乿偺傕偲丄擔杮傪娷傔偨條乆側崙偺嫵堢婡娭偱峴傢傟偰偄傞崙嵺棟夝嫵堢傗懡暥壔嫵堢丄偁傞偄偼奜崙岅嫵堢摍乆偑幚嵺偵偳偺傛偆側峫偊曽偺傕偺偱偳偺傛偆偵峴傢傟偰偄傞偺偐傪斸敾揑偵専摙偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅 |
丂庼嬈偱偺撉彂曬崘乮儈僯儗億乕僩乯丄儕僒乕僠偵娭偟偰偺僾儗僛儞僥乕僔儑儞丄偦偟偰妛婜枛偺儁乕僷乕偵傛偭偰峴偄傑偡丅傕偪傠傫尋媶夛慡懱傊偺愊嬌揑側嶲壛傕戝偒偔昡壙偺懳徾偲側傝傑偡丅 |
僥乕儅偵嫮偄娭怱傪傕偭偰偄傞偙偲丅傑偨丄擔杮岅埲奜偵帺桼偵巊偊傞尵岅偑偁傟偽傛傝朷傑偟偄丅 |
15柤 |
丂 棜廋婓朷幰偼昁偢1寧31擔傑偱偵丄儊乕儖偱扴摉嫵堳傑偱偦偺巪捠抦偟偰偔偩偝偄丅15柤傪墇偊偨応崌偵偼丄奺帺偑偳偺傛偆側偙偲偵嫽枴傗栤戣堄幆傪帩偭偰偄傞偐丄弔妛婜偵尋媶夛妶摦傪捠偠偰偳偺傛偆側偙偲傪婜懸偟偰偄傞偺偐偵偮偄偰丄1000岅掱搙偺巙朷棟桼彂傪採弌偟偰偄偨偩偒傑偡丅傑偨応崌偵傛偭偰偼柺愙傕峴偄傑偡丅慖峫寢壥偼2寧枛傑偱偵儊乕儖偱楢棈偟傑偡丅 |
丂徻偟偄暥專儕僗僩偼戞1夞栚偵攝晍偟傑偡偑丄弔媥傒偺娫偵師偺杮側偳偵栚傪捠偟偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丅 |
|
暯崅尋媶夛丄懢揷尋媶夛丄崱堜尋媶夛 |
僶僀儕儞僈儕僘儉偲尵岅嫵堢惌嶔嘩亅侾乮傑偨嵟弶偵栠偭偰丄尵岅偲擣抦丄暥壔偺娭學偵偮偄偰柾嶕偟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅乯 |
偙偺尋媶僾儘僕僃僋僩偼壩梛擔戞係帪尷偵峴偄傑偡丅乮埲慜偼壩梛擔俆帪尷偱偟偨偑丄崱妛婜偐傜帋尡揑偵係帪尷偵堏峴偟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅乯 |
尋媶僾儘僕僃僋僩嘥