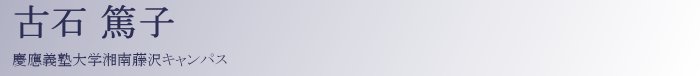「新しい外国語学習環境の創出(1)」 |
|
目的・内容 この研究プロジェクトは國枝孝弘研究プロジェクトとの合同プロジェクトです。木曜5限が國枝による理論編、同曜日6限が古石による実践編になります。履修を考える学生には、この2つの研究プロジェクトを履修することを強く勧めます。とりわけ「実践編」を履修する場合には「理論編」と合わせて履修することが必要となります。 |
|
ディスカッション・グループワーク・演習 |
|
輪読、教材評価などは、担当を決めて全員で行います。それと平行して自分の研究テーマを決めてもらい、中間発表を経て、春学期最後には、実際の学生を相手にしてプレゼンテーションをしてもらいます。自分のデザインした教育プラン、教材が実際に学習者にどのように評価されるのかを知る機会としてこのプレゼンテーションを行います。 |
|
特にありません。フランス語を学びたい人、コンピュータ言語、あるいはオーサリングツールを使って何かを制作をしたいと考えている人など大歓迎です。必要なのは何かを創造していこうとする意欲です。学ぶという行為は知識の吸収だけではなく、その知識を具体的な形に実現することではないでしょうか?個々人の研究が実際に教材という作品として実現する、そしてすぐにフランス語を学ぶ学生からその作品にたいして反応が返ってくる。モノをつくるよろこびは使用者に評価されたとき、何倍も大きくなります。この喜びを皆さんも体験してみませんか?クリエーターとユーザーが同じ学生である-そんな空間を作ることが理想です。 |
|
15名 |
|
履修希望者は3月15日までにメールでその旨を担当教員まで知らせること。(akak@sfc.keio.ac.jp, kunieda@sfc.keio.ac.jp) |
|
國枝孝弘研究プロジェクト |
|
akak@sfc.keio.ac.jp |
|
新しい外国語学習環境の創出(2) |
|
木曜日6限に行います。 |
研究プロジェクトⅡ