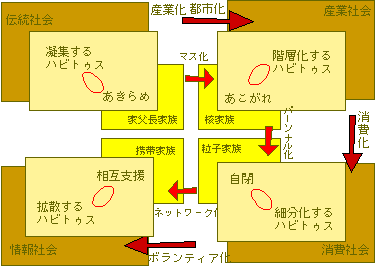|
||||||||||||||||
|
2.ノリとしてのハビトゥス、その生成する/される拡散プロセス 「ハビトゥス」は、フランスの社会学者ピエール・ブルデューの概念である。もともとラテン語で「態度、外観、服装、様子、習慣、気分、性質」などの多様な意味を持つ言葉である。よくいう「ノリ」という言葉は、意外にハビトゥスに近い意味をもっていよう。 葉美が学校の友人と共有していたノリは、彼女の個人的なハビトゥスであり、同時に彼女たちのライフスタイルに固有な構造的なハビトゥスである。だから、葉美は、そのハビトゥスにしたがっていつもの行動(慣習行動の実践)をしていた。しかし父親がパソコンを家にもってきたことで、葉美の行動に変化がみられた。いままでの日常行動にだんだんとズレが感じられるようになって、友人との間に亀裂が生じはじめた。ここに彼女はいままでのノリ(個人ハビトゥス)ではない新しいハビトゥスを生成しはじめた。インターネットという新しいメディアが家庭に入ることで、葉美には自明だった既存のハビトゥスに疑問が生じ、新しい自分にふさわしいハビトゥスの模索がはじまった。いろいろのホームページをながめながら、自分を考えるプロセスを試行することで、ネットワーク環境に生きることの意味がやっとわかるようになっていった。そこでは、情報を共有することで、自分と環境とのバランスがとられ、環境にたいして自分を開くことで、自分の意味が確認できるリアリティが了解されるようになった。これはボランティアだと、実感された。葉美にとって、いままでのハビトゥスは、閉じた豊かさのなかでの自分だけの幸福の世界であり、他のハビトゥスへのまなざしは最初から放棄されていた。見ないことで、自分の閉じた幸福に酔える、というハビトゥスであり、それは、父も母も好き勝手に自分のハビトゥスに籠っていた、という点では同じであった。ここではすべてのハビトゥスが、細分化され、自閉的に孤立していた。これが粒子家族における構造的なハビトゥスであり、そのハビトゥスに導かれて、葉美ばかりでなく、両親もそれぞれ勝手に自分の細分化されたハビトゥスを楽しんでいた。 しかし葉美には、新しいメディアが取り入られることで、まったく予想できなかった変化が発生した。それがインターネットの影響である。最初は、単なるオシャレではじめた行動(このかぎりでは、既存のハビトゥスのなかでの慣習行動)なのだが、気がつくと、ネットワークそのものが与える意味の世界にはいることで、既存のハビトゥスを逆に否定する気分や態度が生成されはじめた。見ないで閉じた豊かさに酔うのではなく、他のハビトゥスをしっかりと見つめ、いままでまったく知らなかったハビトゥスに積極的にリンクをはり、また大胆にコピーをすることで、今まで閉じていた自分の枠がどんどん崩壊していった。しかもその崩壊する自我をみつめることさえ快感になるほど、自分がフリーになっていった。あきらかに、ハビトゥスは拡張していった。リンクされ、コピーすることで、ネットワークでのリアリティを知ることで、葉美のハビトゥスは、開かれた世界そのものに拡張され、そこで共振しあうハビトゥスへと大きく変化していった。このハビトゥスを「拡張するハビトゥス」と呼ぼう。このハビトゥスが、これから葉美の友人をも巻き込み、もっと大きな集合的な広がりをもち、世代やライフスタイルを超えた新しいネットワークを生成するならば、構造ハビトゥスとして意味をもち、社会システムそのものを変革し、ネットワーク社会の実現をもたらそう。そのとき、拡張するハビトゥスは、行動実践から生成されたハビトゥスであるばかりか、社会構造を生成するハビトゥスとして、ネットワーク社会への変革を誘導する役割を担うはずであろう。今、いろいろの場で起こりつつある葉美のような実践は、拡張するハビトゥスへの変容を媒介にして、想像を超えた大きな社会ムーブメントを誘発し生成するはずである。
|
|||||||||||||||