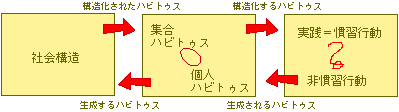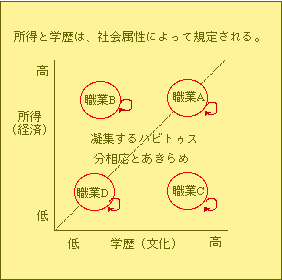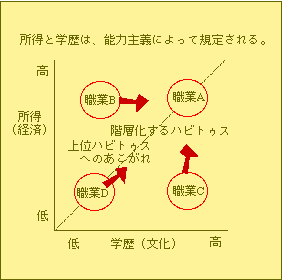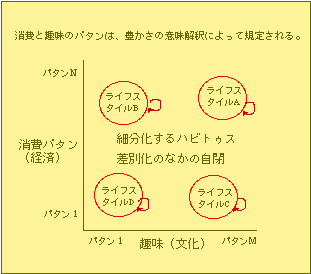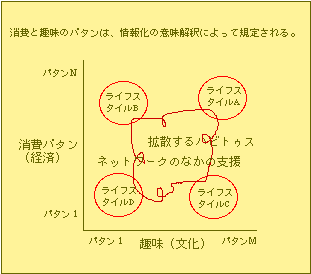|
||||||||||||||||||||
|
3.メディアの変化とハビトゥスの生成プロセス 戦後の日本社会における家族とそこでの個人のハビトゥスの変容は、メディアの変化によって大きな影響を受けている。家庭にメディアが入り、それによって慣習行動がいつのまにか変化し、その影響で、いままで自明だったハビトゥス(家庭と個人のハビトゥス)が大きく揺さぶられ、その結果として、新しいハビトゥスが生成され、さらにそこから新しい構造化が誘発され、社会構造そのものが変革されることにいたる、という大きな社会変革のプロセスが読み取れる。 ブルデューによれば、ハビトゥスは、社会構造を反映する構造ハビトゥスと、実践(習慣行動)を反映する個人ハビトゥスとの関係性のなかに解釈されるものである。社会構造を規定する要因は、経済(とくに、生活次元では収入)と文化(とくに、生活次元で学歴)で、その2つのバランス状態によって、社会的位置(とくに、生活次元では職業)の関係が確定され、それが構造ハビトゥスを構成する。もう一つの個人ハビトゥスは、日常生活における具体的な行動(とくに趣味や所有する財)であり、それが社会的位置に投射されることで、構造と個人のハビトゥスの関係が確定され、ここで確定された位置の分類によって、それぞれのハビトゥスの特徴が明確になる。さらに、各ハビトゥスがどのような関係にあるか、が、ここでのハビトゥスの解釈をさらに重要なものにしている。つまりこの関係の変容がメディアによって大きな影響を受けているのである。
■凝集するハビトゥスと”あきらめ(”みえないハビトゥス) 血縁・地縁の関係によって、イエと親族構造(本家と分家)と地域権力構造が同心円的につながり、その世界で自己完結的な日常生活が維持されていた時代にあって、人々はすべて自分の社会的位置にふさわしい分相応な慣習行動をしていた。農家の息子は農家をつぐために、商家の息子は商家をつぐために、教師の娘は嫁入り前に女学校の先生となるために、それぞれに見合った家族ハビトゥスを学習し、それをそのまま自分の個人ハビトゥスに移植していた。このような地域構造のなかで生活しているかぎり、他の社会的位置にある人々のハビトゥスは「みえない」ままだった。みえないからこそ、彼らはそこから飛び出すことはまれであったし、飛び出そうとする動機づけさえなかった。ある意味では、かれらはみんな、自分以外のハビトゥスを経験することを最初から「あきらめ」ていた。分相応の生き方が暗黙の規範であり、そこからの逸脱が村八分的な制裁つまり死(社会的でもあり、生物的な意味でも)を覚悟することであるとき、他のハビトゥスを夢見ることすら許容されないことであった。このような無意識のあきらめと分相応を善とする規範の遵守のまえに、イエと親族構造のハビトゥスは、それぞれに変ることのない強い凝集性をもち、イエのみんなの慣習行動を規制していた。こうやって、伝統社会における村落共同体的な世界と家父長的な大家族は維持され続けたのである。これが55年までの社会に典型的な「凝集するハビトゥス」である。
■階層化するハビトゥスと”あこがれ”(みえるハビトゥス) 伝統社会を崩壊に導く大きな社会変動が、産業化であり都市化であった。そこでの新しい生産様式(大量生産と大量消費)の導入と新しい生活パターンの提供は、閉鎖的な世界を一気に壊し、すべての人々の日常のまなざしを社会全体にまで拡大させていった。そのとき、都市生活と核家族の優位が決定的になり、さらにマスメディア(ラジオからテレビ)と電話が核家族に浸透し、「まじめに、むだなく、我慢して、大きく」という価値規範が家族全員に共有されていった。 ここにおいて、社会的位置関係を構成する2軸である収入(経済)の高低と学歴(文化)の高低は、いままでのような世襲(社会的な属性)によって強く規定されるのではなく、個人の能力によって獲得されるものになった。それが、産業化と都市化に平行して、社会的位置関係の獲得をよりダイナミックにしていった。その結果、分相応といった規範の制約は崩れ、それぞれのハビトゥスは「みえる」ものになった。 家族にかんしてみると、都市の核家族が一般的なものになり、さらにそこにテレビが入り、電話(一家に一台)が入ることで、外部からの情報が家族の境界を超えて入り、否応無しに社会全体を意識しながら自分の家族ハビトゥスを認知するようになった。ここでは、すべてのハビトゥスがみえる分だけ、自分の家族のハビトゥスの社会的な位置が明確になった。しかもここでは、家族ハビトゥスは父親の社会的位置(どの程度の企業組織に属して、そこでどのような地位にいるか)によって決定されていたから、家族のみんなが好き勝手に自分のハビトゥスを生成しうる余地はなかった。みんな父親をみて、それを自分のハビトゥスにしていたのである。一家に一台の電話、居間にしかない一台のテレビは、家族ハビトゥスが家族全員の個人ハビトゥスであることを強要するシンボルであり、同時に父親の権力を誇示するメディアであった。 ここでのハビトゥスは、きれいに階層化されている。これが産業社会におけるハビトゥスの構造である。しかもどのような社会的な位置にあっても、階層全体はみえるから、下の階層に位置する人は、上の階層ハビトゥスに憧れる、という関係がハビトゥスの間に生成されていた。マスメディアは、その関係を煽るように、上昇指向を支持した。人々は、こぞって豊かな生活を実現するために、高い学歴を求め、高い収入をめざした。高度経済成長期は、まさにこのようなハビトゥスに翻弄された時代であった。
■細分化するハビトゥスと”自閉(とじこもる)”(みないハビトゥス) 75年あたりから、消費社会への変化がみえはじめ、企業でもマーケティング戦略が重要な位置をもつようになった。消費化がバブル期に向かって肥大化していった趨勢への認識は誰もが実感するところであろう。さらにここでメディアが、マスの段階からパーソナル化を重視するかたちで家庭(粒子家族)の各人の個室に浸透していった。ウォークマンやミニコンポやラジカセ、また電話の親子電話が普及して、子機が各人の個室に入り、みんなが個室を中心にして自分の欲望の充足に走る時代になった。 ここで収入と学歴という2次元空間で構成された社会的位置に「消費のパターン」という新たな軸が加わった。人々はあこがれのハビトゥスを目指して貯蓄(そして投資)するだけではなく、消費にかんする多様なパターンを示すようになった。ライフスタイルが職業パターンの反映としては理解できなくなり、消費パターンを含めることではじめて理解できるまでに多様化していった。その結果、家庭のハビトゥスも、父親のハビトゥスで代表されることはなくなり、各人それぞれのハビトゥスに細分化されたまま、それぞれが主張されるようになった。 ここでは家族のハビトゥスは家族のみんなの個人ハビトゥスの総和としてしか意味をもたないものになってしまった。したがってハビトゥスの関係は、それぞれが自分の細分化されたハビトゥスに自閉して、その中だけで自足することが期待され、外部への関心はどんどん希薄になっていった。現在の若者たちに見られる「仲間以外はみな風景」という感受性はこの細分化されたノリとしてのハビトゥスの核を構成する態度様式である。こうして、消費する豊かさの享受は、細分化されたハビトゥスに自閉し、他のハビトゥスをみないという潔さ?のなかで、実践されたのである。
■拡散するハビトゥスと”支援(ささえる)”(みつめるハビトゥス) そして95年あたりから、日本社会はバブルに懲りて消費化からめざめ、新しい方法を模索しはじめた。それが豊かな社会における情報化(情報ネットワーク化)である。ネットワーク環境の急速な基盤整備とそこでのインターネットの普及によって、新しい情報リテラシーの理念(情報所有から情報共有)がある種の社会合意をえることで、新しいコミュニケーション行動が支持されるようになってきた。それが、メタファーとしてのボランティアである。たとえばインターネットでホームページを作成すると、それは情報発信だと思われるようだが、それは間違っている。そこでは、誰も情報を発信していない。そこでの情報は所有されているのではなく、他のすべての人に開かれ、リンクなりコピーされることを期待されているだけである。所有ではなく、共有された情報である。だからウェブで情報を公開することは、相互に情報支援をするためであり、情報所有による経済的交換や権力行使のためではない。これは、コミュニケーション行動を基本から変革するものである。今までの情報行動の図式は、主体が情報を所有することを前提に、その情報をどのようにして他者に伝達するか、というものであった。しかしインターネットでの行動は、それとはまったく異なる。主体はいつも情報を所有していないから、その欠落を埋めるためにインターネットに参加するのである。そして所有している情報は、他のすべての主体の情報ニーズを充足させるための支援に利用されるためのものであり、基本的には、所有というマインドはここにはない。 さらに、メディアとしては、携帯電話のようなメディアがインターネットの世界とつながることで、いつでも・どこでもコミュニケーションが可能になる条件が整いつつある。ユビキタス・コンピューティングの世界がここで実現されつつある。ここではじめて、ネットワーク社会がみえてきた。 このようなネットワーク環境が生成されるとき、そこでコミュニケーション行動を実践するほど、いままでの自分ではない自分を発見するはずである。情報を所有することで関係を維持していた強い自分ではなく、情報を共有することで相互に支援する関係にいる弱い自分をみつけて、そんなはずではない、と思うことだろう。ここで自分の既存のハビトゥスに根本からの変更が迫られる。いままでのように自分だけの関心(趣味)の世界に自閉しているのではなく、一挙に世界に自分をリンクさせることで自分らしさを求める、新しい自分のハビトゥスが生成させられる。このハビトゥスは、自閉するハビトゥスと対照的に拡散するハビトゥスである。自分をどこまでも開放し、世界に一体化することで自分のアイデンティティが獲得されるのだとしたら、その自分のハビトゥスはどこまでも拡散されており、しかも支援する/されるまなざしを自覚して世界とつながる意味で、しっかりと「みつめるハビトゥス」である。
最初に、葉美という架空の女の子を設定したのは、このようなハビトゥスの変容を具体的なイメージを伝えるためである。彼女がいままでの細分化されたハビトゥスから目覚めて新しい自己を生成するには、ネットワーク環境に触れることが必要である。その環境が、新しい自己を誘発し、彼女の個人ハビトゥスの変容を迫るのである。 その個人ハビトゥスが構造ハビトゥスまでに変容するには、彼女のような女の子がどんどんネットワーク環境を楽しむ経験をしなければならない。そのような時がきたとき、細分化された構造ハビトゥスは、拡散する構造ハビトゥスへと移行し、新しいネットワーク社会が社会構造として生成されていこう。これは、これからの21世紀にかけて期待される大きな社会変革である。このとき、ジェンダーとメディアの関係もまったく異なったものになるはずである。 |
|||||||||||||||||||