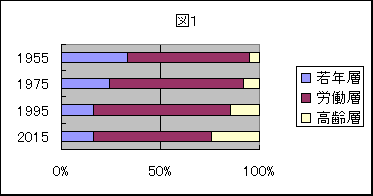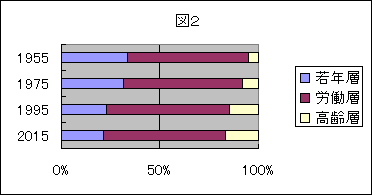|
|||||||||||||||||||
|
1.2015年の解釈 まず人口統計のデータを確認する。ここでは、1955年と1995年と2015年のデー タを比較する。図1は、その3時点ごとに、若年層(14歳以下)・労働人口層(15- 64歳)・高齢者層(65歳以上)の区分で、構成比を示したものである。 ここで指摘できるとは、つぎの3点である。
<1>若年層は、55年〜95年にかけて大幅に減少している。これが少子化である。 しかしこれは95年までの現象であり、2015年にかけてはすでに横這いの状況にあ る。つまり少子化は現在の新しい社会問題ではあっても、20年後の問題ではない。 <2>労働人口が一番多いのは95年である。 55年との比較では、少子化は、単純に高齢化にシフトしたのではなく、生産労働 人口と高齢化を同じ程度に増加させたのである。 <3>2015年の問題は、明らかに高齢化である。 これから20年の間で確実に高齢者層が増加し、それが生産労働人口の減少と表裏 関係になって進行する。21世紀を迎えるにあたって、すべての人が恐れるのは、 高齢化をどうするか、という新しい社会問題である。
しかし、図2をみてほしい。これは、3層の区分を、各年代ごとに若干修正した ものである。55年のデータは図1と同じであるが、75年と95年のデータは、若年 層を19歳までに延長し、労働人口を20-64歳に縮小したものである。これは、75 年以降、ほとんどの若年層が高校卒である、という事実を考慮すれば、納得できる ものであろう。若年層の定義を「労働に従事しない年少人口」とすれば、19歳まで 延長することはより現実に適合したものであろう。さらに、2015年の場合、さら に労働人口層を20-69歳にまで延長し、高齢者層を70歳以上に修正した。この場 合も、戦後生まれが高齢者層になる時には、65歳であっても十分に健康で、身体的 には仕事を継続することは可能だ、という前提を採用した。その結果が図2である。 ここでは、図1と比較して、つぎの2点が重要である。 <1>1995年と2015年は、ほぼ同じようなパターンになっている。 1995年から20年間は、基本的には同じような傾向が続くということである。こ れは、高齢化を異常なまでに恐れる傾向(図1では9.6%の増加)とは対照的に、現 在とほぼ同じ程度の高齢化率(図2では2.5%)にすぎない、ということである。こ の事実は非常に重要で、必要以上に悲劇的なシナリオを描く必要はないのである。 <2>1955年と2015年の相違は、3層区分の定義を単に5年間高い年齢に延ばすと いうことだけである。 若年層を14歳から19歳にシフトし、高齢者になる年齢を65歳 から70歳に延長し、労働人口の期間はどちらも50年間に設定することである。これは 戦後の貧しい社会において、若いとき(中学卒)から仕事についた時代から、そこそ こに豊かになってゆっくり仕事につけばいい(高校卒や大学卒)という時代への変化 であり、高齢者にかんしていえば、貧しい時には65歳になれば、もう体も弱体化して 仕事からの引退が自明だった時代から、豊かな生活のもとで高齢になっても十分に健 康を維持でき、70歳ぐらいまでならば、十分に働ける時代への変化そのものである。 2015年を迎えるにあたって、基本認識とすべきことは、5年間を高い年齢にシフト する社会システムをどのようにして描くか、という問題だけである。これが55年体制 の産業社会のシステムから、2015年のネットワーク社会のシステムへの構造変革の根 幹である。そこでこの構造変革を期待するとしたら、つぎの2つの点を自覚しなけれ ばならない。 |
||||||||||||||||||