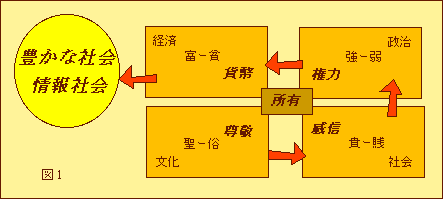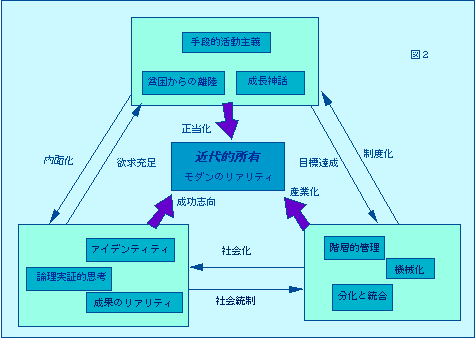|
|||||||||||||||||||||
|
3.パーソニアンのリアリティ パーソニアンがパーソンズから学んだモダンのリアリティとは何だったのだろうか。それを明確にしなければ、『社会学的想像力 ver.3』のヴィジョンは描けない。そこでパーソニア ンが囚われてきたモダンのリアリティを明確にしよう。 1>目的:「貧困からの離陸」の共有 モダンとは「貧困からの離陸を共有の目的とした社会」である。貧困とは経済的貧困であり、いわゆる心の貧困といった文化的で精神的な問題はここでは無視される。目的は明確であり一元的である。モダンは、それ以前の伝統社会の目的(伝統の遵守による安定した社会秩序の維持と存続)を無視し、経済的なブレイクスルーを唯一の社会目的として合意し、そのために社会システムの変革を許容した社会である。それ以前の没意識的でかつ超目的的な社会ではなく、経済的貧困からの離陸という特定化された社会目的を設定し、その実現に向かって社会構造の手段化をはかったユニークな社会、それがモダンである。 これは、個人のレベルでいえば、誰でもが金持ちになりたいと願い、そのために他のすべてを捨てて生きることがモダンにふさわしい生き方だ、ということである。貧乏な過去から金持ちに「なる」ことは、モダンの成功者であるばかりか、権力者であり、社会的威信を獲得することであり、さらには尊敬されるべき名誉であった。経済的な成功はモダンの社会における個人のライフスタイル・モデルであった。 2>価値:手段的活動主義 モダンの社会目的を正当化する価値は「手段的活動主義」である。これは「手段的価値とコンサマトリー価値」と「活動主義と静寂主義」の2軸の交差から成立した一つの価値観である。第1の価値観は、行為を正当化する基準が、行為それ自体にある(コンサマトリー価値)か、それともある目的を達成するための手段にある(手段的価値)か、という対立項からなり、モダンの目的を正当化する価値は後者である。たとえば、「歩く」ことを考えると、直線で歩く場合(買い物にいく)と曲線(散歩を楽しむ)が想定できる。なぜ、直線で歩くのだろうか。それは、ある目的(スーパーである必要なものを買う)を達成する手段としてもっとも合理的で効率的だからである。そこでは歩くこと自体は意味をもたない(つまらない)。だから可能なかぎりその行為にかかるコストを最小化しようとする。その結果が直線である。直線は、目的が達成されることではじめて価値を獲得する。もしも目的が達成されないならば、直線は無駄である。これが手段的価値である。 第2の価値観は、行為を正当化する基準が、現状を維持する行為(静寂主義)か、それとも現状を変革する行為(活動主義)か、という対立項からなり、モダンの目的を正当化する価値は後者である。活動主義は、現状の枠を外に向かってつねに乗り越えることを正当化する基準である。 この2つから、モダンが期待した価値とは「真面目に、無駄なく、我慢して、大きく」生きることだったのである。つまり合理主義・効率主義・禁欲主義・拡大主義は「手段的活動主義」を構成する重要な要因なのである。 3>時間:成長神話 モダンは、社会変動が常態化した社会構造をもつ。そこでの共通の時間感覚は「昨日よりも今日は経済的に成長しているし、明日はもっと成長しているはずだ」という成長神話である。モダンの世界では、すべてが無限に成長する(経済的貧困からの離陸に成功=幸福=目標達成)はずだという、量的拡大が時間の流れ(過去・現在・未来)に相関するコンセプトが共有されている。したがって時間の経過は「未来志向」という価値の表現でもあり、時間経過は成長(経済的量の拡大)を測定する尺度でもある。 4>秩序:分化と統合のメカニズム 社会的な関係はどのように秩序づけられることがモダンらしいことなのか。その秩序のルールが「機能的分化と統合のメカニズム」である。これは、ある所与の目的を合理的に達成するためのメカニズムであり、社会システムの構成要素の機能的特化に着目して、その特化された機能を部分として全体に統合する仕組みである。この場合、特化された機能は自律的ではなく(欠落体としての機能)、全体への部分的貢献によってのみ生存可能である。したがって統合機能がシステム全体の調整・管理機能として不可欠であり、それが特化された機能の部分的貢献を制御する。たとえば、性差の役割分化システム(男は外で、女は内)は、モダンのメカニズムの原点であり、核家族と組織の関係はモダンの社会システムを構成する基本パターンである。つまり機能的分化と統合の秩序原理は、貧しい(=機能的に特化するしかない)主体を効率的に関係づけることで社会の目的達成度を最大化する最適な方法である。 5>権力:階層的な意思決定 モダンの社会秩序を実行可能にするには権力機構が不可欠である。それは能力主義に立脚した階層的な意思決定機構である。機能関係はその基本的な性質において非対称的なので、そこにはなんらかの権力関係が隠されている。たとえば、男女の性差は役割分化であると同時に、「男は女よりも偉い」という権力関係でもある。とすると、社会の目的達成との関連で分化した機能的関係は、同時に「意思決定する力(能力と権利)をもつ主体」と「もたない主体」との階層性になり、その権力関係が社会秩序の実行化をもたらすのである。ビューロクラシーはこの典型である。 6>技術:機械化のテクノロジー 社会システムを構成するのは、秩序(社会)と権力(政治)そして技術(経済)である。モダンの技術とは機械化である。マシーン・テクノロジーの進展がモダンの目的達成の手段として不可欠であった。そればかりか、「分化と統合」の秩序も機械のメタファである。機械のように社会システムを形成することがモダンらしいことなのである。それほどまでに、モダンの目的達成の手段には、機械化が不可欠であり、その拡張としての組織化(人の機械化)と産業化(工業化;機械化と組織化)が望まれたのである。モダンの社会は、物の生産にあっても、人間関係の制御にあっても、すべて機械のようにシステム化されなければならなかった。そうすれば、経済的な貧困からの離陸は可能だった。機械化は、組織化と産業化にまで拡張されることで、経済的成長を推進する先頭にたったのである。この意味で、モダンとは産業社会そのものである。 7>主体:アイデンティティ モダンは、近代的自我という個人を基礎単位として形成される。その個人は、自分らしい欲求充足(目的)を求めて、自由な意思決定力(権力と権利)を発揮する主体であり、外部環境からの影響力に左右されることのない自律的な主体である。その自律的な自己こそがアイデンティティが確立された主体であり、強い自我である。モダンを支える主体のコンセプトはこの強い自我にあり、かれは自分らしい欲求充足へのこだわりを前提にして社会システムの形成を志向する。その場合、この主体は、欲求充足のために他者との関係を手段化し、しかもどこまでも強い意思決定の力を、利害関係(ゲーム)にあってもまた役割関係(ロールプレイ)にあっても発揮しようとする強い主体である。 8>思考:論理実証主義的思考 アイデンティティにこだわるモダンマンにとって、その思考様式は合理的でなければならず、その典型として論理実証主義思考がすべての思考パターンのなかで最高の地位を獲得した。その結果、論理整合性と経験妥当性の基準によって世界を認識し分析し総合する思考がもっとも重視され、感覚的で情緒的な思考パターンは芸術という特殊領域に封鎖され、宗教ように全体的で直感的な思考はもっとも非科学な思考であるとレッテルがはられ、知識体系のなかで最低の地位に位置づけられることになった。このように、科学的=論理実証主義的であることはモダンマンにとって自明の思考パターンであり、したがってその思考を体得しえない場合には、アイデンティティの確立もまた不可能とされた。 9>行動:成果のリアリティ モダンマンは、情報(言葉)よりも行動を重視する。「何を言う」ではなく、「何をした」かがモダンマンの証明として重要である。モダンマンとしての存在のリアリティは、いかなる場合でも行動によってえられる。つまり行動が真の基準であり、情報はその行動との一致の程度によって真偽の評価がなされる。たとえば言行不一致の場合、真は行動にあり、その行動に一致しない情報(言)はどこまでも偽である。 しかもその行動はそのプロセスに価値はなく、行動の成果が問題である。「何をした」が問題であり、「何をしているのか」はなんら価値をもたない。行動の結果が目的をどの程度達成したかによって、行動の成果が評価される。その評価がリアリティを生む。 10>所有:所有のリアリティ モダンの究極のリアリティは「(近代的)所有」にある。とくに貨幣という一般的メディアに集約される社会財を所有すること、しかもその量を可能なかぎり多く所有することがモダンマンのリアリティである。それがモダンに生きる個人のアイデンティティ(成功者)であり、かつモダンの社会システムを産業社会を中核にして構造化する根拠である。
もちろん所有そのものの歴史は、なにも近代社会に固有のものではない。ものを所有する歴史は有史以来のことであり、それは4つの一般的メディア(貨幣・権力・威信・尊敬)の正当性をめぐる歴史である。つまりある時代にあって所有を正当化する根拠となる一般的メディアが何であるかによって、その時代は4つの所有をめぐる歴史を生成したのである。図1に示すように、近代産業社会では、貨幣が所有の正当性を付与する最高のメディアであるからこそ、「富と貧」の社会カテゴリーがもっとも優先され、そこでは富者が時代を所有する地位を獲得したのである。それが近代産業社会である。それ以前は権力メディアを所有する者が「強者」の地位をえて、時代をリードしたし、それ以前は威信(社会的影響力)メディアの所有の有無によって「貴と賎」のカテゴリーが時代を特性づけ、さらにその前には尊敬(価値コミットメント)メディアの所有の有無によって「聖と俗」の時代があった。つまり所有の歴史は、聖者から始まって、貴者そして強者に変化し、さらに産業革命を契機にして富者が時代の所有者の地位を獲得したのである。モダンは所有の歴史の最後の位相にある。 以上10のコンセプトは、図2のように関連している。簡単に説明しよう。
中心は近代的所有にある。これこそがモダンのリアリティの根源である。そこに向けて、3つの(行為)システムが構成された。それが近代的所有を「正当化」するシンボル(文化)システムであり、「産業化」によって近代的所有の社会を実現する社会システムであり、「成功志向」の動機づけによって近代的所有の獲得をめざした個人(パーソナリティ)システムである。 シンボルシステムは、価値と時間と目的から構成される。モダンとは何であるべきか、を明示するのが「手段的活動主義」の価値であり、それを時間に変換した場合が「成長神話」であり、そしてより具体的な目的に特定化した場合が「貧困からの離陸」である。つまりモダンのリアリティをシンボルとして表現するのは「もう貧乏は嫌だ。だからもっと真面目に、無駄なく、我慢して、大きく生きよう。そうすれば、きっと明日は輝いているはずだ」という神話を共有することだった。 社会システムは、この神話を社会的な関係のなかで実現する仕組みを構造化することであった。その構造化を可能にしたのが、秩序(社会)と権力(政治)と技術(経済)である。つまりここでは機械をメタファとして社会的な関係を構造化することが期待された。技術としての「マシーンテクノロジー」の導入ばかりでなく、秩序(水平的関係)の方法としての「分化と統合」メカニズムと意思決定原理(垂直的関係)としての「階層的な権力」によって、手段と技術の問題ばかりでなく、人間関係にかんしても、機械のように分化し統合する合理的で効率的な社会システムが期待されたのである。個人システムは、この神話を個人の欲求充足との関連で実現する仕組みを構造化することであった。その構造化を可能にしたのが、自律性の確立をテーマにした主体と思考と行動である。つまり主体的な意思決定が利害関係にあってもまた役割関係にあっても発揮できる「能力(意思決定力)と役割期待(意思決定権)」を、いかに実現するかがここでのテーマであった。そのためには、個人は「自分とはなにか」というアイデンティティにこだわらざるをえなかったし、しかもそのこだわりは、論理実証的な思考方法を体得し、かつその方法を使用した合理的な目的達成行動によって、意味をもちえたのである。 さらに、その3つのシステムは相互に補完し依存する関係にあり、そこではつぎのような関係が確定していた。まず文化と個人との関係では、文化は個人にモダンの価値規範を内面化させることを求め、個人はその内面化された動機に基づいて行動し、それによって文化の価値規範を遵守することが期待された。その場合、価値規範の遵守が自己の欲求を充足させる、という関係が重要であった。ここでは、価値と欲求が矛盾しない関係を維持することがテーマであった。 つぎに、文化と社会の関係では、文化はその価値規範を社会システムのなかに制度として定着させることを求め、社会は制度化された価値規範を現実の社会関係の中で実現することで社会システムの目標を達成した。その場合、価値規範の遵守が社会の制度の仕組み(秩序・権力・技術)のもとで目的達成をもたらすという、価値と制度の矛盾のない関係の維持がここでのテーマであった。 そして個人と社会との関係では、個人の欲求充足行動を社会システムの役割期待に適合させるように、社会化(欲求を役割期待に誘導するための学習)のメカニズムが作動することが求められ、反対に、社会は個人の欲求充足行動が役割期待から逸脱しないように、報酬と罰(アメとムチ)のサンクションによって個人を社会統制するメカニズムが求められた。この2つのメカニズムは「選択(少数の選ばれた主体だけが自律する成功者であり、かつ社会からの権力・威信・尊敬を占有する)への合意」を前提として成立した。この前提をめぐって欲求と制度の矛盾のない関係を維持することがここでのテーマであった。 このようにして、近代的所有をめぐって、シンボルシステムからの正当化の付与と、社会システムからの産業化の実現と、個人システムからの成功志向へのこだわりによって、さらにそれらの相互補完と相互依存する関係によって、モダンのリアリティは実現されたのである。価値(正当化)と制度(産業化)と欲求(成功志向)の矛盾のない関係が「近代的所有こそがモダンのリアリティである」というコンセプトを支えたのである。 |
||||||||||||||||||||