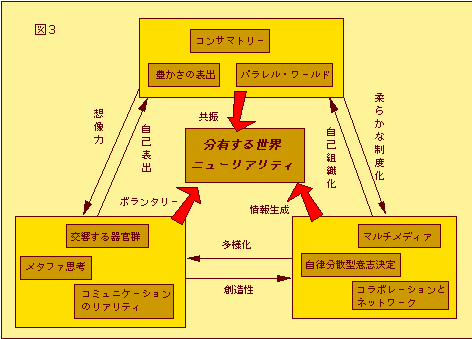|
||||||||||||||||||||
|
4.社会学的想像力 ver.3 パーソンズが描いたモダンのフレームは、上記のようなものであったろう。それは、「近代産業社会とは何か」にたいして、パーソンズが提示した明確な回答であった。 パーソンズの悲劇は、その回答がでた70年代に、モダンの社会がアメリカ社会ではすでに過去のシステムとして、価値としても制度としてもまた欲求としても、否定される方向性に確実に進行していったことである。 モダンの終焉はパーソンズのフレームそれ自体に内在していた。パーソンズは、モダンがその発展によって自生的に崩壊する社会システムであることを知ったうえで、にもかかわらずモダンの総合理論にこだわったとはいえないだろうか。モダンの目的が完全に達成されるとき、それはモダンのシステム全体の変動を余儀なくさせる。無限の目的達成の論理は、貧困からの離陸がまだ低空飛行の段階では、十分に納得できる論理であったが、豊かな段階(50年代のアメリカ)に入ると、それはモダンのトリックでしかないことは暗黙の前提であったはずである。にもかかわらず、この歴史的な段階を理論化することが、パーソンズにとっては“最後のモダニストの巨人”としての使命だったのである。 では、パーソンズのフレームがもつモダンのリアリティはどのようにして喪失されるのであろうか。10のモダンのコンセプトは新しい時代状況のなかでその不動の地位を脅かされ、新しいコンセプトにその地位を譲るとしたら、その移譲のパターンは何なのだろうか。想定される新しいコンセプトを図式的に示そう。(図3)
A.シンボル・システムの変化 まずは、「貧困からの離陸」というモダンの社会目的が達成される。そこで登場する豊かな社会は、目的の変更を迫る。「経済的に豊かになっても、それは豊かさの『獲得』にすぎず、どのように豊かさを表現すればよいのか、わからない」というように、『豊かさの表出』こそが新しい社会のテーマになる。さらに、これは目的を正当化する価値の変更をもたらす。つまり『コンサマトリー価値』へのシフトが期待され、「楽しく、ゆとりをもって、今を大切に、そしてほとほどに生きる」ことが価値をもつようになる。とすれば、成長神話の時間感覚も崩れ、「いま=永遠」といったような新しい時間感覚、過去と現在と未来が一直線で並ぶのではなく、多様な時間が並列する『パラレル・ワールド』の時間感覚にシフトする。その結果、シンボル・システムは「所有こそがモダンの究極のリアリティだ」を正当化するシンボルではなくなる。このシステムは、新しい社会のリアリティを求めるシンボルとなる。そのリアリティは『分有する世界』にある。 B.社会システムの変化 シンボル・システムの変化は新しい社会システムに「柔らかな制度化」を期待する。そこでは機械のメタファは捨てられ、コンピュータのメタファによる構造化が期待される。ここでのメタファとしてのコンピュータはもはや情報処理機械ではなく、情報生成(創造)メディアであり、コミュニケーションのテクノロジーである。このような意味をもつ『コンピュータ・テクノロジー』が技術・産業・生活・都市の社会基盤(コンピュータ・プラットフォーム)を構成する。これが機械化から情報化への変化であり、ここでやっと、情報社会が豊かな社会のシンボル・システムに共鳴し融合するかたちで登場する。 とすると、人間関係の秩序化も、かつてのような機能特化による「分化と統合」のシステム化ではなく、「融合と共振」によるシステム化へと変化する。これは、豊かな主体が多様でしかも柔らかな形で社会的な関係をつける方法であり、『コラボレーションとネットワーク』による秩序化ともいえよう。新しい人間関係は、機械=分業のイメージ(硬い枠と強い絆)による目的達成志向的ではなく、コンピュータ=コラボレーションのイメージ(曖昧な枠と柔かな絆)による創造的でコンサマトリー志向の秩序を求める。意思決定の方法も、ビュロクラシーに典型的な階層的な権力機構ではなく、『自律=分散型』の意思決定メカニズムが期待される。秩序の原理がコラボレーションとネットワークになれば、すべての主体を階層的に統一する強力な権力機構は無用なので、それぞれの主体が分散してかつ自律した意思決定する柔らかな管理=調整システムにならざるをえない。その自律=分散型の調整メカニズムこそ、創造的な社会秩序を維持するために重要な方法である。 このようなコンピュータをメタファとして成立する社会システム(情報社会)は、モダンのリアリティ=近代的所有とは矛盾する。情報社会とは、所有ではなく『分有』にこそ新しい究極のリアリティを求める社会である。とくに「コピー」のコンセプトは、新しい社会システムと『分有する世界』をリンクさせ、かつ豊かな社会のシンボル・システムを実現させる重要なコンセプトである。コピーは、「所有の世界(良いものは希少だ!)では偽物」だが、「分有する世界(良いものはたくさんある!)では、分有それ自体を維持し増幅させるメディア」である。それは新しい社会を想像するトリガーである。 C.個人システムの変化 個人のシステムにかんしても、豊かさの獲得という一元的な評価基準が無効になり、豊かさの表出という多元的なテーマが優先されると、成功志向は意味を失ってしまう。とすると、それを支えたアイデンティティも「なんのためなのか」という疑問に答えることができず、崩壊しはじめる。しかも新しいマルチメディア環境の登場で、アイデンティティと不可分の関係にあった「視覚=活字メディア」の優先性が揺らぎ、新しい個人のコンセプトが期待されるようになる。これを「交響する器官群」と呼びたい。 この新しい主体のイメージは、もはや論理実証主義的な思考方法だけに固執することはない。かれらはもっと柔軟で多様な思考をもつ。そこでは、マルチメディアの影響が強く、視覚=活字メディアと聴覚=音響メディアと皮膚感覚=映像メディアが主体の中で対等な関係でネットワーク化され、それによる思考が自由にかつ多様に発想される。したがって、理解・知識の評価基準も論理的であると同時に感覚的で、経験的であると同時に想像的でもあるといった、多様で包括的な思考が期待される。それをここでは「メタファ思考」と呼びたい。これは、合理的思考のもつ目的論的で縮約的な発想ではなく、拡散的で多様化の発想を重視し、つねに新しい価値の世界を自由に想像し創造することを求める思考方法である。このような思考方法は、行動=成果という制約だらけの現実にリアリティを求めようとはしない。ここでは情報=コミュニケーションにこそリアリティがあって、ある意味では行動=成果は情報=コミュニケーションのリアリティの残滓にすぎない。想像力や自由な発想がリアリティをもつのはまずは情報=コミュニケーション・レベルであり、だからこそ情報が真偽の基準となり、コミュニケーションが行動を評価する基準になる。 このような個人のシステムは、すでに所有にリアリティを求めない。豊かさと情報化の恩恵を受けた個人は、新しい世界にリアリティを求める。それが『分有する世界』である。この世界は、経済的な世界からはもっとも遠い、ボランタリー活動のコミュニティに通じるような世界である。 D.システムとニューリアリティ このように、パーソンズのシンボルと社会と個人のシステムからなるモダンのフレームのなかには、すでに変動の契機がビルトインされていた。豊かな社会と情報社会は、50年代の大衆社会・消費社会・マスメディアの時代から始まり、70年代になって高度化しかつ成熟し、そして現在にいたった。いま、その2つの社会が融合してまったく新しい社会の到来を予告する段階にいたり、モダンのコンセプトをことごとく否定する方向性が暗示されている。それがモダンのリアリティを喪失させるのである。 豊かな社会と情報社会は、それがクロスするとき、『分有する世界こそが、新しいリアリティである』という、近代的所有にかわって、そしていままでの歴史の根幹であった所有のコンセプトを超えた新しい世界の生成を予感させる。 |
|||||||||||||||||||