Creative Reading:『レイモンド・カーヴァー:作家としての人生』
今、この本に出会えてよかった。『レイモンド・カーヴァー:作家としての人生』という本のことである。
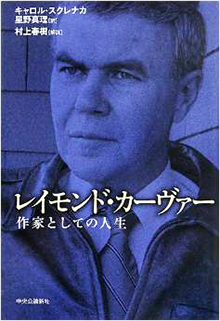 『レイモンド・カーヴァー:作家としての人生』(キャロル・スクレナカ, 中央公論新社, 2013)
『レイモンド・カーヴァー:作家としての人生』(キャロル・スクレナカ, 中央公論新社, 2013)
Carol Sklenicka, "RAYMOND CARVER: A Writer's Life," Reprint edition, Scribner, 2010
本書は小説家レイモンド・カーヴァーの評伝である。巻末には、レイモンド・カーヴァーの本を翻訳してきた村上春樹が解説を寄せている。村上春樹はカーヴァーのことを「疑いなく、僕にとってもっとも価値ある教師であり、最高の文学的同志である」(p.627)と述べている。「その翻訳作業は小説家としての僕にとっても、得がたい勉強になった」(p.729)という。村上春樹は三十五歳のとき(『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を書く直前)に、カーヴァーのもとを訪れている。そのエピソードも本編のなかで紹介されている。
村上春樹の解説部分もすごくよいのだが、それについては後で触れるとして、まずは本編のなかで気になった部分を取り上げていきたい。
まず、個人的に興味深かったのは、創作のための「ライターズ・ワークショップ」についての記述があったことだ。パターン・ランゲージの国際学会では、書いてきたパターン(の論文)をみんなでコメントし合う「ライターズ・ワークショップ」が行われている。このライターズ・ワークショプという仕組みは、約20年前に、ソフトウェア・パターンのカンファレンスを実施するにあたり、ソフトウェア・エンジニアであり詩人でもある Richard Gabrielが創作分野から取り入れ、導入したものだ。以来、ソフトウェア・パターンの国際学会PLoPでは、毎年行われてきた。「行われている」というよりも、それがメインのアクティビティとなっている。
PLoPにおけるライターズ・ワークショップは、ポジティブで建設的なコメントをし合うという場である。特徴的なのは、著者は何も話してはならず、その場では沈黙しなければならない。モデレーターのゆるやかな進行のなかで、著者以外の参加者たちがそのパターンや論文をよりよくするために考え、話し合う。著者はそれを聞きながら、誤解されていることも含めて受け入れなければならない。というのは、その誤解を生んだのは、自分の書いた文章だからである。その誤解が生まれる状況を目の当たりにすることで、著者はその部分を書き直さなければならないということを知るのである。
おそらく、このことは、フリーカルチャーやオープンソース文化が生まれるようなソフトウェア分野の土壌に合っていた。フラットでフランクに語り合い、お互いに相手のためにコメントし合うというよい雰囲気がある。これが、20年間、PLoPで行われてきたタイプのライターズ・ワークショプである。
これに対して、昨年、Richard Gabrielが、「20年経ったことだし、そろそろ違うやり方も試してみてよい頃だと思う」と言い、違うタイプのライターズ・ワークショップをやり始めた(僕はそのワークショップの参加者だった)。違うタイプといっても、別の新しいやり方というわけではなく、創作の分野で行われてきたやり方により近いやり方である。それは、教師が、学生たちに学んでほしいことを抱きながら、学生たちの作品を使ってみんなで議論するというものである。これまでのモデレーターは(原則的には)より中立的で、参加者とかなりフラットな関係があった。これに対し、Richardが創作分野でもともとやられていたワークショップとして始めたものは、モデレーターがかなり議論の流れをつくり、参加者がこの論文やパターンで考え・議論することの水路付けを行う。必要に応じて著者も質問を受けたり、意見を述べたり、一緒に議論したりする。終わってみると、フラット型のライターズ・ワークショップよりも、深い議論ができ、著者としても参加者としても得るものも多かった。
ちょうど昨年のPLoP2014で、そのようなライターズ・ワークショップの体験をしたばかりだったので、カーヴァーの評伝のなかに彼が参加したライターズ・ワークショップの話が出てきて、思わず「わお!」とうれしくなった。やはり、創作の世界のライターズ・ワークショップはそれを担当する教員(作家)の色がかなり強く出るようで、参加者(作家の卵たち)にかなり恐れられている場だったようだ。
伝説的だというアイオワシティのライターズ・ワークショップについての記述を少し見てみよう。
当時の様子が想像できる。しかし、華々しい実績の背後には厳しい面もある。
だからこそ、ライターズ・ワークショップの場は、必死な場となる。ライターズ・ワークショップは何のために行われ、どう実施されたのだろうか。
この記述にあるように、明らかに教育としての場であったことがわかる。
レイモンド・カーヴァーが入ったR・V・キャシルのワークショップは、次のような感じだったようだ。
ワークショップにおける講評会は以下のような感じだったという。講評会は、「ワークショップで週に一回、二時間にわたって開催」されたという。
これは自分に才能があると自信を持っている者にも、不安を感じている者にもきつい環境だったようだ。
作家のジェイ・ウィリアムズは、そこは「毒蛇の巣窟」であったと語っている。
これらの話からもわかるように、かなり強烈な場だったようだ。僕らがパターン・ランゲージで行っているライターズ・ワークショップも、もちろん初心者にはドキドキして緊張する場ではあるが、ここまで厳しい雰囲気ではない。このあたりは、ソフトウェア分野の明るくオープンな雰囲気がうまい具合にブレンドされて進化したと言えるかもしれない。
今回初めて創作の世界でのライターズ・ワークショップの話を読んだのだが、非常に興味深かった。もっと歴史と形態について知りたいと思った。
そして、この本の重要な部分としてやはり触れなければならないのは、「身を粉にして小説を書く」人生を送ったカーヴァーの創作人生についてである。
レナード・マイケルズは、カーヴァー(レイ)が妻のメアリアンとの生活のなかでいかにして小説を生み出してきたのかについて、次のように語っている。
この言葉は、僕にとって非常に発見的だった。「彼がかかわり、一緒に暮らしている人々はみんな、ある意味では彼の小説への参加者だった」という部分と、「それらの小説のための代価として、彼らの人生そのものを支払った」という部分が、である。普通とは異なる見方であるが、それは真実であると思った。そして、僕も同じように、僕のつくり出すもののために、僕とかかわりのある人たちは「参加」し、僕らはその「人生」を対価として差し出している。対価として支払う度合いの違いこそあれ、人はそうやってつくっている。そうやって生きている。
この視点の転換は、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』を読んだときと同じような衝撃があった。ドーキンスは、生物が遺伝子をもっているのではなく、遺伝子が生物をヴィークルとして自らが残るようにさせているのだ、という視点の転換をもたらした。もちろん遺伝子が意思や知能を持っているという意味ではなく、物事の主と従の関係は、僕らが当たり前と思っているほど単純には決められないのだ、という話だ。
これまでも、僕は、作品をつくる人が作品につくらされているという関係になるという話を、宮崎駿の言葉などを引用しながら語ってきたが、それはひとつひとつの作品に対してのことであった。上述のマイケルズの言葉は、それを超える範囲においても、同様のことが言えるのだ、ということである。これはすごい。
レイモンド・カーヴァーは、のちにアイオワでワークショップをもつことになるのだけれども、そのときの学生ダン・ドメネクは、「レイが書くことを愛していることが、僕には魅力的だった」(p.386)と語っている。そして、「書くことについて語るときは、彼は情熱的で、独断的だった」(p.387)と。この部分は、自分の経験に照らしてもよくわかる。
作品集『ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズ』の前書きで、カーヴァーは「幸運」について語っている。
ここで書かれている「酒飲み、禁酒家、女たらし、とろいやつ」というのは、レイ自身が一度はなったことがあった。重要なのは、このあとに続く「雷に打たれる人」についての部分である。カーヴァーは言う。
その通りだと思う。この指摘は真実を射抜いている。常にそれに取り組み、考え、悩み、もがいている人にしか雷は落ちないのである。
「○○にしかできないやり方で、かたちを与えられ、目に見えるようになった美」!なんてかっこいい考え・言い方だろうか。僕もそういうものを自分の分野でつくりたい、そう思った。
最後に本書の最後に寄せられている村上春樹の「解説――身を粉にして小説を書くこと」のなかの言葉を少し取り上げたい。
ここで語られていることは、僕には、村上春樹自身のことにも重なって見える。ただしひとつ違うのは、カーヴァーは様々なものに依存することでそれを埋めようとしたが、村上はそれを自分なりの方法で心身を鍛え、書き続けようとしているということではないだろうか。村上春樹が日々走り、心身を鍛えながら、創作と重ねて行くのは、まさにそのためだろう。僕も自分なりのスタイルを確立していきたい。それがあっとうい間に擦り減ってしまわずに、つくり続けるために必要なことなのだ。
そして、人生というものは死との関係のなかで考えられなければならない。人の生は誰でも限られており、作家も同様に、つくり続ける人生にも終わりが来る。レイモンド・カーヴァーが亡くなったのは、五十歳のときだった。そのとき、四十歳を目前にしていた村上は次のように感じたという。
しかし、実際に自分が五十歳になったときに、そのように考えたことを反省したという。
いま四十歳という位置にいる僕にとって、この村上春樹の言葉から得られるものは大きい。
僕も目の前のことに必死になりながらも、このことを常に考えながら生きていきたい。
自分が限りある人生のなかで、世界にどのような作品・成果をどれだけ残せるだろうか、と。
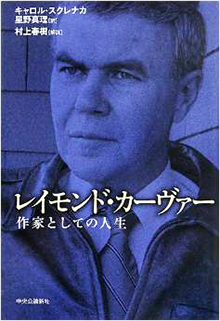 『レイモンド・カーヴァー:作家としての人生』(キャロル・スクレナカ, 中央公論新社, 2013)
『レイモンド・カーヴァー:作家としての人生』(キャロル・スクレナカ, 中央公論新社, 2013)Carol Sklenicka, "RAYMOND CARVER: A Writer's Life," Reprint edition, Scribner, 2010
本書は小説家レイモンド・カーヴァーの評伝である。巻末には、レイモンド・カーヴァーの本を翻訳してきた村上春樹が解説を寄せている。村上春樹はカーヴァーのことを「疑いなく、僕にとってもっとも価値ある教師であり、最高の文学的同志である」(p.627)と述べている。「その翻訳作業は小説家としての僕にとっても、得がたい勉強になった」(p.729)という。村上春樹は三十五歳のとき(『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を書く直前)に、カーヴァーのもとを訪れている。そのエピソードも本編のなかで紹介されている。
村上春樹の解説部分もすごくよいのだが、それについては後で触れるとして、まずは本編のなかで気になった部分を取り上げていきたい。
まず、個人的に興味深かったのは、創作のための「ライターズ・ワークショップ」についての記述があったことだ。パターン・ランゲージの国際学会では、書いてきたパターン(の論文)をみんなでコメントし合う「ライターズ・ワークショップ」が行われている。このライターズ・ワークショプという仕組みは、約20年前に、ソフトウェア・パターンのカンファレンスを実施するにあたり、ソフトウェア・エンジニアであり詩人でもある Richard Gabrielが創作分野から取り入れ、導入したものだ。以来、ソフトウェア・パターンの国際学会PLoPでは、毎年行われてきた。「行われている」というよりも、それがメインのアクティビティとなっている。
PLoPにおけるライターズ・ワークショップは、ポジティブで建設的なコメントをし合うという場である。特徴的なのは、著者は何も話してはならず、その場では沈黙しなければならない。モデレーターのゆるやかな進行のなかで、著者以外の参加者たちがそのパターンや論文をよりよくするために考え、話し合う。著者はそれを聞きながら、誤解されていることも含めて受け入れなければならない。というのは、その誤解を生んだのは、自分の書いた文章だからである。その誤解が生まれる状況を目の当たりにすることで、著者はその部分を書き直さなければならないということを知るのである。
おそらく、このことは、フリーカルチャーやオープンソース文化が生まれるようなソフトウェア分野の土壌に合っていた。フラットでフランクに語り合い、お互いに相手のためにコメントし合うというよい雰囲気がある。これが、20年間、PLoPで行われてきたタイプのライターズ・ワークショプである。
これに対して、昨年、Richard Gabrielが、「20年経ったことだし、そろそろ違うやり方も試してみてよい頃だと思う」と言い、違うタイプのライターズ・ワークショップをやり始めた(僕はそのワークショップの参加者だった)。違うタイプといっても、別の新しいやり方というわけではなく、創作の分野で行われてきたやり方により近いやり方である。それは、教師が、学生たちに学んでほしいことを抱きながら、学生たちの作品を使ってみんなで議論するというものである。これまでのモデレーターは(原則的には)より中立的で、参加者とかなりフラットな関係があった。これに対し、Richardが創作分野でもともとやられていたワークショップとして始めたものは、モデレーターがかなり議論の流れをつくり、参加者がこの論文やパターンで考え・議論することの水路付けを行う。必要に応じて著者も質問を受けたり、意見を述べたり、一緒に議論したりする。終わってみると、フラット型のライターズ・ワークショップよりも、深い議論ができ、著者としても参加者としても得るものも多かった。
ちょうど昨年のPLoP2014で、そのようなライターズ・ワークショップの体験をしたばかりだったので、カーヴァーの評伝のなかに彼が参加したライターズ・ワークショップの話が出てきて、思わず「わお!」とうれしくなった。やはり、創作の世界のライターズ・ワークショップはそれを担当する教員(作家)の色がかなり強く出るようで、参加者(作家の卵たち)にかなり恐れられている場だったようだ。
伝説的だというアイオワシティのライターズ・ワークショップについての記述を少し見てみよう。
カーヴァーがライターズ・ワークショップについて知っていたことは、教師たちから聞いたことのほかは、高級雑誌から得た知識だけで、その雑誌のほとんどに地元アイオワの出身でワークショップのディレクターを務めていた詩人ポール・エングルの写真が載っていた。このような記事には、「学識のある者たちのあいだでは、豚だけでなく、詩もまたアイオワの名物として知られるようになった」というようなキャッチフレーズが書かれていた。また、「アメリカの選りすぐりの作家を輩出」というフレーズもよく見られた。一九六七年七月の「エスクァイア」誌は、「アメリカ文学界の組織図」を掲載した。そこには、かつてアイオワの学生や教授だった四十二人の名が記されていたが、これはリストに挙げられた名前の三分の一を占めていた。またべつの記事は、ワークショップに参加するための必要条件は「才能」である、と簡潔に説明していた。(p.134)
毎年、百人以上の学生を世界中から引き寄せたワークショップの魅力とは、エングルによれば、それが「ハリウッドとニューヨークの中間に位置する選択肢であり<中略>そこでは、作家は自分自身で立ち向かい、それと同時に、ほかの大勢の者と自分の能力を比較できる」ことだった。一九六一年時点では、少なくとも六十作以上の重要なフィクションの作品が、それまでの二十五年間でワークショップ出身の作家によって出版されていた。(p.135)
カーヴァーがアイオワに来たとき、ワークショップは成長期にあり、アイオワの卒業生が開設する創作講座が全国で花開こうとしていた。(p.139)
当時の様子が想像できる。しかし、華々しい実績の背後には厳しい面もある。
アイオワで教鞭を執ったフィリップ・ロスは、「私たちの役目の一つは、十分な才能を持たない学生に、作家になることをあきらめさせるおとだ。自己表現のため、あるいはセラピーのためにやってくる人も大勢いる」と述べた。(p.135)
だからこそ、ライターズ・ワークショップの場は、必死な場となる。ライターズ・ワークショップは何のために行われ、どう実施されたのだろうか。
創作というものを学校で教えられるかどうかについては、盛んに議論が重ねられてきた。これは今でも答えが出ていない問題だが、「ワークショップ」と呼ばれる形式の授業は、この課題に取り組むために進化してきた。アイオワ大学でワークショップが制度化されたのは、ヴァンス・ボアジェイリーの説明によれば、「創作的な作文を教える方法を発明しなければならなかった」からだという。授業の題材となるのは、主として学生の原稿だ。教授とほかの学生の批評が道具となり、教室という工房で原稿が磨きあげられていく。(p.136)
この記述にあるように、明らかに教育としての場であったことがわかる。
一九六〇年代初めのワークショップは、まだかたちが定まらない集まりで、その年に集まった教授陣や学生の個性によって決まる要素が多かった。(p.139)
レイモンド・カーヴァーが入ったR・V・キャシルのワークショップは、次のような感じだったようだ。
キャシルは非常に雄弁で学究的な人物で、知的な議論を好んだ。彼のワークショップは、「誰かが書いた小説を料理する場所だった。気に入った作品があると、食いついて徹底的に分析した」(p.137)
ワークショップにおける講評会は以下のような感じだったという。講評会は、「ワークショップで週に一回、二時間にわたって開催」されたという。
月曜に行われるこの会をドハーティはいつも心待ちにしていたという。「その日は、本物の作家のような気分になれるから、みんな気合いが入っていたよ。ほかの日は、実際に文章を書かなきゃいけないからね」。学生たちが事前にタイプライターで打った短編や詩を教授に提出すると、彼らにはよくわからないプロセスによって教授が作品を選び、学部の秘書にタイプライターで打たせる。その後、選ばれた作品は、青焼き機で複写され、まだ湿って現像液のにおいがする紙の束が、ホッチキスでとめた「ワークシート」と呼ばれる冊子になって学生に配られる。それからの数日間、学生たちはワークシートを読み、それぞれの作品の著者は誰だろうと考える。そして、必然的に、自分の作品と比べて、どちらが優れているだろうと自問自答することになる。また、どうすれば作品を改善できるかについて考える。配られたのが自分の作品だった場合は、ほかの学生がそれを気に入るだろうか、自分の作品だと気づくだろうかと思いを巡らせる。(p.141)
これは自分に才能があると自信を持っている者にも、不安を感じている者にもきつい環境だったようだ。
作家のジェイ・ウィリアムズは、そこは「毒蛇の巣窟」であったと語っている。
そこで彼女は、「自信がなく、麻痺した状態」で学生時代の二年間を過ごしたという。それもすべて、エングルが意図した状況だった。「私たちは、学生を叩き、または説得し、震え上がらせて、駆け出しの作家が自分の作品に対して抱く幻想を振り払う。そこから知恵というものが生まれるからだ」とエングルは語っている。(p.141)
ワークショップの講評会では、「作家たちは集中砲火を浴びている兵士のように頭を下げ、黙って話を聞いてから、その場を立ち去った。自分自身と、自分の作品が、集中砲火を浴びるんだ。強烈だったよ」とドハーティは語る。(p.141)
これらの話からもわかるように、かなり強烈な場だったようだ。僕らがパターン・ランゲージで行っているライターズ・ワークショップも、もちろん初心者にはドキドキして緊張する場ではあるが、ここまで厳しい雰囲気ではない。このあたりは、ソフトウェア分野の明るくオープンな雰囲気がうまい具合にブレンドされて進化したと言えるかもしれない。
今回初めて創作の世界でのライターズ・ワークショップの話を読んだのだが、非常に興味深かった。もっと歴史と形態について知りたいと思った。
そして、この本の重要な部分としてやはり触れなければならないのは、「身を粉にして小説を書く」人生を送ったカーヴァーの創作人生についてである。
カーヴァーは、一九八三年に「パリス・レビュー」のインタビューで、自分の人生の物語をフィクションに変換するためには、「並外れた大胆さと、非常に高い技術と豊かな想像力をそなえていなければならない。そして、自分の秘密をばらす覚悟が必要だ。自分の知っていることについて書けとくりかえし言われてきたけど、たしかに自分の秘密ほどよく知っていることはない」と語った。(p.269)
レナード・マイケルズは、カーヴァー(レイ)が妻のメアリアンとの生活のなかでいかにして小説を生み出してきたのかについて、次のように語っている。
カーヴァーの小説を真似して書くことはできるけど、彼と同じところで生まれ育って、彼の身近な人たちの話をずっと聞いていたのでなければ、本当の意味でカーヴァーのような小説を書くことはできない。彼がかかわり、一緒に暮らしている人々はみんな、ある意味では彼の小説への参加者だった。メアリアンはものすごく大量の題材を彼とともにくぐり抜けてきたんだと思う。そして彼女とレイは、それらの小説のための代価として、彼らの人生そのものを支払ったのだろうと僕は思う (p.294)
この言葉は、僕にとって非常に発見的だった。「彼がかかわり、一緒に暮らしている人々はみんな、ある意味では彼の小説への参加者だった」という部分と、「それらの小説のための代価として、彼らの人生そのものを支払った」という部分が、である。普通とは異なる見方であるが、それは真実であると思った。そして、僕も同じように、僕のつくり出すもののために、僕とかかわりのある人たちは「参加」し、僕らはその「人生」を対価として差し出している。対価として支払う度合いの違いこそあれ、人はそうやってつくっている。そうやって生きている。
この視点の転換は、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』を読んだときと同じような衝撃があった。ドーキンスは、生物が遺伝子をもっているのではなく、遺伝子が生物をヴィークルとして自らが残るようにさせているのだ、という視点の転換をもたらした。もちろん遺伝子が意思や知能を持っているという意味ではなく、物事の主と従の関係は、僕らが当たり前と思っているほど単純には決められないのだ、という話だ。
これまでも、僕は、作品をつくる人が作品につくらされているという関係になるという話を、宮崎駿の言葉などを引用しながら語ってきたが、それはひとつひとつの作品に対してのことであった。上述のマイケルズの言葉は、それを超える範囲においても、同様のことが言えるのだ、ということである。これはすごい。
レイモンド・カーヴァーは、のちにアイオワでワークショップをもつことになるのだけれども、そのときの学生ダン・ドメネクは、「レイが書くことを愛していることが、僕には魅力的だった」(p.386)と語っている。そして、「書くことについて語るときは、彼は情熱的で、独断的だった」(p.387)と。この部分は、自分の経験に照らしてもよくわかる。
作品集『ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズ』の前書きで、カーヴァーは「幸運」について語っている。
ごくまれに、雷が落ちる。<中略>雷に打たれるのは、あなたの友人であるか、かつて友人だった男性または女性かもしれない。その人は酒を飲み過ぎているかもしれないし、まったく飲まないかもしれない。その人は、あなたといっしょに出席したパーティーのあとで、誰かの奥さんと、あるいは旦那さんと、あるいは姉か妹と姿を消したかもしれない。教室の後ろのほうに座って、何かについてひとことも意見を述べなかった若い作家かもしれない。とろいやつだ、とあなたは思っただろう。その作家がトップテンの候補者に選ばれる日が来るとは、誰も想像しなかっただろう。(p.653)
ここで書かれている「酒飲み、禁酒家、女たらし、とろいやつ」というのは、レイ自身が一度はなったことがあった。重要なのは、このあとに続く「雷に打たれる人」についての部分である。カーヴァーは言う。
だがそれは、一生懸命に努力して、書くという行為が人生のほとんどすべてのものより重要で、呼吸をすること、衣食住、愛と神に並ぶほど大事だと思っている人にしか起こらないことだ(p.653)
その通りだと思う。この指摘は真実を射抜いている。常にそれに取り組み、考え、悩み、もがいている人にしか雷は落ちないのである。
まえがきの結びにカーヴァーは、ここにあるのは、「短編小説にしかできないやり方で、かたちを与えられ、目に見えるようになった美にほかならない」ことを読者が発見するように願っている、と書いた。(p.654)
「○○にしかできないやり方で、かたちを与えられ、目に見えるようになった美」!なんてかっこいい考え・言い方だろうか。僕もそういうものを自分の分野でつくりたい、そう思った。
最後に本書の最後に寄せられている村上春樹の「解説――身を粉にして小説を書くこと」のなかの言葉を少し取り上げたい。
カーヴァーはいわば「自分の身を粉にして」小説を書いた人だ。その挽き臼にかけるマテリアルのひとつひとつを、彼は自分の身の内からもぎとっていった。そこにはもちろん痛みがあった。時にはまわりの人々を痛めつけることもあったが、その痛みはだいたいにおいて彼自身に戻ってきた。彼にとって生きるということはそのまま小説を書くことであり、小説を書くというのはそのまま人生を生きることだった。(p.735)
レイモンド・カーヴァーの「生きざま」(あまり好きではない言葉だが、ここにはたぶん相応しい)には、小説家であるというのが本質的にどういうことなのかが、きわめて率直に示唆されていると僕には思える。それは、「何かを書き続けるというのは、自分から何かを削り取り続けるということなのだ」という事実である。僕らはその削り取られたぶんを、どこかからもってきた何かで必死に埋めていかなければならない。(p.736)
ここで語られていることは、僕には、村上春樹自身のことにも重なって見える。ただしひとつ違うのは、カーヴァーは様々なものに依存することでそれを埋めようとしたが、村上はそれを自分なりの方法で心身を鍛え、書き続けようとしているということではないだろうか。村上春樹が日々走り、心身を鍛えながら、創作と重ねて行くのは、まさにそのためだろう。僕も自分なりのスタイルを確立していきたい。それがあっとうい間に擦り減ってしまわずに、つくり続けるために必要なことなのだ。
そして、人生というものは死との関係のなかで考えられなければならない。人の生は誰でも限られており、作家も同様に、つくり続ける人生にも終わりが来る。レイモンド・カーヴァーが亡くなったのは、五十歳のときだった。そのとき、四十歳を目前にしていた村上は次のように感じたという。
彼をこうして失ったことは本当に残念な、悲しい出来事ではあるけれど、五十歳まで生きて、これだけ多くの価値ある作品を書き上げ、それをあとに残して静かに世を去るというのは、ひとつの素晴らしい達成であり、美しい人生のあり方かもしれない、と。そのときの僕には―――実に愚かしいことだが―――五十歳というのはずっと先の方に控えている人生の立派な節目のように思えたのだ。(p.726)
しかし、実際に自分が五十歳になったときに、そのように考えたことを反省したという。
僕自身のことを語らせていただければ、五十歳を迎えた時点では僕は小説家として、自分が書きたいことの―――あるいは書けるはずだと感じていることの―――まだ半分も書いていなかった。「もしこんなところで自分が病を得て、死ななくてはならないのだとしたら、悔しくてたまらないだろうな」とつくづく思った。文字通り死んでも死にきれない気持ちだ。
僕は五十歳というポイントを越えてから、長編小説だけに限っても『海辺のカフカ』を書き、『1Q84』を書き、『色彩を持たない多﨑つくると、彼の巡礼の年』を書いた。その他にもいくつかの短編小説集と中編小説を書いた。もし作品目録からそれらの作品群がまとめて削除されるとしたら、それは(他の人がどのように考えるかはもちろんわからないが)僕としてはとても耐えがたいことだ。それらの作品は今では僕という人間の、欠くことのできない血肉の一部になっているのだから。一人の作家が死ぬというのは、ひとつの命のみならず、来るべき作品目録を抱えたままこの世から消えて行くことを意味するのだ。(p.727)
いま四十歳という位置にいる僕にとって、この村上春樹の言葉から得られるものは大きい。
僕も目の前のことに必死になりながらも、このことを常に考えながら生きていきたい。
自分が限りある人生のなかで、世界にどのような作品・成果をどれだけ残せるだろうか、と。
Creative Reading [創造的読書] | - | -