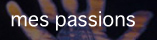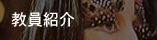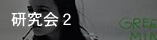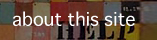2007年11月
この論文は、laconismeとabondanceという対立する2つの文体概念を取り上げ、一般的には革命期のディスクールはlaconismeを評価しabondanceを批判していたという論に対して、その両方が共存していたことを指摘し、laconismeを一方的な支配概念とする従来の見解に修正をはかっている。
I - Le laconisme
論文はまずlaconismeの系譜を辿る。その哲学的観点から挙げられるのは、ジョン・ロックである。人間知性論の中でロックは、「レトリックの方法は、完全なるまやかしをつくる」と主張し、以後啓蒙主義の思想の中では、演説者の「まやかし」を批判することがその課題となる。革命期においては、コンドルセが「演説においては、雄弁に頼る者は、人々の理性をまどわせるだけである。国民の代表者が行なうべきことは民衆の啓蒙である」として、雄弁を断罪する(Condorcet, Rapport sur l'instruction publique, 1792)。またシェイエースなどイデオローグが提唱するのは、分析体«style d'analyse»であり、これは哲学言語として記号の一義性を求めるものである。
文体論からみれば、このlaconismeにたいする「趣味」は、イエズス会などのloquacité(饒舌さ)にたいする嫌悪からである。反対に laconsimeの評価は、たとえばJaucourtによって書かれた百科全書の項目にみられる。またJaucourtの前にはモンテスキューが法的言語は簡素であることを指摘している。革命期においてもlaconismeの文体こそがautoritéが持たなくてはならない言語であるとする。
Il est temps que le style mensonger, que les formules serviles disparaissent, et que la langue ait partout ce caractère de véracité et de fierté laconique qui est l'apanage des républicains. (Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française, 16 prairial an II/4 juin 1794)
嘘の文体、隷属的な表現は消え去る時がきた。言語は、どこにおいても、本物であることと、簡潔さを誇りとする性質をそなえる時がきた。この性質こそが共和主義者固有のものだ。
以上、革命期においては、laconismeこそ、議会、教育といった公のあらゆる場所で重視されるべき文体であると言える。しかし、その一方で、それとは逆の考えも存在した。
II - Un anti-laconisme ?
まず大切なのは、ロックの主張が18世紀の主張がかならずしも支配的な考え方であるとは言い切れないことである。たとえば、synonymeの考察をする立場からは、かならずしもlaconismeが悪いとは言い切れない。Synonymes français(1736)を書いたGirardにおいては、正確に話すことと雄弁であることは矛盾しない。Beauzéeはpléonasmeや métaboleを、 Marmontelは、abondanceやamplificationを使用することを進めているほどである。これは2名に関しては、同時代の中で古典主義的規範に属する人物ではないかという反論もあろう。しかし同じ考えはDiderotやRousseauの中にも認められる。さらにRousseauの後継者を自称するMaratは、«éloquence du coeur»(心の雄弁)を主張する。
III- Deux modèles discursifs pour deux situations de parole
実際に啓蒙主義者たちにとっても、絶対君主制の批判のためには雄弁は必要であったし、百科全書派も、こうした単純な対立を乗り越える道を探っていた。たとえばMarmontelはジャンルによる区別、哲学においては、laconismeを、詩や弁論においてはabondanceを提唱した。前者においては語の「本質」が問題とされ、後者はより「自由」であり、正確さがあれば十分であるとする。また革命家たちも法律の執筆においては laconismeを採用するものの、決してabondanceを捨て去ってはいない。たとえばDomergueにとってはlangue exacteとlangue ornéeは等しい価値を持つものとして扱われる。
La langue exacte est d'une utilité reconnue par tout le monde, sans exception. Ces grands écrivains, qui embellissent la raison des charmes de l'éloquence et de la poésie, en font aimer et en étendent l'empire. La langue ornée va devenir très utile à toutes les institutions publiques, à tous les jeunes gens que le nouvel ordre des choses destine à porter la parole dans les assemblées civiques, à toutes les personnes de l'un et de l'autre sexe qui voudront être initiées dans l'art d'écrire. (Domergue, Journal de la langue française, n° 4, 22 janvier 1791, p. 134-135)
正確な言語は、例外なく全員が有用性があると認めている言語である。これらの偉大な作家たちは、雄弁と詩の魅力で理性をより美的なものとして、理性を愛させ、そしてその帝国を広げるのだ。飾り立てられた言語は、あらゆる公の組織にも、物事の新たな秩序によって、市民の集まりで発言をするようになる若い人々にとっても、書く技術を身につけようとしている人なら男女問わず、有益な言語である。
さらにLa Harpeは弁論術の手ほどきを提言する。また革命期中の唯一の弁論術の書、Drozのl'Essai sur l'art oratoire (1799)は、最終的にはいかなる反響も呼ばなかったが、雄弁の最終的なコンセプトがここに存在する。「自由な状況における弁論術の有用性」ということである。
以上、laconismeとabondanceは概念的な対立があるのではなく、言語のジャンルによって使い分けられるべきなのだ。すなわち哲学者、立法者においては前者の、詩人、演説家においては後者の使用が勧められるのである。
この論文で扱われているのはフランスの文献学の成立における政治性と、その言語と政治の関係性を覆い隠すことによって、言語学の科学性が打ち立てられるようになった19世紀における言語への問いの変遷であり、それをロマンス語の重視と、基層文化としてのケルトの重視という2つの「極端な考え」を、 François RaynouardとFrancisque Michelの活動によって検討するとともに、そうした極端さ、いわば偽りの科学が消えるとともに、中性化された言語学が生まれたことを明らかにする。
まずはロマニスムである。トゥルバドゥールの詩によって代表されるオック語文学は、その草稿が個人によって所蔵され、忘れ去られていたが、18 世紀になると、中世の遺産に注目が集まることになる。しかしそれが文学研究となるためには、コーパスを整備し、一貫性のある原則のもとで研究されなくてはならない。それを最初に手がけた人物として位置づけられるのがFrançois Raynouardである。
アカデミー・フランセーズ辞書第5版の共同執筆者でもあったRaynouard(1761-1836)は、1816年から21年にかけて、Grammaire comparée des langues de L'Europe latine avec la langue des troubadours, Choix des poésies originales des troubadoursを編纂、出版する。そしてこの中でRaynouardは「プロヴァンス語が諸新ラテン語の起源にあった」と主張した。一方今日でも彼の主要な著作とされているのは、死後出版も含む1836-1844年にかけて編纂された6巻本、Lexique roman ou DIctionnaire de la langue des Troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latineである。この書において十分な文献がそろったといえる。ここにおいてロマンス語とは何か、その位置づけが確定することになる。つまりプロヴァンス語が一文化として復活したわけである。
Saint-GérandはRaynouardのトゥルバドゥールの言語に対する考えを次のようにまとめる。
11世紀に新ラテン語諸語の分化が決定的になる前に、ラテン語からロマンス語が生まれており、これが«intermédiaire»、「介在」となっている。ストラスブールの誓約とBoèceの物語を語る南仏の叙事詩がこの言語の書き言葉としての形態を伝えている。1000年頃のシャルルマーニュ帝国の分割後も、この言語は現在の南仏諸地方言語でありつづけた。この考えにしたがえば、ここで推定されるロマンス語とは、ラテン的価値をヨーロッパの別の言語を通して保証していくことになる言語の母であり、かつその長女ということになる。そしてヨーロッパ諸語は、それぞれの民族の発音に対応した変化をこのロマンス語に加えることになったとRaynouardは言う。たとえば、ラテン語のpanemは、南仏、あるいはプロヴァンス語ではpanとなり、これがイタリア語でpane, フランス語でpainとなったとする。このRaynouardの主張が否定されるためには1836年のFriedrich DiezによるGrammatikを待たなくてはならない。これをもってようやくプロヴァンス語も他のラテン語系の言語と等しい位置におかれたのである。
Raynouardの論拠の出発点となったのは、オイル語の音声は、オック語とは異なり、後者が昔からの音声の色合いを保っていたという点である。しかしSaint-Gérandは同時代におけるイデオロギー的なコンテクストを2点指摘する。
まずは比較言語学の影響である。その思想的影響とは、すなわち、印欧諸語を通して、言語と宗教の起源へと遡ることができ、それが人類の文化の原初的状況を明らかにするという点である。この視点から言えば、Raynouardにとってのプロヴァンス語とは、まさに原始語といってよい地位を持っていたのだ。言語の過去を遡ることは、文学テキストという形式のもとで、文化的な財産、共同体の伝統の一部となっていくことを意味する。こうした国民、民族意識は、政治的な意図に先立っているのだ。
2つ目にあげられるのが、詩という表現形式である。スタール夫人が、「ロマン主義の詩がトゥルバドゥールの詩がその起源となっている文学の直接の後継である」だと言う時、このロマン主義の詩とは、フランスという民族、フランスという土地に結びついているものである。この主張は、 Raynouardにとっては、プロヴァンス語とトゥルバドゥールの作品は、民族とその祖先へとつながる伝統を持っていたことを意味する。 ではRaynouardの「誤り」はどこにあったのか?第一の段階においては、Bopp, DiezのようにRaynouardも言語を、言語以外の人間的事象から分離させ、文字、語、語源について歴史的変遷を考察していた。しかし次の段階において、こうした言語形式を、トゥルバドゥールの文学作品に結びつけることによって、言語の中に原初の人間の真実というものをみようとしたのである。この点がSaint-Gérandが指摘する「誤り」である。つまり言語外のものへの言及は、言語の科学性を証し立てるのに役立たないのだ。
次にFrancisque Michelのスコットランド研究が挙げられる。Michelは1830年代から中世のテキストを出版し始めるが、特にイギリスにわたり、様々な第一次資料をまとめあげたことで知られる。つまり国民文学を作り上げるために必要な草稿を収集するのに寄与したわけである。Saint-Gérandが詳細に分析するのはCritical Inquiry into the Scottish Languageである。
Saint-GérandはMichelのテキストを10の要旨にまとめている。1)スコットランド語が古英語の方言であるとすることへの批判、2)英語とスコットランド語は同じ語根を持っているがそれぞれ独立して変化していったということ。3)スカンジナビア諸言語のスコットランド語の単語に対する影響、4)ノルマン民族によるケルト世界の没落と、フランス文化のイギリス圏における影響、5)文学にも適用される氏名の、語源にさかのぼっての作成、6)中世初期におけるフランス語の宮廷における浸透、その一時的衰退と14世紀における復活、7)パリの大学で学んだスコットランドの僧侶たちの言語、文化に対する影響、8)托鉢修道会における説教の言葉への俗なる現地の言葉の使用、9)蔵書における、フランス文学の資料への強い興味、10)スコットランド文学へのフランス文学への影響。つまりMichelの主眼は、フランスという言葉の定義もおろそかに、フランス文学の、スコットランド文化創成期における影響を謳っているのだ。以後、言葉にはひとつの亀裂がはしり、フランス語をモデルとした技術に関連した言語を使う層と、ゲール語の影響を受けた共通語を使う、洗練されていない社会層である。この社会層の中ではフランス語からの借用語は急速に消えていった。
Michelが集めた原典や歴史に関する情報は、同時代においては「信頼に足る入念な仕事」と評され、この時代において知りうることはすべて集約された観があるテキストである。しかしながら、MIchelのテキストにおいては、フランス人がスコットランドに文明をもたらしたという前提がいたるところで見られ、文献学の批評理論にのっとった作業はなされていない。しかしこのような指摘では単に言語学を学問内部に押し込めるだけで、Michelにみられるイデオロギー性、政治的な意味は浮かんでこない、とSaint-Gérandは指摘する。そのためにSaint-Gérandは、Michelにおけるlangueの厳密な定義、そして言語学の論争から生まれてくる様々な考えー国民語、ケルトとロマンスの対立、方言研究の目的と結果ーに着目する。
Michelにとってlangueとはmoyen de communication quotidienne dont la littérature fournit l'image la plus intéressante parce qu'elle en fixe le mouvement et permet l'inscription de norme d'usage「日常のコミュニケーションの方法であり、そのもっとも興味深いイメージは、文学が、その動きを固定し、慣用という規範によって書き記すことによって、もたらしてくれる」という直感的なものでしかなかった。それによってMichelはフランス語は、文明化された社会の表現媒体であり、それがスコットランドにもたらされたという文化論に終始してしまう。またさらに「フランス」語、「フランス」文化、と言った時のフランスそのもののアイデンティティも問われることがない。またスコットランド語の方は、当時の言語学者たちが規定していた「クレオール化」している言語とみなされていた。
第2にSaint-Gérandが挙げるのは、Michelの文献学がロマン主義の時代を出発点としていることである。Saint-Gérandはかつての外交官であったPaul de BourgoingのLes Guerres d'Idiomes et de Nationalitésを取り上げ、言語の特殊性に基づく国民的要求が起こったのが、19世紀半ばであり、これが政治的混乱を作り出しているとするBourgoingの指摘に言及する。この考えに対する返答が4年後のAuguste ScheleicherによるLes Langues de l'Europe moderneである。ここでは民族の歴史が言語の歴史によって強化される。
一方D.Monnierは1823年の時点ですでに、音声現象にもとづく地理的な図を作ることを考える。1844年にはNaberが英語とスコットランド・ゲール語の境界を画定する。1866年、Schuchardtは言語的な境界線が引けるとしてもそれはメタフォリックにしか可能ではないと強調する。1878年にはSébillotがブルターニュの地においてgalloとbritonとを区別する。こうした事実はイデオロギーの反映に他ならない。つまりスコットランド語の語彙の多くがフランス語で構成されているということは、ケルト語の拡張に反対し、ロマンス語に起源を求めることと等しいのであり、征服者のケルト人を文明世界の境界へと、印欧語族の隅へと追いやることに等しいのである。
こうした時代の流れをみてくると、Michelは結局言語を語彙の分類というレベルに限定して、国民的同意によって統一化される共同体の政治表現形式としてのlangueには行き着いていないのだ。Michelの言う、文明の進歩、文献学の方法論といったものの背後には実は、政治性が露見してしまうのだ。 結果として、RaynouardやMichelの考えは、ロマンス語あるいはプロヴァンス語の優越化、フランス文化のスコットランドへの流入という「非学問性」のために、否定されるに終わる。しかしそれにともなって登場した科学とは何か?1866年、言語の起源という言語外的要素に依拠する研究を、パリ言語学協会は拒否する。それはしかし同時に、言語のもつ政治性を覆い隠してしまうことになった。文献学の起源は、起源の問いを無化することから始まり、やがて国語の単一性のために、ロマニスムとケルティスムの対立を消し去ったのだ。つまり学問の科学性は、国家語という政治性と新たに結びつくことで成立したのである。
 「これ絶対気に入りますよ」と、大学時代に後輩が貸してくれたレコードは、Small FacesのSmall Facesと、The WhoのSell outと、John CaleのこのアルバムParis 1919だった。ロックは前衛であるだけではなく、一線を引いたところにもロックを探求したレコードがあるのだと、気づかせてくれたのがこのアルバムである。Velvet Undergrandを信奉したり、Lou ReedのBerlinをやたら褒めそやすのではなく、喧噪のその後にも、たとえポップな音楽であっても、「前衛」でありつづけることができる、 Velvetのようなスタイルをとらなくても、禁欲的に「ロック」であり続けることはできる、それに気づかせてくれたのがJohn Caleである。
「これ絶対気に入りますよ」と、大学時代に後輩が貸してくれたレコードは、Small FacesのSmall Facesと、The WhoのSell outと、John CaleのこのアルバムParis 1919だった。ロックは前衛であるだけではなく、一線を引いたところにもロックを探求したレコードがあるのだと、気づかせてくれたのがこのアルバムである。Velvet Undergrandを信奉したり、Lou ReedのBerlinをやたら褒めそやすのではなく、喧噪のその後にも、たとえポップな音楽であっても、「前衛」でありつづけることができる、 Velvetのようなスタイルをとらなくても、禁欲的に「ロック」であり続けることはできる、それに気づかせてくれたのがJohn Caleである。
今あらためて聴き直してみると、オーケストラの入り方が過剰で、仰々しいのが耳につく。脳天気な曲もあったりして、John Caleの「転向」は果たして正しかったのかと疑問に思わないでもない。
しかしJohn Caleが作りたかった、クラシックとは違う世界での「美の世界」、Roxy MusicやT-Rex、あるいはDavid Bowieのようなまがまがしい見せ物とは違うレベルで追い求めようとした美の世界が、ここにはある。その意味でこのアルバムは、ロックがアンディ・ウォホールが口出しするようなまがいものではなく、ひとつのジャンルとして認識されうる標準まで達したことをきちんと証明してくれるアルバムであると言える。
Lou Reedは「インテリになりたかったやくざ」、John Caleは「やくざになりたかったインテリ」。確かにJohn Caleの音楽は、その品の良さからいえば、インテリの遊戯なのかも知れない。表題曲などは確かにオーケストラを導入して、きわめてインテリぽく作られていて、鼻につくかもしれない。でもこれを聞いていた当時の僕は、たとえ寝そべって聞いていてもロックは存在し続けるのだと、考えていた気がする。それは今から考えれば、早くも60年代半ばにたとえばThe KinksがSunny Afternoonで描いていた世界だ。しかもThe Kinksは70年代にはいってもしつこくその世界をMirror of Loveのような曲で何度も念を押す。John Caleも、Velvetへの反動なのか、Lou Reedへの敵意なのか、そのけだるさを全面的にロックとして演奏してはばからない。その決意がこの70年代初頭の動きだったのだろう。しかしこのけだるさは、けっしてこの時代だけにとどまることはない。ロックを聴き始めて、正面切った反抗だけがロックではないと気づくとき、日常の生活の中でもロックを聞き続けようと思うとき、John Caleの作り上げた様式美もひとつの地道な営為だと思うのだ。
 あるレコード屋(死語!)の試聴機に、「洋楽ファンにもぜひ」と書いてあったので、早速試聴し、見事気に入ってしまった日本のミュージシャン。しかしその音楽は、洋楽とか日本とか、そうした国籍を消し去った雰囲気がある。The Guitar plus meは全編英語で歌っているが、だから洋楽っぽいというわけではない。むしろこうした種類の音作りが、今、世界のあらゆるところで様々なミュージシャンによって行なわれている気がする。趣味や、感性が日本も欧米もそんなに変わらなくなってきているし、日本にこだわって音楽を考える時代でももはやなくなってきている。みな最近の若い人たちは、軽々と国境を越えて、自由に自分の世界を表現しているように思う。
あるレコード屋(死語!)の試聴機に、「洋楽ファンにもぜひ」と書いてあったので、早速試聴し、見事気に入ってしまった日本のミュージシャン。しかしその音楽は、洋楽とか日本とか、そうした国籍を消し去った雰囲気がある。The Guitar plus meは全編英語で歌っているが、だから洋楽っぽいというわけではない。むしろこうした種類の音作りが、今、世界のあらゆるところで様々なミュージシャンによって行なわれている気がする。趣味や、感性が日本も欧米もそんなに変わらなくなってきているし、日本にこだわって音楽を考える時代でももはやなくなってきている。みな最近の若い人たちは、軽々と国境を越えて、自由に自分の世界を表現しているように思う。
the guitar plus meはミニアルバムも含めて5枚ほどアルバムを出していると思うが、どのアルバムも構成はほぼ同じである。無表情なうち込み、ときおりループする電子音と、アコースティックギターの音色がすべての曲調を作っている。
このアルバムのテーマは冬。小品が多い彼の作品の中では珍しく、1曲目Silver snow, Shivering soulは10分ほどもある長尺な曲である。でもこの曲の中で果てしなく続く、打ち込みと電子音のゆらぎがとてもすばらしい。ここまで人工的でありながら、ゆっくり舞い散る雪の自然の情景がとてもリアルに浮かんでくる。
どの曲もリズムは単調であるのだが、その曲、曲ごとにテーマがあって、微妙な曲調の違いがそのテーマを浮き立たせているのが楽しい。例えば4曲目はNew year。新年を迎える時の浮き浮き感が伝わってきて、ちょっとした幸福を噛み締めることができる。
the guitar plus meの憎いところは、同じように見えても、この「テーマ」ということにとてもこだわってアルバムを作っている点である。動物のユーモラスな情景がうかぶZoo, 水をテーマにしたWater musicなど、音によるイメージの喚起がとても上手に作られている。
そう、職人の手仕事感といえばいいだろうか。それが一番よく感じられるのは、やはりアコースティック・ギターの音色である。パーカッションが作る音の空間を刻むようにしてギターの音がおかれていく。そんな構成美にとてもひかれる。そんな構成にとことんこだわったのは、2003年のTouch meだろう。ミニアルバムの5曲目Bakeryから6曲目Castleへの流れは、ギターの音は、チェンバロにも似て、バロック的な構成が見事に生かされている。特に5曲目の終わり、単純なリフを繰り返すギターの音色がだんだん大きくなっていき、突然途切れて終わるところで、僕は大きく息をついてしまう。
 ながらく再発を待っていたカナダのシンガーソングライターBruce Cockburnのセカンド・アルバムです。サードもよいけれども、初めて聞いたのがこちら『雪の世界』だった。弾き語りの質素なアルバムであるが、聞き込むとかなり曲ごとに雰囲気が違うことがわかる。比較的ピッキングが強くて、Stephen Stillsのギターワークを思わせもするが、このアルバムはずっと内省的だ。
ながらく再発を待っていたカナダのシンガーソングライターBruce Cockburnのセカンド・アルバムです。サードもよいけれども、初めて聞いたのがこちら『雪の世界』だった。弾き語りの質素なアルバムであるが、聞き込むとかなり曲ごとに雰囲気が違うことがわかる。比較的ピッキングが強くて、Stephen Stillsのギターワークを思わせもするが、このアルバムはずっと内省的だ。
1曲目はタイトルにブルースとついているが、ギターの音色はずっと軽快で、あざやかなコード進行が楽しめる。朝起きたら外は一面の雪景色、まさにジャケットの写真通りの世界が1曲目から描かれる。2曲目もずっとひかえめなギターとヴォーカルだけで作られていて簡素な感じだが、それでも、ギターの緩急をつけた展開が実はダイナミックな曲だ。
また曲調もヴァラエティに富んでいる。4曲目はカントリー・フォークの懐かしい雰囲気をたたえた曲。かとおもうと5曲目はピアノがはいり、6曲目はブリティッシュフォークの憂いをたたえ、8曲目はブリティッシュトラッドの香りがする。
このように様々なテクニックを随所にちりばめながらも、決してそれを全面に出さず、音を織り込んでいるところがこのアルバムの素晴らしいところである。
曲がずば抜けてよいわけではないし、ボーカルも朴訥として、けっしてうまいとは言えない。アルバムのどこかに盛り上がりどころがあるわけでもない。CDで聞いているとB面の1曲めがどこだか見当もつかない。それほど単色の世界なのだ。しかし、このように控えめでありながら、聞けば聞くほど、1曲、1曲が個性を放ち始めるところが、このアルバムが名盤たるゆえんではないだろうか。
ところでこのBruce CockburnやArtie Traum(名盤Double back!)といったシンガーソングライターは、その後いわゆるギターの教則本といった世界に入っていく。それはそれで彼らのギターテクニックが卓越しているという証拠ではあるのだが、もはやアルバム1枚でひとつの世界を創りだすだけの余力は残っていないのだろうか。そこが少々寂しいところである。ジャケットもそうで、近年のアルバムはなんだかヘアーバンドが似合いそうなふぜいで、それじゃあ南こうせつだと少し悲しくなったりもする。
 お決まりのリフ、無駄なシャウト、どこかで聞いたことのあるおなじみのメロディ展開、そこらへんに落ちている、「ロックンロール」の常套句をちりばめたこのアルバムは、普通のミュージシャンであれば、オリジナリティのかけらもない失敗作として、片付けられてしまうだろう。
お決まりのリフ、無駄なシャウト、どこかで聞いたことのあるおなじみのメロディ展開、そこらへんに落ちている、「ロックンロール」の常套句をちりばめたこのアルバムは、普通のミュージシャンであれば、オリジナリティのかけらもない失敗作として、片付けられてしまうだろう。
でも、Ryan Adamsのアルバムに感じることは、「この程度のことならば、やってしまえる」という、不敵さだ。「ロックンロール」は中途半端な、彼のアルバムにして珍しく、ボーナストラックの方が本編よりいいのではと思ってしまうほど、本心の見えないアルバムなのだが、「望みとあればくだらない作品だって作れるぜ」という歪んだ心情を堪能できるところに、Ryan Adamsの一筋縄ではいかない、持って生まれたロック気質を感じてしまう。こうしたアルバムが出てしまうと、あくせくとロックンロールのパーツを接ぎ木してアルバムを作っている凡百のミュージシャンは塵と消えてしまいそうだ。とはいえ、これは音楽の健全な聞き方ではないだろう。音楽を聞くというより、ミュージシャンの破天荒な生き方そのものに音楽を通して接しているようなものだ。
Neil Youngのアルバムにもそうしたものを感じてしまうことがある。アルバムそのものの楽曲より、こんなアルバムを作ってしまう人間とはいったいどんな人間なのだ、という人本位の聞き方だ。
実際一曲目から、どう考えてもミスマッチなプロデュースでしかない楽曲が並ぶ。ヴォーカルも一歩調子だし、サビも、今は死語かも知れないが「産業ロック」のエッセンスがふんだんにぶちこまれている。シングルカットされたらしい5曲目のSo Aliveなど、ギターのメロディの陳腐さに苦笑いをしないではいられないほどの、古びた80年代ブリティッシュロックを聞かせてくれる。そして10曲目のアルバムタイトル曲Rock N Rollだけがピアノの弾き語り、しかも中途半端なフェイドアウトというふざけ方である。
結局はRyan Adamsが好きだからこそ、こんなアルバムにも価値を認めてしまうのだ。こうした生き方をしてしまうロック・ミュージシャンだからこそ、駄作にもリスナーとして愛を注いでしまうのだ。ミュージシャンにつきあって、新譜がでればどんなものでも買ってしまう、Ryan Adamsはそうしたつきあい方をせまられるミュージシャンである。
日本盤のボーナストラック「Funeral Marching」はなかなかの名曲です。
この「芸術について」という章で明らかにされるのは、ヨーロッパの普遍的な言語になったフランス語が、どのように自らの資質をルイ14世紀下において、完璧にまで高めたかということである。
フランス語がそのような普遍的な地位を占めるためには、ラテン語を凌がなくてはならないが、まず冒頭で紹介されるのは、法律家たちがラテン語では立派な文章がかけても、フランス語ではそれが不可能であるという現実である(p.62.)。
しかし、フランス語の格調高さ、耳への心地よさが、説教という雄弁術(ジャン・ド・ラジャンド)や散文(バルザック)にも見受けられるようになる。そしてフランス語の純化に大きな役割を果たしたものとして、アカデミー・フランセーズ、ヴォージュラの名が挙げられる(p.64.) 。ラ・ロシュフーコーの『箴言集』も、その表現、考えを圧縮した「簡素かつ微妙」な表現という点で引かれている。そしてフランス語の形を決めた作品として、ヴォルテールはパスカルのLettres provincialesを挙げる。またボシュエについても『世界史論』を挙げ、評価するのは、もっぱら、その文体、「雄渾な筆致」、「簡潔で真に迫る表現」である(p.68.)。またこの時代においては、古代にはなかった形式が生まれる。それがフェヌロンの『テレマック』、ラ・ブリュイエールのLes caractèresである。後者において、ヴォルテールは「緻密で、簡潔で、力強い文体、絵画的な表現、斬新で、しかも文法的な規則に背かぬ文章」と述べている(p.71.)。
続いて、ヴォルテールは国民文学の概念に言及する。国民の文学は、「まず詩が天才の手で生まれ、これに導かれて雄弁が現れ」るとする(p.73.)。そしてフランスの場合散文の技量を進歩させた作家としてコルネイユがひかれる。
ヴォルテールは次にラシーヌを引くが、このラシーヌ観こそ、17世紀におけるフランス語の完成という主張の代表であると思われる。ラシーヌはヴォルテールにとって「言葉の自然な美しさを、いわば完璧の域に到達させた」(p.76.)作家である。
ルイ14世の時代の最後に出た作家として挙げられているのがラ・モット・ウダールとジャン=バティスト・ルソーで、後者についてはマロを引き合いにだしているが、マロの文体を「無様な」ものとし、それに対して現代は「純粋な言葉」であるとする。
ヴォルテールは、「時代と、主題と、国民性にふさわしい美」(p.83)は限定されており、一人の作家がそれを表現しえたなら、あとの時代は何も表現することがなくなると述べ、まさにこの時代が、芸術の完成された時代であると位置づける。
そして最後に、いささか唐突に、「フランス語はヨーロッパ語になった」と述べる。ルイ14世紀の偉大な作家たちの後継者が、フランスから外へ出ることによって、フランス人持ち前の社交性を生かし、他国民にフランス語を広めたのである。