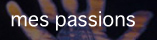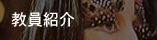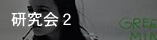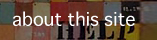2008年5月
 1970年初頭のイギリスのフォークムーブメントを最も良く表現した一枚であろう。重厚なベースの音、スコティッシュな伝統の響き、アコースティックなギターの旋律、そして控えめでありながら全体の空気を作り上げているストリングスなど、シンガーの、こうしたアルバムを創りたいという意図がひしひしと伝わってくる力作である。他人の曲だけを歌っていても、SSWのドノヴァンや、ニック・ドレイクなどに決してひけをとらない、時代を代表するアルバムである。
1970年初頭のイギリスのフォークムーブメントを最も良く表現した一枚であろう。重厚なベースの音、スコティッシュな伝統の響き、アコースティックなギターの旋律、そして控えめでありながら全体の空気を作り上げているストリングスなど、シンガーの、こうしたアルバムを創りたいという意図がひしひしと伝わってくる力作である。他人の曲だけを歌っていても、SSWのドノヴァンや、ニック・ドレイクなどに決してひけをとらない、時代を代表するアルバムである。
しかし、全体が同じ色調で染められているとはいえ、内容は単調ではない。ホプキンのヴォーカルは、瑞々しいが、決して少女っぽい歌い方ではない。むしろ堂々と声を響かせ、凛々しい歌声を聞かせてくれる。There's Got To Be Moreのようにノリがよく、しかも力強い抑揚を聞かせてくれる曲、Streets of Londonのようなフォークのミニマルな美しさが際立つ曲、さらにはWater, Paper and Clayは、単純なメロディが何度も打ち寄せるトラッドっぽい曲であるが、次第に、どんどん熱く荘厳になっていく展開は、決してフォークの一言ではすませられない、豊かな情感を表現している。
このアルバムでのメリー・ホプキンは、まさに日本盤タイトル『大地の歌』にふさわしく、しっかり大地を踏みしめ、自然の息吹を感じながら、生命があふれる喜びを歌っているように感じる。それはジャケットの美しい写真のせいもあるだろう。表のEarth song、裏のOcean Song、それぞれにふさわしい情景の写真が使われている。写真におさまる19歳のホプキンには、イギリスの過去と今が見事に結晶化している。
第四章では、まずプラトンに言及し、詩人が天啓を伝える人として描かれる。それは最初の天啓を受けて、最初の叙事詩を創ったホメロスから、その天啓を広めたrapsodes(吟遊詩人)のように、人々に広がっていく。さらには、教育の基礎ともなる。
この時代には二種類の詩があった。poésie eumolpiqueとpoésie épiqueである。前者はintellectuel et rationnelなものであり、後者はintellectuelでpassionnéなものである(p.74.)。
次にFabreは、劇の起源について述べる。それはオルフェウスの秘犠の俗化したものであり、デュオニソスの収穫の祭りがその始まりである。さらにFabreはdrameの語源に触れ、サンスクリット語で、輝かしい、美しいという意味をもつRamaという名が、フェニキア語でも同じ意味をもち、そこにアラム語とシリア語に共通の指示冠詞がつくことによってdramaという単語が生まれたとする。
最初はぶどうの収穫時の「田舎の余興」であったが、それが人々をすぐれて魅惑したことから、教養層の眼にもとまることになった。それをとりあげたのがThespisとSusarionであり、それぞれが悲劇と喜劇の起源となった。
こうした事態に気づいた国家は、宗教と風俗に危険となる場合、厳格な規則を課した。秘儀をもとに劇を仕立てることは許したが、秘儀の意味を解き明かすことは禁じた。作品の善し悪しを判断するにあたっては、音楽と詩の知識に秀でた審査官を置き、彼らは、すべてを秩序と規則に収めなくてはならなかった。プラトンはこの法がすたれたこと、人民が演劇を支配したことが、芸術の最初の頽廃であると言っている。
アイスキュロスは、演劇の真の創造者であり、ホメロスからうけた天啓にのっとって悲劇のなかに叙事詩の文体をとりこみ、簡潔で荘厳な音楽をつけた。さらに、音楽、絵画、踊りによる総合的な演出を試み、舞台装置による効果を展開した。
ギリシアの劇が秀でていた点は、秘儀の宗教から生まれた道徳的な意味を持っていた点である。したがって、普通の人々が舞台や音楽の華やかさに魅了されているだけなのに対して、賢者は、その中に潜む真理を受け取ることによって、より純粋で永続的な喜びを得ていたのである。
ソフォクレスとエウリピデスは、アイスキュロスの後継者として、ともに秀でていたが、形式を完成させることに心を砕き、劇の本質、すなわちアレゴリーの精神(génie allégorique)を変質させることになったことは否めない。さらには、エウリピデスが描いた逆境において堕落した英雄、恋に狂う王妃、といった情景の魅力が、アテネの道徳の腐敗の原因、宗教の純粋性を貶める最初の原因となった事実を認めざるを得ない。弱さや罪といったものが、本来ならばその意味を探すべきアルゴリーとして示されるのではなく、単なる歴史的出来事、想像力の気まぐれな戯れとして示されてしまっているのである。
こうして二世紀しないうちに、テスピスのもとで生まれ、アイスキュロスによって劇として高められ、ソフォクレスによって栄光につつまれた悲劇は、エウリピデスにおいてすでにかげりをみせ、アガトンの起源の思い出を失い、急速に人々の気まぐれによって頽廃を迎えてしまったのである。
エピカルモスにはじまり、アリストファネスにつらなる喜劇も、同じような歴史をたどっている。
第三章で言及されるのはホメロスである。ホメロスの意図は感情を人格化して描くことにあった。詩の完成に至るためには、精髄を豊かにする想像力とその飛躍を支配する理性を調和させることが必要であるが、ホメロスはそれをなしえた詩人である。ギリシアの詩は、音楽的リズム(rythme musical)によって計られ、長音節と短音節の混合によって構成され、韻の拘束を揺るがしてきた(p.62.)。リズムとは、詩が作られる拍の数とそれぞれの拍の長さのことである。古代ギリシアでは、筆耕法が使われていたが、これは長くは続かなかった。もしこの方式が存続したり、あるいは、韻が形式を拘束していたならば、ホメロスは叙事詩を仕上げることはなかったであろう。韻が詩の形式を支配するところでは、才能はその形式にばかり気を取られ、知的啓示(inspiration intellectuelle)を無駄にしてしまうのだ。
オルフェウス教は、紀元前6世紀に古代ギリシアで発達したが、その意義は、当時のギリシアの市民生活と宗教に対立する運動であったという点である。しかし、「オルフェウスの金板」を除けば、資料としては間接的な証言しかない。またオルフェウス教は、オルフェウスとその弟子ムサイオスを以外は、無名の人々が信者である。このような点で、オルフェウス教の実像を掴むことには困難がつきまとっている。
この教義の重要な点として、生け贄を捧げる義務に反対したことがまずあげられる。次に、死と魂の考え方である。当時ギリシアでは、魂は肉体を離れたあと、死者の国で永遠にさまようものとされた。それに対してオルフェウス教は、魂の不死性を主張した。この意味において人間の魂は、神的な性質を持っていると言える。また魂は決して死ぬことはない。ただしその魂は先祖が犯した殺害という罪で汚れている(p.10)。そしてその戒律は禁欲、身を清め、肉食を禁止することにあった。
オルフェウスの伝説は、「音楽の賛美」である。彼の歌には、全世界のあらゆる存在物を従える、並外れた力がある。その歌の力をたずさえて、死者の国へも降りていったのである(冥界降り katabasis)。また頭を切られても、歌を歌い続ける。(第一章 オルフェウスー神話とオルフェウス精神の成立)
オルフェウスの宇宙誕生譚は、アリストファネスの喜劇『鳥』の中で、宇宙卵(=時の具体化)に言及している箇所にその反映がみられる。またダマスキオスの「ヒエロニュモスとヘラニコス」の誕生譚にも似ているとされる。また『二十四の叙事詩からなる聖なる言説』では、時(クロノス)が原初の生み出す力という非常に重要な役割を演じている。宇宙の統治における最初の存在が、ファネス、プロトゴノス、エリケパイオスである。(第二章世界と支配権)
オルフェウスの人類誕生譚は、ヘシオドスの人間と神々を分離して考える論理とは反対に、人間と神々は本来単一であったという論理に基づいている。その意味で人間は不死性という性質を持つことになる。(第三章 人類誕生譚と人類の不死なる二つの対極)
しかし不死なる魂をもつ人間は、その起源において、神々の間で生じた汚れを負っている。この汚れを清めて救われるためには、神に同化することが必要となるが、これには日常生活において禁欲の掟を実践することが求められている。殺生を禁じることがその第一の掟である。許される肉と許されない肉と区別をしたピュタゴラス主義は、結局生け贄を認めており、それにたいしてオルフェウス教はどんな些細な殺害も禁じている。肉食を控えることは、まさに神々のように振る舞うことである(p.96.)。この菜食主義が古代にはあったという言い回しは、たとえば、オウィディウスがピュタゴラスに語らせるせりふなどで、よく現れる。プラトンも『法律』のなかで、オルフェウス教は先祖伝来の伝統を踏襲していると述べている。生け贄は、神と人間の越えられない距離を前提とするという意味で認められないのである。ただ、オルフェウスの秘儀については仮説の域を出ない。(第四章 日常生活と秘教世界)
魂は死ぬことができないので、取るべき道は、自分を忘れ、その神的起源を忘れるか、神的起源を思い出すかである。前者の道は「忘却」の泉に通じ、ふたたび「陽の光」の下に、新たに誕生することとなる。後者は記憶であり、神との失われた同一性の回復である。それぞれ無知と知ること、不幸と幸福、転生と、誕生の円環からの解放という対立がある。ホメロスの「忘却」は、魂を、地上での過去を決定的に忘れてしまった虚しい影に変える役割を果たすだけである。それに対して、オルフェウスの金板は、「忘却」は、魂のなかにある神的起源の記憶を消すものであり、その結果魂は転生するとする。つまり忘却とは、死の象徴ではなく、生成の円環に投じられることを意味するのである(p.116)。こうした不死の考えは、ヘラクレイトスとも共通点があると言われる。(第五章 死後の世界の記憶)
のちにバランシュは、オルフェウスの教えはキリスト教を予示しているとした。
第二章では、その後のトラキア信仰の拡散を語る。つまり原初の統一を失い、さまざまなセクトが誕生する。ここから半神、高名な英雄などが生まれてくる。ここでFabre d'Olivetは今度は歴史という観点で2つの考え方を区別する。まずはアレゴリーの歴史であり、こちらは、道徳のみを扱う。そして個人ではなく、集まり(masse)の動きを見つめ、そうした集まりを一般的名称(un nom générique)で指し示す。したがって、こうした集まりを統率する長というものもこの歴史の言及するところではない。それにたいして実証的歴史(histoire positive)は、個人が全てである。それらの個人と出来事の日付、経過などを記すのである。
続いてホメーロス以前の詩人、Linus, Amphion, Thamyrisがそれぞれ、月にまつわる詩、太陽にまつわる詩、Olenの普遍的教義をそれぞれ表しているとして紹介される。次にオルフェウスについて語られる。オルフェウスが現れた時期というのは、純粋なアレゴリーと、弱められたアレゴリー、知性で把握できるもの(l'intelligible)と感覚で把握するもの(le sensible)が分かれる時期である。その意味でオルフェウスは理性の能力と想像力を折り合わせることを学んだ。このオルフェウスとともに「哲学」の基礎が生まれたのである。この時期のギリシアはすでに野蛮な状態ではなく、また詩は、人間精神の幼い時期に生まれたのではない。詩は、つねに人々の中に長く生き、進んだ文明を持ち、力強い時代の輝きを持っている。
長い間ギリシアは政治的にも宗教的にも混乱の時代に陥っていた。様々な寺院、都市が割拠し、対立する。その直前にアジアでもインドが分裂し、混乱の状況を迎えていた。地中海と紅海の交通も途絶え、インド洋に定住していた原フェニキア人とパレスチナのフェニキア人の交流も断たれた。アラビア、ペルシアも同様である。エジプトは王権が権力を広く延ばすようになり、ギリシアもその影響下にはいる。
そのような状況の中、トラキアに生まれ、エジプトで学を積み、詩の崇高さ、知識の深さを極めたのがオルフェウスである。Fabre d'Olivetによれば、妻エウリュディケの存在もアレゴリーに過ぎない。それはすなわち、遠ざかっていく美と真のアレゴリーである。真理は知の光の中で初めて到達する、暗闇で凝視したところで、それは決して得られない。このようにFabreはアレゴリーの解釈をしている。
オルフェウスは、神の神秘を知るために、学校を作り、そこで知を高め、真をしるためのイニシエーションの修行を行なわせた。古代においては真理はひとつの声があるだけであり、それはこのオルフェウスに帰せられることはソクラテスの証言通りである。こうした知のあり方は、その前のモーゼ、その後のピタゴラスと同じである。
ここで先ほどの混乱の時代に話題が戻り、Fabre d'Olivetは詩の真理の分裂は、本来の啓示を得ることのできない僧侶たちが、感情の高まりをそれと同等のものと見誤ったことを原因だとする。それによって、神がその能力、そして名前によって数多く生まれることとなった。こうしてそれぞれの都市がそれぞれの神を抱くこととなる。もちろんこれらの神々をよく検討するならば、それらは最終的に普遍的な唯一存在へと還元されるだろう。しかしそれぞれの守護神を見いだしていた民衆にとって、そのような考えをすることは不可能であった。
オルフェウスは、モーゼと同じようにエジプトの寺院で教育を受け、神の単一性についてはヘブライ人と同じ考えを持っていた。しかしこの考えを表に出すことなく、秘儀の根本に据えるとともに、詩の中で、神の属性を人格化した。モーゼの教団が厳格なものである一方、オルフェウスのそれは、輝きがあり、精神を魅惑し、想像力の発展を促すものであった。喜びや快楽の下に、オルフェウスは役立つ教え、教義の深みを隠したのである。詩、音楽、絵画、それらにおける荘厳さ、優美さが信仰者を熱狂で包み込んだのである。オルフェウスの言う真理は、モーゼよりもさらに進んだものであり、時代を先んじていた。オルフェウスは、神の単一性を教え、その存在の計り難さを述べた。またこの唯一神を三神の表象のもとに描いた。
また弟子に芸術がもたらす感興を信者に与え、彼らの生活が簡素で純粋であることを望んだ。こうした教えは後にピタゴラスが引用するものである。
この教えの究極の目的は、神との交流にある。輪廻の輪を断ち切り、魂を純化し、肉体を抜け出した後に、原初の状態、光と幸福に到達するよう、魂を飛翔させることにある。
オルフェウスについて長々と論述してきた理由は、詩が余興の芸術ではなく、それが神の言葉であり、予言者の言葉であることを言うためである。オルフェウスはこの意味で、まさに詩と音楽の創造者であり、神話、道徳、哲学の父であった。オルフェウスが源流となり、ヘシオドス、ホメロスのモデルとなり、それがピタゴラスやプラトンにとっての光明となったのだ。
オルフェウスは、自らの教義を俗なるものと、神秘的なものに分けた上で、詩の中にも神的なものと俗なるものが混じり合っていることから、一方を神学、もう一方を自然学(la physique)にわけた。オルフェウスは、神学と哲学の数多くの詩を作った。それらの作品は残っていないが、人々の記憶には留められた。(この場合の哲学とは、コスモロジー、すなわち、自然学のことか?)。同時にオルフェウスには叙情的な詩群もある。ここからギリシアのメロペーが生まれ、それが次いで、劇を生んだ。