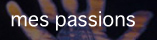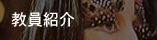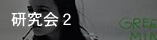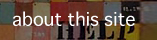Godard, Anne
「ニオベの病」ー子どもの死を嘆き悲しみ、石となる母。この小説における、子を失い、永遠の喪に服そうとする母も、その思いの強さのあまり石となり死んでゆく。
L'Inconsolable「慰めようのない」と題されたこの小説の主題はしかし、喪からの回復の困難さ、死を憧憬する母の存在、あるいは悲しみの永遠性といったものではない。母の感情はもっと激しい起伏をもち、その激情で他者を切りつけ、自己をも苛む。息子の死という出来事以降、その死を軽んじる近親者を責め続け、またその死によって、他者とのつながりがすべて欺瞞であったことが暴き出された自己の卑小な存在も責め続けること、この鎮められぬ母親の感情こそが、tuで最初から最後まで語られる物語りを支配している。そしてその感情の強度と、tuという冷徹な呼びかけのコントラストが、喪に服すことは母親の美しい感情の現れであるとか、思い続けることの切なさであるとか、そうした道徳的な語りをすべて排除し、喪という出来事自体の非情さを強く訴えてくる。
息子の死を想起することがひとつの「強迫」となる。だが、このtuによる語りで、「強迫」の凄まじさは、母親の想念がどこまでも果てしなく続いてしまうことにあるように思われる。息子の命日に、誰の電話もかかってこないが、母は想念をどこまでも続ける「誰かが、今日がその日だと思いもよらずに電話をしてきたとしよう。こちらもそんな相手にあわせてくだらない会話を続ける。震える喜びを感じながら。相手は電話を切ってから、ひょっとして今日は、と考え始める。だが、電話での会話でそんなそぶりを見せなかった以上、相手は困惑するだろう。だが、いや今日だったのだとわかってくる。とはいえ、もう一度電話をかけたりはしないだろう。いったい電話をして、忘れていた、思い出したなどといえるものか。だから相手はこう考えるだろう。いやその話をしなかったのは単に直接切り出すのが、ぶしつけだからだと」(p.15.)こうした想念が果てしなくずっと続いてゆくのだ。あたかも死を想うことが、自己の生の根拠をつくり出すかのように。
想念の羅列は随所に現れる。たとえば家族のアルバムを取り出して、写真に語りかける。「ほら、この人のこと覚えている?子どもに本当にやさしかったわ。(...)」この語りも際限なく続けられる。この反復が底知れぬ「強迫」を作り上げてゆく。
反復は死の原因をめぐっても母を襲ってくる。死はいかに自分が息子のことに無知であったかを知らせ、その原因は、「なぜそれを知らなかったのか」という決して取り返すことのできない、無限の出来事の集積から、後悔となって現れる。いじめ、音楽、家族。そうしたモチーフが連鎖して語られ、やがては結局、自分自身の存在そのもの、とくに自分の無理解に息子の死が結びつけられるのだ。さらに瀕死の息子をそのまま死なせたことがひとつの後悔となって何度でも戻ってくる。
そしてもうひとつの反復が、息子の死を忘れ日常を平然と生きている、他の子どもたちへの攻撃である。死の間際において、自分の死後もひとつの圧迫になるよう、書くことによって言葉を残そうとする。
やがては喪に服す者にも死が訪れる。その死は最終的な忘却だ。「ある日いつも通り、それほど疲れているでもなく、目が覚める。しかし、なにかちょっとしたことを忘れているような気がする。だがそれが何であるかはわからないだろう。ただ、何かとてもはっきりしたもの、それまで他人や自分を判断するのにそんなものを持ち合わせていたなどと気づいてもいなかったものを失った気がする」だが、そのときでも「慰めようもない」ことにずっとよりそっていようと思うだろう。人間の生の欲望は、回復の欲望ではなく、回復しないことのパッションから生まれてくると思わせる結末である。