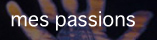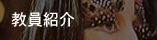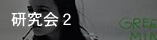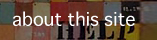Browne, Jackson
 James Taylorの最近のライブを聞くと、若い頃と比べても遜色なく、かえって今のほうがずっと輝きのある声になっていることに驚く。衰えるどころか、今が一番脂の乗り切った充実期であることを感じる。Jackson Browneも、2枚のアコースティックシリーズでの弾き語りを聞くと、依然声質が衰えていないことがわかる。そしてアルバムテイクよりも、実はこちらのアコースティックのほうが曲の良さが断然生かされている。
James Taylorの最近のライブを聞くと、若い頃と比べても遜色なく、かえって今のほうがずっと輝きのある声になっていることに驚く。衰えるどころか、今が一番脂の乗り切った充実期であることを感じる。Jackson Browneも、2枚のアコースティックシリーズでの弾き語りを聞くと、依然声質が衰えていないことがわかる。そしてアルバムテイクよりも、実はこちらのアコースティックのほうが曲の良さが断然生かされている。
そのアコースティックシリーズを経て、今回出されたニューアルバムはバンドでの録音である。Jackson Browneの曲でひっかかるのは、明確なメッセージがあることはわかるが、それを「音楽」という媒体を使って表現する必然性が果たしてあるのだろうかという点である。愚直といえばそれまでで、もちろん愚直であることの潔さを曲から受け取ることはできるのだが、それはたとえばニュース番組と同じで、メッセージが情報として伝達されれば、「再放送」されないように、一回聞けば終わってしまう危うさがある。そうした一回性で終わらないがために音楽が選ばれるのだと思うが、はたしてJackson Browneの曲は、その一回性で終わらないほどのクオリティが保たれているだろうか。
アコースティックシリーズをつい何回も聞いてしまうのは、やはり曲自体をクオリティの高さが一番純粋に出ているからであり、だから繰り返しに耐えられるのだ。
こうした実直なミュージシャンがはまり込む陥穽は、純粋な表現として音楽を作ることができず、自分が置かれている今の状態や、社会情勢にどうしても真摯に立ち向かわざるをえないという不器用さにあると思うのだが、ではこの60歳のミュージシャンが出したこのニューアルバムはどうなのだろうか。なんだか歯切れの悪い言い方になってしまうが、「歌うべきことをもっている限りは、曲は生まれてくる」という点で、命のこもった曲が並んでいるとは言える。しかしそれが初期のアルバムにおさめられたような、永遠性をもちうるかといえば、それはなかなか難しいのかも知れない。アレンジは、大人といえば大人なのだが、あまり切実さが感じられず、バンドといってもお互いに切り結ぶものはなく、雰囲気にながされてしまっている。
だがそれでも歌い続けるということ、その生きる姿をけれん味なくみせてくれるということ、その態度自体がロックなのだろう。誠実に音楽を作り続けるということ、しかも何十年にもわたって。過去ではなく、今を共有できることの喜びはなにものにも代え難い。どんなに歳月を経ても、友人から便りがとどけば、うれしいように、今後も僕は新譜を買い続けるだろう。