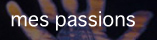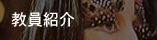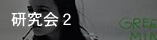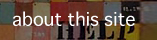Dylan, Bob & The Band
 アルバムというものにはタイトルがつけられ、プロデューサーがいて、どんなものであれ、それはひとつの作品と呼ばれうる。もちろん、曲の間にバランス感がなく寄せ集めと評されるアルバムも多い。しかしそれはあくまでアルバムはまず何よりも作品であり、そのトータル感の濃度ということが評価の基準となっているから、そういう批評がでるのだ。
アルバムというものにはタイトルがつけられ、プロデューサーがいて、どんなものであれ、それはひとつの作品と呼ばれうる。もちろん、曲の間にバランス感がなく寄せ集めと評されるアルバムも多い。しかしそれはあくまでアルバムはまず何よりも作品であり、そのトータル感の濃度ということが評価の基準となっているから、そういう批評がでるのだ。
さて、このアルバムのタイトルはBasement tapes。「地下室」でのセッションを「寄せ集めた」アルバムである。セッションの記録である以上、ここにはアルバムのトータル感=作品としての完成度はもちろんない。しかし、そうした作品性とは別の次元で、アルバムを通した強い意志がすべての曲を覆っている。それは真摯に音楽と対峙し、「私にとっての」音楽とは何か?「今この場で生まれる」音楽とは何か?そうした問いを正面から受け取って、曲をつくり出しているそのエネルギーだ。A面4曲目のYazoo Street ScandalやD面2曲目Don't ya tell henryのロックンロールのヴォーカルと演奏の激しさが物語るエネルギーだ。
とにかく力強さが充満している。いわゆるリハーサル音源なのだが、練習も本番もない。バンドとしての音の強さが、今それぞれの楽器とヴォーカルを合わせようとする緊張感が、アルバム全体を支配している。
トラディショナルなのに新しい。「ロックにはもう何も新しいものはない」といったディランだが、その過去の音楽を自らの手に入れ、そこにロックにしかありえない切迫感をもって演奏しているところが、それまでの音楽にはなかったのではないだろうか。この古い新しさがディランの汲めども尽きせぬ魅力だ。私と伝統の妥協のないぶつかり合い、アメリカの懐の深さを感じさせる。
音質やアレンジではなく、演奏している「人」を感じさせるのが、このセッションだ。The Bandのセカンドだったろうか。全員がやさしく目を閉じて写っている写真があった。うっとりと音楽を聞いているのか、あるいは眠りにつこうとしているのか。そこには死を想わせるほどの静謐があった。20歳そこそこにして人生の悲しみを表現しうるほどの演奏に達してしまった、The Bandの面々そしてディランには、彼らにしか出せない、老成した個性がある。
ところでこのアルバムはディランが素晴らしいのは言うまでもないのだが、実は心につきささるのは、メンバー同士のヴォーカルのかけあいだろうか。A面3曲目Million Dollar Bashの「ウー、ベイビー」というコーラスのはもり、6曲目Katie's been goneはリチャード・マニュエルのリードヴォーカルがまずもって泣ける。そしてB面2曲目Bessie Smithはセカンドあたりにはいっていてもおかしくない。オルガンの音にこれまた泣けるけれど、この曲もハモリが高揚感を募らせる。決定打はやはり「怒りの涙」か、最後の「火の車」か・・・いや、D面1曲目You ain't goin'nowhereのサビの部分だろうか。
ロックはこうして生まれたといっても過言ではない、アメリカン・ロックの礎としてのアルバムだ。
で、ジャケも最高。隠遁しながらも、たえず創造へと向かう、男たちの群れを描いた傑作。