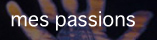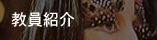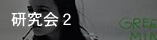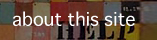Staples, Mavis
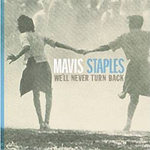 67歳の黒人女性歌手Mavis StaplesとRy Cooderとの共作アルバムである。60年代の公民権運動で歌われた曲を中心に取り上げられているが、過去の歴史に対する郷愁はみじんもない。今に激しく切り込む、メッセージ性の強いアルバムである。
67歳の黒人女性歌手Mavis StaplesとRy Cooderとの共作アルバムである。60年代の公民権運動で歌われた曲を中心に取り上げられているが、過去の歴史に対する郷愁はみじんもない。今に激しく切り込む、メッセージ性の強いアルバムである。
メッセージ・ソングとは何だろうか?たとえば誰にむかって、何を歌うのかが明確になっている歌と定義できるだろう。しかし、そうした対象が明確であればあるほど、メッセージは時の流れには、逆らえない。歌われている問題が解決されていないのに、歌の方が薄命にも消えていってしまうのだ。また訴え方が直情的であればあるほど、それが喚起する反応も一過的なものになってしまう。結局は、当事者たちだけが、苦しみ続け、外にいる者は日々の生活に戻っていく。取り残された者は、表現を失い、内に閉じこもっていく。それがメッセージ・ソングのあやうさであろう。
ではどうしたらメッセージ・ソングは時の試練を経て、生き続ける、あるいは生まれ変わることができるのだろうか?その一つの答えの試みがこのアルバムである。
まずは音の塗り替えだろう。音のバランス、音質が素晴らしい。21世紀らしく、どの音もクリアに録音されている。特にRy Cooderの乾いて張り詰めた音色のギターは、曲に立体感を与え、空間の広がりを堪能させてくれる。きわめて現代的な音響処理である。
そして、Mavisの声が素晴らしい。といっても、それは怒りや、悲壮な訴えなどではない。歌っているうちに、自らが興奮のあまり、気を失ってしまうようなファナティックなものでもない。迫力はあっても、それは、バネのようにしなやかな伸びをもつ声だ。叫んでもつややかな、ささやいても強くひびく声だ。
こうした素晴らしい音楽だからこそ、そこで何が歌われているのか、耳を傾けるようになるのだろう。そして、そこにとても素朴な歌詞を発見する。リフレインで繰り返される言葉が、聞く者の心に強く刻まれる。寄せてはうちかえすリズムでくりかえされるDown to Mississippiのフレーズ。繰り返されるWe shall Not be Movedからは、腕を組み、その場を決して去ろうとしない抑圧された者たちの決意の姿が浮かんでくる。アルバム最後の«Call him up and tell him what you want»の、繰り返すうちに次第に高揚してくるゴスペルの醍醐味。こうしてメッセージは、時と場所を超えて、聞く者の今・ここへと届けられるのだ。そして「あなたはどうする?」と問いかけられる。真の怒りが、告発が始まるのは、ここからだ。
この音楽にはジャンルがない。ゴスペル、ブルース、ロック、フォーク、どの要素もあるが、決して一つにおさまらない。強いていえばここには音楽がある。だからこそ、このアルバムは普遍性を獲得し、永遠のメッセージ・ソングへとどの曲も高められていく。音楽が「芸」である以上、楽しんで歌えて、踊れなくては、聞きはしない。それが真に「芸」としての音楽ならば、声をだし、体を動かしているうちに、その声と体は「行動」へと向かう。権力と差別を撃つ行動へと。