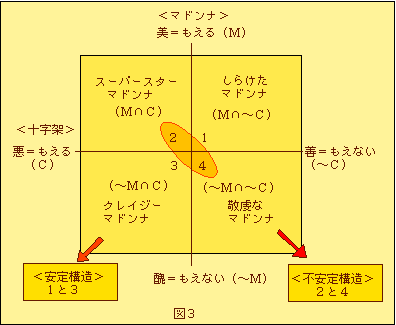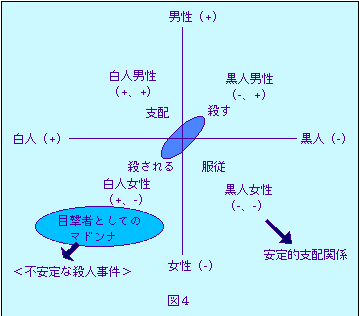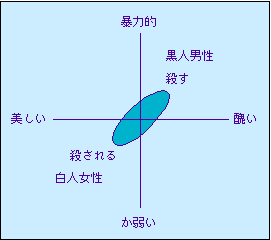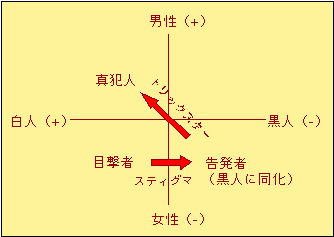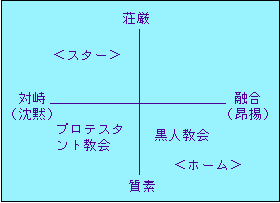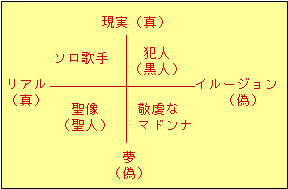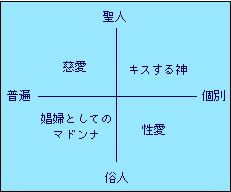|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.シーンのシンボリック・アナリシス 映像の視点からこのビデオの内容の構造を解釈すると、これは、5つのシーンが重層化されてひとつの大きな物語を生成する、という構成になっていることがわかる。そこでまず、この5つのシーンを簡単に説明しよう。 シーン1:燃える十字架とマドンナらしさ これは世の中に大きな物議をかもしだした有名なシーンである。十字架を燃やし、その前でマドンナがセクシーな衣装をまといながら歌うところで、「神への冒涜」がいろいろの方面から騒がれたシーンである。ここでは、「十字架は燃えない(燃やすことは許されない!)、しかし十字架(マドンナ)が燃えている」という規範と現実(虚構?)のズレが重要な刺激(思考の素材)である。 このシーンでも、宗教的な価値判断をめぐる善悪が取り上げられ、神への冒涜か否かが社会問題になったが、ここで重要なことは、善悪どちらか一方に軍配をあげることではなく、立場を違えれば、その善悪の判断はいかようにでもなるということである。 「十字架は燃えてはならない」という価値判断を優先させるクリスチャンからすれば、マドンナが燃える十字架の前で肩ひもをはずしながら歌うことなど、想像を超えた悪の所業と認知されることは自明であろう。これにたいして、マドンナの歌の背景として十字架を想定すると、(もちろん、そこでは十字架を背景に使うこと自体が問題であるということもあるが、一応それには触れないとすると)、マドンナらしい背景としては十字架が燃えていないと「様にならない」ことも自明であろう。もしも燃えていない十字架の前でマドンナが歌うとしたら、そのシーンはどのような意味でマドンナらしさを誘発させるのだろうか。このような視点からすれば、「十字架が燃えることはマドンナが燃えることであり」、だからこそそこにマドンナらしい社会的逸脱者(トリックスターであり、同時にスティグマとしてのマドンナ)としての姿勢が鮮明になってくるのだ。ここでは、マドンナは十字架であり、マドンナが燃える存在であるかぎり、マドンナのメタファとしての十字架が炎に包まれて燃え上がることは当然のことなのである。ここには宗教的な善悪では解読しえない、マドンナらしさの演出が期待されているのだ。
図3に示すように、「十字架(宗教性:善悪)」と「マドンナ(芸術性:美醜)」にかんして「燃える/燃えない」ということで4つの空間が構成されると、それぞれについてマドンナらしさの意味が特定化されてくる。通常の社会規範では、善(−C)と美(M)が共振し、悪(C)と醜(−M)が共振する関係をもつことで安定した価値規範構造が提示されるのだが、マドンナの場合にはそのような安定した構造にはなっていない。つまり善と美のセル(M *−C)では、マドンナはなんらマドンナらしさがなくただまじめに歌うだけの「しらけたマドンナ」になり、対照的に、悪と醜のセル(−M *C)では、マドンナはマドンナのもつ危うさ(許容された逸脱)を放棄して、リアルな逸脱者(「クレイジー・マドンナ」)になるだけである。このような安定的な規範構造にたいして、本来的には不安定的であるはずの構造(悪*美と善*醜)においてマドンナらしさが現れるという「ねじれ」がここにはみられる。つまりマドンナの「スーパースターらしさ」は、トリックスターであれスティグマであれ、悪と美が共振するところ(M* C)に真?(演出された)のマドンナらしさがあり、同時に善と醜が共振するところ(−M *−C)に偽?(リアルな)のマドンナらしさ(「敬虔なマドンナ」)がある。この対照性のなかで描かれるマドンナが、両義性を備えたマドンナである。ということは、映像では、十字架が燃えるところでマドンナが燃えるように歌っていることで「スーパスターとしてのマドンナ」が図となっているが、だからこそその地として「敬虔なマドンナ」(リアルなマドンナは十字架を燃やさない!)がイメージされるのである。しかもその図と地がいかようにでも反転するようにする仕掛けが、不安定な基本構造そのものなのである。 このように解釈されるシーン1は、このビデオでの物語空間のなかで、いわば物語環境として設定されたものである。つまりこのシーンは物語そのものの一部ではなく、物語を支える社会文化的な風土を表現したものであり、そのような環境として「十字架は燃えてはいけない、なのに十字架が燃えている」という多重で矛盾する意味の構造がまずは提示されているのだ。マドンナらしさをめぐる環境そのものの難しさがメタファ的な意味解釈にとって不可欠である、という暗示がすでにここで最初になされるのである。マドンナと社会文化環境とのズレからくる両義性と反転性がこのビデオの基底構造を支えるものである。 シーン2:殺人事件と権力ゲーム このビデオにおける物語性の発端は、ある白人女性がある者によって殺されるという事件にある。マドンナはこの事件の目撃者であるという位置関係から、この物語が展開する構造になっている。ここでは、犯人探しをめぐって、人種とジェンダーがからむことで、物語性がふくらむ仕掛けになっている。
図4に示すように、被殺人者と目撃者が「白人*女性」であるという条件だけが設定され、それを起点に多様な解釈がなされるようになっている。この図は、人種における「白人と黒人」という対照性とジェンダーにおける「男性と女性」の対照性の2つがクロスする構造になっており、さらにそこでの解釈は「権力論」を視点になされるように仕組まれている。つまり「白人は黒人よりも強く、男性は女性よりも強い」という権力前提である。とすると、白人男性(+、+)がもっとも強く、黒人女性(−、−)がもっとも弱い、という権力構図になっている。しかも白人男性と黒人女性との関係は、上下の支配と服従の関係があまりにも確定的なので、安定した権力構造になっている。したがって、ここではそもそも殺人事件は起こらないし、たとえ起こったとしても、事件としての認知はなされない。それほど権力関係は固定的なのである。 これにたいして、人種とジェンダーとの間に強弱上の矛盾やねじれを含む白人女性(−、+)や黒人男性(+、−)の場合には、存在自体が不安定であるから、だからこそ権力ゲームとしては刺激的な構図がそこでは予感されるのである。 この物語は、その不安定な存在である白人女性が殺されるところから始まり、その事件の現場にいたマドンナ(白人女性)がからむことで、事件としての物語は展開するようになっている。当然、犯人は黒人男性とされることになる。この白人女性と黒人男性という危険な対が、事件の意味を増幅させるのである。「美しさ」と「暴力」という正の対照性とその裏にある「か弱さ」と「醜さ」という負の対照性が、「殺される者」と「殺す者」という関係性によって、最高(これしかない!)のそしてもっとも常識的な構図と解釈を呼ぶのである。(図5)
このいわば、白人男性的な視座からの常識は、マドンナという目撃者によって、崩されなければならない。これがマドンナらしさの立場である。しかしマドンナが被殺人者と同様に、白人女性であるかぎり、たとえ本当の犯人が白人男性であっても、この常識から離脱することができない。それが白人女性の標準的な立場というものである。とすると、マドンナが白人女性という立場を離脱する契機をもたないかぎり、この物語には真犯人を告発するという新たな展開は期待できないはずである。 そこで提示されたのが、黒人教会に逃げ込むという行為である。それによって、目撃者である白人女性は、権力的にはより低位の黒人女性に同化することで、かえってそこから安定的権力関係にある白人男性を告発する力を獲得するのである。黒人女性ならば、権力構造のなかで安定的ではあっても絶対的に搾取されるだけの地位にあるが、白人女性がその地位に落ちることで、一気にその権力構造を逆転させる視座を獲得するのだ。そこにマドンナらしさが発揮されるのである。「もっとも弱いからこそ、強くなれる」(もう失うものは何もない!)という潔い開き直りが権力を告発する力を付与するのだ。 単なる目撃者(白人女性)では、たとえマドンナであっても白人男性を告発する力をもたない。白人男性の対極に位置することで、マドンナはスティグマ(黒人に落ちたマドンナ)としてあるいはトリックスター(白人を告発するマドンナ)としての役割を付与されるのである。その役割の変換が起こることで、マドンナはマドンナらしさを発揮するのだ。ここではマドンナは、白人でありながら同時に黒人でもある。その両義性がマドンナの変容(目撃者から告発者)を可能にするのだ。(図6)
このようにシーン2では、このビデオにおける物語の基本構造が提示される。殺人という事件を媒介にして、マドンナと社会常識(白人男性の規範)とのズレを暴き、そのズレのなかで演じるマドンナの両義性がどのようのものであるか、を示すのはここでの重要な解釈である。すでに自明のことだが、社会常識を告発するマドンナのイデオロギー性を主張することがここでのテーマではない。あくまで主張したいことは、マドンナが示すトリックスター(あるいはスティグマ)としてのマドンナらしさである。 シーン3:黒人教会の装置と行動 マドンナは、殺人事件を目撃し、その恐怖から逃れるように無意識に教会に救いを求めて入っていく。これがシーン3である。その救いを求めた教会は、しかしいつもの教会ではなく黒人教会であったが、にもかかわらず、その黒人教会はそんなマドンナを、あたかも家庭に帰ったかのような暖かさで迎えたのである。これがこのシーンでの出来事である。 この黒人教会のシーンでは、教会そのものの装置とその教会で展開される行動との間に奇妙なズレがみられる。それは、簡単にいうと、教会そのものは強くカトリック的なのに、そこでマドンナたちが歌い踊っている行動そのものは黒人教会そのものだ、ということである。通常、カトリック的な教会では、歌い踊るといったことは嫌われるはずである。ここでは、荘厳な装置の前で、ひとり神に向かい沈黙の中に懺悔や告白をしながら神と対話することが期待される行動であるはずである。あくまでも自己という主体をもとに神と対峙する関係のなかに、ある信念を獲得し確認することが重要なはずである。厳格なカトリックの教会であるほど、そこではマドンナ的な振る舞いは拒否されるはずである。 他方黒人教会の特徴は、シンプルな教会のなかで、つまり聖像や十字架といった具体的な偶像を拒否して非常に簡素な装置のなかで、聖歌隊のリーダーのもとで、ソロをとるいわばスターと一緒にみんなでゴスペルを歌いながら、その共同の昂揚感のなかに神との融合的な出会いを感じる、ということを重視するはずである。ここでは、カトリック的な荘厳な装置は不必要なはずである。荘厳さのまえにひざまずき、厳しく自己を見つめるよりも、神との暖かな融合や神への共感を、歌や踊りを集団的な状況のなかで行うプロセスを通していかに共有するかがここでは重要な行為である。 とすると、このビデオでは、黒人教会の装置があまりにもカトリック的でありながら、そこでの行動は黒人教会そのものという、違和感がみられる。もしも、黒人教会のことを精確に表現しようとしたならば、このような装置にはしなかったはずである。ということは、つぎのような解釈が可能になる。マドンナが黒人教会で歌い踊るには、教会の現実を無視してまでも、このようなカソリック的な装置が不可欠であった、ということである。イデオロギー解釈において、マドンナが黒人教会に強い理解を示しているがどうかなどはここではさしたる問題ではなく、重要なことはマドンナらしさの表出には、教会という場面設定のなかで歌い踊る以上、黒人教会での行動とカトリック教会的な装置が、その矛盾を超えて不可欠であった、ということだけなのである。図7に示すように、この矛盾を超えて両立させるのは、トリックスターとしてのマドンナのスーパースター性である。それは、彼女自身が現実の世界では敬虔なカトリックの信者だという事実と、ステージで歌う彼女には黒人教会的な共同的昂揚感が似合っているという事実である。その二つの事実がマドンナの真実であることで、そのビデオ・クリップは通常ならば矛盾でしかない映像を両義的なものとして許容するのである。マドンナは静かに聖像にキスをしながら、同時にみんなと一緒になって神に融合することを求めるのである。この矛盾する関係を無視して、自在に二つの世界を反転させてマドンナらしさを演じてみせるところに、このシーンの意味が隠されているのである。
さらにいうと、黒人教会でみんなと歌い踊る時に感じられる場の暖かさにみられる「ホーム」という融合感覚と、カトリック的に神に対峙するマドンナのスター性(ここでは、マドンナのアップが多様されている)との間にも、マドンナの両義的特性がみられる。スターとして屹立する冷たさと昂揚する肌の暖かさが両立するところが、マドンナらしさにとって重要である。とすれば、黒人教会というシーンであっても、いかにも黒人教会という現実の黒人教会ではない、というよりももっとはっきりと対照的なカトリック教会的な装置をセットすることがどうしても必要になったのである。一面的なイデオロギー解釈よりも、反転する快感こそがマドンナに求められることなのである。 シーン4:夢の夢こそ、リアリティ 黒人教会のなかで、マドンナは夢の世界に入る。救いを求めて教会に入り、さらに祈りのプロセスのなかで、彼女は教会の長椅子に横たわり夢を見始める。これが第4のシーンである。 ここでは、「夢こそがリアルである」という視点をもとに、夢と現実との対照性が問題とされる。その夢の内容が何であるかは、つぎのシーンでのテーマであり、ここでは夢と現実の転換がどのようになされるか、を解釈することが重要である。つまり図8に示すように、夢(偽)と現実(真)という対照性にたいして、その認知がリアル(真)かイルージョン(偽)かという対照性がクロスする構造の中で、常識の世界での認知(現実がリアルだ)が覆され、そうではない「夢の世界こそリアルだ」というリアリティ論がここで展開される。
黒人聖像が涙を流したり、その聖像が人(聖人)に変身したり、といったいわば奇跡ばかりか、現実の世界でみた事件の悲惨さからのがれて聖歌隊のメンバーと一緒に楽しく歌い踊ったりすることまでを含んで、夢の世界こそマドンナにとっては価値のあるリアリティそのものである。ここでは、宗教的なシンボリズムこそが信じられ実感される世界であり、いわゆる現実の世俗的世界は、殺伐とした暴力的な死が氾濫する信じられない世界である。 このような宗教的信念があるからこそ、現実のリアリティが動かされるのである。奇跡を信じる信念が現実を変革するパワーを付与するのである。マドンナが夢から醒めて、真犯人を告発しに社会的現実に向かうとき、そのことが証明されるのである。 しかし常識的信念と宗教的信念があり、後者が重要だという解釈だけでは仕掛けが幼稚である。必要なのは、この二つの信念が融合するプロセスである。そこで聖歌隊でソロをとる女性の意味が重要になってくる。彼女は、マドンナが夢の中に入ったとき、最初に出会い、空から落ちてくるマドンナをしっかりと受けとめ、再度天空に上げる役を演じる。その場面自体はいかにも嘘っぽいところで、奇跡の場面以上にありえないという印象を与える場面であるが、そこでの彼女こそが現実と夢を媒介するメディアとして重要な意味をもっている。 聖歌隊でソロをとるスターは黒人教会のマドンナである。ここで、前述した十字架の前で歌う本物のマドンナと、聖歌隊の前で歌うマドンナ(ソロ歌手)がオーバーラップする。この関係を媒介に、マドンナは黒人教会の中で歌うマドンナに変換されていく。そのとき、マドンナは、もはや十字架を燃やす悪いマドンナではなく、聖歌隊とともに歌う敬虔なマドンナである。しかもこのマドンナは、夢の中のイルージョンであり、嘘(=夢)のまた嘘(=イルージョン)であるという意味で真実である。それは、聖歌隊のソロ歌手が現実の中のリアリティであること対照的でありながら、同じように真実という意味で等価つまり変換可能なのである。 ということは、一方では、奇跡のような宗教的信念が重視されながら、同時に常識的信念が「ソロ歌手=マドンナ」を媒介にして、現実がリアルであることは夢がイルージョンであることでもあるという非常識的な信念にもなる、という反転がさらに重要なことになる。この反転の論理は、奇跡によって変身した黒人聖人が同時に逮捕された犯人でもある、という変換を可能にもするのだ。 このシーンでは、黒人聖像とソロ歌手を起点にして、聖像から聖人への奇跡という宗教的変換と、ソロ歌手からマドンナまた聖人から犯人(真実は違う)へのシンボリックな意味変換が同時にしかも交差しながら進行する、ということが主張されなければならない。これらの変換が自在に反転することで、このビデオ・クリップの形式のおもしろさが浮かび上がるのである。 シーン5:キスする神 夢の中で聖人になった聖像はマドンナにキスをする。それは、神からの慈愛なのか、マドンナの欲望に屈した?性愛なのか、という論争がここでもあった。このビデオクリップでは、シーン1での燃える十字架をめぐる論争とここでの神のキスをめぐる論争が話題になったところである。このような物議を呼んだ神のキスはどう解釈されるのか。
結論は、すでに自明である。「どちらでもある、が、どちらでもない」である。図9に示すように、愛の典型には、慈愛(アガペー)と性愛(エロス)のように、神が自己犠牲においてすべての人に愛を施す慈愛と、男女の個別の関係に限定された性的関係をもとにした性愛がある。ここでは、愛の主体が神(聖人)なのか人(俗人)なのかという軸と、愛の対象が誰でもいいという普遍かそれとも二人という個別な関係かという軸がクロスして構成されたフレームのなかで、慈愛と性愛の位置づけがなされている。ここから分かるように、ビデオでの聖人とマドンナの関係は、基本的には慈愛でも性愛でも、どちらでもない。慈愛とするには、神はあまりにもマドンナという個別性にこだわっているし、しかし性愛と呼ぶには聖人にはある種の強く潔い禁欲感がみられる。このような意味では、聖人とマドンナにたいするキスは慈愛でも性愛でもないといわざるをえない。しかし同時に、聖人のキスにはマドンナとの関係そのものへのこだわりが感じられる意味では性愛的であるし、同様ににもかかわらず強い禁欲感には慈愛への視線が感じられる。このような意味では、このキスは性愛的でもあるし慈愛的でもあるといえよう。 さらに神からの視点でのみキスを解釈するのではなく、マドンナの視点から解釈をすることも必要であろう。このとき、マドンナが俗人でありながら普遍的な愛を求めているという前提が認められなければならない。つまりマドンナは娼婦である。それが、マドンナがあのセクシーな衣装を身にまとって登場することの意図である。マドンナは、聖人を含んで誰とでも性的関係を許容する娼婦である。だからこそ、聖人ですらマドンナとの関係では性愛としての意味付与がなされてしまうのである。ここから、神の視点からみれば、基本的には「慈愛でも性愛でもない」となるが、マドンナからすれば「性愛でもあり慈愛でもある」という意味が基本に据えられるのである。その結果、性愛か慈愛か、という論争は、そのどちらかを選択するのではなく、常に反転を繰り返すというかたちで解釈されるべきものになる。 キスする神は、マドンナというもう一つの神(誰にでも愛を、という娼婦という神)の前で、いかようにでも解釈されてしまうのである。これこそが、スティグマとして娼婦性をもつマドンナがトリックスターとして自在に神の愛を操る姿なのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||