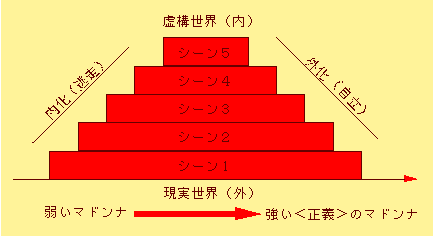|
||||||||||||||||||||||||||
|
4.映像のシークエンス:構造とプロセス 上記5つのシーンはどのように関係づけられているのだろうか。それぞれのシーンの解釈は全体の解釈にいかにして関連づけられるかを考えなければならない。 関係づけには、一つは映像の流れが重要である。ここでは、基本的には映像の流れによって、一つの物語が作成されている。図10に示すように、映像の流れは、シーン1から始まり、シーン2にすすみ、さらに3・4・5へといき、そして今度は逆にシーン4に戻り、3・2そしてシーン1におりて終わるという構成になっている。いわば階段を登りそして降りるという展開になっている。これは、映像の流れとしては、階段の上下運動であるが、その背後には5つのシーンが並列して同時進行していることが想定されるし、その同時進行の5つのシーンが重層化されている構造のなかで、映像は一つだけのシーンを選択するかたちで重層構造の階段を上下しているだけだ、といえよう。
重要なのは、このような上下運動が5つの同時に進行するシーンの重層性の中で行われるプロセスの背景に、その重層性が「外と内」という軸によって構造化されていることである。十字架を燃やすような荒れた一般的な社会環境(シーン1)のなかで、殺人事件が起こり(シーン2)、その現場を目撃してしまったマドンナが逃れるように教会に入り(シーン3)、その暖かな教会の中で夢の中にさらに逃れ(シーン4)、そして黒人の神とのキスによって目覚め(シーン5)、夢の中で聖歌隊のみんなに勇気づけられ(シーン4)、夢から醒め、現実の中にいる目撃者としてのマドンナを強く自覚して教会をでて(シーン3)、そして警察に出向いて逮捕されていた黒人青年の無実を証明し(シーン4)、最後に燃える十字架の前でマドンナらしいメッセージを一般社会に伝えて(シーン5)、終わるという流れになっている。ここには、外から内に逃げる前半と内から外へ立ち向かう後半というように、現実から虚構へと逃走する内化のプロセス(弱い<自己弁明>するマドンナ)から、虚構から現実へと挑戦する外化のプロセス(強い<正義>のマドンナ)へと変身するマドンナが描かれている。 しかしこのようなプロセスをみると、マドンナの両義的な特性が全面的に否定されることになる。つまり弱いマドンナよりも強いマドンナの方が魅力的だというイデオロギーになってしまう、という矛盾が露呈してしまう。シーンの個別の解釈ではマドンナの両義性がみられたのに、それが全体に構造化されると、そのスタティクな構造としては両義的ではあっても、映像のシークエンスでその全体の構造を解釈するかぎり、所詮どちらか一方の価値が選択されるというイデオロギーになってしまうではないか、という結論になってしまう。このかぎりでは、その通りである。 しかしそうではないのである。このビデオ・クリップはもう一つの仕掛けを用意しているのである。それが、最後の場面で、この5つのシーンからなる物語は、お芝居だった、という舞台装置(シーン6)をみせるところである。これによって、強い正義の味方<だけの>マドンナというイデオロギーが暴露され、プロセスによる一面的な解釈が逆転される仕組みが提示されるのである。こうして、マドンナがどちらの見方なのかというイデオロギー解釈が一笑にふされ、重要なことはイデオロギー解釈をあっちにいったりこっちにいったりして弄ぶこと自体がマドンナらしさの表現として価値があるのだ、と主張されるのだ。やはり反転する快感こそが、マドンナなのだ。 |
|||||||||||||||||||||||||