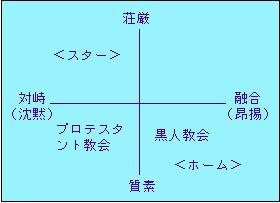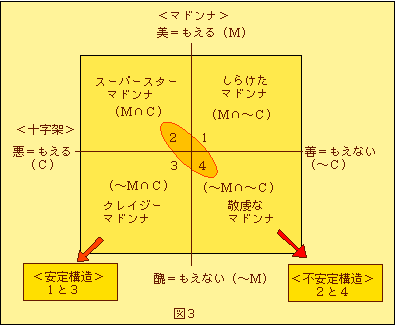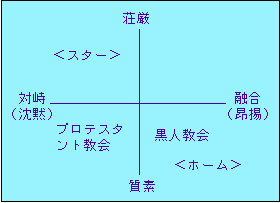|
||||||||||||||||||||||||||||
|
5.歌詞のオーバーラップ:6重奏 歌詞はどうなのだろうか。いままでは映像にのみ焦点をあてて解釈をしてきたが、歌詞はどのような意味を映像との関連性で示すのだろうか。 歌詞は、その内容は平凡で、映像のもつ強いインパクトと対照的に穏やかな心情を語る内容でしかない。また映像のシークエンスでは、現実世界からいったん虚構の世界に入り、そして再び現実世界に戻るように、映像の基本が現実社会を起点にした虚構世界との循環プロセスにあるのと対照的に、歌詞の内容は終始夢(虚構)の世界に没頭している。 しかしこの穏やかな虚構の世界にいるからこそ、マドンナの思考は多様な「Like(〜のような)」という想像力を働かすことが可能になるのだ。歌詞のなかで、マドンナはつぎの6つの「Like」を使用している。歌詞のなかででてくる順に示すと、つぎの通りである。 1:like home 2:like a prayer 3:like an angel 4:like a child 5:like a muse 6:like a dream この6つの「ライク」で、映像と歌詞の意味が一致しているのは、最初の「ホーム」だけで、そこではマドンナが教会に逃げ込んだ瞬間の映像で、歌詞の「like home」が重なり、教会が「ホームのようだ」と認知される仕組みになっている。つまりここでは、映像のシーン3が歌詞の「ホーム」と共鳴する関係になる、という意図がはっきりとしている。黒人教会は、救いを求めるすべての人にとって暖かさとやすらぎを与えるホームだ、というメッセージが込められている。図7との関連性で述べれば、「装置=カトリック教会と行動=黒人教会」という対立的かつ両義的関係のなかで、マドンナのスーパースターとしての役割が対立を超えた両義性を誘発するのにたいして、「ライク ホーム」は黒人教会は「ホームである」と主張するのである。しかし同時に、ライクである以上、ホームではないという対立する意味もここには隠されている。それがカトリック教会の装置性(=「ホームではない」)に共振するのである。このように、「ライク ホーム」は、図7での行動と装置の対照性をそのまま補強し、同時にやや行動の要素を重視する、というかたちで歌われている。これは、映像が強く装置性にこだわることにたいしてバランスをとるという意味でも重要な仕掛けなのである。
このように歌詞と映像のシーンとの間に対応関係があるとしたら、他の5つのライクはどのような対応関係をもつのだろうか。やや強引にだが、つぎのような対応関係をみつけることができる。 1:like home ・・・・シーン3:黒人教会の装置と行動 2:like a prayer・・ シーン1:燃える十字架とマドンナ 3:ike an angel ・・ シーン5:キスする神 4:like a child ・・・ シーン2:殺人事件と権力ゲーム 5:like a muse・・・ シーン4:夢の夢こそ、リアリティ 6:like a dream ・・ シーン6:舞台装置 《like a prayer ⇔ シーン1:燃える十字架とマドンナ》 このビデオ・クリップのタイトルでもある「ライク・ア・プレイヤー」は、マドンナの祈りそのものであり、シーン1に対応する歌詞である。燃える十字架の前で歌い踊るマドンナはマドンナではあっても、敬虔なカトリック信者のマドンナではない。その後者のマドンナを支えるのが「祈りを捧げるマドンナ」である。マドンナは歌詞では強く「祈りを捧げる人であり」、図3との関連で述べれば、「敬虔なマドンナ」(<善:−C>*<醜:−M>)なのである。この位置づけによって、映像で強くアピールされる「スーパースターとしてのマドンナ」(<悪:C>*<美:<M>)との間に対照的なバランスが保たれるのである。もちろん「ライク・ア・プレイヤー」である以上、「祈りと非祈り」の両義性はつねに有効な仕掛けなので、マドンナは敬虔なマドンナであると同時に敬虔なマドンナではないのだ。それがスーパースターとしてのマドンナを意味することは自明であろう。このように、この歌詞はシーン1との対応づけられることで、シーン1の意味をさらに増幅させているといえよう。
《like an angel ⇔ シーン5:キスする神》 神がマドンナと性的な関係をもつ、というイメージが映像にあることは確かである。その宗教的・道徳的な善悪とは別に、映像では、神のもつ超越的普遍性が否定されて俗化した神と、マドンナという普遍化された個人(娼婦というスーパースター)との間に、慈愛と性愛を超えた愛=セックスの関係が存在している。このような関係(図7)を、歌詞でシンボリックに伝えているのが「ライク・アン・エンジェル」である。エンジェルのもつ性的な両義性(男でもあり、女でもある)が、エロス=アガペーの関係を超越する「娼婦としてのマドンナと俗人になった神」の関係にかぶさることで、映像でのキスするシーンの性的リアリティがエンジェルのイノセンスによって昇華され、「個別性をもつ普通の(天使のような)女の子としてのマドンナと普遍性をもつ聖人としての神」という慈愛の関係への収斂が意図されている。つまり「ライク・アン・エンジェル」が、映像の奇妙な関係を補完することで、キスする神のシーンにある安定感・安心感を付与するのである。天使のようなイノセンスが、普通の愛を期待することで、映像におけるキスする神の歪んだ意味を救うのである。このような補完関係のなかで、歌詞と映像が新しい融合を示すのである。
《like a child ⇔ シーン2:殺人事件と権力ゲーム》 子供は天使のようだ、というが、そこには「本当は、子供は悪魔だ」という意味がこめられている。子供は、そもそもイノセントであるがゆえに、残虐な行為を平気で行う存在である。イノセンスは、それゆえに、どの方向にも極端に走る傾向をもつ。その危険性が子供にはいつもつきまとう。 際限のないいじめ、その究極にある残虐な殺人はここでも起こった。それがシーン2である。ここには、白人が殺害した(黒人が間違って逮捕された)、という人種問題と同時に、それはあきらかに大人の仕業であるが、それはいかにも子供じみた事件でもあるという解釈が隠されている。これは、シーン4の夢の中に登場する聖歌隊のメンバーである子供(アップで歌う黒人少年)が、一方で天使のような子供であると同時に、すべてを悟った大人のように穏やかな表情で歌っている、というシーンと対照的である。現実の世界での「子供じみた出来の悪い大人」と夢の世界での「悟りきった大人のような出来の良い子供」という対照性が、「大人と子供」をめぐる常識的な図式(大人=秩序<善>と子供=無秩序<悪>)を反転させ、「悪い大人と良い子供」を生成させるばかりか、さらにこの常識的図式を融合させ、「子供じみた大人」と「大人じみた子供」という両義的な役割設定を導くのである。この年齢役割の両義性と価値の反転が、「ライク・ア・チャイルド」から誘発され、シーン2の子供じみた殺人事件の現実を解釈する方向を示唆するのである。 《like a muse ⇔ シーン4:夢の夢こそ、リアリティ》 ここでのミューズはメディテーション(瞑想)であり、夢の中に入っていくことそのものである。お祈り(プレイヤー)は、マドンナを夢の世界に誘導する呪文であり、教会に迷いこんだマドンナにミューズ(夢の中)という状態を与え、やすらぎと安心感を与える。 しかし「ライク・ア・ミューズ」は「ミューズではない」という意味をも含む。それは、「夢の中だからこそ、それがリアリティになる」というシーン4をめぐる解釈を補強することになる。とすれば、「ライク・ア・ミューズ」は、その両義性ゆえに、シーン4の映像解釈そのもののとなる。 またミューズは、語感からすれば「ミューズ=女神」と同一であるから、その意味あいもここでは配慮されているはずである。とすると、女神は、聖歌隊のリーダーである「ソロ歌手」であり、そこから意味変換されたマドンナそのものとなる。つまり夢の中で、マドンナは女神になることで、聖人との関係にあるバランスが生成され、このバランスが聖人とマドンナとのキスするシーンへの導入を容易にするのである。とはいえ、ここでもマドンナには「女神ではない」という意味あいも隠されているから、それは「キスする神」のシーン5におけるマドンナの娼婦性との関係で、対照的でありながら共振するという二重の関係をすでにここで用意するのである。かくして、「ライク・ア・ミューズ」は、シーン4に対応する意味連関を、瞑想と女神という2つの点で明確に示している。 《like a dream ⇔ シーン6:舞台装置》 最後が「ライク・ア・ドリーム」である。これは、このビデオのエンディングで仕掛けられた映像の「この5つのシーンからなる物語は、お芝居(嘘)だった」という暴露に対応する。この5つのシーンからなる物語は、所詮夢の中の嘘であり、正義の味方のマドンナといったイデオロギー解釈からは無縁なものだ、と主張がなされるのである。 しかし「ライク・ア・ドリーム」は「夢(嘘)ではない、それが現実なのだ」というメッセージ性をも含むから、その意味では、お芝居という嘘は、嘘ではなく現実なのだ、ということにもなる。とすると、ここでは、お芝居もどきの映像のエンディングは、嘘くさいからこそ本当なのだ、という再度の反転がみられることになる。 「ライク・ア・ドリーム」は、したがって、エンディングのお芝居を一方で補強しながら、他方でそれを否定することで、マドンナの両義性を最後まで確保するのである。ここには、「結論はだせない」仕掛けになっている。解釈はどこまでも自由であり、多様であり、だからこそマドンナらしさがみられるのだ、というメタレベルでの戦略がみえるだけである。 |
|||||||||||||||||||||||||||