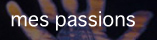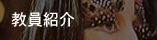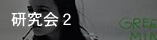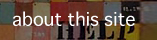Apr
15
2007
Carole King, Writer (1970)
 ポップスからロックへの移行をこの「Writer」ほど象徴的に表しているアルバムもないだろう。「Writer」の登場は、キャロル・キングという天才ライターのロックミュージシャンへの変化を意味するだけでなく、ロックというジャンルそのものの確立を意味している。もちろん、ことアメリカにかぎっても、すでにロックは存在していた。だが、それまでのロックはポップスのアンチテーゼという、「反」としての存在だった。キャロル・キングのロックは、時代遅れになりつつあったポップスというジャンルを吸収した上で成り立つロックである。
ポップスからロックへの移行をこの「Writer」ほど象徴的に表しているアルバムもないだろう。「Writer」の登場は、キャロル・キングという天才ライターのロックミュージシャンへの変化を意味するだけでなく、ロックというジャンルそのものの確立を意味している。もちろん、ことアメリカにかぎっても、すでにロックは存在していた。だが、それまでのロックはポップスのアンチテーゼという、「反」としての存在だった。キャロル・キングのロックは、時代遅れになりつつあったポップスというジャンルを吸収した上で成り立つロックである。
ではこのアルバムの何がロックと呼ばせるのか?まず明らかなのは「Writer」というタイトルが示しているSSW(シンガーソングライター)という、個人を出発点とした音楽制作スタイルである。ポップスが担っていた、作曲家と歌い手という、職人の分業体制によって担われるビジネスではなく、個人の発露として音楽が生まれることがロックである。
そして個人の発露というのは、キャロル・キングの場合、その唱法にある。いや、彼女は、意識してこのように歌っているのではないだろう。その歌は、一本調子で、はりはあっても、ふくよかな陰影はない。あくまでもストレートで、ただ声がのびるにまかせるような歌い方である。言ってしまえば職業歌手としては失格なのだ。しかしこの不器用なストレートさは、ピュアであることの裏返しだ。キャロル・キングの最高傑作といってもよい「The Carnegie Hall Concert - June 18 1971」で、この瑞々しい歌声は十分に満喫できる。
そして楽曲の構成であろう。アレンジの妙はいかされているが、何よりも心をひくのは、ピアノやギターの生の感触だろう。その意味でたとえば「Rasberry Jam」のような曲は、どんなにすばらしいアレンジを聞かせてくれても、このアルバムの中ではすでに「時代遅れ」である。そして時代の幕開けを飾るのはアルバムの最後の曲「Up on the roof」だ。「The Carnegie Hall 〜」で、ジェームス・テイラーという、もう一人のSSWとの美しいコラボレーションが聞けるこの曲こそ、70年代ロックを運命づける一曲であり、そしてこの時点でロックは、前衛や実験であることをやめた。