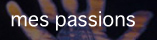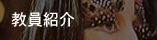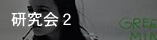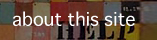Leibniz(ライプニッツ)「ドイツ語の鍛錬と改良に関する私見」(1697執筆)『ライプニッツの国語論』所収
ことばは、当然のことながら、生きて話している人間の生の具体性と切り離すことはできない。それは言語を思想として考える場合でも変わらない。普遍・抽象・理論化をいたずらに急ぐのではなく、その人の生きている現実の中から、思想が紡がれてくる過程を丹念に追ってみなくてはならない。ライプニッツについて考えるときも、彼の生きたその環境、時代の流れに、彼の思想を位置づけることは必須である。歴史的に言えば「三十年戦争の不幸の結果地に落ちていたドイツ語」(バッジオーニ『ヨーロッパの言語と国民』p.236)を、どのように復興するか、それはライプニッツの時代の課題であったろう。実際ライプニッツ自身『私見』において、「我々の言語は略奪され、フランス語かぶれが横行した」と述べている。まさに「私見」は、ドイツの国家、言語への誇りを回復するための試みなのである(『私見』pp.53-55)。また言語思想の流れからは、母なる言語としてのヘブライ語という聖書的世界観、すなわち、世界を説明し尽くす普遍的言語ではなく、感覚論(sensualisme)の広まりとともに、他者を理解する、つまり「人々の世界観や、内面の過程」の表現としての言語へと変化したことを十分考慮する必要がある(Droixhe, De l'origine du langage aux langues du monde, バーリン『北方の博士 ハーマン』p.112)。普遍から、歴史としての言語というこの転換期は、ラテン語の退潮と、普遍言語の構想から、フランス語のヘゲモニーの確立へと移っていく時期とも重なる。
ライプニッツはまさにこうした転換の中で、結合術、普遍言語、国語の賞揚という様々な言語(および記号)をめぐる考察を行なった。言語思想はライプニッツの思想全体の根幹とも言える。普遍言語と言語の自然性については『人間知性新論』第三部「言葉について」の中にその主張がおさめられており、カッシーラー(『象徴形式の哲学』)、ロッシ(『普遍の鍵』)、エーコ(『完全言語の探求』)、ジュネット(『ミモロジック』第4章「言語創始者ヘルモゲネス」)など枚挙にいとまがない。
以上のような背景をふまえてここでは1697年にドイツ語で書かれた『ドイツ語の鍛錬と改良に関する私見』(Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutchen Sprache)を見ていきたい。
最初に注目すべきは言語の起源についての考察である。『私見』では、ドイツ語が「主幹言語」(Haupt-Sprache)であるという、起源の言語としてのドイツという見方が踏襲されている。したがって太古のドイツ語は、ラテン語の起源であり、またケルト人、スキタイ人と共同体を作っていたとされる(『私見』p.65)。この言語系統論は、十七世紀以降に広まる「スキタイ人起源論」である(cf.原聖『<民族起源>の精神史』p.103.)。ライプニッツのゲルマン、ケルト、スキタイの関係についての論考は、『私見』、『新論』、『小論』と立場を変えていく。(Cf.L'harmonie des langues, p.195.)。『新論』でははっきりと、「ひとつの根源的で原初的な言語がある」と述べられている。これはアダムの言語のような起源を認めてはいるが、その言語は「歴史的」に共通語根を遡ることによって見つけることができるという歴史性のもとづいた起源の言語の探求なのである。この転換に、ライプニッツの言語思想を位置づけることができよう(現在のところ、その起源をドイツ語とする主張については調べが追いついていないが、『新論』p.23.にはそのような訳注がつけられている)。
起源ということに関しては、語源の探求におけるライプニッツの立場は、「クラテュロス」的である。語源を探求する過程において、単語が「何人かの人がいうほどに恣意的または偶然的なものではない」と指摘する(『私見』p.70.)。そして、『私見』では、およそ偶然というものを否定している。ここではヤコブ・ベーメ流に解釈された自然主義的言語の立場をはっきりととっている。しかし、こうした見方にもやがて時の流れという歴史性が導入される。それはジュネットがひく『小論』の一節、「しかし大抵の場合、時間の経過と数多くの派生の結果、原初の語義はかわってしまったか、あるいは不明瞭になってしまった」(ジュネット、邦訳p.93.)。である。
ドイツ語の改良のために、全体を通してライプニッツが気を配るのは「単語」である。単語とは、「知性の鏡」(p.42.)であり、「言語の基礎および基盤であり、その単語という土壌の上でいわば表現という果実が成長する」という(p.57.)。ライプニッツには観念を適確にあらわす記号の術への強い関心があるのだろうか。語彙の拡充、特に抽象語彙の拡充をライプニッツは強く説くとともに、辞書の必要性とそのための単語の調査に取り組むこと、他の単語と調和した新語の形成を強く訴える。それらはすべて「的確に」を目標としたものであり、それが民衆の教育向上につながると考えていたライプニッツはすでに十八世紀の初頭にして、啓蒙主義的な視野を持っていたと言えよう。