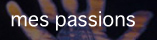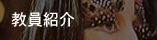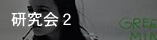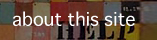Rahsaan Patterson, LOVE IN STEREO (1999)
 ソウルというジャンルはいったいどうやって分類されるのだろうか?ひとくちにソウルといってもその幅はきわめてひろい。たとえばリズムの躍動はソウルの本質だろうか。それはジェームス・ブラウンのようなきわめて個性的なミュージシャンに負うところが大きいのかも知れない。ソウルのもつ高揚感、グル−ブ感ならば、まずはマーヴィン・ゲイを思い浮かべるだろう。そして黒人の魂の訴えならば、単なるメッセージソングに堕することはなく、しかし政治的なムーブメントとして大きな流れを作っていくほどの力をもったアルバムを生んだカーティス・メーフィールドだろうか。ここまで黒人の名前ばかりを挙げたが、ソウルは黒人の専有物ではない。60年のロック草創期からすでにスティーブ・ウィンウッドのようなきわめてブラックな、そして質の高いソウルフルなミュージシャンがいる。その歌唱の素晴らしさは、「ソウル=黒人文化」というきわめて安易な図式を払拭してくれる。
ソウルというジャンルはいったいどうやって分類されるのだろうか?ひとくちにソウルといってもその幅はきわめてひろい。たとえばリズムの躍動はソウルの本質だろうか。それはジェームス・ブラウンのようなきわめて個性的なミュージシャンに負うところが大きいのかも知れない。ソウルのもつ高揚感、グル−ブ感ならば、まずはマーヴィン・ゲイを思い浮かべるだろう。そして黒人の魂の訴えならば、単なるメッセージソングに堕することはなく、しかし政治的なムーブメントとして大きな流れを作っていくほどの力をもったアルバムを生んだカーティス・メーフィールドだろうか。ここまで黒人の名前ばかりを挙げたが、ソウルは黒人の専有物ではない。60年のロック草創期からすでにスティーブ・ウィンウッドのようなきわめてブラックな、そして質の高いソウルフルなミュージシャンがいる。その歌唱の素晴らしさは、「ソウル=黒人文化」というきわめて安易な図式を払拭してくれる。
少し振り返っただけでも、ソウルの歴史は、さまざまな豊かな財産を持っているわけだが、97年にファーストアルバムを出した、このRahsaan Pattersonの音楽が、ソウルと呼べるとしたら、それはどんな意味だろうか?
まずはっきりしているのは、90年代以降のソウルの流れは、かつての黒人という人種的枠組みにもとづく、プロテストとしてのソウルとは根底から異なっているということである。また汗の匂いといった肉体性も、パッションを歌い上げるような魂の叫びもない。しかしそれでもなぜ彼の音楽がソウルとしてここまで人の心をひきつけるのか?
Pattersonのソウルの魅力は、緻密に練り上げられた、楽器それぞれの粒だった音の構成にあるのではないだろうか?たとえばソウルを聞きながら「快適」と言えるのは、そのストリングスのアレンジのバランスの良さにあるように思う。それは、ソウルが本来持っていた、情念とも言えるスピリチュアルな部分を抜き取ってしまい、メロディの妙だけで聞かせるイージーリスニングにも似たお手軽なソウルになってしまったという危険も意味する。
しかしPattersonの音楽が、そうした批判に耐えうるとしたら、それはまさに計算されつくした、楽曲のよさによる。それぞれの音が個性を持ちながら、うまくアレンジされることで、曲としての一体感を醸し出していく。音と音の間の取り方が、いわゆるグルーブを生み出していく。そこがかろうじてソウルなのだと言えよう。つまり徹底的に知性的な音作りをしているのである。天性の才能や、人間の激しい生き様を聞くのではなく、最高のスタジオ環境で、過剰になる部分は極力抑えながら、音を重ね合わせていくその妙を堪能するのだ。そうした音作りは、彼の男性としては、ずいぶん細くて、高音にいけばいくほど、金属質になっていく声質にとてもあっている。この中性的な声は、音のアレンジの中でほとんど楽器の一部として溶け込んでしまっている。いってみれば人工的なソウル。しかし音楽の楽しさは、なにも生身の人間らしさだけにかかっているわけではない。スタジオワークによってここまで完璧な音作りをしてくれれば、それは、ひとつのエンターテイメントとして、聞くに堪えると言えよう。
なお、Rahsaan Pattersonはこれまで3枚のアルバムを出している。デビューはRahsaan Patterson, 2ndはAfter hours。どのアルバムも素晴らしいクオリティである。