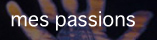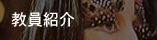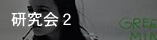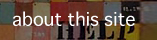May
17
2007
Eric Andersen, Blue River (1972)
 ジャクソン・ブラウン、ジェームス・テイラー、エリック・アンダーソン。長髪の顔立ちには、内面のナイーブさ、繊細さが映し出されているかのようだ。社会に跳びかかっていくのでなく、自分を破綻に追いつめるのでもない。情熱と狂気が失われてしまった時代にあって、自分の立っている場所をもう一度見つめ返すような内省的な態度といえばいいだろうか。エリック・アンダーソンの2枚のアルバムジャケットは、どちらも本人のポートレイトである。そのまなざしは、外に向かって投げかけられた、というよりも、おそらくは自分自身の内にむかって深く沈んでいくような印象をうける。しかし、それは決して自己閉塞ではなく、控えめであっても何かを見据えた力強いまなざしだ。
ジャクソン・ブラウン、ジェームス・テイラー、エリック・アンダーソン。長髪の顔立ちには、内面のナイーブさ、繊細さが映し出されているかのようだ。社会に跳びかかっていくのでなく、自分を破綻に追いつめるのでもない。情熱と狂気が失われてしまった時代にあって、自分の立っている場所をもう一度見つめ返すような内省的な態度といえばいいだろうか。エリック・アンダーソンの2枚のアルバムジャケットは、どちらも本人のポートレイトである。そのまなざしは、外に向かって投げかけられた、というよりも、おそらくは自分自身の内にむかって深く沈んでいくような印象をうける。しかし、それは決して自己閉塞ではなく、控えめであっても何かを見据えた力強いまなざしだ。
1972年に出されたこのアルバムは、もはやフォーク・シンガーのアルバムではなかった。フォークというには、あまりにも老成している。誠実ではあっても、もはや素朴ではない。いわゆるトラッドという、過去の伝承を歌い継いでいくような素朴さは、もはやここには認められない。憂愁や追慕はあっても、それはきわめて個人的なものである。この私的な音楽が、しかし、人々の心をとらえていくのだ。
先に挙げた3人の中で、エリックの声が一番線が細い。ジャクソン・ブラウンの力強さ、ジェームス・テイラーのきらびやかな歌声に比べてと、エリックの声の特徴は、その震えだと言えないだろうか。名曲Blue Riverでは、ゆったりとしたリズムにあいまって、高音の震えがはっきり伝わってくる。感情をあらわにすることなく、たんたんと歌を紡ぎだす。もしかしたら、押し殺した感情があるのかもしれない。でももはやそれを語る時代ではないのだ。その失われたものへの憧憬をもちながらも、一歩前へ踏み出す決意、それがSSWたちの創造への意欲だったに違いない。
この音楽はやさしい。軟弱といえばそれまでだが、あくまでも誠実な歌である。人に聞いてもらおうと、わざとおもねりはしない。彼の声はひとすじのよびかけだ。たとえどんなにかぼそくとも、よびかけは、多くの人の心に届いていく。エリック・アンダーソンを聞く者は、その音楽によって、孤独とは何か、おそらく問いかけるはずである。そうした繊細な魂に、彼はよびかけるのだ。Be true to youと。