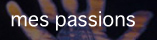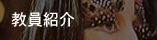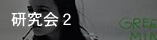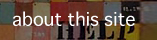W.G.ゼーバルト(Sebald), 『空襲と文学』(2001, 邦訳2008)
ゼーバルトは言う。「歴史的ないし文学的描写によって、空襲の恐怖を公共の意識にもたらすことに私たちは成功していないのではないか」と。この講演では、歴史的な事象にたいして、文学はどのような表現をもちうるのか、そして文学的な表現をいままで戦後ドイツはもちえなかったのはなぜなのか、が主題となっている。
ゼーバルトは、戦後、ドイツが戦時下において、ほとんど正当化される理由もなく無差別な空襲を受けたこと、それも徹底的な絨毯爆弾によって、市民も巻き添えにした潰滅的な破壊が国土においてなされたことが、これまでほとんど書かれなかった事実を指摘する。それはあたかも健忘症にかかったかのような症状とでも言える。しかしゼーバルトが語るのは次のようなことではない。「空襲について語ろうとするのは、戦争の加害者は同時に被害者でもあった、ところが加害者としてのナチスの行為があまりにもひどいものであったため長らくドイツは自らが被害者でもあり、それを主張する権利をもっていない、被害を訴えることはタブーであるために長らく沈黙してきた」云々...したがって、次のような主張とは全くもって異なっている。
「もうそろそろ我々も被害者であったのだ、連合軍から悲惨な目にあわされたのだ、ということを主張してよいのではないか」。
ゼーバルトが「告発」といってもよいほど強く、かつ執拗に訴えるのは、それら沈黙は自重や遠慮ではなく、むしろ自らその過去を封印することで、戦後の復興を成し遂げ、また自信を回復してきたのだ、という点である。それはすなわち、心理の巧妙なすりかえがあったのだということだ。たとえば戦後すぐドイツではオペラが上演され、三島憲一『戦後ドイツ』によれば、「ベルリンで毎晩200個所以上で芝居が上演され、毎日最低六つの演奏会があり、そして、オペラハウスも休演することがめったになかった」とのことである。こうした戦後のドイツの風景にたいしてゼーバルトは、「人類の歴史において、このような演奏をおこなうのはドイツ人のみであり、これほどの苦難を耐え抜いたのもドイツ人のみであるといういびつな誇りに、彼らの胸はふくらみはしなかったか」と。いびつな誇り、その心持ちが戦後の荒廃したなかでドイツ人に新しい生を歩ませることになる。三島憲一はそのあたりの事情を「このあたりの変わり身の早さは、ドイツ人全体にも共通している」と、辛辣な表現で指摘している。ゼーバルトは「当時のドイツほど、知りたくないことを忘れる人間の能力、眼前のものを見ずにすます能力が端的に確かめられた例は希有であったろう」と述べている。そしてその実体は「抑圧のメカニズム」の働きなのである。
では文学は何をしてきたのか。あるいは言語は何を表象してきたのだろうか。いや問いとしては、なぜ文学はその描写をもちえなかったのか。言語はどんな表現に逃げをうったのか、と問うほうがより的確だろう。
まずそもそもは、上記で言われた「変わり身の早さ」によって、そもそも描写の対象にしなかったということが挙げられる。そしてもうひとつは言語の表象の困難さという問題である。
空襲とはひとつの言語に絶する出来事である。それは「生の形では描写を拒む現実」である。人が「思考や感覚の許容量」を超える体験をしたとき、その表現は、思考や感覚が麻痺しているゆえに、ほとんどが紋切り型の表現になってしまう。それによって、現実と言語の間には大きな齟齬が生まれてしまうのである。それは同時に、理解を絶する体験を本当に表象するところまでいかず、「蓋をして毒消し」をしてしまうことになる。
だが、最大の問題は、表象が不可能だったのではなく、もちろんきわめて難しいとはいえ、それがタブーだった点にある。空襲を表象しようとする試みは、戦後復興のなかで誇りを取り戻そうとしてきたドイツ国民に対して、その誇りによって戦後、精神衛生を保ってきたドイツ国民に対して、じつは壁の裏側には、おびただしい死者、死臭、残骸、荒廃、血と汚物、そうした我々の精神に混乱をもたらす事実が、いたるところに転がっていることに言及せざるをえないからである。ゼーバルトはレーディヒという忘れ去られた作家を持ち出し、かれの「嫌悪と嘔吐を催させる」文体が、戦後に忘却の上に成り立つ戦後の文化的記憶から締め出されたのは、「防疫ラインを破るおそれがあったからだ」と述べている。空襲について語ることは、それが我々を忘却へと葬ってしまうほど、紋切り型でしか表現できないほど、我々の経験を超えた出来事である。しかしもしそれについて語りうるならば、それが同時に戦後ドイツという過去の忘却の上に今まで成り立ってきた文化が実は幻想であることを、それゆえに書くことがその幻想から覚まし、時間の寸断(戦前と戦後)というまやかしを暴き出すことになること、これこそが恐怖であり、ドイツの理性はその恐怖を今まで封印にしてきたことを、ゼーバルトは告発するのだ。
しかしでは、どのような表象ならば語ることが可能なのか。ゼーバルトが挙げる数少ない成功例がノサックである。ノサックは「非人間性と紙一重の、倫理的感覚の欠如」を書き残す。
文学が歴史と異なってできることはこの点だ。文学は、歴史と異なり、ひとつの断片、物語化されえないひとつの断片でさえ、言語として表象する可能性を持っている。それが個人の視野におさめられたものでもかまわない。ただし、それが個人にとどまってしまえば、それは文学とならず、日記や覚書となろう。また装飾を交えてしまっては神話となってしまうだろう。文学とは、あくまでも「虚飾をまじえぬ客観性に裏打ちされた真実」を語らねばならないのだ。それでこそ、ひとつの断片であっても、他者とつながる契機が生まれるのである。歴史であれば、個の断片は、普遍性へと回収され、歴史的意味を帯びる。文学はこの大きな意味とはことなる、個でありながら、他者と了解可能な表象を探る言語の実践なのではないだろうか。
だからこそゼーバルトは「私の人生と、空襲の歴史とが交錯する点」をいくつも述べてきたのではなないだろうか。