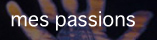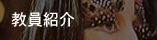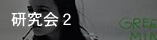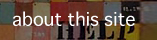2009年4月
 自分があまり今のソウルを聞けないのは、どれほど才能があると思っても、音がきわめて企画化されてしまっていることが多いからだ。美しい声、恵まれた声量をもって、メロディアスな歌を歌っても、バックの打ち込みや、おきまりのアレンジに、ミュージシャンの個性がかき消されてしまっている(日本で最近よく聴く歌姫たちもそうだろう。一人一人がきわめて才能の高い歌い手であるにもかかわらず、売れ筋の歌しか歌っていない。もっと魂をこめた曲を歌わせてあげられないものだろうか)。
自分があまり今のソウルを聞けないのは、どれほど才能があると思っても、音がきわめて企画化されてしまっていることが多いからだ。美しい声、恵まれた声量をもって、メロディアスな歌を歌っても、バックの打ち込みや、おきまりのアレンジに、ミュージシャンの個性がかき消されてしまっている(日本で最近よく聴く歌姫たちもそうだろう。一人一人がきわめて才能の高い歌い手であるにもかかわらず、売れ筋の歌しか歌っていない。もっと魂をこめた曲を歌わせてあげられないものだろうか)。
このCorneilleも本編の方は、ちょっと類型化された音作りで、彼にどんなバックボーンがあろうと、その内面にまで入っていきにくい。ただ、彼には歌うべき詩がある。そしてその詩がきりきりする程の痛みとともに伝わってくるのは、Disc2のアコースティックバージョンの方だ。一聴して胸を激しく揺さぶられた。あまりの切なさに電車の中でも泣きそうになって、必死にiPodを握りしめた。
アコースティックであるだけ、歌詞の青い、甘ったるいところが、切実に胸にせまってくる。この青さを許してしまうのは、この歌手があまりにも壊れやすい弱さを感じさせるからだろうか。
たとえばDisc2の1曲目Sans rancune(恨みっこなしさ)のサビの部分。
Sans rancune
La première étoile que je déchroche,
je te la donne
La première place dans mon rêve,
je te la réserve
恨みっこなしさ
僕がつかんで降ろす最初の星
それを君にあげるから
僕の夢のとっておきの場所
それは君にとっておくから
こうしたみえすいた言い訳は、ナイーブさの裏返しだ。
Je suis désolé
mais il faudra que je prenne ma chance.
悪いけど
でも自分の運をためさないと
Corneilleは惜しげもなく自分について歌う。
On dit : Corneille est froid
Il n'a rien dans le coeur que sa maudite carrière
On me reproche, entre autre
De n'avoir la tête qu'à mes poches et pas assez aux autres
人は言う「コルネイユは冷たいやつだ」と
あいつのこころには、自分の忌まわしい仕事のことしかない
人は僕をせめる、とくに
自分のことしか頭になく、他人のことはあんまり考えないと
こうしたフラジャイルな内面をもちながら、Corneilleは言う。
Le but de ma démarche est plus grand que ça
僕がこうしていることの目的は、みなが考えていることより大きいんだ
そして、モントリオール、パリ、ルワンダとそのために自分が渡っていくんだと歌う。
ナイーブにも自分の内面をさらけ出してしまうこの若さ、そこにとても惹かれるのだ。
そしてアコースティックバージョンは、無駄な装飾がない分だけ、曲それぞれのヴァラティの豊かさが感じられる。ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ大陸をわたってきた人物らしい、様々なバックボーンを感じさせる曲々だ。歌い方はソウルフルなところもあれば、北アフリカっぽいリフレインがあったり、シャンソンの叙情性を感じたり、フォークのたたずまいがあったりと、彼の豊かな音楽経験が上品にそれぞれの曲に溶け込んでいる。
コルネイユにはどうしてもそのルワンダでの体験が、影を落としている。
C'est la mémoire qui m'empêche de vivre
dont souvent je me sers afin de survirre
私が生きてゆくのを邪魔するのはあの記憶だ
そして私は生き続けるためにこの記憶に頼るのだ
このアンビヴァレントな歌詞が、Corneilleの傷つきやすさをとてもうまく表現しているように思える。強いメッセージと、それを直接には表現せず、歌という美しさにのせるCorneilleのアーティストとしての意識が、このアルバムをクオリティの高い1枚にしている。
 「芸術のための芸術」といった世界となんの関わりももたないような、自律した芸術作品という考えに立ってものを考えることは、最近はあまりないが、しかし、ロックには、幻覚作用によって、この世界を消し去ってしまう強い魅力があることは確かである。現実を忘れさせるような、強いカリスマ性をもったロック・スターが、60年代から70年の初頭にかけて何人も登場した。その中でもデヴィッド・ボウイは審美性が高く、「地球に墜ちてきた男」という形容が実にふさわしいアーティストだ。
「芸術のための芸術」といった世界となんの関わりももたないような、自律した芸術作品という考えに立ってものを考えることは、最近はあまりないが、しかし、ロックには、幻覚作用によって、この世界を消し去ってしまう強い魅力があることは確かである。現実を忘れさせるような、強いカリスマ性をもったロック・スターが、60年代から70年の初頭にかけて何人も登場した。その中でもデヴィッド・ボウイは審美性が高く、「地球に墜ちてきた男」という形容が実にふさわしいアーティストだ。
初めて聞いたボウイのアルバムは、『スケアリー・モンスターズ』だった。Ashes to ashesの壊れやすいヴォーカルが、自分にとっては以後好きなロックを見分けるひとつのレフェランスになった気がする。たとえばOrange Juiceのエドウィン・コリンズのヴォーカルなど、自分にとっては「高音裏返り男性ヴォイス」の代表だった。
『スケアリー・モンスターズ』をエア・チェックしたFM番組は、しかし一曲目にボウイの代表曲として「Starman」をかけた。そのときの、文字通り鳥肌がたった瞬間は今でも覚えている。アコースティックギターとささやくような軽くかすれたヴォーカルから、サビのスターマンへと一気にもりあがる曲の展開は、けっして大げさではなく、しかしドラマティックだった。もちろんジギー・スターダストの高揚感にくらべれば地味かもしれない。だが、音をどれだけ削りとったとしても、聴く者を幻惑するロックの魅力をスターマンという曲はそなえている。わずか数分の間に、圧倒的な盛り上がりへと至る展開は、ボウイの当時の曲のエッセンスといってもいいのではないだろうか。
『ジギー・スターダスト』という時代を象徴するアルバムと聞き比べると、『ハンキー・ドリー』はその予兆をこめた一枚ともいえる。しかしけっしてその前段階にあるアルバムではない。このアルバムには、「ブリティッシュ・ロック」ならではのメロディセンスがあふれた名曲がいくつもおさまっている。まず一曲目のChanges。サビの「チェ、チェ、チェ、チェンジ〜ズ」のところで、開始そうそう胸が締め付けられる。二曲目はピアノのイギリスっぽい旋律に、ボウイのヴォーカルがかさなり、またまた胸がどきどき。Oh! You Pretty Thingsの歌詞の部分、たそがれた雰囲気を醸し出しながらも、力強く歌われる展開が実にロマンチックで、イギリスのロックにしかありえない甘美なメロディだ。4曲目の「火星の生活」のイントロも甘美でありながらも、瑞々しく、ダイナミックで、ストリングスもはいる。それなのに大げさではないのは、曲のコンセプトがしっかりしているからだろう。
今回聴き直して思ったのは、本当にイギリスでしか出せない音がここにはつまっているということ。6曲目Quicksandの展開もそうだ。ヴォーカルにアコースティックギター、ピアノの伴奏、そしてやはり一気にさびへといたる展開は、まさにイギリスのもつ叙情性の最高の表現だと思う(CDにおさめられているデモトラックは実にかっこいい)。そうボウイはライブで「Thank'you sincerely」と言ってしまうようなイギリス人なのだ。
最初に、この世界を消し去る魔力がこのアルバムにあると書いた。だが同時に、このアルバムを聞いたあとには、世界の見方が変わってしまう。それは単に耽美やアングラという趣味の問題ではない。そうではなくて、ボウイの生き方自体がこちらを挑発するのだ。60年代後半から70年代を疾走したボウイのようにだれも生きることはできない。生のエネルギーをあれほどまでに激しく燃焼させることはだれにもできない。だから、1980年にLodgerのジャケットのように死ぬべきロック・スターは、実はボウイだったのではないか。
リクールは、この著書の第一部第三章で個人の記憶と集団の記憶の関係を扱っている。個人の記憶を語るにあたってリクールが援用するのがregard intérieur「内省のまなざし」である。そして「誰が」想い出すのか、という点に留意をすることのなかった古代ギリシアの思想家たちに対して、「内省のまなざし」の伝統の端緒に位置づけられるのがアウグスティヌスである。リクールは『告白』の第十巻、第十一巻を検討しながら、記憶と時間の問題が、個人の内面、において展開されることを述べる。
«C'est moi qui me souviens, moi l'esprit»(Ego sum, qui memini, ego animus. 山田訳は「記憶するのはこの私、すなわち心としての私です」。第十巻第十七章25)
アウグスティヌスの内面とは「苦しみの探究」に他ならない(une quête douloureux de l'intériorité, p.118.)。なぜなら告白の時とは、悔悛の時であり、その悔悛は、記憶と自己への現前における苦悩(「記憶なしには、私は私ということばすら発することができないはずなのに、その自分の記憶の力を、私自身完全にとらえることができないのです」山田訳p.352.)と結びつけられているからである。
リクールはアウグスティヌスの個人的記憶を語るにあたって、記憶の3つの特徴をまとめている。
1) 記憶は、体験と同じように共有不可能な単独のものである。
2) 記憶は人格の時間的同一性を保証する。ここでリクールはsouvenirとmémoireを区別する。前者は複数形で、それらが意味合いによって並べられたり、断絶がありうる。それに対してmémoireは単数形であり、時間を切れ目なく遡ることを可能にする。したがって、記憶は、souvenirが断続的であったとしても、そして現在の自己が、切り離されたsouvenirに現在の自己との異質性を認めるとしても、その異質な自己も自己であることを保証するのだ。
3) 時間の流れの方向性(過去から未来へ、未来から過去へ)を定めるのは記憶の働きである。
この3つの特徴によって、「内省のまなざし」の伝統がうち立てられる。そしてアウグスティヌスがこの伝統の最初に位置づけられるのは、キリスト教への改宗という内面的な出来事ゆえである。リクールは、「内省のまなざし」がその頂点に達するのはフッサールであるとし、ロックによって扱われるアイデンティティやカントによる「主体」といった問題は、アウグスティヌスには現れてはいないが、アウグスティヌスの重要性を記憶の分析と時間の分析を結びつけた点に認めている。
アウグスティヌスにおいては、「わが神は、わが内なる人間にとっての光であり、声であり、香りであり、食物であり、抱擁なのです」(第六章8)と言われる通り、神が求められるのはわが内面である。そして自己の内面とは、記憶の「宏大な広間」(第八章12)である。記憶は、宏大であり、かつ対象を想い出すとき、私はその時の私自身も想い出している。
とはいえ、記憶には忘却がつきまとう。記憶は「広間」であると同時に、思い出の「墓地」にもなりうる。この忘却を超えて、記憶の偉大な力を確信するも、アウグスティヌスは、神に達するためには、記憶すらも超えてゆくという。ここにも大きなアポリアがある。
«Si c'est en dehors de ma mémoire que je te trouve, c'est que je suis sans mémoire de toi ; et comment dès lors te trouverai-je si je n'ai pas mémoire de toi ?» (山田訳「もしも私の記憶の外にあなたを見出すのだとすれば、私はあなたを記憶していないはずです。けれども、もし私があなたを記憶していないとすれば、どうしていまあなたを見出すことができるのでしょうか」第十七章26)。
第十一巻で問題になるのは「時間の計測」である。時間とは流れてゆくものであるが、実際に計測可能なのは過去と未来である。ここでリクールはdistentioという概念によって現在を3つにわける。過去の現在=記憶、未来の現在=期待、現在の現在=注意である。アウグスティヌスも同じように言う。「それにしても現在の時は、測られるとき、どこから来たり、どこをとおって、どこに過ぎ去っていくのでしょうか。どこからーもちろん未来から。どこをとおってーもちろん現在をとおって。どこへーもちろん過去へです」(第十一巻第二十一章27)。
個人の内面における記憶と時間の関係。これを基礎として、リクールは共同の記憶へと考察を進める。
 ベースメントテープスの音源と同じ67年に収録されたこのアルバムは、音数も最小限で、曲も非常にシンプルである。しかし、きわめて豊かな深みをもったアルバムだと聞くたびに感じる。どの曲もほとんど2,3分で、4分を越える曲が1曲、5分を越える曲が1曲である。そんな小品が集められたこのアルバムだが、力を抑えている分だけメロディの美しさが際立つ。アルバムと同タイトルのJohn Wesley Hardingは、一聴してすぐに口ずさめてしまう親しみやすいメロディだ。激しいライブテイクのほうが印象に強い「見張塔からずっと」のオリジナルテイクは、各楽器の生の音が際立つきわめて簡素な曲だ。それでももちろんメロディの切迫感は、どれほど音がアコースティックでもひしひしと伝わってくる(ちなみにこの曲のベースラインは裸のラリーズの「何が欲しいときかれたら、紙切れだと答えよう〜」と似ている)。
ベースメントテープスの音源と同じ67年に収録されたこのアルバムは、音数も最小限で、曲も非常にシンプルである。しかし、きわめて豊かな深みをもったアルバムだと聞くたびに感じる。どの曲もほとんど2,3分で、4分を越える曲が1曲、5分を越える曲が1曲である。そんな小品が集められたこのアルバムだが、力を抑えている分だけメロディの美しさが際立つ。アルバムと同タイトルのJohn Wesley Hardingは、一聴してすぐに口ずさめてしまう親しみやすいメロディだ。激しいライブテイクのほうが印象に強い「見張塔からずっと」のオリジナルテイクは、各楽器の生の音が際立つきわめて簡素な曲だ。それでももちろんメロディの切迫感は、どれほど音がアコースティックでもひしひしと伝わってくる(ちなみにこの曲のベースラインは裸のラリーズの「何が欲しいときかれたら、紙切れだと答えよう〜」と似ている)。
そして同じメロディが繰り返される小品も多い。次の「フランキー・リーとジュダス・プリーストのバラッド」は、ほとんど単純なリフが繰り返されるだけだ。二人の登場人物を巡る寓話につけられた伴奏のようである。ちなみにこの曲だけが5分35秒と1曲だけ長い。
一番好きな曲はI pity the poor immigrantだ。3拍子の切ない美しいメロディの曲である。とても単純なメロディなのに激しく心を揺さぶられる。怒りや、激しい感情の起伏がなくとも、いやそうしたセンチメンタルさがないぶんだけ、ディランの声からは憐れみと悲惨がこぼれおちてくる。歌詞が難解なぶんだけ、明確なメッセージ性を感じることは難しい。だが、それゆえに、たとえば「笑いに満たされた口」、「彼の血でつくられた街」など、きわめて象徴性の高い比喩的形象によって、移民のあわれな物語が紡がれる。わずか4分で、一人の人生を語り、かつその世界を私たちに届けてしまうディランとは、ほんとうに優れた詩人なのだ。
しかしそれは(人間が生の悲惨さから逃れ、救済されるということ)、普通の人間にはできない。えらばれた聖者が、清浄無垢の生活により、即身に救済を成就する。信者は、聖者の説教を聞き、聖者の行なう秘儀にあずかり、これに生活の資を供養することにより、聖者を通して救われる。(p.25)
イェルペルセンは、その著書『言語』の冒頭で、「言語の科学」の始まりは、言語が複数存在していること、言語の起源、言葉と物の関係などの問いが生まれたときであると述べている。この部分が、古代の、科学未満にとどまる言語考察の書き出しであるとはいえ、言語について考えを押し進めてゆくと、この始まりと有契(縁)性(motivation)をどうしても考えざるをえないのではないか。『言語』の第二部が子ども、第三部の第一章が外国人であるのは、最初は驚くが、子どもは言語を話し始めてゆく起源の問題、外国人は言葉と言葉が接触によって生まれる「誕生」と「歴史的変化」についての考えの反映なのではないだろうか。
西洋の18世紀は、まさに「言語の起源についての試論の時代」である(Droixhe, linguistique..., cité par Berbounioux, «L'origine du langage : mythe et thérie», p.20)。そして言語の起源をintrospection(感覚表現による言語の形成)と、interation(人間同士の伝達の必要性からの言語の誕生)の大きく二つに分類すれば(Cf.Bergounioux)、コンディヤックの言語起源論は前者の代表的著作と言えるだろう。1746年に刊行された『人間認識起源論』である。第二部第一章「言語の起源と進歩について」は、表題通り、言語の起源とその言語の変化を追っている。この言語の考察における感覚論をもっともよく表しているのは、コンディヤックが引用するロックの『人間知性論』の次の一節だろう。
「もし全ての単語をその源まで遡ることができるとすれば、どの言語の場合でも、感官にとらえられないような事物を表すために使われる単語が、その起源においては感覚的な観念から引き出されてきたということが、疑いもなく分かるであろう。そしてそれが分かれば、初めてこういう言語を話した人々がどのような類いの概念をもっていたのか、それらの概念はどこから彼らの精神にやってきたのか、そして彼らがそれらの事物に付けた名前そのものが、いかに雄弁に人間のあらゆる知識の起源や原理を問わず語りに示唆しているか、といったことがらについて、我々は推測を巡らせることができるのである」(p.133)。
これはコンディヤックが魂の運動を物体の運動の間に、人間が連関を見出していった過程について述べた箇所につけた注に載せられたテキストである。
まず物体の運動を受容し、認識する人間の感覚の働きがある。しかし人間の感覚の対象となるものは、外界の具体物だけではない。人間は、その外界の物体の運動と魂の運動とのアナロジーによって、分節音からなる抽象的な言葉を生み出していった。したがって、「もっとも抽象的な言葉といえども、それは感覚的な対象につけられた最初の名前に由来する」(p.132.)のだ。
このようにあらゆる名前が、起源においては具体的な形象をもっていたとするのが、コンディヤックの感覚論における言語発生論の基盤となる考えである。そして自己の魂の中でうまれているものにたいし、人間が名前をつけるのは、身体と深く結びついた「欲求」(besoin)による。
「感覚論」に根幹を置くコンディヤックの言語起源論であるが、しかし、よく読んでみると、そうとも言い切れない、様々なニュアンスを含んだ言語論であることがわかる。たとえば、冒頭第一章の言語の起源では、「情念の叫び声といくつかの知覚とが結びつく」ようになり、叫び声が、知覚の自然な記号となったと言うが、そのように魂が働くためには、二人の子どもが「相互に交渉しあう」(p.17.)ことが前提となっている。確かに、他者の苦しみを見るという知覚の働きから苦しみを感じ、その欲求から叫び声や身振りの言語が生まれてくるというとき、そこには感覚の受容があることは間違いがない。また、何かを伝えるという主体の意志がその動因となっているわけではない。しかし言葉の生まれる現場に他者が介在しているということは、言葉を生む人間は孤独な詩人のように単に外界のオブジェを、それへの反応としてのことばと結びつけるだけではないだろう。
進歩とは、叫びと身振りという、状況や対象と密接に結びついた言語から、恣意的な言語の発生への変化である(p.20.)。そして最初は叫びであった音は、抑揚をもった声へと進歩し、それが感情を素朴ではありながら表現することになる。そしてこの素朴な段階とは、模倣の段階である。
「様々な動物に付けられた最初の名前はおそらくその鳴き声を模倣したものであっただろうと付け加えることができよう。そしてこのことは、風や川、そして物音を立てる全てのものに付けられた名前についても等しく言えるであろう。こういう[物音の]模倣をするためには、非情にはっきりした音程差でもって音声が語られたであろうということは明らかである」
つまりここには自然を模倣し、その音そのものが言語となるというオノマトペとの親縁性を認めることができるのだ。
コンディヤックの言語論は言語一般についての考察だけではない。「風土」や「国民性」の問題も扱われている。たとえば、「北方に住む冷淡で粘液質の人々がこのようなアクセントや音節の長短を保持し続けることは、その気候[風土]が許さなかった」(p.83.)は、風土の違いによる言語の特質の違いという関係を前提としているし、第十五節は「諸言語のそれぞれの特質について」と題され、風土と政体による気質の決定について、モンテスキューの『法の精神』よりも2年前に説いていることは特筆に値する。またこの節では、その国民の国語の特質が、偉大な作家の助けを借りることなくしては、開花するに至らないとして文学言語の言語一般への影響を問うていることにも注目しなくてはならないだろう。メショニックが指摘するように、ここには典型的な「言語を問うことは文学言語を問うことと等しい」という命題の具体例を認めることができる。
最後に指摘しておきたいのが、言語と物の関係の進展である。まず身振りの言語の段階では、表現とは模倣でしかなく、細かい部分にわたって表現することは無理であった。したがって、人々は「貧しい言語」を使って、比喩にたよるしかなかった。冗語法は、適切な言語がないことから人々がたよった欠陥であったが、それは「粗雑の精神」には他に頼るものがなかったのである。つまりコンディヤックの描く言語の進歩とは音節言語の進展にともない言葉が豊となり、語彙が増え、観念と言語の一致が果たされることを意味するのだ。「必要な観念にそれぞれぴったりと合う単語が十分に整い」(p.96.)は、そうしたコンディヤックの言語観を集約した表現であると言える。そしてその意味でも言語の起源には詩と音楽が、社会的伝達の手段として人々の間に存在していたということが言える。文字の誕生は、そうした音楽や詩の機能を実用から喜びへと変化させる役割を担ったのである。