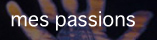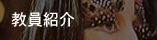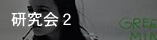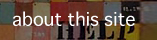2009年6月
本書は歴史家Mona Ozoufが一般向けに行なった講演を冊子にしたものである。この短い講演の趣旨は、Jules Ferry(1832-1893)の再評価である。
Jules Ferryといえば、第三共和制において義務教育の拡充をはかった人物であり、また同時に植民地拡張政策を推進した人物である。後者については、たとえばTodorovはその著書『われわれと他者』(nous et les autres)のなかで、わずかなページではあるが、全国民の文化水準を上げるための無償義務教育の政策と、教育と文明化の使命を帯びた植民地政策に連続性をみて、痛烈な批判をしている。
しかしながら、この小著では、当時、左右両派から非難を受け続けた政治家に潜む偉大さを掬いとる試みがなされている。
まず最初にFerryの生まれてからの政治家になるまでの足跡が簡単に述べられているが、この中で取り上げたいのは次のニ点であろう。第一点は、Ferryが旅行するなかで、イギリスの現実主義的な気質に触れたこと(p.13.)、第二点は、若いときに二月革命から第二帝政、すなわち「共和制の敗北」(p.16)に遭遇した世代であるということである。
こうしたFerryの若い時の時代を素描した後で、Ozoufは、Ferryには解くべき3つの謎が科せられたとする。1)中央集権化。ここでOzoufは、FerryがToquevilleにならって、政治的な中央集権と行政的な中央集権を区別し、国家に対して社会が自律して、「自由な議論と会合ができる体制」を重視していたことを指摘する。2)共和主義体制の不安定さ。3)フランスが孕む対立項。この対立項とは、フランス革命を肯定するのか、否定するのかという対立である。
この2), 3)の解決としてFerryが持ち出したのが、フランス革命と共和主義を切り離して考えるという視点である。そしてここでもOzoufが強調するのは、Ferryが、フランス革命における国民の単一性は結局専制主義的な形でなされてしまったのに対し、この単一性は、あくまでも自由において、たとえば出版の自由、地方自治や組合(p.31.)のような中間団体の設立さえも可能とする自由において、うち立てられなくてはならないと考えていたことを強調する。
この自由の確立において、教育の問題も考えられる。Ozoufの後半の主題はこの教育における自由の問題である。それは次のようにまとめられよう。
学校制度においては共同体の精神原理として、神という絶対的価値基準、すなわち宗教的な価値基準ではなく、フランスの歴史という過去の共同性を置くことが、フェリーの関心の中心となる。共和国においては、フランス革命によって根こそぎにされた近代ではなく、それ以前から脈々とつながる「フランス国民の魂」こそが統合の原理となる。したがってフランス革命時の共和主義移行によって否定された王や臣下たちが、歴史的な対象として学ばれる。すなわち、フランス革命による断絶を修復し、歴史による過去の共同性によって統合原理を構成するのがフェリーの目的である。教育こそ、19世紀以来なんども倒されてきた共和国を安定させる鍵であると、フェリーは考えていたのである。
この共同性さえ学校という公的な空間で構成できれば、宗教は、18世紀の啓蒙主義のように無知蒙昧の迷信、国家の敵とはならない。それどころか、フランスという国はキリスト教による安寧のもとに成立していることをフェリーは進んで肯定する。フランス人の心性がキリスト教にあることを認めているのである。フェリーはナポレオンによるコンコルダートさえ否定することはなかったのである(その破棄は1905年の政教分離法である)。このあたり、Ozoufは、Ferryの現実主義的な考え方を例証している。
では自由とは何だろうか。OzoufはFerryが女子教育にも力を入れたことを述べているが、その理由を次のようにまとめている。
Il s'agissait bien de former des femmes capables de partager avec leurs époux le goût de la discussion politique et le souci de l'éducation civique de s enfants.
女性を、政治的な話題への興味や子どもの市民教育への配慮を夫とともに分かち合えるよう、教育することが主眼であった。
つまり女性にplus de lumières「より多くの知性」とmoyens critiques「批判的方法」を与えることがその目的であったとOzoufは指摘する。
Ozoufは、Ferryのなかに自由と批判的精神が堅固に結びついていることをこの講演の主題としているのだろう。自由とは批判の精神である。ではcritiqueとは何だろうか。それは、このFerryの思想に従うならば、自ら思考し、相手にその思考を伝える言語化の技術であり、ある価値を鵜呑みにせずみずから検証する作業であり、そしてそうごにその意見を交わして議論するための知的活動である。そしてわれわれには、われわれの意見を書き、話し、議論する自由があるということ。Ozoufはこの自由の保証こそが、共和国を永続化させるための根本であるとフェリーが考えていたとする。そしてフランスという国家の単一性を自由の上にうち立てようとしたことに(p.61.)ことにFerryの独自性をみているのである。
 自分がくるりに求めてきたのは何だったのだろうか。それは青春の未熟さ、そして未熟ゆえのたわいもない毒ではなかったか。そして未来へのあいかわらずあいまいな希望。「なにか悪いことやってみようかな」とか、「車の免許とってもいいかな」とか、そうした獏とした未熟さがくるりの魅力ではなかったか。せっぱつまった青さ。どうにもならないいらだちからの毒づき。そんなアンバランスさがくるりの魅力ではなかったか。
自分がくるりに求めてきたのは何だったのだろうか。それは青春の未熟さ、そして未熟ゆえのたわいもない毒ではなかったか。そして未来へのあいかわらずあいまいな希望。「なにか悪いことやってみようかな」とか、「車の免許とってもいいかな」とか、そうした獏とした未熟さがくるりの魅力ではなかったか。せっぱつまった青さ。どうにもならないいらだちからの毒づき。そんなアンバランスさがくるりの魅力ではなかったか。
今では新譜の発売日に即購入するミュージシャンはほとんどいない。くるりはその珍しい例外で、発売日前夜に買ってここ三日間聞き込んできた。悪くはない。だがここに並べられた曲はいったい何の表現なのだろうか。何を追求しているのだろうか。必然性とか、性急さのような素人くささはない。だが「太陽のブルース」、「夜汽車」「リルレロ」と続くところなど、もうお約束を聞かされているようで、これらの曲をだれが10年後に思い出すだろうか?
自分が聞きたいと思うのは、たとえばたくたくで行なわれたバンド編成のライブ。これを聴いていて気持ちよいのは、そのつんのめるような、ライブハウスのテンションだ。もちろん曲自体のもつ魅力もあるけれど、それを超える音楽が発する高揚感、そしてその高揚感を下支えするくるりの技術と表現力。一言「ロックって最高!」と言ってしまえる潔さがある。これを聞いていると、そうしたライブハウスへ足を運ぼうともしない自分のほうが今度はロックをかたるだけの欺瞞に満ちた存在に思えてくる。
じゃあアルバムに何を求めるのか。それは何らかの意図を貫徹できるはずの場所であり、曲のよさを超えて、私たちにつたえられるそのバンドの音楽へのひたむきさを求めたいと思う。そう、曲のよさについてはそれほど言うことがない。むしろそれを通してこちらに伝わってくる魂の情動こそ感じたいのだ。くるりの最近のアルバムにはそれが希薄なような気がしてならない。そう、Come togetherという感覚。その感覚がだんだん希薄になっているような気がする。
よい曲ならいくらでもかけるだろう。しかし私たちを今いるこの場所からどこかへ連れて行ってはくれない。そんな失望をこのアルバムに感じざるをえないのだ。
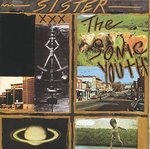 中三のときに、いつも夕方聞いていたFM愛知の番組でパーソナリティが「今日は、今までとまったく違う音楽をおかけします」といって紹介したのが、ラフ・トレードの初期リリース5枚だった。そのほとんどを買ったのだが、そこにはポップ・グループ、キャバレー・ヴォルテールという名前が並び、5枚目は「クリア・カット」というオムニバスで、ジョゼフ・K, スクリッティ・ポリティ、ザ・フォール、オレンジ・ジュースそして、ロバート・ワイアットというごった煮状態の曲がおさめられていた。パンク以後、「オルターネイティブミュージック」のイギリスでの誕生である。ニューヨーク・パンクは詳しくないので、ポスト・パンクもふくめてきちんとしたことが書けないのだが、ノイズとはその後White Houseなどの殺戮的な実験音楽、あるいはDAFのようなインダストリアル・ロック(その後のノイバウテン)、そして日本の裸のラリーズへと自分のなかでは広がっていった。しかしこうした名前を並べただけで、ノイズといってもそれは音の表面的な印象を指すに過ぎないということは明らかだろう。ラリーズをノイズ・ロックと言ってしまっては、ラリーズの夜の闇と夜明けの曙光をまったく看過してしまうことになる。
中三のときに、いつも夕方聞いていたFM愛知の番組でパーソナリティが「今日は、今までとまったく違う音楽をおかけします」といって紹介したのが、ラフ・トレードの初期リリース5枚だった。そのほとんどを買ったのだが、そこにはポップ・グループ、キャバレー・ヴォルテールという名前が並び、5枚目は「クリア・カット」というオムニバスで、ジョゼフ・K, スクリッティ・ポリティ、ザ・フォール、オレンジ・ジュースそして、ロバート・ワイアットというごった煮状態の曲がおさめられていた。パンク以後、「オルターネイティブミュージック」のイギリスでの誕生である。ニューヨーク・パンクは詳しくないので、ポスト・パンクもふくめてきちんとしたことが書けないのだが、ノイズとはその後White Houseなどの殺戮的な実験音楽、あるいはDAFのようなインダストリアル・ロック(その後のノイバウテン)、そして日本の裸のラリーズへと自分のなかでは広がっていった。しかしこうした名前を並べただけで、ノイズといってもそれは音の表面的な印象を指すに過ぎないということは明らかだろう。ラリーズをノイズ・ロックと言ってしまっては、ラリーズの夜の闇と夜明けの曙光をまったく看過してしまうことになる。
Sonic Youthは今まで素通りしてきたバンドである。先日Télérama musiqueで72年生まれの作家が自分のロック経歴を語るインタビューがあり、そこでこのSisterに収められているSchizophreniaを初めて聴いて、さっそくアルバムを980円(at レコファン)で購入。インディ時代の最後のアルバムとのことである。発表されたのはもう20年も前のことだが、まったく時代の流れに巻き込まれてしまうことなく、今でも一枚の完成度の高いアルバムとして聞くことができる作品だ。
オルタナバンドによくある、衝動の垂れ流しではまったくない。とはいえ、ヘヴィメタバンドのように計算高いところもない。形式へ上昇しようとする美しさとそれを破綻へと至らしめる衝動のアンバランスさと緊張関係が素晴らしい。ノイズ・ギターの一音が、ハウリングをともなって消えてゆくとともに次の一音のために弦が鳴らされる。Dinosaur JRのギターが絶え間ないメロディの叙情性をたたえているとするならば、Sonic Youthのギターは叙情性を切り刻んでしまうカッティングギターだ。
Sonic Youthは、Killing JokeやHappy Birthdayなどのグランジという言葉が生まれる前のノイズ・ロックの文脈に位置づけられるように思う。ひるがえってDinosaurは、これは疑うべくなくニール・ヤングのフォーク・ロックの文脈だ。前者がニューヨークのハコでセッションを繰り返しているイメージなら、後者は自分の部屋にギターとアンプをもちこんで、ヘッドホンをつけてベットの上でギターを弾きまくっているイメージだ。
繰り返しになってしまうが、ノイズ・ロックはジャンルではない。もしそれをジャンルとするならば、White Houseのようなもはや曲や音楽とはいえない「雑音の塊」しか扱えないだろう。ノイズ・ロックはあくまでも技法であって、その技法の先に音楽が現れる。よく聴いてみると、Sonic YouthもDinosaurも、叫び、わめくようなヴォーカルは驚くほど少ない。叫ばずとも、わめかずとも、その衝動を伝える音楽を創作することはできる。この創作への意識の高さが、Sonic Youthを現在でも最高のロックバンドのひとつにしているのであり、エレクトリックという電気で生まれる音をどう音楽にするのか、そのロックの課題にジミ・ヘン以後最も誠実に答えを出したのがこのバンドではないか。聞くに耐えない音楽と、何度もターン・テーブルをまわしてしまう音楽の境目にあるこのバンドの音楽はまさに中毒になる魅力をたたえている。