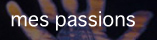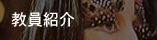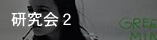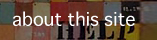畑谷史代
Apr
19
2009
心に石を抱いて歩いてゆく。だがときに目にみえぬその石の重みに耐えられず、体がよろめきくずおれる。そうした比喩を思い出す。言葉はそのやせ細った体の杖となれるのだろうか。
「終わらない戦後」。石原吉郎は1953年、シベリアからの引き揚げ船に乗った811人のうちのひとりとして舞鶴に降り立つ。8年という時間の流れは日本で暮らす人々にとっては、戦争を過去へと流すに十分な時間であった。確か『東京物語』が同じく昭和28年ではないだろうか。わずか8年であるが、戦前と戦後の切れ目を意識するには十分な時間であったようだ。
一方復員兵にとっては、その8年は麻痺した時間に等しい。極限を生きた体を背負って帰ってきた者は、まさに「浦島太郎」(p.22)のような状況に置かれたのだろう。端的に言えば、「忘れられた」(p.84.)存在である。戦争に動員され、シベリアでの強制労働を体験し、そして日本に戻ってくれば、故郷でさえ歓迎されることはない。生と死を彷徨いながら、それでも生きているとするならば、その生はどこによってたつものを求めたのだろうか。もはや「兵士として」、「抑留者として」、「日本人として」生きる可能性はすべて絶たれている。それらがすべて裁ち切られたあとに残ったのが、筆者のいう「人間として立とうする」(p.69)意志ではないだろうか。そして人間として立とうとするとき、石原の眼前にはおびただしい死者という人間が浮かびあがってきたのではないだろうか。
では、強制収容所における人間と人間のつながりとは何か?それは「共生・連帯・民主主義」である。だがその意味は、「お互いがお互いの侵犯者」であることがわかったうえで、自らの延命のために、成立する約束である。二人一組にスープが、毛布が支給される。自分の命を維持するためのつながりでしかない他者は、用がすめば圧倒的な無関心の対象である。すぐそばに人間がいる。しかしその人間にはまったく関心が注がれることはない。そして最終的に至る地点は、自己への無関心である。自己の単独性をはぎ取られ、数として、つまり無名の他者として自分自身も死んでいくあり方、しかもそうした自己の死へも無関心である状態である。
そうした「猿のような」状態を反転させうることができるとしたならば、それは、死をみとる者がいることではないだろうか。「死においてただ数であるとき、それは絶望そのものである。人は死において、一人一人その名を呼ばれなければならないものなのだ」(p.99. 「確認されない死のなかで」)。だから私は生き残りなのだ。無数の死者の名前を、その限りにおいて固有の死者を覚えている者として。だがそれは自己の正当化ではない。むしろ、自分が他者を凌いで生き残ったことを問い続けることでもあるのだ。ここに体験の特殊性、死と他者の結びつきの特異な体験がある。他者を押しのけて生きてきた、「加害と被害」の特異な体験である。あるいは、それは実は私たちの、薄められているが日常に偏在している「他者を押しのけて生きる」、犠牲にして生きることの、もっとも壮絶な形なのだろうか。
第4章には、石原と同じようにシベリア抑留を体験した人々、あるいはその家族の話がおさめられている。そこには60年を経てようやく語り始める人、最後まで固く口を閉ざしたまま亡くなっていった人、その家族の話がおさめられている。ここからは筆者の死者の固有性を書くことで残そうとする強い意志が、ひかえめな筆致から浮かんでくる。私たちの日常のなかで、人々が歴史にならぬ証言、証言ともならぬ体験を抱えて生きていること。その人間たちが今も死に逝こうとしている。その人たちの固有の人格を少なくとも名前としてでも記録すること。それが今を生きる生者の私たちの記憶になるのだろう。