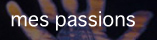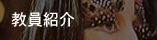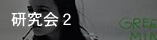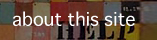くるり
 自分がくるりに求めてきたのは何だったのだろうか。それは青春の未熟さ、そして未熟ゆえのたわいもない毒ではなかったか。そして未来へのあいかわらずあいまいな希望。「なにか悪いことやってみようかな」とか、「車の免許とってもいいかな」とか、そうした獏とした未熟さがくるりの魅力ではなかったか。せっぱつまった青さ。どうにもならないいらだちからの毒づき。そんなアンバランスさがくるりの魅力ではなかったか。
自分がくるりに求めてきたのは何だったのだろうか。それは青春の未熟さ、そして未熟ゆえのたわいもない毒ではなかったか。そして未来へのあいかわらずあいまいな希望。「なにか悪いことやってみようかな」とか、「車の免許とってもいいかな」とか、そうした獏とした未熟さがくるりの魅力ではなかったか。せっぱつまった青さ。どうにもならないいらだちからの毒づき。そんなアンバランスさがくるりの魅力ではなかったか。
今では新譜の発売日に即購入するミュージシャンはほとんどいない。くるりはその珍しい例外で、発売日前夜に買ってここ三日間聞き込んできた。悪くはない。だがここに並べられた曲はいったい何の表現なのだろうか。何を追求しているのだろうか。必然性とか、性急さのような素人くささはない。だが「太陽のブルース」、「夜汽車」「リルレロ」と続くところなど、もうお約束を聞かされているようで、これらの曲をだれが10年後に思い出すだろうか?
自分が聞きたいと思うのは、たとえばたくたくで行なわれたバンド編成のライブ。これを聴いていて気持ちよいのは、そのつんのめるような、ライブハウスのテンションだ。もちろん曲自体のもつ魅力もあるけれど、それを超える音楽が発する高揚感、そしてその高揚感を下支えするくるりの技術と表現力。一言「ロックって最高!」と言ってしまえる潔さがある。これを聞いていると、そうしたライブハウスへ足を運ぼうともしない自分のほうが今度はロックをかたるだけの欺瞞に満ちた存在に思えてくる。
じゃあアルバムに何を求めるのか。それは何らかの意図を貫徹できるはずの場所であり、曲のよさを超えて、私たちにつたえられるそのバンドの音楽へのひたむきさを求めたいと思う。そう、曲のよさについてはそれほど言うことがない。むしろそれを通してこちらに伝わってくる魂の情動こそ感じたいのだ。くるりの最近のアルバムにはそれが希薄なような気がしてならない。そう、Come togetherという感覚。その感覚がだんだん希薄になっているような気がする。
よい曲ならいくらでもかけるだろう。しかし私たちを今いるこの場所からどこかへ連れて行ってはくれない。そんな失望をこのアルバムに感じざるをえないのだ。
 一聴して、解放感のあるアルバムだと思った。それはロックの切迫感をかなりそぎ落とし、メロディの流れにヴォーカルを乗せていく、曲調のせいだろうか。
一聴して、解放感のあるアルバムだと思った。それはロックの切迫感をかなりそぎ落とし、メロディの流れにヴォーカルを乗せていく、曲調のせいだろうか。
そして、とにかくやりたいことをやってみたという潔さがある。しかし制約を受けずに自由にまかせて創られた作品が、その人間の想像力と創造力を十分に発揮した作品になるわけではない。限られた機材、予算、時間、スタッフ、そうした制約の中でぎりぎりの状態で創られた作品であっても、歴史的な価値を生む作品はいくらでもある。その意味でくるりの文脈では、意味をもつ作品であっても、現在の日本のロックシーンへの位置づけとしてはどれだけの価値をもつ作品になるだろうか?そうした今現在への共振の少ない作品であることは確かである。
しかし走り続けるということは、ある意味貪欲に様々なものを吸収、咀嚼しないでは難しいだろう。様々なものに影響を受けつつ、しかし自分を律することで、自分であり続ける。それはけっしてたやすいことではない。なにせ自分で居続けるために、外からの影響を受けないではいられないというジレンマをかかえるわけだから。メンバーもどんどん少なくなっていく今のくるりはまさに「長距離ランナーの孤独」という状態かもしれない。しかし、作品がでるたびに、その作品に対峙し、丁寧に聞き込んでいるリスナーは数多くいるだろう。また真剣にアルバムに向かわせるほど、くるりの凝縮度は、今の日本のロックシーンにあって群をぬいている。今後どんな方向に向かおうと、誠実に創られたアルバムが創られる以上、それをきちんと受け止めるリスナーは存在し続けるだろう。
今回も佳曲が多い。その意味では『アンテナ』以降のストレートな曲調が、このアルバムでも引き続き生かされている。特にアルバムの最後に無理矢理押し込められたような「言葉はさんかく、こころは四角」は、単純だが、くるりの叙情性がいかんなく発揮された曲だ。「ブレーメン」や「ジュビリー」も、『NIKKI』に入っていてもおかしくない、盛り上がりどころを心得た楽曲になっている。また初期ルースターズのような「アナーキー・イン・ザ・ムジーク」や、東欧民謡といった風情の「スラヴ」のような曲も、いさぎよいほどストレートに、シンプルに曲が創られている。その意味では、途中で聞くのをやめたくなるほど極端ではなく、とにかく「まやかしのない楽曲」が並んでいる。ただ、コンセプト性はほとんど感じられない。だからCMソングになっても十分通用するのだ。
消費される音楽にどれだけ立ち向かえるか、くるりの果敢な挑戦にこれかも胸を躍らせていきたい。
 ノイズに満ちた音で癒される。このアルバムで構築される音の渦は、ノイズと呼んでいいだろう。そのノイズの渦に身を浸しながら、癒されれていく体験がこのアルバムにはある。それはどんな感覚だろうか。2曲目は「静かの海」。深海で砂が何らかの拍子にふと舞い上がるときのかすかな音は、きっとこのアルバムで聞かれるような音に違いない。それは音楽とはいえない、たんなる音のかたまり。しかしその音こそが癒しをもたらしてくれる。そんな雑音がちりばめられたこの「The world is mine」は、くるりの最高傑作である。ここまで音響、音の破片でしかないものが、ひとつの音楽に結晶するなど、いったいどんな力量があればできることなのだろう。
ノイズに満ちた音で癒される。このアルバムで構築される音の渦は、ノイズと呼んでいいだろう。そのノイズの渦に身を浸しながら、癒されれていく体験がこのアルバムにはある。それはどんな感覚だろうか。2曲目は「静かの海」。深海で砂が何らかの拍子にふと舞い上がるときのかすかな音は、きっとこのアルバムで聞かれるような音に違いない。それは音楽とはいえない、たんなる音のかたまり。しかしその音こそが癒しをもたらしてくれる。そんな雑音がちりばめられたこの「The world is mine」は、くるりの最高傑作である。ここまで音響、音の破片でしかないものが、ひとつの音楽に結晶するなど、いったいどんな力量があればできることなのだろう。
しかしこのアルバムが恐ろしいのは、極端に音数が少なくなる瞬間があることだ。「アマデウス」は、たとえいくつもの音が聞こえるとしても、印象に残るのは単調なピアノの音色とヴォーカルだけだ。そしてもう一つの特徴は、メロディとリズムの反復だ。「Buttersand/Pianorgan」や「Army」は、うねるノイズだけで構成されている楽曲だといえよう。
しかしそんなアルバムの印象も「水中モーター」あたりから、ロック色が強まっていく。「水中モーター」のヴォーカルはスチャダラパー的なアプローチといってもよいが、そうした雑食性もまたくるりの楽しさである。「男の子と女の子」は、ハナレグミもカバーしているが、あきれるほどめめしい曲だ。そんなロックのストレートさは、「Thank you my girl」で最高潮になる。そして再びアルバムは、「砂の星」、「Pearl river」を辿って、深海へ戻っていく。たゆたう水のうねりがゆったりとはてしなく円を描く。
このアルバムが最高傑作と言えるのは、どう頭をひねってもシングルカットできない曲ばかりならんでいるからだ。どの曲もこの音の流れから引きはがすことができない。それほどの緊張感をもって作り上げられたアルバムである。
 地方性を感じさせるミュージシャンがいる。くるりは京都の出身であり、様々な曲の京都を思わせる歌詞、ジャケットに使われる写真など、自分たちの故郷への執着を感じさせる。ただここではそのような地方への執着とは違う意味で、もう少し地方性ということを考えてみたい。
地方性を感じさせるミュージシャンがいる。くるりは京都の出身であり、様々な曲の京都を思わせる歌詞、ジャケットに使われる写真など、自分たちの故郷への執着を感じさせる。ただここではそのような地方への執着とは違う意味で、もう少し地方性ということを考えてみたい。
たとえば若き日の細野晴臣が、東京の自宅で舶来品に囲まれながら、銀座山野楽器で買ってきた最新の輸入盤を友人たちと聞きながら、曲をコピーするような都会性にたいして、音楽の情報といえばNHK-FMの番組しかなく、地元の県庁所在地に、一軒かろうじて輸入盤屋があるような地方性という意味ではない。くるりの世代であれば、そのような情報格差はもはやなかっただろう。ブリティッシュロックの30年を咀嚼しつくしたような楽曲を聴くだけで、彼らがおびただしい量の音楽に触れてきたことはすぐにわかる。
ここで考えたい地方性とは、東京へ出てきた人間が、地方の風土への感覚を、肌の感覚として忘れずに、自分たちの音楽へと組み込んでいく、その姿勢である。
このアルバムにおさめられている「東京」で、彼らはこんな風に歌う。
話は変わって今年の夏は暑くなさそう
あいかわらず季節には敏感にいたい
東京以西の人間からすると、東京ではよく三月に冬が戻ってきて、雪もちらつく風景をみることがあるが、そんな時に地方との差を肌で感じるような感覚である。自分の中はすでに春になっているのに、東京にいると、その肌に冷たい風がふいてきて、不意をうたれるような感覚である。
早く急がなきゃ飲み物を買いにいく
ついでにちょっと君にまた電話したくなった
日常の切れ端のなかで、かつての自分の生活の場所を思い出すようなスケッチである。東京での生活の中で、「ついで」でするようなこと、「忘れてしまって」思い出せないようなこと、それが、心を強く締めつける感覚。電話の世界は、きっとすでに遠い世界なのだろう。でもそれが切れ端の間から、ふと痛みをもって、戻ってくる。
岸田繁のこの曲でのヴォーカルは激しい。彼のすきっ歯から、絞り出されてくるだけに、いっそうその声は、切実さを帯びる。いったい彼の黒めがね、やせ細った頬、分厚くて紅い唇、そして歯並びの悪い口ほど、ロックっぽいものはあるだろうか。
そしてこの曲の最後のさびの「ぱ、ぱ、ぱっぱぱっぱ」というコーラスを聴くと、実に仲のよいバンドなのだと思ってしまう。
このファーストアルバムには、『アンテナ』以降ふりきった、屈折が痛ましいほど感じられる。でもくるりの最高傑作は『The world is mine』です。