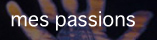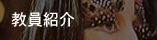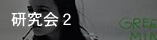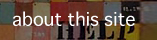Dylan, Bob
 「創造の瞬間」に立ち会えるアルバムである。Bootlegというものの、未完成の曲の集まりではない。アルバムテイクになる前の、曲が誕生した瞬間をおさめた貴重な録音がならぶ。単にアコースティックだから生々しいのではない。ディランが演奏をし、歌詞を口ずさむ。時代を越えて、まるで聞いている者がディランの創造の証言者になったような気にさせる、古びない記録がこのアルバムだ。
「創造の瞬間」に立ち会えるアルバムである。Bootlegというものの、未完成の曲の集まりではない。アルバムテイクになる前の、曲が誕生した瞬間をおさめた貴重な録音がならぶ。単にアコースティックだから生々しいのではない。ディランが演奏をし、歌詞を口ずさむ。時代を越えて、まるで聞いている者がディランの創造の証言者になったような気にさせる、古びない記録がこのアルバムだ。
特に63年から74年までをおさめた2枚目をよく聴く。のっけからもうすでにロックなディランが聞ける。Subterranean Homesick Bluesのたたみかけるディランの唱法やSitting On a Barbed wire Fenceのディランのぶっきらぼうな歌い方は、きわめて攻撃的で、65年の時点でロックが生まれていたことを実感する。It Takes a lot to laughに至っては、もろエレクトリックギター弾きまくりで、激しいロックサウンドになっている。驚くのはこうしたアウトテイクに「手探り感」がまったくないことだ。強い確信を持って演奏しながら、けっしてとどまることなく曲を創作してゆくディランは、若さといったエネルギーとは別種の強い創造力がやどっている。
そして後半にはThe Bandとの共演もおさめられていて、これがまたしぶい。けっして派手ではなく、じわじわと盛り上がってゆくところで、こちらも高揚させられる。このセッションもまた「創造の瞬間」だ。今、ここでしか生まれない音楽だ。
そして名盤『血の轍』からのアウトテイク。最後の曲はIdiot windだ。この曲もアルバムテイクとはかなり異なる。演奏とはそういうものだろう。コピーしたり、完成形をなぞったりするものではない。もう二度と同じ演奏はできないその鬼気迫るものがこのブートレッグシリーズにはある。
ディランの新譜にしても、ニール・ヤングのアーカイブにしても何種類もの仕様で出したり、あまりにもせせこましくないか。「これを聞け!」と堂々とリスナーに届けてもらいたいものである。それでこそこちらも真剣に音楽に対峙できるのだから。単なるコレクターのための、お蔵出しはやめてほしい。そこにはロックの研ぎすまされた緊張などありはしないのだから。
 ベースメントテープスの音源と同じ67年に収録されたこのアルバムは、音数も最小限で、曲も非常にシンプルである。しかし、きわめて豊かな深みをもったアルバムだと聞くたびに感じる。どの曲もほとんど2,3分で、4分を越える曲が1曲、5分を越える曲が1曲である。そんな小品が集められたこのアルバムだが、力を抑えている分だけメロディの美しさが際立つ。アルバムと同タイトルのJohn Wesley Hardingは、一聴してすぐに口ずさめてしまう親しみやすいメロディだ。激しいライブテイクのほうが印象に強い「見張塔からずっと」のオリジナルテイクは、各楽器の生の音が際立つきわめて簡素な曲だ。それでももちろんメロディの切迫感は、どれほど音がアコースティックでもひしひしと伝わってくる(ちなみにこの曲のベースラインは裸のラリーズの「何が欲しいときかれたら、紙切れだと答えよう〜」と似ている)。
ベースメントテープスの音源と同じ67年に収録されたこのアルバムは、音数も最小限で、曲も非常にシンプルである。しかし、きわめて豊かな深みをもったアルバムだと聞くたびに感じる。どの曲もほとんど2,3分で、4分を越える曲が1曲、5分を越える曲が1曲である。そんな小品が集められたこのアルバムだが、力を抑えている分だけメロディの美しさが際立つ。アルバムと同タイトルのJohn Wesley Hardingは、一聴してすぐに口ずさめてしまう親しみやすいメロディだ。激しいライブテイクのほうが印象に強い「見張塔からずっと」のオリジナルテイクは、各楽器の生の音が際立つきわめて簡素な曲だ。それでももちろんメロディの切迫感は、どれほど音がアコースティックでもひしひしと伝わってくる(ちなみにこの曲のベースラインは裸のラリーズの「何が欲しいときかれたら、紙切れだと答えよう〜」と似ている)。
そして同じメロディが繰り返される小品も多い。次の「フランキー・リーとジュダス・プリーストのバラッド」は、ほとんど単純なリフが繰り返されるだけだ。二人の登場人物を巡る寓話につけられた伴奏のようである。ちなみにこの曲だけが5分35秒と1曲だけ長い。
一番好きな曲はI pity the poor immigrantだ。3拍子の切ない美しいメロディの曲である。とても単純なメロディなのに激しく心を揺さぶられる。怒りや、激しい感情の起伏がなくとも、いやそうしたセンチメンタルさがないぶんだけ、ディランの声からは憐れみと悲惨がこぼれおちてくる。歌詞が難解なぶんだけ、明確なメッセージ性を感じることは難しい。だが、それゆえに、たとえば「笑いに満たされた口」、「彼の血でつくられた街」など、きわめて象徴性の高い比喩的形象によって、移民のあわれな物語が紡がれる。わずか4分で、一人の人生を語り、かつその世界を私たちに届けてしまうディランとは、ほんとうに優れた詩人なのだ。
 『血の轍』は、おそらくディランの数々の素晴らしいアルバムの中で、「歴史的名盤」、ロックの歴史を刻む記念碑的アルバムではないだろう。むしろきわめてプライベートな愛聴盤として、ごく個人的に孤独のうちに聴かれながら、実に多くの人々の心をとらえきたアルバムと言えるだろう。きわめて個人的な事柄が、大きな普遍性をもつ、その意味でこのアルバムは、名盤である。
『血の轍』は、おそらくディランの数々の素晴らしいアルバムの中で、「歴史的名盤」、ロックの歴史を刻む記念碑的アルバムではないだろう。むしろきわめてプライベートな愛聴盤として、ごく個人的に孤独のうちに聴かれながら、実に多くの人々の心をとらえきたアルバムと言えるだろう。きわめて個人的な事柄が、大きな普遍性をもつ、その意味でこのアルバムは、名盤である。
これだけ美しい曲が並んでいるのに、好きな女の子にあげる編集テープにはどの曲も入れられない。それがディランのヴォーカルの魅力。みうらじゅんが書いていたが、なんでこんなダミ声の唸るような歌が、心を引くのか。本当にそう思う。中学生のときに聴いたディランは、とにかく曲という体裁を感じられなくて、ブツブツ言っている感じがして、聴けなかった。
ディランをあらためて聴いたのは大学時代の先輩の最も好きな曲が、このアルバムにおさめられている、You're gonna make me lonesome, when you goとIf you see her, say helloだというのを知ったからだ。
このアルバムにはディラン自身の別離から始まる、喪失やあきらめや、人生へのまなざしといったものが痛々しいほど散りばめられている。
Simple Twist of Fate「運命がくるっと回る」とでも訳せばいいのか自信がないが、
彼が目をさますと 部屋はからっぽ
彼女はどこにもいなかった
彼はかまうことないと自分に言い聞かせ
窓を大きく開けて
空虚を中に感じた
それは彼がかかわることのできない
運命のひとひねり
朝目を覚ます。それは毎日訪れるささいな事柄だ。昨日とも明日とも変わらない。しかしそこではすでに運命がひとひねりしてしまっている。今日からは空虚なのだ。この喪失がこのアルバム全体を浸している。Lonesomeからsay helloまで心はどのような軌跡を描くのだろうか。それが描かれているのがこのアルバムである。
その軌跡とは「血の轍」である。心から血を流すディランの痛ましさが、ロックという音楽に乗って、同じ心を持つすべての人を訪れるのだ。
 アメリカ建国200周年を機に行なわれたライブツアー「ローリング・サンダー・レビュー」。旅芸人のように街から街を巡りながら、その日その日の音楽を奏でていく。同じ演奏は2度とできない。その瞬間、その場所で音楽が生まれていく。そんな音を切り取って収められたのがこのライブ・アルバム「Hard Rain」だ。このタイトル通り、とても激しい音楽である。といってもディストーションでひずんでいるとか、大音量で圧倒されるというわけではない。むしろそれぞれの楽器の音はひかえめでさえある。ギターはつまびかれ、ヴァイオリンの音は、哀愁を感じさせる。それでも激しいのは、ディランの魂の圧倒的な存在感、これにつきる。
アメリカ建国200周年を機に行なわれたライブツアー「ローリング・サンダー・レビュー」。旅芸人のように街から街を巡りながら、その日その日の音楽を奏でていく。同じ演奏は2度とできない。その瞬間、その場所で音楽が生まれていく。そんな音を切り取って収められたのがこのライブ・アルバム「Hard Rain」だ。このタイトル通り、とても激しい音楽である。といってもディストーションでひずんでいるとか、大音量で圧倒されるというわけではない。むしろそれぞれの楽器の音はひかえめでさえある。ギターはつまびかれ、ヴァイオリンの音は、哀愁を感じさせる。それでも激しいのは、ディランの魂の圧倒的な存在感、これにつきる。
ディランの歌声は、本能的な感情の叫びではない。それは、確信をもった魂のうなりだ。単なるその場だけの感情の爆発ではない、表現をしようとする魂の激しい動きが、そのまま声にのりうつる。
ディランの本質は、よく言われるようにアルバムではなく、ライブにあるのだが、それはこのレコードでも実感する。一曲目のギターのチューニングのような音を聞いているうちに、いきなり演奏が始まる。この唐突な始まり方に、鳥肌がたつ。そして例のごとく、原曲をとどめないアレンジに、この曲が Maggies' Farmだとはなかなか気づかない。この曲、ブレイクの仕方が最高にかっこいい。そして二曲目One Too Many Morningsは感傷的なようでいて、バンドの高揚感が激しいエネルギーを感じさせてくれる。そして三曲目The Memphis Blues Againは、サビの部分、ディランの声が虚空に響き、ゆっくり消えていく終わり方が最高です。四曲目はOh, sister.『欲望』収録の曲だが、張り詰めた空気の圧倒感で、こちらのライブバージョンのほうが断然いい、B面一曲目のShelter From The Stormはギターのかけ合いが最高、こんな生き生きしたナンバーを耳にしたら、踊り狂ってしまう・・・と、きりがないのだが、どの曲もその演奏のテンションの高さに驚かされる。『血の轍』と交互に聞きたいアルバム。そうでないと、こちらの緊張感がもたない。しかもどちらもLPで。
76年11月にはThe Bandのラスト・ワルツが行なわれている。このコンサートは、ロックの終焉とよく言われるが、このディランのツアーと重ね合わせれば、確かにロック・コンサートのもたらしてくれるユートピア幻想に決定的な終止符がうたれたのがこの時期であるというもうなづける。ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリンなど、ロックの伝説が死んでいくなか、残されたミュージシャンたちの苦しい模索が今後始まることになる。