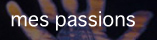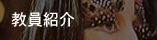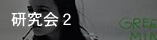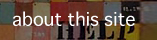2009年5月
 「創造の瞬間」に立ち会えるアルバムである。Bootlegというものの、未完成の曲の集まりではない。アルバムテイクになる前の、曲が誕生した瞬間をおさめた貴重な録音がならぶ。単にアコースティックだから生々しいのではない。ディランが演奏をし、歌詞を口ずさむ。時代を越えて、まるで聞いている者がディランの創造の証言者になったような気にさせる、古びない記録がこのアルバムだ。
「創造の瞬間」に立ち会えるアルバムである。Bootlegというものの、未完成の曲の集まりではない。アルバムテイクになる前の、曲が誕生した瞬間をおさめた貴重な録音がならぶ。単にアコースティックだから生々しいのではない。ディランが演奏をし、歌詞を口ずさむ。時代を越えて、まるで聞いている者がディランの創造の証言者になったような気にさせる、古びない記録がこのアルバムだ。
特に63年から74年までをおさめた2枚目をよく聴く。のっけからもうすでにロックなディランが聞ける。Subterranean Homesick Bluesのたたみかけるディランの唱法やSitting On a Barbed wire Fenceのディランのぶっきらぼうな歌い方は、きわめて攻撃的で、65年の時点でロックが生まれていたことを実感する。It Takes a lot to laughに至っては、もろエレクトリックギター弾きまくりで、激しいロックサウンドになっている。驚くのはこうしたアウトテイクに「手探り感」がまったくないことだ。強い確信を持って演奏しながら、けっしてとどまることなく曲を創作してゆくディランは、若さといったエネルギーとは別種の強い創造力がやどっている。
そして後半にはThe Bandとの共演もおさめられていて、これがまたしぶい。けっして派手ではなく、じわじわと盛り上がってゆくところで、こちらも高揚させられる。このセッションもまた「創造の瞬間」だ。今、ここでしか生まれない音楽だ。
そして名盤『血の轍』からのアウトテイク。最後の曲はIdiot windだ。この曲もアルバムテイクとはかなり異なる。演奏とはそういうものだろう。コピーしたり、完成形をなぞったりするものではない。もう二度と同じ演奏はできないその鬼気迫るものがこのブートレッグシリーズにはある。
ディランの新譜にしても、ニール・ヤングのアーカイブにしても何種類もの仕様で出したり、あまりにもせせこましくないか。「これを聞け!」と堂々とリスナーに届けてもらいたいものである。それでこそこちらも真剣に音楽に対峙できるのだから。単なるコレクターのための、お蔵出しはやめてほしい。そこにはロックの研ぎすまされた緊張などありはしないのだから。
 Tétéの3枚目にして、代表作といえるアルバム。1stのビートルズ、ボブ・マーリーに触発されたフォーク・ロックを聞いたときに、フランスにもついに野暮ったさとは無縁のロック・ミュージシャンが現れたと感動した。セネガルで生まれ、その後すぐにフランスへ。そのせいかアフリカを背景に感じさせるものはなく、かといってフランスの音楽の影響もない。そんな無国籍のなかで育まれたのがTétéのロックだ。とはいえ、とくにボブ・マーリーの影響は明らかで、たとえ彼のRedemption songが最高の1曲だといっても、それは素直なオマージュ、レスペクトにとどまっていた。
Tétéの3枚目にして、代表作といえるアルバム。1stのビートルズ、ボブ・マーリーに触発されたフォーク・ロックを聞いたときに、フランスにもついに野暮ったさとは無縁のロック・ミュージシャンが現れたと感動した。セネガルで生まれ、その後すぐにフランスへ。そのせいかアフリカを背景に感じさせるものはなく、かといってフランスの音楽の影響もない。そんな無国籍のなかで育まれたのがTétéのロックだ。とはいえ、とくにボブ・マーリーの影響は明らかで、たとえ彼のRedemption songが最高の1曲だといっても、それは素直なオマージュ、レスペクトにとどまっていた。
2枚目は、叙情性のあふれる美しいアルバムである。メランコリックで繊細なTétéのよさが出ている。とはいえトータルなコンセプト性は薄く、「よい曲を並べました」という印象が強い。
だが、この3枚目はアルバム全体を貫くコンセプトが明快であり、ついにミュージシャンがアーティストになったと確信させる傑作となった。「レミングの朝明け」で幕が開け、「レミングの夕暮れ」で幕が閉じられるまで、ひとつの色調で曲が成り立っている。その色調とは、「悲喜劇」だ。喜びのなかにある悲しみ、ペーソス感といおうか。単に叙情性に流れないドラマがどの曲にもある。そのためどの曲も3分かせいぜい4分なのに、十分聞きごたえがある。
Fils de ChamやLa Relanceで聞けるとぼけた雰囲気のなかに哀れみを感じさせるようなメロディはTétéにしか作れないオリジナリティあふれるものだ。Madeleine Bas-de-LaineやCaroline On yeah Heyは、Tétéらしい繊細かつポップなメロディが美しい佳曲。そしてComme Feuillets au ventのように懐かしさやせつなさを感じさせる美しいメロディ。またA la vie à la mort、A Flanc de Certitudes、Mon Trésorのようなジプシーとは言わないが、昔の民衆歌謡を彷彿とさせる曲もある。
このように書くと、きわめてバラエティに富んだ印象もうけるが、Tétéの曲にはどれにも単純にはわりきれない情感の豊かさを感じる。その情感の起伏に今回のアルバムでは特にストリングスなどのオーケストラをバックとして、奥行きが与えられている。
アフリカ、パリ、モントリオール。Corneilleはそうした旅を余儀なくされた人物であるが、彼の音楽は素直なほど、アメリカのソウルの文脈に忠実である。それに対してTétéは同じように音楽の旅を続けながら、そしてどんよくに様々な音楽を吸収しながら、やがて彼にしか作れない、豊かな叙情の音楽へと至った。その美しく細いヴォーカル、決してわかりやすくはないが随所に感じられるユーモアセンスや寓話性に満ちた歌詞、そして最初からTétéの才能を決定づけていたメロディの美しさ、それらをすべて含みこんだうえで、出来上がったのがこのサードアルバムである。
 「オブラートにつつんだ」声と言おうか。ハナレグミの魅力はその少しだけハスキーで、少しだけ鼻にぬけるような、ノスタルジックな気分にさせる声だ。肩肘をはらず、ジャケットのようなギターの弾き語りを中心につくったアルバムは、とてもパーソナルで、大上段にかまえたところがない。ロックがもっていた批判精神のようなものはすっかり抜け落ちている。その代わりここで描かれるのは、日常へのオマージュだ。CMにも使われた「家族の風景」は、まさにそうしたパーソナルで、普段の生活の風景を描いている。ハイライトとウイスキー。
「オブラートにつつんだ」声と言おうか。ハナレグミの魅力はその少しだけハスキーで、少しだけ鼻にぬけるような、ノスタルジックな気分にさせる声だ。肩肘をはらず、ジャケットのようなギターの弾き語りを中心につくったアルバムは、とてもパーソナルで、大上段にかまえたところがない。ロックがもっていた批判精神のようなものはすっかり抜け落ちている。その代わりここで描かれるのは、日常へのオマージュだ。CMにも使われた「家族の風景」は、まさにそうしたパーソナルで、普段の生活の風景を描いている。ハイライトとウイスキー。
アレンジもきわめてひかえめで、楽器の木のぬくもりがするような音作りだ。レゲエやスカのリズムはあまりにもあっけらかんとしすぎであるが、それは愛嬌ということで受け流しておこう。そうしたちょっとはずかしいアプローチは3枚目の『帰ってから歌いたくなってもいいようにと思ったのだ』ではすっかり消えてしまい、アルバムの完成度としてはこちらのほうが高いだろう。ハナレグミ節が十分満喫できて、ゆとりさえ感じられるし、「催促嬢」のようなふざけた曲も十分楽しめる。それに比べれば『音タイム』はあまりにも素直すぎる曲が多い。でもそれでも歌いたいことがいっぱいあったのだろう。そんな音楽への愛着と衝動が感じられる若いアルバムだ。
そしてなによりもこのアルバムには前述の「家族の風景」が収められている。この一曲がはいっているだけで「買い」だ。(ただ、やはり聞き比べると『帰ってから〜』はやっぱり充実している。くるりの「男の子と女の子」、ラブソング「僕は君じゃないから」、単純な弾き語りだけどメロディが印象に残る「かえる」、「おまえはポールか」とちゃちゃを入れたくなる「ハナレイ ハマベイ」など。う〜ん、やっぱり3枚目を推します)。
『喪の日記』と題されたRoland Barthesの遺稿は、母の死の翌日から書き留められた日々の断章からなる。これらの断章は、330枚のカードに書かれて残されていた。Barthesの著作には頻繁に断章形式が用いられるとはいえ、この日記はそうした作品群に属するものですらなく、日記というよりも、むしろ「覚書」と言った方がよいだろう。いずれはこの断片から、喪についての作品が生まれるはずであったのだろうか。
日々の覚書は、ときに文ですらなく、単語が並べられただけの脈絡のない時もある。それらの単語は、自らの意味を見出すことなく、ただ母の永遠の不在のまわりにただようだけだ。ことばを「言う」ことはできる。しかし「表現」することはできない。それが実は喪の証しとなる。表現できるならば、それは「文学をする」こと、母を文学として語ることになってしまう。それはBarthesにとってはこの上ない恐れである(p.33.)。そもそも言葉にすることは不毛なのだ(l'insignifiance de notre verbalisation, p.260.)。
しかし、それでも記憶をとどめるものとしてBarthesは日記を書く。
Barthesはdeuilをnévroseという病理の状態と峻別する。フロイト自身はdeuilとmélancolieを分け、むしろ後者を病理的な症状とみなしているわけだが、それにもかかわらずBarthesは、フロイトを念頭においたうえで、deuilという言い方はあまりにも精神分析的だと言う(p.83.)。すでに『恋愛のディスクール』において、«Cette tristesse n'est pas une mélancolie»「この悲しみは鬱ではない」という文章に出会うが、日記の中でも喪の病理性は否定される。「母が生きていたときのほうが、母を失うおそれのあまり精神症にかかっていた」。そして「むしろ喪は、それゆえに神経症ではないのだ。むしろ母の死は、そうした病理を遠くへと追いやってしまったのだ」(p.140.)と。つまり喪は精神分析の対象にはなりえない、それがフロイトへの違和感の表明となって現れているのだ。
だが同時に喪が病でないということは、それは治癒できる対象ではないということだ。やはり『恋愛のディスクール』において、喪は「治癒」という進歩的なものではないと言われている。喪とは回復するものではないのだ(p.18.)。もし人間存在、人間の生の根拠が、可変可能性であるならば(人間は変わってゆく存在である)、喪の苦しみがやまないということは、「変わりはしない」という意味で、その人間が死んでいるというのに等しい。
他者の死は、自己の生を無化していまう。Barthesは言う。「愛していた人が死んだあとも生き続けるとは、思っていたほどその人のことを愛していなかったということだろうか」(p.78)。喪とは死者への後悔の念でもある。もしかしたら自分が思っていたほど愛していなかったかも知れないとは、それは死者への取り返しのつかない後悔となる。
先ほど述べたようにBarthesにとっては喪ということばは、自己の内面を「表現」することばとはならない。彼が何度も用いることばはchagrin「悲しみ」である。Chagrinと対立することばとして、やはり何度も現れるのがémotionである。
Chagrinとémotionはどう異なるのか。Émotionとは、自らの身体における動きであり、反応である以上、身体は受け身の状態にある。またそれは刺激である以上、ある緊張を強いたあとは、鎮まってゆき、また私たちを襲うような現象であろう。しかしchagrinは鎮まりはしない。「悲しみはすり減らない」のだ(P.81.)
その喪とは他者には見えないものだ。その人がどのような悲しみの淵にいるとしても、その悲しみを抑えて人は生きる。Barthesはいう「もっとヒステリックになって、沈鬱な表情を見せて、みなを追い返し、社会のなかで生きるのをやめてしまえば、私はそれほど不幸ではなかっただろう」(p.139.)それでも喪は内に秘められれば、それを示す外的な指標はない。
Au deuil intériorisé, il n'y a guère de signes.C'est l'accomplissement de l'intériorité absolue. Toutes les sociétés sages, cependant, ont prescrit et codifié l'extériorisation du deuil. Malaise de la nôtre en ce qu'elle nie le deuil.
社会は人々にその喪を外の表現することを、一定の儀式にのっとって喪を外に表現することで、喪の作業を遂行し、そこから回復することを強いるのだ。だから社会は喪を否定する。
ここに集められた断片は「覚書」に近い。だが、やはり覚書ではなく日記であるのは、これが日々の記録、その日のうちに書き留められたであろう記録であることだ。その集積の意味は、喪は決して終わらないということである。昨日と今日は違う一日だ。しかしそれでも今日も悲しみに浸される。日記とは終わらない喪である。
 深夜にすっかり酔っぱらっているのに、まだまだウイスキーを飲みたいときに聞きたいもっとも最高のバンドといえば、もうこのフェイシズ以外には考えられない。なぜロニー・レインのしぶい曲をここまでロッドが歌い込めるのか。その一点だけでロッドは天才ヴォーカリストだ。と同時に、不器用な連中のなかにあって、ロッドだけがスター街道を歩めたのはいったいなぜなんだろうという疑問もわく。バンドの仲が悪かろうと、ぐだぐだだろうと、こうしてレコードに刻まれた音は、このバンドが最高に「イカしたイカれたバンド」だとわかる。
深夜にすっかり酔っぱらっているのに、まだまだウイスキーを飲みたいときに聞きたいもっとも最高のバンドといえば、もうこのフェイシズ以外には考えられない。なぜロニー・レインのしぶい曲をここまでロッドが歌い込めるのか。その一点だけでロッドは天才ヴォーカリストだ。と同時に、不器用な連中のなかにあって、ロッドだけがスター街道を歩めたのはいったいなぜなんだろうという疑問もわく。バンドの仲が悪かろうと、ぐだぐだだろうと、こうしてレコードに刻まれた音は、このバンドが最高に「イカしたイカれたバンド」だとわかる。
一曲目のひずんではじけたギターのリフがまず最高。ロッドの疾走感あふれるヴォーカルにおもわずこちらもシャウトしたくなるご機嫌な一曲。さらにファンキーなオルガンとスライドギターが重なり、聞き所が多い。そして二曲目は、Ronnie Laneの名曲Tell Everyone。この曲のTo wake up with you / Makes my morning so brightという何の変哲もない歌詞がなぜだかLaneの心持ちを表している気がしてとっても好きだ。三曲目はロッドの泣き泣きのヴォーカルに思わずしんみりしてしまう佳曲。四曲目はLaneのヴォーカルによる家畜の匂いただようほのぼのカントリーソングだ。
B面の一曲目も適度にひずんだギターから始まり、そこにピアノが重なってくる始まり方がまたまたかっこいい。しかもサビの部分のロッドのシャウトの濃密感がたまらない。その勢いがそのままピアノやブラスバンドへ流れこむ展開に実に圧倒される。そして最後はRonnie Woodのボトルネックギターに聞き惚れながら、アルバムが終わり、完全にボトルが空になる。
ライブが二曲収められていたり、アルバムのトータル感などあっさり無視しているかのように、雑多な曲が並んでいるが、でも楽器をもたせたら最高の連中がそろい、しかもそこにロッドがヴォーカルをとるわけだから、これはもう無敵です。