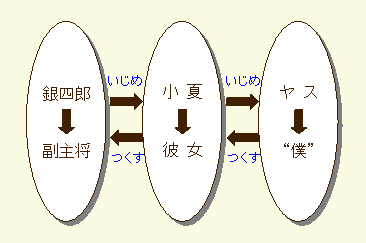|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4−2.長時間プレイへの回答 “僕”はどうすればいいのか。それは、蒲田行進曲をモデルとして採用することです。下のようなキャスティングにもっていけば、“僕”には愛がみえてくるはずです。
“僕”が彼女との関係においてヤスと同様の演技をしていることは明らかです。彼女の“僕”にたいするいじめは、小夏以上だといえるでしょう。では、彼女と副主将の関係はどうでしょうか。この関係については、「愛する人の美点を語る」ところから推測すると、彼女が副主将のことを熱っぽく語っている分だけ、副主将と彼女の間にも『いじめ/つくす』の関係がかなり色濃くあると予想されます。とすると、この三人の関係に蒲田行進曲のトリアド・モデルと同型の構造があると断定してもよい、といえましょう。 このような前提に立脚して、愛のシナリオを考えてみましょう。まず最大のテーマは、『階段落ち』に対応する芸を“僕”がやってみせることができるか、です。できたら、“僕”と彼女と副主将の愛の絆は、いままで以上に強まっていくことでしょう。 そこで、彼女が提案してきた『長時間プレイ』は、“僕”にとって不幸ではあっても、絶好のチャンスである、という認識が必要です。なぜかというと、『長時間プレイ』は『階段落ち』に相当する凄い至難技だからです。彼女は“僕”に死と再生を期待して、この至難技に挑戦することを求めてきたのです。『階段落ち』が死(“いじめ”が“つくす”を制御)と再生(“つくす”が“いじめ”を超越)の物語であるように、長時間プレイも同様の物語を構成しているのです。 もう一つのテーマは、副主将と彼女の関係を、銀四郎と小夏の関係に近づけることです。現状では、その辺の事情がいまいちはっきりしていません。ですから、副主将が彼女を明確にいじめるような状況を創出することが肝心でしょう。この点にかんしては、蒲田行進曲では、銀四郎のライバルに橘さん(正確には、ライバルというよりも、銀四郎以上の大スター。しかも若い)がいて、かれによって、銀四郎が暗にいじめられるという構図が背景にあったことを参考にしてシナリオを考えることにしましょう。 《シーン1》:“僕”、喜んでプレイを始める “いじめ”と“つくす”の関係である以上、“僕”にとって彼女に逆らうなんてタブーです。“僕”に相応しい演技は彼女のいかなる提案をも喜んで受け入れるポーズです。当然、それは底抜けの明るさをもった喜びではありません。いじめられる男が、あなたのためなら喜んで何でもします、という必死だけど滑稽な決意を示したポーズなのです。だから、“僕”は、心では「彼女にすがって、こんなゲームは止めて、と泣き叫んでいる」のに、演技としては進んでプレイの執行を迫ってみせるのです。自ら不幸を背負うことで、“僕”はこの状況を劇的な空間へと変換させなければなりません。こうやって、『長時間プレイは死のドラマである』ことを、彼女に認識させることがファースト・シーンでのテーマなのです。 そこで、このシーンではつぎのような展開が想定できます。
あっというまに彼女は消えていき、残った僕は眼に涙を一杯にためて、ただ呆然と彼女のいなくなったあとをみつめるのです。そのつらい思いは消えた彼女のハートにチクリとでもいいから伝わるのでしょうか。 いじめが極限に近づくほど、いじめられる方はつくす状況を最適なものにもっていかなければいけません。だから、プレイの開始を引き延ばすようなことはやってはいけません。即座に、やります、と決断することが、劇的な空間を創出するのです。彼女は、その時、“僕”を捨てる演技に最高の快感を覚えるはずです。 《シーン2》:ボロボロになった“僕”、野球部に入る “僕”はかぎりなく死に近づかなければいけません。彼女に逢えない辛さを表現するために、食事をとらない(拒食症っぼく)→やせる→やつれる→身も心もボロボロになる、といった一連の演技をしなければなりません。そして、学校で彼女に不意に出会った時には、すぐに逃げなければいけません。逃げることで、プレイがまだ継続中であることを彼女に知らせなければいけません。もしも彼女が“僕”を捨てたと勘違いでもしたら、芝居は台無しですから、そのためにも、ボロボロになった“僕”をチラッとみせるテクニックをマスターしなければなりません。 つぎに“僕”は、野球部に入らなければいけません。そこで、副主将にしごいてもらうことが肝心です。「オラオラ、なにやってんだ、そんなへっぴり腰で球がとれるか」といったいじめをしてもらいましょう。しかも、その光景を彼女がじっと影から見つめているような舞台を設定することが重要です。もちろん、彼女は副主将にうっとりするだけで、“僕”など眼中にありません。ふと、気がつくと、“僕”がいじめられているのが分かった、といった程度の認知で充分です。ここでは、副主将のいじめのパワーを増進させることがテーマなのです。これで、“僕”と副主将にかんする舞台の準備は整いました。 さて、副主将と彼女にかんしてですが、副主将が彼女をいじめにかかってくれないと困るので、副主将に『蒲田行進曲』をプレゼントして歴史研究会の研究課題に取り上げてもらうことにしましょう。“新撰組をめぐる愛の構造”といったテーマなんかいいのではないでしょうか。そうすれば、優秀な副主将は自分と彼女と“僕”の関係がどのような構造になっているか、を察知するはずです。愛の価値は、トリアド・モデルの『いじめ/つくす』関係によって実現されるものであり、安直なダイアド・モデルの『やさしさ』の相互依存関係なんかは陳腐だということに気づくことでしょう。その時、副主将は“僕”がなぜ今頃になって野球部に入部したかを理解するはずです。 副主将は、いじめの意味を悟ります。いじめは、壊れやすい愛の絆をしっかりと保つために、現代社会に残された唯一の表現方法であることを、彼は本質的に直感します。なぜいじめるのか、それは強い者が弱い者との関係で、弱い者を捨てることなく関係を継続させる唯一の救済手段であり、愛のメソドロジーなのです。 すべての事情が理解できた副主将は、彼女にも、そして“僕”にも、強烈ないじめを展開します。“僕”は野球部でしごかれるほど、彼の愛の深さに感動します。そして彼女は、そのような愛の構造が読めないために、副主将の、突然でしかもキツイいじめに、不安な眼差しになります。 《シーン3》:いじめが過激になって、“僕”は道化になった 最初のうち、彼女は、“僕”が野球部に入ったのは、彼女に長時間プレイでいじめられ、それを忘れるためだ、と誤解するはずです。でも、すべてを理解した副主将が“僕”を野球で異様なまでにしごく時、彼女のなかにも何か得体のしれないエイリアンが忍び込み、“僕”を捨ててほっとしていた気持ちに異変が生じます。“僕”と副主将のいじめ関係をみつめるほど、彼女には、“捨てる”のではなく、“いじめ”なのだ、という意識が明確になってきます。やっと彼女のハートにも、愛は“いじめ”にしかない、という真実が浸透しはじめます。 副主将がいじめの意味を理解したのは、“僕”との関係だけではありません。実は、強力なライバルが転校してきたんです。そいつは、転校してくるとすぐに「ネットワーク理論研究会」を創設し、そしてサッカー部に入り、そのあまりにも高度なテクニックのためにすぐに主将の地位を移譲された、という偉才なのです。副主将には、かなりショックだったようです。オールマイティは自分だけだと確信していたのに、それ以上の奴が出現したのですから。 周りの人は、副主将の“僕”へのいじめは、ライバル出現のための憂さ晴らしだと噂していますが、真実はそんな単純なものではないことはもう理解されていることでしょう。副主将は、ライバルの出現によって、愛の価値に目覚めたのです。 そのために副主将は、“僕”だけでなく、彼女を過激にいじめ始めました。彼女の手造りの愛情弁当に、昔は「おいしい」を連発していたのに、最近はいつも難癖をつけて、ひどい時(それは、“僕”が視界に入っている場合)には、弁当を彼女の顔に投げつけ、「こんな弁当ならホカホカ亭のノリ弁当のほうがましだ」なんて言うんです。“僕”のほうがいたたまれなくなります。でも、彼女はじっと耐えて、つくします。 つくすことが、今度は“僕”へのいじめになって返ってきます。もちろん長時間プレイの最中ですから、逢うのではなく、接触によって“僕”をいじめにかかります。“僕”が廊下を歩いていると、彼女が後ろから走ってきて、いきなりバットで頭を殴ってきます。「ギャッー」と叫ぶと、「アラ、当たった?ごめんなさい」とだけ言って消えていきます。またこの間なんかは、電話をデタラメな名前でかけてきて、「テレフォン・セックス」の真似をするんです。この時だけは、“僕”も悩みました。電話の主が彼女であることは、お互い暗黙に理解しているうえでのことですから…。“僕”は、「テレフォン・セックス」を拒否すれば、彼女を馬鹿にしたことになるし、かといって一緒になって楽しんだら、「あなたは、誰とでもヤルのね」ということで、これまた彼女を馬鹿にしたことになります。まったくもう、完全にダブル・バインドです。これぞ袋小路のどんづまりです。 それでどうしたかって、いうんですか。逃げるしかないじゃーありませんか。とっさに“僕”は留守番電話になって、「コレハ留守番電話デス、ゴ用ノ方ハ、“ピー”トイウ音ノアトニ、ゴ用件ヲオ話シクダサイ。ノチホドコチラカラオ電話ヲサシアゲマス、“ピー”………」ですよ。 《シーン4》:愛の価値に向かって “僕”はピエロです。何をやってもドジばかりです。副主将にいじめれても、一向にうまくなりません。“僕”のトンネルがあまりにも見事すぎて、見ている補欠達もつい笑いだしてしまいます。真面目に歯をくいしばって球を追い掛けるほど、“僕”の姿はマンガになってしまうようです。“僕”は生まれながらの道化なんでしょう。そのためか、いま“僕”は仲間から『(長嶋)一茂ちゃん』と呼ばれています。そう呼ばれて喜ぶ“僕”は、やはりおかしいでしょうか。 もしも“僕”にもいじめることができる女の子がいたら、その子をいじめていたでしょう。それは、いじめの無限連鎖講です。でも、幸いなことに、いじめは“僕”のところで歩詰まりです。ですから、みんなからのいじめのパワーを一人で受け止めなければなれません。その場合方法は、“道化になる”しかありません。みんなのいじめを笑って受け止める芝居に徹する場合にのみ、いじめ連鎖講は、単純な強者と弱者の関係(=ゲーム)を超越して、価値(=愛)を実現するための絆へと、その道を開くのです。 そして《再生の物語》が始まります。 クライマックスは、“僕”が野球の試合に代打で出場する場面です。その日、いつものレギュラー達が食中毒をおこしてばたばたと倒れ、ついに“僕”が、九回裏二死満塁9対9同点の場面で代打に出場することになりました。副主将一人で自軍の8点を叩き出し頑張っていますが、この場面では“僕”に頼るしかありません。副主将は言います「打たなかったら、どうなるか分かってるだろうな。これですべてが終わるぞ」。“僕”も必死でした。彼女が応援(当然、副主将の応援ですが)に来ているのに、ここで無様な格好はできないと真剣になりました。なのに、みんなは「一茂ちゃーん」と応援します。真面目な顔が緩むのが自分でも分かりました。すぐに思い直し、バッターボックスに入りました。一球目、空振り。二球目、また空振り。これで相手ピッチャーは安心しきって、ニャッとほくそ笑みながら次の球を投げました。 ボコッと音がし、気がついたら、“僕”はベンチで寝ていました。試合はサヨナラで勝ちました。劇的なデットボールで、“僕”は勝利の女神になりました。こうして、三人の愛の絆は一気に強くなりました。彼女は、長時間プレイをまだしっかり守ってくれています。“僕”は毎日充実した日々をおくっています。 物語はいつも劇的でなければなりません。しかも“僕”の芝居は、ドジで間抜けで、でも同時にひた向きで一途な道化でなければなりません。道化であることが、ダブル・バインドな状況を一挙に乗り越える力をもたらすのです。 さてこれでおしまい、です。ゲームの達人のような結論にはなっていません。戦略的な思考ではなく、物語の思考でシナリオを描くとき、どのような世界になるかを示してみました。“僕”には、参考になったでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||