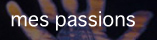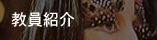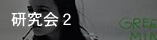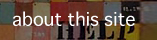mes passion
 往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
そうした最高度のテンションで、バンドの音を作り上げるようなロックがあるとするならば、Aimee Mannのこのアルバムはおよそそうした創作の仕方とは対極にあるものだろう。このアルバムは決して「偶然の産物」ではない。丁寧に織り上げられたハンド・メイドの肌触りがあるアルバムだ。これだけポップな曲作りをしていながらも、安易な既製品の音はまったく聴かれない。こうした仕事にはいったいどのくらい時間がかかるのかわからないが、音楽にまっすぐに対峙して、丹誠をこめて作られた曲が並んでいる。
これだけポピュラーな音作りをしていながら、なぜ平板な音にならないのだろうか?たとえばReal Bad Newsのアレンジは、夫Michael Penのアルバムにも似てとても深みがあるエコーの音で、けっこう不思議な音色だ。Pavlov's Bellのギターソロは、これだけ聞くと、曲の憂うつな感じとはそぐわない結構派手な音なのに、曲の中では違和感がない。そしてInvisible Inkの慎ましやかなヴォーカルに重ねられる控えめなストリングス・・・どの曲も実によく練り上げられたプロの音だ。Aimee Mannのヴォーカルを一切邪魔することなく、いやそれどころか単に美声で歌われるだけのなじみやすいメロディでは終わらない、聞き込めば聞き込むほど、全体のカラーが浮かんでくるコンセプトのしっかりしたアルバムに仕上がっていることがわかる。もちろんAimeeのヴォーカルの表現力もすばらしい。 This is How It goesのようなヴォーカルが全面に出ている曲での、彼女の抑揚の効いた歌い方は、とても地味なのだが、聞き終わった瞬間から、心の中で彼女の声が再生し始めるような印象深い歌い方だ。Pavlov's〜のOh Mario, という歌いだしなど、ほんとうにぞくぞくする。
なぜこんな音作りができるのだろう。それはやはりこのアルバムがソロ・アルバムではなく、バックミュージションとの共同作業によって作られたことが大きいのだろう。しかしそれが仲間内の楽しみに終わらないところが、Aimee Mannというミュージシャンの職人芸のなせるわざなのだろう。どこにもあるようでいて、実はどこでも得られないような、コマーシャルに十分なれるのに、安易な使い回しの手法は一切ないというストイックさに貫かれているアルバムだ。この作品は上質なポップアルバムとして、年を経ても聞き継がれていくであろう名盤である。
 Ryan Adamsの在籍したWhiskey Townのセカンドアルバムがデラックスエディッションで再発になった。オルタナ・カントリーと言われる彼らの音楽だが、聞いていて感じるのは若さゆえの、破裂感を持ったと言おうか、結構パンキッシュな曲が多いのに驚く。この青々しさを聞いていると、Byrds〜Gram Personsというより、ニュー・ウェーブの動きを作り上げていった、あるいは、その中から生まれてきた、Big Star, dB's、Feeliesなどの、熱さの中にもどこか醒めてしまったバンドの音がむしろ浮かんでくる。だからBurn's on fire sessionsのプロデューサーに、元dB'sのChris Stamyの名前があることにとても納得がいく。
Ryan Adamsの在籍したWhiskey Townのセカンドアルバムがデラックスエディッションで再発になった。オルタナ・カントリーと言われる彼らの音楽だが、聞いていて感じるのは若さゆえの、破裂感を持ったと言おうか、結構パンキッシュな曲が多いのに驚く。この青々しさを聞いていると、Byrds〜Gram Personsというより、ニュー・ウェーブの動きを作り上げていった、あるいは、その中から生まれてきた、Big Star, dB's、Feeliesなどの、熱さの中にもどこか醒めてしまったバンドの音がむしろ浮かんでくる。だからBurn's on fire sessionsのプロデューサーに、元dB'sのChris Stamyの名前があることにとても納得がいく。
屈折したというほどニヒルではなく、情熱を向けるほどの希望への確信もない。そんな中途半端なやるせなさが、いろんな曲調で表現されたのが本作ではないだろうか。喜びや怒りといった単純な感情に流されることもできなくなってしまったアメリカの若者の心理を知るためには、もっとアメリカの時代思潮を考えた上で捉え返してみる必要があるのだろう。そうすればREMなどとつながる線もみえてくるかもしれない。
Ryanのアルバムを聞いていてうれしいのは、突然、今まで聞いたこともない美しい曲に出会えることだ。もう何十年も音楽を聞き続けているはずなのに、Ryanの曲にはいつも新鮮な発見がある。様々なバックボーンを感じさせながらも、新しく瑞々しい体験をさせてくれる、これこそRyan Adamsが天才的とよべる証拠ではないだろうか・・・
 Paul Simonのソロ作品は、ワールド・ミュージックの剽窃だなどとよく言われたせいか、自分の中でも、安易なミュージシャンというイメージがずっと残っていた。それはピーター・ガブリエルが、同じくワールド・ミュージックの文脈に依拠しながらも、それをスタジオ・ワークによって高度に再構築してみせたアルバムを出していただけに、Paul Simonのアルバムは、ろくに聞いたこともないのに、素人くさいものと思ってしまっていた。
Paul Simonのソロ作品は、ワールド・ミュージックの剽窃だなどとよく言われたせいか、自分の中でも、安易なミュージシャンというイメージがずっと残っていた。それはピーター・ガブリエルが、同じくワールド・ミュージックの文脈に依拠しながらも、それをスタジオ・ワークによって高度に再構築してみせたアルバムを出していただけに、Paul Simonのアルバムは、ろくに聞いたこともないのに、素人くさいものと思ってしまっていた。
今回この実質ソロ2作目を初めて聞いてみて、Paul Simonの仕事の根幹には、良い意味でも悪い意味でも、「アメリカ」をどう歌い込むかという問いがあると感じた。そして、それらを飾るアレンジはまさに飾りでしかないと。
1993年12月号の『レコード・コレクターズ』で高橋健太郎は次のように書いている。
「ただし音楽的にそのような要素を取り入れても(レゲエやゴスペルコーラスなど)、サイモンのアプローチにどこか醒めた距離感があり、ニューヨークのインテリが作り上げた文学的、あるいは映画的な作品であることを逸脱しない」
つまりどのような他者の音楽に触れようと、結局出来上がった作品は、アメリカのポップ・エッセンスをセンスよく取り込んだものになっている。ゴスペルやカリプソがあったてもそれは、ゴスペル「風」、カリプソ「風」であって、趣味の範疇をでるものではない。そしてこのアルバムには、永遠に歌い継がれるだろうポップソングが、上質なアレンジでもっておさめられている。それは4曲目のSomething so right、そして6曲目のAmerican tuneだ。この2曲に代表される質の高いポップスこそ、このアルバムの通底音ではないだろうか。「明日に架ける橋」ほど大げさではない。 American tuneで歌われるアメリカは、mistaken, confusedといった言葉に象徴されるような疲弊したアメリカである。しかしそれでもtomorrow's going to be another working dayと歌われるように明日がやってくる。このささやかさがこのアルバムをつくったときのPaul Simonの気持ちではないだろうか。
だからこのアルバムは奔放な音楽探究の旅とは到底言い難く、たとえば自分の子供のためにつくった子守唄、St Judy's cometが、Paul Simonのプライベートな心情をつづっているように、パーソナルな小品をまさにアルバムジャケットの様々なオブジェのように集めたイメージが強い。 Something〜も、パートナーにあてた感謝の気持ちをこめたラブソングだ。このように自分の生活に向き合っている姿を素直に眺めれば、様々な音の意匠はまさに飾りで、そこには音楽を丹念に生み続けるひとりの才能あるアメリカの音楽家の姿が浮かび上がってくるのではないか。イギリスにPaul McCartneyがいるように、アメリカにはこのPaul Simonがいる。そして何よりもこの2人のポールの曲は思わず口ずさみたくなるほど、親しみがあり、それでいてきらめくほど美しい。
ところで、06年の紙ジャケにはボーナストラックがはいっているが、これが最高によい。あらゆる意匠をとりさった、原曲だけが歌われている。
 まず耳をうつのは、何年にもわたって使い込まれたと感じさせる、素朴だけれども味わいの深い楽器の音色だろうか。日本盤ライナーにあるように、プロデューサーのチャド・ブレイク、そしてレコーディングに参加しているミッチェル・フレームのコンビといえば、ロン・セクススミスでの仕事が思い浮かぶ。たとえば 5曲目、Never Yoursのアコースティック・ギターのエコー処理、同じリフが浮遊感をもってくりかえされるところなど、同じ空気を共有しているといってよいだろう。弦楽器の弦がゆっくり指ではじかれる響きや、パーカッションの鉢が太鼓の表面をかすめる響きが、丁寧に掬い取られて、やがて少しずつ消えていく、そんな一音のはかなさにまで気を使った音作りである。
まず耳をうつのは、何年にもわたって使い込まれたと感じさせる、素朴だけれども味わいの深い楽器の音色だろうか。日本盤ライナーにあるように、プロデューサーのチャド・ブレイク、そしてレコーディングに参加しているミッチェル・フレームのコンビといえば、ロン・セクススミスでの仕事が思い浮かぶ。たとえば 5曲目、Never Yoursのアコースティック・ギターのエコー処理、同じリフが浮遊感をもってくりかえされるところなど、同じ空気を共有しているといってよいだろう。弦楽器の弦がゆっくり指ではじかれる響きや、パーカッションの鉢が太鼓の表面をかすめる響きが、丁寧に掬い取られて、やがて少しずつ消えていく、そんな一音のはかなさにまで気を使った音作りである。
なかでも一番好きな曲は3曲目の3,000 milesだ。パーカッションの懐かしい響きから始まり、そこにトレーシー・チャップマンの声が重なる。さびのI'm 3,000 miles awayの誠実な歌い方が心をうつ。次のGoing Backもよい。とても淡々とした曲なのだが、そのゆっくりとしたリズムが、心を落ち着かせる。
トレーシー・チャップマンは88年にデビューしているので、今年で20年になる。こうしたミュージシャンが20年にわたって活動をし、7枚のレコードを出していることを考えるとき、アメリカの音楽の奥深さを感じないではいられない。もちろん、彼女が優秀なシンガーソングライターであることは間違いない。しかしそれでも、彼女の作品は、けっしてコマーシャルではないし、派手な社会的メッセージを全面に出す訳でもない。彼女にあるのは歌だけだ。しかしその歌には確信がある。ことばがひとを揺り動かす、そのフォークロックのスピリットがまだ、彼女には生き続けているようだ。そんな存在が、きちんと評価されて、コンスタントにアルバムを出せるアメリカとは、やはり文化の度量が広いと言わねばならない。
 このアルバムは、まるで自分自身に対する鎮魂歌のようである。初期の3枚にあった激しい情念はここではすっかり昇華されている。しかし確信をもったその歌い方は、初期のアルバムと変わらない。強い情念として歌を表現する代わりに、ゆっくりとやさしく、しかし強靭な精神をたたえて歌が表現される。
このアルバムは、まるで自分自身に対する鎮魂歌のようである。初期の3枚にあった激しい情念はここではすっかり昇華されている。しかし確信をもったその歌い方は、初期のアルバムと変わらない。強い情念として歌を表現する代わりに、ゆっくりとやさしく、しかし強靭な精神をたたえて歌が表現される。
「癒し」とはいったいなんだろうか?心が平安を取り戻し、前向きになれるということだろうか?ローラ・ニーロの声を聞いて感じるのは、そうした単純な自己肯定ではない。もっと深く自分の生をみつめ、その生を愛する、その人生のすべてを含み込んで愛する、きわめてひかえめな態度だ。それは肯定ではなく、希求だ。
Angel of my heart
Come back to me
Angel in the dark
So I can see
Cause I can't live no more
Without an angel
Of love so if you hear.
祈りの中の愛の希求、ここにローラ・ニーロの音楽が真のソウル・ミュージックであると言える理由がある。誰かが、何かがそばにいてくれないと、すぐにもくずおれてしまうような弱さ、そんな弱さを抱え込みながらも、人生をしっかりと自分の目で眺め、自分の足で歩んでいく、達観した強さ、それがローラ・ニーロの魂だ。彼女のまわりでは天使だけではない、子どもたちや、犬たちも彼女のやさしいまなざしとほほえみの中、踊っている。ニューヨークのビルの屋上に偶然根をおろした一本の草花への愛から、大地にしっかりと根を下ろした木々へ愛へと、ローラ・ニーロのみている世界は変わっていった。しかし、歌うことによる、対象への愛は、どの時代のアルバムであっても、どの曲であっても変わらない。
このアルバムにはキャロル・キングのカバーなどもおさめられているが、オリジナルを知らなければ、すべてローラ・ニーロの曲だと思ってしまう。それほどどの曲も強い説得力に満ちている。何度も何度も聴き直しても、決して感動は薄れることのない傑作である。
 冒頭の、イギリスの田園風景をツアーバスが走り、ミュージシャンたちのインタビューが挟まれるシーンをみただけで、この映画がいかに素晴らしいかよくわかる。ロニー・レインの生涯を素直に追っていく構成だが、使われる映像、写真、そして曲の選択、どれもがいかに制作者がロニー・レインを愛しているかを教えてくれる。
冒頭の、イギリスの田園風景をツアーバスが走り、ミュージシャンたちのインタビューが挟まれるシーンをみただけで、この映画がいかに素晴らしいかよくわかる。ロニー・レインの生涯を素直に追っていく構成だが、使われる映像、写真、そして曲の選択、どれもがいかに制作者がロニー・レインを愛しているかを教えてくれる。
70年代にキンクスがPreservation を発表し、いったいどこに行ってしまうのかという混沌とした状況の中で、結局はアメリカに渡り、ハードロックバンドとして成功を収めたのに対し、ロニー・レインの場合は、そうした道に重なるようでいて、決してショー・ビズの世界には身を染めなかった。
君と一緒に目覚める
朝の光がさしこんでくる
外では犬の鳴き声がする
ファーストソロアルバム(Anymore for anymore)に収められているTell everyoneの一節だが、ここに描かれる農村での生活の情景が実際にはどのようなものであったか、今回の映画をみてよくわかった。ファーストアルバムは、セカンド、サードにも増して名曲ぞろいだが、これら素晴らしい曲が、こうした生活だったから生まれたのか、それともこうした生活をしていたにもかかわらずなのかよくわからない。それほどロックとは遠く隔たった世界なのだ。でも仲間との演奏が、農作業や、パブでの談笑や、そうした日々の一部であり、彼らの生活そのものから生まれてきたことはとてもよくわかる。
普通に考えれば、ロニー・レインほど、ロックの裏街道のような人生を歩んだ人もいないだろう。なにせまわりにはスティーブ・マリオット、ロッド・スチュワートという、稀代のヴォーカリストがいた(映画では彼らがいかに才能があり、ロック的興奮のるつぼにいたのかを実感させられるライブ映像があって、どぎもをぬかれる。ロッドスチュワート、まさにスーパースターです)。そしてクラプトンにピート・タウンゼント。マリオットを除けば、みなロックの栄光を掴んだ連中だ。そんな人脈がありながら、ロニー・レインだけはロック的成功とは縁遠い生活を送る。
インタビューの中で、「みな、アメリカへ行こう。アメリカに行けば成功が待っている。しかし実際に行くことはなく、バンドは解散した」という証言がある。すでに病の予兆があったのかも知れない。ロニーは、田舎の生活を続ける。その後多発性脳脊髄硬化症の基金設立のためにようやくアメリカへ行ったときには、基金を横領されるという不運に見舞われる。みなが成功したその場所でロニーだけは裏切られるというのが何とも痛ましい。
マリオット、スチュワートというカリスマティックなヴォーカルがいたので、目立たないのだろうが、しかし、ロニーのヴォーカルはとても素敵だ。何と言ってもアコーディオンやマンドリン、そうしたトラディショナルな演奏に見事に溶け合った声だ。スリム・チャンスに関係する、グリースバンド、ギャラガー・アンド・ライル、マクギネス・フリントも同じ空気をもっていて楽しめるが、やっぱりロニーのヴォーカルが最高だろう。
映画の最後の方で、病気が進行し、もうベースも弾けなくなった(バンドを始めたころ一番人気のなかったベースを担当したというのもロニーらしい)ロニーが、腰をかけて、精一杯声を振り絞って歌う姿が素晴らしい。これが音楽だと思う。ロックを聞いてきて、ロニー・レインに会えてよかったと思う。
インタビューに答えたすべての人々がロニーを愛していた。ロニーのレコードを聞けば、だれもが彼を愛したくなる。そうならないではいられない。
ロニー自身が最後に言っている。「人生は短編映画だ」でも、その短い一瞬に無限の愛が込められている。
 「これ絶対気に入りますよ」と、大学時代に後輩が貸してくれたレコードは、Small FacesのSmall Facesと、The WhoのSell outと、John CaleのこのアルバムParis 1919だった。ロックは前衛であるだけではなく、一線を引いたところにもロックを探求したレコードがあるのだと、気づかせてくれたのがこのアルバムである。Velvet Undergrandを信奉したり、Lou ReedのBerlinをやたら褒めそやすのではなく、喧噪のその後にも、たとえポップな音楽であっても、「前衛」でありつづけることができる、 Velvetのようなスタイルをとらなくても、禁欲的に「ロック」であり続けることはできる、それに気づかせてくれたのがJohn Caleである。
「これ絶対気に入りますよ」と、大学時代に後輩が貸してくれたレコードは、Small FacesのSmall Facesと、The WhoのSell outと、John CaleのこのアルバムParis 1919だった。ロックは前衛であるだけではなく、一線を引いたところにもロックを探求したレコードがあるのだと、気づかせてくれたのがこのアルバムである。Velvet Undergrandを信奉したり、Lou ReedのBerlinをやたら褒めそやすのではなく、喧噪のその後にも、たとえポップな音楽であっても、「前衛」でありつづけることができる、 Velvetのようなスタイルをとらなくても、禁欲的に「ロック」であり続けることはできる、それに気づかせてくれたのがJohn Caleである。
今あらためて聴き直してみると、オーケストラの入り方が過剰で、仰々しいのが耳につく。脳天気な曲もあったりして、John Caleの「転向」は果たして正しかったのかと疑問に思わないでもない。
しかしJohn Caleが作りたかった、クラシックとは違う世界での「美の世界」、Roxy MusicやT-Rex、あるいはDavid Bowieのようなまがまがしい見せ物とは違うレベルで追い求めようとした美の世界が、ここにはある。その意味でこのアルバムは、ロックがアンディ・ウォホールが口出しするようなまがいものではなく、ひとつのジャンルとして認識されうる標準まで達したことをきちんと証明してくれるアルバムであると言える。
Lou Reedは「インテリになりたかったやくざ」、John Caleは「やくざになりたかったインテリ」。確かにJohn Caleの音楽は、その品の良さからいえば、インテリの遊戯なのかも知れない。表題曲などは確かにオーケストラを導入して、きわめてインテリぽく作られていて、鼻につくかもしれない。でもこれを聞いていた当時の僕は、たとえ寝そべって聞いていてもロックは存在し続けるのだと、考えていた気がする。それは今から考えれば、早くも60年代半ばにたとえばThe KinksがSunny Afternoonで描いていた世界だ。しかもThe Kinksは70年代にはいってもしつこくその世界をMirror of Loveのような曲で何度も念を押す。John Caleも、Velvetへの反動なのか、Lou Reedへの敵意なのか、そのけだるさを全面的にロックとして演奏してはばからない。その決意がこの70年代初頭の動きだったのだろう。しかしこのけだるさは、けっしてこの時代だけにとどまることはない。ロックを聴き始めて、正面切った反抗だけがロックではないと気づくとき、日常の生活の中でもロックを聞き続けようと思うとき、John Caleの作り上げた様式美もひとつの地道な営為だと思うのだ。
 あるレコード屋(死語!)の試聴機に、「洋楽ファンにもぜひ」と書いてあったので、早速試聴し、見事気に入ってしまった日本のミュージシャン。しかしその音楽は、洋楽とか日本とか、そうした国籍を消し去った雰囲気がある。The Guitar plus meは全編英語で歌っているが、だから洋楽っぽいというわけではない。むしろこうした種類の音作りが、今、世界のあらゆるところで様々なミュージシャンによって行なわれている気がする。趣味や、感性が日本も欧米もそんなに変わらなくなってきているし、日本にこだわって音楽を考える時代でももはやなくなってきている。みな最近の若い人たちは、軽々と国境を越えて、自由に自分の世界を表現しているように思う。
あるレコード屋(死語!)の試聴機に、「洋楽ファンにもぜひ」と書いてあったので、早速試聴し、見事気に入ってしまった日本のミュージシャン。しかしその音楽は、洋楽とか日本とか、そうした国籍を消し去った雰囲気がある。The Guitar plus meは全編英語で歌っているが、だから洋楽っぽいというわけではない。むしろこうした種類の音作りが、今、世界のあらゆるところで様々なミュージシャンによって行なわれている気がする。趣味や、感性が日本も欧米もそんなに変わらなくなってきているし、日本にこだわって音楽を考える時代でももはやなくなってきている。みな最近の若い人たちは、軽々と国境を越えて、自由に自分の世界を表現しているように思う。
the guitar plus meはミニアルバムも含めて5枚ほどアルバムを出していると思うが、どのアルバムも構成はほぼ同じである。無表情なうち込み、ときおりループする電子音と、アコースティックギターの音色がすべての曲調を作っている。
このアルバムのテーマは冬。小品が多い彼の作品の中では珍しく、1曲目Silver snow, Shivering soulは10分ほどもある長尺な曲である。でもこの曲の中で果てしなく続く、打ち込みと電子音のゆらぎがとてもすばらしい。ここまで人工的でありながら、ゆっくり舞い散る雪の自然の情景がとてもリアルに浮かんでくる。
どの曲もリズムは単調であるのだが、その曲、曲ごとにテーマがあって、微妙な曲調の違いがそのテーマを浮き立たせているのが楽しい。例えば4曲目はNew year。新年を迎える時の浮き浮き感が伝わってきて、ちょっとした幸福を噛み締めることができる。
the guitar plus meの憎いところは、同じように見えても、この「テーマ」ということにとてもこだわってアルバムを作っている点である。動物のユーモラスな情景がうかぶZoo, 水をテーマにしたWater musicなど、音によるイメージの喚起がとても上手に作られている。
そう、職人の手仕事感といえばいいだろうか。それが一番よく感じられるのは、やはりアコースティック・ギターの音色である。パーカッションが作る音の空間を刻むようにしてギターの音がおかれていく。そんな構成美にとてもひかれる。そんな構成にとことんこだわったのは、2003年のTouch meだろう。ミニアルバムの5曲目Bakeryから6曲目Castleへの流れは、ギターの音は、チェンバロにも似て、バロック的な構成が見事に生かされている。特に5曲目の終わり、単純なリフを繰り返すギターの音色がだんだん大きくなっていき、突然途切れて終わるところで、僕は大きく息をついてしまう。
 ながらく再発を待っていたカナダのシンガーソングライターBruce Cockburnのセカンド・アルバムです。サードもよいけれども、初めて聞いたのがこちら『雪の世界』だった。弾き語りの質素なアルバムであるが、聞き込むとかなり曲ごとに雰囲気が違うことがわかる。比較的ピッキングが強くて、Stephen Stillsのギターワークを思わせもするが、このアルバムはずっと内省的だ。
ながらく再発を待っていたカナダのシンガーソングライターBruce Cockburnのセカンド・アルバムです。サードもよいけれども、初めて聞いたのがこちら『雪の世界』だった。弾き語りの質素なアルバムであるが、聞き込むとかなり曲ごとに雰囲気が違うことがわかる。比較的ピッキングが強くて、Stephen Stillsのギターワークを思わせもするが、このアルバムはずっと内省的だ。
1曲目はタイトルにブルースとついているが、ギターの音色はずっと軽快で、あざやかなコード進行が楽しめる。朝起きたら外は一面の雪景色、まさにジャケットの写真通りの世界が1曲目から描かれる。2曲目もずっとひかえめなギターとヴォーカルだけで作られていて簡素な感じだが、それでも、ギターの緩急をつけた展開が実はダイナミックな曲だ。
また曲調もヴァラエティに富んでいる。4曲目はカントリー・フォークの懐かしい雰囲気をたたえた曲。かとおもうと5曲目はピアノがはいり、6曲目はブリティッシュフォークの憂いをたたえ、8曲目はブリティッシュトラッドの香りがする。
このように様々なテクニックを随所にちりばめながらも、決してそれを全面に出さず、音を織り込んでいるところがこのアルバムの素晴らしいところである。
曲がずば抜けてよいわけではないし、ボーカルも朴訥として、けっしてうまいとは言えない。アルバムのどこかに盛り上がりどころがあるわけでもない。CDで聞いているとB面の1曲めがどこだか見当もつかない。それほど単色の世界なのだ。しかし、このように控えめでありながら、聞けば聞くほど、1曲、1曲が個性を放ち始めるところが、このアルバムが名盤たるゆえんではないだろうか。
ところでこのBruce CockburnやArtie Traum(名盤Double back!)といったシンガーソングライターは、その後いわゆるギターの教則本といった世界に入っていく。それはそれで彼らのギターテクニックが卓越しているという証拠ではあるのだが、もはやアルバム1枚でひとつの世界を創りだすだけの余力は残っていないのだろうか。そこが少々寂しいところである。ジャケットもそうで、近年のアルバムはなんだかヘアーバンドが似合いそうなふぜいで、それじゃあ南こうせつだと少し悲しくなったりもする。
 お決まりのリフ、無駄なシャウト、どこかで聞いたことのあるおなじみのメロディ展開、そこらへんに落ちている、「ロックンロール」の常套句をちりばめたこのアルバムは、普通のミュージシャンであれば、オリジナリティのかけらもない失敗作として、片付けられてしまうだろう。
お決まりのリフ、無駄なシャウト、どこかで聞いたことのあるおなじみのメロディ展開、そこらへんに落ちている、「ロックンロール」の常套句をちりばめたこのアルバムは、普通のミュージシャンであれば、オリジナリティのかけらもない失敗作として、片付けられてしまうだろう。
でも、Ryan Adamsのアルバムに感じることは、「この程度のことならば、やってしまえる」という、不敵さだ。「ロックンロール」は中途半端な、彼のアルバムにして珍しく、ボーナストラックの方が本編よりいいのではと思ってしまうほど、本心の見えないアルバムなのだが、「望みとあればくだらない作品だって作れるぜ」という歪んだ心情を堪能できるところに、Ryan Adamsの一筋縄ではいかない、持って生まれたロック気質を感じてしまう。こうしたアルバムが出てしまうと、あくせくとロックンロールのパーツを接ぎ木してアルバムを作っている凡百のミュージシャンは塵と消えてしまいそうだ。とはいえ、これは音楽の健全な聞き方ではないだろう。音楽を聞くというより、ミュージシャンの破天荒な生き方そのものに音楽を通して接しているようなものだ。
Neil Youngのアルバムにもそうしたものを感じてしまうことがある。アルバムそのものの楽曲より、こんなアルバムを作ってしまう人間とはいったいどんな人間なのだ、という人本位の聞き方だ。
実際一曲目から、どう考えてもミスマッチなプロデュースでしかない楽曲が並ぶ。ヴォーカルも一歩調子だし、サビも、今は死語かも知れないが「産業ロック」のエッセンスがふんだんにぶちこまれている。シングルカットされたらしい5曲目のSo Aliveなど、ギターのメロディの陳腐さに苦笑いをしないではいられないほどの、古びた80年代ブリティッシュロックを聞かせてくれる。そして10曲目のアルバムタイトル曲Rock N Rollだけがピアノの弾き語り、しかも中途半端なフェイドアウトというふざけ方である。
結局はRyan Adamsが好きだからこそ、こんなアルバムにも価値を認めてしまうのだ。こうした生き方をしてしまうロック・ミュージシャンだからこそ、駄作にもリスナーとして愛を注いでしまうのだ。ミュージシャンにつきあって、新譜がでればどんなものでも買ってしまう、Ryan Adamsはそうしたつきあい方をせまられるミュージシャンである。
日本盤のボーナストラック「Funeral Marching」はなかなかの名曲です。
 ギターを弾くのが大好きな青年が、その自己満足的な音楽生活を捨てて精一杯攻撃的なレコードを作った。それが思いもせず90年代のアメリカを代表とするアルバムとなった。
ギターを弾くのが大好きな青年が、その自己満足的な音楽生活を捨てて精一杯攻撃的なレコードを作った。それが思いもせず90年代のアメリカを代表とするアルバムとなった。
Matthew Sweetはカリスマ的なロッカーでも、超絶なテクニックをもつミュージシャンでもない。それでもキャッチーなメロディがかける大学生、ただプロとしてもそこそこは売っていけるミュージシャンとして、Girlfriendの前に2枚のアルバムを出している。2ndのジャケットをみれば分かるように、内省的な青年が自宅録音をしたような、ナイーブなアルバムである。
ところがGirlfriendとの別離を契機にして、どん底の生活から、なんとか音楽を作ってみるという、これまたナイーブな場所から届けられたこのアルバムは、ギターの音も生々しく、すべてをぎりぎりまでそぎおとした、きわめてストイックな作品として完成をみる。どんな加工もせず、そのまま感情を投げ出し、その感情をギターのひずんだ音色に反映させた時、Matthew Sweetは、他の誰にもまねのしようがない、ストレートな世界を作り上げることに成功する。ふだんは恥ずかしくて絶対に言えないようなこと、たとえば I'm alone in the worldのような歌詞を平気で歌う。しかも叙情的なギターのフレーズつきで。しかしそのいさぎよさ、時代の音など何も意識しない、虚飾のない音楽こそが、聞く者も、おそらく味わったことのあるつらい体験をやさしく包み込んでくれるのだ。
川崎チッタで、Matthew Sweetが姿を現した時、会場がどよめいた。その理由は、アルバムの裏ジャケットの写真とは似ても似つかない、普通のアメリカ人並みに太ったおにいちゃんがステージに現れたからだ。本人はその観客の反応の意味はつかみかねていただろう。せつないほど、センシティブで神経質な青年を予期していた客の前には、ぜい肉のだらしなさがTシャツから透けて見えるアメリカ人が、脳天気にギターをひきまくっているのだ。
その後、Matthew SweetはGirlfriend以上のアルバムは作れていない。というか作りようがないだろう。この密度ある時間はもう決して戻ってこない。それは青春時代に誰にも訪れる一瞬だけの才能だったのだ。だがその一瞬が、このアルバムに結晶として収められている。
 CDで2枚組、原盤は18曲入りのアルバムである。といっても散漫な作りの曲は1曲もない。Ry CooderやJohn Hiattあたりの作品に敬意をはらいながらも、しかしそうした完成度の高さとは無縁でありたい、いつまでも未熟でありたいというロック的な激しい欲求が「オルタナ・カントリー」というような安易な呼称を斥けている。親しみのある思わず口ずさみたくなるメロディでありながら、しかしけっしてBGM的な心地よさへとリスナーを誘いはしない、正面切った叫びがこの作品をまさにロックのアルバムにしている。
CDで2枚組、原盤は18曲入りのアルバムである。といっても散漫な作りの曲は1曲もない。Ry CooderやJohn Hiattあたりの作品に敬意をはらいながらも、しかしそうした完成度の高さとは無縁でありたい、いつまでも未熟でありたいというロック的な激しい欲求が「オルタナ・カントリー」というような安易な呼称を斥けている。親しみのある思わず口ずさみたくなるメロディでありながら、しかしけっしてBGM的な心地よさへとリスナーを誘いはしない、正面切った叫びがこの作品をまさにロックのアルバムにしている。
曲はどれも、ひとひねり効いていて、単純な展開を許さない。たとえばCherry Laneは、ガレージバンド風な始まり方をするが、途中でささやかれるI can never get close enoughのリフレインはほとんど後期のフリードウッド・マックといってもよいセンチメンタルな曲調だ。しかしそんな展開もまったく無理なく聴かせてしまう曲作りの才能が彼にはある。
『Gold』はまさに青くて、胸がひりひりさせられるが、『Cold roses』はもう少し、自分に対する距離感が生まれているようだ。また演奏そのものも、バンドに対する信頼が、安定感を生んでいるのか、余裕が感じられる。もちろん『ゴールド』もよいアルバムなのだが、多少型にはまりすぎた曲もあるのに対して、『Cold roses』は、アルバムのトータルなイメージがきちんと作り込まれている。どの歌詞にもroseがちりばめられいて、ちょっときざなのも、かれの羞恥心の現れのような感じがしてとてもよい。
Ryan Adamsのヴォーカルは、Stan RidgwayやChris Isaakなど、憂愁を帯びた感じなのだが、センチメンタルな叙情には流されない激しさを持っている。それが彼のどのアルバムも生々しい感情を感じさせる理由だ。
60年代にBob Dylanの音楽が生まれ、70年代にはそれをBruce Springsteenが受け継いだ。どの時代にもその時代と対峙するボブ・ディランが必要ならば、00年代のディランはこのRyan Adamsだ。ファースト・ソロアルバム『Heart Breaker』の2曲目「To be young」の始まりは、完全に「Subterranean Homesick Blues Farm」、あるいは「Maggie's Farm」のそっくりコピーだが、これは単にディランへの憧憬ではない。ディラン程度のことなら、こんなに簡単にコピーしてしまえるという、Ryan Adamsの若々しい、不敵な決意の宣言だ。しかしその決意は、まさにHeart Breakerという言葉が表すように、傷を隠しきれないナイーブさと同居している。Dyranは70年代にはいってThe Bandと組む。Ryanも同じようにCardinalsというバックバンドとくんで、『Cold roses』などのアルバムを作りあげることになる。それによって、たくましい土着のアメリカン・ロックをこの時代に謳いあげることに成功した。その骨太さがいかんなく発揮されたのがこのアルバムだと言える。
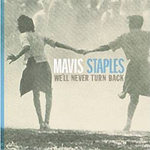 67歳の黒人女性歌手Mavis StaplesとRy Cooderとの共作アルバムである。60年代の公民権運動で歌われた曲を中心に取り上げられているが、過去の歴史に対する郷愁はみじんもない。今に激しく切り込む、メッセージ性の強いアルバムである。
67歳の黒人女性歌手Mavis StaplesとRy Cooderとの共作アルバムである。60年代の公民権運動で歌われた曲を中心に取り上げられているが、過去の歴史に対する郷愁はみじんもない。今に激しく切り込む、メッセージ性の強いアルバムである。
メッセージ・ソングとは何だろうか?たとえば誰にむかって、何を歌うのかが明確になっている歌と定義できるだろう。しかし、そうした対象が明確であればあるほど、メッセージは時の流れには、逆らえない。歌われている問題が解決されていないのに、歌の方が薄命にも消えていってしまうのだ。また訴え方が直情的であればあるほど、それが喚起する反応も一過的なものになってしまう。結局は、当事者たちだけが、苦しみ続け、外にいる者は日々の生活に戻っていく。取り残された者は、表現を失い、内に閉じこもっていく。それがメッセージ・ソングのあやうさであろう。
ではどうしたらメッセージ・ソングは時の試練を経て、生き続ける、あるいは生まれ変わることができるのだろうか?その一つの答えの試みがこのアルバムである。
まずは音の塗り替えだろう。音のバランス、音質が素晴らしい。21世紀らしく、どの音もクリアに録音されている。特にRy Cooderの乾いて張り詰めた音色のギターは、曲に立体感を与え、空間の広がりを堪能させてくれる。きわめて現代的な音響処理である。
そして、Mavisの声が素晴らしい。といっても、それは怒りや、悲壮な訴えなどではない。歌っているうちに、自らが興奮のあまり、気を失ってしまうようなファナティックなものでもない。迫力はあっても、それは、バネのようにしなやかな伸びをもつ声だ。叫んでもつややかな、ささやいても強くひびく声だ。
こうした素晴らしい音楽だからこそ、そこで何が歌われているのか、耳を傾けるようになるのだろう。そして、そこにとても素朴な歌詞を発見する。リフレインで繰り返される言葉が、聞く者の心に強く刻まれる。寄せてはうちかえすリズムでくりかえされるDown to Mississippiのフレーズ。繰り返されるWe shall Not be Movedからは、腕を組み、その場を決して去ろうとしない抑圧された者たちの決意の姿が浮かんでくる。アルバム最後の«Call him up and tell him what you want»の、繰り返すうちに次第に高揚してくるゴスペルの醍醐味。こうしてメッセージは、時と場所を超えて、聞く者の今・ここへと届けられるのだ。そして「あなたはどうする?」と問いかけられる。真の怒りが、告発が始まるのは、ここからだ。
この音楽にはジャンルがない。ゴスペル、ブルース、ロック、フォーク、どの要素もあるが、決して一つにおさまらない。強いていえばここには音楽がある。だからこそ、このアルバムは普遍性を獲得し、永遠のメッセージ・ソングへとどの曲も高められていく。音楽が「芸」である以上、楽しんで歌えて、踊れなくては、聞きはしない。それが真に「芸」としての音楽ならば、声をだし、体を動かしているうちに、その声と体は「行動」へと向かう。権力と差別を撃つ行動へと。
 一聴して、解放感のあるアルバムだと思った。それはロックの切迫感をかなりそぎ落とし、メロディの流れにヴォーカルを乗せていく、曲調のせいだろうか。
一聴して、解放感のあるアルバムだと思った。それはロックの切迫感をかなりそぎ落とし、メロディの流れにヴォーカルを乗せていく、曲調のせいだろうか。
そして、とにかくやりたいことをやってみたという潔さがある。しかし制約を受けずに自由にまかせて創られた作品が、その人間の想像力と創造力を十分に発揮した作品になるわけではない。限られた機材、予算、時間、スタッフ、そうした制約の中でぎりぎりの状態で創られた作品であっても、歴史的な価値を生む作品はいくらでもある。その意味でくるりの文脈では、意味をもつ作品であっても、現在の日本のロックシーンへの位置づけとしてはどれだけの価値をもつ作品になるだろうか?そうした今現在への共振の少ない作品であることは確かである。
しかし走り続けるということは、ある意味貪欲に様々なものを吸収、咀嚼しないでは難しいだろう。様々なものに影響を受けつつ、しかし自分を律することで、自分であり続ける。それはけっしてたやすいことではない。なにせ自分で居続けるために、外からの影響を受けないではいられないというジレンマをかかえるわけだから。メンバーもどんどん少なくなっていく今のくるりはまさに「長距離ランナーの孤独」という状態かもしれない。しかし、作品がでるたびに、その作品に対峙し、丁寧に聞き込んでいるリスナーは数多くいるだろう。また真剣にアルバムに向かわせるほど、くるりの凝縮度は、今の日本のロックシーンにあって群をぬいている。今後どんな方向に向かおうと、誠実に創られたアルバムが創られる以上、それをきちんと受け止めるリスナーは存在し続けるだろう。
今回も佳曲が多い。その意味では『アンテナ』以降のストレートな曲調が、このアルバムでも引き続き生かされている。特にアルバムの最後に無理矢理押し込められたような「言葉はさんかく、こころは四角」は、単純だが、くるりの叙情性がいかんなく発揮された曲だ。「ブレーメン」や「ジュビリー」も、『NIKKI』に入っていてもおかしくない、盛り上がりどころを心得た楽曲になっている。また初期ルースターズのような「アナーキー・イン・ザ・ムジーク」や、東欧民謡といった風情の「スラヴ」のような曲も、いさぎよいほどストレートに、シンプルに曲が創られている。その意味では、途中で聞くのをやめたくなるほど極端ではなく、とにかく「まやかしのない楽曲」が並んでいる。ただ、コンセプト性はほとんど感じられない。だからCMソングになっても十分通用するのだ。
消費される音楽にどれだけ立ち向かえるか、くるりの果敢な挑戦にこれかも胸を躍らせていきたい。
 Brian Enoは、私がロックを聴き始めたころに知った名前のひとつである。最初に夢中になったのは、Police, Elvis Costello, Ian Dury and the BlockheadsそしてTalking Heads(この中でPoliceだけがライブに行ったことがない!再結成ライブには行かねば)。このTalking Headsのプロデューサーとして、そしてDavid Burnとアルバムを作ったミュージシャンとしてEnoの名前を知った(発売日の前の晩に、閉店ぎりぎりに金宝町の電波堂にて購入)。その後 Discreet Musicを聞いたりはしていたが、ロックミュージシャンとしてのEnoの音楽はずっと聞く機会がなかった。70年代後半のEnoは事実、ロックミュージシャンを半ばやめていたのではないだろうか?
Brian Enoは、私がロックを聴き始めたころに知った名前のひとつである。最初に夢中になったのは、Police, Elvis Costello, Ian Dury and the BlockheadsそしてTalking Heads(この中でPoliceだけがライブに行ったことがない!再結成ライブには行かねば)。このTalking Headsのプロデューサーとして、そしてDavid Burnとアルバムを作ったミュージシャンとしてEnoの名前を知った(発売日の前の晩に、閉店ぎりぎりに金宝町の電波堂にて購入)。その後 Discreet Musicを聞いたりはしていたが、ロックミュージシャンとしてのEnoの音楽はずっと聞く機会がなかった。70年代後半のEnoは事実、ロックミュージシャンを半ばやめていたのではないだろうか?
大学に入ってしばらくしてから、友人が「Enoはこんなことをしていたんだよ」と貸してくれたのがTaking Tiger Mountainである。聴いてすぐ、そのポップセンスにうたれた。Enoのソロ4枚は、動から静を描いているが、このアルバムはまさに躍動感のあるポップミュージックである。Another Green WorldのB面や、Before and after scienceのB面における、静謐なメロディも大好きだが、1st, 2ndはそのジャケのごちゃごちゃ感もあいまって、Enoのポップへの病的とまで言えるこだわりを堪能させてくれる。
このアルバムを聴くと、Talking Headsとの共通点が、まずはなによりもその「ひきつり感」にあることがわかる。たとえば一曲目のギターのリフなどは、なんだか普通ではない。しかし曲調には上品さがあり、このアンバランスがおかしい。二曲目も三拍子にEnoのひきつったボーカルがかさなるのがなんともミスマッチだ。他にもバックヴォーカルの声質とか、数え上げたらきりがないほど、「ビザール」なレコードだ。70年代初頭のポップとは、このエキセントリックさをいかにポップなものとして仕上げるかにその価値があったのではないか? それは職人といってもよい作業である。そうしたテイストがたとえばバウハウスのようなバンドに引き継がれていったのもおもしろい。つまり「ひきつり感」は、ニュー・ウェーブの先鋭性にもつながりをもつのだ。70年代に多くのミュージシャンがプログレに流れていったが、そうした大げさな音楽ではなく、あくまでも3分間のポップ・ミュージックにこだわったのがEnoである。そのひねくれ感こそが、次の世代を用意したのだ。B52'sや前述のTalking HeadsそしてDevo、Ultravox のようなテクノ黎明期のバンドもふくめて、Enoがその出発点であったことはこのアルバムがはっきり示してくれる。たとえばB面3曲目の反復されるメロディは、この数年後にうまれてくる交配雑種のニュー・ウェーブの音をすでに実現している。それは801Liveのような冗長なプログレとは完全に一線をかくしている。
B面の最後Taking Tiger Mountainは、そうしたアグレッシブなポップの雰囲気にあって、唯一、けだるさを演出してくれるインストゥルメンタルの曲だ。この曲を初めて聴いて、おそらく僕はロックにおける成熟を知ったのだと思う。それはロキシーの喧噪からぬけだした、Enoの音楽に対する意思表明でもあった。そのEnoの姿に背伸びして、自分のロック観をかさねあわせていたのだろう。
 The Whoのディスコグラフィーをみていて驚くのは、このWho's Nextがわずか5作目だということだ。わずか5作にして、ビートバンドからはるかに遠い地点にまで到達してしまった。25、26歳の若者たちがすでにブリティッシュ・ロックの金字塔を打ち立ててしまった。
The Whoのディスコグラフィーをみていて驚くのは、このWho's Nextがわずか5作目だということだ。わずか5作にして、ビートバンドからはるかに遠い地点にまで到達してしまった。25、26歳の若者たちがすでにブリティッシュ・ロックの金字塔を打ち立ててしまった。
ロジャー・ダルトリーの一本調子の「がなり唱法」は正直苦手で、ピート・タウンゼントのソロ・アルバムの方にむしろ情感がわくのだが、このアルバムに限っては、アルバムのトータル性という点で、ほとんど気にならない。ヴォーカルも曲のうねりの中に見事に調和している。ピートの素晴らしいギター奏法、キースのドラムワークの独創性(一人ドラムの天才を選べと言われれば間違いなく彼を選ぶであろう)、そして控えめながらも曲を下支えするジョンのベース、どのメンバーが入れ替わっても、もはやこのような作品は不可能であると言えるほど、4人のパフォーマンスがしっかりと結ばれている。
だから、どの曲も展開が頻繁で、ドラマチックであっても、決して大げさにはならない。ハードロックの頂点にたつレッド・ツェッペリンの音楽の美学がその形式性にあるのにたいして、The Whoの音楽は、4人の力量が渾然一体となったところからうまれてくる圧倒的な力のようなものにその魅力がある。だから、ツェッペリンのライブでは、ソロの聞かせどころがあり、それが時に冗長な感じが否めないのにたいして、The Whoにはそういったソロが際立つということがない。いかに素敵なパフォーマーたちであろうと、実は他のメンバーとの緊密な関係の上に成り立っているのだ。それがThe Whoという「バンド」の「バンド」たるゆえんだ。
アルバムはシンセサイザーの人工音ではじまる。それが空間をゆったりとめぐる。そこにピアノ、そしてキースのドラムが重ねられる。この余裕をもった展開の中、ロジャーの正統的なヴォーカルが始まる。この始まりだけをとってみても、音の絡まりのスリリングさが伝わってくる。2曲目でほほえましいのは、クラップ音だ。こうした小細工も実はThe Whoの魅力だったりする。そしてA面の最後の曲The song is overには、小尾隆さんが指摘しているように、Pure and easy(Odds and Sods収録)からのフレーズが織り込まれている。これはピート・タウンゼントのファーストWho came firstの一曲目にもそのデモバージョンが収められている。実に美しい曲だ。
めまぐるしい展開があっても、それが緊張感を保って曲として成立しているのは、「余裕」があるからである。それは「風格」といってもいいだろう。ロックが若者の好むやかましい音楽ではなく、楽曲としても成熟し、作品として十分聞かれ続けるにたる、そんな大人のロックが、The Whoによって始まった。それがイギリスの1971年だ。
 本人は、どんなジャケットで、どの曲が、CDになって発売されたか知る由もない。しかし、この作品をみたら、きっと本人は満足するに違いない。ミュージシャンの死後、周りの人間がその仕事をきちんと外にだしてくれる。そうした作品に触れるたびに、そのミュージシャンがいかに愛されていたのかがわかる。そして私たちファンもそんな愛をともにする。
本人は、どんなジャケットで、どの曲が、CDになって発売されたか知る由もない。しかし、この作品をみたら、きっと本人は満足するに違いない。ミュージシャンの死後、周りの人間がその仕事をきちんと外にだしてくれる。そうした作品に触れるたびに、そのミュージシャンがいかに愛されていたのかがわかる。そして私たちファンもそんな愛をともにする。
From a Basement of the Hillは、制作途上のアルバムであり、そのせいか、アレンジのバランスが悪かったり、曲の展開が散漫だったり、やはり途中の仕事という事実は否めなかった。それに対して、アウトテイクを集めたNew Moonは、アウトテイクとはいえ、完成された曲ばかりだ。95年から97年ごろの曲が中心に集められており、Another Either/Orという雰囲気の曲が多い。これ自体が、アルバムとして発表されてまったくおかしくない。10年のブランクを経て私たちに贈られたアルバムと言ってもよいだろう。
なかでもうれしいのはDisk1の13曲目、Thirteen。Big Starのファースト、No.1 Recordの4曲目に収められた曲のカバーだ。クリス・ベルとアレックス・チルトンの2人によるBig Starのラフさや、叙情的なメロディ、枯れた雰囲気は、エリオット・スミスに大きな影響を与えたに違いない(Big Starについては、そのアルバムもそうだが、クリス・ベルのソロ作品I Am the Cosmosもおさえておきたい)。そう、エリオット・スミスを語る際にニック・ドレイクの名前が出されることに今一歩しっくりこなかった理由は、ここにある。クリス・ベルやアレックス・チルトンの名前をむしろ出すべきだろう。彼らの音楽の質感のほうがずっとエリオット・スミスの曲の質感に近いからだ。ニック・ドレイクの叙情性は、けっこう華美だし、ウエット感がある。しかしエリオット・スミスの叙情性は、ずっと乾いた感じがする。言ってみれば大げさではないのだ。この乾いた感じがエリオット・スミスをBig Starにひきつける。
このアウトテイク集を聞いて、様々なバリエーションの中から、アルバムテイクが生まれていったことがわかる。しかし、あらためてくりかえすが、ここに収められているのは、制作の途中のスケッチではない。セッションでギターをかなでる姿は、きっと幸福感にあふれていたのではないか。そうした自分の曲への愛情という点では、アウトテイクもアルバムテイクも何も変わりはしない。
 アメリカ建国200周年を機に行なわれたライブツアー「ローリング・サンダー・レビュー」。旅芸人のように街から街を巡りながら、その日その日の音楽を奏でていく。同じ演奏は2度とできない。その瞬間、その場所で音楽が生まれていく。そんな音を切り取って収められたのがこのライブ・アルバム「Hard Rain」だ。このタイトル通り、とても激しい音楽である。といってもディストーションでひずんでいるとか、大音量で圧倒されるというわけではない。むしろそれぞれの楽器の音はひかえめでさえある。ギターはつまびかれ、ヴァイオリンの音は、哀愁を感じさせる。それでも激しいのは、ディランの魂の圧倒的な存在感、これにつきる。
アメリカ建国200周年を機に行なわれたライブツアー「ローリング・サンダー・レビュー」。旅芸人のように街から街を巡りながら、その日その日の音楽を奏でていく。同じ演奏は2度とできない。その瞬間、その場所で音楽が生まれていく。そんな音を切り取って収められたのがこのライブ・アルバム「Hard Rain」だ。このタイトル通り、とても激しい音楽である。といってもディストーションでひずんでいるとか、大音量で圧倒されるというわけではない。むしろそれぞれの楽器の音はひかえめでさえある。ギターはつまびかれ、ヴァイオリンの音は、哀愁を感じさせる。それでも激しいのは、ディランの魂の圧倒的な存在感、これにつきる。
ディランの歌声は、本能的な感情の叫びではない。それは、確信をもった魂のうなりだ。単なるその場だけの感情の爆発ではない、表現をしようとする魂の激しい動きが、そのまま声にのりうつる。
ディランの本質は、よく言われるようにアルバムではなく、ライブにあるのだが、それはこのレコードでも実感する。一曲目のギターのチューニングのような音を聞いているうちに、いきなり演奏が始まる。この唐突な始まり方に、鳥肌がたつ。そして例のごとく、原曲をとどめないアレンジに、この曲が Maggies' Farmだとはなかなか気づかない。この曲、ブレイクの仕方が最高にかっこいい。そして二曲目One Too Many Morningsは感傷的なようでいて、バンドの高揚感が激しいエネルギーを感じさせてくれる。そして三曲目The Memphis Blues Againは、サビの部分、ディランの声が虚空に響き、ゆっくり消えていく終わり方が最高です。四曲目はOh, sister.『欲望』収録の曲だが、張り詰めた空気の圧倒感で、こちらのライブバージョンのほうが断然いい、B面一曲目のShelter From The Stormはギターのかけ合いが最高、こんな生き生きしたナンバーを耳にしたら、踊り狂ってしまう・・・と、きりがないのだが、どの曲もその演奏のテンションの高さに驚かされる。『血の轍』と交互に聞きたいアルバム。そうでないと、こちらの緊張感がもたない。しかもどちらもLPで。
76年11月にはThe Bandのラスト・ワルツが行なわれている。このコンサートは、ロックの終焉とよく言われるが、このディランのツアーと重ね合わせれば、確かにロック・コンサートのもたらしてくれるユートピア幻想に決定的な終止符がうたれたのがこの時期であるというもうなづける。ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリンなど、ロックの伝説が死んでいくなか、残されたミュージシャンたちの苦しい模索が今後始まることになる。
 ジャクソン・ブラウン、ジェームス・テイラー、エリック・アンダーソン。長髪の顔立ちには、内面のナイーブさ、繊細さが映し出されているかのようだ。社会に跳びかかっていくのでなく、自分を破綻に追いつめるのでもない。情熱と狂気が失われてしまった時代にあって、自分の立っている場所をもう一度見つめ返すような内省的な態度といえばいいだろうか。エリック・アンダーソンの2枚のアルバムジャケットは、どちらも本人のポートレイトである。そのまなざしは、外に向かって投げかけられた、というよりも、おそらくは自分自身の内にむかって深く沈んでいくような印象をうける。しかし、それは決して自己閉塞ではなく、控えめであっても何かを見据えた力強いまなざしだ。
ジャクソン・ブラウン、ジェームス・テイラー、エリック・アンダーソン。長髪の顔立ちには、内面のナイーブさ、繊細さが映し出されているかのようだ。社会に跳びかかっていくのでなく、自分を破綻に追いつめるのでもない。情熱と狂気が失われてしまった時代にあって、自分の立っている場所をもう一度見つめ返すような内省的な態度といえばいいだろうか。エリック・アンダーソンの2枚のアルバムジャケットは、どちらも本人のポートレイトである。そのまなざしは、外に向かって投げかけられた、というよりも、おそらくは自分自身の内にむかって深く沈んでいくような印象をうける。しかし、それは決して自己閉塞ではなく、控えめであっても何かを見据えた力強いまなざしだ。
1972年に出されたこのアルバムは、もはやフォーク・シンガーのアルバムではなかった。フォークというには、あまりにも老成している。誠実ではあっても、もはや素朴ではない。いわゆるトラッドという、過去の伝承を歌い継いでいくような素朴さは、もはやここには認められない。憂愁や追慕はあっても、それはきわめて個人的なものである。この私的な音楽が、しかし、人々の心をとらえていくのだ。
先に挙げた3人の中で、エリックの声が一番線が細い。ジャクソン・ブラウンの力強さ、ジェームス・テイラーのきらびやかな歌声に比べてと、エリックの声の特徴は、その震えだと言えないだろうか。名曲Blue Riverでは、ゆったりとしたリズムにあいまって、高音の震えがはっきり伝わってくる。感情をあらわにすることなく、たんたんと歌を紡ぎだす。もしかしたら、押し殺した感情があるのかもしれない。でももはやそれを語る時代ではないのだ。その失われたものへの憧憬をもちながらも、一歩前へ踏み出す決意、それがSSWたちの創造への意欲だったに違いない。
この音楽はやさしい。軟弱といえばそれまでだが、あくまでも誠実な歌である。人に聞いてもらおうと、わざとおもねりはしない。彼の声はひとすじのよびかけだ。たとえどんなにかぼそくとも、よびかけは、多くの人の心に届いていく。エリック・アンダーソンを聞く者は、その音楽によって、孤独とは何か、おそらく問いかけるはずである。そうした繊細な魂に、彼はよびかけるのだ。Be true to youと。
 恋人の贈ってくれた歌を歌う時、人はどんな気持ちになるのだろう。愛し合う者同士の心は、きわめて私的なものだ。ジャクソン・ブラウンの曲を歌うときの、ニコの心情、ニコの歌を聞くジャクソン・ブラウンの心情、ふたりの想いは決して外の人間にはわからない。それなのに、私たちは、アルバムを聴きながら、ニコの声に心をうたれる。音楽の限りない魅力の秘密は、きわめて個人的なものが、多くの人々の心に共感を得て広がっていくところにあるのではないか。いつまでも手元に置いておきたい、そんな思い入れを強く感じさせるアルバムだ。
恋人の贈ってくれた歌を歌う時、人はどんな気持ちになるのだろう。愛し合う者同士の心は、きわめて私的なものだ。ジャクソン・ブラウンの曲を歌うときの、ニコの心情、ニコの歌を聞くジャクソン・ブラウンの心情、ふたりの想いは決して外の人間にはわからない。それなのに、私たちは、アルバムを聴きながら、ニコの声に心をうたれる。音楽の限りない魅力の秘密は、きわめて個人的なものが、多くの人々の心に共感を得て広がっていくところにあるのではないか。いつまでも手元に置いておきたい、そんな思い入れを強く感じさせるアルバムだ。
このアルバムが出されたのが67年10月。その数ヶ月前には、ヴェルヴェットアンダーグラウンド&ニコのファーストアルバムがでている。ロックがひとつの前衛であること、トータルな芸術運動であることを、一つの作品という形におさめた類い稀なアルバムだが、ロックのコミューンとしての性格は、じつはヴェルヴェットよりニコのアルバムのほうが色濃くでているかも知れない。ヴェルヴェットがあくまでもバンドのサウンドを全面に出しているのに対して、ニコのアルバムは、ジョン・ケールとルー・リードのコラボレーションが音作りに生かされているからだ。ニコ、ケール、リードのとりあわせは、ロックが共同体の中から生まれてくる芸術であることを教えてくれる。人と人がある時、偶然出会い、お互いを触発し、強い創造性を生むこと、そこにロックの醍醐味があることを教えてくれる。
だから、ソロアルバムでありながら、ニコと、彼女を取り巻く様々な人々のサポートによって出来上がったこのアルバムは、合作という感じが強い。しかし出来上がった音はあくまでもストレートでシンプルだ。弦楽器や吹楽器の音は美しく、ニコの声はとても生々しい。その少し鼻にかかったような、しかし芯のある歌い方は、ニコの魂の赤裸々な姿だ。
死の直前のニコのライブは、すでに祈りにも似た、厳粛なものだった。しかしこのファーストアルバムのニコは、けだるくも、十分に瑞々しさを感じさせてくれる。実は光りにあふれたた、優しさに満ちたアルバムだ。
 10年ぶりにだされたDinosaur Jrの再結成アルバム Beyondを聴いた直後に、Green Mindを聴き直した。Matthew SweetのGirlfriendと並んで、90年代のアメリカのロックの冒頭を飾る傑作である。新作と聴き比べて歴然としているのは、やはり若いアルバムだということだ。この疾走感はもう二度と再現できないのではないか。Green Mindは、確かにそれ以前のDinosaurのアルバムより数段ポップで聞きやすい。しかしそれは、決してメジャー向きの音楽に転向したわけではなく、バンドのメンバーの緊張が結果としてバランスのとれた曲を生んだのだと思いたい。
10年ぶりにだされたDinosaur Jrの再結成アルバム Beyondを聴いた直後に、Green Mindを聴き直した。Matthew SweetのGirlfriendと並んで、90年代のアメリカのロックの冒頭を飾る傑作である。新作と聴き比べて歴然としているのは、やはり若いアルバムだということだ。この疾走感はもう二度と再現できないのではないか。Green Mindは、確かにそれ以前のDinosaurのアルバムより数段ポップで聞きやすい。しかしそれは、決してメジャー向きの音楽に転向したわけではなく、バンドのメンバーの緊張が結果としてバランスのとれた曲を生んだのだと思いたい。
特にギターの轟音と、音数の多いドラムとの絡みはこのアルバムの魅力のひとつである。たとえば3曲目の「Blowing it」から4曲目「I live for that look」へのスリリングな流れは、ドラムからギターへと音の主役が移っていくことによっている。「Blowing it」のノリを決めているのは、まさにドラム。フックの効いた間合いの取り方がこの曲のスピード感を高めている。そして曲の最後になってからの轟音のギターが、4曲目への橋渡しをしてくれる。こうしてアルバムの構成に注意してみると、Mascisの爆音ギターは、ノイズの垂れ流しどころか、ここぞという微妙なタイミングで流れてくることがよくわかる。もちろんギターとドラムのかけあいは一つの美しいユニゾンも作ってもいる。たとえば8曲目(というか、 LPのB面2曲目)の「Water」では、ギターとドラムが同じ調子でリズムを刻む。2分26秒あたりの「ダ、ダ、ダ、ダ、ダ」というドラムにあわせサビが始まる瞬間のギターのメロディ、そしてその美しいメロディにかさなる「カモン、ベイビー」という歌詞の高揚感は、このアルバムの白眉と言ってもよい。
そして耳をすませばすぐにわかることだが、Mascisのギターの美しさは、やはりニール・ヤングゆずりである。「Thumb」のようなスローテンポの曲では、まさに泣きのギターが堪能できる。ただそれは、ジョージ・ハリスン、エリック・クラプトンとは異なる泣きのギター、優秀なギターリストの音ではなく、衝動のギターリストの音なのだ。
Dinosaur Jrの魅力はもちろんMascisのヴォーカルにある。特に彼の声が裏返った時の、情けない歌い方は、このバンドの人生に対するだめさ加減をこれでもかと伝えてくれる。そう、このだめさ加減がまた若いのだ。人生の目的をさだめてしまった大人には決してこのロックの素晴らしさはわからないだろう。そしてこんな音楽にのぼせてしまった人間は、いつまでたっても人生に責任をとるほどの成熟さには至ることができないだろう。だらしなくて、いいかげんで、無能な人間が、汚いソファーにぐったり寝そべって、ヘッドホンで大音量で聞く音楽。それがDinosaurだ。
 ポップスからロックへの移行をこの「Writer」ほど象徴的に表しているアルバムもないだろう。「Writer」の登場は、キャロル・キングという天才ライターのロックミュージシャンへの変化を意味するだけでなく、ロックというジャンルそのものの確立を意味している。もちろん、ことアメリカにかぎっても、すでにロックは存在していた。だが、それまでのロックはポップスのアンチテーゼという、「反」としての存在だった。キャロル・キングのロックは、時代遅れになりつつあったポップスというジャンルを吸収した上で成り立つロックである。
ポップスからロックへの移行をこの「Writer」ほど象徴的に表しているアルバムもないだろう。「Writer」の登場は、キャロル・キングという天才ライターのロックミュージシャンへの変化を意味するだけでなく、ロックというジャンルそのものの確立を意味している。もちろん、ことアメリカにかぎっても、すでにロックは存在していた。だが、それまでのロックはポップスのアンチテーゼという、「反」としての存在だった。キャロル・キングのロックは、時代遅れになりつつあったポップスというジャンルを吸収した上で成り立つロックである。
ではこのアルバムの何がロックと呼ばせるのか?まず明らかなのは「Writer」というタイトルが示しているSSW(シンガーソングライター)という、個人を出発点とした音楽制作スタイルである。ポップスが担っていた、作曲家と歌い手という、職人の分業体制によって担われるビジネスではなく、個人の発露として音楽が生まれることがロックである。
そして個人の発露というのは、キャロル・キングの場合、その唱法にある。いや、彼女は、意識してこのように歌っているのではないだろう。その歌は、一本調子で、はりはあっても、ふくよかな陰影はない。あくまでもストレートで、ただ声がのびるにまかせるような歌い方である。言ってしまえば職業歌手としては失格なのだ。しかしこの不器用なストレートさは、ピュアであることの裏返しだ。キャロル・キングの最高傑作といってもよい「The Carnegie Hall Concert - June 18 1971」で、この瑞々しい歌声は十分に満喫できる。
そして楽曲の構成であろう。アレンジの妙はいかされているが、何よりも心をひくのは、ピアノやギターの生の感触だろう。その意味でたとえば「Rasberry Jam」のような曲は、どんなにすばらしいアレンジを聞かせてくれても、このアルバムの中ではすでに「時代遅れ」である。そして時代の幕開けを飾るのはアルバムの最後の曲「Up on the roof」だ。「The Carnegie Hall 〜」で、ジェームス・テイラーという、もう一人のSSWとの美しいコラボレーションが聞けるこの曲こそ、70年代ロックを運命づける一曲であり、そしてこの時点でロックは、前衛や実験であることをやめた。
 ノイズに満ちた音で癒される。このアルバムで構築される音の渦は、ノイズと呼んでいいだろう。そのノイズの渦に身を浸しながら、癒されれていく体験がこのアルバムにはある。それはどんな感覚だろうか。2曲目は「静かの海」。深海で砂が何らかの拍子にふと舞い上がるときのかすかな音は、きっとこのアルバムで聞かれるような音に違いない。それは音楽とはいえない、たんなる音のかたまり。しかしその音こそが癒しをもたらしてくれる。そんな雑音がちりばめられたこの「The world is mine」は、くるりの最高傑作である。ここまで音響、音の破片でしかないものが、ひとつの音楽に結晶するなど、いったいどんな力量があればできることなのだろう。
ノイズに満ちた音で癒される。このアルバムで構築される音の渦は、ノイズと呼んでいいだろう。そのノイズの渦に身を浸しながら、癒されれていく体験がこのアルバムにはある。それはどんな感覚だろうか。2曲目は「静かの海」。深海で砂が何らかの拍子にふと舞い上がるときのかすかな音は、きっとこのアルバムで聞かれるような音に違いない。それは音楽とはいえない、たんなる音のかたまり。しかしその音こそが癒しをもたらしてくれる。そんな雑音がちりばめられたこの「The world is mine」は、くるりの最高傑作である。ここまで音響、音の破片でしかないものが、ひとつの音楽に結晶するなど、いったいどんな力量があればできることなのだろう。
しかしこのアルバムが恐ろしいのは、極端に音数が少なくなる瞬間があることだ。「アマデウス」は、たとえいくつもの音が聞こえるとしても、印象に残るのは単調なピアノの音色とヴォーカルだけだ。そしてもう一つの特徴は、メロディとリズムの反復だ。「Buttersand/Pianorgan」や「Army」は、うねるノイズだけで構成されている楽曲だといえよう。
しかしそんなアルバムの印象も「水中モーター」あたりから、ロック色が強まっていく。「水中モーター」のヴォーカルはスチャダラパー的なアプローチといってもよいが、そうした雑食性もまたくるりの楽しさである。「男の子と女の子」は、ハナレグミもカバーしているが、あきれるほどめめしい曲だ。そんなロックのストレートさは、「Thank you my girl」で最高潮になる。そして再びアルバムは、「砂の星」、「Pearl river」を辿って、深海へ戻っていく。たゆたう水のうねりがゆったりとはてしなく円を描く。
このアルバムが最高傑作と言えるのは、どう頭をひねってもシングルカットできない曲ばかりならんでいるからだ。どの曲もこの音の流れから引きはがすことができない。それほどの緊張感をもって作り上げられたアルバムである。
 エリオット・スミスの曲がとても生々しく聞こえるのは、それは「音楽が生まれる瞬間」に立ち会っている印象をとても強く受けるからではないだろうか?最小限の楽器。あらかじめ決まめられたリズムや、コード進行もないかのように、最小限のささやきと、ギターを刻む音で、音楽が始まる。エリオット・スミスが最初に浮かべたメロディそのまま、音はおさめられ、聞く者にとどけられる。だからエリオット・スミスの音楽を聞くと、本人の存在をとても身近に感じられる。エリオット・スミスの曲は、加工という作業からもっとも遠い。だから皮膚がすり切れるような痛々しいつぶやきまで僕たちは感じてしまう。
エリオット・スミスの曲がとても生々しく聞こえるのは、それは「音楽が生まれる瞬間」に立ち会っている印象をとても強く受けるからではないだろうか?最小限の楽器。あらかじめ決まめられたリズムや、コード進行もないかのように、最小限のささやきと、ギターを刻む音で、音楽が始まる。エリオット・スミスが最初に浮かべたメロディそのまま、音はおさめられ、聞く者にとどけられる。だからエリオット・スミスの音楽を聞くと、本人の存在をとても身近に感じられる。エリオット・スミスの曲は、加工という作業からもっとも遠い。だから皮膚がすり切れるような痛々しいつぶやきまで僕たちは感じてしまう。
およそ他人に聞かせることなど念頭になかったのだろう。おそらくはBasement tapesにおさめられたまま、誰にも聞かれずに忘れ去られていくはずだったろう。しかし本人の意図とは別に、「グッド・ウィル・ハンティング」のサントラ曲として、突然、広く知られることになった。その時の違和感は確かに、彼の素直な反応だったのではないだろうか。自分の独り言にも似たメロディが、人にも聞かれてしまい、気に入られてしまうという戸惑い。そんな戸惑いによってその後の生き方そのものを縛られてしまうミュージシャンは多い。ピンクフロイドのシド・バレットはロック(産業)の歴史の中で、その最初のミュージシャンだろう。そして同時代のカート・コバーンを思わずにはいられない。ただしエリオット・スミスとカート・コバーンはとても対照的なミュージシャンでもある。あくまでも内に沈潜していくエリオットに対して、カートはやはり攻撃的だ。たとえその攻撃が結局は自分に向かってしまうとしても。
タイトルもない、断片だけの曲。エリオット・スミスにとってはそれだけで十分だったに違いない。しかしエリオット・スミスは、自閉的な、自己満足の音楽ではない。彼の歌の中には、時に他人との深い関わりを感じさせる歌がある。そのときの彼のメロディは本当に優しい。
I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. (Say yes)
恋する彼女の目を通して、世界を見る。そんな風に他人と重なるような一瞬がある。たとえ淡く崩れてしまう一瞬でも、それを静止画のように切り取ることのできるエリオット・スミスは素晴らしい詩人だ。こうしたまなざしをもったエリオット・スミスは、これからもロックを聞く者たちに一番に愛され続けていくだろう。ロックの優しさをここまで純粋に感じされてくれるミュージシャンは希有なのだから。
 ソウルというジャンルはいったいどうやって分類されるのだろうか?ひとくちにソウルといってもその幅はきわめてひろい。たとえばリズムの躍動はソウルの本質だろうか。それはジェームス・ブラウンのようなきわめて個性的なミュージシャンに負うところが大きいのかも知れない。ソウルのもつ高揚感、グル−ブ感ならば、まずはマーヴィン・ゲイを思い浮かべるだろう。そして黒人の魂の訴えならば、単なるメッセージソングに堕することはなく、しかし政治的なムーブメントとして大きな流れを作っていくほどの力をもったアルバムを生んだカーティス・メーフィールドだろうか。ここまで黒人の名前ばかりを挙げたが、ソウルは黒人の専有物ではない。60年のロック草創期からすでにスティーブ・ウィンウッドのようなきわめてブラックな、そして質の高いソウルフルなミュージシャンがいる。その歌唱の素晴らしさは、「ソウル=黒人文化」というきわめて安易な図式を払拭してくれる。
ソウルというジャンルはいったいどうやって分類されるのだろうか?ひとくちにソウルといってもその幅はきわめてひろい。たとえばリズムの躍動はソウルの本質だろうか。それはジェームス・ブラウンのようなきわめて個性的なミュージシャンに負うところが大きいのかも知れない。ソウルのもつ高揚感、グル−ブ感ならば、まずはマーヴィン・ゲイを思い浮かべるだろう。そして黒人の魂の訴えならば、単なるメッセージソングに堕することはなく、しかし政治的なムーブメントとして大きな流れを作っていくほどの力をもったアルバムを生んだカーティス・メーフィールドだろうか。ここまで黒人の名前ばかりを挙げたが、ソウルは黒人の専有物ではない。60年のロック草創期からすでにスティーブ・ウィンウッドのようなきわめてブラックな、そして質の高いソウルフルなミュージシャンがいる。その歌唱の素晴らしさは、「ソウル=黒人文化」というきわめて安易な図式を払拭してくれる。
少し振り返っただけでも、ソウルの歴史は、さまざまな豊かな財産を持っているわけだが、97年にファーストアルバムを出した、このRahsaan Pattersonの音楽が、ソウルと呼べるとしたら、それはどんな意味だろうか?
まずはっきりしているのは、90年代以降のソウルの流れは、かつての黒人という人種的枠組みにもとづく、プロテストとしてのソウルとは根底から異なっているということである。また汗の匂いといった肉体性も、パッションを歌い上げるような魂の叫びもない。しかしそれでもなぜ彼の音楽がソウルとしてここまで人の心をひきつけるのか?
Pattersonのソウルの魅力は、緻密に練り上げられた、楽器それぞれの粒だった音の構成にあるのではないだろうか?たとえばソウルを聞きながら「快適」と言えるのは、そのストリングスのアレンジのバランスの良さにあるように思う。それは、ソウルが本来持っていた、情念とも言えるスピリチュアルな部分を抜き取ってしまい、メロディの妙だけで聞かせるイージーリスニングにも似たお手軽なソウルになってしまったという危険も意味する。
しかしPattersonの音楽が、そうした批判に耐えうるとしたら、それはまさに計算されつくした、楽曲のよさによる。それぞれの音が個性を持ちながら、うまくアレンジされることで、曲としての一体感を醸し出していく。音と音の間の取り方が、いわゆるグルーブを生み出していく。そこがかろうじてソウルなのだと言えよう。つまり徹底的に知性的な音作りをしているのである。天性の才能や、人間の激しい生き様を聞くのではなく、最高のスタジオ環境で、過剰になる部分は極力抑えながら、音を重ね合わせていくその妙を堪能するのだ。そうした音作りは、彼の男性としては、ずいぶん細くて、高音にいけばいくほど、金属質になっていく声質にとてもあっている。この中性的な声は、音のアレンジの中でほとんど楽器の一部として溶け込んでしまっている。いってみれば人工的なソウル。しかし音楽の楽しさは、なにも生身の人間らしさだけにかかっているわけではない。スタジオワークによってここまで完璧な音作りをしてくれれば、それは、ひとつのエンターテイメントとして、聞くに堪えると言えよう。
なお、Rahsaan Pattersonはこれまで3枚のアルバムを出している。デビューはRahsaan Patterson, 2ndはAfter hours。どのアルバムも素晴らしいクオリティである。
 このアルバムを聴くとちょっと驚くことがある。それは曽我部恵一の声が、とてもハスキーになっていることだ。ツアーのさなかで声が枯れてしまったのか?それとも彼の声は、シャウトするとこのようなしゃがれた感じになるのだろうか?憂歌団というには、そこまで成熟していないというか、成熟を拒否しているか、どちらかなのだが、いずれにせよ、観客への挑発という点では、かなり魅惑的な声質だ。それは曲と曲の間に入れられている、しゃべりの部分でも同様だ。当日ライブの場に居合わせた観客はもちろん、このライブアルバムを聴く者さえ、どんどん音楽のなかに引き込んでいく。
このアルバムを聴くとちょっと驚くことがある。それは曽我部恵一の声が、とてもハスキーになっていることだ。ツアーのさなかで声が枯れてしまったのか?それとも彼の声は、シャウトするとこのようなしゃがれた感じになるのだろうか?憂歌団というには、そこまで成熟していないというか、成熟を拒否しているか、どちらかなのだが、いずれにせよ、観客への挑発という点では、かなり魅惑的な声質だ。それは曲と曲の間に入れられている、しゃべりの部分でも同様だ。当日ライブの場に居合わせた観客はもちろん、このライブアルバムを聴く者さえ、どんどん音楽のなかに引き込んでいく。
サニーディ・サービスのころには、こんなしゃがれた声を聞くことはなかった。「東京」のクレジットに記された吉井勇という詩人の名が示すように、とても内省的で、叙情的な詩にふさわしい声。「江ノ島」に歌われる、ゆるやかなカーブ、平日の昼間の海といった、静謐さを歌うのにふさわしい声、それが曽我部恵一の声だったと思う。でもこのライブアルバムでは、たとえば「浜辺」のような、グルーブたゆたう曲でさえ、彼の声は枯れて、震えている。
そんな声質の違いが、サニーディ・サービスとソロになってからの彼の音楽の違いなのだと思うが、それでも変わらないところはいっぱいある。それはたとえば、「恋の始まり」。曽我部恵一ほど、「恋の始まり」を素敵にスケッチしてくれるミュージシャンもいないのはないだろうか。「恋に落ちたら」は、今日のデートで、おそらく二人は、お互いがすきだってことを感じるはず、だから、今家をでて、デートに向かう「僕」の心を歌う。「テレフォン・ラブ」は、相手が見えないのに、声だけは耳に生々しくすぐ近く聞こえてくる、「電話」。それはいざとなれば真夜中だって彼女の声がきけるのに、でもダイヤル(!)するには、とっても勇気がいる、そんな「恋」を歌ってくれる。
ちなみにこのアルバムの名義は「曽我部恵一Band」である。Bandってなんだろうか?それはアンサンブルなんだけど、それぞれのパートが勝手に自己主張するグループのことではないだろうか。そんな緊張感をここちよく感じながら、一気につっぱしって聴いてしまえる、イカしたライブアルバムである。
 ケヴィン・エアーズの曲には、「ブルース」とつくタイトルの曲が多い。この「夢博士の告白とその他の物語」にも2曲おさめられている。一聴すると、どの曲もブルースっぽいところはないのだが、エアーズが「ブルース」とつける理由は、おそらく、ロック調のめりはりではなくて、ルーズさが曲の魅力だいうことなのだろうか。とにかくルーズという言葉がぴったりな人だ。ソフトマシーンにいながら、さっさと脱退してしまう。髪の毛もぼさぼさで、かなりだらしないヒッピーの雰囲気である。カンタベリー系のミュージシャンには結構ポップ志向の強い人がいるが(たとえばホークウィンドのロバート・カルバート。名盤多し)、エアーズほど、能天気なポップアルバムを作る人もいないだろう。
ケヴィン・エアーズの曲には、「ブルース」とつくタイトルの曲が多い。この「夢博士の告白とその他の物語」にも2曲おさめられている。一聴すると、どの曲もブルースっぽいところはないのだが、エアーズが「ブルース」とつける理由は、おそらく、ロック調のめりはりではなくて、ルーズさが曲の魅力だいうことなのだろうか。とにかくルーズという言葉がぴったりな人だ。ソフトマシーンにいながら、さっさと脱退してしまう。髪の毛もぼさぼさで、かなりだらしないヒッピーの雰囲気である。カンタベリー系のミュージシャンには結構ポップ志向の強い人がいるが(たとえばホークウィンドのロバート・カルバート。名盤多し)、エアーズほど、能天気なポップアルバムを作る人もいないだろう。
しかしこのアルバムのポップさは、かなりシュールなポップさである。複雑な転調を繰り返すが、けっしてプログレのように壮大な展開にはならない、でもやはり直尺ものの曲。メランコリーな色調で心情にうったえるというよりも、こちらの頭の活動を鈍らせるような夢幻的なバラード。そんな一筋縄ではいかない曲がつまっている。
そして何よりもエアーズの魅力は、その低くて、やや鼻につまった声だろう。アルバム最後のTwo goes into fourは、その低い声で紡がれる優しい子守唄である。リンゴ・スターのGood nightと並ぶ最高のおやすみソングだ。
この後、エアーズのアルバムは、どんどん平板なポップへと流れていく。しかし、決してルーズさは失っていないし、ルーズな人間ならではの優しさをつねに持っているミュージシャンである。下北沢のディスクユニオンで、あまりきちんとチューニングしているとは思えないギターで数曲を歌い、その後サイン会までしてくれたエアーズは、ずっとほほえんでいた。九段会館のコンサートでは、すでに客席に明かりがつき、終了のアナウンスが流れている中で、何度もアンコールをしてくれた。アンプも最後には故障してしまったが、そんなことは関係なく、楽しそうにギターをひいていた。そんなケヴィン・エアーズを私はこよなく愛している。人から「聴いてごらん」と貸してもらったレコードで、もっとも深い印象を抱いたのがこのThe confessions of Dr.Dream and other storiesである。
 地方性を感じさせるミュージシャンがいる。くるりは京都の出身であり、様々な曲の京都を思わせる歌詞、ジャケットに使われる写真など、自分たちの故郷への執着を感じさせる。ただここではそのような地方への執着とは違う意味で、もう少し地方性ということを考えてみたい。
地方性を感じさせるミュージシャンがいる。くるりは京都の出身であり、様々な曲の京都を思わせる歌詞、ジャケットに使われる写真など、自分たちの故郷への執着を感じさせる。ただここではそのような地方への執着とは違う意味で、もう少し地方性ということを考えてみたい。
たとえば若き日の細野晴臣が、東京の自宅で舶来品に囲まれながら、銀座山野楽器で買ってきた最新の輸入盤を友人たちと聞きながら、曲をコピーするような都会性にたいして、音楽の情報といえばNHK-FMの番組しかなく、地元の県庁所在地に、一軒かろうじて輸入盤屋があるような地方性という意味ではない。くるりの世代であれば、そのような情報格差はもはやなかっただろう。ブリティッシュロックの30年を咀嚼しつくしたような楽曲を聴くだけで、彼らがおびただしい量の音楽に触れてきたことはすぐにわかる。
ここで考えたい地方性とは、東京へ出てきた人間が、地方の風土への感覚を、肌の感覚として忘れずに、自分たちの音楽へと組み込んでいく、その姿勢である。
このアルバムにおさめられている「東京」で、彼らはこんな風に歌う。
話は変わって今年の夏は暑くなさそう
あいかわらず季節には敏感にいたい
東京以西の人間からすると、東京ではよく三月に冬が戻ってきて、雪もちらつく風景をみることがあるが、そんな時に地方との差を肌で感じるような感覚である。自分の中はすでに春になっているのに、東京にいると、その肌に冷たい風がふいてきて、不意をうたれるような感覚である。
早く急がなきゃ飲み物を買いにいく
ついでにちょっと君にまた電話したくなった
日常の切れ端のなかで、かつての自分の生活の場所を思い出すようなスケッチである。東京での生活の中で、「ついで」でするようなこと、「忘れてしまって」思い出せないようなこと、それが、心を強く締めつける感覚。電話の世界は、きっとすでに遠い世界なのだろう。でもそれが切れ端の間から、ふと痛みをもって、戻ってくる。
岸田繁のこの曲でのヴォーカルは激しい。彼のすきっ歯から、絞り出されてくるだけに、いっそうその声は、切実さを帯びる。いったい彼の黒めがね、やせ細った頬、分厚くて紅い唇、そして歯並びの悪い口ほど、ロックっぽいものはあるだろうか。
そしてこの曲の最後のさびの「ぱ、ぱ、ぱっぱぱっぱ」というコーラスを聴くと、実に仲のよいバンドなのだと思ってしまう。
このファーストアルバムには、『アンテナ』以降ふりきった、屈折が痛ましいほど感じられる。でもくるりの最高傑作は『The world is mine』です。
 ニール・ヤングのライブアルバム「Live Rust」は、その前作「Rust Never Sleeps」のツアーから収録された。「Rust〜」はヤングからの「パンクへの回答」と表現されることが多い。このアルバムのA面はアコースティック、B面はエレクトリックで構成されている。確かにこのB面のエレクトリックな曲調の激しさは、ロックがもつ緊迫感、「明日を生きられない」といった性急さを、見事に表している。それをパンク世代ではなく、60年代後半からアメリカン・ロックを生き抜いてきたヤングがしたことに、大きな意味がある。
ニール・ヤングのライブアルバム「Live Rust」は、その前作「Rust Never Sleeps」のツアーから収録された。「Rust〜」はヤングからの「パンクへの回答」と表現されることが多い。このアルバムのA面はアコースティック、B面はエレクトリックで構成されている。確かにこのB面のエレクトリックな曲調の激しさは、ロックがもつ緊迫感、「明日を生きられない」といった性急さを、見事に表している。それをパンク世代ではなく、60年代後半からアメリカン・ロックを生き抜いてきたヤングがしたことに、大きな意味がある。
パンクとは果たしてそれまでのロックへの否定、断絶だったのであろうか?今から振り返ると、そうした「否定、断絶」といった衝撃度は、むしろショービジネスとして演出されたものという面が強い。たとえばピストルズの曲なども、今から聞けば、いたってポップ、言動に反社会的印象がつきまとうとしても、音楽的には、既存の音楽の破壊といった斬新さは認められない。つきつめていえば、パンクは、ロックがそれまで標榜してきた「否定、断絶」といったものを、ファッションのレベルで、パロディ化してしまったものではないだろうか。そして、もしロックの存在価値のひとつが「否定、断絶」にあるならば、まさにそれはヤングが70年代に実践してきたことである。
ヤングの場合、「代表的なアルバム」というのが挙げにくい。まずどのアルバムも似ていない。毎回やることが違うのである。そして、アルバムを単位として聞くというよりも、ひとつの曲の緊張感に対峙するという、聞き方をせまられるのである。この決して一カ所にとどまることなく、常にぎりぎりの切迫感をもって、ロックミュージックを作り上げてきた、この態度こそ、ヤングが「パンクへの回答」としたものではないか。
このライブアルバムもアコースティックから始まり、そしてエレクトリックへと展開していく。しかしある曲をアコースティックで仕上げるか、エレクトリックで仕上げるかはたいした問題ではないだろう。それは「My, My, Hey, Hey」、「Hey Hey, My, My」の2曲が端的に示している。Suger Mountainの澄み渡ったギターの音色も、Powder fingerの大音量のバンドのアンサンブルも、どちらであっても、会場に張りつめる緊張感は変わらない。