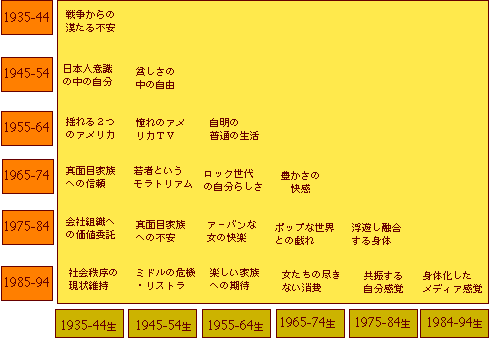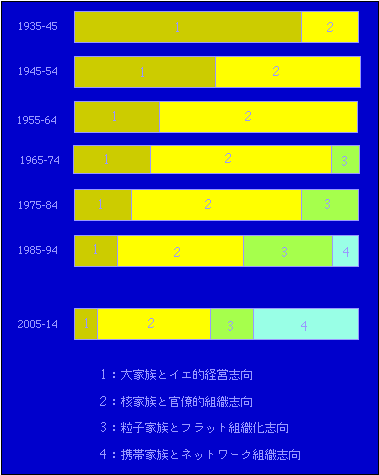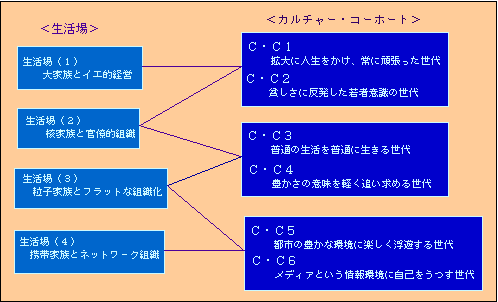|
||||||||||||
| 2−3カルチャー・コーホート(C・C)別の期待と関心 C・Cの視点から、生活情報を歴史的に読みかえるとどうなるのだろうか。同じ時代を共有しても、C・C(=世代)の違いが、その時代性の解釈を異なったものにしていることが分かる。以下、C・Cごとに、どのようなライフスタイルが時代とライフサイクルとの関連で描かれるか、を検討する。 (1)C・C1:(1935ー44に誕生) 「拡大に人生をかけ、つねに頑張った世代」 このC・Cは、軍事的な拡大のヴィジョンのその挫折を、誕生から10代にかけて経験してきた世代であり、戦争体験において漠然たる死の不安感を身近に感じ、その後の敗戦にあっては絶対的な貧しさを体験した世代である。しかし戦争体験も、まだ幼児期のものであるために、社会環境からの無意識な不安感を刷り込まれたことはあっても、戦地に向かった世代とは違うので、その意味では、より前の世代とは違った戦争体験であろう。意識化された実体験としては、敗戦後の貧しさと自由の解放感の方に大きな記憶の重さが残っていよう。食糧難やDDTの身体散布などの貧しさの極致の体験が一方にあり、他方、敗戦から立ち直る過程での大人達の力強い生き方に新しい自己の再形成のきっかけを見つけたことであろう。古橋の世界新・湯川博士のノーベル賞受賞・白井義男の世界チャンピオン、そして力道山の活躍は、この世代の日本人としてのアイデンティティの回復にも大きな貢献をした。この過程で獲得した自我がその後の拡大のヴィジョンを先導する原動力になったのであろう。 このC・Cは、戦争での挫折を、経済的な拡大のヴィジョンを達成することで、解消するように、夢中になって働き、高度経済成長を支える主役になっていった。かれらには、明確なモデルがあった。アメリカは、政治・軍事的な意味で圧倒的な権力を発揮すると同時に、生活と文化において、ここでも圧倒的な豊かさのイメージをもたらす国であった。安保反対と太陽族は、「反米なのに、アメリカに追いつけ追い越せ」を目標にする、この世代に共有されたジレンマであった。 このジレンマにあっても、社会システムの仕組みにかんしては合意された了解があった。それが、組織(大企業)と核家族への信頼である。いまでも、その信頼は変わらないのが、この世代の特徴である。中年になり、経済成長に貢献した見返りに獲得した組織での高い地位に満足し、組織そのものが変容の状況にあっても、現状の枠の中で思考することが自明なのである。同様に、家庭にあっても、真面目な核家族の維持に信頼感をもち、自分の子供たちがもはや異なった家族イメージを抱いていても、それを理解できることができない。それだけ、既存の社会システムへの信頼感が強い。それが、この世代の基本的な生き方である。 (2)C・C2:(1945ー1954に誕生) 「貧しさに反発した若者意識の世代」 このC・Cは、敗戦後の貧しさを身体的な記憶として強くもつ。貧しさからの離脱が共有した目標であり、その点では、C・C1に共通した経験をもつ。しかしC・C1のようなアメリカへの歪んだ思いはなく、あるのはライフスタイルとしてのアメリカ文化への強烈な憧れである。10代に、テレビが家庭に浸透し始め、そこで流れたアメリカのミドルクラスの豊かなライフスタイルは、この世代の現実の貧しさとのギャップを意識させ、同時に憧れの距離を少しでも縮めることを迫った。ここには、その後の経済成長期に最後の先兵として組織で頑張ったという経験が強くオーバーラップしてくる。しかしその距離が絶望的なまでに長いことの意識はあった。それだけ、アメリカ文化がテレビでみせたミドルの普通の生活は、彼らにとっては眩しい夢であった。 アメリカ文化の洗礼は、このC・Cに永遠の若さへの信仰を植え付けた。自由な若者のライフスタイルは、この世代をとらえ、一方では社会的反抗をする若者をつくり、他方ではヤング・アット・ハートのライフスタイルをつくった。大学紛争とVANのファッションは、同じ若者のムーブメントであった。 このC・Cが、結婚し子供をもつようになると、若さでのこだわりとの間にジレンマが生じてきた。大人になれない世代に、家庭や子供の誕生は大人への変貌を期待した。だから、としをとることはこの世代にはつらい選択を迫った。また組織の中でも、ミドルになるほど、管理職への役割期待が迫られるが、ここでも適応は容易というわけではなかった。自由な若者意識から逃れない世代は、真面目な核家族に不安をもつし、組織でも素直に管理職の期待にこたえられなかった。にもかかわらず、時代の変化によって、もう真面目な家族ではなく、楽しい家族への変容が下の世代からもたらされると、そこにもなぜか適応できない、難しさが残った。それは、組織でのリストラが叫ばれた時には、かえって既存の組織に固執することと同じである。ここには、この世代が、豊かさの時代に生きるスタイルをもっておらず、貧しさに反発することにしか生きる方法をもたなかった悲劇がみられる。 (3)C・C3:(1955ー1964に誕生) 「普通の生活を普通に生きる世代」 戦後は終わったと宣言されたように、このC・Cには、すでに過去の二つの世代に共有されていたような絶対的な貧しさの悲壮感はない。同じ拡大のヴィジョンでも、経済的拡大に突入した時代に産まれ育ち、そして青春を迎えた世代である。この世代は、アメリカ文化のたいする距離感の取り方も、前の世代とはあきらかに異なる。かれらには、無意識のレベルでアメリカ文化が刷り込まれ、自分たちが若者に成長した時には、日本社会も大きく経済成長をはたしているので、アメリカ文化への距離感が、夢のような憧れといった遠い距離にあるものではなく、やや身近なものと認知されるようになっていた。かれらには、すでに普通の生活を普通に送れる素地が確立されていた。 同じ若者文化でも、反抗することで自由の主張をした前の世代と違って、都市のカタログ文化を素直に受けとめ、都市での楽しい生活を十分に堪能するのであった。都市のファッションは、若者らしさの表現であった。それが、かれらには普通の生活であった。 もちろん、まだ豊かさがあふれるような状況ではないから、実際には一部の若者に限られた現象ではあっても、そこでの豊かなライフスタイルは、都市化とカタログ文化の浸透によって、多くに若者に共有される「イメージとしてのライフスタイル」として重要な意味をもっていった。都市は、この世代から「消費し、イメージによっても消費し、そして快楽を享受する場」に変容しはじめた。東京は、この世代によって大きく変化させられた。田中康夫の小説は、都市を消費するガイドブックであり、商品カタログであった。 このC・Cが20歳代になって体現しはじめた、1975年あたりの都市生活のライフスタイルから、日本社会には、拡大ヴィジョンとはまったく違う新しいヴィジョンに共鳴するライフスタイルが出現した。これは、いままでの世代がもつ拡大ヴィジョンに貢献するライフスタイル(真面目に、無駄なく、我慢して、大きく)とは異質の新しいヴィジョンに共鳴するライフスタイルであった。それが「たのしく、ゆとりをもって、いまをいきて、じぶんらしく」という生き方であった。頑張るという言葉は、この世代から似合わないものになっていった。じぶんらしく、これがこの世代からの生き方の基本になっていった。 (4)C・C4:(1965ー1974に誕生) 「豊かさの意味を軽く追い求める世代」 東京オリンピックを知らないC・Cがここから始まる。高度経済成長のシンボルであり、日本人というナショナル・アイデンティティの最後の機会であった東京オリンピックを知らない世代には、もう貧しさの絶対的な実感はもうない。あるのは豊かさの問題であり、豊かな生活をどうすればいいのか、その模索がこの世代から始まる。 このC・Cがこの世にボーンインした時は、ユーミンが歌の世界に登場し、いままでの歌の世界とはまったく異質な、都会に暮らす普通の女の子の恋愛などのたわいのないライフスタイルが、圧倒的な支持を受け、豊かな時代への変容が若い女性から確実に起こり始めた時であった。またもちろん若い女性ばかりでなく、中流意識という言葉が流行し始めたのも、65年以降のことであり、それはその後、年々自明なものになり、日本人はすべて中流意識という常識までになっていった。その中流意識を実質的な生活感覚として支えたのが、新しい3種の神器であり、カラーテレビと自家用車の普及はその点で大きな意味をもっていった。これらの変化も、この世代が誕生した時の出来事である。このような普通の豊かさが、どんどん現実のものになって、目の前に並べられ、そのなかで生活することが自明だ、という環境で育ったのが、この世代なのである。 このC・Cが大学生になったころには、カーライフをはじめとしたさまざまな豊かさを表現する生活環境がかれらのライフスタイルにはかかせないものになっていった。それは、都市という環境がさらによってさらに増幅され、そしてバブルの時代の環境によって一層自明な望ましさへと拡張されていった。この世代こそ、もっともバブルの恩恵を素直に受けた世代であり、そのなかで、今までの世代には経験のない、多様な豊かさの前に自分の意味を問い直すことを迫られたのであった。しかしその問い直しを、自己のアイデンティティを徹底して問う、という重たい反応(アイデンティティ・クライシス)ではなく、じつに軽やかに、あたかも食べ散らかすように、意味の多様性を感得していったのが、この世代の反応パターンである。 「あしたのジョー」が終わり、長嶋が引退し、「モーレツからビューティフルへ」がはやり、ユーミンがデビューし、ドラエもんが創られた、そんな時代にボーンインした世代には、完全に貧しさの実感は欠落し、豊かさの意味を追い求めるところに、生きている原点があったのである。 (5)C・C5(1975ー1984に誕生) 「都市の豊かさ環境に楽しく浮遊する世代」 このC・Cは、高度経済成長を教科書の世界でしか知らない団塊ジュニアからはじまる世代である。日本が頑張ることでここまで成長してきた、という共有感覚をもてない世代が、ここから始まる。この世代にとって、東京はTOKIOであり、楽しさを消費されてくれる巨大な欲望装置であり、「なんでも望みをかなえてくれるドラエもんのポケット」である。「なんとなく、クリスタル」で、新しい都市のライフスタイルがマニュアル的に語られ、YMOが新しい音楽をかかげて、テクノポップの世界都市・東京を暗示し、「おいしい生活」が都市的な生活のあり方ですよ、と提案される、そんな環境のなかにボーンインし、ピンクレディをみて、「Dr.スランプ」をみて育つ。 このC・Cにとって、豊かな生活はすでに自明なものであり、その豊かさの意味を問うことが問題なのではなく、その豊かさの多様性のなかから、何を選択すればいいのか、その選択をサポートするマニュアルは何なのか、を悩むことが価値あることである。もっと軽く、もっと楽しく、いまある豊かさのなかを浮遊することに自分らしさをみつけるのが、この世代である。とうぜん、ある意味での保守性はかれらの特徴である。つぎからつぎへと、楽しみの対象を変えながら、その楽しみに浮遊する感覚からは逃れられない、という点で、その豊かさを保証する環境の現状維持には強い保守的なこだわりを示す。微細な楽しさをかぎわけ、その多様性を使い分ける手際の良さをもちながら、DCブランドしか評価しないといった枠を壊せないところに、この世代の消費=快楽指向と保守性という両面をみるのである。 このC・Cから、「頑張る」ことの本質的・歴史的な意味を理解できない世代が始まった、といえよう。団塊の世代が味わった「貧しさ、だから頑張る」という図式は、ここでは完全に過去のものにすぎない。しかもこの親の世代(C・C2)が、この新しい環境のなかで、自明と思っていた家族観(真面目な核家族)に揺らぎが生じ、みずからの生活基盤に疑問を抱かざるをえない状況におかれる。そんな生活環境で育つこの世代が、親の世代の家族をモデルにしないのは当然であろう。家族のあり方(脱核家族化・家族の多様化)が大きく変容するのも、この世代からである。 (6)C・C6(1985ー1994) 「メディアという情報環境に自己をうつす世代」 このC・Cがどうなるのか、わからないところがあまりにも多い。しかしつぎに期待されているヴィジョンが情報化だとすれば、そのヴィジョンを先取りする世代がすでに出現していなければならない。その先行する世代がこの世代なのだろう。とすれば、ファミコンのもつ意味は、想像を超えて大きい。ファミコンが家庭に入ることで、家庭のメディア環境化の方向はセットされた。組織にパソコンが導入され、組織の変革が叫ばれているが、それ以上に大きな意味をもつのがファミコンの家庭への浸透であろう。ファミコンで育つメディア・キッズには、新しい身体感覚が備わり、メディア環境に融合する形で自己の表れが確認されようとしている。自己はすでにメディアであり、自己と環境の明確な境界は曖昧になり、対象化された自己と内在化された環境との融合が始まる。メディア・キッズには、モダンの自己イメージはない、まったく異なった自分論が必要である。 このC・Cを扶養する親の世代は、C・C3である。親においてすでに、普通の生活が後退し、核家族が自明ではなくなりつつある。とすれば、この世代が期待する家族のイメージがどのようなものになるのか、その領域は核家族を超えて多様である。「ノーライフキング」で描かれたように、母子家庭は、ここではけっして欠損家族ではなく、あたらしい可能性を示す家族のひとつである。この家族は、多様な役割関係を内包しながら、状況に応じて多様な役割が演技される空間としてあるが、そもそも、それ以上に、共有する空間によって家族を規定することができない状況も、この世代にふさわしい家族として生じてこよう。いわゆるネットワーク環境のなかで、家族を考える必要性もここでは生じよう。そんな環境にあるこの世代は、その家族のあり方についても、まったく新しい概念が必要になる。情報化は、このような世代と家族の登場を期待しているのだろう。
|
||||||||||||