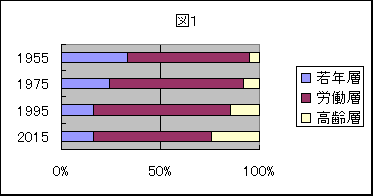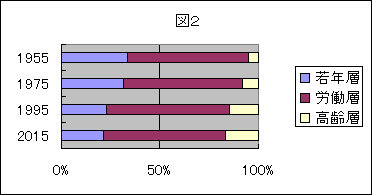|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2015年の成熟化問題 まず人口統計のデータを確認する。ここでは、1955年と1995年と2015年のデー タを比較する。図1は、その3時点ごとに、若年層(14歳以下)・労働人口層(15- 64歳)・高齢者層(65歳以上)の区分で、構成比を示したものである。 ここで指摘できることは、つぎの3点である。
※2015年のデータにかんしては、厚生省人口問題研究所の平成4年9月の将来推計人口を採用。 1:若年層は、55年?95年にかけて大幅に減少している。これが少子化である。しかしこれは95年までの現象であり、2015年にかけてはすでに横這いの状況にあ る。つまり少子化は現在の新しい社会問題ではあっても、20年後の問題ではない。 2:労働人口が一番多いのは95年である。55年との比較では、少子化は単純に高齢化にシフトしたのではなく、生産労働 人口と高齢化を同じ程度に増加させた。 3:2015年の問題は明らかに高齢化である。 これから20年の間で確実に高齢者層が増加し、それが生産労働人口の減少と表裏 関係になって進行する。21世紀の冒頭ですべての人が恐れるのは高齢化社会の到来という新しい社会問題である。
しかし、図2をみてほしい。これは3層区分を各年代ごとに若干修正したものである。55年のデータは図1と同じであるが、75年と95年のデータは、若年層を19歳までに延長し、労働人口を20-64歳に縮小した。これは、75 年以降ほとんどの若年層が高校卒であるという事実を考慮すれば、納得できるものであろう。若年層の定義を「労働に従事しない年少人口」とすれば、19歳まで 延長することはより現実に適合したものであろう。つぎに2015年の場合、さらに労働人口層を20-69歳にまで延長し、高齢者層を70歳以上に修正した。この場 合も、戦後生まれが高齢者層になる時には、65歳であっても十分に健康で、身体的 には仕事を継続することは可能だ、という前提を採用した。その結果が図2である。 ここでは図1と比較して、つぎの2点が重要である。 1:1995年と2015年はほぼ同じようなパターンになっている。1995年から20年間は、基本的には同じような傾向が続くということである。これは、高齢化を異常なまでに恐れる傾向(図1では9.6%の増加)とは対照的に、現在とほぼ同じ程度の高齢化率(図2では2.5%の増加)にすぎないとする解釈によるものである。この事実は非常に重要で、必要以上に悲劇的なシナリオを描く必要はないのである。 2)1955年と2015年の相違は、3層区分の定義を単に5年間高い年齢に延ばすという操作だけである。若年層を14歳から19歳にシフトし、高齢者になる年齢を65歳 から70歳に延長し、労働人口の期間はどちらも50年間に設定するにすぎない。これは 戦後の貧しい社会において、若いとき(中学卒)から仕事についた時代から、そこそこに豊かになってゆっくり仕事につけばいい(高校卒や大学卒)という時代への変化 であり、高齢者にかんしていえば、貧しい時には65歳になれば、もう体も弱体化して 仕事からの引退が自明だった時代から、豊かな生活のもとで高齢になっても十分に健 康を維持でき、70歳ぐらいまでならば、十分に働ける時代への変化そのものである。 以上から2015年を迎えるにあたって基本認識とすべきことは、5年間を高い年齢にシフトする社会システムをどのようにして描くか、という『成熟化問題』である。これが55年体制 の産業社会システムから、2015年のネットワーク社会システムへの構造変革の根幹である。その場合に、ネットワークがもたらす社会的意味合いを媒介として、ネットワーク社会がいかなる社会ヴィジョン(ネットワークコミュニティ)として描けるか、が問題なのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||