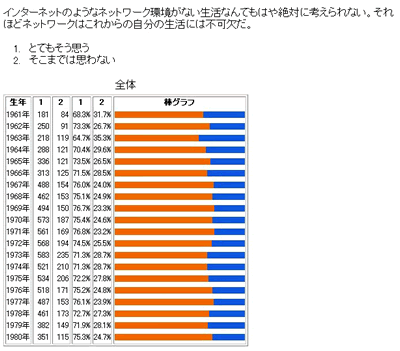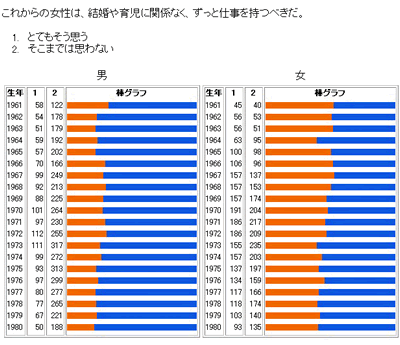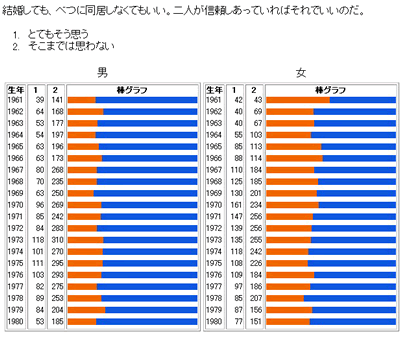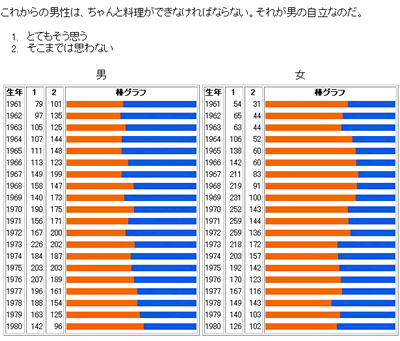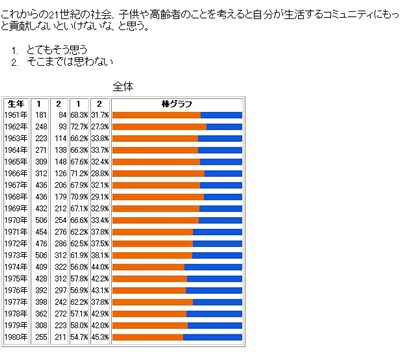|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.ネットワークコミュニティのヴィジョン 5)現実からの支持 上記の携帯家族の論理はどの程度支持されるか。現在、熊坂研究室でネットワーク上に公開しているサイト(iMap: http://www.imap.gr.jp/)に参加している約13000人の価値観を分析すると、つぎのような傾向がみられる。 1: 生活環境としてのネットワーク 「ネットワークは生活に欠かせない環境である」という意識はもはや自明のことである。世代を越えて70%の人が、ネットワークは生活のすべてに関与する生活基盤そのものであると意識している。これは携帯家族に不可欠な環境認知である。(図3)
(図3) 2: 仕事する女性 「女性は、結婚や育児に関係なく、つねに働くべきだ」という考えにたいして、ネットワークを活用する「女性」は、世代を超えてかなり強い支持を表明している。これは男性とは対照的である。女性は男性よりも携帯家族を支持している。(図4)
(図4) 3:別居する家族 「結婚しても、同居しなくてもいい」について、女性は男性に比較して、別居志向が強い。女性の場合、世代を超えて40%に近い数字が「結婚即同居」の考えを価値観として否定している事実は、ネットワーク社会になれば、より明確な携帯家族化への拍車がかかると思われる。しかしここでも、ジェンダーをめぐる争いは大きな社会問題になるだろう。ネットワーク化はあきらかに女性に共感されている。(図5)
(図5) 4: 家庭内の役割融合 「男性も料理ぐらいはできなければならない」という家庭内の役割融合にかんしては、男性も支持を表明している。とくに若い世代になるほど、男性は家庭内での役割融合を自明と思っている。男性でさえもネットジェネレーションになるほど携帯家族化を支持している。(図6)
(図6) 5: コミュニティ意識 「高齢者や子供のためにコミュニティに貢献しなければならない」というコミュニティ意識は、ジェンダーや世代を越えて非常に強い。自分の生活を、身近なコミュニティとの関連で考えようとする人々がネットワークに参加するほど強まる、と予感されるほどである。常識的にはネットワークを活用する人々は地域社会から遊離した生活を送るイメージがあるが、それは、このデータにみられるように、誤った認識である。ネットワークが生活に密着するほど、人々は自分のコミュニティへの貢献を考える。(図7)
(図7) 以上のデータ分析から、携帯家族のヴィジョンへの共感が得られている事実がある程度理解できよう。コンセプトしての携帯家族は、予想以上に、ネットワーク環境で生活する人々に支持されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||