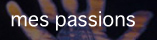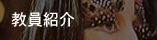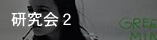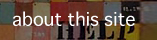覚書
本書は歴史家Mona Ozoufが一般向けに行なった講演を冊子にしたものである。この短い講演の趣旨は、Jules Ferry(1832-1893)の再評価である。
Jules Ferryといえば、第三共和制において義務教育の拡充をはかった人物であり、また同時に植民地拡張政策を推進した人物である。後者については、たとえばTodorovはその著書『われわれと他者』(nous et les autres)のなかで、わずかなページではあるが、全国民の文化水準を上げるための無償義務教育の政策と、教育と文明化の使命を帯びた植民地政策に連続性をみて、痛烈な批判をしている。
しかしながら、この小著では、当時、左右両派から非難を受け続けた政治家に潜む偉大さを掬いとる試みがなされている。
まず最初にFerryの生まれてからの政治家になるまでの足跡が簡単に述べられているが、この中で取り上げたいのは次のニ点であろう。第一点は、Ferryが旅行するなかで、イギリスの現実主義的な気質に触れたこと(p.13.)、第二点は、若いときに二月革命から第二帝政、すなわち「共和制の敗北」(p.16)に遭遇した世代であるということである。
こうしたFerryの若い時の時代を素描した後で、Ozoufは、Ferryには解くべき3つの謎が科せられたとする。1)中央集権化。ここでOzoufは、FerryがToquevilleにならって、政治的な中央集権と行政的な中央集権を区別し、国家に対して社会が自律して、「自由な議論と会合ができる体制」を重視していたことを指摘する。2)共和主義体制の不安定さ。3)フランスが孕む対立項。この対立項とは、フランス革命を肯定するのか、否定するのかという対立である。
この2), 3)の解決としてFerryが持ち出したのが、フランス革命と共和主義を切り離して考えるという視点である。そしてここでもOzoufが強調するのは、Ferryが、フランス革命における国民の単一性は結局専制主義的な形でなされてしまったのに対し、この単一性は、あくまでも自由において、たとえば出版の自由、地方自治や組合(p.31.)のような中間団体の設立さえも可能とする自由において、うち立てられなくてはならないと考えていたことを強調する。
この自由の確立において、教育の問題も考えられる。Ozoufの後半の主題はこの教育における自由の問題である。それは次のようにまとめられよう。
学校制度においては共同体の精神原理として、神という絶対的価値基準、すなわち宗教的な価値基準ではなく、フランスの歴史という過去の共同性を置くことが、フェリーの関心の中心となる。共和国においては、フランス革命によって根こそぎにされた近代ではなく、それ以前から脈々とつながる「フランス国民の魂」こそが統合の原理となる。したがってフランス革命時の共和主義移行によって否定された王や臣下たちが、歴史的な対象として学ばれる。すなわち、フランス革命による断絶を修復し、歴史による過去の共同性によって統合原理を構成するのがフェリーの目的である。教育こそ、19世紀以来なんども倒されてきた共和国を安定させる鍵であると、フェリーは考えていたのである。
この共同性さえ学校という公的な空間で構成できれば、宗教は、18世紀の啓蒙主義のように無知蒙昧の迷信、国家の敵とはならない。それどころか、フランスという国はキリスト教による安寧のもとに成立していることをフェリーは進んで肯定する。フランス人の心性がキリスト教にあることを認めているのである。フェリーはナポレオンによるコンコルダートさえ否定することはなかったのである(その破棄は1905年の政教分離法である)。このあたり、Ozoufは、Ferryの現実主義的な考え方を例証している。
では自由とは何だろうか。OzoufはFerryが女子教育にも力を入れたことを述べているが、その理由を次のようにまとめている。
Il s'agissait bien de former des femmes capables de partager avec leurs époux le goût de la discussion politique et le souci de l'éducation civique de s enfants.
女性を、政治的な話題への興味や子どもの市民教育への配慮を夫とともに分かち合えるよう、教育することが主眼であった。
つまり女性にplus de lumières「より多くの知性」とmoyens critiques「批判的方法」を与えることがその目的であったとOzoufは指摘する。
Ozoufは、Ferryのなかに自由と批判的精神が堅固に結びついていることをこの講演の主題としているのだろう。自由とは批判の精神である。ではcritiqueとは何だろうか。それは、このFerryの思想に従うならば、自ら思考し、相手にその思考を伝える言語化の技術であり、ある価値を鵜呑みにせずみずから検証する作業であり、そしてそうごにその意見を交わして議論するための知的活動である。そしてわれわれには、われわれの意見を書き、話し、議論する自由があるということ。Ozoufはこの自由の保証こそが、共和国を永続化させるための根本であるとフェリーが考えていたとする。そしてフランスという国家の単一性を自由の上にうち立てようとしたことに(p.61.)ことにFerryの独自性をみているのである。
『喪の日記』と題されたRoland Barthesの遺稿は、母の死の翌日から書き留められた日々の断章からなる。これらの断章は、330枚のカードに書かれて残されていた。Barthesの著作には頻繁に断章形式が用いられるとはいえ、この日記はそうした作品群に属するものですらなく、日記というよりも、むしろ「覚書」と言った方がよいだろう。いずれはこの断片から、喪についての作品が生まれるはずであったのだろうか。
日々の覚書は、ときに文ですらなく、単語が並べられただけの脈絡のない時もある。それらの単語は、自らの意味を見出すことなく、ただ母の永遠の不在のまわりにただようだけだ。ことばを「言う」ことはできる。しかし「表現」することはできない。それが実は喪の証しとなる。表現できるならば、それは「文学をする」こと、母を文学として語ることになってしまう。それはBarthesにとってはこの上ない恐れである(p.33.)。そもそも言葉にすることは不毛なのだ(l'insignifiance de notre verbalisation, p.260.)。
しかし、それでも記憶をとどめるものとしてBarthesは日記を書く。
Barthesはdeuilをnévroseという病理の状態と峻別する。フロイト自身はdeuilとmélancolieを分け、むしろ後者を病理的な症状とみなしているわけだが、それにもかかわらずBarthesは、フロイトを念頭においたうえで、deuilという言い方はあまりにも精神分析的だと言う(p.83.)。すでに『恋愛のディスクール』において、«Cette tristesse n'est pas une mélancolie»「この悲しみは鬱ではない」という文章に出会うが、日記の中でも喪の病理性は否定される。「母が生きていたときのほうが、母を失うおそれのあまり精神症にかかっていた」。そして「むしろ喪は、それゆえに神経症ではないのだ。むしろ母の死は、そうした病理を遠くへと追いやってしまったのだ」(p.140.)と。つまり喪は精神分析の対象にはなりえない、それがフロイトへの違和感の表明となって現れているのだ。
だが同時に喪が病でないということは、それは治癒できる対象ではないということだ。やはり『恋愛のディスクール』において、喪は「治癒」という進歩的なものではないと言われている。喪とは回復するものではないのだ(p.18.)。もし人間存在、人間の生の根拠が、可変可能性であるならば(人間は変わってゆく存在である)、喪の苦しみがやまないということは、「変わりはしない」という意味で、その人間が死んでいるというのに等しい。
他者の死は、自己の生を無化していまう。Barthesは言う。「愛していた人が死んだあとも生き続けるとは、思っていたほどその人のことを愛していなかったということだろうか」(p.78)。喪とは死者への後悔の念でもある。もしかしたら自分が思っていたほど愛していなかったかも知れないとは、それは死者への取り返しのつかない後悔となる。
先ほど述べたようにBarthesにとっては喪ということばは、自己の内面を「表現」することばとはならない。彼が何度も用いることばはchagrin「悲しみ」である。Chagrinと対立することばとして、やはり何度も現れるのがémotionである。
Chagrinとémotionはどう異なるのか。Émotionとは、自らの身体における動きであり、反応である以上、身体は受け身の状態にある。またそれは刺激である以上、ある緊張を強いたあとは、鎮まってゆき、また私たちを襲うような現象であろう。しかしchagrinは鎮まりはしない。「悲しみはすり減らない」のだ(P.81.)
その喪とは他者には見えないものだ。その人がどのような悲しみの淵にいるとしても、その悲しみを抑えて人は生きる。Barthesはいう「もっとヒステリックになって、沈鬱な表情を見せて、みなを追い返し、社会のなかで生きるのをやめてしまえば、私はそれほど不幸ではなかっただろう」(p.139.)それでも喪は内に秘められれば、それを示す外的な指標はない。
Au deuil intériorisé, il n'y a guère de signes.C'est l'accomplissement de l'intériorité absolue. Toutes les sociétés sages, cependant, ont prescrit et codifié l'extériorisation du deuil. Malaise de la nôtre en ce qu'elle nie le deuil.
社会は人々にその喪を外の表現することを、一定の儀式にのっとって喪を外に表現することで、喪の作業を遂行し、そこから回復することを強いるのだ。だから社会は喪を否定する。
ここに集められた断片は「覚書」に近い。だが、やはり覚書ではなく日記であるのは、これが日々の記録、その日のうちに書き留められたであろう記録であることだ。その集積の意味は、喪は決して終わらないということである。昨日と今日は違う一日だ。しかしそれでも今日も悲しみに浸される。日記とは終わらない喪である。
リクールは、この著書の第一部第三章で個人の記憶と集団の記憶の関係を扱っている。個人の記憶を語るにあたってリクールが援用するのがregard intérieur「内省のまなざし」である。そして「誰が」想い出すのか、という点に留意をすることのなかった古代ギリシアの思想家たちに対して、「内省のまなざし」の伝統の端緒に位置づけられるのがアウグスティヌスである。リクールは『告白』の第十巻、第十一巻を検討しながら、記憶と時間の問題が、個人の内面、において展開されることを述べる。
«C'est moi qui me souviens, moi l'esprit»(Ego sum, qui memini, ego animus. 山田訳は「記憶するのはこの私、すなわち心としての私です」。第十巻第十七章25)
アウグスティヌスの内面とは「苦しみの探究」に他ならない(une quête douloureux de l'intériorité, p.118.)。なぜなら告白の時とは、悔悛の時であり、その悔悛は、記憶と自己への現前における苦悩(「記憶なしには、私は私ということばすら発することができないはずなのに、その自分の記憶の力を、私自身完全にとらえることができないのです」山田訳p.352.)と結びつけられているからである。
リクールはアウグスティヌスの個人的記憶を語るにあたって、記憶の3つの特徴をまとめている。
1) 記憶は、体験と同じように共有不可能な単独のものである。
2) 記憶は人格の時間的同一性を保証する。ここでリクールはsouvenirとmémoireを区別する。前者は複数形で、それらが意味合いによって並べられたり、断絶がありうる。それに対してmémoireは単数形であり、時間を切れ目なく遡ることを可能にする。したがって、記憶は、souvenirが断続的であったとしても、そして現在の自己が、切り離されたsouvenirに現在の自己との異質性を認めるとしても、その異質な自己も自己であることを保証するのだ。
3) 時間の流れの方向性(過去から未来へ、未来から過去へ)を定めるのは記憶の働きである。
この3つの特徴によって、「内省のまなざし」の伝統がうち立てられる。そしてアウグスティヌスがこの伝統の最初に位置づけられるのは、キリスト教への改宗という内面的な出来事ゆえである。リクールは、「内省のまなざし」がその頂点に達するのはフッサールであるとし、ロックによって扱われるアイデンティティやカントによる「主体」といった問題は、アウグスティヌスには現れてはいないが、アウグスティヌスの重要性を記憶の分析と時間の分析を結びつけた点に認めている。
アウグスティヌスにおいては、「わが神は、わが内なる人間にとっての光であり、声であり、香りであり、食物であり、抱擁なのです」(第六章8)と言われる通り、神が求められるのはわが内面である。そして自己の内面とは、記憶の「宏大な広間」(第八章12)である。記憶は、宏大であり、かつ対象を想い出すとき、私はその時の私自身も想い出している。
とはいえ、記憶には忘却がつきまとう。記憶は「広間」であると同時に、思い出の「墓地」にもなりうる。この忘却を超えて、記憶の偉大な力を確信するも、アウグスティヌスは、神に達するためには、記憶すらも超えてゆくという。ここにも大きなアポリアがある。
«Si c'est en dehors de ma mémoire que je te trouve, c'est que je suis sans mémoire de toi ; et comment dès lors te trouverai-je si je n'ai pas mémoire de toi ?» (山田訳「もしも私の記憶の外にあなたを見出すのだとすれば、私はあなたを記憶していないはずです。けれども、もし私があなたを記憶していないとすれば、どうしていまあなたを見出すことができるのでしょうか」第十七章26)。
第十一巻で問題になるのは「時間の計測」である。時間とは流れてゆくものであるが、実際に計測可能なのは過去と未来である。ここでリクールはdistentioという概念によって現在を3つにわける。過去の現在=記憶、未来の現在=期待、現在の現在=注意である。アウグスティヌスも同じように言う。「それにしても現在の時は、測られるとき、どこから来たり、どこをとおって、どこに過ぎ去っていくのでしょうか。どこからーもちろん未来から。どこをとおってーもちろん現在をとおって。どこへーもちろん過去へです」(第十一巻第二十一章27)。
個人の内面における記憶と時間の関係。これを基礎として、リクールは共同の記憶へと考察を進める。
しかしそれは(人間が生の悲惨さから逃れ、救済されるということ)、普通の人間にはできない。えらばれた聖者が、清浄無垢の生活により、即身に救済を成就する。信者は、聖者の説教を聞き、聖者の行なう秘儀にあずかり、これに生活の資を供養することにより、聖者を通して救われる。(p.25)
イェルペルセンは、その著書『言語』の冒頭で、「言語の科学」の始まりは、言語が複数存在していること、言語の起源、言葉と物の関係などの問いが生まれたときであると述べている。この部分が、古代の、科学未満にとどまる言語考察の書き出しであるとはいえ、言語について考えを押し進めてゆくと、この始まりと有契(縁)性(motivation)をどうしても考えざるをえないのではないか。『言語』の第二部が子ども、第三部の第一章が外国人であるのは、最初は驚くが、子どもは言語を話し始めてゆく起源の問題、外国人は言葉と言葉が接触によって生まれる「誕生」と「歴史的変化」についての考えの反映なのではないだろうか。
西洋の18世紀は、まさに「言語の起源についての試論の時代」である(Droixhe, linguistique..., cité par Berbounioux, «L'origine du langage : mythe et thérie», p.20)。そして言語の起源をintrospection(感覚表現による言語の形成)と、interation(人間同士の伝達の必要性からの言語の誕生)の大きく二つに分類すれば(Cf.Bergounioux)、コンディヤックの言語起源論は前者の代表的著作と言えるだろう。1746年に刊行された『人間認識起源論』である。第二部第一章「言語の起源と進歩について」は、表題通り、言語の起源とその言語の変化を追っている。この言語の考察における感覚論をもっともよく表しているのは、コンディヤックが引用するロックの『人間知性論』の次の一節だろう。
「もし全ての単語をその源まで遡ることができるとすれば、どの言語の場合でも、感官にとらえられないような事物を表すために使われる単語が、その起源においては感覚的な観念から引き出されてきたということが、疑いもなく分かるであろう。そしてそれが分かれば、初めてこういう言語を話した人々がどのような類いの概念をもっていたのか、それらの概念はどこから彼らの精神にやってきたのか、そして彼らがそれらの事物に付けた名前そのものが、いかに雄弁に人間のあらゆる知識の起源や原理を問わず語りに示唆しているか、といったことがらについて、我々は推測を巡らせることができるのである」(p.133)。
これはコンディヤックが魂の運動を物体の運動の間に、人間が連関を見出していった過程について述べた箇所につけた注に載せられたテキストである。
まず物体の運動を受容し、認識する人間の感覚の働きがある。しかし人間の感覚の対象となるものは、外界の具体物だけではない。人間は、その外界の物体の運動と魂の運動とのアナロジーによって、分節音からなる抽象的な言葉を生み出していった。したがって、「もっとも抽象的な言葉といえども、それは感覚的な対象につけられた最初の名前に由来する」(p.132.)のだ。
このようにあらゆる名前が、起源においては具体的な形象をもっていたとするのが、コンディヤックの感覚論における言語発生論の基盤となる考えである。そして自己の魂の中でうまれているものにたいし、人間が名前をつけるのは、身体と深く結びついた「欲求」(besoin)による。
「感覚論」に根幹を置くコンディヤックの言語起源論であるが、しかし、よく読んでみると、そうとも言い切れない、様々なニュアンスを含んだ言語論であることがわかる。たとえば、冒頭第一章の言語の起源では、「情念の叫び声といくつかの知覚とが結びつく」ようになり、叫び声が、知覚の自然な記号となったと言うが、そのように魂が働くためには、二人の子どもが「相互に交渉しあう」(p.17.)ことが前提となっている。確かに、他者の苦しみを見るという知覚の働きから苦しみを感じ、その欲求から叫び声や身振りの言語が生まれてくるというとき、そこには感覚の受容があることは間違いがない。また、何かを伝えるという主体の意志がその動因となっているわけではない。しかし言葉の生まれる現場に他者が介在しているということは、言葉を生む人間は孤独な詩人のように単に外界のオブジェを、それへの反応としてのことばと結びつけるだけではないだろう。
進歩とは、叫びと身振りという、状況や対象と密接に結びついた言語から、恣意的な言語の発生への変化である(p.20.)。そして最初は叫びであった音は、抑揚をもった声へと進歩し、それが感情を素朴ではありながら表現することになる。そしてこの素朴な段階とは、模倣の段階である。
「様々な動物に付けられた最初の名前はおそらくその鳴き声を模倣したものであっただろうと付け加えることができよう。そしてこのことは、風や川、そして物音を立てる全てのものに付けられた名前についても等しく言えるであろう。こういう[物音の]模倣をするためには、非情にはっきりした音程差でもって音声が語られたであろうということは明らかである」
つまりここには自然を模倣し、その音そのものが言語となるというオノマトペとの親縁性を認めることができるのだ。
コンディヤックの言語論は言語一般についての考察だけではない。「風土」や「国民性」の問題も扱われている。たとえば、「北方に住む冷淡で粘液質の人々がこのようなアクセントや音節の長短を保持し続けることは、その気候[風土]が許さなかった」(p.83.)は、風土の違いによる言語の特質の違いという関係を前提としているし、第十五節は「諸言語のそれぞれの特質について」と題され、風土と政体による気質の決定について、モンテスキューの『法の精神』よりも2年前に説いていることは特筆に値する。またこの節では、その国民の国語の特質が、偉大な作家の助けを借りることなくしては、開花するに至らないとして文学言語の言語一般への影響を問うていることにも注目しなくてはならないだろう。メショニックが指摘するように、ここには典型的な「言語を問うことは文学言語を問うことと等しい」という命題の具体例を認めることができる。
最後に指摘しておきたいのが、言語と物の関係の進展である。まず身振りの言語の段階では、表現とは模倣でしかなく、細かい部分にわたって表現することは無理であった。したがって、人々は「貧しい言語」を使って、比喩にたよるしかなかった。冗語法は、適切な言語がないことから人々がたよった欠陥であったが、それは「粗雑の精神」には他に頼るものがなかったのである。つまりコンディヤックの描く言語の進歩とは音節言語の進展にともない言葉が豊となり、語彙が増え、観念と言語の一致が果たされることを意味するのだ。「必要な観念にそれぞれぴったりと合う単語が十分に整い」(p.96.)は、そうしたコンディヤックの言語観を集約した表現であると言える。そしてその意味でも言語の起源には詩と音楽が、社会的伝達の手段として人々の間に存在していたということが言える。文字の誕生は、そうした音楽や詩の機能を実用から喜びへと変化させる役割を担ったのである。
Vivant jusqu'à la mortは、Ricoeurの死後草稿のまま残されていた未完成の原稿を発表したものである。実際には1995年頃に書かれ始め、そのままにされたということであるが、死をimminent(切迫した)ものであると意識していたRicoeurの思考の姿がうかんでくる。ときに、覚書にとどまり、十分な展開はなされていない部分もあるし、言いよどみ、繰り返しも多いが、それゆえに、Ricoeurの思考の筋道を丁寧に追って私たちはこのテキストを読むことができる。
骨子のひとつは「生き残り」(survivant)ということだ。しかしそれは、最後の審判におけるrésurrectionではない。Ricoeurは物体として肉体そのものが最後の審判において復活するという「想像」は否定する。Préfaceを書いたOlivier Abelによれば、それは神話の解体であり、「報い、償い、罰という概念」の否定である。しかしそれは、ひとつの宗教の否定であって、宗教性そのものの否定ではない。死を生き残りとして問うことは、他者との関係を問うことであり(生き残るとは、私の死を超えて生き残る他者、他者の死を超えて生き残る私という本質的関係を定義する)、その他者とのつながりを考えるとき、そこには愛と倫理が生まれ、必然的に宗教的なるものへと近づいてくる。「想像」を否定するとは、宗教を否定することであっても、宗教性を否定することではない。
死は知りえないものであるからこそ、私たちの「想像的なるもの」が働き、死者の運命を問いかけざるをえない。また、死後のイメージは、あらゆる文化によって形成されてきた。私たちはこうして「死後」を先取りして、想像をするのだが、Ricoeurが批判するのが、この想像である。その批判の根拠は、私たちが人生の終わりまで生きる喜び、gaietéと呼ばれる生きることの欲求への配慮のためである。
次に考察されるのが、moribondという概念である。moribondとは人間をagonie(死への衰退)の状態として、すなわち直に死ぬ者として扱うことである。しかし重要なのは、encore vivant(まだ生きている)と、生の面をとらえることである。つまり、死後に存在するものへの配慮ではなく、生の最も深い源(les ressources les plus profondes de la vie)をとらえることである。Ricoeurによれば、grâce intérieure(精神的な恵み?どのように訳すべきか宗教的な含意がどこまで反映しているのか?)は、終末において、本質が浮かび上がることにある。これは告白を行なう宗教とは異なる、religieux commun(共通の宗教性?)であると言う。ここは難解なところだが、宗教であれば、それは歴史的、文化的事象として本質が限定されてしまう。そうした限定性から解放された真に深い場所にあるところの「本質」ということだろうか?死という現象が文化に限定されないこともあるが、ここには、告解という死にゆく者として、他者をとらえることに対するRicoeurの批判があるのだろうか。そして死に逝く者によりそいながら、その死に逝く者を、死者として先取りしてしまう(il sera mort)想像のあり方が批判されているのだろう。
では死に逝く者への視線とは、どのような視線なのか、Ricoeurは次のように言う。
C'est le regard de la compassion et non du spectateur devançant le déjà mort.
それは共苦の視線であり、すでに死者となっている者と先回りをして見つめる者の視線ではない。
Compassionーともにといっても同一化するわけではない。そこには友情という距離があるのだ。
それでは生者とともにいる(accompagner)者はどのような態度であればよいのか。ここで引用されるのがホルヘ・センプルンの『ブーヘンヴァルトの日曜日』(原題L'écriture ou la vie)である。センプルンがモーリス・アルブヴァクスをみとったときの証言である。Ricoeurは、Ricoeurはアルブヴァクスがセンプルンの手を握り返す場面に、「与えるー受け取る、まだここで」と注をつけている。人と人がお互いの生を確証する。生の根拠が他者によって与えられること、私は死んではいないことは他者との生の交感によって確証されることをRicoeurは指摘しているのではないか。
Ricoeurはさらにセンプルンが、死期のせまった友人によりそって、医学的でも、告解でも、詩の言葉をつぶやくことに着目する。「彼(アルブヴァクス)は微笑む、死にながらも、私を見つめて、友愛の」。Ricoeurはここに「本質」があるという。
この死と対照となる死が、カディッシュをとなえる「死」の苦悶の声である。Ricoeurは、センプルンが「死が歌っている」というのは比喩でもなんでもないという。なぜなら「みとる者なしに死に逝くことは、死者(moribond)と、人物となった死(mort)の区別をつけないことである」からだ。イディッシュ(死者の祈り)のことばが自分自身に向けられたものであるならば、そこにはユダや民族の歴史全体が集約されているとする。そして、「自分自身」にむけられたということは「与えるー受け取る」という行為を可能とする外部が(レヴィナス)不在であるということだ。
Moribondとmortの区別がつかなくなった状況、それはmasse indistinctな状況である。ここでRicoeurはセンプルンの選択を問題にする「書くことか?生きることか?」生きるとは忘れることであり、思い出すとは書くこと、語ることであるが、それは生きることを阻害する。なぜならば、死こそが現実であり、生は幻影に過ぎないからだ。この状況を生み出すのは、死というものが、絶対悪のしるしのもとに置かれたときである。友愛と絶対悪の二項対立、これがマルローに言わせれば、最も古いキリスト教の対話である。ならば悪がなければmoribondとmortの混濁はないのか?悪の問題で看過しえないことは悪とは体系化できないということである。どちらがより悪か、といった比較はできないし、個別の事象から総体を作り上げることもできない。だが、神学においてはあらゆる死が、暴力的な死として同一視されているのではないか。罪を背負って死ぬということである。これがRicoeurが、1)死後、2)死に続いて、批判の対象としてとりあげる3)絶対的悪による集団としての死である。
Ricoeurはここから「いったい、普通の死は、どのような状況下で、極限の死=恐怖の死に汚染されるのだろうか?」。ここで「恐怖を悪魔払い」するものとして出てくるのが、「記憶の作業」、「喪の作業」である。ここで再びセンプルンの書くこと=思い出すことに焦点があてられる。死から生還したもの、すなわち証人となった幽霊である。
だがここでRicoeurが引用しながら、言及していない点を考えなくてはならない。それはこの書くことというのが、センプルンによれば、「文学的エクリチュール」として可能だと言われており、またその意味が«Avec un peu d'artifice»と言われていることの意味だ。文学的エクリチュールでなくては、たとえば宗教的な祈りのことばという内部化された「与えるー受け取り」のないエクリチュールになってしまうだろう。しかし文学がartificeであるならば、それは、物語の留め具として、つまり、物語を理解可能とするための留め具として使われてしまう危険を意味しないだろうか。誰もが想像しうる物語とは、artificeというわかりやすい虚構仕立てをするということではないだろうか。
もちろん書くことが、死者についての記憶を回復することであり、忘却から生き延びることが、実は自分の生を危うくするというこの悪がもたらす矛盾に書く者をさらし続ける。Ricoeurが引用するように「収容所を<現在>として語ること」ができないならば、なおのこそ、文学的エクリチュールの孕む「物語」のあやうさを、もっと緻密に分析するべきではないのか。
しかしRicoeurの本論での意図は、死後という問題を、宗教によらず、また宗教がもたらす死後の想像的形象によらず扱うことにある。その意図から、この表象の難しさを、死の瞬間の形象の難しさへと転用する。だからこそ、Ricoeurは死から生還してきたrevenants(死から戻ってきた者=亡霊)という名のsurvivants(生き残り)に、集団としての死の先取りを読み取るのだ。
Ricoeurは自問する。センプルンは生きることと書くことを両立することができた。レーヴィにはなぜ不可能だったのか。ここでティリッヒのThe courage to beへの言及があるが、書き込みだけで終わってしまっている。
最後に、先ほど述べたartificeについて言及がなされる。
Si l'écriture a quelque chance de se réconcilier avec la vie, lorsqu'elle est au service de la «mémoire de la mort», tout n'est pas attendu de la technique du récit, de l'artifice.
もし書くことが、現実の生と和解できるなにかを有するとしても、そして、書くことが「死の記憶」に役立つとしても、すべてを物語の作法、技巧に期待することはできない。
Ricoeurは「記憶が記憶の作業と喪の作業をひとつにあわせなくてはならない」という。Ricoeurにとって、それは集団の中に消滅してしまう死から(これは、自己の消滅の問題ではなく、死後の生という人間の想像を問題にしていると思われる。これは文化的事象とはいえ、こうした死の捉え方をするのは、自己の死を想像する自己の問題になるのだろう)、死を救い出すのは、この死の記憶でしかないという。ここも解釈に慎重になるところだが、喪の作業とあわせるということは、自分の死との関係において生き残る他者に自己の死後の生をゆだねるということだろうか。それが悪から解放された死の位置づけということになる。ならば、悪そのものとはどのような対峙をすべきなのだろうか。ここについてはRicoeurの「悪」として洞察を深める必要があるだろう。
他者という問題。最後に触れられるのが他者という問題である。それは「書くことが自己を抑えながら自己からの離脱する方法であり、それはつまり人が常にそうである他者の存在をみとめ、その存在を生み出すことで自己自身であるということだ」。書くことがどれほどの困難であっても、non-dit「言うことのできないもの」=沈黙でないという一点で、希望を持ちうる。記憶の作業、喪の作業は、この希望のことばでならなくてはならないとRicoeurは言う。つまり書くことへと至らせる根拠はfraternité(友愛)なのだ。
子供時代の読書の回想から始まり、私たちは、その記憶の風景に瑞々しい感覚の充溢を感じる。しかしこのエセーが読書論である限り、この作品の中心は知性の働き、思想の創造的な構築にあるのではないだろうか。
プルーストは、ラスキンの講演に同意するかにみえて、実は会話にも比せられるラスキンの教養としての読書とは異なる、読書の観念について語っている。それは、読書とは会話とは異なり、「他の一つの思想からコミュニケーションを受ける」ことであり、そのためには読者は、強靭な知性を持っていなくてはならない。それは、単に自己の精神を深めるということではなく、他者から思想を受け取った上で、それを知性によって深めながら、自らも思想を創造してゆくーそこに至ってはじめて読書の価値があるということではないだろうか。
読書とはしたがって読んで終わりではなく、あくまでも出発点である。書物とは読者にとってあくまでも「うながし」なのだ。「われわれの叡智は、著者のそれの終わるところで始まる」とプルーストは言う。思想を創造してゆくとは、自らの知性の営為であり、だからこそ、書物に回答はなく、私たちには、読書の後に、回答を求める欲望が生まれてくるのである。「読書は精神的生活の入り口にある」のだ。自分で考え、独創的活動をしない以上、読書とは結局無駄ではないのか。書物には真理があるのではなく、真理の予告があるだけで、真理は、読者の「生人の個人的な創造」によって生まれるのである。知識で頭を虚しくするという表現が浮かんでくる。それは知性の頽廃と言ってもよいだろう。
最後にプルーストは古典の意味に触れている。そこには「もう二度と作られることのない美しいもの」があると。過去の名残、廃棄されたことば。失われた美に私たちは読書を通じて出会うのである。
プルーストのテキストはいつも格言で満ちているが、この作品にも次のような言葉があった。「われわれ生者はみな、まだ職務についていない死者にすぎない」。
「ニオベの病」ー子どもの死を嘆き悲しみ、石となる母。この小説における、子を失い、永遠の喪に服そうとする母も、その思いの強さのあまり石となり死んでゆく。
L'Inconsolable「慰めようのない」と題されたこの小説の主題はしかし、喪からの回復の困難さ、死を憧憬する母の存在、あるいは悲しみの永遠性といったものではない。母の感情はもっと激しい起伏をもち、その激情で他者を切りつけ、自己をも苛む。息子の死という出来事以降、その死を軽んじる近親者を責め続け、またその死によって、他者とのつながりがすべて欺瞞であったことが暴き出された自己の卑小な存在も責め続けること、この鎮められぬ母親の感情こそが、tuで最初から最後まで語られる物語りを支配している。そしてその感情の強度と、tuという冷徹な呼びかけのコントラストが、喪に服すことは母親の美しい感情の現れであるとか、思い続けることの切なさであるとか、そうした道徳的な語りをすべて排除し、喪という出来事自体の非情さを強く訴えてくる。
息子の死を想起することがひとつの「強迫」となる。だが、このtuによる語りで、「強迫」の凄まじさは、母親の想念がどこまでも果てしなく続いてしまうことにあるように思われる。息子の命日に、誰の電話もかかってこないが、母は想念をどこまでも続ける「誰かが、今日がその日だと思いもよらずに電話をしてきたとしよう。こちらもそんな相手にあわせてくだらない会話を続ける。震える喜びを感じながら。相手は電話を切ってから、ひょっとして今日は、と考え始める。だが、電話での会話でそんなそぶりを見せなかった以上、相手は困惑するだろう。だが、いや今日だったのだとわかってくる。とはいえ、もう一度電話をかけたりはしないだろう。いったい電話をして、忘れていた、思い出したなどといえるものか。だから相手はこう考えるだろう。いやその話をしなかったのは単に直接切り出すのが、ぶしつけだからだと」(p.15.)こうした想念が果てしなくずっと続いてゆくのだ。あたかも死を想うことが、自己の生の根拠をつくり出すかのように。
想念の羅列は随所に現れる。たとえば家族のアルバムを取り出して、写真に語りかける。「ほら、この人のこと覚えている?子どもに本当にやさしかったわ。(...)」この語りも際限なく続けられる。この反復が底知れぬ「強迫」を作り上げてゆく。
反復は死の原因をめぐっても母を襲ってくる。死はいかに自分が息子のことに無知であったかを知らせ、その原因は、「なぜそれを知らなかったのか」という決して取り返すことのできない、無限の出来事の集積から、後悔となって現れる。いじめ、音楽、家族。そうしたモチーフが連鎖して語られ、やがては結局、自分自身の存在そのもの、とくに自分の無理解に息子の死が結びつけられるのだ。さらに瀕死の息子をそのまま死なせたことがひとつの後悔となって何度でも戻ってくる。
そしてもうひとつの反復が、息子の死を忘れ日常を平然と生きている、他の子どもたちへの攻撃である。死の間際において、自分の死後もひとつの圧迫になるよう、書くことによって言葉を残そうとする。
やがては喪に服す者にも死が訪れる。その死は最終的な忘却だ。「ある日いつも通り、それほど疲れているでもなく、目が覚める。しかし、なにかちょっとしたことを忘れているような気がする。だがそれが何であるかはわからないだろう。ただ、何かとてもはっきりしたもの、それまで他人や自分を判断するのにそんなものを持ち合わせていたなどと気づいてもいなかったものを失った気がする」だが、そのときでも「慰めようもない」ことにずっとよりそっていようと思うだろう。人間の生の欲望は、回復の欲望ではなく、回復しないことのパッションから生まれてくると思わせる結末である。
アメリカの心理学者ジョン・H・ハーヴェイの『悲しみに言葉を』は、喪の作業において、体験の言語化が、どのようにその悲しみから人を立ち直らせるのか、幅広く検証した研究書である。その意義のひとつは、悲しみから立ち直ることは、その人を成長させるといった、体験を踏み台にし、喪失を自明のものとする考え方ではなく、「喪失を意味づけることによって、何か肯定的な事柄を他者に伝えること」に重きをおいている点である。
喪において成長は必要不可欠ではない。それよりもむしろ他者とのつながり、ある場所を共有すること、そしてさらにはそれが何らかの共感(理解ではなく)へと至ることが、喪を避けることのできない必然として生きる人間にとって重要なことなのだろう。
こうした喪の意味づけが、たとえば精神療法において、その人間の生の尊厳を回復するという意味においてなされる限り、意味づけは、慎重にそして最大限の思慮をはらってなされるべき営みであろう。
ハーヴェイは様々な喪失体験を挙げているが、ここで考えたいのがホロコーストと戦争における喪失体験である。この喪失体験は、いかにこうした惨禍が起きないようにするのか、すなわち個人の回復の次元を超えて、私たち人間全体の課題としてここでは挙げられている。
戦争においては個人の体験と、歴史的意味がときに激しく緊張関係を持って切り結ぶことになる。心的外傷が明るみに出されたのも、戦争に狩り出された兵士たちの戦争体験からである。ハーヴェイは戦争体験者たちの証言を取り上げながら、喪にことばを与える彼らの言動に大きな尊厳を与えている。たとえばつぎのような具合に。
恐ろしかったのは確かです。でも、崇高な大義のために戦っていることがわかっていたので、恐怖に打ち克つことができたのです。
自分自身よりもほかの人間のことを思いやる。誰かのために自分の命を捨てることができるーこれが勇気というものでしょう。
これはノルマンディー上陸作戦に参加した兵士の証言であり、50周年の記念式典に際して、ハーヴェイ自身が立ち会って聞いた声である。この声にたいしてハーヴェイは「こうした記念行事は、(...)新しい人生、意味、希望を含み込むことになるのである」と述べている。(以上、引用も含め、『悲しみに言葉を』p.190-191.)
記念するとは、喪の行為に対する50年たってからの「新しい意味が付け加えられた」ということだ。ハーヴェイは続けて、この新たな慰霊碑は、人々の「集合的な記憶のイメージそのものだ」と付け加えている。
だがここでさらに付け加えて言わなくてはならなかっただろう。「集合的な記憶は、歴史とは異なる」と。「集合的な記憶は、体験の正当化には役立ち、それがひいては個人に希望をもたらすかもしれないが、それは、あらゆる正当化は歴史の営みとは本質的に異なり、無反省な混同をときにはもたらしてしまう」のだと。
私たちは歴史と記憶とを混同してはならないと思う。歴史とは出来事を人間の共同性の次元でとらえたものだと、おおまかに言ってしまうならば、歴史とは、記憶に依拠することが、個人がその体験の記憶を想起することが、そのまま他者の記憶と接触し、交渉することが必然となる場所である。この他者とどのような形であれ関係性を成立させてしまうのが、歴史という共同性の必然ではないか。そうでなければそれは歴史という名では語れないだろう。
戦争体験においては、個人の自らの体験の意味づけが、歴史という共同性の確立において否定されるということがおきる。それは、戦争が、死者の死を蹂躙し、生者の生をも否定する、その意味で人間性を破壊する出来事であることを訴えている。だからこそ戦争の記憶は時に隠蔽され、だからこそ、個人の証言が大きな意味をもつ。この個と共同性の記憶と意味づけをめぐる矛盾こそが、戦争の歴史の難しさだ。死の問題を避けない以上は、この矛盾は必ず私たちの前に立ち表れてくるのではないか。
この論議を、アイマンの記憶についての考察を助けにして考えてみたい。
第6章では、それまでのロックやワーズワースを引用しながら想起とアイデンティティの連関を探究したあと、この同じ連関を社会学、歴史学において検討している。ニーチェ、アルヴァックス、そしてノラの名前を挙げたうえで、かれらの記憶理論に、「想起の構成主義的で、アイデンティティを確保する性格」が強調されているとする。
想起・構成・アイデンティティと個人と共同性の歴史意識をめぐる問題がこの三語によってかなり明らかになると思われる。
想起とは、フロイトの事後性によって説明されている。事後性とは、「知覚された対象は、想起の行為において初めて、つまり、場合によっては数年後あるいは数十年後になって初めて解釈される」という意味である。「フロイトは、記憶の痕跡(注:これは全体を持たない破片、意味づけを欠いたイメージとして理解できるだろう)を活性化することを書き換え」と呼んだが、体験の50年を経ての意味づけはまさにこの書き換えであり、戦争の知覚は、50周年の記念行事によって、解釈され直されるのだ。
構成とは、下記にみる機能的説明で整理されているように、「ある部分を想い起こし、ある部分を忘れる」という「選択的」な振る舞いによって、想起が成立することを意味する。
そしてアイデンティティとはまさに、この想起の構成主義は、アイデンティティを保証する重要な作用だということだ。戦争体験者は、みずからの体験をまさに構成主義的に想起することによって、みずからの生を意味づけ、人生を肯定する姿勢が生まれてくる。
さらに、この想起の構成主義は、個人の想起のメカニスムだけではなく、この著書の中心的課題である文化的記憶についてもおなじ作用が働くことが指摘される。
今ここで、アスマンがモデルとして提出している記憶の二つの作用、機能的記憶と蓄積的記憶を整理しておこう。ただし、アスマンの力点はこの二つの記憶の間でたえず流通が行なわれているとするパースペクティブに置かれていることに注意すべきである。
機能的記憶とは、住まわれた記憶とも言われているもので、i)集団、機関、個人であれ、何らかの担い手と結びつき、ii)過去、現在、未来を橋渡しし、iii)選択的な作用をもち、iv)アイデンティティの輪郭を描き、行為に価値を与えるとされる。個人の記憶として考えれば、「思い出や経験を一つの構造につなぎ合わせ」、「形成的な自己像として生を規定し、行為に方向性を与える」。したがってある主体(個人であれ、共同体であれ)は、機能的な記憶によって、過去を取捨選択し、ひとつの時間性を描けるよう出来事を再構成し、それを人生の価値基準としてゆくのだ。
一方蓄積的記憶とは、i)特定の担い手とは切り離され、ii) 過去、現在、未来は切り離され、iii)価値付けの序列はなく、iv)真実を志向するがゆえに、価値や規範が保留されている。つまり、この記憶にとって過去とは、「無定形な集塊」であり、「使用されず融合されていない思い出の暈」とされる。ただし、重要ななのはこの記憶は機能的な記憶と対立するのではなく、一部は無意識のままとどまるように、いわば背景として沈潜しているということだ。いまだ意味づけられることなく、使用価値が与えられることなく、しかし消え去ってはいないアーカイブなのだ。これは<人類の記憶>と呼ばれているが、むしろ記録と呼んだほうがよいかもしれない。
では機能的な記憶の役割とは何か。ここで取り上げたいのが、「正当化」である。「正当化は、公的あるいは政治的な記憶の最優先の関心事」だとされる。体験者の想起による、過去の意味づけは必ずこの正当化をはらんでしまうのだ。ハーヴェイの上にみた指摘は、まさに意味づけによる喪からの回復の物語に、個人の生の肯定を見るゆえに、この記憶が果たしている、過去の体験者の自己への、そしてその体験者が参与した戦争行為の、正当化をまったく看過してしまっているのだ。
そしてもう一点、なぜ機能的な記憶の役割が歴史を形成しないのか。これについてはアスマンが引いているアルヴァックスの考察が役立つだろう。それは、集合的な記憶が、出来事のシンボル化に過ぎないからだ。シンボル化に過ぎない以上、まさにアルヴァックスが言うように、「集合的記憶は、それが結びついている集団と同様に常に複数形で存在する」のである。これは、歴史の記憶、すなわち「単数形で存在」することと対立する。歴史が純粋に単数形で存在することは、もちろん前提とはできない。ただ、ここで確認したいのは、集合的記憶とは、もしそれが歴史とされるとならば、その歴史は、集団の利害、行為の正当化、相対主義的な歴史観を必ず孕んでしまうということだ。もっと単純に言ってしまうならば、集合的記憶はシンボル化=この戦争は何だったのかという問いへの、事後的に構成された答えなのだ。
それに対して、蓄積的記憶は歴史に何らかの寄与をしうるのだろうか。アスマンは蓄積的記憶は、「文化の知識を更新するための基本的資源」であるとする。この二つの記憶が間の境界が「高度に透過的」でなくてはならないという。しかしそれがいかに可能で、どのようにその透過性が保証されるのか。そこには「検証」が必要となるだろう。この検証こそが歴史的事実と呼ばれるものではないだろうか。それがシンボルや選択といういわば言語化において避けることのできない作用を認識しながらも、それを絶えず修正していく歴史的な理性の謂いとなるのではないだろうか。
だが、これだけでも十分ではない。こうした考察を深めた後にもう一度証言者のディスクールに戻ってこないといけない。利害をもたない証言者の記憶の物語について、それが検証に耐えうるかどうかということも含めて、さらに考えなくてはならない。そこには倫理が最終的に要請されるのだろうか。
ゼーバルトは言う。「歴史的ないし文学的描写によって、空襲の恐怖を公共の意識にもたらすことに私たちは成功していないのではないか」と。この講演では、歴史的な事象にたいして、文学はどのような表現をもちうるのか、そして文学的な表現をいままで戦後ドイツはもちえなかったのはなぜなのか、が主題となっている。
ゼーバルトは、戦後、ドイツが戦時下において、ほとんど正当化される理由もなく無差別な空襲を受けたこと、それも徹底的な絨毯爆弾によって、市民も巻き添えにした潰滅的な破壊が国土においてなされたことが、これまでほとんど書かれなかった事実を指摘する。それはあたかも健忘症にかかったかのような症状とでも言える。しかしゼーバルトが語るのは次のようなことではない。「空襲について語ろうとするのは、戦争の加害者は同時に被害者でもあった、ところが加害者としてのナチスの行為があまりにもひどいものであったため長らくドイツは自らが被害者でもあり、それを主張する権利をもっていない、被害を訴えることはタブーであるために長らく沈黙してきた」云々...したがって、次のような主張とは全くもって異なっている。
「もうそろそろ我々も被害者であったのだ、連合軍から悲惨な目にあわされたのだ、ということを主張してよいのではないか」。
ゼーバルトが「告発」といってもよいほど強く、かつ執拗に訴えるのは、それら沈黙は自重や遠慮ではなく、むしろ自らその過去を封印することで、戦後の復興を成し遂げ、また自信を回復してきたのだ、という点である。それはすなわち、心理の巧妙なすりかえがあったのだということだ。たとえば戦後すぐドイツではオペラが上演され、三島憲一『戦後ドイツ』によれば、「ベルリンで毎晩200個所以上で芝居が上演され、毎日最低六つの演奏会があり、そして、オペラハウスも休演することがめったになかった」とのことである。こうした戦後のドイツの風景にたいしてゼーバルトは、「人類の歴史において、このような演奏をおこなうのはドイツ人のみであり、これほどの苦難を耐え抜いたのもドイツ人のみであるといういびつな誇りに、彼らの胸はふくらみはしなかったか」と。いびつな誇り、その心持ちが戦後の荒廃したなかでドイツ人に新しい生を歩ませることになる。三島憲一はそのあたりの事情を「このあたりの変わり身の早さは、ドイツ人全体にも共通している」と、辛辣な表現で指摘している。ゼーバルトは「当時のドイツほど、知りたくないことを忘れる人間の能力、眼前のものを見ずにすます能力が端的に確かめられた例は希有であったろう」と述べている。そしてその実体は「抑圧のメカニズム」の働きなのである。
では文学は何をしてきたのか。あるいは言語は何を表象してきたのだろうか。いや問いとしては、なぜ文学はその描写をもちえなかったのか。言語はどんな表現に逃げをうったのか、と問うほうがより的確だろう。
まずそもそもは、上記で言われた「変わり身の早さ」によって、そもそも描写の対象にしなかったということが挙げられる。そしてもうひとつは言語の表象の困難さという問題である。
空襲とはひとつの言語に絶する出来事である。それは「生の形では描写を拒む現実」である。人が「思考や感覚の許容量」を超える体験をしたとき、その表現は、思考や感覚が麻痺しているゆえに、ほとんどが紋切り型の表現になってしまう。それによって、現実と言語の間には大きな齟齬が生まれてしまうのである。それは同時に、理解を絶する体験を本当に表象するところまでいかず、「蓋をして毒消し」をしてしまうことになる。
だが、最大の問題は、表象が不可能だったのではなく、もちろんきわめて難しいとはいえ、それがタブーだった点にある。空襲を表象しようとする試みは、戦後復興のなかで誇りを取り戻そうとしてきたドイツ国民に対して、その誇りによって戦後、精神衛生を保ってきたドイツ国民に対して、じつは壁の裏側には、おびただしい死者、死臭、残骸、荒廃、血と汚物、そうした我々の精神に混乱をもたらす事実が、いたるところに転がっていることに言及せざるをえないからである。ゼーバルトはレーディヒという忘れ去られた作家を持ち出し、かれの「嫌悪と嘔吐を催させる」文体が、戦後に忘却の上に成り立つ戦後の文化的記憶から締め出されたのは、「防疫ラインを破るおそれがあったからだ」と述べている。空襲について語ることは、それが我々を忘却へと葬ってしまうほど、紋切り型でしか表現できないほど、我々の経験を超えた出来事である。しかしもしそれについて語りうるならば、それが同時に戦後ドイツという過去の忘却の上に今まで成り立ってきた文化が実は幻想であることを、それゆえに書くことがその幻想から覚まし、時間の寸断(戦前と戦後)というまやかしを暴き出すことになること、これこそが恐怖であり、ドイツの理性はその恐怖を今まで封印にしてきたことを、ゼーバルトは告発するのだ。
しかしでは、どのような表象ならば語ることが可能なのか。ゼーバルトが挙げる数少ない成功例がノサックである。ノサックは「非人間性と紙一重の、倫理的感覚の欠如」を書き残す。
文学が歴史と異なってできることはこの点だ。文学は、歴史と異なり、ひとつの断片、物語化されえないひとつの断片でさえ、言語として表象する可能性を持っている。それが個人の視野におさめられたものでもかまわない。ただし、それが個人にとどまってしまえば、それは文学とならず、日記や覚書となろう。また装飾を交えてしまっては神話となってしまうだろう。文学とは、あくまでも「虚飾をまじえぬ客観性に裏打ちされた真実」を語らねばならないのだ。それでこそ、ひとつの断片であっても、他者とつながる契機が生まれるのである。歴史であれば、個の断片は、普遍性へと回収され、歴史的意味を帯びる。文学はこの大きな意味とはことなる、個でありながら、他者と了解可能な表象を探る言語の実践なのではないだろうか。
だからこそゼーバルトは「私の人生と、空襲の歴史とが交錯する点」をいくつも述べてきたのではなないだろうか。
 自分のまわりで死が頻繁に起こる。友人たちが短期間に次々と死んでゆく。それは「殺戮」と表現されている。しかし「死は死でしかない」とは、誰がどのように死のうが、その差異を抹消してしまうほど、死は圧倒的な一つの事実であるということだ。あらゆる差異を消し去り、人を無名性に押しやるほど、死の力は強い。
自分のまわりで死が頻繁に起こる。友人たちが短期間に次々と死んでゆく。それは「殺戮」と表現されている。しかし「死は死でしかない」とは、誰がどのように死のうが、その差異を抹消してしまうほど、死は圧倒的な一つの事実であるということだ。あらゆる差異を消し去り、人を無名性に押しやるほど、死の力は強い。
友人が次々と死んでゆくとは、同時に自分が歳をとってゆく過程でもある。それは青春の終焉でもあり、そしてまだいつかは見えないものの、やがて来る自分自身の死の準備となるだろう。ただし、「いつかは見えない」、「やがて」というあいまいなときは、今来てもまったく不思議ではないあいまいなときだ。いつかはわからないとは、いま来てもおかしくはない。やがてとはすぐ先の未来であってもおかしくはない。
死者へと意識的なあるいは無意識的な思いは常に残る。「夜中にものを考え過ぎる」というとき、それは、生者の死者に対する一つの喪の作業となるだのだろう。その喪に直面するのを避けるためには身体を動かすしかない。「掃除機をかけたり、窓を磨いたり」とは、きわめて日常的な社会性であろう。もうひとつの方法はテレビだ。「好きなときに消せる」とは、つながりうる関係を、突然断ち切ってしまうことを意味する。その可能性、私と他者とのつながりの可能性そのものを断ち切ることになるのだ。死があらゆる無名性へと人を落とし込むならば、友人の死も、テレビの中の死も何も変わりはない。それは「匂いのない死」だ。「あなたは私が殺した人に似ている」ならば、「あなた」の方が死んでいてもなんの違和感もないのだ。生者と死者を分つものなどなにもない。
しかし、もし無名性から死者を救うために、「夜中に物事を考え始める」ならば、それはテレビの世界にもやがてつながることになる。それは息をひそめて待っている人を、助けに地下へ降りてゆくことになる。テレビの向こう側に、地下奥深くに、沈黙して待っている人がいる。もし私たちが、向こう側に渡れるならば、地下に降りてゆけるならば、私たちは、その人にしかない匂いをかぎながら、救助へと向かうことができるのだろうか。
第一部記憶と想起について、第二章訓練される記憶力ー慣用と濫用、第二節自然的記憶力の濫用、3.倫理的・政治的レベルー強いられる記憶力をまとめる。
ここでリクールは、この場所ではまだ時期尚早であると断りながらも、記憶の義務の批判を行なっている。その批判の中心は、思い出すことへの命令が、歴史の作業を短絡化してしまうことにある。
まずリクールはアリストテレスの「記憶と想起について」で述べられている想起の自発性(évocation spontanée)と、記憶の義務とを対比する。果たすべき務めとして過去へと向かってゆくと同時にその動きは未来を志向する記憶(過去にあったことを未来においても忘れるな)と、記憶の作業、喪の作業の関係を問う。
たとえば、精神治療においては、記憶の義務は務めのように定式化されている。被分析者の精神分析に寄与する意図は、命令の形をとっている。一方、喪の作業においては、失われたものと自分とをつなぐ絆をひとつずつ切り離していく作業を続け、和解への作業は果てしないものである。
このように考えてくると記憶の義務と対比したとき、記憶の作業と喪の作業という「作業」(travail)に欠けているのは、「命令的要素」(élément impératif)だと言える。さらに明確に言えば、義務(devoir)には以下の二つの面がある。一つは、外部から欲望に強制が課されるいうこと、二つめは主観的に感じられる制約が、実は課されるべきものとして働くということである。そしてこの二つの面が結びつくのは、justiceの理念においてである。
こうしてリクールは次にjusticeの理念と記憶の義務の関係について問う。その答えは次の三つである。1.justiceの美徳は他者へと向かう美徳であること、記憶の義務は他者の正しさを認める義務である。2.負債の概念。我々は現在のある部分を過去の人々に負っている。3.我々が負債を負う他者の中で、道徳的な優先権は犠牲者に与えられる。この犠牲者とは我々以外の犠牲者である。
ではこうした三点において、記憶の義務が正義の義務として正当化されるのならば、どのように濫用という事態が、良き利用の上に現れてくるのか、とリクールは問い、それは、歴史のより広汎で批判的な目的に対立して、記憶の義務に脅迫的な色合いをつける、感情的な記憶、傷ついた記憶によってあると言明している。
そして、やはり留保はつけつつも、慣用が濫用へと至ることについて二つの解釈を述べている。ひとつはアンリ・ルッソの『ヴィシー・シンドローム』の説明。ここでの記憶の義務は、direction de conscienceが、犠牲者のjusticeの要求を代弁する形でなされており、記憶の濫用はまさにこのような形で犠牲者の無言のことばが絡めとられてしまうことにある。二つ目はピエール・ノラの『記憶の場』の説明である。それは記念顕彰のモデルが歴史のモデルに勝利してしまったという事態である。
最終的にはリクールは、justiceの命令としての記憶の義務は道徳の問題に属するとする。
二宮宏之のテキストは、例えばアンシャン・レジーム期の社会を具体的なフィールドとし、検証を重ねた緻密な歴史研究を実践する一方で、自らの思索に裏打ちされた歴史学そのものへの批判的視野をも兼ね備えた、第一級の研究者である。
ここに紹介する「歴史の作法」は、叢書『歴史を問う 4 歴史はいかに書かれるか』の序に代わるテキストであるが、今現在歴史学がかかえる問題を包括的に示すだけでなく、筆者の考えも綿密に盛り込まれた、文章である。多くの史料、文献を読み込み、かつ、日々自ら思考をたゆまぬ筆者ならではの卓見に富んだ文章である。
1.で問題になるのは歴史家の出発点である「問い」である。その「問い」をまず「今」と「自分」から始めている。「自分」については、色川大吉への上野千鶴子のインタビューを取り上げ、主体的な歴史という考えを紹介するととともに、自己の記憶が本当に自分固有のものであるとは簡単に断言はできない、この問題の複雑さをまとめている。「今」については、発生史的、遡行的発想と、「いま」を異文化として再発見する発想の二つにわけて整理されている。前者は過去と現在を反復する運動であり、後者は、現在の視点から過去を理解することを戒める態度である。たとえば今の意味概念で無神論者というレッテルでラブレーを眺めるような姿勢を批判する態度である。
2.で問題にされるのは、過去という痕跡とどう向かい合うかという問題である。普通に考えれば、過去の痕跡とは史料ということになるが、史料を再検討することが歴史の課題となってきた。そのため、考古資料、民族史料、絵図・古地図、絵画史料、文学作品までもが歴史の対象となってきたのである。そしてもう一つの問題は痕跡の欠如である。たとえば、文字の世界に現れてこない、女あるいは子供の世界、男の世界であっても被支配者層や被差別民の歴史などである。さらにはアーレントの「忘却の穴」の問題が挙げられる。
3.では、歴史記述の問題があげられる。ここで挙げられるのは19世紀ヨーロッパで支配的となった実証主義的歴史認識論に対する、「言語論的転回」の潮流である。これは「物語り論的転回」として歴史学の分野では現れてくる。ここではダントー『歴史の分析哲学』、ホワイト『メタヒストリー』、リクール『時間と物語』が紹介される。
この歴史叙述の問題を3つの部類にわけて考えることで、今まで混乱して語られてきた歴史の物語性の問題を明快に整理している。第一の部類は、「歴史を大局的に捉える歴史記述」である。特定の時代の全体像を描いたり、評伝などがこれにあたる。代表例として挙げられるのがギボンの『ローマ帝国衰亡史』、ミシュレの『フランス革命史』である。第二の部類は、研究論文である。ここでは史料に基づいて綿密な検証を行ない自説を提示することがその目的となる。ここに、歴史家の問い、史料の読み(分析)そしてなによりも論文の構成という点で、ナラティブ性を認めることができる。第三の部類は、年表や歴史地図である。そこに載せる出来事、表示、表現も決して価値中立的ではない。ここにもひとつのテクストとして固有のナラティブ性を認めることができる。
4.では、歴史記述の固有のナラティブについて言及する。ここではたとえば、歴史と文学に関して二宮の所見が示される。ここで二宮が依拠するのは歴史家の仕事が具体的にどう進められるかという点である。ここで二宮は歴史家には2つのオペレーションー史料を発見し読解することと、そのように読み解いた諸々の事柄を相互に関連づけ構成していくことーがあり、この2つの側面が重なり合って進んで行くことが歴史家の作業であるとする。確かに歴史家の本文として、読む=読者でなければ出発できないということ、文学者にとっては、この条件は必要条件とは必ずしもならないところに歴史と文学の叙述の差があるように思える。この両者の違いは虚構性と事実性の違いではないのだ。その意味で歴史家の作業、「読む込むことと、読み込んだものの意味連関の構築」に求めていることが二宮の卓見であると言える。文学者はむしろ、言語そのもの、表現の彫琢を相手にしているのではないだろうか。
最後に二宮は、こうした以上の主張は歴史を限りなく歴史家の方に引き寄せたものだと述べている。その上で、こうした論考が相対主義に陥らないのは、歴史家がみずからの責任と矜持をもってみずから構成した歴史を述べているからであり、また歴史家は絶対的神ではありえず、常に他者と論じあう開かれた場所に身をおくからである、と述べている。「相互の討議の場」これがなければ、歴史は真実と混同されてしまうだろう。
トドロフの思想とは、一言でいうと「中庸」の思想である。そして中庸の見定めは、あくまでも討議することによって、行なわれる。その意味で対話者の関係の中で、暫定的な真理が生まれてくると言えよう。しかしそれはあくまでも暫定的であって、決して絶対的=不変不動の真理ではない。むしろ絶対を標榜し、議論を排する態度こそ、トドロフにとってはもっとも排すべき考えである。また対話によって真理を見定めてゆくということは、相対主義、すなわち、干渉しない複数の真理が並び立つということを戒めるという意味でもある。そして対話の原理は、彼のバフチン論にその起源を求めることも可能であろう。
Mémoire du mal, tentation du bienの第4章Les usages de la mémoireでも、「記憶」利用の2つの極端なあり方、sacralisationとbanalisationを排し、歴史における記憶の位置づけについて検討を重ねている。
トドロフは「記憶それ自体は、良いものでも、悪いものでもない」という。しかし、それが極端な二つの方向、sacralisation「思い出を根本的に分離すること」か、banalisation「現在と過去を過度に同質化すること」のどちらかに傾く危険があることを指摘する。
ではsacralisationの問題とは何か。まず、sacralisationは出来事の唯一性とは異なる。出来事の唯一性が問題なのではなく、その出来事が、別格のものとして、他の出来事との関係づけ、比較、検討も許されない、「触れられない絶対的な出来事」として祭り上げられることが問題なのである。それは理解の不可能性、表象の不可能性ということばで語られるが、これは実際には理解や表象を「禁止」しているのである。それによって、人類は、その唯一の出来事から教訓を引き出すことがもはや不可能となる。
出来事のsacralisationはどのような事態をもたらすのか。トドロフが指摘するのは、現在と過去の遮断である。「ホロコーストを忘れるな」と叫ぶそのそばで、ルワンダの虐殺に対しては無関心である現実をトドロフは批判する。
一方banalisationとは何であろうか。その危険性は、現在の固有の出来事が、過去と同一化されることによって、その固有性を失う点である。たとえば、ある人物を、「現代のヒットラーだ」と安易に形容することによって、現在の特殊性を等閑視してしまうという態度である。
過去がそれ自身では善でも悪でもないということは、過去と現在との関係において、過去における<悪>が、現在において<善>を生むどころか、新たな<悪>を生む下地となる、という逆説的な事実からも言える(言わざるをえない)ことである。非抑圧者は、それによって善を備えた人物となるわけではない。トドロフはいくつかの例を出しながら、この事実を指摘する。簡単に言ってしまえば、「他者の過ちから何も学ばない」ということである。それが「復讐の連鎖」という事態を生む。その最たる例が、イスラエルの場合であり、過去の経験というものが、現在の政治の正当化に利用され、結果サイードのいう「犠牲者の犠牲者」が生まれている。その意味で、トドロフにとっては、20世紀末におけるアルジェリアの暴力は、それまでの120年に渡る植民地化での暴力のトラウマの結果であり、悪が容易に消えるのではなく、むしろ悪の波及という現実があることのひとつのヴァリエーションである。
こうしてトドロフは、歴史の教訓とは、過去からそのまま引き出されてくるものではなく、現在における政治的・倫理的確信から生まれてくるものであると言う。
ここでトドロフはひとつの問いを立てる。「記憶よりも忘却の方が望ましいのではないか」と。そして、記憶の問題として、トドロフは「復讐」の問題を取り上げる。つまり、過去を記憶によって喚起することが、復讐のきっかけになっており、新たな悲劇の到来は、この「許さないこと、忘れないこと」から起こることも確かである。しかも、「復讐」とは、我々にとって、決して無縁のものではない。それは、死刑という制度に根強く残っている。死刑をめぐって、トドロフは、復讐を法の正義と対置する。復讐とは、許しと同じく個人的なものであり、それに対して、法とは非人称なものである。しかし、たとえ抽象的かつ非人称的であるとはいえ、法こそが暴力を減じる唯一の方策であるとトドロフは言う。
記憶が復讐の原因になることがあるとはいえ、忘却がよしとされるわけではない。ここで取り上げられるのが精神分析で言われるところの抑圧である。それは過去を回復(recouvrement)することをめざす。喪の作業と同じく、過去を忘れるのではなく、その位置、イメージを変えることによって、その過去から解放されることが目的となる。では公のレベルではどうだろうか。トドロフがここで主張するのは、やはり「変化」ということである。この場合の変化は、ある個別の出来事から一般的な行動基準への変化である。具体的には、そこから公的正義の基準、政治的理想、倫理的基準を引き出すことである。この抽象化は、個別のケースから離れるということであり、上述の非人称の抽象化を経ることで、法は到来するのである。
従って過去を思い出すこと、再生産することが記憶の利用の目的ではない。その目的は、我々の価値の選択によるのであって、思い出に忠実であることではない。そのときに重要となることは、個人のアイデンティティを正当化し、近隣者の死を悲しむことは十分真っ当なことである。しかし、他者の不幸へと自らを転じるとき、そこにはさらにおおきな尊厳と価値があるとトドロフは言う。ユダヤ民族の大虐殺から、黒人奴隷の問題へと転じたシュワルツ=バール、アルジェリアでの拷問を前にして職を辞した、収容者Paul Teigenなどの例が出される。
「記憶の義務」と言う時、それはえてして、過去を回復し、その過去の事実を解釈していく営みではなく、むしろある事実を選び取ることの正当性を訴え、善悪を固定化することに通じてしまう。したがって、必要とされるのは、ポール・リクールが言うように、「記憶の作業」である。この作業とは、それだけでは何の価値や意味もない歴史的過去を問い直し、判断していくことを意味する。トドロフは最後に、「理性の鍛錬」、「討議の試練」に過去をさらし、自らの利益ではなく、他者にとっての倫理とすること、ここに記憶の利用がかかっているとする。
第四章では、まずプラトンに言及し、詩人が天啓を伝える人として描かれる。それは最初の天啓を受けて、最初の叙事詩を創ったホメロスから、その天啓を広めたrapsodes(吟遊詩人)のように、人々に広がっていく。さらには、教育の基礎ともなる。
この時代には二種類の詩があった。poésie eumolpiqueとpoésie épiqueである。前者はintellectuel et rationnelなものであり、後者はintellectuelでpassionnéなものである(p.74.)。
次にFabreは、劇の起源について述べる。それはオルフェウスの秘犠の俗化したものであり、デュオニソスの収穫の祭りがその始まりである。さらにFabreはdrameの語源に触れ、サンスクリット語で、輝かしい、美しいという意味をもつRamaという名が、フェニキア語でも同じ意味をもち、そこにアラム語とシリア語に共通の指示冠詞がつくことによってdramaという単語が生まれたとする。
最初はぶどうの収穫時の「田舎の余興」であったが、それが人々をすぐれて魅惑したことから、教養層の眼にもとまることになった。それをとりあげたのがThespisとSusarionであり、それぞれが悲劇と喜劇の起源となった。
こうした事態に気づいた国家は、宗教と風俗に危険となる場合、厳格な規則を課した。秘儀をもとに劇を仕立てることは許したが、秘儀の意味を解き明かすことは禁じた。作品の善し悪しを判断するにあたっては、音楽と詩の知識に秀でた審査官を置き、彼らは、すべてを秩序と規則に収めなくてはならなかった。プラトンはこの法がすたれたこと、人民が演劇を支配したことが、芸術の最初の頽廃であると言っている。
アイスキュロスは、演劇の真の創造者であり、ホメロスからうけた天啓にのっとって悲劇のなかに叙事詩の文体をとりこみ、簡潔で荘厳な音楽をつけた。さらに、音楽、絵画、踊りによる総合的な演出を試み、舞台装置による効果を展開した。
ギリシアの劇が秀でていた点は、秘儀の宗教から生まれた道徳的な意味を持っていた点である。したがって、普通の人々が舞台や音楽の華やかさに魅了されているだけなのに対して、賢者は、その中に潜む真理を受け取ることによって、より純粋で永続的な喜びを得ていたのである。
ソフォクレスとエウリピデスは、アイスキュロスの後継者として、ともに秀でていたが、形式を完成させることに心を砕き、劇の本質、すなわちアレゴリーの精神(génie allégorique)を変質させることになったことは否めない。さらには、エウリピデスが描いた逆境において堕落した英雄、恋に狂う王妃、といった情景の魅力が、アテネの道徳の腐敗の原因、宗教の純粋性を貶める最初の原因となった事実を認めざるを得ない。弱さや罪といったものが、本来ならばその意味を探すべきアルゴリーとして示されるのではなく、単なる歴史的出来事、想像力の気まぐれな戯れとして示されてしまっているのである。
こうして二世紀しないうちに、テスピスのもとで生まれ、アイスキュロスによって劇として高められ、ソフォクレスによって栄光につつまれた悲劇は、エウリピデスにおいてすでにかげりをみせ、アガトンの起源の思い出を失い、急速に人々の気まぐれによって頽廃を迎えてしまったのである。
エピカルモスにはじまり、アリストファネスにつらなる喜劇も、同じような歴史をたどっている。
第三章で言及されるのはホメロスである。ホメロスの意図は感情を人格化して描くことにあった。詩の完成に至るためには、精髄を豊かにする想像力とその飛躍を支配する理性を調和させることが必要であるが、ホメロスはそれをなしえた詩人である。ギリシアの詩は、音楽的リズム(rythme musical)によって計られ、長音節と短音節の混合によって構成され、韻の拘束を揺るがしてきた(p.62.)。リズムとは、詩が作られる拍の数とそれぞれの拍の長さのことである。古代ギリシアでは、筆耕法が使われていたが、これは長くは続かなかった。もしこの方式が存続したり、あるいは、韻が形式を拘束していたならば、ホメロスは叙事詩を仕上げることはなかったであろう。韻が詩の形式を支配するところでは、才能はその形式にばかり気を取られ、知的啓示(inspiration intellectuelle)を無駄にしてしまうのだ。
オルフェウス教は、紀元前6世紀に古代ギリシアで発達したが、その意義は、当時のギリシアの市民生活と宗教に対立する運動であったという点である。しかし、「オルフェウスの金板」を除けば、資料としては間接的な証言しかない。またオルフェウス教は、オルフェウスとその弟子ムサイオスを以外は、無名の人々が信者である。このような点で、オルフェウス教の実像を掴むことには困難がつきまとっている。
この教義の重要な点として、生け贄を捧げる義務に反対したことがまずあげられる。次に、死と魂の考え方である。当時ギリシアでは、魂は肉体を離れたあと、死者の国で永遠にさまようものとされた。それに対してオルフェウス教は、魂の不死性を主張した。この意味において人間の魂は、神的な性質を持っていると言える。また魂は決して死ぬことはない。ただしその魂は先祖が犯した殺害という罪で汚れている(p.10)。そしてその戒律は禁欲、身を清め、肉食を禁止することにあった。
オルフェウスの伝説は、「音楽の賛美」である。彼の歌には、全世界のあらゆる存在物を従える、並外れた力がある。その歌の力をたずさえて、死者の国へも降りていったのである(冥界降り katabasis)。また頭を切られても、歌を歌い続ける。(第一章 オルフェウスー神話とオルフェウス精神の成立)
オルフェウスの宇宙誕生譚は、アリストファネスの喜劇『鳥』の中で、宇宙卵(=時の具体化)に言及している箇所にその反映がみられる。またダマスキオスの「ヒエロニュモスとヘラニコス」の誕生譚にも似ているとされる。また『二十四の叙事詩からなる聖なる言説』では、時(クロノス)が原初の生み出す力という非常に重要な役割を演じている。宇宙の統治における最初の存在が、ファネス、プロトゴノス、エリケパイオスである。(第二章世界と支配権)
オルフェウスの人類誕生譚は、ヘシオドスの人間と神々を分離して考える論理とは反対に、人間と神々は本来単一であったという論理に基づいている。その意味で人間は不死性という性質を持つことになる。(第三章 人類誕生譚と人類の不死なる二つの対極)
しかし不死なる魂をもつ人間は、その起源において、神々の間で生じた汚れを負っている。この汚れを清めて救われるためには、神に同化することが必要となるが、これには日常生活において禁欲の掟を実践することが求められている。殺生を禁じることがその第一の掟である。許される肉と許されない肉と区別をしたピュタゴラス主義は、結局生け贄を認めており、それにたいしてオルフェウス教はどんな些細な殺害も禁じている。肉食を控えることは、まさに神々のように振る舞うことである(p.96.)。この菜食主義が古代にはあったという言い回しは、たとえば、オウィディウスがピュタゴラスに語らせるせりふなどで、よく現れる。プラトンも『法律』のなかで、オルフェウス教は先祖伝来の伝統を踏襲していると述べている。生け贄は、神と人間の越えられない距離を前提とするという意味で認められないのである。ただ、オルフェウスの秘儀については仮説の域を出ない。(第四章 日常生活と秘教世界)
魂は死ぬことができないので、取るべき道は、自分を忘れ、その神的起源を忘れるか、神的起源を思い出すかである。前者の道は「忘却」の泉に通じ、ふたたび「陽の光」の下に、新たに誕生することとなる。後者は記憶であり、神との失われた同一性の回復である。それぞれ無知と知ること、不幸と幸福、転生と、誕生の円環からの解放という対立がある。ホメロスの「忘却」は、魂を、地上での過去を決定的に忘れてしまった虚しい影に変える役割を果たすだけである。それに対して、オルフェウスの金板は、「忘却」は、魂のなかにある神的起源の記憶を消すものであり、その結果魂は転生するとする。つまり忘却とは、死の象徴ではなく、生成の円環に投じられることを意味するのである(p.116)。こうした不死の考えは、ヘラクレイトスとも共通点があると言われる。(第五章 死後の世界の記憶)
のちにバランシュは、オルフェウスの教えはキリスト教を予示しているとした。
第二章では、その後のトラキア信仰の拡散を語る。つまり原初の統一を失い、さまざまなセクトが誕生する。ここから半神、高名な英雄などが生まれてくる。ここでFabre d'Olivetは今度は歴史という観点で2つの考え方を区別する。まずはアレゴリーの歴史であり、こちらは、道徳のみを扱う。そして個人ではなく、集まり(masse)の動きを見つめ、そうした集まりを一般的名称(un nom générique)で指し示す。したがって、こうした集まりを統率する長というものもこの歴史の言及するところではない。それにたいして実証的歴史(histoire positive)は、個人が全てである。それらの個人と出来事の日付、経過などを記すのである。
続いてホメーロス以前の詩人、Linus, Amphion, Thamyrisがそれぞれ、月にまつわる詩、太陽にまつわる詩、Olenの普遍的教義をそれぞれ表しているとして紹介される。次にオルフェウスについて語られる。オルフェウスが現れた時期というのは、純粋なアレゴリーと、弱められたアレゴリー、知性で把握できるもの(l'intelligible)と感覚で把握するもの(le sensible)が分かれる時期である。その意味でオルフェウスは理性の能力と想像力を折り合わせることを学んだ。このオルフェウスとともに「哲学」の基礎が生まれたのである。この時期のギリシアはすでに野蛮な状態ではなく、また詩は、人間精神の幼い時期に生まれたのではない。詩は、つねに人々の中に長く生き、進んだ文明を持ち、力強い時代の輝きを持っている。
長い間ギリシアは政治的にも宗教的にも混乱の時代に陥っていた。様々な寺院、都市が割拠し、対立する。その直前にアジアでもインドが分裂し、混乱の状況を迎えていた。地中海と紅海の交通も途絶え、インド洋に定住していた原フェニキア人とパレスチナのフェニキア人の交流も断たれた。アラビア、ペルシアも同様である。エジプトは王権が権力を広く延ばすようになり、ギリシアもその影響下にはいる。
そのような状況の中、トラキアに生まれ、エジプトで学を積み、詩の崇高さ、知識の深さを極めたのがオルフェウスである。Fabre d'Olivetによれば、妻エウリュディケの存在もアレゴリーに過ぎない。それはすなわち、遠ざかっていく美と真のアレゴリーである。真理は知の光の中で初めて到達する、暗闇で凝視したところで、それは決して得られない。このようにFabreはアレゴリーの解釈をしている。
オルフェウスは、神の神秘を知るために、学校を作り、そこで知を高め、真をしるためのイニシエーションの修行を行なわせた。古代においては真理はひとつの声があるだけであり、それはこのオルフェウスに帰せられることはソクラテスの証言通りである。こうした知のあり方は、その前のモーゼ、その後のピタゴラスと同じである。
ここで先ほどの混乱の時代に話題が戻り、Fabre d'Olivetは詩の真理の分裂は、本来の啓示を得ることのできない僧侶たちが、感情の高まりをそれと同等のものと見誤ったことを原因だとする。それによって、神がその能力、そして名前によって数多く生まれることとなった。こうしてそれぞれの都市がそれぞれの神を抱くこととなる。もちろんこれらの神々をよく検討するならば、それらは最終的に普遍的な唯一存在へと還元されるだろう。しかしそれぞれの守護神を見いだしていた民衆にとって、そのような考えをすることは不可能であった。
オルフェウスは、モーゼと同じようにエジプトの寺院で教育を受け、神の単一性についてはヘブライ人と同じ考えを持っていた。しかしこの考えを表に出すことなく、秘儀の根本に据えるとともに、詩の中で、神の属性を人格化した。モーゼの教団が厳格なものである一方、オルフェウスのそれは、輝きがあり、精神を魅惑し、想像力の発展を促すものであった。喜びや快楽の下に、オルフェウスは役立つ教え、教義の深みを隠したのである。詩、音楽、絵画、それらにおける荘厳さ、優美さが信仰者を熱狂で包み込んだのである。オルフェウスの言う真理は、モーゼよりもさらに進んだものであり、時代を先んじていた。オルフェウスは、神の単一性を教え、その存在の計り難さを述べた。またこの唯一神を三神の表象のもとに描いた。
また弟子に芸術がもたらす感興を信者に与え、彼らの生活が簡素で純粋であることを望んだ。こうした教えは後にピタゴラスが引用するものである。
この教えの究極の目的は、神との交流にある。輪廻の輪を断ち切り、魂を純化し、肉体を抜け出した後に、原初の状態、光と幸福に到達するよう、魂を飛翔させることにある。
オルフェウスについて長々と論述してきた理由は、詩が余興の芸術ではなく、それが神の言葉であり、予言者の言葉であることを言うためである。オルフェウスはこの意味で、まさに詩と音楽の創造者であり、神話、道徳、哲学の父であった。オルフェウスが源流となり、ヘシオドス、ホメロスのモデルとなり、それがピタゴラスやプラトンにとっての光明となったのだ。
オルフェウスは、自らの教義を俗なるものと、神秘的なものに分けた上で、詩の中にも神的なものと俗なるものが混じり合っていることから、一方を神学、もう一方を自然学(la physique)にわけた。オルフェウスは、神学と哲学の数多くの詩を作った。それらの作品は残っていないが、人々の記憶には留められた。(この場合の哲学とは、コスモロジー、すなわち、自然学のことか?)。同時にオルフェウスには叙情的な詩群もある。ここからギリシアのメロペーが生まれ、それが次いで、劇を生んだ。
Fabre d'Olivetによるピタゴラス『黄金の詩』フランス語翻訳につけられた詩論である。論文タイトルにあるように、詩を「本質」と「形式」に分けて検討している。
以下簡略訳をしながら要旨をまとめる。
序文で、ピタゴラスの詩のフランス語訳が、フランス語自体にもたらす有用性に触れた後、第一章では、まずベーコンの『学問の尊厳と進歩』を引用し、詩が本質と形式に分けられていることに言及する。本質とは、想像力に属するものであり、これだけで学問の一分野を構成する。形式とは文法に属するものであり、哲学の、理解の合理的形式に包含される。この考えはプラトンに流れを発するものであり、プラトンによれば、詩はひとつに思想にそれに合致した形式をあたえる技術であり、これはたんに才能による。もうひとつは、神の啓示である。したがって、詩人とは単に詩作の才能をもった人間と指すのではない。魂を高揚させるこの神の熱狂を身にたずさえてこそ、詩人となるのである。
この意味で、オルフェウス、ホメロス、ピンダロス、アイスキュロス、そしてソフォクレスの名声が、単に作品の構成、詩節の調和、その才能にあるのだと考えることは誤りである。これらは単に詩の形式に過ぎず、本当の詩というものは、詩人の精髄(génie)が、その高揚の状態において、知性(nature intellectuelle)によって捉える本源的な概念(idées primordiales)にあるのであり、この概念は、続いて、詩人の才能によって、自然要素(nature élémentaire)の中で明らかにされる。これは自然界の物質の似姿を、魂の啓示を受けた動きに会わせるのであって、この動きを似姿に合わせるのでは決してない。これについては、ベーコン自身が次のように言っている。
「感覚の世界は魂の世界より劣っている。詩がこの性質に、現実が拒んでいるものを与えなくてはならない。詩が新たな存在を生み出すのだ。摂理の歩み(la marche de la Providence)が、出来事に潜む最も隠された原因を明らかにするのである。」
ベーコンにとって詩の登場人物とは仮象であって、それら登場人物の善悪、行為の中には深い意味が込められており、そこに宗教の神秘、哲学の秘密が隠されているのである。現実世界の法を離れた行為の根底には、崇高なる哲学が潜んでいるのである。それが本質と呼ばれるものであり、形式が時の流れとともに変質するのにたいして、本質は不変である。
この本質とはアレゴリーの精神(génie allégorique)、啓示、すなわち精神の魂への流入によって直接生まれるものである。それは上に述べたように、知性(nature intellectuelle)においては潜在的に留まっていたものが、行為によって自然要素(nature élémentaire)を通過することによって顕在化するのである。詩人の詩作とはこの自然要素に感覚しうる形式をまとうことである。これが神的な啓示であって、知性(nature intellectuelle)から生まれでて、時代、民族を越えて共通である。これが精髄(génie)を作り上げる。一方、俗に啓示と呼ばれている、心の内的な動き、未完成な感情(passion)の方は、感性(nature sensible)に備わるもので、こちらは時代、風俗によって様々に変化する。こちらは精神(esprit)と呼びうるものだ。
こうしたことは新しい発見ではなく、ヘラクレダイ一族、ストラボンが指摘していることであり、デュオニュシオス・ハリカルナッセウスが「自然の神秘、道徳の最も崇高な概念は、アレゴリーのベールによって覆われた」と言っている通りである。
古代ギリシアの初期においては、詩とは祭壇にまつられ、人民の教化(instruction)のためにのみ、神殿から出された。つまり、詩、詩節で書かれたテキストとは、神託、教義、道徳戒律、宗教上の、あるは社会生活上の決まりなどである。その意味で詩とは神の言葉である(Fabre d'OlivetはCourt de Gébelinを引用し、語源的にもpoésieはlangue des Dieuxを意味するとする)。
この詩の起源はThraceトラキアであり、それを聞かせた者をOlenと呼んだ。Fabre d'Olivetはそれぞれの語源をl'Espace éthéré、l'Etre universelであるとする。
さらにこれらpoésieの歴史を考えるうえで、そこにはフェニキア人の言葉の影響がギリシアの地にれっきとして残されていることを考えなくてはならない。
トラキアは古代ギリシアの信仰の中心であった。このトラキア人たちからギリシア全体へ神の神託が広まったのである。デルフォイの神託も同じように考えることができるであろう。この2つの信仰は、前者がバッカスとケレス、あるいはディオニソスとデメテル信仰に、後者が本来のギリシアにおける信仰、アポロンとディアナ信仰となった。
この分裂がどうであれ、ながらくギリシアを支配したのはトラキアの信仰であり、デルフォイの信仰はほとんど知られていなかった。その近くに生まれたヘシオドスがなんの言及もしていないのがそのよい例である。ミューズ、詩の女神がうまれたピエリ(Piérie)もトラキアの山である。
『零度のエクリチュール』はフランスにおいて、langue、あるいはstyleの歴史ではなく、文字(文学・文章)言語の歴史を追うことを目的とした作品である。(p.6)
バルトは、ブルジョワジーのイデオロギー的単一性が続いている間は、作家とは普遍性の証人であった。この意識は1850年ごろ終焉をむかえる。それはフローベールにとって「オブジェ」という対象物になり、形式の制作が始まり、そしてマラルメによる言語の破壊(いわゆる指示対象の不在ということか?)となる。p.6.
Langueとstyleは人間の歴史的事実の外側にあるということか。バルトはこれら二つは「時間と生物学的人間の自然な所産」と述べ、それを「文法の規範や文体の常数」と言い換えている。それにたいして文字言語は「歴史的な連帯行為」であるとする。文字言語には選択とその選択の制限が働く。作家はある文学言語を選択し、また過去の全体を含みこんで活動をしていく。p.15.
歴史的な行為である以上、そこにはイデオロギーが発生する。それは政治的ディスクールにおいて顕著となる。知識人的エクリチュールも同様である。これらは制度であり、「わたし」はそれによって拘束され、「形式」は自律的なオブジェになる。p.25.
古典主義的言語は、個人や意味の創造、偶発性を欠いた言語であり、伝統への厳格な依拠によって中性化され、語彙は慣用としての語彙であり、その語を集め、関係づける表現術なのである。したがって修辞や決まり文句は語と語の関係によって成り立っているもので、驚きを生むことはない。このような古典主義的言語は、ある集団に閉じられた社会的な言語であり、その集団の人々の間を流通するという意味において、厳しい法則をもっていながらも本質的にはひとつのパロールである。p.44.
この文字言語が現れるのは、まず言語が国民的に構成され、それが否定性を帯びるようになる、すなわち、起源や正当性を問題にすることなく、禁じられているものと許可されているものをと隔てる地平線となるときである。そしてこのとき言語は、時間的推移というものを離れ、普遍的なものとなる。そしてこのときとはフランス社会においてブルジョワが勝利をおさめたときである。したがって、それは、民衆の自然発生的な主観性による文法的手続きを純化することによって、作られた階級的な言語である。p.52.
ここで問題になるのは修辞、すなわち言述の秩序だけであり、道具的、装飾的な単一の文字言語だけが存在する。このイデオロギーは革命をくぐりぬけて1848年までつづくことになる。ロマン主義も道具性という古典主義言語の本質を保持しているのである。p.53.
1850年以降、ヨーロッパ人口の増大、近代資本主義の台頭、社会における階級分裂と自由主義の幻想の崩壊という3つの歴史的事実が、ブルジョワ・イデオロギーの単一性、普遍性を終焉させ、文字言語は以後多様化し、作家たちは、みずからのおかれた条件そのものの不安定さという悲劇をかかえることになるのである。p.56.
言語は、古典主義自体には共有財産であり、使用価値を持っていたわけだが、これ以降、作家たちは職人のように自らの形式を彫琢することなり、この価値は労働価値へと転化する。この職人芸的文字言語もブルジョワ的遺産の内部にあり、決して秩序を乱すことはなかった。これらの作家は文字言語を解放するのではなく、自らを正統化できる言語を創造する。そして解体をめざす作家は、基本的には書くことの不可能性、言語の崩壊、そして沈黙へと陥る。もうひとつの解決策は中性の文字言語の創造である。それは直説法的な言語、否定的な法であり、社会的、神話的性格は廃棄される。
バルトがこの作品を書いていた時期の眼下に広がる世界は、市民世界が自然を形作り、その自然が語りはじめている世界である。作家は歴史に準拠するかぎり、つまり歴史性をもった文字言語しか使えないならば、作家はこの世界から除外されてしまう。こうした伝統としての記号をどう断ち切って文学を創造するか、はたして零度の文字言語が構想できるのか、ここに新しい文学のユートピアがかかっている。
篠田浩一郎は『形象と文明』で、ブルジョワジーに関する一章をとりあげ次のようにまとめている。ルネッサンス期は個人単位で自由奔放なフランス語であり、17世紀前半はマレルブが、古語、外来語、新語、地方語、技術語を追放し、代名詞の省略を禁止する。つまりフランス語の「純化」が行なわれる。そしてアカデミの設立によって文法と語彙を国家がコントロールするとともに、近隣の諸言語に対してフランス語の支配権を要求する時代となった。これらはヴォージュラによって完成する(ヴォージュラは古典的文章言語を権利の状態ではなくて事実として勧告する)。この17世紀の文法家たちはフランス語という言語体系の非時間的な根拠を創りだすことによって体系を普遍的なものにした。このシステムは、政治的、文化的な力によって固定され、この国語の書き方が制度化され、「唯一のもの」となったときに、姿を現す。
1803年、Fabre d'Olivetが36歳の時にパリで出されたLe Troubadour, poésies occitaniques du XVIIIe siècleの文学的な意味についての論文。この作品は作られた当初から、Fabre d'Olivetの作為によるものであることはほぼ明らかであった。そもそもFabre d'Olivetの意図は、その序文ですでに明らかなように(p.VII.)、北方のオシアンと同じ価値をもつ南方のトゥルバドゥールの広く知らしめることにあったのだ。
このような作品を生み出すにあたって、Robert Lafontは、まずFabre d'Olivetのオキシタン語とフランス語という2重言語状況から、vocation «patriotique»を説明する。vocation patriotiqueとは、故郷を愛するがゆえに、その故郷のために自分が何をすることができるのか問いかけることを意味すると言ってよいであろう。その気持ちは、早くも1787年、20歳の時にlangue d'ocで書かれたForça d'amourとして結実している。
ここで着目しなくてはならないことは、Lafontによれば、Fabre d'Olivetは故郷という場所の「原初的な文化の復元」(primitivité de la culture restaurée)を試みたのではなく、オキシタン文学の系譜に自らを置いたことである。
この文学の系譜の筆頭に挙げられるのがPèire Godolinである。またpré-renaissance d'ocとしてJean-Baptiste Fabre (l'abbé Fabre)も挙げなくてはならないだろう。18世紀のこのようなラングドックの文学思潮にFabre d'Olivetは位置づけられるのである。
もう一つ挙げなくてはならないのは中世史家の系譜である。特に1774年に出版されたl'abbé Millotによるl'Histoire littéraire des troubadoursである。これは当時から議論のあった北と南の優越性についての問題につらなるものである。またたとえばMme de Staelの北方文学と南方文学の主張にもつらなっている。しかしこれらの風潮はきわめてパリという場所で起きている風潮であった。
このパリにおけるオクシタンの復興という歴史的状況のなかで、Fabre d'OlivetのTroubadoursは、伝統の覚醒であると同時に、きわめて近代的な事象として位置づけることができる。
さらにこの時期に、1575年に書かれたJean de NostredameのVies des plus célèbres et anciens poètes provançauxが、当初の政治性という面は忘れられ、神話的な面だけが語られ続けることになる。その中でもっとも重要なのが«cours d'amour»であり、Fabreはこの作品から第2巻の題材すべてを借りてきている。ただし、Nostredameのようにすべての詩人をプロヴァンス化してはいない。つまりFabreは別の資料ももちいて再構築をしていたのである。
Fabreは、騎士道的な愛とトゥルバドゥールの関係について19世紀の中世学者と同じ見識を明らかにする一方で、あまりにもキリスト教的な解釈に偏っているところがあり、アルヴィジョワ十字軍以降の詩人にのみ見られるような恋愛感情と宗教感情の関係を強調しすぎているのだ。このあたりには ChateaubriandのGénie du christianismeやCoppetなどの考えにつらなるものがある。つまりFabreのTroubadoursはNostredameの親和性と当時の風潮の混淆として考えることができるのである。
このキリスト教的なモチーフというのは作品の中に強く見られ、たとえばmerveilleux chrétienをもちいたり、さらにはサンクレティスムのモチーフもみられるのである。つまり、最終的にはトゥルバドゥールもNostredameもひとつの機縁にすぎず、19世紀において開花する、ネルヴァル的なサンクレティスムが展開されているのである。
したがってLafontはこの作品にみられるFabreの「恋愛と詩に関する感受性」から考えて、これは中世的なものではなく、フランスの18 世紀とヨーロッパのロマン主義の交錯点に位置するものとし、古典主義としては、作品における、トゥルバドゥールとは異なるエロティスムの展開を、そしてロマン主義としては「ウォルター・スコット」を彷彿とさせる、やはり、トゥルバドゥールからはほど遠い、登場人物の悲壮な状況における詩的感興を指摘するのだ。
しかし、こうした作品世界は、オクシタン語の表現を近代的なものへと押しやるひとつの機会になっている。そのためにLafontはオクシタン語での「引用」部分に着目する。といっても、ここでもFabreは原典を引用するのではなく、自らの創作を載せているのである。つまりここで扱われる作品はトゥルバドゥールの仮装のもとに現れる19世紀の詩人Fabre d'Olivetの言語なのだ。そしてLafontは、偽装ではなく、自ら詩人として現れれば、当時のもっとも優れた詩人とみなされたであろうと最大限の評価をしている。 以下、そのいくつかの例が示されている。
PhaonとSaphoの手紙における、rhétorique d'écoleによるérotique classicisant、トゥルバドゥールのジャンル、pastorèlaであり、ヴェルサイユ風のPastoura acoutidaであり、そして当時パリでも好評を博したCassanéa de MondonvilleのDaphinis et Alicimadureのようなオクシタンのジャンルでもあるpasotorale enrubanéeなどに、あたらしい「近代の」文学言語を認めることができるのだ。つまり、Lafontの洞察によれば、Troubadourは新しい近代的表現の開拓ということになる。Lafontはこの言語の完成が、フランス語からの借用ではなく、オキシタン語の内部で行なわれたことに関して Fabre d'Olivetを最大限に評価する。
つまりFabre d'Olivetはその作品Troubadoursにおいて、文芸復興のための言語的彫琢を行なったと言える。この言語という表現手段を彫琢したからこそ、大きなジャンル、Chant royal, Sirventés、そしてフォルクロールなどの作品も創造することが可能となった。この文学作品の創造こそ、19世紀におけるrenaissance occitaneの始まりである。
その後Fabre d'OlivetはLangue d'oc rétablieを構想する。ここでは確かに言語の神話的起源が夢見られてはいるが、それ以上に比較言語学的な枠組みをもつものであり、アルプスからピレネーにわたる地域の言語としてオック語を考えようと試みた。
(國枝付記)
ここで大切なのは、言語の復興が、文学言語の復興であるということ、言語への問いは、詩的言語の彫琢であることに、Lafontの言う18世紀的古典主義とロマンティスムの交錯が認められるということではないか。言語について問うとうことが、18世紀的なレトリックの創造になっているということは、言語そのものに対する視線が、文学へはむけられても、言語そのものの歴史性には届いていないことを意味する。それもそのはずで中世の作品を標榜しながら、ここで行なわれていることは、文献学的な探索ではなく、この時代の文芸思潮におけるオキシタン語の文学言語としての表現の拡大可能性なのである。母語を契機としながらも、その別離を越えて、表現へと立ち向かう時、Fabre d'Olivetの行なったのは、歴史的に高度な文学言語をもっていたオキシタン語の、19世紀初頭現在における彫琢であった。なぜ母語幻想が文学に結びつくのだろうか。
まずは12世紀の南仏の愛の形式を語る前に、11世紀末に書かれた『ローランの歌』の内容を概括し、「粗野で無骨な、戦闘的なゲルマン民族の一途な騎士魂の発露というものが見られ」るが、「女性への愛や雅の精神のひとかけらも」見られないと指摘する。
その上でトゥルバドゥールの検討にはいるが、伊東はまず、トゥルバドゥールの語源オック語のtrobarの起源を、アラビヤ語のtariba「喜びや悲しみにより心が動かされる」(p.250.)ではないかと推測する。また吟唱のために用いた学期luteもアラビア語が語源であるとする。 そしてジョフレ・リュデルやベルナール・ド・ヴァンタドゥールを取り上げて、その伝記に描かれる「命を賭ける愛」というテーマが、ギリシア、キリスト教世界にもなく、トゥルバドゥールに淵源をもつものであるとする。
伊東は、このような「ロマンティックラブ」の出現は、「アラビアに発してスペインのカタルーニャから南仏のラングドック、プロヴァンスへと伝えられたため」(p.259.)と推定している。実際にアンダルシアからスペインの東海岸に沿って、トゥルバドゥールに近いものがすでに存在していた。
ひとつの具体例として、13世紀前半の『オーカッサンとニコレット』が挙げられ、主人公の設定、名前にアラビアとヨーロッパの混淆がみられること、形式の上で、韻文と散文が交互に現れることがアラビアの韻文の形式に似ているなどのことから、「アラビア的色彩がきわめて強い作品において、典型的なロマンティック・ラブの物語が現れてきた」ことが指摘される。
実際に重要なことはアラビア文化のヨーロッパへの影響は、「十字軍と同一視」(p.264.)できるものではなく、上述のロマンス語圏がひとつながりとなって、文化を形成しており、「騎士道とか婦人に対する礼儀の理想は、イスラム教下のスペインで、一足先に作られていた」という事実である (p.264.)。
ではイスラムの騎士道とはどのようなものであったのか。イスラムにおいては、すでに「道徳・倫理上の準則があり、武術や馬術も立派な芸術」となっていた。11世紀から12世紀にかけてのスペインでは、すでに華麗な宮廷生活がなされており、貴族はすでに詩歌を評価していた。より具体的には、コルドバ生まれの詩人イブン・クズマーンが、アンダルシアで目覚ましい発展を遂げた叙情詩の形式の名手として知られ、女性をたたえた愛の歌は、その韻の踏み方においてトゥルバドゥールに影響を与えたと言われている(p.267.)。
また形式だけではなく、両者には、内容の上でも共通する点があった。「官能的な恋愛」、「恋人を守るために自分の身を犠牲にする男性の心情を歌うこと」、「女性への尊敬と奉仕」である(p.267.)。そして、このトゥルバドゥールは、スペインで発祥し、アラビア楽器のリュートとともに北上していったのである。一方武勲詩においては、ロマンティックな要素もなく、またオウディウスのラテン詩の伝統においては、「恋の手練手管」を語るものであり、トゥルバドゥールとは大きく異なっている。つまりは、アラビア世界に早くから存在していた伝統につらなっているのである。
そもそもアラビア世界には、ロマンティックな愛の観念の伝統があり、リュデルの歌った「遥かなる愛」は、『アラビアン・ナイト』680話にも見いだすことができ、さらに古くは、ウズラ族には、純潔の恋を歌う伝統がある。それをイブン・ダーウードは『花の書』にまとめている(p.272.)。
こうしたイスラムの愛の伝統を11世紀において受け継ぐのがイブン・ハズムの『鳩の頸飾り』である。第4章「噂に始まる愛」では、「噂を聞いただけでその女性が好きになり、熱烈な恋に陥るタイプの愛」を取り上げ、また第12章「愛の秘匿」では、恋愛の相手の名前は言ってはいけないというトゥルバドゥールと同じ戒律を述べている。伊東は、この書を「11世紀のスペインのハティバで書かれた、このアラビアの指南書が、その後のヨーロッパの同種の書の起源となると同時に、12世紀のトゥルバドゥールの思想に、何らかの仕方で少なからぬ影響を与えた」と結論づける。
さらに13世紀のはじめにはスーフィー神秘主義者の一人であるイブヌル・アラビーの愛の叙情詩集『渇望の解釈者』では、愛の象徴と宗教思想をつなぐものとして女性が描かれている。ダンテのベアトリーチェへの愛は、トゥルバドゥール的愛にこの形而上学的愛が重なったものとして解釈される。こうして最終的に、ダンテとペトラルアによってトゥルバドゥールの愛の形式は完成をみる。
最後にまとめとして、次の4点が「イスラムにおける愛の伝統がトゥルバドゥールの発生を刺激した」として述べられている。
- 時代的地理的関係
- 詩には歌がともなったが、それはリュートによって奏でられた。
- 詩の形式が、スペインで盛んであった詩の形式の似ている(ロマンス語の混入したザジャル体の詩)
- 詩の内容
Fabre d'Olivetは、Langue d'oc retablieにおいて、トルバドゥールの詩人たちによって、アラビアの詩形式が、現代の詩にまで伝えられた、つまりトルバドゥールの詩人たちは、アラビア文化の影響を受けて詩を書いたことを述べている。本論文では、このトルバドゥールとアラビヤ文化の影響関係が自明のこととして語られることに対し、それを前提としながらも、より精緻な指摘を行なっている。
まずはトルバドゥール芸術とはどのようなものであるか、愛について再定義を行なう。新倉のよれば、これらは「優れて精神的でありながら、最終的には肉体の合一を希求する愛を歌った作品」(p.287)であるとし、プラトニックな愛であるとするルージュモンに代表される考え方を排除する。そしてこのような女性を崇敬し賛美する文献が、すでに聖職者の手になるラテン語詩の中に存在する事実を指摘する。またさらに音楽の形式は、「西ヨーロッパの最もキリスト教的環境に生まれたとするのが、現在の通説である」とする(H.ダヴァンソン『トゥルバドゥールー幻想の愛』を参照)。
とはいえ、アラビヤ文化の影響もれっきとして存在する。新倉が挙げるのは、9世紀バグダットの「ウズリー的愛」の観念(p.299)、そして 11世紀初頭のイスラム=スペインにおけるイブン・ハズムの『鳩の頸飾り』である。後者については、特に第4章の「噂に始まる愛』が、ジョフレ・リデルを想起させるとする。それ以外にも第12章「愛の秘匿」における「恋の相手の名を絶対に口外してはならないとするトゥルバドゥールの戒律と軌を一にする」とする(p.290.)。以上に基づき新倉は「アラビヤのエロチックが、トルバドゥール分かの形成と精錬の課程においてかなり重要な役割を果たした可能性を否定できない」とする(p.291.)。
フランス文法の非ラテン語化
1. 形容詞の独立
ラテン語文法において、adjectifはsubstantifと同じ語形変化をすることから、品詞の一分類とは見なされていなかった。 substantifもadjectifも「名詞」のカテゴリーであった。フランス文法もこれを踏襲していたが、adjectifを初めて独立させたのは、l'abbé Gabriel Girardであった(Les vrais principes de la langue française, 1747)。以後、この方式がBeauzé, Court de Gébelin, Domergue, Lhomondによって継承される。
2. 語形変化の放棄
16、17世紀のフランス文法の伝統では、フランス語の名詞は、ラテン語同様、格変化をすると教えられていた。フランス語とラテン語を並列に扱うことによって、フランス語をラテン語の学習をするための、準備段階としていたのである。もちろん、教師も文法家も、フランス語から格変化は消滅していることは知っていたが、ラテン語の衰退を先延ばしにするためにこのような策を講じたのである。たとえばRestautは、先達と同じく、「nominatif(主格)はle Prince, génitif(属格)はdu Prince、accusatif(奪格)はle Prince」と記述している。 Restaut自身、フランス語の格は存在しないことは自明であり、「語尾は、単数と複数、男性形と女性形を区別するためにあり、ある名詞と別の語の関係を明示するものではありえない」と述べているにも関わらずである。
1670年から1750年にかけて、学校のフランス語文法の教科書は、格体系のフランス化を、統辞のレベルで考えることにより、格を nominatif, datif(与格), génitifの3つにまとめるようになる。しかしそれは、ラテン語の体系に模してフランス語を叙述するだけであり、たとえば、àに先立たれる名詞はすべてdatifとみなされた。こうしたラテン語とフランス語の間に起こる齟齬があったにも関わらず、ラテン語格体系のフランス化は18世紀なかごろまで続く。こうした格変化の放棄は、1794年のNoël-François de WaillyのGrammaire française, ou la manière dont les personnes polies et les bons auteurs ont coutume de parler et d'écrire (1763年の再版時にPrincipes généraux et particuliers de la langue françaiseと名前を改称)になってようやくなされたのである。
18世紀を通じて、Restautの著作とDe Waillyの著作は競合関係にあったが、徐々にDe Waillyが優勢となる。これはつづり字の教育が、基本文法の教育よりも重要視されるようになった流れと期を同じくしている。しかしながら1810年まで、フランス語の名詞の格変化は数々の文法テキストに残っていたのである。
3. 主格、«un cas particulier»
nominatifという用語は、フランス語文法の中でも使われ、その後sujetという用語が使われるようになるのだが、両者は同義語ではない。sujetとは「話題」であり、論理哲学では、「文の主辞」である。一方nominatifは格変化とは関係がなく、「動詞と一致をする語」という意味である。このように文法用語として、フランス文法においては、長らくこの「nominatif du verbe 動詞の主語」という言い方がなされた。
Propositionという概念の導入によって、sujetとcomplémentというコンセプトが広まったが、nomnatifと長い間共存することになる。sujetが広く優勢になるのは、1780年代のことである。
4. «particule»の消滅
Parciculeという用語の定義は、明確になされることはなく、たとえばイエズス会の教育者たちは、この中に、ラテン語学習を単純化するために、学習者にとって学習上の難問をこのカテゴリーに入れていた。
基本的にはparticuleは前置詞、接続詞、代名詞、冠詞を指す。18世紀のフランス語文法の発展にあわせて、particuleという概念もあらためて厳密さをもって文法理論の中に取り込まれるようになる。Pariculeが、完全にひとつの品詞として確立できるかどうかということをめぐり、Dangeau, Girardがそれぞれの著作(1717, 1747)でparticuleという章をさくが、実際には後継者はあらわれず、Restaut, Beauzée, Domergue, Lhomondもparticuleについては言及をしてない。また一般文法でも、純粋に便宜的に役に立つだけのこのカテゴリを認めていない。この一般文法と文法分析の勝利とともに、particuleは、他の品詞分類に改称されていく。しかしそれは1830年代に入ってからのことである。というのも、 particuleに何らかの意味を与えようとした教師や学校機関の長がいたからである。ある者は、たとえばpréfixeのような語をさすことで、他の品詞とは分類を分けたり、不変化語をここにまとめたり、と様々な見解が出されたが、対象が「小辞」であることを除いては、統一したものはなかった。
5. いくつかの痕跡
フランス語文法の非ラテン語化は、いくつもの跡をのこしている。たとえばrégimeはラテン語文法から生まれた概念だが、19世紀半ばまでフランス語の学校文法の中に残っていた。substantifはadjectifが品詞として認知されたときに、nomにとって代わるはずであったが、 Lhomond(1780)、Chapsal(1823)は依然としてsubstantifを使っていた。«nom ou substantif»という表記は実に20世紀初頭まで続くこととなる。
«Degré de signification»は、フランス語文法に定着しているが、それにも関わらずcomparatif, superlatifは教科書に留められ使われ続けている。
動詞の活用分類は、ラテン語の動詞が4つに分類されていたことから、それにならってフランス語も-er, -ir, -oir, -reの4つに分類されていた。最終的に3つのグループにまとめる分類方法が大勢を占めるのは19世紀末になってからである。言語学者たちは、4つのカテゴリーのうち、2つだけが現在も「生きていて」、新しい動詞を造ることができる、それに対して、他の2つはそうしたさまざまな活用をする、古い動詞が入れられているという根底的な違いがあるとしたのである。
この論文は、laconismeとabondanceという対立する2つの文体概念を取り上げ、一般的には革命期のディスクールはlaconismeを評価しabondanceを批判していたという論に対して、その両方が共存していたことを指摘し、laconismeを一方的な支配概念とする従来の見解に修正をはかっている。
I - Le laconisme
論文はまずlaconismeの系譜を辿る。その哲学的観点から挙げられるのは、ジョン・ロックである。人間知性論の中でロックは、「レトリックの方法は、完全なるまやかしをつくる」と主張し、以後啓蒙主義の思想の中では、演説者の「まやかし」を批判することがその課題となる。革命期においては、コンドルセが「演説においては、雄弁に頼る者は、人々の理性をまどわせるだけである。国民の代表者が行なうべきことは民衆の啓蒙である」として、雄弁を断罪する(Condorcet, Rapport sur l'instruction publique, 1792)。またシェイエースなどイデオローグが提唱するのは、分析体«style d'analyse»であり、これは哲学言語として記号の一義性を求めるものである。
文体論からみれば、このlaconismeにたいする「趣味」は、イエズス会などのloquacité(饒舌さ)にたいする嫌悪からである。反対に laconsimeの評価は、たとえばJaucourtによって書かれた百科全書の項目にみられる。またJaucourtの前にはモンテスキューが法的言語は簡素であることを指摘している。革命期においてもlaconismeの文体こそがautoritéが持たなくてはならない言語であるとする。
Il est temps que le style mensonger, que les formules serviles disparaissent, et que la langue ait partout ce caractère de véracité et de fierté laconique qui est l'apanage des républicains. (Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française, 16 prairial an II/4 juin 1794)
嘘の文体、隷属的な表現は消え去る時がきた。言語は、どこにおいても、本物であることと、簡潔さを誇りとする性質をそなえる時がきた。この性質こそが共和主義者固有のものだ。
以上、革命期においては、laconismeこそ、議会、教育といった公のあらゆる場所で重視されるべき文体であると言える。しかし、その一方で、それとは逆の考えも存在した。
II - Un anti-laconisme ?
まず大切なのは、ロックの主張が18世紀の主張がかならずしも支配的な考え方であるとは言い切れないことである。たとえば、synonymeの考察をする立場からは、かならずしもlaconismeが悪いとは言い切れない。Synonymes français(1736)を書いたGirardにおいては、正確に話すことと雄弁であることは矛盾しない。Beauzéeはpléonasmeや métaboleを、 Marmontelは、abondanceやamplificationを使用することを進めているほどである。これは2名に関しては、同時代の中で古典主義的規範に属する人物ではないかという反論もあろう。しかし同じ考えはDiderotやRousseauの中にも認められる。さらにRousseauの後継者を自称するMaratは、«éloquence du coeur»(心の雄弁)を主張する。
III- Deux modèles discursifs pour deux situations de parole
実際に啓蒙主義者たちにとっても、絶対君主制の批判のためには雄弁は必要であったし、百科全書派も、こうした単純な対立を乗り越える道を探っていた。たとえばMarmontelはジャンルによる区別、哲学においては、laconismeを、詩や弁論においてはabondanceを提唱した。前者においては語の「本質」が問題とされ、後者はより「自由」であり、正確さがあれば十分であるとする。また革命家たちも法律の執筆においては laconismeを採用するものの、決してabondanceを捨て去ってはいない。たとえばDomergueにとってはlangue exacteとlangue ornéeは等しい価値を持つものとして扱われる。
La langue exacte est d'une utilité reconnue par tout le monde, sans exception. Ces grands écrivains, qui embellissent la raison des charmes de l'éloquence et de la poésie, en font aimer et en étendent l'empire. La langue ornée va devenir très utile à toutes les institutions publiques, à tous les jeunes gens que le nouvel ordre des choses destine à porter la parole dans les assemblées civiques, à toutes les personnes de l'un et de l'autre sexe qui voudront être initiées dans l'art d'écrire. (Domergue, Journal de la langue française, n° 4, 22 janvier 1791, p. 134-135)
正確な言語は、例外なく全員が有用性があると認めている言語である。これらの偉大な作家たちは、雄弁と詩の魅力で理性をより美的なものとして、理性を愛させ、そしてその帝国を広げるのだ。飾り立てられた言語は、あらゆる公の組織にも、物事の新たな秩序によって、市民の集まりで発言をするようになる若い人々にとっても、書く技術を身につけようとしている人なら男女問わず、有益な言語である。
さらにLa Harpeは弁論術の手ほどきを提言する。また革命期中の唯一の弁論術の書、Drozのl'Essai sur l'art oratoire (1799)は、最終的にはいかなる反響も呼ばなかったが、雄弁の最終的なコンセプトがここに存在する。「自由な状況における弁論術の有用性」ということである。
以上、laconismeとabondanceは概念的な対立があるのではなく、言語のジャンルによって使い分けられるべきなのだ。すなわち哲学者、立法者においては前者の、詩人、演説家においては後者の使用が勧められるのである。
この論文で扱われているのはフランスの文献学の成立における政治性と、その言語と政治の関係性を覆い隠すことによって、言語学の科学性が打ち立てられるようになった19世紀における言語への問いの変遷であり、それをロマンス語の重視と、基層文化としてのケルトの重視という2つの「極端な考え」を、 François RaynouardとFrancisque Michelの活動によって検討するとともに、そうした極端さ、いわば偽りの科学が消えるとともに、中性化された言語学が生まれたことを明らかにする。
まずはロマニスムである。トゥルバドゥールの詩によって代表されるオック語文学は、その草稿が個人によって所蔵され、忘れ去られていたが、18 世紀になると、中世の遺産に注目が集まることになる。しかしそれが文学研究となるためには、コーパスを整備し、一貫性のある原則のもとで研究されなくてはならない。それを最初に手がけた人物として位置づけられるのがFrançois Raynouardである。
アカデミー・フランセーズ辞書第5版の共同執筆者でもあったRaynouard(1761-1836)は、1816年から21年にかけて、Grammaire comparée des langues de L'Europe latine avec la langue des troubadours, Choix des poésies originales des troubadoursを編纂、出版する。そしてこの中でRaynouardは「プロヴァンス語が諸新ラテン語の起源にあった」と主張した。一方今日でも彼の主要な著作とされているのは、死後出版も含む1836-1844年にかけて編纂された6巻本、Lexique roman ou DIctionnaire de la langue des Troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latineである。この書において十分な文献がそろったといえる。ここにおいてロマンス語とは何か、その位置づけが確定することになる。つまりプロヴァンス語が一文化として復活したわけである。
Saint-GérandはRaynouardのトゥルバドゥールの言語に対する考えを次のようにまとめる。
11世紀に新ラテン語諸語の分化が決定的になる前に、ラテン語からロマンス語が生まれており、これが«intermédiaire»、「介在」となっている。ストラスブールの誓約とBoèceの物語を語る南仏の叙事詩がこの言語の書き言葉としての形態を伝えている。1000年頃のシャルルマーニュ帝国の分割後も、この言語は現在の南仏諸地方言語でありつづけた。この考えにしたがえば、ここで推定されるロマンス語とは、ラテン的価値をヨーロッパの別の言語を通して保証していくことになる言語の母であり、かつその長女ということになる。そしてヨーロッパ諸語は、それぞれの民族の発音に対応した変化をこのロマンス語に加えることになったとRaynouardは言う。たとえば、ラテン語のpanemは、南仏、あるいはプロヴァンス語ではpanとなり、これがイタリア語でpane, フランス語でpainとなったとする。このRaynouardの主張が否定されるためには1836年のFriedrich DiezによるGrammatikを待たなくてはならない。これをもってようやくプロヴァンス語も他のラテン語系の言語と等しい位置におかれたのである。
Raynouardの論拠の出発点となったのは、オイル語の音声は、オック語とは異なり、後者が昔からの音声の色合いを保っていたという点である。しかしSaint-Gérandは同時代におけるイデオロギー的なコンテクストを2点指摘する。
まずは比較言語学の影響である。その思想的影響とは、すなわち、印欧諸語を通して、言語と宗教の起源へと遡ることができ、それが人類の文化の原初的状況を明らかにするという点である。この視点から言えば、Raynouardにとってのプロヴァンス語とは、まさに原始語といってよい地位を持っていたのだ。言語の過去を遡ることは、文学テキストという形式のもとで、文化的な財産、共同体の伝統の一部となっていくことを意味する。こうした国民、民族意識は、政治的な意図に先立っているのだ。
2つ目にあげられるのが、詩という表現形式である。スタール夫人が、「ロマン主義の詩がトゥルバドゥールの詩がその起源となっている文学の直接の後継である」だと言う時、このロマン主義の詩とは、フランスという民族、フランスという土地に結びついているものである。この主張は、 Raynouardにとっては、プロヴァンス語とトゥルバドゥールの作品は、民族とその祖先へとつながる伝統を持っていたことを意味する。 ではRaynouardの「誤り」はどこにあったのか?第一の段階においては、Bopp, DiezのようにRaynouardも言語を、言語以外の人間的事象から分離させ、文字、語、語源について歴史的変遷を考察していた。しかし次の段階において、こうした言語形式を、トゥルバドゥールの文学作品に結びつけることによって、言語の中に原初の人間の真実というものをみようとしたのである。この点がSaint-Gérandが指摘する「誤り」である。つまり言語外のものへの言及は、言語の科学性を証し立てるのに役立たないのだ。
次にFrancisque Michelのスコットランド研究が挙げられる。Michelは1830年代から中世のテキストを出版し始めるが、特にイギリスにわたり、様々な第一次資料をまとめあげたことで知られる。つまり国民文学を作り上げるために必要な草稿を収集するのに寄与したわけである。Saint-Gérandが詳細に分析するのはCritical Inquiry into the Scottish Languageである。
Saint-GérandはMichelのテキストを10の要旨にまとめている。1)スコットランド語が古英語の方言であるとすることへの批判、2)英語とスコットランド語は同じ語根を持っているがそれぞれ独立して変化していったということ。3)スカンジナビア諸言語のスコットランド語の単語に対する影響、4)ノルマン民族によるケルト世界の没落と、フランス文化のイギリス圏における影響、5)文学にも適用される氏名の、語源にさかのぼっての作成、6)中世初期におけるフランス語の宮廷における浸透、その一時的衰退と14世紀における復活、7)パリの大学で学んだスコットランドの僧侶たちの言語、文化に対する影響、8)托鉢修道会における説教の言葉への俗なる現地の言葉の使用、9)蔵書における、フランス文学の資料への強い興味、10)スコットランド文学へのフランス文学への影響。つまりMichelの主眼は、フランスという言葉の定義もおろそかに、フランス文学の、スコットランド文化創成期における影響を謳っているのだ。以後、言葉にはひとつの亀裂がはしり、フランス語をモデルとした技術に関連した言語を使う層と、ゲール語の影響を受けた共通語を使う、洗練されていない社会層である。この社会層の中ではフランス語からの借用語は急速に消えていった。
Michelが集めた原典や歴史に関する情報は、同時代においては「信頼に足る入念な仕事」と評され、この時代において知りうることはすべて集約された観があるテキストである。しかしながら、MIchelのテキストにおいては、フランス人がスコットランドに文明をもたらしたという前提がいたるところで見られ、文献学の批評理論にのっとった作業はなされていない。しかしこのような指摘では単に言語学を学問内部に押し込めるだけで、Michelにみられるイデオロギー性、政治的な意味は浮かんでこない、とSaint-Gérandは指摘する。そのためにSaint-Gérandは、Michelにおけるlangueの厳密な定義、そして言語学の論争から生まれてくる様々な考えー国民語、ケルトとロマンスの対立、方言研究の目的と結果ーに着目する。
Michelにとってlangueとはmoyen de communication quotidienne dont la littérature fournit l'image la plus intéressante parce qu'elle en fixe le mouvement et permet l'inscription de norme d'usage「日常のコミュニケーションの方法であり、そのもっとも興味深いイメージは、文学が、その動きを固定し、慣用という規範によって書き記すことによって、もたらしてくれる」という直感的なものでしかなかった。それによってMichelはフランス語は、文明化された社会の表現媒体であり、それがスコットランドにもたらされたという文化論に終始してしまう。またさらに「フランス」語、「フランス」文化、と言った時のフランスそのもののアイデンティティも問われることがない。またスコットランド語の方は、当時の言語学者たちが規定していた「クレオール化」している言語とみなされていた。
第2にSaint-Gérandが挙げるのは、Michelの文献学がロマン主義の時代を出発点としていることである。Saint-Gérandはかつての外交官であったPaul de BourgoingのLes Guerres d'Idiomes et de Nationalitésを取り上げ、言語の特殊性に基づく国民的要求が起こったのが、19世紀半ばであり、これが政治的混乱を作り出しているとするBourgoingの指摘に言及する。この考えに対する返答が4年後のAuguste ScheleicherによるLes Langues de l'Europe moderneである。ここでは民族の歴史が言語の歴史によって強化される。
一方D.Monnierは1823年の時点ですでに、音声現象にもとづく地理的な図を作ることを考える。1844年にはNaberが英語とスコットランド・ゲール語の境界を画定する。1866年、Schuchardtは言語的な境界線が引けるとしてもそれはメタフォリックにしか可能ではないと強調する。1878年にはSébillotがブルターニュの地においてgalloとbritonとを区別する。こうした事実はイデオロギーの反映に他ならない。つまりスコットランド語の語彙の多くがフランス語で構成されているということは、ケルト語の拡張に反対し、ロマンス語に起源を求めることと等しいのであり、征服者のケルト人を文明世界の境界へと、印欧語族の隅へと追いやることに等しいのである。
こうした時代の流れをみてくると、Michelは結局言語を語彙の分類というレベルに限定して、国民的同意によって統一化される共同体の政治表現形式としてのlangueには行き着いていないのだ。Michelの言う、文明の進歩、文献学の方法論といったものの背後には実は、政治性が露見してしまうのだ。 結果として、RaynouardやMichelの考えは、ロマンス語あるいはプロヴァンス語の優越化、フランス文化のスコットランドへの流入という「非学問性」のために、否定されるに終わる。しかしそれにともなって登場した科学とは何か?1866年、言語の起源という言語外的要素に依拠する研究を、パリ言語学協会は拒否する。それはしかし同時に、言語のもつ政治性を覆い隠してしまうことになった。文献学の起源は、起源の問いを無化することから始まり、やがて国語の単一性のために、ロマニスムとケルティスムの対立を消し去ったのだ。つまり学問の科学性は、国家語という政治性と新たに結びつくことで成立したのである。
この「芸術について」という章で明らかにされるのは、ヨーロッパの普遍的な言語になったフランス語が、どのように自らの資質をルイ14世紀下において、完璧にまで高めたかということである。
フランス語がそのような普遍的な地位を占めるためには、ラテン語を凌がなくてはならないが、まず冒頭で紹介されるのは、法律家たちがラテン語では立派な文章がかけても、フランス語ではそれが不可能であるという現実である(p.62.)。
しかし、フランス語の格調高さ、耳への心地よさが、説教という雄弁術(ジャン・ド・ラジャンド)や散文(バルザック)にも見受けられるようになる。そしてフランス語の純化に大きな役割を果たしたものとして、アカデミー・フランセーズ、ヴォージュラの名が挙げられる(p.64.) 。ラ・ロシュフーコーの『箴言集』も、その表現、考えを圧縮した「簡素かつ微妙」な表現という点で引かれている。そしてフランス語の形を決めた作品として、ヴォルテールはパスカルのLettres provincialesを挙げる。またボシュエについても『世界史論』を挙げ、評価するのは、もっぱら、その文体、「雄渾な筆致」、「簡潔で真に迫る表現」である(p.68.)。またこの時代においては、古代にはなかった形式が生まれる。それがフェヌロンの『テレマック』、ラ・ブリュイエールのLes caractèresである。後者において、ヴォルテールは「緻密で、簡潔で、力強い文体、絵画的な表現、斬新で、しかも文法的な規則に背かぬ文章」と述べている(p.71.)。
続いて、ヴォルテールは国民文学の概念に言及する。国民の文学は、「まず詩が天才の手で生まれ、これに導かれて雄弁が現れ」るとする(p.73.)。そしてフランスの場合散文の技量を進歩させた作家としてコルネイユがひかれる。
ヴォルテールは次にラシーヌを引くが、このラシーヌ観こそ、17世紀におけるフランス語の完成という主張の代表であると思われる。ラシーヌはヴォルテールにとって「言葉の自然な美しさを、いわば完璧の域に到達させた」(p.76.)作家である。
ルイ14世の時代の最後に出た作家として挙げられているのがラ・モット・ウダールとジャン=バティスト・ルソーで、後者についてはマロを引き合いにだしているが、マロの文体を「無様な」ものとし、それに対して現代は「純粋な言葉」であるとする。
ヴォルテールは、「時代と、主題と、国民性にふさわしい美」(p.83)は限定されており、一人の作家がそれを表現しえたなら、あとの時代は何も表現することがなくなると述べ、まさにこの時代が、芸術の完成された時代であると位置づける。
そして最後に、いささか唐突に、「フランス語はヨーロッパ語になった」と述べる。ルイ14世紀の偉大な作家たちの後継者が、フランスから外へ出ることによって、フランス人持ち前の社交性を生かし、他国民にフランス語を広めたのである。
Urbain Domergueが1791年から1811年までに設立した言語学の団体についてその詳細を検討するとともに、団体の組織が何にモデルにして構成されたのかを明らかにした論文。4つの団体について言えることは、そのどれもがフランス語の普及と完成を目指していることである。会誌を発行しながら(Le Journal de la langue française)、フランス語の具体的な問題を解決していくことを目的としている。
これらの団体は、いずれも同時代の政治的状況と密接な関係を持っている。Domergueは、時の革命思想を指示した、熱烈な革命主義者であったが、彼の団体はその言語的活動における実践である。délibéranteやlibreという言葉、また«La langue française est devenue un besoin pour tous»というSociété libre des amateurs de la langue françaiseの標語に示されているように、国民みなにむけたフランス語のモデルの具現化という使命を持っている。
国家とフランス語という問題に解決をもたらすという団体の活動は、当然ながらAcadémie françaiseの活動をかさなってくる部分がある。Domergue自身、Académie françaiseの改革案を何度か提案している。40人に限定するのではなく、広く才能ある作家に席を用意し、衆人の目の前で言語の完成のための方策をはかっていくこと(Prospectus de la société des amateurs de la langue française 1791)、言語は3つの方法で完成されることー天分をもつ作家の作品、書く方法についての考察、文法についての洞察ーそして、それだけでなく、一般の言語の愛好者も含めること(le 15 mars, 1788)を提案する。実際1795年にアカデミー入りしたDomergueはAcadémieと自らの団体を橋渡しする役目を担った。
では、このようにAcadémieとは異なる実際的な役割をもった団体は、どのようなモデルにそって構成されたのだろうか?これは疑いようもなく、Républiqueのモデルである。Domergueは言語を完成へ導くという目的の具体的イメージを「憲法の高みまで我々の言語を近づける」と表現している。
団体の組織と機能は、Assemblée législativeをモデルにしている。各種のcomité(委員会)で個別の問題が討議される。メンバーはどの委員会に、いくつ加入しても自由である。またAssemblée nationaleが政治の問題を議論するように、団体のAssemblée généraleも言語にまつわる種々の問題を取り扱うことになる。このようにDomergueにおいては、政治がまさに言語のモデルとなっていたのである。以後こうした団体は1837年のSociété linguistiqueまで続くこととなる。
以上が論文の概要であるが、ここで留意したいことはDomergueがCondillacと同じく、言語の完成には、grands écrivainsの存在だけでは不十分であると考えていること、同様にgrands écrivainsのフランス語はフランス語の完成ではなく、規則も明確で、だれにも等しく手に届く言語になってこそ、完成であると考えていたことである。もちろんDomergueはLe Jounalで言語をexacteとornéeにわけて、grands écrivainsを排除してはいない。しかしその影響力はきわめて相対的なものへ低く見積もられている。Académieの改革案で4つの社会カテゴリーが提案されているということは、裏を返せばGrands écrivainsは言語を完成するためのその一部にしか過ぎないのである。革命期にあっては、Grands écrivainsだけがAcadémieを支配することは、貴族階級の特権にひとしく、社会を抑圧することにしか働かない。愛国主義者Domergue はアカデミシャンもふくめ、国民が広く参加する「文芸の共和国」を構想するのである。Domergueのjaconbin派としてのDeviseはまさに régénération des languesである。その意味からも、新たな言語の完成を考えることは必然であったろう。そして新たな言語、すなわち明晰な言語とはidéologue の考えにそった、一言で言えば「語ともの」の一致をめざす言語である。そして、ならば、どのようにフランス語の規則を明確にしていくかがその課題となってくるのである。
ユダヤ系フランス人の言語学者Arsène Darmesteterの歴史的位置づけを、社会学的観点、特にブルデュー理論に依拠し、学問を社会的・歴史的制度として捉える観点から検討した研究である。
Arsène Darmesteterは1846年に生まれ、1888年に42歳の若さで世を去っている。早くに世を去ったこともあり、その業績は忘れ去られた観がある。しかし決してDarmesteterの業績が価値のなかったものではない。その再評価を試みたのがBergouniouxの本論文の意図である。
19世紀後半のユダヤ系フランス知識人にみられたように、Darmesteterは、ユダヤ人であることをその特殊性ではなく、フランスの中に同化させることから研究を初める。21歳から準備し始めた博士論文の研究、Les Laaz(ヘブライ語の語彙の欠如のために、古フランス語から借りてきて、ヘブライ語で表記した言葉)は、ユダヤという過去と、自分の祖国フランスという2つの文化的潮流を融和させるものであった。ここには「人種や祖先ではなく、文化への忠誠を誓う愛国主義」(p.109)がある。
故郷のLorraineを離れたDarmesteterはEcole pratique des Hautes Etudesのロマニスト、オリエンタリストたちに迎え入れられることになる。ここに集った面々の特色は1)ラテン・ギリシア研究を行なうソルボンヌに大公して、中世のフランス語テキストを典拠とすること、2)大教室での授業ではなく、少人数でのセミナー形式であること、3)言語そのものを研究対象とすること、であった。ノルマリアンでもなく、また反ユダヤ主義からも守られた場所として、DarmesteterはGaston Parisによってこの場所に迎えられることになる。ここでLaazの研究を押し進めるわけだが、しかし、父の死などもあり、経済的に困窮した DarmesteterはHatzfeldの辞書の編纂に関わることとなる。
1872年DarmesterはE.P.H.E.で自習監督となる。この時期提出した論文De la formation des noms composés en françaisでは、これまでゲルマン系の言語にしかなく、それがこの言語の優位の根拠となっていた、名詞の複合をロマン語系のフランス語に認める内容であった。
当時の言語学を巡る社会学的状況を考察すると、文学のヘゲモニーにたいする言語からの対抗と言えるであろう。「趣味と感受性」、「文芸の創造的特質」、「Lénientの中世の愛国的な詩についての講義」にたいして、「ドイツの批判学派」、「文献学の不毛さ」、「Parisによる聖アレクシスの講義」という対立である(p.112)。もうひとつ重要なのはロマニストたちが、フランス語のmanuscritsを対象とする過程において、ロマン語同士に生まれるのは、civilisationを基軸とした共同性であり、これはスラブ、ゲルマン系のraceに基軸をおく考え方とは根本的に対立している。
DasmesteterがE.P.H.E.で直面した研究課題は、phonétiqueとsémantiqueである。Phonétiqueに関しては、文学よりの研究者たちに、音の価値を認めさせることが課題となった。この分野では«La protonique, non initiale, non en position»(1876)という論文で、accent toniqueの問題を扱っている。Sémantiqueに関しては、«Sur quelques bizarres transformations de sens des mots»(1876)で、言語の変化における意味の問題を扱っている。
1877年Darmesteterはソルボンヌにおいて二つの博士論文を提出する。ひとつはラテン語で書かれた文学論で、ここで Darmesteterは、国民的な伝説が、トゥルヴェールによって詩形式におかれ、ヨーロッパ全般に広まったとする。この見解は、ドイツの学会のゲルマン系の神話学に西洋叙事詩の伝統を置く考え方と対立し、また文学部の、叙事詩の起源はラテン語であり、僧侶たちによって伝えられたものだという考え方とも対立する(p.115)。この見解は、民衆のなかから創作者が生まれたとするロマン主義の考えと共通するが、これを契機として、Mistralと接近することとなる(1883年には«Félibrées de Languedoc»をMistralとともに主催する)。
フランス語の博士論文は、De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française et des lois qui les réagissentという題名で、まさに文学言語ではない言語を扱うという意味で、ソルボンヌの教授陣にとっては、ほとんど承服し難いものであった。Saint-René Taillandierの助けのもと論文は受理され、Darmesteterはソルボンヌの教授となる。
Romaniaがあまりにも文学的であったためDarmesteterはRevue Pédagogiqueに投稿するようになる。この雑誌は高級官僚による教育改革を目指して作られたものであり、Darmesteter自身 E.N.S.de Sèvresの女子学校でフランス語文法を教えることとなる。この時に編まれたのがCours de grammaire historique de la langue françaiseである。また綴り字改革の提案にも賛成の立場を表明する。
70年代暮れから、DarmesteterはRevue des Etudes Juivesに関わることになる。ここでも彼が目指したのは「賞賛もロビーの精神もない」歴史研究である。1886年にはLa vies des mots étudiée dans leurs significationsを書くが、これは最初の意味論のテキストであると言ってよい。
しかし、1888年に42歳の若さで亡くなる。この早すぎる死によって、辞書における功績はLittréの影に隠れてしまい、意味論の研究は Bréalの華々しい活躍によって忘れられてしまった。また音声学における功績も、文字中心の研究の中では、かき消されてしまった。また彼を継承する弟子もいなかったことがDarmesteterを忘れられた言語学としてしまったのである。
テキストは、Etienne Pasquier, Recherches de la France(1561)の引用から始まる。 Pasquierはフランス語がラテン語に匹敵するだけの価値をもち、イタリア語よりも優れた言語であることを同書で述べた。しかしフランス語の出自が「俗なる=崩れた」フランス語であり、また、中世における言語の混乱状態(様々なidiomeの存在)を持っていることは、フランス語を顕揚する上で、おおきな支障となった。ここからフランス語の起源の神話形成が始まるのである。崩れたものではなく、純化された起源、あるいはラテン語以外の起源の探求、単一性と一貫性の検証、そしてIle-de-France優位の論証付けなどである。Cerquiligniは、français orphelineが正統なる両親=出自を求めていく歴史を緻密に跡づけていく。
Chapitre I MISERE DE FILIATION
第一章Misère de filiationは、フランス語とラテン語の関係をめぐる考察である。法律文書におけるフランス語使用を義務づけたヴィレ=コトレの勅令(1539)や、Louis Meigretによる最初のフランス語文法書(1550)が示すように、16世紀半ば以降、フランス語が支配を拡大するようになった。それと同時にこの言語の起源の探求が行なわれるようになる。そして、ヘブライ、ギリシア、ケルト諸語(ケルトマニーの強い運動があるとは言え)ではなく、ラテン語をその起源とするためには、なぜラテン語とフランス語は、屈折、語順、単語、どれをとってもかくも離れているのかを証明しなくてはならなかった(p.15.)。ここで生まれるのは、Claude Faucher(Recueil des Antiquités gauloises et françoises, 1579 ; Recueil de l'origine de la langue et poésie françoise, 1581)やGilles Ménageのような混合説である。しかしケルト系、ゲルマン系の影響を認めながらも、柱となるラテン語を古典ラテン語に求めていたところに限界があった。
こうした«érudits»には堪え難い事実、それがラテン語には古典ラテン語以外に、もうひとつのラテン語、こちらは古典ラテン語より劣った、田舎の、そして民衆のラテン語である。このラテン語こそ、フランス語の起源となったラテン語である。この考え方が主張されるには18世紀を待たねばならない。 Cerquigliniが重要視するのがPierre-Nicolas Bonamyである。BonamyはSur l'introduction de la langue latine dans les Gaulesのなかで、フランス語の起源は「日常表現の中で話され、使われていたラテン語に他ならない」と明確に主張する(p.18.)。フランス語の起源を俗ラテン語とする考え方は、この時点においても大胆きわまりないものであった。
18世紀におけるフランス語は矛盾を抱えていた。それは普遍的な言語として、ヨーロッパに拡張する傍らで、フランス語は17世紀に古典主義の作家によって完成され、以後は頽廃をしていくしかないという矛盾である。したがって思潮はpurismeという言葉通り、規範からの逸脱を許さない保守主義的傾向にはいっていた。そうした傾向のなかで、名声を克ち得たフランス語が「泥にまみれた出自」(=une source bien bourbeuse, p.21)であるという事実こそ、文法家たちをメランコリーに追い込むものであった。
しかし、メランコリーの要因は、その親となるラテン語の性質だけではなく、様々な他の言語との接触による「クレオール化」にもあった (p.23.)。つまり、10世紀におけるフランス語のプロトタイプは、口語としてのラテン語が、ゴロワと接触し、そして続いてフランク、すなわちゲルマンとの接触をうけて形成されたのである(そしてゲルマンとの接触が強かった北部ではlangue d'oilが、弱かった南部ではlangue d'ocが形成されることとなる)。
ならば、puristeたちはどのような方向へ向かうのか?それはフランス語を上品で、ラテン語に匹敵するものにするという古来からの欲求の充足である。それが新旧論争における、Modernes派の勝利である。ここでフランス語の顕彰は、王を讃えることと同義となる(p.26.)。 Dominique BouhoursのEntretien d'Ariste et d'Eugèneをひきながら、Cerquigliniは、出自不明のフランス語でありながら、その比類なき精髄(génie)、大作家による賞揚、そしてフランス王によってもちいられることによって、フランス語が「偉大さ」を獲得する過程を追う。
出自の不明をあがなう方法としては、上述のフランス語を高貴なものにする以外に、フランス語の「ラテン語化」が挙げられる(p.28.)。ラテン語からの借用による新語の増加(たとえば、entierに対応するintègre)、つづり字(書かれた文字としてのフランス語は、ラテン語に典拠する)におけるラテン性の保持である。ここからフランス語を改革することに対する論争の激しさも理解できる。またその言語的アイデンティティを脅かすようなヴァリエーションの存在への嫌悪も理解できる。
こうした単一性を乱すものへの恐れは、政治的理由とも関係する。たとえば19世紀のRaynouardがlangue d'ocはlangue d'oilの前身となる形式だということで、単一性のほころびを回避する(p.32.)。Langue d'ocのラテン語との近親性、文学的成果などにもかかわらず、言語的多様性は、「豊かさ」(abondance)ではなく、「放棄」(abandon) に結びついてしまう。それはすなわち、地域の口語への軽蔑や、patoisの撲滅、第三共和政の代表的ロマニスト、Paul MeyerやGaston Parisのgallo-romanに本質的な単一性を認めようとする試み、といった政治的、歴史的、そして学問的態度にまで現れてくるのである。
Chapitre II EPIPHANIE PARISIENNE
この章では、パリの言葉が、フランス語の規範とみなされるに至った歴史的経緯を振り返る。Cerquigliniによれば、言語的優位性をある地域に与えるならば、それはどこがふさわしいかという問いは、歴史的には二つの時代、16世紀と19世紀に検討されることになる。この章では、16世紀にパリをその地として選ぶに至った経緯を跡づける。
まず、パリの言語的優位性の考えが、同時代のイギリスから出てきた(フランス語を外国語として考察する時代に入ったことを意味する)ことに言及した後、フランスにおいては、言語は変化する、要は、頽廃に向かっているという悲壮な考えから出発しているために、当初は、パリの言葉も他の方言と同じく、不完全なものであるという認識があったことを指摘する。これはたとえばGeoffroy Tory(Champ Fleury, 1529, p.39)のように、そうした認識をもつ人物がラテン語学者であったためである。また同じ認識にたつJacques Duboisは、フランス語をラテン語のような当初の純粋性を取り戻す意図をもって、文法論を書くが、その典拠となったのはノルマンディー、ピカルディー方言であった。Charles de Bovellesはよりいっそう悲観的に、言語の混乱状態を嘆く。パリの言葉もその分散してしまった一方言に過ぎない。
したがって、パリの優位性という考えが出てくるためには、まずは俗なる言語に対する肯定的な考え方が始まらないといけない。これは同時に俗なる言語としてのフランス語を、そのもの自体として考察するということを意味する。その第一歩がLouis MeigretによるLe Tretté de la Grammere Françoezeである。ここでMeigretは、正しい用法を、パリ、すなわちフランス宮廷、すなわち王とその一族に求めるのである(p.43.)。この問題を考えるにあたっては次の二つの要素を考慮する必要がある。
まず、言語の規範を問うときにおける社会階層という観点である。Ile-de-Franceから特にパリに言語的優位性を与える考え方が広まる。しかし優位性は地理的な意味だけではなく社会的な意味でも問われなくてはならない。たとえばHenri Estienneにおいて、規範はパリのエリートたちの言語である。これは社会的にみて、パリは一様ではないことを示している。たとえばRamusは、パリの民衆のことばに規範をもとめる。しかしパリの民衆の口語は、以後価値のないものとして貶められ、社会階層的な亀裂が生まれる。つまり言語の規範化を問うことはこの時点ですでに社会階層的要素を含み込むものだったのである(p.46.)
次にEtienne Pasquierによる宮廷言語の批判である。ひとつはフランス語の最もよい用法フランソワ一世の時世においてのみ達成されたということ。二つ目は、パリの優位性により、他の口語はその正当性を失っていくが、そうした言語から、パリの言葉は様々な言葉を吸収していくということである。
Chapitre III LA FABRIQUE DE L'ORIGINE
この章では、19世紀におけるフランス語の起源についての思潮を扱う。19世紀とは史的言語学が形成された世紀である。印欧語族の系譜について科学的に検証され、フランス語がラテン語起源であることはもはや前提となった。それと同時に、ナショナリスムの勃興によって、国民語、つまり国語としての言語の起源の探求が始まることになる。そして、フランスにおいては、この国民的共同体は中世に求められることになるのだが、このことがまた失望を生んだ。そしてそもそもがこの考え方自体が誤りに満ちたものだったのである。
失望ーそれは、中世に国語の起源を求める場合、その資料となるのは、文学作品であったが、それがおおよそ統一的な基準を欠いたヴァリアントの集積として、目の前に呈されたからである。その意味でこの時代の学問は、一見ばらばらな状態にみえているテキスト間をつなぐような法則性を求めていくことになる。しかしそれがはたして真正なるものなのか?ここに疑問が生まれてくる。
では実際にはどのような解決策がはかれるだろうか?ひとつは文学作品ではなく、尚書局の証書の現物を資料として用いることである。日付も場所も確定できるし、公的文書である以上、書き手の主観も混じることがないので、まさに信用できる資料、というわけだ。こうして1821年、古文書を解読する専門家を要請する期間が設置され、以後、19世紀を通じ、現在にいたるまで、古文書の出版がなされる足場が築かれた。問題はフランス語で書かれたといえる公式文書は、13世紀以降にしか現れず、それ以前のものはやはり文学作品に頼る必要がある。しかし、国家語としてのフランス語を考えるには、こうしたテキストに現れる言葉はあまりにも一貫性を欠いたものであった。
この問題を解消するのが文献学の読解方法の厳密な適用である。それにより、変質前のテキストと言語の、完全な形での復元が可能であるとされる。 Lachmannの方法によれば、数学的方法によって、正しい読み方を決定することが可能であり、それによって、作品のオリジナルな状態、すなわち、作者が最初の書記に書き取られた状態、誤りのない状態が復元できるとする。CerquigliniはこうしたLachmannの方法論に、初期の印欧語族研究と同様の、比較という方法論、復元の欲求、そして始源の状態からの頽廃という要素を指摘する。これは始源から線上につらなる、過ちの系譜であって、それゆえにヴァリアントが生まれるのだという考え方である。Lachmannによれば、同じ間違いはそのまま引き継がれ、またある一つのmanuscritと複数のmanuscritの対立がある場合は、後者に真正さがあるとする。
Cerquigliniが批判するのはこの、真正なるテキストという大前提、それに伴う著者という独自の存在それ自身である。つまり Cerquigliniによれば、中世の作品というものは、口語にきわめて近い書き言葉の文化に属しており、著者概念、さらにはそれを取り巻く権威という概念はさらさらなく、常なる書き換え、解釈をもたらすものであった(p.58.)。これがラテン語、ギリシア語を対象とする文献学と異なる点である。
たとえば聖アレクシスの校訂を出したGaston Parisは実証文献学の目的は「作者の手を離れた瞬間の作品の形式をできる限り復元すること」(p.61.)、「オリジナル」(p.62.)をできる限り復元することであった。しかしCerquigliniはこのParisの作業が必ずしも「数学的方法」にのっとって行なわれたわけではないことを、例証する。Parisの主眼にあったのは、古フランス語によるテキストの復元であり、その意味ではParis自身が最もオリジナルに近いとする manuscritに準拠しない解釈がいくつも現れている。その結果、古フランス語自体(Parisによれば11世紀なかば)がParisの手によって「純粋、優美、簡潔」(p.64.)なものにされていくのである。つまりは文学作品を通して、ラテン語に似た簡素さをそなえたまま生まれたフランス語、優美なるフランス語が「発見」されたのである。しかしこの「発見」は、Parisによる「始源の創作」(fiction de langue primitive)に他ならない。冠詞、代名詞、前置詞をフランス語における夾雑物、ロマネスク様式に12,13世紀になって付け加えられた装飾と Parisは見なしているが、これらはすでに俗ラテン語の中にみとめられる。Parisはしかしその点に言及することはないのである。
さらにParisはこの言語の地理的起源をIle-de-France、とりわけParisに置こうとする。Parisによる方言数はきわめて数が少ない。その中でも断定はしないがSaint-Germain-des-Présという中心がParisの中で浮かび上がってくるのである。
こうして19世紀におけるParisを代表とする文献学は、異本の中から純粋な言語を構築(=再現)することによって、冒頭で述べたように、国民語を中世において起源づけることに寄与したのである。
一方、異本の中にみつかる規則性を欠き、つづり字もばらばらで、一貫性を欠いた状態、そのものが始源のフランス語であると考える学者もいた。たとえばFrançois Guessardは、このフランス語を、言語そのものの子ども時代と考える。
しかし、大方の学者たちは、これとは逆の方向を辿る。言語の規則性の探究において注目されるのは、文法性である。たとえば現在完全に規則化されている複数の-sは、古フランス語においては、きわめて不確か(aléatoire)なものであった(p.68.)。この現象は古フランス語の整合性を持ち合わせていないことの代表的な例であった。しかしプロヴァンス語専門家であるFrançois Raynouardは、18世紀の南仏語研究者Hughes Faiditを読み、-sの使用に規則性があることを示した(p.70.のCerquigliniの引用を参照のこと)。Raynouardの学説は、形態論的にみて規則性(語の位置の自由を規則によって裏打ちされたものとして保証する規則,p.72.)が働いていることを証し、さらにその規則性は曲用というラテン語との系統をしめすものであった。
この結論に対し、前述のGuessardはさっそく批判を開始するが、AmpèreやBurguyといった古フランス語研究者は賛辞を惜しまない。Burguyは、この形態論的規則性が示すラテン語との親縁性によって、古フランス語は、現在のフランス語よりも調和のとれた明晰な言語であるとする。つまり18世紀にRivarolがフランス語の明証性の根拠とした語順の厳密さという根拠にまっこうから対立する。この根底には起源としての言語を完成したもの、均整のとれたものであってほしいという学者たちの欲望があるのである。
Chapitre IV LA RAISON DIALECTALE
フランスの言語学史における1830年から1860年の30年間は、言語有機体説と国民語としての言語の起源の探究、すなわち、土地の言葉=方言、俚語の探究と2つの傾向が交錯する時代であった。たとえばGustave Fallot(1807-1836)は、この両方について考察を進めた言語学者であった。
言語有機体説においては、Fallotは、あらゆる言語はという3段階にわたる円環を巡るとする(p.77.)。そしてフランス語ももちろん、内在的な法則に典型的に従っている言語であり、またfixationの段階は中世に相当するとした。Fallotが対象として選択するのは13世紀の公的文書であり、目的はそこに使われているフランス語から、文法的規則性を見いだすことである。ここでCerquigliniが注目するのは、Fallotが、Gaston Parisのように始源における言語の完全性というものは信じていず、また、混沌状態だとも捉えていない点である。Fallotによれば、13世紀は、ある完全な形態(=fixation)へ向かっていった時期なのである。
方言の重要視については、Fallotは方言に着目することによって、語の形態の分類が可能になるとする。
事実1830年代にはpatoisへの興味が再びわき上がってくる。patoisは長らく、矯正する対象であり、地域のヴァリエーションが学問の対象になるということがなかった。百科全書のpatoisの定義が示すように、これは頽廃した(corrompu)言葉だったのである。それが19世紀にはいって、考察の対象になったのには様々な理由が考えられる。1806年にMonbretによって行なわれた「放蕩息子」に関する方言調査はフランスにおける地理言語学の基礎を打ち立てた。このようなpatoisへの興味は、「民衆へのロマン主義的興味、過去への憧憬、オシアンの風景といった文学、南仏やブルターニュといった地方主義的運動、そして革命によって行き場を失った田舎貴族の自らの土地への回帰ちった政治」(p.82.)という三重の運動として考えることができる。
地方における失われた民族的過去を復権する試みが、patoisの再評価へとつながる。たとえばCharles NodierはNotions élémentaires de linguistique(1834)の中でpatoisが書き言葉よりも豊かであると主張し、patoisのことばはそのことばが形成された時の起源を宿しているとした。つまりpatoisの研究こそが、フランス語のかつての綴り字、発音を知る手立てになるのである。
またpatoisが、「言語の本質と言うだけではなく、具体的な存在物であり、フランス語の頽廃した形ではなく、原初形態」であるみなされる背景には、フランス語がラテン語起源であること、またラテン語からプロヴァンス語、そしてフランス語と変化したのではなく、ラテン語が、それぞれのロマンス語に分化したこと、それが「方言」となっていたという認識がある。
方言学は、当初応用音韻論として始まる。また地域を確定していくことも重要な作業であった。しかしこの確定という作業は困難を伴う。 Cerquigliniが引用するBrun-Trigaudによれば、19世紀を通じてlangue d'ocとLangue d'oïlの確定は大きな論点であった。
だが、話し言葉であるpatoisの探究は、地域の方言による発音の差が、つづり字のヴァリエーションをもたらすというように、混乱の理由を明示することができる。綴り字と音との関係を、3つの方言(ノルマンディ、ピカール、ブルゴーニュ)にまとめること、これがFallotが行なったことである。これは別の観点から言えば、Fallotが言語の単一性というものを認めていないということを意味する(p.89. l'ancienne langue laquelle ne possédait aucune langue)。そしてFallotにとって、この差異は、歴史的事象ではなく、言語に内在する特徴であり、歴史性によらないということは、パリを上位に置く言語的ヒエラルキーの正当性を認めないということを意味する。そして書くという行為が始まって(14世紀より前ではない)、共通語の形成がなされるようになる。混合と融合から書き言葉としてのフランス語が形成され、このことによってdialecteはpatoisへと座を追われることになる (p.90.)。
次にCerquigliniが検討するのは、「進歩と理性」、ジャコバン的思想をもつ言語学者、François Géninである。GéninはFallotの業績であった、ドイツの言語学、古フランスにおけるflexionの問題、そしてflexionに関連する方言の問題、これらをすべて否定する。Géninは、Fallotと同じく古フランス語の一貫性を求めようとするが、彼の目的はあくまでも始源の言語の根本的単一性を明るみにだすことにあった。Fallotの功績は、混沌としたものと思われていた中世の言語に方言化という考えを提出したことにあった。しかしこの方言化ということは、まさにフランス語は、最初の段階において「地域ごとのヴァリエーション」(p.94.)でしかないことになる。この点がジャコビニストGéninには到底受け入れられない点である。たとえば、規範と普遍をもとめるGéninにとって綴り字とは、音と文字が正確に一致しなくてはならないものである。表面上のヴァリアントに目先が狂い、古フランス語の単一性に気づいていないのがFallotの致命的欠点である。Géninにとって、国の中心はすでにパリに置かれ、フランス国民という一つの集団には、フランス語というひとつの言語があったのである。
同じく国民語の誕生を描いたのがJean-Jacques Ampère(p.99.)である。Ampèreが強調するのは、中世の言語における一貫性と法則性であり、共通語が現れたのは決して遅い時代ではない、という点である。Fallotの主張では、中世の言語の異質性だけが目立ってしまい、現在のフランス語とのつながりが見えなくしてしまう。またパリに中心を置き、francienのフランス語を区別し、そこに現在のフランス語との関連を直接づけたのもAmpèreであった。
Chapitre V LES RECITS DE LA GENESE
19世紀の国民語の起源の学説は大きく次の2つにまとめることができる。一方はFallot, Littré, Brachetの系譜で、古フランス語の諸方言にはみな同等であり、統一化は遅くになってからであるという立場。他方は、Ampère, Génin, d'Abel du Chevalletの系譜で、中央のフランス語によって統一化がはかられたという立場である。
この章でCerquigliniが最初に取り上げるのは、Emile Littréである。Littréは起源のフランス語と、フランスそれ自体の歴史的栄光(Charlemagneをはじめとしたヨーロッパにおけるフランスの覇権)を重ね合わせる(p.111.)。Littréが着目するのがflexionとdialectesである。
まずLittréがdéclinaisonを研究するのは、langue d'ocとlangue d'oïlだけが、ラテン語のdéclinaisonをとどめているからである。そしてdéclinaisonをもつ、すなわち学者語であるラテン語との系列関係をもつならば、この、ラテン語ほど複雑ではないものの、現代語ほど単純でもないこの古フランス語にpatois grossierという言葉をあてることはおかしいとする(p.112.)。こうして今まで貶められていた古フランス語をとして復権をはかったのである。以後歴史的にみると、14世紀にflexionの衰退が始まり、15世紀以降、現在のフランス語の形成が行なわれる。そして LittréがFallotと異なるのは、歴史的経緯を論証に用いる点である。封建制、俗文学の隆盛、こうした歴史的要素が古フランス語の再評価に役立ったのである。
dialecteについては、Littréはdialecteを4つにわける。ノルマンディ、ピカール、ブルゴーニュに加えて、フランス中心部が加わる。そしてあくまでもこれらは、patoisではなく、dialectesである。その意味で、中心部のフランス語も地方の一つのヴァリアントとみなされ、idiomeとpatoisにわかれてはいなかった(p.115.)。
La culture était égale partout : la Normandie, la Picardie, les bords de la Seine produisaient, à l'envi, trouvères, chansons de geste ou d'amour, fabliaux. Il est manifeste que les auteurs ne se conformaient pas à une langue littéraire commune et qu'ils composaient chacun dans le dialecte qui lui était propre.(Emile Littré, Histoire de la langue française. Etudes sur les origines, l'étymologie, la grammaire, les dialectes, la versification et les lettres au Moyen Age.I. p.127)
つまり、Littréにとって、フランス語という呼称は、抽象化でしかなく、諸方言の類似につけられた名前に過ぎないのである。そしてこの認識は、 Diez, Fallotの影響を受けながらも、やはり歴史的要素を考慮している点で、Littré独自のものである。それはつまり、封建制の形態である。地方が同等に併存する封建制という政治的形態こそが方言の分化状態を保証していたのである。そして王権の伸張による封建制の解体が、同時に中央部の方言の進展につながる。それが14世紀のことである。そしてそれはflexionを含んだ言語の消滅でもある。こうして14世紀を転回点とした13世紀から15世紀への、古フランス語から現代フランス語への変化をLittréは見事に描いてみせる。
しかし、現実には、歴史は長期持続の中であくまで変化していくのであり、断絶という見方をとらない。たとえば、987年、カペー朝の始まりにおいて、言語と政治の関連性がすでにみられる。つまりLittréがいう14世紀よりかなり前のことである。これに対してLittréは、王と諸侯との関係が、「臣従の誓い」をしないうちは、langue d'ocもlangue d'oïlも方言の状態のまま存在しつづけているとする(p.119)。だがlittré自身、変化や動きはないという主張の一方で、歴史事象における、王権の漸次的伸張、パリの言葉の漸次的伸張を認めてしまっている。
結局Littréは、中央部の方言が、それ以外の方言と融合し、現在のフランス語になったことをあくまでも主張し、中央部の方言が、はやばやと優位を占めたという考えをきっぱりと否定する。
Cerquigliniによれば、Littréの誤りは、パリの他地域への伸張をあまりにもはやく認めすぎた点にあった。しかし、言語学において、歴史的観点を取り込んだ点は、大いに評価できる。
Albin d'Abel du Chevalletも、歴史的見地になって中世における諸方言を考える。そしてFallotなどとくらべChevalletによる方言数は飛躍的に多い。こうした細分化の意図は、Ile-de-Franceの優位さを打ち立てるためである。この方言がフランス語という名で呼ばれることになり、また王権の伸張によって、この言語も同様に優越性を持つようになる。こうしたChevalletの考えには、はっきりした時代区分がなされていないが、12世紀にはこの優位性が獲得されたとする。Chevalletはその理由として、2人の証言をひく。Conon de BéchuneとAymon de Varennesである。たとえば、後者は自らの母語、リヨンの言葉で書くことを望まない。そしてこれ以降、Ile-de-Franceの言葉は、王権の補助も得て、広まっていったとする。ここにある物語(récit)は、フランスにおいて言語は、長らく国家が関与する問題であったことを示している。これは現代にまで続く物語となる。
Chapitre VI L'INVENTION DU FRANCIEN
1870年以降、共和国の体制が整うのと呼応するかのように、言語学もひとつの科学的学問として確立される。Gaston Paris, Paul Meyer, Michel Bréal, Arsène Darmesteterは、g言語学の学者・研究者として、学派を形成していく。言語学、文献学、文学など多方面における活躍、そして、綴り字改革や教育改革などの社会参加など、さまざまな形で共和国そのものに関わっていく言語学者たちの課題は、もはやラテン語という親の問題ではなく、フランス語そのものの起源をいつ、どこにおくかということであった。つまり俗ラテン語という失望の事実よりも、フランスの国土において、中世という時期にどのように起源を画定できるかということが問題となった。
この課題は、Fallot-Littréが古フランス語に規則性を見いだしたものの、結局は諸方言が同等にばらばらに存在するという見解の見直しを目的とする。それは、第3共和制において、教育現場で、共通の言語、すなわち、共和国と理性の言語であるフランス語を普及させるという使命と深くつながっている。つまり言語的統一のためにdialectの併存という事実は都合がわるいのである。
こうして言語学者たちは言語における規範の形成へと乗り出していく。その規範は、貴族の作り上げたものではなく、パリの大衆の言語実態から得られることが求められる。首都とは、国家と学問と言語(p.130)を一緒に結びつける場所なのである。特にパリの方言の優越性を証だてる理論的構築がセダンの戦いの後、本格化する。
その代表的な学者がGaston Parisである。Parisの言語観は、ドイツにおいて積み重ねられた言語有機体説からの脱却であり、言語の変化において歴史的要素を導入することであった。その考えが展開されるのが、1868年、ソルボンヌにおける開講講義«Grammaire historique de la langue française»である。
言語とは、社会的対象物であり、生活様式、時の権力、そして土地の影響を受ける。実際、言語は文化の伝達手段であり、文化もまた言語を形づくる(p.132.)。ただし、Parisは「歴史」と「科学」とに言語研究を分割するのではなく、両者を融合することを提案する。
Le développement du langage est dirigé par des lois qui lui sont propres, mais rigoureusement déterminés par des condition historiques.
言語の発達は、それに本来的にそなわった法則によって導かれる。しかし、同時に歴史的条件によって厳密に規定されている。
しかし、この歴史的条件は、大きな力を持ち、言語の不動性に「打撃」を与えることになる。その大きな力とは、「文芸文化」(la culture littéraire)である。この文化こそが、言語における「慣用」と「恣意性」をもたらし、その一方で、言語に美的価値を与えることになるのである。
この歴史的手法においてフランス語が検討される。フランス語の歴史、それは間違いなく、ラテン語を起源とするものであり、そこからの継続性はもはや明らかである(la continuiét est indéniable, p.134.)。しかしラテン語が、様々な言語に分化したことが事実である以上、この「ばらばら状態」から出発するしかない。しかしParisの中でそれが最終的に「フランス語」として統一されることは、必然であった。そのために選ばれたのが、Ile-de-Franceの方言である。
Parisは5つの方言群を分類するが、その中にIle-de-Franceが含まれている。しかしそれは明確に画定されるのものではない。むしろ4つの方言に「含まれない」方言という消極的なものであった(p.135.)。しかしParisはIle-de-Franceという言葉がFrance という言葉と同時に生まれたものと考える。さらに奇妙なことにfrançaisという呼称を、なんの証拠もなく、langue d'ocに対立するものとみなす。CerquigliniはParisの理想を「ガロ=ロマン語のLangue d'ocとlangue d'oïlへの分裂、langue d'oïlの分裂とそれによって生まれる諸方言の同等性、Ile-de-Franceの言語の価値付け」と整理する(p.139.)。しかしParisの論拠では、時間軸の取り方の上で、方言の同等性の時代を設けるのは難しく、ひとつの言語の正当性を言う以上、その他の言語はpatoisと見なさざるを得なくなる。
それから20年後、文部大臣を含めたインテリ階層に向けて行なった、«Les parlers de France»と題する講演において、Parisは、国民語の浸透によりpatoisが死滅の状態に陥っているという前提から出発し、その保護を聴衆に向かって呼びかけるが、それは、patoisのヴァリアントがそのままラテン語から離れて以降の変化を跡づけるからという理由のためである。そして郷土の風習、民話に結びついたpatoisはこれまで、地元の愛好家によってもっぱら保存されていたが、今後は科学的学問の対象として取り扱うべきだと訴える。
またParisは、イタリアのロマンス語学者Ascoliが3つ目の言語としてfranco-provençalを提唱したことに対し、これまでの方言学の成果を無視してまで、その論を否定しようとする。それは、1870年の普仏戦争を契機とし、フランスが分割されることを拒否するためである。ここにはParisの矛盾が浮き彫りになっている。学者としては言語の分割が、言語の変化において必然であることを理解していながら、ジャコバン派としては、フランスの統一を希求してやまないからである。
この矛盾を解くために、Parisは3つの概念を提唱する。一つ目はcontinuum「連続帯」(p.145.)である。隣の住民との相互理解という点から、等語線を否定する。二つ目はlangue d'ocとlangue d'oïlの分割の否定である。フランスはタピスリーのような広がりであって、現実に境界を引くことは不可能であるとする。三つ目はdialecteではなくtrait dialectalという概念を入れることによる、分割地図ではなく、様々な特徴が偏在する地図を作り上げることである。こうした操作により、Paris はフランスの分割は避けようとする。そしてフランスにおける言語的単一性は、ラテン語からの変化の敷布での上から、Ile-de-Franceで編まれた一様な敷布がフランスを覆うことよによって実現したとする(p.147.)。
Ile-de-Franceの言葉は、Parisに言わせれば、古い形をほとんどそのままとどめている言語である。なぜこのようなファンタスム(p.149.)が可能になったのか?Parisにとっては、この言語は、中世においてはっきりとした言語的特徴を持った言語ではなく、他諸方言の均衡の上に形成された言語である。土着ではない分、どのようなoïlの話者によっても受け入れられる。こうしてIle-de-Franceの言葉は、最初からフランス語として、フランス全国土を覆っていったという考えをParisは強く表明する。
しかしIle-de-Franceの言葉を現代フランス語の始源とするには様々な欠点がある。たとえば、その地方の言葉をさす用語さえ存在していない。
このフランス中心部の言葉の重要性を深く検討したのは、文献学の分野で進んでいたドイツである。Ernest Merzkeはその博士論文(1880, 1881)において、13,14世紀の中心部の言葉の特徴を、他の言葉が持っている「特徴の欠如」(p.151.)にあるとする。続いてSuchier (1888)は、北の文学語の基礎となる方言を、中心部と類縁性をもつノルマンディー方言であるとする。そしてその方言が、中心のことば、Suchier の言うfrancischへと移っていったとする。これが中心部のことばをさす「名」であり、francienと翻訳される。
Parisはこのfrancienという考えを積極的に押し進める。Ferdinand Brunotが、Ile-de-Franceの言葉に対して、政治的状況以外の優位性を与えることに慎重であるのに対して、ParisはBrunotの仕事に敬意を払いながらも、まさにその点が不十分であるとする(p.156.)。Brunotはfrancienという言葉を用いないし、Ile-de- Franceで話されていた言葉の地理的な画定もしない。それにたいして、Parisは批判を行なうのである。
Brunotは1905年のHistoire de la langue françaiseの第一巻において、ついにfrancienという言葉を用いる。
Le francien ne doit pas être considéré comme un amalgame, une sorte de koiné, analogue à la koiné grecque. C'est essentiellement le parler d'une région, comme le normand est le parler d'une autre.(p.325.)
以後、francienは辞書の世界にも入っていくこととなる。francienという新語は、恣意性がみとめられず、領土を画定するでもなく、しかし中央部と関係し、さらにその名から国家的統一も喚起する。ここにきて、francienはfrançaisとみなされる。そしてParisにとっては、この言葉は最終的にparisienにもつながっていく。
以下続く
再生ということばは、革命以前に遡るが、しかし現実味を帯びたのはルソー以降である。その意味で、再生は革命による断絶がきっかけになっているといってよい。またこの再生は、あらゆる領域に関わる再生である。
たとえば、子ども、若者、老人に関わる肉体自身の再生。また宗教的な意味に捉えられれば、新たな生(洗礼による生まれ変わり)、原初社会の再生という意味にもなる。たとえキリスト教という宗教的文脈に頼らなくとも、革命の思想の中に、法から慣習までのすべてを含み込んだ「回心」を認めることは誰もが受け入れる考えであったろう。
そして「再生」ということばは、「改革」という言葉を追いやった。なぜならば、「改革」には、まだ過去の痕跡が残っているからである。それは「専制、教権、封建制」の残滓といってよく、革命は、それらの過去を「腐敗と頽廃」とみなす。こうした過去を裁断し、あらたな人民(peuple)を到来させるために「再生」を必要とするのだ。
この再生の具体的方法としては2つの方法が示される。一方は未曾有の出来事をした人間は、「自然と」、「突然奇跡のごとく」新しく生まれ変わるという考え方である。他方は、「再生」を遂げるためには、まだ過去の残滓があり、これを抹殺しなくてはならないという人々の考え方である。現実の変化と魂の変化の間にはまだ差が存在している。これを考えていかなくてはならない。そのためにはまず内心の中にある過去の残滓を強制的であっても解体しなくてはならない。しかしこの考え方は、疑わしき成員を、再生された共同体から排除していくことも意味する。
そして重要なのは、この自由・自律の再生と制約・他律の再生とは、異なる政党、異なる時期、異なる人物にきれいにわけることができないという点である。
再生において最も重要になるのが教育の再生であり、子どもをより有益な国民にするために、学校は課題の中心を占める。そしてやはり自由か規律かということで方針はたえず揺れ動くこととなる。たとえば革命初期におけるコンドルセの公教育案は自律と自由にまかせたものであり(無償で、義務ではない教育を提案)、一方ジャコバン期の教育とは、制約である。この案では、再生の道具は、寄宿舎と義務である。
しかしこの2つの再生には共通点がある。それは第一に「時間」がもたらす限界である。実際に精神や魂の育成には時間が必要となるが、「突然奇跡のごとく」再生が果たされると思っている革命家たちにはこの遅さは致命的である。また、体系的に新しい人間を創り上げていこうと考える革命家にとっては、時間の存在は、いくら法令を布告しても、時間の経過によってこそやりとげられる現実もあるということを思い知らせる存在なのである。
第二に、新しいものの誕生に古い世界を使うことはできないということである。前者にとってはすでにそれは存在しないものであり、後者にとってはそれは消えるべきものである。
最後は、感覚論である。この問題は、前者に、個人が変わるのは、たとえば革命の光景といった外在的なものであり、その意味で人間個人の自発性とは言い難い。他方、後者にとっては、制約を課す教育も、人間が変わりやすい存在である以上、その制約は逆の教育によって解体されてしまうという危機意識である。そして、この統制主義が優位にたっていく。
革命の難しさは、個人にそのまったき権利を与えた後に、その個人を集団へとつなぎ止めなくてはならない点にある。革命が混乱の事態に陥るにつれ、個人の精神を従わせることのできるほど強力な集団精神が必要となった。そして集団精神により大きな統制力をもたせるために、権力はあらゆる方法を用いるのである。
200ページにも満たない小書である。しかし筆者は、この本を書き始める前に、いったいどれだけの莫大な時間をかけたであろう。イギリスからピエモンテへ、おびただしい資料にあたりながら、丁寧にヴァルド派の歴史を追った労作である。イギリス名誉革命期のプロテスタントを専門とする著者が、ヴァルド派の人々の書簡に目を留め、やがて「プロテスタント同盟」の信仰篤き人々とともにヴァルド派の谷へ旅行をし、そこでイギリスで学んだシプリアン・アッピアの手による教区簿冊を発見するくだりは、読者の感動をさそう。この本の醍醐味は、我々の記憶から消えて、文書の中に乾燥した形でしか残っていなかった人間の事実を、丹念に文書から読み明かし、当時のヨーロッパをかけめぐった人間の生の歴史を、そして、ヴァルド派を基軸とした当時のヨーロッパの広汎なネットワークを、まざまざと復元してくれる点にある。人間の具体的な生を描き、かつ歴史の大きなうねりも丁寧にたどっていく、優れた歴史書である。
ヴァルド派とは、中世ヨーロッパにおいて、聖書主義を厳格に守り、キリスト教会から異端とされた宗派である。しかしその歴史は、宗教改革から弾圧の時期を乗り越え、現代まで命脈を保っている(工藤進『ガスコーニュ語への旅』によれば、フランス北方のカトリック国家に対する南仏の不満が「異端」という形をとったとされている。ちなみにカタリ派ともそうした不満から生まれた「異端」であるが、教義上の共通点は少ない。またこの本の中で、百年戦争がフランス南西部を占めているイギリス勢力と北のフランスとのフランス国内での争いにほかならないとする、くだりがある。これが南仏軍の敗北であるとする見解に、『ヴァルド〜」と同じく、汎ヨーロッパ的視野にたつ著者の鋭さが認められる。)
ヴァルド派の人々が住む谷は、サヴォイア公国ピエモンテ地方、すなわち、フランスとサヴォイアの国境地帯にまたがっている。この地形がヴァルド派をヨーロッパの歴史の変動の中に絶えず巻き込むことになる。それは領地だけの問題ではなく、プロテスタントの国、オランダ、そしてイギリスと深いつながりを持つことになる。そこには「ローマ教会はすでに腐敗し、ヴァルド派のみが真の教会を伝え、プロテスタントはその後継者である」という(p.37)根強い信念があった。
著者が足跡を追う中心的な人物シプリアン・アッピアは、1680年か82年に「谷」で生まれている。その後捕虜としてジュネーヴに向かう。その後「谷」に戻ったか、そのままローザンヌの神学校に送られたかは定かではない。その後「谷」は、イングランドやオランダの援助を受けながら復興していくことになる。このあたりのつながりを考えるにあたり、やがてはもう啓蒙の時代はすぐそこまで来ているヨーロッパにおいて、たとえ政治的なもくろみはあったにせよ、宗教によってつながるネットワークがあったことは、まさに著者が言うように、プロテスタントの国際主義があったわけであり、宗教的イデオロギーの冷たい戦争がまだ続いていたことがわかる(pp.95-96)。
こうした「プロテスタントの環」の中で、シプリアンは弟ポールと主にイングランドへ送られ、聖職者として勉学に励む。1707年「谷」にもどったシプリアンとポールは、聖職者総会で問題を起こすことになる。それは二人がイングランド国教会の普及に燃えていたことである。しかしやがて二人はヴァルド派の中心人物としてコミュニティに溶け込み、聖職者として活発に動き回る。そしてイングランドのとのつながりも決して絶やさないし、また当時のイングランドではヴァルド派に対する関心は十分に保たれていた。シプリアンは1744年に、ポールは1754年に死去する。そして時代はいよいよ啓蒙の時代へと入り、宗教によるつながりの意識は失われていく。
こうした失われた記憶が復活してくるのは、19世紀にはいり、イギリスで出版されるヴァルド派に関する書物による。たとえ現実には異なっていても書物で描かれるヴァルド派はやはり、真のキリスト者なのである。イギリス福音主義の高まりが、ヴァルド派への関心の再興を促すのである(p.158)。その後イタリアにおける国民意識の高まりが、ヴァルド派の同化を促すが、ヴァルド派の特異さは現在まで受け継がれている。
まさに中世から現在にわたるヨーロッパ史として読める作品である。この見取り図がヴァルド派という「異端」とみなされる宗派の資料の読解から語られることにこの本の深い意義がある。
この報告は、2005年にパリ第4大学で行なわれたシンポジウム、「1902-1914, la première guerre des humanités modernes」で行なわれた。Chirstophe Charleは特に19世紀後半における知識人研究などで知られている研究者である(『「知識人」の誕生1880-1900』(藤原書店)参照のこと)。 Histoire de la langue françaiseの著者であるFerdinand Brunotの、論争家、活動家としての面に焦点をあてて、第三共和制において、言語学者がどのような社会的立場を担ったのかを解明する報告である。事実、Charleが挙げるようにBrunotは時代と正面から向き合った言語学者である。大学改革、ドレフュスの擁護、中等教育改革、綴り字改革、文法教育の現代化、女子への教育の擁護、外国におけるフランス語の普及、などその活動には枚挙にいとまがない。その中でCharlesは次の3点を挙げて、それぞれにおけるBrunotの立場を明らかにする。
- 1899年中等教育に関する調査
- 1905年の綴り字論争
- 現代における古典教育とフランス語
1)1899年中等教育に関する調査: Brunotの改革の骨子は、反教権主義に基づいたものであり、宗教から公空間へ教育を導くことに重要性を置く。そのためにBrunotはカトリックの学校に対抗しうるだけの、質の高い教師の養成を目指し、また初等教育の自習監督の採用を視野にいれるための、agrégationの改革を要請する。
次にBrunotが批判するのは、古典教育のカリキュラムである。ただ廃止するのではなく、ギリシア語、ラテン語は一握りのエリートにとっては重要でああるが、一般の生徒にとっては廃止してもよい科目であるとする。つまり中等教育とは、ラテン語知識階級である聖職者によって独占されるものではない。それは同時にフランス語を教育の中心に置くことを意味する。ここにはひとつの新旧の文化闘争があるわけである。そしてフランス語を深く知るためのギリシア語、ラテン語という位置づけ自体を変えるために、Brunotはフランス語の歴史を教えるという可能性を示唆する。そしてその延長上には古典の作家ではなく、ヨーロッパ文学の作家たちのテキストを教えるということも浮上してくる。 いずれにせよ、宗教と古典教育という結び付きに対して、現代的な観点から、一部古典教育を残しながらも、フランス語の教育を促進し、公教育を宗教学校に対抗させることが主眼となっている。
2)つづり字の現代化: 1903年に文部省によりつづり字改革の委員会が設置された。Brunotはそのメンバーとなる。ちなみにこの委員会は、アカデミー・フランセーズの会員が一人だけであった。この委員会が1904年に出した改革案には、アカデミー、雑誌、大学界からの非難を受けることになる。Brunotは、彼らが打ち出す伝統擁護の姿勢に対して、大作家のものと言われる作品でも、彼らが書いていた当時と、現在ではすでに綴り字に顕著な違いがあることを指摘する。1906 年に最終報告書がBrunotによって書かれるが、その骨子は大多数の人々が、苦労なく文字がかけるよう配慮するというものであった。つまり、つづり字の規則化、簡素化である。Charleは、報告書の次の部分を引用する。
「我々が忘れているのは、かなり多くの国民にとって、フランス語はまだ母語ではなく、獲得言語であるということである。子供たちは学校で、おそらくは口頭練習や、読書をしながらフランス語を学んでいる。また、小学校で学業をやめてしまう子供たちは、かなりの言葉を知らないままだ、ということも我々は忘れている。こうした子供が大人になって、新聞を読んだとしても、聞いたこともない言葉は、ほとんど外国語に等しい。そしてそうしたことばを書いてある通りに読むために、その読み方はきわめて奇妙なものになってしまっている。」
Brunotにとって、こうした単純なつづり字は、外国人や植民地の人間たちが、フランス語を学ぶときの障害になっているという認識にたった上での要請でもある。また、反対派の根拠である「伝統の擁護」については、Brunotはつづり字の規則は、実は19世紀において、学校教育の中で教えられて定着したにすぎず、反対派がやはり根拠とする「大作家」もつづり字上のミスをしていることを指摘する。すべての人間が、言語および文字を maitriserできること、これがBrunotにとっての共和国の命題である。言語的な階層差、文化障壁をなくすことが、共和国の単一性を保つのである。
3)現代における古典教育とフランス語:教育におけるラテン語の位置づけについては、2つの愛国主義が対立している。一方は伝統の擁護と、古典文化の遵守のために、ラテン語教育の退潮が、フランス文化の危機をもたらすという立場。他方は、フランス語の単一性を共和国の単一性実現の一つの必要条件と考え、フランス精神の普及を考える立場である。この普及はもちろん、国内にとどまらず、世界中へのフランス語の普及へと拡大していく。また普及ということ自体にフランス精神の栄光があるわけである。 Charleが引用する、フランス民族の精神が、経済的、政治的には影響力を失った植民地国で、フランス語によってふたたび領土を回復しつつあるというくだりは、Brunotの姿勢を如実にあらわす一節である。Brunotはこの後者の意味での愛国主義者として、旧守派に対して精力的に論陣を張る。 Brunotにとって、前者がいうフランスの危機とは、これまで一部の知識階級、ソルボンヌによって独占されてきた、知、および、その知によって成り立つ職業階層という旧習の危機に過ぎない。最後にCharleは、Brunotが中心となった団体「Les amis du français et de la culture moderne」の1911年の宣言を引用する。ここでは、ラテン語の優位性、ラテン語を通したフランス語の理解という主張をきっぱりと断罪する。こうした宣言文を読むといかにBrunotが戦闘的な言語学者であったのか理解できる。Charleのこの報告は、まさにこうした時代の論争の中心人物としての Brunot像をよみがえらせてくれる。
ことばは、当然のことながら、生きて話している人間の生の具体性と切り離すことはできない。それは言語を思想として考える場合でも変わらない。普遍・抽象・理論化をいたずらに急ぐのではなく、その人の生きている現実の中から、思想が紡がれてくる過程を丹念に追ってみなくてはならない。ライプニッツについて考えるときも、彼の生きたその環境、時代の流れに、彼の思想を位置づけることは必須である。歴史的に言えば「三十年戦争の不幸の結果地に落ちていたドイツ語」(バッジオーニ『ヨーロッパの言語と国民』p.236)を、どのように復興するか、それはライプニッツの時代の課題であったろう。実際ライプニッツ自身『私見』において、「我々の言語は略奪され、フランス語かぶれが横行した」と述べている。まさに「私見」は、ドイツの国家、言語への誇りを回復するための試みなのである(『私見』pp.53-55)。また言語思想の流れからは、母なる言語としてのヘブライ語という聖書的世界観、すなわち、世界を説明し尽くす普遍的言語ではなく、感覚論(sensualisme)の広まりとともに、他者を理解する、つまり「人々の世界観や、内面の過程」の表現としての言語へと変化したことを十分考慮する必要がある(Droixhe, De l'origine du langage aux langues du monde, バーリン『北方の博士 ハーマン』p.112)。普遍から、歴史としての言語というこの転換期は、ラテン語の退潮と、普遍言語の構想から、フランス語のヘゲモニーの確立へと移っていく時期とも重なる。
ライプニッツはまさにこうした転換の中で、結合術、普遍言語、国語の賞揚という様々な言語(および記号)をめぐる考察を行なった。言語思想はライプニッツの思想全体の根幹とも言える。普遍言語と言語の自然性については『人間知性新論』第三部「言葉について」の中にその主張がおさめられており、カッシーラー(『象徴形式の哲学』)、ロッシ(『普遍の鍵』)、エーコ(『完全言語の探求』)、ジュネット(『ミモロジック』第4章「言語創始者ヘルモゲネス」)など枚挙にいとまがない。
以上のような背景をふまえてここでは1697年にドイツ語で書かれた『ドイツ語の鍛錬と改良に関する私見』(Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutchen Sprache)を見ていきたい。
最初に注目すべきは言語の起源についての考察である。『私見』では、ドイツ語が「主幹言語」(Haupt-Sprache)であるという、起源の言語としてのドイツという見方が踏襲されている。したがって太古のドイツ語は、ラテン語の起源であり、またケルト人、スキタイ人と共同体を作っていたとされる(『私見』p.65)。この言語系統論は、十七世紀以降に広まる「スキタイ人起源論」である(cf.原聖『<民族起源>の精神史』p.103.)。ライプニッツのゲルマン、ケルト、スキタイの関係についての論考は、『私見』、『新論』、『小論』と立場を変えていく。(Cf.L'harmonie des langues, p.195.)。『新論』でははっきりと、「ひとつの根源的で原初的な言語がある」と述べられている。これはアダムの言語のような起源を認めてはいるが、その言語は「歴史的」に共通語根を遡ることによって見つけることができるという歴史性のもとづいた起源の言語の探求なのである。この転換に、ライプニッツの言語思想を位置づけることができよう(現在のところ、その起源をドイツ語とする主張については調べが追いついていないが、『新論』p.23.にはそのような訳注がつけられている)。
起源ということに関しては、語源の探求におけるライプニッツの立場は、「クラテュロス」的である。語源を探求する過程において、単語が「何人かの人がいうほどに恣意的または偶然的なものではない」と指摘する(『私見』p.70.)。そして、『私見』では、およそ偶然というものを否定している。ここではヤコブ・ベーメ流に解釈された自然主義的言語の立場をはっきりととっている。しかし、こうした見方にもやがて時の流れという歴史性が導入される。それはジュネットがひく『小論』の一節、「しかし大抵の場合、時間の経過と数多くの派生の結果、原初の語義はかわってしまったか、あるいは不明瞭になってしまった」(ジュネット、邦訳p.93.)。である。
ドイツ語の改良のために、全体を通してライプニッツが気を配るのは「単語」である。単語とは、「知性の鏡」(p.42.)であり、「言語の基礎および基盤であり、その単語という土壌の上でいわば表現という果実が成長する」という(p.57.)。ライプニッツには観念を適確にあらわす記号の術への強い関心があるのだろうか。語彙の拡充、特に抽象語彙の拡充をライプニッツは強く説くとともに、辞書の必要性とそのための単語の調査に取り組むこと、他の単語と調和した新語の形成を強く訴える。それらはすべて「的確に」を目標としたものであり、それが民衆の教育向上につながると考えていたライプニッツはすでに十八世紀の初頭にして、啓蒙主義的な視野を持っていたと言えよう。
フランソワ・フュレは、革命史家として、フランス革命をブルジョワ革命とみなす史観を否定し、また、アンシャン=レジームと革命に断絶があり、それによって、旧・新という裁断が生まれたという見方を、19世紀以降に作られたものとして退ける。こうしたフュレの革命観は、トクヴィルの革命観と非常に共鳴している。そのフュレによる、トクヴィルの『一七八九年以前と以後におけるフランスの社会的・政治的状態』(1836)、『旧制度と大革命』(1856)を丹念に読解したのが、この論文である。
断絶を否定するとは、たとえば、フランス革命を始まりと捉えるのではなく、結果と捉えるということを意味する。まず経済面においては、18世紀のフランスは、たとえ制度上は不平等であっても、習俗としては「民主的な」国になっていたとする。それは貴族層が、土地の細分化によって、中産階級の個人の集まりに解消されたり、第三身分の上昇によって、革命前にすでに「平等理念」が人々の精神に入っていたとする。政治面では、地方政権が、貴族階級の手を離れ、国王に与えられることによって、パリの地位的優位ならびに、ばらばらの地方の統一の必要性という事態から、中央集権化過程が押し進められていたとする。フュレは、このようなトクヴィルの見方を、ギゾーが情報源であるとする。特に封建制のなかから、君主制と自由が生まれてくる。つまり「下からは自由の名で、上からは公共秩序の名で」(p.248.)攻撃を受けるのである。ただし、ギゾーにとってフランスには「真の貴族主義的政治社会は決して存在しなかった」のに対して、トクヴィルにとっては、貴族社会とは、「中央権力に対して個人の自由を保証する家父長的地方社会」であり、この貴族社会が消えていったことによって、自由ではなく、平等へと道が開かれることになる(p.251)。つまり、これがトクヴィルにとっての民主主義なのである。これは「貴族制の諸社会は地方政権に傾斜するのに対し、民主制の諸社会は中央集権政府に傾く」(p.264.)という理論にまとめられよう。
次に、フュレは『旧制度と大革命』を読み直していく。封建的諸権利の問題、旧制度と大革命の連続性の例証としての公共権威と行政的中央集権化の発展の問題である。と同時にトクヴィルの不分明さも指摘する。君主制官僚機構の形成にとって最も大切な官職売買への言及のなさ、中央集権化過程における伝統的な年代記に沿った発展(進歩)を裏づける根拠の希薄さ、経済的な現象に対する言及の少なさ、貴族の立場の変遷を言う場合の通俗にとどまる見解などである。
そして、『一七八九年以前〜』と、『旧制度〜』を対比し、後者を支配するペシミズムから、トクヴィルの回帰したいと願う失われた時代のイメージを、貴族とその下に集う農民共同体として描き、それを君主制が破壊したのだと指摘する。またそれに続いて貴族主義的伝統は、気概と自由の感覚であり、それが民主主義的凡庸さと対照をなすのだと指摘する。
『旧制度〜』第三部については、革命は、貧困が問題ではなく、むしろ裕福な国を襲ったという事実、行政の面では、一七八七年、つまり、革命の2年前にすでに行政改革(選挙で選ばれる議会を地方総監のかわりに設ける)が行なわれたという事実をあげ、革命によって「再生」が実現したという革命観を否定する。ならば革命現象とはなにか?それは「暴力の役割とイデオロギー(言いかえると、知的幻想)の役割」である。
このようにフュレにとって、大革命はすでに大革命のときにはおわっていたということになるのだろう。そしてこうしたイデオロギーを否定する態度が、フュレの同時代的な意識なのである。我々は果たして時間にくさびを打ち込むことができるのかという疑問、そしてアナール派のような、ゆっくりとした時間の流れにおけるたえざる変化という歴史構造に、フュレが位置していたことを知るのである。
Ferdinand Brunot(1860-1938)は、第三共和政下において、大きな足跡を残した言語学者である。とりわけL'Histoire de la langue française(以下HLF)は1905年に着手され、彼の死後も公刊され続け、11巻、20,000ページ以上に及ぶ畢竟の大作である(その後HLFは弟子の Charles Bruneauに引き継がれ13巻となった)。「人権擁護連盟」の設立に加わり、「Association des amis de l'abbé Grégoire」が、グレゴワール師没100年を機に、また時代の全体主義的な風潮への危機意識の中で1931年「Société des amis de l'abbé Grégoire」と改称したとき、その議長を、ソルボンヌ大学文学部名誉学部長として、務めたことからもわかるように(Cf. Rita Hermon-Belot, L'Abbé Grégoire, La Politique et la vérité, p.254.)、熱烈な共和国主義者であった、Brunotは、フランス語教育、その普及政策にも深く関わった。彼が傾倒したグレゴワール師と同様、啓蒙と進歩への揺るぎない確信から、その根底を作るとされる言語を多くの人間が学び、理解していくことに心を砕き、骨を折ったのである。ここでは「心を砕き、骨を折った」と言ったが、それは例えば、Louis-Jean Calvetが引用するように、「良き共和国主義者であるためにはフランス語を話さなくてはならない」という手段ー目的が明らかな前提になっており (Cf. Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme, p.214. )、Calvetのような言語学における人種差別的偏見に敏感な立場から見れば、こうしたBrunotの愛国主義的態度は、人種差別、植民地主義の裏返しとうつるであろう。確かに、例えばLHM第9巻は革命期の言語の問題を扱っているが、国民語形成の事実を、冒頭に載せたRenanの論調通り、「国民の意志がなしとげた、フランス語による言語統一」という観点が、ページの随所に見られる。しかし、こうしたイデオロギー的立場から、共和国主義者として生きた Brunotを裁断する前に、今一度、HLFという作品を検討してみなくてはならない。
Les Lieux de mémoireの第3巻「Modèles」におさめられたJean-Claude Chevalier, L'«Histoire de la langue française» de Ferdinand Brunotは、その意味でいえば、イデオロギー色を排した、「人と作品」に焦点をあてた、Brunotの紹介である。ノルマリアンとしての大学でのキャリア、フランス語の教科書の出版、そして、録音という方法を使った口語資料の収集などを挙げながら、今現在のフランス語自体が、学問の対象となり、また学ぶべき教科の対象となっていく時代の中心としてBrunotを位置づける。それはつまり、規範としてのフランス語を明示し、伝える(学ばせる)ことを意味する。このことが「真理の追求、自由への愛、科学の信仰」(p.3391.)という共和国の価値に即していることはあきらかだろう。こうした信条をもった Brunotがフランス語教育法のマニュアルを書いたり(L'Enseignement de la langue française. Ce qu'il est, ce qu'il devrait être dans l'enseignement primaire)、正書法の改革に乗り出したのも、至極当然である。
論文の後半は、中世、16世紀、古典主義時代、18世紀、そして革命期にわけてHLFの内容が紹介されている。その基本線は、旧体制下の連邦主義的な言語のあり方に対する、革命時の言語の政治学のあり方である。Chevalierのこの論文ではそのような視点には立っていないが、先に触れたCalvetが言明するように、フランス語以外の話者の地域=反革命の温床とは言い難く、またBrunotもおそらくはそうした淡白な見方はしていないだろう。ちなみにこの巻は、Brunot自身も認めている通り、他の巻に比べて恐ろしく資料が欠落している巻である(cf.久野誠「革命前後の仏語研究小史」http://www.ha.shotoku.ac.jp/~hisano/revolution.html)。
Chevalierはここで、革命期の語彙の増加、共同体の紐帯としてのフランス語という観点を概観しているが、その中でpatoisに対する、 Brunotの見識が、この人物の寛容さの証拠として述べられている。確かにBrunotはグレゴワール師と同じく、patoisを「啓蒙を阻み、国語の理想に反し、そして地方の連帯をも阻害する(patoisはさらに細分化されたものであるから)」ものと考えている。しかし、だからといってpatois を破壊するような、性急な態度はとらない。それはpatoisは話者の生活、日々の活動、深い感情の印だからである。Brunotは強制ではなく、「学校を通した自然な学習、時代を経て、そして人々の良識」に期待しているとChevalierは理解する。これは国家という枠組みと、その枠組みの中で制度化された学校を前提とした上で、Brunotの信条である、「人々が学びたいという意志の尊重」を意味する。すなわちフランス語とpatoisとはその慣用がまったく異なるのである。フランス語とはまさに国民語であり、啓蒙の言語、それに対してpatoisはやはり、人々の生活にとどまる言葉である。そしてさらにその前提には「愛国」、誰もが国を愛する証明としてフランス語を話したいという前提が不文律としてあるのではないか。
Pendant la première période de la Révolution, les Sociétés populaires alsaciennes n'ont pas travaillé consciemment à la diffusion du français. Néanmoins, j'estime qu'elles l'ont servie. Des gens de langue allemande y coudoyaient des Français et c'était beaucoup. Pour peu qu'ils eussent une première teinture de français, ils apprenaient à comprendre, sinon à parler. Si jamais la méthode directe a donné des résultats, ce fut là, dans ces milieux échauffés, où le patriotisme avivait singulièrement la curiosité, et où l'on souffrait impatiemment de paraître des Français incomplets.
「フランス革命の第1期においては、アルザス民衆協会は、意識的にフランス語の普及に務めてはいなかった。しかしながら、私は、協会はフランス語の普及に役立ったと考えている。ドイツ語を話す人々は、そこでフランス人と膝と膝を突き合わせた。それだけで十分だったのである。かれらは、話すことはなくても、理解することは学んだ。もしダイレクト・メソッドが結果をもたらしたとすれば、まさにこの熱気のこもった場所である。ここでは愛国主義は強く好奇心を刺激し、不完全なフランス人に見えることには、とにかく耐えられなかったのである」
(Ferdinand Brunot, L'Histoire de la langue française, Tome IX, p.70.)
ここには、人々の愛国心への十全たる信頼がある。これがあるからこそ、Brunotは強制に頼らず、慣用に任せるという立場に立てたのではないか。
この章は5つの節から構成されている。
第1節:普遍言語を作るという欲求は、言語の多様性が人々の分裂を解消するという信念から生じる。また既存の言語は社会的慣用を作り出し、人をその意味である社会集団に属させるものであるから、この社会集団からの解放にも基づいたものである。しかしこれは、ひとつの夢に終わる、言語の文法性は決して普遍言語が望むような簡便なるものとしては構想できない。
第2節:ならば、既存の言語に関する創造としてはどのようなことが言えるであろうか?言語の歴史をみてみると、それは「改革」と「保存」であるといえる。しかもしそれは、民族意識が、文化や言語に関わる時期に現れる。具体的には、つづり方の問題、文法書、辞書の発刊、または国家が積極的に関与する新語の創作の場合などが挙げられる。
第3節:ただしこうした言語の創造は、語彙のレベル以外にはほとんどの不可能と言える。ただし、それでも、人間は自然に囲まれ、自然を加工していくように、言語に対しても同じ行為を働こうとする。こうした言語道具観の内部にあるのは、言語の機能の根本がコミュニケーションという認識である。この認識から生まれるのが、「言語計画」である。
第4節:こうした公的な形による言語の統制化に対する反論は、たとえばノディエの引用が示すように、その土地のことばの消滅に対する警鐘という形をとる。規範化は「改革」と「近代化」という意味合いを持ち、支配文化・社会と結びつき、マイナーな言語を追いやっていく。
第5節:以上、言語の改革、規範化はまさに政治と結びついている。
本書は物語的歴史理解のこれまでの論争を概観し、その上で「可能性の歴史」という、歴史の周辺に追いやられたもの、未然の形でとどまっているものの掘り起こしをめざす歴史観を考察する。その出発点は、ヘーゲル、カント、ハイデガー、それぞれの一節である。
「現に存在するこの家郷性そのもののうちに、さらにはこの家郷性の精神のうちに〔中略〕、この自由で美しい歴史性、追憶(彼ら〔ギリシア人〕が現にそうあるところのものが、追憶として彼らのもとにありもするということ)の性格のうちに、思想の自由の萌芽もまた存する」(ヘーゲル『哲学史講義』、p.99より抜粋)「われわれは人間のやることなすことが大きな世界の舞台の上で演じられるのを眺め、そこに個々の点ではときおり知恵が現れはするけれども、全体としてはすべては結局のところ愚昧と子供っぽい虚栄によって、またしばしば子供っぽい悪意と破壊欲によって織りなされているのをみいだすとき、ある種の不快の念を禁じえない」(カント「普遍史のための理念」、p.156より抜粋)
「歴史学的対象の第一次的な主題化は、かつて現存在としてあった現存在を、そのもっとも固有な実存可能性へと向けて投企する」(ハイデガー『歴史と時間』、p.213より抜粋)
いずれも物語的歴史に言及したものであるが、ヘーゲルの例は、現在を規定する過去を起源として位置づけることにより、そこに家郷のような居心地のよさを感じるという、「起源-現在」への「共同体の来歴」の物語の特性を明かし立てている。カントの例は、普遍史のような歴史の見方(ヘルダーに代表されるような)への懐疑の念をカント自身がいだいていたことをうかがわせる。そしてやがては普遍史の断念へといたる。ただし共同体としての歴史ではなく(民族に集約されるような)、あくまでも普遍史の構想を考えたことは、啓蒙と人類という<脱=共同性>の精神をそこにうかがうことができる。ハイデガーの例は、歴史が過去の遺物ではなく、まさに「可能性」にかかわっていることを強く訴える。未然のままにとどまる過去の潜在性を現在の生において「取り戻す」という読み方である。それが本来性の次元で行われるとするのがハイデガーの歴史論である。おそらくこれだけでは語弊があるハイデガーの読みをベンヤミンと対比させることによって、歴史から忘れ触れた人々の「取り戻し」を諮ろうとしたのが筆者の意図ではないだろうか。「危機の瞬間にひらめくような想起」(p.233)を既成解釈から解き放たれた時の、人間の生の可能性ととらえ、そこに「歴史の屑ひろい」の栄光を考えるのである。
本書の意図は、啓蒙の時代の様々な思潮を、現代に生きる我々が批判的に受け継ぐために、検証することにある。今「批判」ということばを用いたが、このことばこそ、啓蒙の時代をそれ以前・それ以後からわけ隔てる根本的な人間の思想的態度であり、またトドロフの考え方の根本でもあると言える。批判をするとは、もちろん、自分とは異なる立場・意見を否定することではない。そうではなくて、絶対的な存在、絶対的真理、そして絶対であるゆえに人間から超越した存在というものを前提としないということである。そしてそれゆえに自律する人間が、おのおの価値を吟味するとともに、他者の価値をも吟味することによって、そのつどそのつどの暫定的な「真理」を作り出していくこと、つねに批判・吟味にさらされる合意を形成していくことである。啓蒙主義がその最終目的として、完全なる幸福の世界をユートピア的に描いたとすれば、トドロフが描くのは、相対主義に陥らない、多様性の尊重であろう。みなが賛成するような世界は一種の全体主義である。その具体的な現れが植民地主義における"bombes humanitaires"(p.106)であろう。また他方お互いの伝統文化を絶対的に他者が理解できない領域として批判を棚上げしてしまうのは、相対主義の悪しき形態である。たとえば死刑や、拷問への批判は人間の権利という、共通のノルムに則って、否定される。全体主義と相対主義を両極としながら、トドロフは、批判という動的な人間の思考の動きによって、決してその両極へと陥らない思想的態度をとる。
トドロフが本書で特に依拠しているのは、モンテスキュー、コンドルセ、ルソーである。特にコンドルセのAutonomieを持った人間を形成するための教育の意義には深く納得されられるものがある。
Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger(p.44)
このように評価をしながらも、それを絶え間なく改善していこうという姿勢、これこそがよりよき社会を形成するのだというコンドルセの考え方は、権力の維持のために教育によって、絶対的価値を国民うえつけようとする教育(これは教育ではなく、訓練であろう)と真っ向から対立するものであり、公教育を考えようとした当時の人々の最良の部分を明かしだてるものであろう。それ以外にもなぜヨーロッパで啓蒙主義が最も明白な形で現れたのか(この地域に様々な国が並立していること、それによって、国が違えば、常識が違うというような現実に接触していたこと)、など、示唆に富む見解が得られる書物である。
コンドルセに関しては
富永茂樹『理性の使用』(みすず書房)
フランスの公教育に関しては
コンドルセ他『フランス革命期の公教育論』(岩波書店)
第4回目の授業(2006年春学期「言語とヒューマニティ」)では「虚構」ということばを使い、我々が他者を理解する時に「虚構」が付きまとう、しかし虚構をもって、意味づけることによって、我々は世界というものを生きていけるという話をした。下記の小川洋子の講演にある「物語」とは、まさに「虚構」であり、我々は人生を物語を形成しながら生きていくとされる。
以下引用
たとえば、非常に受け入れがたい困難な現実にぶつかったとき、人間はほとんど無意識のうちに自分の心の形に合うようにその現実をいろいろ変形させ、どうにかしてその現実を受け入れようとする。もうそこで一つの物語を作っているわけです。あるいは現実を記憶していくときでも、ありのままに記憶するわけでは決してなく、やはり自分にとって嬉しいことはうんと膨らませて、悲しいことはうんと小さくしてというふうに、自分の記憶の形に似合うようなものに変えて、現実を物語にして自分のなかに積み重ねていく。そういう意味でいえば、誰でも生きている限りは物語を必要としており、物語に助けられながら、どうにか現実との折り合いをつけているのです。
作家は特別な才能があるのではなく、誰もが日々日常生活の中で作り出している物語を、意識的に言葉で表現しているだけのことだ。自分の役割はそういうことなんじゃないかと思うようになりました。
「これらの詩人たちは神々のことについてはいうまでもなく、あらゆる技術と、悪徳と徳にかかわるすべての人間的なことがらについても専門知識をもつとされている」(プラトン『国家』598E)詩人とは個人の芸術的創造を行う者ではなく、社会において必要な知識、しきたりを伝達する役割を持っていた。その行為は声によって行われたのである。そして文字の導入は、この古代ギリシアの文化にどのような変化をもたらしたのか?声の文化から文字の文化への移行に、プラトンによる詩人批判(国家追放)の理由を探ったのが、本書である。様々な知識を記憶するためには、自分の具体的な体験に結び付けて、覚えるのでなければ、到底覚えきれるものではない。「覚えるべき」ことを復唱する(真似する)と同時に、そこに個人の体験を練りこんでいくのが、口承の文化であった(主観と客観の混同)。「生きた記憶」によって、法や慣習が保たれていたのである。それに対して文字の文化では、個人とは、「覚えるべき」ことを批判的に吟味し、検証していく存在となる。つまり文字文化において、人は「自己」に目覚める。その自己は熟慮をし、深く物事を分析・理解するようになる。そして抽象的な思考が可能となるのである(ここからイデアについての考えも生まれてくるだろう)。この個人とはだれか?それは哲学者である。プラトンの詩人追放とは、哲学者の登場を促すためであったのである。「彼ら哲学者たちは、生成と消滅によって動揺することなくつねに確固としてあるところの、かの真実在を開示してくれるような学問に対して、つねに積極的な熱情をもつということを確認しておこう」(プラトン『国家』485B)
エリック・A・ハヴロック『プラトン序説』(新書館)
声を主体にした人間の活動と、文字が現れて以降の人間の活動の変化を対象とした研究である。この中で特に扱われているのは、ホメロス問題に発する、古代ギリシアの声の文化から文字の文化への移行の問題である。ホメロスの叙事詩とは、まさに口承の文化であり、詩人は、詩の中に託された社会にとって重要な情報を、その社会という共同体の人々に語り継いだ。つまり声の文化とは共同体の文化であり、声とは個人のものではなく、共同体のものである。それに対して文字の文化は、正確に物事を論証し、人間が論理的活動をすることを可能にした。この物事を深く考えるとは、まさに個人が内面で行うことであり、文字の文化は、個人の営みを可能にしたと言える。共有される知識の伝達が声の文化ならば、文字の文化は、個人の思想の正確な表現であるといえよう。
J-W・オング『声の文化と文字の文化』(藤原書店)
ここで扱われているのはプラトンの『クラチュロス』である。ここではクラチュロスとヘルモゲネスが「名の正当性」について論議をしている。クラチュロスは物の名は、その物の性質に照らし合わせて、必然的なものが選ばれているとする。例えばディオニソスはディオデュスとオニノンに語源的に分解できる。これは「ワインを与える者」という意味になる。一方ヘルモゲネスは名に正当性を与えるのは、社会的規約であるとする。社会的取り決めによって名はその正当性をもつのである。さてクラチュロスにおける名の必然性はどのように証明されるのか?それは2つの方法によってである。1つは上にあげた「語源」をさかのぼる方法。しかしこれは所詮は語の分解に過ぎない。もう1つは音の象徴性である。例えばrの音は運動の象徴である。たとえば流れるはrheinという。しかしこの音の象徴性も全て語に当てはまるわけではない。そこからソクラテスが下す結論は「言語は決して完全ではない」というものである。ここから「完全な言語」という西洋思想における大きな夢想が始まるのである。
ジェラール・ジュネット『ミモロジック』(書肆風の薔薇)
ここで問題にしているのは音が人間にもたらす感覚についてである。本書では1-2「音声の象徴性」、1-3「音と意味」、1-4「類音類義」で特にこの問題が扱われている。例えば記号としての言語観を相対化するための擬音語、擬態語の例などである。また、音がもたらす印象について、[i]の音が小ささを表すといった例が引かれている。こうした音のもたらす感覚の普遍性についての論証は、「充分」と言える地点まで至ることはないであろう。しかしこうした音象徴の例が音、音楽、楽器にまつわる文化的事象へと結び付けられるのが本書の特徴であるし、文化人類学者の視点からみた言語というものが浮かび上がってくるのである。
川田順造『声』(筑摩書房)
日本の哲学者和辻哲郎を批判的に読解した本で、和辻哲郎の倫理学の出発点を「私たちが社会で(共同体で)生きるということは表現と理解が一体化した状態だ」という認識におく。つまり私たちが相手に何か表現するということは、その場の状況やお互いの関係が理解できているから行えるのだという前提がある。だから社会は共通の理解のもとで成り立っている。しかしこのような認識は言葉をお互いが共有するものだという前提があるということも意味しており、さらにいえば、お互いが約束事を履行しながら生きているということにもなる。言葉が通じるということは「人間存在の共同性」があるからだ。それはそうでお互いが約束を守らなければ、つまり「倫理」がなければ、社会は社会として機能しなくなってしまう。、和辻は人間のあり方を四辻を歩く人間とたとえる。たとえば、異なる職業、年齢の人間たちが、相手とぶつかりもせず、四辻を交差する、そうしたイメージで、社会におけるお互いの存在了解を考える。しかしそこには、思わず歩みを止めてしまわざるをえないような、そんな言葉の存在もあるはずだ、というのがこの本の骨子である。それを「言葉の形式」(つまり意味を運ぶための一定の言語形式)、「感情に適合することば」といった表現で呼んでいる。
菅野覚明『詩と国家』(勁草書房)
この本の優れている点は、日常の観察から初めて、言語論にまつわるタームを明快に解きほぐしているところである。例えば第一章冒頭の富士山の例をとってみよう(p.21〜)。ここで言われていることは、富士山という言葉から喚起するイメージは人によって異なる。しかし意味の了解が取れているということは、誰もが「あああの富士山ね」と、自分の知識から富士山の「意味」を呼び覚ますからである。この意味こそ、言葉のシニフィエと呼ばれているものである。つまり人の知識はそれぞれであるが、それでもその知識の共通項があるからこそ、お互いに意味の疎通ができるのである。この最大公約数的な意味の領域がシニフィエなのである。そして言語が示すのは、じつはこの意味の領域なのであって、決して現実の富士山ではない。このことがはっきりわかる例が「山」である。山は世の中にありとあらゆるほどある。そのどれもを山と呼ぶが、もっとも山らしい山というのは世の中に存在しない。それは我々の頭の中だけにある。その概念と照らし合わせて、目の前のものを「山」と読んでいるのである。この作品ではそれを「山という語の表す山は、一種の抽象的典型としての山である」と言っている。言い換えれば世の中に一つとしてまったく同じ形をした山は存在しない。つまりすべて異なるのにそれをひっくるめて山と呼べるのは、この抽象的典型としての概念が我々の頭の中にあり、その概念を分かち持っているから意味の疎通が行われるのである。
斧谷彌守一『言葉の二十世紀』(筑摩書房)