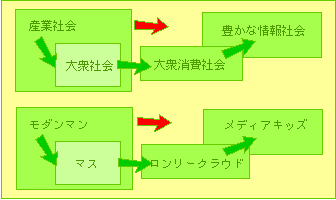|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.ポスト・ロンリークラウド 『大衆(マス)』という概念が死語になりつつある。これがまずは重要なことである。それは、すでに大衆消費社会というネーミングにはやくもその矛盾があらわれている。大衆は、情報化(マスメディア)と消費社会の到来によって、かつての「エリート対大衆」とその亜流のコンセプトから解放されて、新しい意味を付与された。それを明確にしたのがデヴィット・リースマンの『淋しい群衆(lonelycroud)』である。ここでの大衆つまり「ロンリークラウド」は、かつてのような実体としての弱者ではなく、生活の諸領域の境界線(組織でもなく、家庭<核家族>でもなく、そのどちらにも帰属しない曖昧な生活領域、典型的には「盛り場」)において、ホワイトカラーが自分に期待された役割演技にふさわしい空間(組織)から一時的に逸脱して、ある意味での自由を求めたときに成立する概念である。盛り場とは、ホワイトカラーがロンリークラウドとして振舞う舞台であり、組織から家庭へ移行するための境界領域であり、基本的には社会的に『許容された逸脱空間』である。そこは、ホワイトカラーが仕事の疲れを癒そうとして寄り道する場であり、家庭での主人の役割(真面目で、我慢強く、高い地位を求めてひたすら頑張るお父さん)に移行するまでの一瞬のやすらぎの空間であった。 このような父親=主人にだけ付与されていた特権的な憩いが、豊かさの獲得と情報化の浸透(テレビと電話の家庭生活への普及)によって、核家族の全員に共有されるようになったとき、ロンリークラウドはその歴史的な使命を終えるのであった。父親だけが盛り場にたたずむロンリークラウドである必要はなくなり、父も含んで家庭でみんなで一緒に楽しみ(団らんと娯楽)を享受できるようになった。マイホーム主義と家族のレジャー化という社会現象は、いままでの核家族の理念(まじめな家族)の変容を予感させる最初の現象であった。テレビというマスメディアはそこでの最高のスーパーメディアであり、同時に最高のおもちゃ箱だった。
そもそも大衆の概念は、その成立において、近代的自我(モダンマン:リースマンのいう内部志向型)との対立から発生したものであり、その社会的背景には近代の産業社会がその構造を変化させようとしている、という社会認識がある。産業社会が自己発展することで、その裏(許容された逸脱)のシステムとして大衆社会が生成され、その裏のシステムが徐々に勢力を延ばすことで、表のシステムとして社会的正当性を獲得し、その結果として大衆消費社会に変容した、という社会変動のプロセスがここにはある。その過程で、モダンマンから大衆が派生し、さらにその大衆からロンリークラウドが派生的にあらわれ、そしてそれが家庭でも許容されることで、まったく別のタイプが生成されようとしている。それを、ここでは「メディアキッズ」と呼ぼう。(図2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||