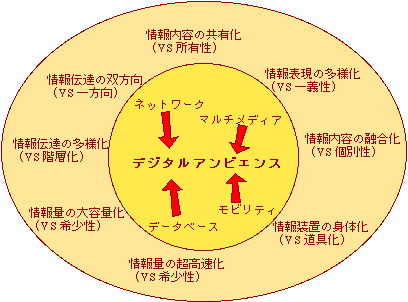|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.デジタル・アンビエンス やっと情報化の意味が分かりかけてきた。テレビや電話といった従来のメディアからコンピュータをベースにした新しい情報環境が生まれつつある。この予想される情報環境を「デジタル・アンビエンス」と呼ぼう。それは、あらゆる情報ツールの情報をデジタル化して処理でき、全ての情報を等価に、そして自由で容易に操作できる環境が、いつでも・どこにでもたちあげることができることだ。文字も映像も音も、手書き文字も活字も、静止画でも動画でも、会話でも音楽でも、すべての情報が同じように扱える電子環境がそこでは立ち上がる。したがって書類も電話もファクスも、また写真もテープレコーダーもビデオも、すべて互換的な情報処理と情報生成が可能になる。 もちろんこのような情報環境がオフィスや生活環境として自明になる日はまだ先の話である。しかし時間の問題であることも事実だ。現状では、電子メールの環境が整備され、その上でパソコンを使って、ワープロと表計算とプレゼンテーション用ツールが活用できるといった程度が、せいぜいである。でもここまでくれば、もうそれだけで十分に新しい情報環境が立ち上がっている。この状態は、デジタル・アンビエンスの、ささやかであっても重要な最初の一歩だ。この一歩を情報環境として共有するかしないかは、基本的で抜本的な差異をもたらすはずだ。 このようなデジタル・アンビエンスの生成には4つの条件が不可欠である。それは『データベース・マルチメディア・ネットワーク・モービリティ』である。これらは、ジャーナリズムの世界ではすでにファッションではなく、恥ずかしいまでの常識用語であり、言葉としてだけならば、誰もが「いまさら!」と言い切れるほど自明な言葉である。(図7)
第一に情報量にかんする環境が、従来とはまったく異なってくる。大量の情報がハイスピードで貯蔵され処理されることが重要である。情報は希少だから価値が生成される、というかつての発想はここにはない。データベースを重視する発想では、情報は、現状よりももっと大量でなければならないし、しかもその大量の情報が瞬時に貯蔵され処理されなければならない。平均的な認識として、よく「現在の情報化社会では、情報にあふれ、その選択に困惑する人が・・・・」といった発言があるが、これなどはまったくの誤解である。現状の情報量にかんしては、容量もスピードもまだまだ過度に不足している。桁違いの情報量とスピードが、データベースの発想には不可欠である。 この発想は、情報は大量で超速であるとき、はじめて価値が生成される、という反希少性の価値認識を前提にして成立する。あっというまに膨大な情報が目の前に現れても、それが当然と思えなければ、またそうでなければ仕事ができない、と考えられないかぎり、データベースを活用することにはならない。デジタル・アンビエンスは、このような意味での新しい情報環境の認識を重視する。 第二に情報表現にかんする環境がまったく異なってくる。文書主義に典型的に表れる文字・活字表現だけの情報環境ではなく、映像や音響の情報をも含み、しかもそれらの多様な情報をデジタル化することで等価に処理し、だからこそ多様な表現を可能にした情報環境がここに生成される。多様な情報の統合と表現の多様化がマルチメディアという情報環境に期待されることである。 デジタル・アンビエンスは組織の情報環境としてマルチメディア化を要請する。従来のように文書だけが唯一の表現手段である、という時代状況ではない。情報社会における組織では、たとえばプレゼンテーションはマルチメディアを駆使してなされるはすだ。納得とか理解といったことが、従来のように数字や文字だけではなく、たとえば動画をみせることで一瞬のうちに了解される、といったことがますます重視されるようになるのが、新しい組織における情報環境のあるべき姿である。デジタル・アンビエンスは、このようなマルチメディア環境を重視する。 ここでは、多様な情報を等価なデジタル情報として扱えるという統合化がきわめて重要な意味をもつ。統合化によって、組織における情報の価値格差(文字情報が優位で、映像情報は劣位)は解消され、必要に応じて、いかなる情報でも利用できる可能性が開かれる。産業社会では、組織では文字情報に特化し、その他の情報(映像や音響)は特殊な領域(たとえば芸術)に封じ込めることで、文字情報以外すべてを組織は排除してきた。それが産業化の歴史である。しかし情報社会では、すべての情報は等価である。説得も理解も了解も、その状況に応じて、文字ばかりでなく、映像も音響が優位に立ってなされるようになる。このように、情報の統合化は、同時に情報表現において多様な表現を可能にする。統合化と多様化はコインの両面である。文字でも、映像でも、音響でも、「なでもあり」という表現ができるためには、統合化が不可欠なのである。この両面性が確保されることがマルチメディア環境なのである。 現状の組織にとって、情報環境としてもっとも必要なのは、データベースの充実を前提とすると、このネットワーク化であろう。ネットワークは、情報を双方向で共有することを可能にする点で、いままでの情報をめぐる社会関係を根本的にかつ抜本的に変革する。従来の産業社会の組織における情報は、その希少性を前提とすることで、所有されることで価値を生成していた。その情報所有をめぐる格差が地位の上下関係であり、それが組織を管理する最重要な視点を構成したのである。従来の組織が管理機能によって了解されるのは、情報は所有されて価値を生成するという認識があったからである。 このような情報所有をもとにした社会関係を崩壊させるのがネットワーク化である。ここでは情報は組織のメンバーすべてに共有されてはじめて価値を生成する、という価値認識がある。情報を所有しない下位のメンバーにたいして、情報を所有していることを武器に操作したり管理したりすることで、組織化が維持された既存の構造が、ネットワーク化によって一挙にその存立基盤が撤去されてしまう。具体的には、なぜ組織のトップなのか、その地位を保証する根拠はなんなのか、が喪失してしまう。管理機能の情報的根拠が失われたとき、管理者はなぜ必要なのか、管理者は自己の存在理由を失う。 同一の情報をみんなが同時に共有したとき、何が組織化の原理になるのか。管理機能に変わって、組織化を維持する機能は何か。これはシンボリック・ガヴァナンスで扱う大きな問題である。 ネットワークは、誰でもが誰にでも即座にかつ同時にコミュニケーション(n−n)できる情報環境を構築する。従来、多数(無数)への情報伝達は送り手を固定(1-n)させなければならなかった。これが組織の上下関係を規定するメディア上の制約条件であった。これが取り払われるのがネットワークであるから、新しいネットワーク環境では、上下関係で情報が伝達される必要がなくなる。とすれば、ここでも管理機能は後退せざるをえない。 第四は情報装置の携帯性にかんしてである。現在でも電子手帳のような新しいツールが続々と開発され、新しい情報環境が身体に装着されつつある。この傾向は今後一層進むはずである。これがデジタル・アンビエンスにおけるモービリティである。 これは2つの情報環境の変化をもたらす。1つは情報環境の自在な移動性である。いつでもどこでも情報環境が立ち上がるという特徴は、環境が固定されて、そこに個人が移動しないかぎり何もできない、という情報環境の外在性に大きな変化をもたらす。情報行動が環境の外在性によって制約されることがなくなり、瞬時にどこにでもコミュニケーションがとれる状況が生成されることで、リアルな対面的行動と情報行動との差異が意味を失う。情報行動は、ヴァーチャルでありながらリアルな行動になり、行動そのものになる。 もう1つは、上記3条件を備えた情報環境が身体化されることで、単にいつでもどこでも情報環境が立ち上がるという環境の大きな変化ばかりか、新しい情報主体の基本コンセプトが大きく変化する。近代産業社会での個人にとって、情報環境はどこまでも個人の外部にあり、そこでの関係はあくまでも道具にすぎなかった。ここでは情報環境は外部であり、身体化された装置ではなかった。せいぜい名刺ぐらいがシンボリックに個人に装着していた程度である。 これにたいして、デジタル・アンビエンスでは、情報環境が身体化されることで、それは環境でありながら同時に自己(情報主体)でもある、という両義性が発生する。自他の境界が曖昧になり、自己の境界が自在に変容することで、つねに新しい自己が生成される仕組みがビルトインされることになる。メタファーで言えば、「等身大の鏡をもつ自分」が新しい自己である。鏡に映る自分は、自分であって、自分ではない。その二つの自分にたいする微妙な認知のズレが、自己をいつも再編成させるプロセスを要求するのだ。 新しい情報環境は、以上のように、データベース・マルチメディア・ネットワーク・モービリティから構成される『デジタル・アンビエンス』を必要とする。これは、現状での条件整備で言えば、十分なメモリーを積んだかなり高速のノート型パソコン(データベース/モービリティ)で、電子メールができ(ネットワーク)、そしてワープロと表計算とプレゼンテーション用のソフトを活用して作業ができる(マルチメディア)、という条件が整備されていることである。これが現状で考えられる一応のデジル・アンビエンスである。当然、これはデジタル・アンビエンスの最低限の条件であり、にもかかわらず、やっと少数の組織で採用されはじめた情報環境である。 しかしこの程度の情報環境でも、その有無は決定的である。なぜならば、その差異は組織の構造の差異を規定するほど大きな意味をもつからである。たかが電子メールであるとしても、それがもつ意味は想像以上に大きい。電子メールの環境が整備されたならば、それは従来の階層的な管理機能を核とした組織形態を本質的に変革することを要請するのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||