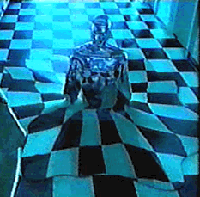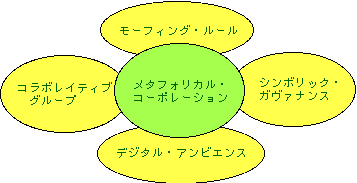|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.メタフォリカル・コーポレーション 最近の組織論は、リエンジニアリングで一杯である。組織論をめぐるここ10年のファッションをみると、バブル経済最盛期の「コーポレート・アイデンティティ」から始まり、崩壊の危機に慌てて組織「リストラクチャリング」が主張され、そして、危機からの脱出と新しい組織への再生を求めて「リエンジニアリング」が登場してきた。そのコンセプトの提唱者であるマイケル・ハマーは、事実自信たっぷりに、アダム・スミスの名著『諸国民の富』に代わって、自分の『リエンジニアリング革命』を位置づけている。 この自信の裏付けは、つぎの2つの新しい視点にある。1つは情報システムを組織のインフラの最重要要因として位置づけていることだ。もう1つは、情報システムを前提とすると、従来の分業システムを超えた新しい作業方法が可能になることを明言したことである。
では、デジタル・アンビエンスという新しい組織にふさわしいメタファは何なのか。現実にはまだない、映画『ターミネーター2』に登場する「液体金属<T―1000>」がもっともふさわしい、と思われる。組織のメタファが「機械」から「液体金属<T―1000>」に変化するとき、組織は、従来の階層的な構造とはまったく異なった組織として想像されるはずである。そこでイメージされるものは、三角形の硬いピラミッドとはまったく対照的で、瞬時にいかようにでも変容し、いかなる状況にあってももっとも最適な形態を示して、どのような事態にたいしても十分な対応力をみせる、常識を超えたどこまでも創造的なるのもの、といったことである。 産業社会が想像した機械またその発展型の有機体としての組織は、能力主義を前提に構成された管理機構を核に、そこで発生する情報所有の格差を媒介にして、1対nのコミュニケーションを手段としてもっとも効率的な目的達成を目指した組織であり、同時に下位のnの間のコミュニケーションを最小化するために作業の分業化をはかり、そのかぎりでの閉じた部分的な専門性を追求させることでもっとも効率的な目的達成をめざした組織でもある。情報所有と管理機構と分業体制と効率的な目的達成は、近代産業社会が求めた組織の原理である。 このような階層的な組織は、しかし豊かな社会の到来と情報社会の到来によって、その社会的・歴史的な使命を終えようとしている。組織は、社会の大きな変化のなかで、その変化をもたらした階層的な組織それ自体を自己否定せざるをえない状況に追い込まれている。 どう変わればいいのか。機械と有機体に代替する新しいメタファーは何なのか。 ボイス・プロジェクトは、それを、映画「ターミネーター2」の『液体金属<Tー1000>』に求めた。そこから喚起されるイメージは、今までの組織のメタファーを超える新しい何かを暗示していた。そのメタファーを手がかりに、新しい組織とは何か、を想像するとき、まったく新しい組織のイメージが浮かんできた。それが『メタフォリカル・コーポレーション』である。 これは、機械のメタファーからもっとも遠い距離にあるメタファーから創造された新しい組織のヴィジョンである。それは、4つの形態をもつ。
どんなに多様な形態をダイナミックに示すものであっても、それが組織である以上、それなりのルールが必要であることは自明であろう。しかしそのルール自体が変容する多様性を示すものでなければならず、ルールがもつ固定的なイメージからいかに距離をとれるか、が問題になった。その結果が「モーフィング・ルール」である。モーフィングという多様に変容するプロセスだけが価値をもつソフトをメタファーに、新しいルールを想像するとき、組織の創造性と効率性の融合と両立を可能にするルールが発見された。組織のあり方を正当化するルール自体が柔軟で曖昧で、そして多様でダイナミックでなければならないのである。 とすれば、組織化のあり方も、従来のような管理機能を核とした組織統合の視点ではない新しい組織化の原理が期待されるはずである。それが組織融合であり、「シンボリック・ガヴァナンス」である。この組織はもはや管理者を必要としない。期待されるのは、組織の新しいヴィジョンをシンボリックにあるいはメタファーを使って想像力豊かに、組織の内外にアピールできる顔である。新しい組織の方向を誘発し誘導するイマジネーションがそこでは必要である。しかもそれだけではく、下からの支援が大事である。仕事の環境を整え、メンバーが気持ちよく仕事ができるような環境の整備をする機能が求められる。これは、権限委譲ではなく、エンパワーメントである。上から下に権力を付与するという意味での権限委譲はもはやここにはない。あるのは、メンバーのために心地よい作業環境をつくる支援をする機能である。サッカーのサポーターであり、コンピュータのクライアントーサーバーにおけるサーバー(奉仕者)が、ここでのメタファーである。組織化は、サポーターとかサーバーの仕事である。だからこそ組織統合ではなく、組織融合が組織化の原理なのである。 もちろん組織融合といっても、組織の効率的な運営を無視するわけではない。その逆で、より一層の効率化は自明のことである。組織のフラット化をはじめとした分業を超えた新しい効率性の追求はより厳しくなる。また同時に人事考課などの評価の方法も変わらざるをえない。情報共有を前提とした方法が重視され、セルフナビゲーションによる自己評価を含んだ新しい評価方法の開発が求められよう。 第三には、ワークスタイルが変わる。分業を超えた新しいスタイルが模索される。それが「コレボレーション」という新しいグループワークの方法であり、その方法を採用する作業集団が「コラボレイティブ・グループ」である。 コラボレーションをするには、新しいリテラシーが必要である。文書主義を超えたネットワークとマルチメディアを駆使するデジタル・リテラシーが期待される。その新しい情報リテラシーをもった専門家の出現が必要である。その専門家は自立した個であると同時に、ネットワークを介して開かれた専門家にならなければならない。専門家の役割融合をいかに成功させるか、それがコラボレーションの課題である。 最後に、メタフォリカル・コーポレーションはデジタル・アンビエンスを必要とする。データベース・マルチメディア・ネットワーク・モービリティから構成されるデジタル・アンビエンスと、それに共振するフレキシブル・スペースは、今までにない新しい情報環境を提供する。この情報環境が整備されるとき、はじめてメタフォリカル・コーポレーションが作動する。 電子メールを利用したパソコン環境は、このデジタル・アンビエンスの原初形態として重要である。この環境があるかないかは、メタフォリカル・コーポレーションの生成を規定しよう。この環境は、情報所有を情報共有に変換させる突破口であり、単にメールが送れるといった個別の現象を超えた、もっとも変革的で根本的な意味をもつものなのである。だからこそ、戦略的には、この情報環境をいかに現在の組織に受容させるかが問題である。 このように、メタフォリカル・コーポレーションのコンセプトは、新しい情報環境の間近に迫った実現可能性の中で、それに対応した新しいワークスタイルとそれを組織化する新しい原理を検討し、さらにそれらを正当化する新しい組織ルールを構想するものである。機械や有機体といった産業社会の組織を超えた新しい情報社会の組織ヴィジョンを、メタフォリカル・コーポレーションとして提示する。ターミネーター2の「液体金属<Tー1000>」は、メタフォリカル・コーポレーションを想像する力を喚起する重要なメタファーである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||